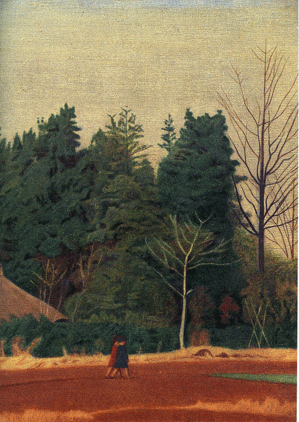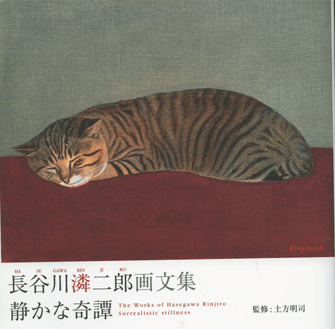孤高の人・長谷川りん二郎(その1)
生きているうちに、色々なことをやってみたいと思っている。そのやってみたいことの中には、落語をゆっくり聞いてみたいというような欲求もあるけれども、一番やりたいのは絵を描くことなのだった。それで、退職したら絵に着手しようと油絵の道具を揃えたものの、なかなか絵筆を取る気になれなかった。
そんなことをしているうちに、絵の具が硬化する気配を見せ始めたので、勇を鼓して風景画を一枚描いてみたら、自分でも呆れるくらい下手糞なものになってしまった。その原因は明らかだった。絵を描くにも日頃の訓練が必要なのだが、それを欠いたままでいきなり油絵を描こうとしたから失敗したのだ。
昔、NHKの教育テレビで、「平山郁夫の絵画教室」というのをずーっと見ていたことがある。講師の平山は4,5人の受講者に壺などの画題を与えて写生させながら、自分でも鉛筆を動かして同じ壺をスケッチしていた。その鉛筆捌きの素早さと的確なことには、思わず目を見張った。まるで熟練工みたいだった。
平山は美術大学の学長になってからも、絶えずスケッチを続けており、それは死の直前まで続いたといわれる。名人・天才といわれる芸術家でも日頃の訓練を怠れば、技量はたちまち落ちて行くのである。まして、ずぶの素人の私などは、スケッチ帳を片手に絶えず写生を繰り返して、最低限の技術を身につけていなければ、油絵などを描けるはずはないのだ。
しかし、そんなふうに考えていたのは私の錯覚だったのである。問題は、写生の訓練を続けるというようなことではなくて、対象をじっくりと観察することだったのである。私は中年以後、アメリカのワイエスや岸田劉生から始まって、熊谷守一や高島野十郎の作品を好んで眺めるようになったが、これらの画家たちはいずれも描こうとする風景なり静物なりを長い時間をかけて観察し、そのものの「真」を捉えてから着筆していたのだ。
彼らの作品を眺めているうちに、何となく私にも自信が湧いてきたのだ。自分はスケッチを怠り、日常的な訓練を怠って今日まで過ごしてきたが、それでも時間をかけて対象を観察する癖を身につければ,それなりに意味のある作品が生まれるのではないかという自信が湧いてきたのである。
肝心なのは、作品の見た目の巧拙ではないのだった。その作品に描き手の捉えた「真」が現れているかどうかなのである。セザンヌはリンゴの絵を描くに当たって、あまりにも長時間観察を続けたためにリンゴが腐ってしまい、新しいリンゴを補充しなければならなかった。
そんなふうに小さな開眼をした私が、目下魅了されているのは長谷川りん二郎 で、彼もまた描きながら観察を深めて行く熟視型の画家なのである。
長谷川りん二郎を知ったのは、例によってNHKの「日曜美術館」だった。彼は高島野十郎と同じように画壇とほとんど関係を持たない無名の画家だったが、生前にも少数の熱狂的な支持者を持っていたため、戦後になって評価されるようになったのだ。
私はテレビに次々に映し出される彼の作品の一枚一枚に、あたかも異界にいざなわれるような戦慄を覚えた。例えば、「荻窪風景」と題する次の絵である。すごい絵だった。
番組の出席者たちは、これらの作品について、口々に、「平明な絵の背後から,未知の世界が浮かんでくる」と言っていた。大下智一も、「長谷川りん二郎画文集」の解説で、こう指摘している。
りん二郎の自
然観賞は、自然(対象)そのものを観察するという
より、対象の鑑賞を通じて「違う何か」を見ること
にある。すなわち、「見ること」は正確な描写を
求めるというより、その裏側にある世界への入り口
を探すことなのだ。
まず、りん二郎は、「写生」を通じて、外的世界に
幻視を見る。長谷川りん二郎自身も、「現実を超えて、現実の奥に隠れて、それでいて表面にありありと表れるもの」を描くといっている。
彼の絵の背後に別の世界が隠されているように感じるのは、なぜだろうか。
光がどこから射してくるのか分からないからだ。空は曇っていて灰色であり、それに呼応するように道路もまたくすんだ色をしている。そのせいか、小粒に描かれている人間の足下に影がない。
画面全体がフラットで、中軸となって画面を引き締めているいるものがない。ここには、ロマンもなければ物語もない。まるで夢の中の一場面のようなのだ。白昼の光景であるにもかかわらず、やけに静まりかえって,物音がしない。平明にして静謐、死後の世界のようである。私は無神論者で、死後の世界などを信じていないが、こういう種類の絵を見ると、何時でも冥府の光景を想像してしまうのだ。次の絵は、「早春」と題する作品の一部である。
こうした樹木を描いた作品を眺めた後で、二階北側の小窓を開けたら、書庫の屋根越しに「ハナモモ」と紅梅の樹が目に映った。思わず、(ああ、いいなあ)と思った。長谷川の作品から樹木の見方を学び、いわば彼の目を通して庭の木を見直し、樹の美しさを再発見したのだ。
今度は階下に降りて、玄関脇の窓から同じハナモモと紅梅の木を眺めてみた。曇り空の下で,組み合わさった木の枝が濃淡の影をまとっている。その樹のたたずまいが始めて見るように新鮮に映った。
(長谷川りん二郎の「りん」は、漢字。しかし、この漢字を呼び出すことができなかった。それで、題名に「りん」の字の出てくる本を紹介しておきます)