再訪-孝行猿の家
孝行猿の家は、秋葉街道の奥にある。秋葉街道は、伊那谷を縦貫する伊那街道と並行するように走る街道だが、南アルプスと伊那山脈の間の谷間を走る「隠れ街道」「裏街道」というような存在である。
この秋葉街道の中心地の一つが市野瀬という部落で、孝行猿の家がある柏木という部落に行くには市野瀬から急な坂を上って山の上に出なければならない。
14年前、柏木に上る坂道で眼下に見える市野瀬を写真に撮っている。下の写真である。

今度、柏木を再訪するに当たって、同じように市野瀬を見下ろす写真を撮ってみた。前回は季節が秋だったが、今回は夏で、樹木の色が違っている。

前回にも注意をひかれたのが集落の向こうにある丘陵上の開拓地だった。確か、そこには、2〜3軒の開拓農家があったような気がする。だが、下図に見るとおり今回、それが見えなくなっている。

曲がりくねった坂道を上りきると、柏木の部落に出る。この部落は掌に乗せて宙に差し上げたような高地にあるから、からっと明るく光に溢れている。周囲には重畳する山波が連なり、見晴らし台に立ったような気がする。下の写真が、柏木の部落だ。

記憶をたどって、孝行猿の家にたどりつく。家は14年前とほとんど変わっていない。次の二枚の写真を見比べていただきたい。上の写真が14年前のもの、下の写真が現在のものである。
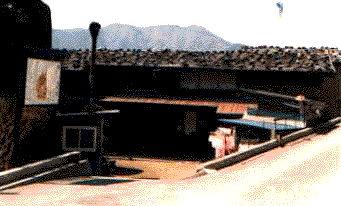

今では何処にも見られなくなった「石置き屋根」も、以前のままだ。孝行猿は柏木部落の名所のようになっているから、この家では簡単に屋根替えも出来ないのかもしれない。
変わっているところはただ一つ、資料館が出来ていることだった(矢印で示したところ)。
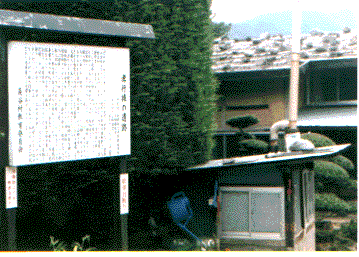
家の入り口にある説明板は、公費で作られたものに違いない。だが、「資料館」の方は多分、この家が私費で作って無料で公開しているものである。家屋の一角に4畳半程度の部屋を増築し、そこに昔の囲炉裏や生活用具を並べただけのものだ。陳列品に専門家の手が入っていないことは一目で分かる。並べられた品々は、間違いなくアマチュアが個人の手で集めたものである。
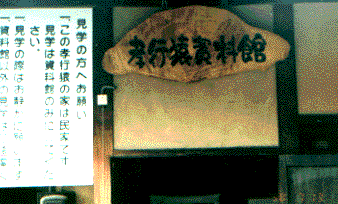
資料館を覗いてから、その資料館の屋根を撮影する。二段になっている屋根のうち、下方の小さな屋根が資料館のものだ。昔は屋根と言えば、大部分が茅葺きの屋根か石置き屋根だった。江戸時代、屋根を葺くのに使う「屋根板」を現物年貢として徴収する制度が伊那地方にあり、召し上げられた屋根板は江戸に送られ町屋の屋根などになっていたのである。

孝行猿の家を出て、細い道を隔てた向かいあいの家に目をやったら、荒れ果てた廃屋になっていた。これも14年の間に起きた変化である。

(折りがあったら、又、ここに来てみよう)と思いながら、柏木を後にした。