物言わぬ立像
今回伊那谷を見て歩いて感じたことの一つは、地区内の各地にいろいろな銅像が立てられていることだった。私が子供の頃は、小学校に二宮金次郎の石像があり、公園に郷党の生んだ軍人や政治家の胸像があるといった程度だった。だが、今では小学校から高校まで、ほとんどすべての学校に銅像があるし、公園や駅前に裸婦像などが立てられ、いたる所で立像にお目にかかるようになっている。
銅像で驚かされたのは、人気のないたんぼ道に母子像が立っているのを見たことだった。下図で見るように道ばたにコンクリートの台座をしつらえ、その上に人体に近い大きさの銅像が立っていたのである。費用もかかったであろうに、こんなところに立派な銅像を設置したのは、なぜだろう。

何処でもお目にかかれるようになったのは、下図のような裸婦像である。その昔、私は「裸婦像や菰巻く園の枯れし木々」という漫画みたいな俳句を作って失笑を買ったことがある。この写真はアルバムの中にあったが、何処で撮ったか皆目覚えていない。

下図の二枚は、広々とした公園に行って撮影した組写真に見えるかもしれない。さにあらず、某高校の校門近くで撮った写真なのだ。敷地をこんなにたっぷり使った高校は、いかに地方といえども、そう多くはない。銅像の周囲に白樺の木が植えられているところは、山国信州の学校らしい感じが出ている。
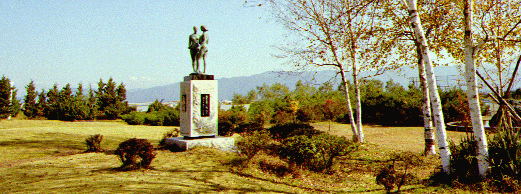
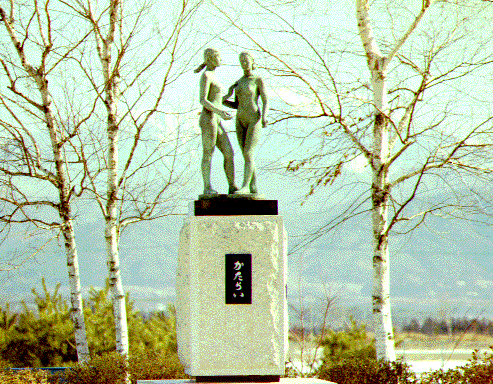
物言わぬ立像を最も多く見かけるのが、墓地である。下の写真は急傾斜の山腹を削って造成された雛壇上の墓地で、その最上段に観音像がそびえている。相当大きな立像で、高さが5〜6メートルはありそうな感じだ。間近まで行って確かめてみたかったが、この墓地にはなぜか部外者の立ち入りを拒むような雰囲気があって果たさなかった。

立ち並ぶ石塔の中に、下図のような観音像が混じっているのも墓地だからこそである。こうした石像がたくさんあれば、墓地巡りに拍車がかかるのだが。
出張の度に、その地の墓地を訪ねるのを習慣にしたのは森鴎外である。彼は墓群を巡り歩いて、墓誌があればそれを手帖に書き写していた。鴎外は宴会を嫌い、芸者などは見るのもイヤだと語っている。そうした彼は出張先での宴席を断り、名所旧跡の見物もしないで、その地の墓地を訪ね歩いていたのだ。

別に森鴎外の真似をしたわけではないけれど、地区の某寺に立ち寄ったら、石垣を背に「馬頭観世音大士」と彫り込んだ石塔があり、その横に首の欠け落ちた観音像があった。この像の頭はどこに行ったのだろう。首が欠け落ちている像をそのままにしているのには、何かいわれがあるのか。妙に気に掛かって、下の写真を撮ってきたのだった。
