生きていくということは、磁石を引きずって砂場を歩くようなものかもしれない。磁石に砂鉄が付着するように、頭のなかに何時のまにか断片的な知識や記憶が一杯くっついている。それら断片的な知識・記憶はそのまま立ち枯れてしまうことも多い。が、たまには、長い時を経て、その一つがまとまったイメージにまで結実することがある。それまで無意味だったものが、意味を持った印象にまで成長するのである。私にとって吉行淳之介のケースがそれだった。
吉行淳之介とは、結核療養所で同じ病棟にいたのである。
だが、彼とは、別の大部屋にいた関係で、直接言葉を交わすことはなかった。それでも、洗面所や食堂は共通だったから、彼の姿をよく見かけた。彼との関係は、その程度のものでしかなかった。
療養所では、吉行淳之介は誰とも親しくならず、淡々と行動していた。が、その所作は、ひどく垢抜けていて、洗い晒した木綿の布みたいな感触があった。それが興味をひいた。私が彼を意識して見守るようになったのは、彼が今売り出し中の新進作家だったからではなく、ほかの誰もが持っていないような不思議な人間的感触を漂わせているからだった。
彼には、世の中についても、自分についても、冷たく見切りをつけているようなところがあった。周囲の人間に関心がないし、回りが自分をどう見ているかについても関心がない。しかし完全に目をふさいでいるというのではなく、回りを、ちゃんと見ている。見てはいるが、感情を動かすことなく、ただ無表情で対象を黙視しているという感じなのである。
その彼が、新しく入院してきた新聞記者には、珍しく自分の方から話しかけていた。彼も人の子だなという気がした。吉行淳之介にも、商売気があるのである。
手術を間近に控えた彼が個室に入った時、私は偶然開いたドアの間から夫人を垣間見たことがある。新進作家の妻だから知的な美女かもしれないという予想を裏切って、夫人はどこにでもいるような、むしろ無粋な感じの女性だった。夫人はベットの仰臥した吉行淳之介の間近に座り、人の好さそうな笑顔を浮かべて夫に話しかけていた。吉行淳之介はそれを無言で聞き流しながら、廊下を通り過ぎるこちらにちらりと視線を投げてよこした。彼は、妻に対しても患者仲間に見せるのと同じ無感動な醒めた表情を見せていた。
患者自治会が仲介に立って、倒産出版社の本を患者たちに安く斡旋したことがある。本のカタログと一緒に注文の本を書きこんだ紙が回ってきたが、吉行淳之介が注文したのは、すべて翻訳小説だった。カタログには、日本の文学書や多様なジャンルの本が並んでいる。彼は、それらには目もくれず、翻訳された海外の作家の小説だけを選んでいた。新進作家の秘密をのぞいたような気がした。
私は、吉行淳之介が芥川賞を取ってから、初めて彼の作品を読んだ。
感覚だけがキラキラ浮き上がっているような感じで、作品の中にスムースに入っていけなかった。作家の人間性というのか、体臭というのか、そうしたアットホームなものが欠けている。私は読んでいる間、彼のしらじらとした表情を思い出していた。
先輩作家の一人は、吉行淳之介の特異な感覚を具体例を挙げて褒めそやしていた。あこがれの女性の使った後のトイレに入った吉行が、その女性が残した空間の鋳型に自分の体を合わせようとする場面がいいというのである。私には、面白くも、何ともなかった。
私は吉行淳之介への関心を失って、彼の短編二つに目を通しただけで、その後作品を読むこともなくなった。だが、マスコミが取り上げる彼に関するゴシップは、随時、耳に入ってきたし、偶然開いた雑誌や週刊誌に載っている彼のコラムやエッセーなどは読んでいた。
意外だったのは、彼が宮城まり子と深い仲になり、愛人関係を長く続いけているというゴシップだった。私は、宮城まり子の歌もドラマも見聞きしたことがなかったが、彼女は典型的なファニーガールという感じで、吉行淳之介の愛人としてはぴったりしていなかった。それは、吉行淳之介の妻がぴったりしていなかったのと同様だった。
やがて、吉行淳之介は文壇の重鎮になり、「暗室」「砂の上の植物群」などが名作として喧伝される一方で、彼の女遊びが頻繁に話題にされるようになった。純文学の名手としての評価が定着すると、世間は彼の放蕩も一種の息抜きとして許容するらしく、吉行淳之介のバー通いを伝えるマスコミの記事はおおむね好意的だった。
そうした空気を感じ取って、彼は自分の方から色道修行を口にするようになった。「モモヒザ3年、尻8年」という言葉を編み出したり、男娼を試して大腸菌をプレゼントされたとうち明けたり、現代版好色一代男を気取るようになったのである。
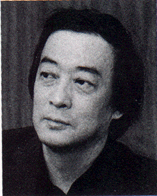 吉行淳之介
吉行淳之介私はこういう吉行淳之介を永井荷風と比較してみたりした。
永井荷風は、日本の家族制度への反発やら、大逆事件をフレームアップした当局への抗議から、世の良風美俗に背を向けて「狭斜の巷」を徘徊するようになる。軍国日本というものに息苦しさを感じていた彼は、性をひさぐ女たちといるときにだけ、リラックスできた。
吉行淳之介は、太平洋戦争が始まったとき、興奮する学生仲間の中にあって一人暗澹たる絶望に襲われたという。戦後には、マルクス主義運動に反発し、戦争中と同じように時代に背を向ける姿勢をとり続けた。彼は永井荷風同様、自分を取り囲む大状況と和解できず、女遊びに精を出すことになったのである。
永井荷風には森鴎外という師があり、戦うべき敵があり、文明批評のための哲学があった。吉行淳之介には何もなかった。核となるものを何も持たずに、実社会と人間に見切りをつけ、娼婦を漁るために「原色の街」に入り浸った。時代に愛想を尽かした彼にとって、たったひとつ残された興味の対象は、セックスを媒介にして女とまじわることだけだった。
私たちは、歴史上この種の蕩児たちを数多く見ている。カサノバや在原業平、後宮に多くの愛妾を蓄えていた帝王たちも、その心境は永井荷風や吉行淳之介と同じようなものだったに違いない。
その後、偶然手にした彼の作品は、「街の底で」という文庫本一冊だけであった。この小説の主人公はコピーライターで、娼婦のところにいるときにだけ 「神経と筋肉をほぐして安らかな心持ちでいることができる」 ので、娼婦の部屋を訪れないではいられないという男である。しかし、女が真剣になってくると、それを負担に感じて逃げ出したくなる。彼は絶えず娼婦やコールガールの街をさまよいながら、そこに根を下ろすことができず、結局自分は色街の「旅行者」に過ぎないと思う。
現世に根を下ろすことができないので、娼婦の街に出かける。が、その娼婦の街にも根を下ろすことができないとしたら、この男の住む場所は何処にもない。吉行淳之介は、このコピーライターを使って自画像を描いているのである。
永井荷風はその豊かな教養をバックに現世を俯瞰する視点を持ち得たけれど、吉行淳之介はいずれ負担になると承知しながら、性をひさぐ女たちを追い求めることしかできなかった。療養所で見かけた彼の洗い晒したような風貌は、どこにも落ち着く先を見いだすことができない孤独な男の顔だったのである。
何かの雑誌で、身辺雑記風の彼の短文を読んだ。彼はホテルの部屋で突然胸苦しさに襲われ、洗面台にしがみついて嘔吐している。その文章から感じ取れるのは、彼が無明の闇をさまよっているということだった。出口なし。その身辺雑記を読んでいるうちに、そんな言葉が、自然に浮かんで来た。
先日、テレビで吉行淳之介と宮城まり子の関係を扱った番組を見ているうちに感じたのは、自分が二人の関係はもちろん、吉行淳之介についても何も知らないでいたということだった。その番組で私は、吉行が作家になった理由を 「自分の感覚・感性を生かしてやる場所が欲しかったからだ」 と語っていることを知ったが、あの洗い晒したような風貌は、自身の特異性を自覚して、孤独な人生を歩んでいくしかないと思い決めた青年の顔だったのである。私は、吉行淳之介を過小評価していたのかもしれなかった。
吉行淳之介を間に挟んで、吉行の妻と宮城まり子が息詰まるような争いを続けていたことも初めて知った事の一つだった。宮城まり子は、夜更けに裸足になって吉行の家の回りを巡り歩き、吉行の妻は宮城まり子に無言電話を掛け続ける。宮城まり子は、吉行との関係に悩んで、服毒自殺を図っているし、身ごもった吉行の子を中絶するようなこともしている。こうした険悪な状況の中で、吉行は相変わらずバーに出かけている。
野坂昭如は、吉行が出かけるバーに作家たちが集まり、そこが「文壇バー」になったと語っている。彼が、すーっと入っていくと、たちまち店が華やぎ、彼が店の中心になった。ホステスだけでなく、野坂も吉行の近くにいると安心できたという。
村松友視も、ホステスたちが吉行のそばにいたがり、ほかの客のところに行っても、しばらくすると又彼の席に戻ってきたと語っている。療養所にいた頃の吉行淳之介からは、想像もつかないような話である。
この番組を見た後で、少し、彼の作品を読んでみようと大型古書店を回ってみた。妻と宮城まり子を巡る修羅場を書いたという「闇のなかの祝祭」や、代表作の「砂のなかの植物群」「暗室」を手に入れるためだった。が、どの店にも吉行淳之介の本はわずかしか置いてない。薄っぺらな文庫本が1,2冊並んでいるだけだった。やむを得ず、「夕暮れまで」という小説とエッセー集を買ってきたら、エッセー集の方に次のような一文が載っていた。
私が二十代の頃、親しい画家の家へときどき訪れていた。当時の私は無口で、陰気な人間であったが、その画家の家では歓迎されていた、とおもっていた。ところが十年ほど経って、真相が分った。その画家夫人がその夫に、「あの人なんだか薄気味わるくて仕方ないから、あまり来ないようにしてもらって頂戴」と、しばしば頼んでいたというのである。私はその話を聞いたときガクゼンとしたが、今あらためてそのことを思い出すと、どうやらラクロの挿話に似ているではないか。
この文章は、「危険な関係」の著者ラクロが上流夫人から嫌われて訪問を拒絶されたという挿話に関連して書かれている。吉行淳之介が何故ラクロに似ていることを喜んだかという件は、今は問わない。だが、吉行が画家夫人から薄気味悪く思われたという話は、実によく分かるのだ。私は洗い晒したような彼の風貌に興味をひかれたが、世慣れた女性から見ればあれは何とも薄気味悪い顔かもしれないのである。
他人の前に出たとき、場面場面に応じて人は表情を作る。敬意や親愛の情、場合によれば無関心や怒りの表情を、半ば意識して相手に見せるのだ。ところが吉行淳之介は、こういう対外表示用とでもいうべき表情をほとんど見せない。表情の消えた、可もなし不可もなしという顔で人に臨んでいた。
世慣れた女は、相手がどんな表情をしているか素早く読みとって、それに応じた適切な態度をとる。しかし吉行のような男を前にすると、相手の内面を知る手がかりが皆無だから戸惑ってしまう。これが画家夫人に薄気味悪く思われた理由なのである。
しかし、問題は「無口で陰気な人間」だった吉行淳之介が、その後どうして作家仲間やホステスを身辺に吸い寄せるようなカリスマ性のある存在に変わったのかということだ。
この変化は、実は作品にも現れているのである。
私が読んだのは、初期の「驟雨」「原色の街」と中期以降の「街の底で」「夕暮れまで」の四つに過ぎない。しかも、最初の二つを読んだのは、40年も前のことで、今ではおぼろな記憶しか残っていない。それでも、初期の作品が色街をさまよう孤独な青年の心象を中心に描いているのに対して、後の二つが男と女の関係を俯瞰的に書いていることは断言できる。
つまり、初期の作品は個の感覚や心象に執着して、第三者的な視点を獲得するに至らなかったのに、中期以降になると、永井荷風的な視野を身につけるようになっている。永井荷風は男と女の関係を、愛や痴情の観点からだけ見るのではなく、双方の駆け引きという観点、セックスを媒介にした知恵比べという観点から眺め(「腕くらべ」「四畳半襖の下張り」)、さらに男女の営みを風物詩の一こまとしてとらえるところ(「墨東綺譚」)まで行っている。
吉行淳之介の「街の底で」は、娼婦に心惹かれて通っているうちに相手が本気になり、男を追い回し、果ては男を脅迫するようになる話が軸になっている。「夕暮れまで」は、中年男が「処女」を守ろうとする娘を軟化させて遂に攻め落とすが、そのときには相手は既に経験者になっていたという話である。
この二つの作品の裏にある主題は、男と女がセックスで結びつきながら、互いに欲しいものを奪い取ろうとして狡知を働かせているという実態である。作者は今や、当事者の立場から抜け出て、傍観者の対場に移行し、人生の機微を余裕を持って眺める地点に達している。
吉行淳之介が中期以降、人柄と作品の点で大きく変わっていったのは、作家生活がもたらした必然の流れかもしれない。しかし、私はこれには宮城まり子から受けた影響も大きいと思うのである。
吉行と宮城まり子の関係を取り上げたテレビ番組を見ていて一番驚いたのは、吉行の友人近藤啓太郎の談話だった。彼が吉行と話しているところに、宮城まり子から電話が掛かってきた。すると、吉行は彼女と延々と話し続けるので、後で近藤がそのことを冷やかしたら、吉行がぽろぽろと涙を流したというのである。
この挿話を紹介した後で、近藤は「彼は本当に宮城まり子が好きだったんだな」と語っている。
酸いも甘いもかみ分けた遊び人の吉行淳之介が、宮城まり子のようなタイプの女性を心底から好きになるとは信じられなかった。だが、テレビ番組を見ていると、近藤の言葉に嘘はないらしいのである。
吉行が宮城まり子と知り合ったのは、雑誌社か何かの企画でもう一人を交えて三人で対談する機会があったからだった。暫くして、吉行は宮城まり子に「今、病気で入院しているから、見舞いに来てくれ」と手紙を書いた。その手紙には「見舞いの品を持って」とあったから、彼女は見舞いの品を持参して病院を訪れる。これが二人の交渉の発端になったのである。相手に働きかけたのは、吉行の方からだった。
妻を挟んで三角関係になり、宮城まり子が吉行との関係を清算するためヨーロッパに逃れたとき、彼女を呼び戻す手紙を再三書き送ったのは吉行であり、これにほだされて宮城まり子が帰国すると、吉行は家を出て彼女と同棲を始めている。そして、この同棲は吉行が死ぬまで35年の長きに及ぶのである。
宮城まり子は旅芸人の子で、子供の頃から各地を転々としていた。かわいらしい妖精のような役柄を舞台の上で演じているうちに、習い性となって大人になってもそうした性格が身に付いたのかもしれない。彼女は成人してからも、何気ない仕草に子供っぽさを見せた。
吉行は、夕方、宮城まり子とデーとしていて、彼女が「あら、真っ赤な夕日」といって、その場でくるっと一回転するようなところに参ってしまった。相手の天衣無縫な明るさ、子供のように無邪気なところに惹きつけられたのだ。花街に入り浸っている遊び人の吉行だったから、天真爛漫な宮城まり子に魅力を感じたともいえる。
吉行が書斎で原稿を書いていると、宮城まり子が「ただいま」と書斎まで筒抜けになるような声をかけて帰ってくる。そして、そのまま「淳ちゃん」といいながら書斎に飛び込む。二人の家では、これが十年一日のように繰り返される光景だったのである。
実際、彼女は溢れんばかりの愛情の持ち主だった。子供が持てなくなった彼女は「ねむの木学園」を開設して障害児たちの面倒を見たし、吉行が肝臓ガンのため70歳で死ぬときには、二ヶ月間、付きっきりで看病した。医師も看護婦も、これほど精魂込めて看病する人を見たことがないと驚くほどの看護ぶりだった。吉行淳之介のいまわの際の言葉は「まりちゃん」だった。
吉行淳之介は、その洗い晒したような風貌や、その老熟した作家の眼によって、同業者やマスコミ関係者からコワモテしていた。その印象を和らげるために彼は、「ももしり3年」などと言っておどけて見せたが、それも彼の声価をたかめる原因になった。
しかし吉行は、ファニーな少女に幻惑される純な少年の心も隠していたのである。彼はその特異な家庭環境の故に、子供の頃から、幼な心を内に封じ込め、大人の目で周囲を見ていたのかもしれない。宮城まり子と知り合ったとき、彼の内面深くに秘められていた幼な心がよみがえってきたのではないか。
吉行と宮城まり子は、家では子供のように自由に振る舞っていた。宮城まり子の話で面白かったのは、吉行がそばに宮城まり子がいてくれた方が執筆が進むといって彼女を書斎に呼び寄せ、椅子に座らせていたという挿話だった。暫くすると、吉行はじっとしていられると気が散る、何か読んでいてくれと命じ、彼女が言われたとおりにすると、紙をめくる音がうるさいとか、なんだかんだと注文を付けたという。
訳知りの苦労人だった吉行淳之介が、こうした子供のような振る舞いをするとはちょっと信じられないが、彼が好き勝手なことを要求したのも、相手が宮城まり子だったからである。二人は心を許した「純愛」の日々を送っていたからこそ、吉行はバーに出かけて女を買い、男娼と寝るようなこともしたのである。吉行淳之介の眼にかかれば、どんな悪女の手練手管もお見通しで、彼は女たちの術策を内心で楽しんでいた。こうした放蕩を続けたのも、宮城まり子をバックにしている吉行の安心感から来ている。
作家と女優の共同生活が、35年間も破綻なく続いたのは、愛する相手が好きなことをするのを妨げないという相互の黙契があったからだった。これも二人が、深いところで子供同士として結びついていた証左ではないだろうか。幼い恋人たちは、遊ぶときには、それぞれギャングごっことか、人形遊びとか、男女別々のことをするものである。