茅葺きの家
このホームページに茅葺き屋根の写真を載せようと思って、バイクを走らせたけれど、なかなか見あたらない。その理由が分かったのは、幹線道路から脇道に入り込んで、一車線半位の細い道を走っているときだった。
目的の家は、幹線道路の周辺では見つからないのである。そこから離れた脇道に入ってゆけば、かなりの確率で茅葺き屋根の家を発見できるのだ。
最初に見つけたのが、下図の家だった。
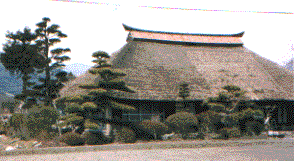
周囲に邪魔になるものが無かった。それで、茅葺き屋根の全景を、そっくりカメラに収めることが出来たのだった。
この写真を撮ってから、その近所をバイクで走っていたら、直ぐ近くにもう一軒茅葺きの家があった。

その家は回りに直線状の青垣を巡らしていて、玄関にはいるのに迷路ゲームのルートのような区画を通って行くのである。
(面白い家があるものだな)と思ってこの家の写真をたくさん撮った。

側面に移動すると、上図のような蔵があった。蔵の壁は塗り直したと見えて、ピカピカに光っている。にもかかわらず、母屋は古色蒼然としている。つまり、この家の住人は、今では残り少なくなった茅葺き屋根の家を心から愛しているのだ。新しく家を建て替えることもできるが、あえて古い家に住んでいるのである。

あえて茅葺きの屋根を残していると言えば、上図の寺院もそうだ。これは伊那山脈の中腹にある、かなり大きな寺である。周囲の植え込みや、石段、鐘楼などの手入れが行き届いているところをみると、経済的にも安定した寺だと思われるのに屋根は茅葺きなのだ。

茅葺き屋根の家が、景観として美しいことは疑いない。上図の家などは、日本画はもちろん、油絵の素材としても絶好だと思うのだが、どうだろうか。
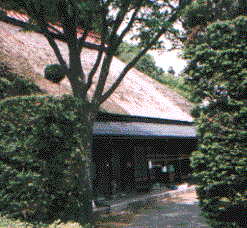
市の中心から離れて、村部に入り込むと、上図のような家をちょいちょい見かける。
家の周囲に風よけの木を植え、それを防壁のように高く育てている。その切れ間が入り口になっていて、そこから母屋の縁側や物干し場が見える。変に懐かしい光景である。ちょいと中に入ってみたいような親近感がある。

茅葺きの屋根は、雨水の浸入する屋根のてっぺんを注意してカバーする必要があるらしい。昔は囲炉裏を使っていたから、屋根の頂上に煙り出しを設ける必要もあって、この部分の作りには神経を使ったようである。
このため、どの家もてっぺんの棟の部分に趣向を凝らしている。上の家はトタン板でカバーして、それを赤いペンキで塗り上げている。
次の図は、もう少し手の込んだ作りになっている。

茅葺き屋根の家は、冬温かく、夏涼しく、暮らしてみるとなかなか快適だそうだが、泣き所は二階建てにすることが難しく、どうしても一階建ての、ただっぴろい平屋になってしまうことだ。すると、家の中が暗くなる。それを防ぐには、北側を除いて、三面に窓をめぐらすことである。次の図は外光を取り込むために窓やガラス戸を多く取り付けた家だ。

何といっても、茅葺き屋根の最大の欠点は、素材の不足、屋根葺き職人の不足で、葺き替えが不可能に近くなっていることだ。今度、いくつもの茅葺き屋根を見て回って、ほとんどすべての屋根が耐用年数を超えてしまっているらしいことに気がついた。

上図の屋根は、老人の肌のように、縦皺が走り、表面の凹凸が目立つようになっている。
素材である茅が脆くなって、崩れはじめているのだ。

白線で囲った部分に窪みが出来、そこに湿気が集まって草が生えている。
草の生えた屋根を、別の所でも見た。
屋根を補修しようにも簡単には出来ないということになったら、今ある屋根を慎重に保存して行くしかない。それには屋根全体をトタン板で包んでしまえばよい。茅葺き屋根をトタンで覆った屋根もあちこちで見かけた。次の写真はその一つである。

この家はトタンで覆われた屋根がバラ色に輝き、大変、印象的だった。古拙の形をした屋根、それが日差しの関係で目も綾な金属色で輝いているのである。
次の写真も、茅葺き屋根をトタンで覆ったものだ。前出の家もそうだが、この種の家は屋敷の内外がきちんと整っていて、遺漏のない感じがする。主人が伝来の家を愛し、自宅の庭を愛し、身辺を整然と整えているからなのだろう。
