ワイエスの名前を知ったのは、NHKの美術番組「日曜美術館」を見ているときだった。そこで紹介された彼の作品のうちの二点に心を惹かれたが、それ以外に格別の感想はなく、この番組で紹介される多くの現代画家と同様に、彼のことはそのまま忘れてしまうかに思われた。
ところが、問題の二点の絵が、どうしても頭から離れないのである。
その一つは穀物か何かを収納しておく納屋の羽目板を描いたものだった。水彩画に近いような淡泊な作品で、画面の大半が平塗りで描かれた板壁によって成り立っている。
もう一つも水彩画のように淡泊な絵で(実際、水彩画だったかもしれない)、これも何処にでもあるただの草原を描いたものであった。画面いっぱいに拡がる草が描かれているだけなのである。
イラストみたいにありきたりで、挿絵にあるように平明なこの二つの作品が、なぜか頭の中でどんどん鮮明になって行くのである。何処にでもある素材を描きながら、これら作品には精神的な輝きがあるからだった。私には、この二作品が存在の本質を指し示しているように思われたのである。
しかし、テレビでワイエスの絵を見てから10年あまりもすると、さすがに二つの絵の記憶も薄れてくる。すると、是非とも彼の作品にもう一度触れてみたくなった(私の手元にあるワイエスの図版は、「週刊朝日百科」〈世界の美術〉の68冊目に採録されていた「クリスティーネの世界」という作品だけである)。新聞にワイエスの展覧会に関する二行記事が出ているのを見たりすると、名古屋にでも、鎌倉にでも何処へでも出かけたくなる。
 「クリスティーネの世界」
「クリスティーネの世界」そのくせ、展覧会にも出かけず、彼の画集さえ手に入れる算段をしなかったのだから、どうかしている。私は思い立っても、実際に着手するまでに時間のかかる迂遠な人間なのである。そして、ようやく書店に行ってワイエスの画集を注文したときには、ワイエス画集3巻目の「ヘルガ」しか手に入らなかった。その他は、すでに絶版になっていたのだ。
こうなれば、この一冊の画集によって、ワイエスに接近していくしかない。画集の冒頭に載っている解説記事や、図版のあちこちにちりばめてあるワイエスの言葉を頼りに、彼のイメージを構築しなければならない。
ワイエスというのは、孤独な影をまとった不思議な画家だった。「アメリカの国宝」と呼ばれ、世界的な有名画家になったのに田舎に引っ込んで暮らし、ヘルガという農婦を15年の長きにわたって黙々と描き続ける。そして240点にも及ぶその作品を誰にも見せずに手元に保管していたのだ。「ヘルガ」は、その240点の作品をもとに編集された画集なのである。
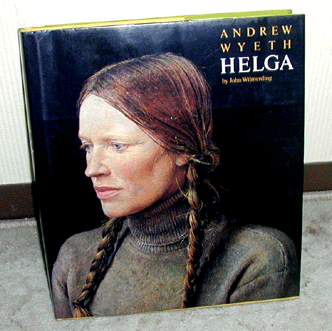 ワイエス画集Ⅲ「ヘルガ」
ワイエス画集Ⅲ「ヘルガ」彼は同一人物をモデルにして絵を描き続ける癖があるらしく、ヘルガをモデルにする以前にも、シリという少女をモデルにした連作を描いている。このときもワイエスは、シリが法的に成人に達するまで、このシリーズを秘密にして発表しなかった。
何十枚、何百枚という絵が、未発表のまま画家の手許に保管されていて、誰も気づかなかったのは、この時期に彼が別の作品を発表していたからだった。熊谷守一は年に数点しか絵を描かなかった。だが、ワイエスは、自ら「今までの40年間、狂ったように描き続けてきた」と告白しているように恐るべき多作家だったから、アトリエに秘密の作品を隠くしておくことも可能だったのである。
一方は極端な寡作家、他方は極端な多作家でありながら、熊谷守一とワイエスには共通するところがある。熊谷守一のことを頭に置きながら、ワイエスの生き方を探ってみよう。
ワイエスは芸術的な雰囲気の中で育っている。父親は挿絵画家としても知られる職業的な画家だった。彼は父のアトリエで絵の手ほどきを受け、画家として一本立ちしてからは、ニューヨークやロサンゼルスには住まず、ペンシルベニア州にある古い邸宅を買い取って住まいにしている。そのためか、ワイエスは人間嫌いとして知られている。
18世紀の昔に自然石で建てられたこの家は、母屋・アトリエ・製粉所の三つの部分から成り立っていた。製粉所は水車で石臼をまわす三階建ての大きなものだったが、ワイエスはこれを丹念に修復して水車が昔通りに動くようにした。
このほかに彼はメイン州の農村に別荘を持ち、本宅と別荘の間を行き来しながら数十年を過ごしている。彼は華やかな都会を嫌い、田舎の限定された場所で生きることを求めた。孤独と瞑想を好んだ彼は、「ひとつの対象を発見すると、そこに世界が見つかる」とか、「平凡なものも注意深く観察されて、すばらしいものになる」と言っている。
彼の同じような発言を随所に発見することが出来る。
「平凡なことがいい。だが、それを見つけるのは容易なことではない。平凡なものに信頼を置き、それを愛したら、その平凡なものが普遍性を持ってくる」
「私は秋と冬が好きだ。その季節になると、風景の骨格が感じられてくる。その孤独、冬の死んだようなひそやかさ」
「あるものとじっくりつき合っていると、しまいには自分がそのなかに生きているような気がしてくる」
田舎に住み、身近にある平凡なものと深くつき合うというワイエスの生き方が、その独特の作品群を生んだのだった。メイン州の別荘にいるときには、彼は隣りに住むクリスティーネ・オルソンをモデルにして描き続け、クリスティーネが亡くなると、近所に住む少女シリをモデルにして多くの連作を制作した。
本宅でも同じだった。隣の農場主カーナー夫妻のそれぞれをモデルに大量の作品を製作し、カーナーが病気になると、その看病にやって来た近所の農婦ヘルガをモデルにして絵を描き続けた。そして、それが15年間の長きに及び、240点もの作品となって結実するのだ。
ヘルガは、若くもないし、美しくもなかった。ワイエスが初めてヘルガを鉛筆でスケッチしたとき、彼女はすでに38歳になっていた(ワイエスは53歳だった)。彼が見栄えのしないヘルガを描き続けたのは、彼女が辛抱強く、寒い戸外に立たせても雪や風に不平を言うことがなかったし、屋内では命じられたポーズを忠実に守り続けたからだった。次に示すのは、最初に描かれた38歳のヘルガ。
 最初のスケッチ
最初のスケッチ次のものは、最後に描かれたヘルガで、15年が経過しているが顔立ちはほとんど変化していない。
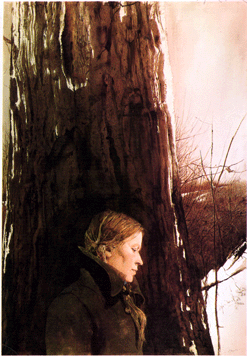 「隠れ家」
「隠れ家」同一のモデルを手を変え品を変えて240点も描き続けたのは、名もない一人の中年女の中に無尽蔵ともいえる魅力が潜んでいたからだ。「ページ・ボーイ」という名前が付けられた次の作品には、沈鬱で禁欲的なヘルガが描かれている。
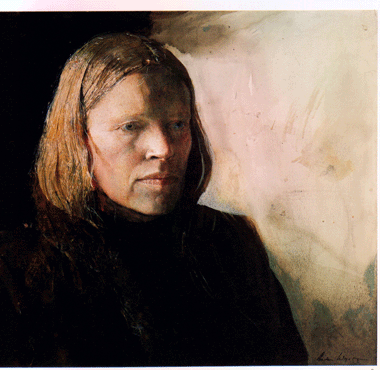 「ページ・ボーイ」
「ページ・ボーイ」だが、「恋人たち」と題する次の作品では、ヘルガは意外に豊満な肉体を見せている。
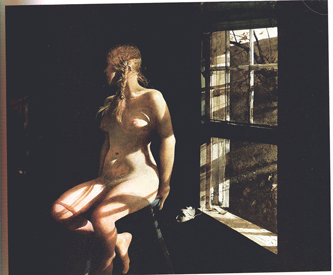 「恋人たち」
「恋人たち」同じ裸体でも背面から描くと、また、別の魅力がある。次は「仮収容所」と題する二点。
 「仮収容所」のためのデッサン
「仮収容所」のためのデッサン
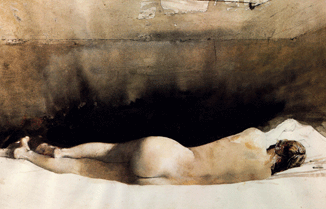 「仮収容所」
「仮収容所」
ヘルガ像は、鉛筆・水彩・油絵具・テンペラなど、多様な素材で描かれている。参考のため水彩で描かれた小品も挙げておきたい。
 「果樹園にて」
「果樹園にて」ヘルガシリーズは、モデルの年齢や風貌の関係もあって、全体として暗く重い感じがする。その点は、冒頭に紹介した「クリスティーネの世界」と比較してみれば明らかになる。
 「クリスティーネの世界」
「クリスティーネの世界」
ヘルガの娘
「農道」
「クリスティーネの世界」は、遠くに住宅を望む丘が背景になっている。丘は枯れ草で覆われているけれど、全体の印象は明るく、ロマンティックな感じさえする。だが、「ヘルガの娘」と「農道」の背景は「クリスティーネ」に似ているものの、丘は暗い色で塗られ、もはや牧歌的な感じはない。室内でヘルガを描いた絵になると、暗鬱な印象が一層強くなり、作品に閉鎖的で秘密めいた感じが濃くなる。
ワイエスが同一の対象を繰り返し描く理由は、どうすれば作品に精神的な深さを盛り込むことができるか模索を続けていたからだ。彼が描こうとしているのは芸術的な作品というよりも、魂の救済をもたらすような作品なのである。そのために彼は、角度をずらし、構図を変え、背景を入れ替えるなど、あらゆる努力をしている。そしているうちに、構図は次第に単純明快になり、背景からはよけいな付加物が削り落とされて、画面は世界の素形を示すように純化されて行く。
彼が「狂ったように」絵を描き続けるのは、そうしなければ内部の虚無感に押しつぶされてしまうという事情もあった。彼は書いている。
「私は静かに瞑想しながら考える。人は皆孤独だと。人がいつも感じるのは哀しみだと」
「人はよく私の絵にはメランコリーが漂っているという。たしかに私には強い無常感があり、なにかをしっかり捕まえていたいという憧れがある」
ワイエスは自らのメランコリックな気分に対抗するために、内部に物語の世界を育てはじめた。彼は述懐する。
「私はものごとに対してロマンティックな空想を抱いている。それを私は絵に描くのだが、リアリズムによってそこに到るのだ」
内面に憂鬱な気分とロマンティックな夢想を同居させていた彼が、制作の面でロマン的な世界をリアリズムでもって表現するという矛盾した方法を採用したのは興味あることだ。彼は、夢を現実で裏付けることによって芸術作品にしたのである。
内面に明と暗を抱え込んでいたが、ワイエスは当初「明」に比重をかけた作品を描いていた。初めてワイエスの絵を見たときから、私の心に焼き付いている二枚の絵(羽目板と草原の絵)も、明るい向日的な作品だったし、「クリスティーネの世界」もそうである。それがヘルガ・シリーズになると、明暗のバランスが崩れて「暗」に傾斜している。
ワイエスと熊谷守一は、平凡なものに目を向け、それを静かに観察し続けた点で共通していた。彼らが愛した風景も人物も、人が見捨てて顧みないようなものばかりだった。だが、観察を続けているうちに、彼らは対象の具有する本来の骨組みを自得するようになって、それを画布の上に写し取ることが出来るようになったのである。
人が「美しい景色」や美女を愛するのは、それらが希少だからである。希少価値を我がものにするには、世俗の世界に身を置いて、食うか食われるかの競争を演じなければならない。だが、普遍的な真実や永遠なるものは、どこにでもある平凡なもののなかにある。これを追求するのに埃を立てて走り回る必要はない。「その居に安んじる」という日常、そして目の前にあるものを静かに眺めるという習慣があれば、十分なのである。
ワイエスも熊谷守一も、静かに生きた。だが、違いも大きい。ワイエスが憑かれたように描き続けたのに対して、熊谷守一は寡作であり、ワイエスがリアリズムの道を押し進めたときに、熊谷は抽象画に近い独自の画風を開拓している。晩年のワイエスは暗い方向に傾斜していったが、熊谷守一の方は年を追って明るくなっている。これには、西洋と東洋の差が影響しているのであろうか。