1
書棚を調べていたら、辻潤に関係した本が二冊出てきた。
ひとつは昭和5年に出版された「絶望の書」(辻潤)で、とにかく古色蒼然たる本である。裏表紙には鉛筆で「40」と記入してあるから、この古本を戦後になって40円で購入したことが分かる。
もう一つは三島寛という精神病医が書いたパトグラフィ双書中の一冊「辻潤」で、こっちの方は新本で購入した。だが、窓を開けたまま本を机の上に出しておいたため、雨が吹き込んでびしょぬれになり、表紙がひん曲がってしまっている。二冊とも、それぞれ本としては難点があるので、これまで私はこれらを手にとって読むこともなく過ぎていたのだ。
伊藤野枝のことを調べている際、辻潤の本が何冊かあったはずだと思出して探したが見あたらなかった。だが、彼女と大杉栄に関する記事をHPにアップした後になって、この二冊が見つかったのである。必要な参考書がちゃんと書棚にあるにもかかわらず着筆中に見逃してしまうという現象は、三島由紀夫や芥川龍之介について調べているときにも起きている。
 「絶望の書」
「絶望の書」 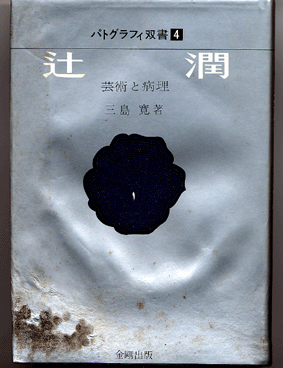 パトグラフィ双書「辻潤」
パトグラフィ双書「辻潤」
さて、改めてこれら二冊の本を読んで、辻潤と大杉栄の精神史が実によく似ていることに驚かされた。第一に、二人はほぼ同時期にうまれているのである。辻潤の出生は明治17年10月4日であり、大杉栄はその三ヶ月後の明治18年1月17日に生まれているのだ。
大杉は陸軍幼年学校に入学するために新発田中学を二年で中退した。辻潤の方は学資がつづかなかったため開成中学をやはり二年で終えている。青年期に入って内村鑑三の影響を受けクリスチャンになり、そしてキリスト教を棄ててから「平民新聞」の読者になる点も同じで、二人はまるで双生児のようによく似たコースを歩んでいる。大杉は辻宅を訪ね、辻潤が「平民新聞」を初号から大事に保存していることを知って感銘を受けるのである。
大杉はその後社会主義者になるが、辻潤は上野高等女学校の教員になる2年前、「社会主義夏期講習会」に参加していながら、実践運動にタッチすることはなかった。しかし、辻は左翼運動への同情を生涯持ち続けた。彼はマルクスには心から敬意を払っていたけれども、集団への嫌悪と徒党精神の欠如から「橋の手前」で踏みとどまったのだ。二人が、左翼思想を持ちながら、スチルナーの唯我哲学に傾倒している点も共通している。
辻潤と大杉の似ているのはここまで、以後の辻はダダイストになり、大杉がアナーキストになって相反する方向に進んだように見える。しかしダダイストもアナーキストも、日本的順応主義に反旗を翻しているという点では同じなのである
日本人には、社会全体の傾向に自らを合わせ、外部の権威に随順することを競い合う傾向がある。だから、吉本隆明などは連帯よりも自立を先行させるべきだと説くのである。
大杉栄は、日本的順応主義の根っこには奴隷根性があるという。そして、マルクスの理論に忠実な経済学者や社会主義者をも、奴隷根性に毒されていると酷評する。辻潤も「凡そダダイストにとってはこの世に許され得ない言語行動などというものは一つとして存在し得ないのである。・・・・・彼は何を選択しなければならないかというような一切の義務をも責任をも感じないのだ」と述べて、世のモラルや秩序を公然と無視した。
だから辻潤にも危険思想の持ち主だとして警察の尾行がついた。大杉は逮捕されても傲然たる態度を崩さなかったが、辻潤は警官の前で「天皇陛下バンザイ!」と叫んだり、「お前は、共産主義者だろう」と尋問されて、「いえ、降参主義です」と答える。不服従のための表現法は異なるけれども、権力に屈服しなかった点で両者は共通している。とにかく二人とも、パフォーマンスの達人だったのだ。
大杉が「一等俳優」だったとすれば、辻潤も一等俳優だった。辻は何度も精神病院に強制入院させられているが、彼の狂気も実は佯狂(詐病)だったのではないかという疑いが濃い。社会的締め付けの強い社会では、信念を貫き通すには奇行によって自己を韜晦しなければならず、辻も大杉も有名人として活躍する立場上、「奇人」「変人」という中江兆民以来の伝統的なカモフラージュを借用しなければならなかったのである。
2
札差の家に生まれた辻潤は、幼い頃、四、五人の女中にかしずかれた典型的なお坊ちゃまだった。母は世間知らずの家付き娘で、養子だった父もごく常識的な男だった。だから、彼は誰に頭を押さえられることもなく、のびのびと育っことができた。
だが、明治維新後、旧幕時代に培ってきた蓄えも乏しくなって、父は東京市役所教育課に勤務することになる。だが、無能な父は程なく整理され、生活は日を追って苦しくなった。辻は父のことをこう語っている。
「(父は)無能で淘汰されてからは、士族の商法のような骨董屋を始めたが、それも一向商売にならず、始終生活を脅かされ、挙げ句の果てには、気が狂って死んでしまったとは、なんたる愚にも気の毒なおやじだったことよ」
彼は父が狂死したと語っているけれども、事実は井戸に飛び込んで自殺したのである。こうした父の血を引いたためか、辻潤には戦う前から負けを選んでしまうような弱気なところがあった。彼は自伝的な小説「三ちゃん」のなかで、自分の肖像を次のように描いている。
「自分は、母から弱虫とか意久地なしとかいわれるたびに、はなはだ残念に思ったのです。自分は、元来幼ないころから、人の前に出ることなど嫌がった性分で、朋友遊びもあまり出来なかったので、自然、人から臆病だと思われておりました」
父の死によって、開成中学を二年で退学しなければならなかった辻潤は、伝手を求めて会社の給仕になった。
「内気の自分は、最初のうち、口もロクロクきけず、嫌で嫌でたまりませんでした。そのころの楽しみというものは──悲しい中にも楽しみはありました──乏しい月給の幾分を割いて、好きな小説を読むこと、散歩することくらいでした」
給仕をしながら、彼はどんな本を読んでいたろうか。後年、彼は幼児期には「西遊記」、十四五才になってからは「徒然草」を座右の書にしていたと語っている。
「(西遊記)が、ボードレールになり、ホフマンになり、ポーになるのになんの不思議なことがあろう? (徒然草)が老荘になり、伝道の書になり、スチルナアになり、スターンになり、セナンクールになり、レオパルヂになるのに、なんの不思議なことがあろう?」
余暇に読書に熱中しながら、彼は嫌で嫌でたまらない会社勤めから脱出するために語学によって身を立てようと考え始める。伝統的な日本社会に息苦しさを感じる若者が、語学に関心を持つのは自然の流れといっていいだろう。大杉も語学が好きだった。
辻潤はアテネ・フランセ・国民英学会・自由英学会などの聴講生になって、英語の勉強に打ち込んだ。好きなことにはとことんのめり込む性格が効果的に働いて、彼は間もなく英語の原書を苦もなく読みこなすようになった。
「自分は独学の書生である。故にひどく変則で、なにごとによらず、自分流儀にしか出来ない。これは、少年の時から自修の癖がついて、それが、骨の髄まで染み込んでしまったというところだ」
16才になると、彼の読書傾向は一変した。語学の勉強中に、キリスト教のテキストに触れて、宗教的な世界に関心を持つようになったのだ。
「子供のくせに、おかしなほど真面目で、教会にいくようになってからというものは、自分の好きな小説は一切仕舞い込んでしまった。……それから、にわかに三叉の(キリスト伝)、内村先生の(求安録)、村田某の(ルーテル伝)などに早変りをした」
辻潤の弟が語るところによれば、「兄貴は24,5才までは模範青年で、酒もタバコもやらなかった」という。辻は子供の頃から「おかしなほど真面目」な少年だったのである。
もともと内向的で人間嫌いだった彼は、クリスチャンになったことで、いよいよ孤独を愛するモラリストになった。彼は会社を辞めて小学校の教師になり、かたわら私塾のやとわれ教師になったりした。やがて、彼は英語の実力を見込まれて、25才で上野高等女学校の教師になる。その前年に父が飛び込み自殺をしているから、彼は母と妹を扶養して行く為にも上野高女からの収入を必要としていたのだ。
「24,5才までは模範青年だった」というのが本当だとすれば、辻は上野高女に就職し、伊藤野枝と恋愛関係になるまでは真面目だったということになる。つまり、彼がポケットをひっくり返すように「無頼な人間」になったのは、野枝と暮らすようになってからということになるのだ。
3
辻潤が養っていたのは、善良ではあるけれど生活力に乏しい母と妹だった。辻を溺愛していた母親は、野枝との問題で上野高女を追われた息子が新しい仕事を探そうともせず、家でぶらぶらしていても、息子を叱ろうとしなかった。そればかりか、「おまいさんも、着たきり雀で可哀想だねえ」と息子に同情して涙ぐむというありさまだった。そういう善人ばかりの貧しい旧家に、伊藤野枝というとびきりバイタリティーに富んだ九州女がとびこんできたのである。
20代の半ばまで女を知らなかった辻は、学校を退職してからというもの、夜も昼も野枝との愛欲生活に惑溺した。やがて野枝が雑誌「青鞜」で活躍するようになると、性生活だけでなくあらゆる意味で野枝に依存して生きるようになった。
辻はゴーストライターになって野枝の名前で翻訳を発表した。原稿の売り込み先も野枝に探してもらった。「天才論」の翻訳が日の目を見たのも、野枝が出版社と辻の間に仲介に立ったからだった。だが、「天才論」がベストセラーになり、辻の名前が世に知られるようになると、これはマイナスに働いた。辻が全く働かないようになったのである。
そのうちに野枝と木村荘太の「恋愛事件」が新聞を賑わし、そこらの寄席までが二人の関係を新講談にして売り物にするようになった。ショックを受けた辻は、野枝をなじろうとしたが言葉にならず、筆談で胸の内を相手にぶっつけている。野枝も筆談で応じ、同じ家にいながら彼らは書面で対話したのだった。この恋愛事件で一躍「青鞜」の看板ライターになった野枝は、平塚らいてうから奪い取るようにして「青鞜」の編集長になる。そして、アナーキストの大杉栄と深い仲になり、辻に対して離婚を切り出すのだ。
辻は表面上別れ話を淡々と受け入れたが、その傷心は大きかった。彼はこの直後、土岐哀果宛の手紙に、「例の一件コノカタというもの、一通りや二通りのショゲ方ではなく──日に二度食べる御飯ですら、辛うじてノドへ通るか通らないかという有様で、型のごとくエンセイヒカン──その意気地のなさ加減と来たら、実にもってお話のホカです」と訴えている。
彼はショックを和らげるために上野寛永寺の一室に閉じこもり、何とか元気を取り戻した。そして、下谷稲荷町に引っ越し「英語・尺八・バイオリン教授」の看板を出した。尺八の修行を彼は15歳の時から始めており、弟子を取ることができるだけの腕前になっていたのである。
辻はこれらの教授で細々と食いつなぎながら、さかんに浅草の興行街にいりびたり、舞踊家の石井漠、オペラ役者の伊庭孝、評論家の安成貞雄などと交わっている。そして、浅草オペラの役者が足りなくなると、エキストラになって舞台に上がり小遣銭にありついたり、文芸講演会の講師になって謝礼を貰ったりしていた。
添田知道が「未来派講演会」と題する集まりに出かけたら、講師の辻潤が赤ん坊を抱いて壇上に出てきて、ぼそぼそ話をしていたという。
重症の「引きこもり病者」だった辻が、オペラの舞台に立ったり、講演会で話をしたりするにはアルコールの力を借りる必要があった。酒が入っているときにだけ、彼は外部の刺激に耐えることが出来た。だから、これまで渉外係を引き受けていた野枝を失ってからは、彼は酒を常用して世間に立ち向わなければならなかったのである。かくて辻は、野枝と離婚後急速にアルコール依存症になっていく。
辻は、離婚後の5年間、作品らしい作品を一つも書いていない。浅草でオペラ・ゴロの生活をつづけたのちに、彼は心構えを新たにして武林無想庵の紹介で比叡山宿坊にこもり、スチルナーの翻訳に着手したものの、訳稿はなかなか完成しなかった。
比叡山でスチルナーを徹底的に読み込んだことは、辻に大きな変化をもたらした。一皮むけたのである。
僕はスチルナーを読んで初めて、自分の態度が決まったのだ。ポーズが出来たわけだ。そこではじめて眼が覚めたような気持ちになったのだ、今までどうにもならないことに余計な頭を悩ましてきたことの愚かなことに気がついたわけだ(「自分だけの世界」)。
彼は自分の性格が「水性」であり、別れた妻野枝の方は「火性」だったことに思い当った。所詮、二人は別の世界の人間だったのである。彼は考えた、これまでの偽りの生活をさらりと捨て、自分の本質に則して生き直さなければならぬ。
自分はなによりも先ず無精者だ。面倒くさがりやである。常に『無為無作』を夢みている。無目的にまったく飄々乎として歩いていると、自分がいつの間にか風や水や草やその他の自然の物象と同化して、自分の存在がともすれば怪しくなってくることは、さして珍らしいことではない。自分の存在が怪しくなってくる位だから、世間や社会の存在は、それ以前に何処かへ消し飛んでる。そんな時に、どうかすると『浮浪人の法悦』というようなものを感じさせられる(「浮浪漫語」)。
教師になり、その収入で母と妹を養っている頃、辻は対人恐怖症者だった。お人好しの家族が寄り集まり、互いを慰め合って暮らしている時にだけ、安らかな気持ちになれた。その家に野枝がやってきて、社会に通じる風穴を開けてくれたのである。
野枝が去ってしまうと、彼は妻が開けてくれた風穴から世間に出て行って、酒の力を借りて食い扶持を探すことになった。すると、感情の逆転が起ったのである。静止していることに不安を感じるようになった。彼は身体のどこかに酒の酔いを感じながら、静から動、安定から不安定を求めてあてどもなく歩いているときに、「浮浪人の法悦」というようなものを感じるようになった。
辻は「酔生夢死」という言葉を愛し、「浮遊して求めるところを知らず、猖狂して往くところを知らず」という生き方を求めるようになった。放浪の後半生が始まったのである。
 辻潤
辻潤4
手元にある「絶望の書」「パトグラフィ双書─辻潤」の二冊だけを読んで、辻の人生を概観しようとすると、手に余ることが多い。例えば、評伝の体裁を取っている「パトグラフィ双書─辻潤」には、辻の放浪生活のはじまりを比叡山の宿坊を出てからとしている(辻─33才)。と思うと、同じ本の別のところには、放浪生活は東京市内を尺八を吹きながら門付けをしていた昭和10年頃(辻─51才)から始まるとしている。
分からないのは、辻が各地を放浪したり精神病院や留置場に放り込まれている間に、母や妹、それに長男の一(まこと)はどうしていたかということだ。妹はその後結婚しているし、母は仕立屋をしていた辻の弟義郎に引き取られたかもしれないから心配ないとしても、長男のまことは辻が育て、パリに出かけるときにも一緒に連れて行っているのだ。この父子がどんな暮らしをしていたのか、少なからず気になる。
彼の生涯については分からないことばかりだが、比叡山の宿坊を下りてからの彼がその頃世間の耳目を集めた神近・大杉による日蔭茶屋事件の隠れた関係者として、ジャーナリズムから注目されだしたことだけは確かなようである。年譜を見ると、下山の翌年には「阿片溺愛者の手記」「狂楽人日記」の訳書を出版しているし、やっと完成した「唯一者とその所有」の翻訳を4回に分けて雑誌に連載している。
各種の翻訳を雑誌に掲載しながら、虚無的な色彩の濃い独白・随想・交友記・生活記録のたぐいを発表しているうちに、彼はいつの間にか日本におけるダダイズムの始祖になっていた。辻は、この立場から高橋新吉・林芙美子を世に送り出し、世に先んじて宮沢賢治の「春と修羅」論を評価する批評を読売新聞に書いている。
大杉栄と野枝が憲兵隊で虐殺されたときには、辻は押しも押されぬ文壇の雄になっていた。事件後、彼は野枝を追想する文章を書いた。
夕方道頓堀を歩いているときに、はじめてアノ号外を見た。地震とは全然異った強いショックが、僕の脳裡をかすめて走った。それから僕は、何気ない顔付をして俗謡の一節を口吟みながら、朦朧とした意識に包まれて、夕闇の中を歩き続けていた。野枝さんは僕と約六年たらず生活して二人の子を生んだ。だから新聞では、僕のことを野枝の先夫だとか亭主だとか書くが、いかにもそれに相違なかろう。だが、僕のレエゾン・デートルが、野枝さんの先夫でのみあるような、またあたかも僕がこの人生に生れて来たことは、伊藤野枝なる女によって有名になり、その女からふられることを天職としてひきさがるようなことをいわれると、僕だとて時に癪にさわることがある。
・・・・・・ 野枝さんのような天才が、僕のような男と同棲して、その天分を充分に延ばすことの出来ないのははなはだケシカランというような世論がいつの間にか僕等の周囲に出来あがっていた…。
野枝さんは、メキメキ成長して来た。僕とわかれるべき雰囲気が充分かたち造られていたのだ。そこへ、大杉君が現われて来た。一代の風雲児が現われて来た。とても耐ったものではない。
・・・・・僕のようなダダイストにでも、相応のヴァニティはある。それは、ただしかし世間に対するそれではなく、僕自身に対してのみのそれである。自分は、いつでも自分を凝視めて自分を愛している。
自分に恥ずかしいようなことは出来ないだけの虚栄心を、自分に対して持っている。ただそれのみ。世間を審判官にして争うほど、まだ僕は自分自身を軽べつしたことは一度もないのである。
代表的なダダイストとして世間から一目置かれるようになってからも、辻は世俗の目を過剰に意識し、野枝に棄てられた男と見られることを気にしている。辻には根深い劣等感があり、それを押し返す大衆侮蔑の感情も持っていた。
社会意識がない、独善だ、不真面目だ、馬鹿だ、──その他、なんでもかんでもどんな悪罵でも冷罵でも私は謹んで引き受ける。
と殊勝な表情で書いたと思うと、「まったく今の民衆野郎の低脳無智下劣浅薄なのには呆れケエルが何匹跳ね返っても足りないくらいさ」と居直ってみせる。野枝を追想する文章にも、こうした彼の屈折した心情があらわに出ている。
大杉・野枝虐殺事件の後、改めて野枝の前夫の辻の動向が注目されるようになった。そのせいか、彼の本はよく売れるようになり、昭和5年11月5日発行の「絶望の書」は、その月の末に早くも第6版を出している。
普通なら、これだけ羽振りがよくなったら、ペン一本で十分に食っていけたはずである。ところが、彼は何時も借金に追われ、大正の末年には、新居格・村松正俊・室伏高信・宮島資夫・加藤一夫らを発起人とする「辻潤後援会」の援助を受けなければならなかった。
彼は東京の蒲田に暮らしていた頃、戸締まりもしないで深夜の来客を誰でも迎え入れていた。それで、彼の住む長屋は仲間によって「カマタホテル」と呼ばれていたが、後援会の発起人に名前を連ねている面々は、このカマタホテルの厄介になった者が多かった。こうした八方破れの暮らしぶりやら過度な飲酒癖が、彼を常に経済的な危機に追い込んでいたのである。
何時も借金に追われている辻にも、幸運が訪れてきた。「唯一者とその所有」が春秋社の世界大思想全集中の一冊に採用され「大金」が転がり込んできたのだ。その印税の予想外の多さにたまげたらしく、彼はこれを「莫大なめくされ金」と言ったり、自分のことを「印税成金」と呼んだりしている。
この金で、中学生の息子を連れてパリに出かけることにしたのも、いかにも辻潤らしかった。彼は金のつづくかぎりパリに滞在することにして、読売新聞社から第一回パリ文芸特置員にしてもらった。新聞社と契約して定期的にに文芸通信を送りつづければ、その報酬でパリ滞在期間をのばせると考えたのである。
だが、彼はパリに着いてもほとんど出歩くことがなかった。パリ到着後の最初の一ヶ月間は、安ホテルに閉じこもって日本から持ってきた中里介山の「大菩薩峠」と観音経を読んで過ごした。息子のまことは、既に船内で「大菩薩峠」を読んでいたが、父の読み終わったこの本をもう一度読み返しているので、辻は「いい加減でやめろ」と注意しなければならなかった。
辻は、「大菩薩峠」のお陰で、「フランス語の勉強をソッチのけにしてしまって、この一ヶ月あまりを親子二人で棒にふってしまった」とフランス滞在記に書いている。
それでも、まことは、間もなく自転車に乗ってパリのあちこちを見物に出かけるようになった。が、辻は相変わらず古新聞やタバコの吸い殻で足の踏み場もないほど散らかった室内に寝ころんで動かなかった。人に会うといえば日本からやって来た武林無想庵や村松正俊、林倭衛などだったから、折角パリまでやって来たのに彼は昔と変わらぬ生活をつづけた。
辻潤父子は、パリ滞在一年の後に、印税の金を使い果たして、かの道元のように「無所得」のまま日本に帰ってきた。得たものがあるとしたら、何処に行っても変わらぬ自分自身の気質を再確認したことだった。帰国後、辻はこれからもダメ人間でありつづけようと思い決めた。「低人教」の誕生である。
「低人」とは、ニイチェの「超人」に対抗して辻が考え出した造語で、これにはダメ人間はダメ人間として生きていくしかないのだという決意がこめられている。彼は他人と関わることも、働くことも好まないと語り、自分は社会人としての義務を果たす気はないと宣言する。
──僕は現在の社会制度に於いて如何なる職業にもありつくことを好まない甚だアンチソシャルな人間なのだ。──どんな人間でも、労働の嫌いな点で、僕にかなう人間はいまい。第一、そいつがどうしても避けられないときているから、益々僕は考えただけでも嘔吐を催したくなる。
──僕は結局自分に惚れてばかり暮らしてきた人間だといっていいかもしれない。したがって他人や、社会のことには、昔からあまり興味が持てなかった。(僕は)自画像を描いては、自慰をやっていた人間なのだ。
──人間は自分と類似な人間を好む。つまり結局自分が好きだというだけだ。
時代は満州事変前夜で、「治安維持法」によって左翼勢力を押しつぶしながら、軍部が暴走を開始した頃だった。ジャーナリズムの世界では、暗い未来を予見して、狂騒的なエロ・グロ・ナンセンスが流行し、辻潤のダダイズムもその変種として多くの読者に歓迎された。
吉行淳之介の父吉行エイスケも、辻潤の膝下にはせ参じた一人だった。
岡山の不良美少年エイスケ・ヨシユキなる変態性欲の問屋で、オスカア・ワイルドのお稚児さんよろしくといった男が、オリーブ色の鉢巻きをして「ダダイズム」をふりまわして僕のところに乗り込んできた。
辻はこうした同志や配下をバックにして、文壇の人気者に噛みついている。
菊池寛や久米正雄・・・・・仄聞するところに寄れば君達はなにかメリケンの下等な商人の真似をして取らすとを組織し、文壇?とやらを独占しようという計画だそうだが、万一それが本当の了簡ならコッチにも相当の覚悟くらいは持ち合わせていないわけじゃない。
だが、辻がこんな威勢のいい啖呵を切ることができたのも、僅かな期間に過ぎなかった。エロ・グロ・ナンセンスも、ダダイズムも戦時色を濃くして行くジャーナリズムから忘れ去られ、原稿の注文がすっかり途絶えてしまった。辻の飲酒癖が加速するのも、この頃からだった。
「泥酔することは、間接に、一時的に自殺することだ」と知りながら、彼は酒を飲み続け、「酒を呑まずに生きていられるような無神経な人間になれたらさぞよかろう」とつぶやく。実際、彼は酒を呑まないと人に会う気がしなかったし、会っても全く感興が沸かず、タバコばかりを吹かしていた。
辻が初めて「アルコール性幻覚症」の発作を起こしたのは、昭和7年3月のことだった。自分が天狗になって背中に羽が生えてきたという幻覚に襲われ、屋根から飛び降りたのだ。幸い、軽傷で済んだが、夜の街頭を怒鳴り歩くようになったので、彼は精神病院に入院させられることになった。
その後も、辻は錯乱状態に陥って、警察に検束され精神病院に強制入院させられることを繰り返している。入院中は飲酒が禁じられているため幻覚症状がなくなり、退院を許可される。だが、社会に出ると、たちまち深酒をして錯乱状態に陥るのである。
ある日、息子のまことが見舞いにいったら、入院中の辻が日向ぼっこをしていた。その肩には雀がとまっていて、まことが近づいていくと飛び去っていった。釈迦やフランチェスコにも同種の話があり、この手のエピソードには何となくうさんくさい感じがつきまとっているけれども、狂人や聖者が周囲に対して完全に無関心になれば、小鳥たちも安心して近づいてくるかもしれない。このエピソードは、辻の病気が佯狂などではなかったことを示している。
辻の一回目の入院時には、「辻潤後援会」が発足している。今度の会には、佐藤春夫・武者小路実篤・北原白秋・谷崎潤一郎などが名を連ね、文壇・劇団人らの揮毫した書画の即売展が開催された。その売上金は、退院後の辻の療養費として贈られた。
二回目の入院を終えて辻が退院したときにも、谷崎潤一郎・佐藤春夫・萩原朔太郎などが、「辻潤君全快祝いの会」を開いてやっている。彼は多くの文壇人に愛されていたのである。
しかし辻が性懲りもなく無銭飲食を重ね、酒を手に入れるために友人知己から借金をつづけると、旧友たちも彼を見放すようになった。辻は虚言と詐欺行為に明け暮れる自分自身を例の駄洒落で「日々是口実」と自嘲している。
東京を食い詰める形になった辻は、日中戦争が始まる頃には全国を放浪して歩いている。地方には、辻に心酔する「辻マニア」がいて、これら崇拝者の家を飛び石を渡るように歴訪して行けば野垂れ死にするおそれはなかった。
辻マニアの家に泊まると、彼は「死に瀕した犬の苦悶と、勲章をつけた将軍の断末魔との間に一体何処に相違があるのかね」というようなことを話して聞かせる。だが、それらはトルストイなどからの受け売りであり、それを自分の発想として語っているのだった。放浪をつづけるうちに彼は、こうした方法で相手を煙に巻く「芸」を身につけるようになっていた。
辻はパトロンの家で酔いつぶれ、タバコの火で畳に焼けこげを作ったりした。だが、彼が辞去するときには、家人は手ぬぐい・ちり紙・足袋・小遣い銭などを持たして送り出した。すると、辻はそれらを無造作に懐に入れて立ち去るのである。
辻の親友萩原朔太郎は、辻と弟子たちの関係を次のように述べている。
耶蘇の弟子達が、漁師や乞食であったように、辻潤の弟子もまた市井の『飢えたるもの』『貧しきもの』の一群である。彼はこれらの弟子たちに囲まれながら、たえず熱心に虚無の福音を説教している。しかし耶蘇のような態度ではなく、ヴェルレーヌのような酔態で、ヨタのでたらめを飛ばしながら説教する。そこで彼の弟子たちは不敬にも師のことを『辻』と呼びつけにし、時には師の頭を撲ったりする。これは不思議な宗教である。
・・・・・辻潤はいつも酔っている。もし酒を飲まなければ、生きることの苦悩と悲哀に耐えないからだ。彼はまさしく無能力者で、低人的痴呆のように見えるのである。それで彼の敬虔なる信徒たちが、喜捨の代りに御神酒を捧げ、ロボットの心臓部へ電気をかけて、脈の動きだすのを待っているのである。
かくして江戸前の駄酒落と共に、彼の心学低人教が始まってくる。それは弱者の宗教であり、無産者の宗教であり、エゴイストの宗教であり、性格破産者の宗教であり、そして同時に、最も純粋で悲しい近代インテリの宗教なのだ。
辻の放浪生活は、戦争が悪化するにつれて次第に困難になっていった。
彼の生活を支えてくれた弟子たちは、出征したり徴用に取られたりで数が少なくなった上に、食料が配給制になって何処の家でも辻に与える食事に窮するようになった。
辻は東京の淀橋区上落合にある知人所有のアパートにこもって動かないようになる。そして、食べ物を恵んでくれる者があれば食べるし、さもなければ何も口にしないようになった。昭和19年11月24日の朝、いつものようにアパートの管理人が外から声をかけたが、辻の部屋から返事がなかった。ドアを開けてみると、辻は部屋の中で餓死していた。
私が辻潤を愛する理由は、彼が日本的順応主義を最後まで拒み通したからである。諸悪の根源は、立身出世主義とこれに連動する日本的順応主義にあるのだ。