伊那谷の地政学
東と西
木曽谷と違って、伊那谷は横幅が広い。そこで、ここは谷ではないよ平坦地だよという意味で「伊那平」と呼ぶ向きがあるくらいだ。その伊那谷が天竜川によって二分されている。天竜川の東側を「竜東」、西側を「竜西」と呼ぶのがならわしだから、この言い方を使って両地区の違いについて考察してみたいと思う。同じ伊那谷でも、東と西では相当に違っているのである。
井月という乞食俳人の行動圏を調べてみると、両地区の違いが鮮明に浮かんでくる。彼は幕末に伊那谷に現れ明治20年に死去するまで約30年をこの地で過ごしている。この間井月は竜西地区にはほとんど姿を現さず、主として竜東地区を活動拠点にしている。竜東地区の方が、はるかに住心地が良かったのである。
俳諧に通じ、一種風格のある「書」を書く井月は、その才能を愛する旦那衆の家に立ち寄って酒を振る舞われ、一宿一飯の恩義に預かっていた。竜東地区には井月がやってくれば家に上げて、酒食を振る舞ってくれるパトロンが数多くいたから、彼は川東に居着いたのだ。彼が残している遺墨や短冊のたぐいも、その大半は竜東地区から発見されている。
井月が竜東地区から離れなかったのは、もっと単純な理由からかも知れない。乞食の境涯にある者にとって、一番の大敵は子供と犬だろうと思われる。井月を記念する文集を読んでいたら、地元で少年時代を過ごした人の追想記が載っていた。井月に石を投げつけて遊んだ後で、家に戻ってみたら顔から血を流した井月が来ていたので、ぎくっとしたというのである。こうした文章をみれば、井月がこの地を去らなかったのは、竜東地区に乞食をいじめる悪童や野犬が少なかったからだという想像も成り立つ。だが、もし悪童や野犬が少なかったとしたら、それも竜東独特の温和な土地柄のせいだったということになるのだ。
もう一つ、両地区の違いを際だたせているのが「部落」の問題で、竜西地区には存在しない「部落」が竜東地区にはいくつも残っている。東に乞食俳人を受け入れる旦那衆が数多くいたという事実と、「部落」がいくつも存在したという事実には、相互に何か関連があるだろうか。あるのである。守旧的傾向がそれで、竜東地区は、竜西地区に比べて、ずっと守旧的だったのである。
幕末期に竜西地区の富農や商人の間では、国学が流行していた。彼らの間には、時流に敏感に反応して尊皇攘夷運動に熱を上げるような進歩的な雰囲気があった。これに対して竜東地区の上層農民は、身辺の幸福に目を向け、昔ながらの生活に喜びを見いだし、乞食俳人を迎えてその時々の座興を楽しんでいたのである。西は古いものを捨て去って新しいものを追い求め、東は古いものに執着して新しいものを忌避した。では、両地区のこの違いはどこからきているのだろうか。
廊下地形と袋地形
天竜川を中心においてその左右を眺めてみる。下図の地図ではあまりハッキリしないが、天竜川が伊那山脈に沿うようにして流れていることは見て取れると思う。唯一の例外は、三峰川によって天竜川が西側に押しやられている部分で(そのあたりに伊那市がある)、竜東地区のその他地域は天竜川と伊那山脈に挟まれていて僅かな空間しか余していない。
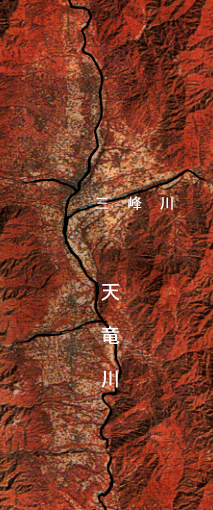
バイクで「竜東線」と呼ばれる竜東地区の幹線道路を走ってみると、天竜川と伊那山脈の間の細長い空間がいくつにも区切られていることが分かる。袋状の独立世界が一列に並んだような格好になっている。誇張していえば、竜東地区は行き止まりの袋状地を数珠繋ぎにして形成されているのである。
竜東地区を袋地形とすれば、竜西地区は廊下地形である。中央アルプスの麓は広々とした段丘になり、これが一続きになって竜西地区を長大な廊下に変えている。こうした地域には、中央の権力が入り込みやすい。律令政府は竜西地区を完全に支配し、ここに東山道を敷設している。江戸時代の中山道は木曽谷を通過しているが、それ以前、律令時代・平安朝時代の幹線道路は美濃から御神峠を越えて伊那に入り、竜西地区を縦貫して北上していたのである(現在、高速道路の中央道も同じところを通っている)。
東山道という官用道路が敷設され、公私の物資・人馬が往来することになれば、竜西地区に市場が発生し、職人や商人が住み着くようになる。そして、一旦こうしたルートができ、これを様々な職種の人間が支えるようになれば、その上を物資・人馬だけでなく新しい生活スタイルや文物が流れてくるようになって、古いものは駆逐されて行く。人文地理学の教えるところでは、廊下状地形には伝統や文化遺産が残らず、行き止まりの袋状地に古い慣習や伝統が残るのである。
中山道が木曽谷を通るようになってからも、竜西地区には伊那街道が栄えた。物資移動に関する限り、規制の厳しい中山道より伊那街道を流れる量の方が多かったのだ。江戸時代後半には中馬による物資輸送が盛んになり、伊那地方はその拠点になって行く。伊那には新時代の空気が流れこみ、幕末になれば反体制的な国学が流行したりする。だが、竜東地区はそうした空気とは無縁の旧態依然たる世界に止まっていた。
障害物としての天竜川
現代では、竜東と竜西の違いはほとんど消滅してきている。天竜川が東西を分かつ障害物ではなくなって、竜東地区と竜西地区が地続きのようになっているからだ。しかし昔は「暴れ天竜」の異名が示すように天竜川は毎年のように洪水を繰り返し、両地区を阻む険しい障害になっていた。江戸時代の記録を読むと、天竜川の流路が毎年のように変わるため、年毎に新たに木橋を架け替える必要に迫られている。
小中学校の頃、戦中派の私は、竜西地区に住んでいたが、川向こうは別世界のように遠く感じられていたことを思い出す。川向こうに親戚でもあればともかく、川を越えた向こうとの交流が皆無だったからだ。
明治以前、竜東の袋状地区で暮らす農民は、たまにしか川向こうの「町場」に出なかった。彼らは必要な物を村内の万屋で手に入れるか、自給自足によってすべてをまかなうかしていた。村の人口が少なく、農民主体の人口構成なら、村内で商いするのは万屋一軒で事足りる。ということになれば、商人同士の競争は起こらない。古いしきたりに従って商品を仕入れ、顔見知りの客に決まった量を売りさばいていれば商売は成り立つのだ。
竜東の村部で、明治時代を生きた老人から「昔は、金はなかったが、ゆったり暮らせたなあ」という話を聞いたことがある。たいていの物は自給自足していたから、金がなくてもやって行けたというのだ。
「村のお祭りには親類が来るんで、ご馳走を出さなきゃならん。しかし、そんなときだって、裏の竹藪からタケノコを掘ってきたり、囲炉裏の煙で薫製にしておいた川魚を出しておけばよかった」
老人から色々聞いた中で、面白かったのは川魚の話である。天竜川が作り出す網の目のような流路の一つを選び、その横腹に小さな池を作る。この盲腸のような池に松葉を敷き詰めておくと、川魚が入り込んできて卵を生み、養魚池のようになる。年に一度、この池の入り口を閉め切って魚を捕り、串刺しにして囲炉裏の自在鍵に巻き付けた藁筒にさしておく。すると、自然に魚の薫製ができあがる。これを春まで取っておいて、醤油(これも自家製)で煮て来客用のご馳走にしたというのだ。
天竜川が障害として立ちはだかっていたから、竜東地区には小単位の純農村が多く残った。ここへは外部から新しいものがなかなか入ってこなかったし、一度入ってきたものは容易に出て行かなかった。とすれば、この地区が守旧的になっていくのもやむを得なかったのである。
中央権力と地方権力
廊下地形の竜西地区には、中央の権力が進出してくるけれども、その支配力は天竜川に阻まれて竜東地区にはおよばない。そこで竜東地区には土着勢力が育つことになる。伊那谷の古墳を調べてみると、川の西側には箕輪町松島地区に「王墓」と命名された大きな前方後円墳が目に付くだけで、小さな古墳はあまり見あたらない。川の東側はこれとは逆で、巨大な古墳は存在しないけれども、「群集墳」と呼ばれる円墳が数多く見つかっている。
「王墓」に葬られているのが何者かは分かっていない。しかし、これほど巨大な墓が造営された事実をみれば、この地に広い範囲を支配した権力者がいたことは確実だろう。中央から派遣されてきた支配者が豪族化したか、あるいは在地の有力者が中央政府の支配下に入ることで次第にその支配力を強め、これほどの墓を作るまでに強大化して行ったに違いない。
竜東地区の集落は分散し自立しているために、地区全体を覆うほどの強力な権力者を生み出すことがなかった。それぞれの集落は村落内に居住する有力家族の連合体によって運営されていたかもしれない。段丘突端などに並んでいる円墳を見ると、形も規模も複製品のように酷似しているのだ。
中央の権力と地方権力が、天竜川を挟んで対峙するという構図は、古墳時代以降もずっと続いている。南北朝時代には、竜東地区は南朝を支持している。南朝の宗良親王は南信濃に落ちのびてきて、反中央的気分が濃厚な在地勢力に支持され、竜東の大鹿村に拠点を置いたのである。
中世期を通じて南信州における反中央的在地勢力の中心は諏訪にあったらしい。諏訪の勢力は杖突峠・金沢峠を経て秋葉街道筋に入り込み、竜東の村々をその影響下に置いたのだった。
幕藩体制が成立してからも、傾向としてはこの構図が残っている。高遠藩が上伊那地方のすべてを領有していたのではない。伊那街道沿いの竜西地区は、その多くが幕府領になっており、江戸の旗本がやってきてこれらの村々を支配していたのだ。江戸幕府という中央権力と、高遠藩という地方権力が竜西地区と竜東地区を分け持っていたのである。
アメーバ的発展
戦前は無論のこと、戦後も長い間、経済発展の基軸は竜西地区にあった。天竜川の西を走る国道153号線が、人の流れ・物の流れの主軸だった。
伊那市についていえば、国道153線上にある「通町」に有力な商店が集中し、地の利を得ていずれも繁盛していた。通町に店を持っているということは、子々孫々まで続く繁栄を約束されたことであり、無形の資産を与えられたということだった。伊那市だけでなく上伊那一円の住民は、大きな買い物をするときには伊那市の通町にやって来るのが通例になっていたからだ。
市役所・警察署・郵便局・銀行本店などの公的機関も又、国道沿いにあった。だから、伊那市民はここまで足を延ばさないと用が足せなかったのだ。
通町の繁栄はいつまでも続くと思われていたが、やがて、時代の変わり目がやってくる。日本が高度経済成長の時期に入り、伊那市も遅ればせながら発展の兆しを見せ始めたのだ。が、既存の商店街は用地の点で限られていて、新しい勢力が入り込んでくるゆとりがない。そこで新たに参入するスーパーや大型店は、郊外の水田地帯に立地することになる。郊外の新開地ということになれば、伊那市には天竜川の東側に広々とした水田地帯が広がっているのである。一般に貧しい後背地しか持たない竜東地区のなかで、伊那市だけが三峰川の切り開いた広大な沖積地を川東に抱えている。
だが、スーパーや大型店は、竜東地区を無視して、これまでの繁栄路線の延長線上に狙いを付ける。そして、惜しげもなく国道153線上の水田を埋め立てて飛行機の格納庫のような店舗をこしらえて行ったのだった。
やがて、何時までも続くように見えた竜西地区の黄金時代にも、陰りが見えるようになった。アメーバは抵抗がなければ、既定の方向に触手を伸ばし続ける。が、抵抗にぶつかれば触手を別の方向に向ける。竜西地区の水田地帯も、次々に参入してくる郊外店によって食いつぶされ、敷地が不足するようになってきたのだ。
ここまできて、ようやく竜東地区の出番が訪れる。
駐車場不足に悩んでいた警察署や市役所が敷地に余裕のある竜東地区に移転し、銀行本店・農協本部もその後を追い、政治経済の中枢が竜西から竜東に移動し始めたのがきっかけだった。高遠と直通する自動車道路が開通したことも影響している。ここ数年の竜東地区の変貌は目を見張るばかりで、伊那市内に新規に開店する大型店のほとんど全部がこの地区に集中するようになったのである。
そして、今や伊那谷を特色づけていた竜東地区の竜西地区の格差が消え去ろうとしている。こうした地域差の急速な消失は、モータリゼーションの普及、工業技術の進歩がもたらしたものだ。技術革新が止まない限り、この傾向は今後もずっと続いて行と思われる。