映画「たそがれ清兵衛」を見たときには、清兵衛一家は貧しいながらもにぎやかで幸せそうに見えた。庭には放し飼いの鶏が餌をついばみ、家の中には幼い女の子が二人元気にはしゃいでいる。加えて、親友の妹が時々訪ねてきて、家事を整え、子供たちの面倒を見てくれる。
ところが文庫本になっている原作を読んでみると、清兵衛家は訪れる者が誰もいない寒々とした家なのである。夫が城に出仕した後は、家には病床に臥せる清兵衛の妻だけが取り残されるといった具合なのだ。
清兵衛が黄昏時に急いで帰宅するのは、子供たちの世話を焼くためではなかった。足腰の立たなくなった妻を抱えて厠に連れて行くためなのだ。労咳を患っている妻は、便意をじっとこらえて夫の帰りを待っているのである。
原作には、こんな問答が描かれている。清兵衛に上意討ちを命じた家老と清兵衛の間に交わされる問答である。
杉山(家老)は笑いをひっこめて、しみじみと清兵衛を見つめた。
「女房は、そなたが帰るまで、尿(しし)を我慢して待っておるのか?」
「はあ」
「それはよくない。身体にごくわるい」
家老はつぶやいたが、やがてやっと話を本題にもどした。
「しかし、そなたに命じておることは藩の大事じゃ。女房の尿の始末と一緒には出来ん。当日は誰か、ひとを頼め」
「ご家老、その儀はお許しねがいます」
清兵衛は畳に額をすりつけた。
「余人には頼みがたいことでござります」
こうして清兵衛は家老の命令を頑なに拒むのだが、原作では彼が病妻に尿をさせるために帰宅したことが、次に来る波瀾の伏線になっている。上意討ちは、城内で行われることになっていたけれども、清兵衛がなかなか戻ってこないので、家老らはやきもきするのだ。
この上意討ちの場面も、原作と映画では大きく異なっている。
文庫本には、「たそがれ清兵衛」のほかに七つの短編が収められている。それら短編の主人公は、いずれも「うらなり与右衛門」「ごますり甚内」などとあだ名で呼ばれている下級武士である。
彼らはだいたい50石取りの貧乏侍で家中の者から小馬鹿にされているけれども、実は、すぐれた剣技の持ち主であり、それがあだとなって藩内の派閥抗争に巻き込まれ秘剣を振るうことになるのだ。
原作の清兵衛は、重職会議の席から退出しようとする家老の一人に追いすがって一撃を加えることになっている。映画ではこの部分が変更され、彼は藩に逆らって屋敷に立て籠もった凄腕の剣客と死闘を演じるという風に変えられている。この死闘の箇所は、文庫本の短編「祝い人助八」から取ったもので、映画は短編集の内容をあちこちから集めてつぎはぎする形で作られているのである。
映画を作った山田洋次監督は、原作のままでは彩りに欠けると考えたのだろう、登場人物を増やし、友人の妹と清兵衛との色模様をつけ加えてエンタテイメント作品に仕立てている。お陰で映画は大衆受けする内容になった代わりに、原作の持つ静かな味わいが失われてしまった。ここは清兵衛と病妻の関係だけに焦点を当て、下積みの藩士の夫婦愛をしみじみと描くところだったのである。
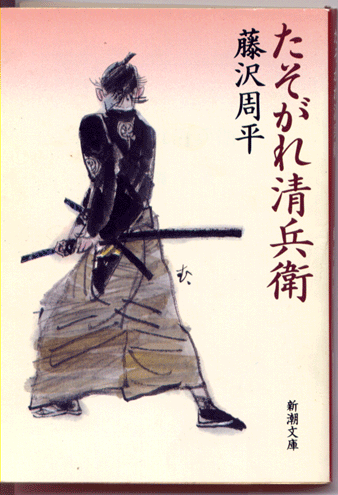 新潮文庫「たそがれ清兵衛」
新潮文庫「たそがれ清兵衛」厳密に言えば、原作の「たそがれ清兵衛」には、かなりおかしなところがある。
50石取りの侍というと、いかにも貧乏侍という感じがする。作者はその貧しさを誇張して書いているけれども、50石取りといえばれっきとした士分であり、その下には10石、15石というような下級武士がたくさんいたのである。50石の藩士は、今の制度でいうと係長クラスといった役どころで、経済的にある程度の余裕があったのだ。
清兵衛夫婦にはほかに係累が無く、夫婦二人だけの暮らしだったから、病人を看護するために婆やなり小女なりを雇う余力は十分にあったはずで、それに、昔は「おまる」と呼ぶ持ち運び式便器が広く使われていたから、用便のためにいちいち厠に通う必要もなかった。
しかし、物語では清兵衛をいったん帰宅させる必要があった。これらの条件を勘案して、尚かつ清兵衛を早々と帰宅させるには、作品の中に新たな条件を設定しなければならなくなる。病妻が神経質でおまるを使うことをいやがるとか、夫以外の人間に厠に連れて行ってもらうことを恥じる、などの条件である。
さらに最も大事な条件として、病妻の清兵衛に対する甘えとそれを許容する清兵衛の愛を付け加えておかなければならない。清兵衛が家老に向かって「余人には頼み難いことでござります」と訴えたのは、病妻が清兵衛に頼り切って夫以外の人間の介助を拒むからなのだ。
こういう条件を設定しておけば、夫婦愛を基調にした映画も制作可能になる。上意討ち以前の清兵衛夫婦の日常を淡々と描き、その要所要所に回想形式で夫婦の過去を織り込んで行けばいいのだ。
清兵衛のところには、妻女が病気になっても誰も手伝いにくるものはない。こうした孤立を生んだのには、過去に何か特別な因縁があったはずなのだ。清兵衛の妻は孤児だったかも知れないし、夫婦は漱石の「門」の夫婦のように親戚縁者から義絶されるような事件を起こしていたかもしれない。
病妻が清兵衛ただ一人を頼りにするのは、それだけの理由があるからだった。ここに重点を置いて夫婦の過去を描き、清兵衛が上意討ちを引き受けたのも過去の汚名をそそぐためだったというふうにすれば、映画もかなり違ったものになったろうと思われる。
山本周五郎、藤沢周平が時代小説の作家として成功したのは、時代小説という形式を借りて、実は現代小説を書いたからだった。「たそがれ清兵衛」も、日陰で生きる現代人夫婦の心理を清兵衛夫婦の上に投影させている。映画もこの線で押していったら、もう少し原作に近い感じを出せたろうと思う。