まだ独身だった頃、美校を出た画家の卵二人と知り合いになったことがある。この二人と同席して話を聞いていたが、彼らの会話が私には全く分からなかった。「マチエール」だとか、何とか、聞きなれない言葉が次々に出てきて話のポイントがつかめないのである。
好きな画家の話になっったので、私にもようやく口を挟めるチャンスがきた。私が「林武が好きだ」というと、二人のうちの一人が「彼はねっちこくてねえ」といい、もう一人も「うん、奴はくどすぎるな」と相づちを打った。林武の作品を静かで深みがある思っていた私は、あっけにとられて二の句がつげなかった。
私は、世界美術全集に載っていた「星女嬢」という林武の作品に魅入られていたのである。これはろくろっ首のように長い首を持った娘の横顔を描いた絵で、「アサヒグラフ」別冊林武集の解説者が「東洋的な精神主義」と注釈をつけている作品である。
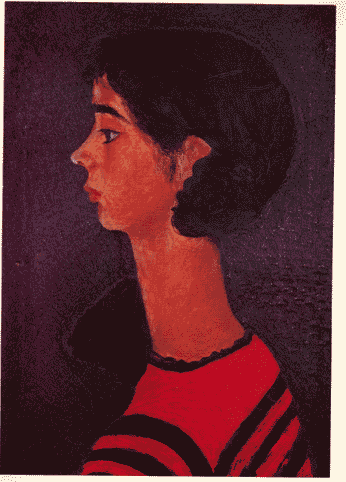 「星女嬢」
「星女嬢」描かれた娘は、内面的なものを削ぎ落としたような単純な顔をしている。なにか鳥を思わせる「非精神的な」表情をしているのである。それ故に画面全体に、逆に精神的な感じが強く出ている。
この作品について林武は「首がのびるのは、顔と胸の量のバランスから画面の主体性がそう要求」したからだと語っている。彼は単に画面構成の必然からろくろっ首にしたので、別に他意はなかったといっているのだ。としたら、彼の意図しないところで、作品に深い精神性があらわれたということになる。
とにかく私は、林武を「精神的な画家」だと思っていたから、画家の卵たちから「ねちっこい」とか、「くどすぎる」とかいう評言を聞かされてあっけにとられたのだ。しかし、その後彼のほかの作品に接するようになって、成る程と思うようになった。
林武の画集を開くと、なんとも凄まじい絵が並んでいるのだ。豊満な肉体を持ったピカソ風裸婦像、血が滴るような富士山図、いまにも飛びかかってきそうな海浜風景・・・・批評家が「鬼気迫る悽愴な作品」というのも頷けるような絵が並んでいる。
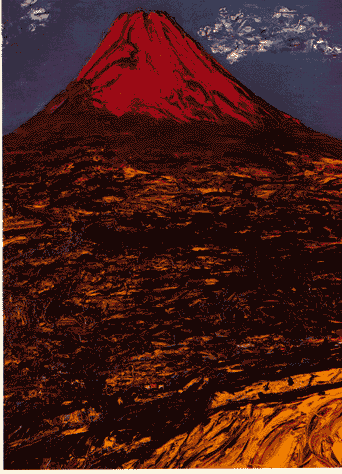 「富士」
「富士」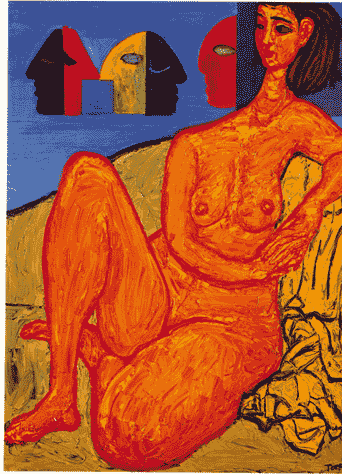 「裸婦」
「裸婦」その反面、「星女嬢」シリーズとか、「妻の像」「本を持てる婦人像」とか、「十和田湖」など、静かで深みのある作品もある。彼には、これでもか、これでもかと情熱をぶっつけてくる激しい絵と、抑制のきいた静かな絵があるのだ。
小学校の頃からの友人東郷青児は、彼が繊細な男だったといっている。
武さんという人は純心無垢で、繊細な感受性の持ち主だったと思っている。・・・・・(ところが、ある日突然様相が一変して)彼は人が変わったように嗜虐的になり、自己の本質を鍛え直そうとでもするかのごとく悪戦苦闘し、文字通り骨身を削って目前の断崖に体当たりし続けていたような気がする。
私はそんな状態で武さんが死んでしまったことが何より残念で仕方がない。描きたくもない富士山とバラに絵具を叩きつけ、武さんらしくもなく剛直さを売り物にしたのは周囲の者の筋書きだったような気がしてならない。
私の知っている武さんは心のやさしい、これ見よがしなことの嫌いな、奥ゆかしさを体中にたたえた静かな人だった。
東郷青児にいわせると、林武は本来「慈母のような沈静な美」を表現する画家だったのに、間違って「無理な激しさ」を追求する画家になってしまったというのだ。
彼の前には二つの路線があった。彼は静かな路線を選ぶべきだったのに、激しい路線を選んでしまったと、東郷青児はいうのだが、では彼はどうして選択を誤ってしまったのだろうか。
林武の父甕臣は代々続いた国語学者の家に生まれ、華族女学校で国語国文学を講じていた。が、研究に熱中して家庭を全く顧みなかったため、家は赤貧洗うがごとしという状態だったらしい。そのため、五男の末子だった林武は、子供の頃から兄たちと牛乳配達をしていた。凍傷で崩れた手足の痛みに耐えながら、雪の日も牛乳を積んだ重い荷車を引いたのである。ある朝、泣きながら車を引いているときに、彼は不思議な霊感に襲われる。
そのときである。不意に、僕のひたいのあたりがぱっと光り輝いた。それは何か遠くの高いところで輝いている感じであった。それは神秘の光明だった。あれは、一種の霊感のようなものであったろうか。そのとたんに、僕は、全身から力がわくのを感じた。
……僕は自分が年もいかない子供であることも考えず、一家を支えるために、家族みんなのために、自分が先に立ってやらなけれぱならないと思い、倒れそうなからだで根かぎりやった。そして、あのつらい雪のなかで天の啓示のように光り輝くものを見た。それはなにであったかはわからない。僕はそれをだれにも語らなかった。けれどもこのとき感じた不思誕な輝きは、その後、苦境に立ったびによみがえって僕を元気づけた。
小学校を卒業して早稲田実業学校に入学した後も、家のために身を粉にして働きつづけた。一日に3〜4時間しか眠らないで、勉学と労働に頑張り続けたのだ。そのため、過労で胃潰瘍になり、学校を一年足らずで中退している。健康が回復してから歯科医の助手になり、東京歯科医学校に入学したが、これも長続きしなかった。その後、彼は文学を志して新聞配達・牛乳配達をすることになる。
彷徨と模索の末に画家になることを決意して日本美術学校に入学したときには、彼はすでに24歳になっていた。彼はやっとのことで自分の進むべき方向を掴んだのだ。こうした半生の苦闘のあとは、彼の皺深い容貌に刻み込まれている。
 林武肖像
林武肖像画家になることを決意したが、気持ちはまだ定まらなかった。煩悶はなおも続き、せっかく入学した日本美術学校も翌年には止めてしまっている。絵の世界から足を洗おうとして、絵の道具一切を片づけてしまったこともあった。やがて彼は、終生女神のように崇めることになる妻と結婚する。その妻のためにもと頑張ったが、どうしても目の前に立ちはだかる壁を越えることが出来ず、ついに一番大事だった絵を捨てることを決意する。
一生を賭けた絵を捨て、それまで彼を金縛りにしていた執着を投げ捨てたときに、彼の眼前に全く新しい世界が見えてきた。
それは一種の解脱というものであった。絵に対するあのすごい執着を見事にふり落としたのだ。僕には、若さのもつ理想と野心があった。自負と妻に対する責任から、どうしても絵描きにならなければならなかった。だからほんとうに絵というものをめざして、どろんこになっていた。そのような執着から離れたのであった。
外界に不思議な変化が起こった。外界のすべてがひじょうに素直になったのである。そこに立つ木が、真の生きた木に見えてきたのである。ありのままの実在の木として見えてきた。同時に、地上いっさいのものが、実在のすぺてが、賛嘆と畏怖をともなって僕に語りかけた。きのうにかわるこの自然の姿それは天国のような真の美しさとともに、不思議な悪魔のような生命力をみなぎらせて迫る。僕は思わず目を閉じた。それはあらそうことのできない自然の壮美であり、恐ろしさであった(林武「美に生きる」)
林武はこの体験以後、一切の迷いを捨てて画業に専念するようになる。彼は言っている。
僕は絵を描く以外に、なんにもできない。趣味と呼ぶようなものは、一つもない。・・・・生涯において、ついに僕には絵を描く以外になにかする余裕はなかった。
・・・・こうした彼の屈折を重ねた生き方は、「霊的体験」のメカニズムによって解明出来るかもしれない。
霊的な体験が突発するのは、人がふた通りのやり方で外の世界を見ていることに起因している。一つは自我を通して外界を眺める立場、もう一つは自我という枠を取り外して素直に世界を眺める立場だ。自我を通してという言い方が分かりにくければ、欲望を通してといってもいい。欲望が強ければ強いほど、視野は狭くなる。この広大な世界に生きていながら、目に映るのは一つだけというようになってしまう。
自我の枠を取り外した時に現れる超自我的な自己を「真我」とでも呼ぶとすれば、この真我は素直にありのままの世界を見る。ただ見るだけである。真我には、それ以外に実体はない。従って、真我は中身のないがらんどうであり、無我であり、世界そのものだといってもいい。
幼い林武が牛乳車を引きながら、ぱっと輝く神秘の光明を見たのは、自我圏に集中させていたエネルギーが、その背後の真我圏に移ったためだろう。彼は末子の身で、一家の窮境を救うには「自分が先に立ってやらなければならない」と思い詰めていた。小さな身体に背負いきれないほどの使命感をかかえこんでいたのだ。つまり、自我圏に過剰なエネルギーを増投し続けたのである。エネルギーの過剰投与が続くと、自我はこれを支えきれなくなる。エネルギーは雪崩をうって真我圏に奔入し、このとき光の幻覚が生まれるのである。
禅僧はいくら考えても答えの出てこないような「公案」と取り組んでいるうちに、自我圏にあったエネルギーが真我圏に雪崩れ込む。このときに光明感覚が生まれる。イスラム教徒も、長い祈りと瞑想の果てに、禅僧が体験したのと同じ光明感覚に到達する。彼らはこれを簡単明瞭に「イルミネーション」と呼んでいる。幼い林武が感じたのもこのイルミネーションなのである。
この事情は、結婚後の解脱体験で一層明らかになる。
林武は絵しか生きる道はないと思い詰めて、必死になって努力を続けた。そしてエネルギーの過剰投与によって「どろんこ」のようになり、苦し紛れに絵に対する執着を振り捨てた。そしたら、真実の世界が見えてきたのである。解脱した禅僧やイスラム教徒が見たのと同じ世界が見えてきたのだ。
これで林武がなぜ彷徨を重ね、屈折した生涯を送ったかという理由が分かる。彼は思いこむとエネルギーを次々に自我に注ぎ込むタイプなのだ。そして自ら負荷に耐え得なくなると、エネルギーを自我圏の外に解放する。これを何回も繰り返したから、彼の人生コースは幾変転を重ねることになるのである。
「解脱体験」後、林武は心構えを新たにして絵を描き続けた。しかし彼が世に認められるようになるのは、53歳になって第一回毎日美術賞を貰ってからだった。それまでは、画布から掻きおとした油絵の具を団子に丸めて屋根の雨漏りを塞がなくてはならないような生活をしている。
世に認められてからの彼は、トントン拍子で名声の頂点を極めていった。芸大の教授にもなったし、文化勲章も貰った。彼の周辺には、十数人の若い画家が集まり、彼はその面倒をよく見た。彼らをはげますための賞と賞金を設定し、彼らの懐を潤すために展覧会に出かけて作品を買い上げてやった。
私が林武に惹かれるのは、彼の荒魂と和魂のうちの和魂に対してであり、東郷青児のいう「慈母のような沈静の美」を愛するからだ。
彼は自我圏にエネルギーを集めて荒魂の絵を描き、その傍らエネルギーを自我圏から解放して和魂による絵を描いたのだが、彼が東郷青児に「無理な激しさ」と言わせるような方向に傾斜していったのは、画商らの要求に応えるためというより、彼を取り囲む若い画家たちの期待に応えるためだったにちがいない。
「慈母のような沈静な美」を示した作品に、夫人をモデルにした「本を持てる婦人像」がある。晩年になって妻を描いた「妻の像」も落ち着いた感じのいい作品である。
 「本を持てる婦人像」
「本を持てる婦人像」 「妻の像」
「妻の像」冒頭に掲げた「星女嬢」は、ろくろっ首のように長い首をしていた。しかし、この娘をモデルにした連作の中には、あまりデフォルメされない尋常な肖像画もある。それには、ろくろっ首と同じ「星女嬢」という名前がついている。下図の絵がそれである。
 「星女嬢」
「星女嬢」この穏和で優しい丸顔の娘が、彼の手にかかると鳥のような横顔を持った娘に変貌し、一種精神的な作品になる。そして更に手を加えると、下に示すような巫女風の肖像になる。
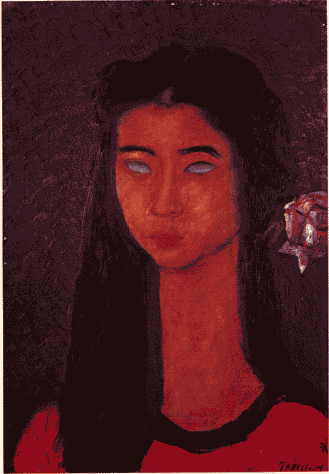 「前向き少女」
「前向き少女」私は林武が、こうした和魂による絵、精神の深さを感じさせる作品をもっとたくさん残してくれたらと、残念でたまらない。そして、彼が「道を誤って」過激な方向に走ってしまったのは、内心で静かな生活を望みながら情に流されてこれを実現できなかったためだと考えている。彼は芸大教授に就任するように依頼されたとき、固辞するつもりだったが、結局周囲の懇請に負けて承諾している。熊谷守一は文化勲章を辞退し、ワイエスは人間嫌いの看板を掲げて、田舎にこもった。いい作品をものするには、こうした情に流されない強さも必要なのである。
精神的な絵とは、真我の見る世界にわれわれをいざなってくれるような絵である。そして、そのような作品は静かな生活を背景にして生まれるのである。この場合、「静かな生活」とは、象徴的な表現であるけれども。(02/4/29)