三浦久さんのアルバム「千の風」を聴いていたら、「碌山」というタイトルの歌があった(三浦久さんについては別項「三浦久の青春」参照)。萩原碌山の悲恋をテーマにした歌である。「碌山」は次のようなフレーズで始まっていた。
それは明治30年
安曇野の春のはじめ
彼は畦道に腰をおろし
常念岳をスケッチしていた「こんにちわ」という声に振り向けば
徹笑みかける美しい人
彼は思わず頬をそめた
胸の高鳴り押さえがたく
萩原碌山に「こんにちは」と声をかけたのは、安曇野の名門相馬家に嫁いできていた相馬黒光だった。その後、ニューヨークやパリに赴いて絵と彫刻を学んだ萩原碌山(守衛)は、帰国後に新宿で中村屋というパン屋を開業していた相馬黒光と再会することになる。
同じ新宿にアトリエを構えた萩原碌山は、中村屋を訪ねて一人で奮闘する相馬黒光を手伝うようになった。彼女の夫は留守がちだったのである。
ある晩店の奥の部屋で
彼は突然血を吐いた
障子や畳を真っ赤に染めて
30年の生涯を終えたその人は彼の柩をつかみ
人目もはばからずに泣き崩れた
その時その人は初めて知った
彼こそ魂の兄弟だったと
相馬黒光は、萩原碌山の死後数日して、彼のアトリエを訪ねる。彫刻台の上には、最後の作品と覚しき塑像が残されていた。それは両手を後ろに回してひざまずいている女の裸像だった。
両手を後ろに回し、ひざまずき
何かから逃れようと身体をよじり
顔を上げ光を求める自分の姿
その人はその場に崩れ落ちた愛することに理由はない
愛してる時だけ人は生きている
彼はそのためだけに生まれてきた
愛する人の像を創るために
私は安曇野にある「碌山美術館」を二度訪れているけれども、萩原碌山と相馬黒光の関係については全く知らなかった。
私が萩原碌山よりも相馬黒光に興味を感じたのは、相馬黒光を美しく歌い上げている三浦さんのアルバムを聞いたためだった。私は家にある相馬黒光の自伝「黙移」を読み、さらに相馬黒光の評伝(「新宿中村屋相馬黒光」宇佐美承)を取り寄せて通読した。相馬黒光の生涯は波瀾に満ちていて大変面白かったが、彼女は私が想像していたような孤独な女でも、やさしい女でもなかったのだ。炎のような情熱と冷たい野心を併せ持った男勝りの激しい女だったのである(以下に掲載する写真は、「新宿中村屋相馬黒光」から借用させてもらった)。
「相馬黒光」の相馬は婚家の姓であり、黒光はペンネームで、結婚前の彼女の名前は星良という。星が姓で、良が名前である。
良は明治16年、仙台市内の小学校に上がった時から、先生のお気に入りだった。彼女の通っている片平丁小学校では、生徒たちの間でこんな歌がうたわれていた。
ひとつとや 人よりきれいなお良さん お良さん
秋保の惚れたも無理がない 無理がない
女学生時代の相馬黒光
秋保という担任の教師が、怜悧で綺麗な良を手の中の珠のように寵愛したことがこの歌によって知られるのだ。
小学生の良は、押川方義が創設した仙台教会に通っていた。三年生になると、彼女は子供相手の日曜学校では満足できなくなって、成人対象の礼拝会に出席して押川方義の熱弁に耳を傾けるようになる。
良は押川方義からも目をかけられたが、彼女を最も愛したのは押川の開いた神学校の第一期生島貫兵大夫だった。良より9才年長で、まだ20になるかならぬかの島貫は、師の押川に劣らぬ情熱的な説教をして信者たちから「島貫先生」と呼ばれていた。
この島貫が良を妹のように可愛がってくれたのである。良は彼に日に二度、三度と手紙を書くようになり、すると、相手から「妹よ、すぐ来たれ」という連絡が入るので、良は島貫の下宿に飛んで行くのだった。
小学校を卒業した良は、島貫から女学校に進学するように説得される。そして、曲折の末に、アメリカからの資金で設立されたミッションスクール宮城女学校に入学することになった。島貫の尽力で、学費が免除になったからだった。
この学校の校長は、アメリカから派遣されてきたミス・ブルボーで、その下にもアメリカ女性の教師がいて、教育方針は何から何までアメリカ式だった。
これに不満を感じた生徒が、校長に教育内容を変更するように「建白書」を出したために、学校側は首謀者と目される5名の生徒に退学処分を言い渡した。退学処分の宣告は、全校生徒を講堂に集め、その前で校長が「Go
away! Go away!」と叫んで5名をその場から追い出すという激しいものだった。
退学になった5名の上級生から可愛がられていた良は、彼女らに殉じる形で自発的に学校を去っている。宮城女学校に在学すること僅か1年で早々に自主退学してしまったのだ。退学して家で過ごすことになった良は、それまで目をそむけるようにしてきた自家の惨状に直面することになる。
星の家は、子沢山で良を含めて男女8人の子供がいた。にもかかわらず、養子だった父の生活力はゼロにちかく、その父が、良の宮城女学校在学中に肺ガンで亡くなってしまったので一家は貧窮のどん底に落ちていた。
仙台藩時代は奉行職にあった星家は、維新以後、幸運から見放されたかのようだった。中の兄は東京で勉学中にチフスにかかって死んでいるし、弟は骨膜炎を患って右脚を付け根から切断してしまった。そこへ上京していた姉の蓮子が発狂して家に戻ってきたのである。発狂の原因は、婚約していた相手の親から突然破約をいいわたされたためだった。事情を知った良は、まるで人が変わったようになる。
実際私は姉が発狂してから笑わない子供になりました。宮城女学校時代に小此木先生が「あの子はどうして笑わないのだろう、花はどうして美しいのですか、何故おかしいのですかとあの子は言う」と言われたそうでございます。
そうして成長した私は極端に異性を憎悪し、またいささかこちらが強くなると相手を嘲弄したりして手のつけられぬ見事悍馬になってしまいました。これがため周囲の異性や夫を如何に苦しめ、迷惑をかけましたか、思えば恐しいことでございます(「半生を顧みて」)
:
相馬黒光の「男性憎悪」がその後いかなる人生を彼女にもたらすことになるか、やがて明らかになる。彼女の挑戦的姿勢は男性に対してだけではなかった。良がクリスチャンになったのも、自由民権論者になったのも、男性優位の社会に対する怒りからだった。
彼女の祖父は儒者だったから、兄は妹が教会に通うのを見て「お前は先祖の道に背くのか」と叱りつけた。けれども、良はそんな小言を歯牙にもかけず、自分が洗礼を受けるだけでなく、母・祖母・弟妹まで教会に引っ張っていくようになった。家族に対する良の発言力は、兄を凌駕していたのである。
良が押川方義や島貫兵大夫に心酔して、彼らの説教会が開かれると聞けば、何処へでも駆けつけたところは、現代の「追っかけ」を思わせる。こうした行動は、彼女の父親が居ても居なくてもいいような影の薄い存在だった為と思われる。良は、押川と島貫に父親の面影を見ていたのだ。
外の世界に父親役の男性を求めた良が、家の中にあっては父の役割を代行したのは興味深い。良は兄を除く家族全員をキリスト教に入信させただけでなく、島貫兵大夫が東北救世軍を創設すると、火の車のような家計の中からこれに寄付するように要求し、父が死亡したときには葬儀を耶蘇式にすように言い張って、その主張を押し通している。この小生意気な少女は、母には大好きなタバコをやめさせておきながら、自分は脚気の治療を口実にして温泉に保養に出かけた。
「新宿中村屋相馬黒光」の著者は、明治期のキリスト教指導者について、次のように書いている。
そのころ仙台、松山にかぎらず命永らえた旧賊軍の者は新時代に陽の目をみることがなく、なかに耶蘇教に救いを求める者がいた。同じ立場の幕臣山路愛山が、植村正久や押川など明治初期の著名キリスト者の名をあげて「総ての精神的革命は多くは時代の陰影より出づ」(『基督教評論』)と書いたほど、その数は多かった。
明治のキリスト教指導者に共通する時代に対する反骨は、仙台藩儒者の孫娘良の心にも脈々と流れていた。少女期の良は、自由民権運動の女性闘士だった景山英子と岸田綾子にあこがれ、結婚して最初に生んだ女児に岸田綾子にちなんで「綾子」という名前を付けている。
宮城女学校を退学した良は、身をもてあましていた。「建白書」騒動の中心人物だった斉藤お冬さんをはじめ、同志の4人はそれぞれ新しい方向を見つけて東京の明治女学校などに移った。だが、彼女は激しい抵抗精神を抱いたまま、檻の中のけもののように家に縛り付けられイライラしているだけだった。
それ故私は宮城女学校を退学いたしましても、直ぐにお冬さん達の後を追うて上京するということは出来ませんで、この陰惨を極めた家の中で、空しく都の空を眺めつつ、恨みを呑んで幾月かを待たねばなりませんでした。
これはアンビシャスガールの私(島貫さんは私のことをいつもこう称びました)に取り非常な苦痛でありました。母は私のこの焦燥を察し、困難の中から意を決して遂に私に上京の許しを与え、古い家のこの重圧から私を解放してくれることになりました。私は天にも上る思いで、この報告を持って押川先生と島貫さんに飛んでまいりました(「黙移」)。
良の宮城女学校入学に尽力した押川と島貫は、再び、彼女の再出発の相談に乗ることになる。二人は協議の末に、良は将来語学で身を立てるのがいいということになり、日本で最高のミッションスクールだった横浜のフェリス女学校に良を入学させることにした。良にも異論はなかった。押川は早速、フェリス女学校の教頭星野光多(校長はアメリカ人)に連絡を取って、良をフェリスに入学させる手続きを取ってくれた。
フェリス女学校に入学してからも、良は校長や教頭を始め、多くの教師に愛されている。校長らは彼女が脚気になると千葉県の医師宅に転地するように計らってくれ、そこで良は一人娘のように大事にされて一夏を過ごした。彼女はフェリス女学校の関係者から可愛がられただけではなかった。斉藤お冬さんの学んでいる明治女学校の有力者星野天知の知遇を受けることにもなるのである。
星野天知は、江戸時代から続く豪商の息子で、北村透谷や島崎藤村の拠った雑誌「文学界」の金主であり編集者だった。良は明治女学校に転入した宮城女学校時代の友人に連れられて星野天知の私宅を訪問し、それが縁になって鎌倉にある彼の別荘に出入りすることを許されたのだ。
これはと思う人物に目をつけると、ぐいぐい迫っていって相手の懐に入ってしまうのが相馬黒光の特技のようなものだった。彼女は病気を口実にフェリスを休み(仮病であることを知らない外人教師は、良のことをシックチャイルドと呼んでいたわってくれた)、鎌倉の星野別荘に出かけて所蔵のライブラリーを読んだり、原稿を書いたりした。星野の許しを得て、留守番の爺やと一緒に、別荘に泊まり込むこともあった。彼女は星野の別荘を自分のための憩いの場にしてしまったのである。
「思えば何という横着な私でしたでしょう」と相馬黒光は「黙移」のなかで半ば自分にあきれているが、横着という点では彼女は全くその通りだった。そして、遂に彼女はフェリスに籍を置くこと3年で、明治女学校に転校してしまうのだ(相馬黒光は転々と学校を変える自分のことを「たちが悪い渡り者」と自嘲している)。
確かに、明治女学校には北村透谷・島崎藤村などの優秀な教師がおり、学風は自由で、文学的な雰囲気にあふれていた。相馬黒光は「黙移」のなかで、この学校で見聞した明治文学史に残るようなエピソードをいくつも披露している。
次に引用するのは、宮城女学校時代の先輩「斉藤お冬さん」と北村透谷に関するエピソードである。
透谷の時間となると何故かお冬さんが一番に冴えて見え、そして最も手応えがある、すると透谷もやはりお冬さんを目当にして講義をするという形になります。熱心に聴く、真剣に質問する、熱心に講義し、力をこめて応える、この距離がだんだん接近して、いつの間にか透谷とお冬さんは一つ机をほさんでむかい合い、まるで一間一答の形で教え、質し、論ずる。級友はその二人の一問一答から聴いて、非常に興味深く勉強するという有様であったということです。ある日透谷は、かぜを引いてしきりに洟が出るのをすすりすすり講義していました。そのうち洟が落ちそうになると、お冬さんは懐から紙を探って差出す、透谷がそれを受取って洟を押える、しかも講義は白熱の状態でつづけられており、その紙を渡すのも受取るのも無意識になされているという風で、すべて以心伝心、これ程の一致を以て教え教えられるのですからお冬さんの感激も察しられます。
このケースだけでなく、明治女学校では教師と生徒の間の恋愛沙汰が日常茶飯事のようになっていたが、良が教師を恋愛の対象とすることはなかった。彼女は例の「男性憎悪」のお陰で真剣な恋愛をすることが出来ず、才力・知力において自分より劣る男性、自分がウワテに回って自由に操縦できるような男性を相手に恋愛遊戯をすることを好んだ。
仙台の教会に通うころから、良にはそういう意味の男友だちがたくさんいた。フェリスの寄宿舎にも彼らから盛んに手紙がくるので、舎監から「星さんは男好きですね」と嫌味をいわれるほどだった。でも、数ある男友達の中に、良がひそかに好意を寄せている男性が一人だけいたのである。
相手は布施淡(あわし)という仙台支藩の領主の孫で、画家を目指して勉強中の若者だった。彼は耶蘇教徒になったために祖父から勘当され、牛乳配達のアルバイトをして糊口をしのいでいた。このときに、良の方から声をかけて二人は親しくなったのである。
布施淡との関係は、良がフェリス女学校の夏休みに帰省した際に進展した。帰省して数日後の夜更けに、彼が訪ねてきて散歩に誘ったのだ。それ以後、二人は夜道を散歩することを習慣にするようになり、途中で義大夫流しに出会ったりすると、良はなけなしの50銭銀貨を与えて自宅に呼び入れるような気まぐれな行動に出た。最初、仰天していた祖母と母は、義大夫流しの浄瑠璃を聞いているうちに涙を流した。
夜の散歩だけでは満足できなくなった布施淡は、良に3泊4日の旅に出ないかと誘った。布施がもう一人の男友達も同行すると説明したので、良は承知し、三人連れの旅に出る。二人の男は、良を人力車に乗せて自分たちは歩いた。
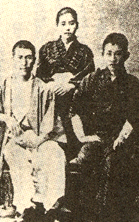 三人の旅(右端が布施淡)
三人の旅(右端が布施淡)良は、まだ封建道徳が色濃く残っていた明治25年に、こうしたことをやってのけて周囲を瞠目させるが、布施淡と深い関係になることは避けていた。彼女は姉を見て異性に強い警戒心を抱いていた上に、キリスト教の影響を受けて、性行為に対して強い嫌悪感を持っていたからだった。
相馬黒光は、フェリス時代、明治女学校時代を通して、寄宿舎から通学していた。だが、東京の日本橋にある叔母の邸には足繁く出かけていた。叔母(母の妹)は裕福な医者の妻になって、佐々城豊寿と名乗っていた。彼女はキリスト教の有力組織である東京婦人矯風会の創設者であり、上流社会に広く名前を知られている「女名士」だった。彼女は、抜けるように白い肌、目鼻立ちのくっきりした瓜実顔など、その派手な美貌でも知られていた。
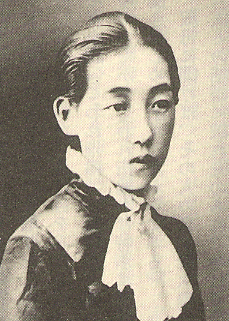 佐々城豊寿
佐々城豊寿叔母の家に行くと、驚くことばかりだった。客がひっきりなしに出入りしている。徳富蘇峰・中島信行・島田三郎・巖本善治など政界・言論界の名士を筆頭に、文士、新聞記者、代言人、学者らが織るようにやってくる。叔母は彼らに手製の西洋料理を振る舞いながら、客と対等に政治・思想・宗教について論じていた。
日清戦争が終わったとき、佐々城豊寿は自邸に従軍記者たちを招いて慰労会を開いた。この夜招かれた記者たちの中に国木田独歩がいて、豊寿の娘の佐々城信子と恋に落ちたことは、有島武郎の「或る女」に書かれている。
信子という娘は、仲間が髪を銀杏返しか桃割れに結っている時代に、一人だけ髪を切り下ろしてリボンで飾っているという風なハイカラ娘だった。彼女はアメリカに留学して、将来ジャーナリストになりたいと夢見ており、母の豊寿もそれに賛成していたのだが、その娘が周囲の反対を押し切っていきなり貧乏作家と結婚してしまったから、怒り狂った豊寿は娘に家に出入りすることとを禁じ、事実上勘当してしまった。
結婚して半年もすると、信子は独歩と一緒になったことを後悔するようになった。が、家に戻ることは出来ない。こうした状況の下で、良は信子と独歩の問題に深く巻き込まれて行くのである。
四月の日曜日の正午近く、明治女学校の寄宿舎にいた良の所へ独歩の監視をかいくぐって信子が駆け込んできた。そして、真っ青な顔をして「これから姿を隠すから一円貸してくれ」という。良が一円を貸し与えると、信子は蒼惶として姿を消した。間もなく、今度は顔色を変えた独歩が飛び込んできて「信子が何処に行ったか知らないか」と詰問する。
良のもとを去った信子は知り合いの病院に隠れていた。そうとは知らない独歩は、その後も半狂乱になって信子を捜し回り、良のところにも日に二度も三度も様子を聞きに来るという有様になった。事情を知った寄宿舎の舎監も女学生たちも皆独歩に同情する。良も「黙移」のなかで「あんまり我儘過ぎて従妹ながらも愛想が尽きてしまうのでした」と信子を責めている。
 佐々城信子
佐々城信子独歩もついに諦めて信子との離婚を承知する。すべてが終わったあとで、相馬黒光は事件をこう総括するのである。
この騒動によって独歩の純情を見て泣かないものは一人もないのでした。まして私は苦しい役を負わされ、独歩に対して申訳のない手伝いをしてしまったのですから、一層辛かったのでございます。叔母は世間に対して深く不明を恥じ、矯風会の方を辞し、その他公けの交際はすべて遠慮して、ようやく四十あまりの活勤盛りの身を以て引退しました。
相馬黒光のその後の生き方を見れば、彼女が叔母から大きな影響を受けていることが判明する。叔母は千客万来のにぎやかな家を切り盛りしながら、同時に事業欲にも燃えていた。相馬黒光は、こうした叔母の多彩な生き方を見て、これを模倣し、その跡をなぞるような生涯を送ることになる。
彼女は従妹からは、これを反面教師とすることを学んだ。だが、学んだのは、性的に深入りすることの危険性についてだけで、彼女の異性に対する放胆ともいえる行動には従妹との相似性が見られる。
国木田独歩が信子と良の比較論を展開しているので、参考までに紹介しておきたい。
信子=勤勉家・実際家・家政家・横着の人・実行の人で政治家の妻に相応しい
良=同情の人・人性を解せる人・感情の人・野心なき人・上品の人・赤面する人・黙想の人
独歩は、衝動的な情熱家と見られている佐々城信子を勤勉な実際家と評価し、事業家風の性格特徴を列挙している。だが、これらの資質は、中村屋を経営して事業家として成功した相馬黒光のものだった。
そして独歩は、良の冷徹な実務家という側面を見落として、彼女のことを情にもろい内省的な娘だと書いている。
相馬黒光と佐々城信子という従姉妹同士は、実は相似た性格を持ち、二人とも意志的な側面と情にもろい感情家という二面性を持っていたのだ。独歩はこの二人の女について、その一面だけを見てしまったのである。
良は明治女学校に学ぶ多くの女学生と同様に、閨秀作家になることを夢見ていた。彼女は独歩との関係を通して田山花袋などの作家と知り合いになっていたし、東京の九段に移り住むようになった島貫兵大夫に紹介されて、多くの出版関係者とも顔なじみになっていた。
良が雑誌に「情話小説」を発表できたのも、こうしたツテに恵まれていたからだった。彼女は以前にも、小説を書いて「文学界」の編集人だった星野天知に見せたことがある。星野が所有する鎌倉の別荘に泊まり込んで書き上げた労作だった。
だが、星野は評価しなかった。彼は後年当時のことを回想してこう書いている。
逗留して居る中に小説を書いたからと原稿を持参された。田舎言葉で幼稚な筆ではあるが齢に似合はぬ男女の交渉が語られてある。中々の物だと思ったが『まだ情話小説などは書かぬ方が好い一意読書さる時代だ』と圧えて置いた。
良が雑誌に発表した作品は、星野が雑誌に掲載することを拒んだ「情話小説」だったかもしれない。とにかく、彼女はこの一作によって周囲から将来作家として立つ女性だと見られるようになった。しかし、この作品によって彼女は思わぬしっぺ返しを受けることになる。良に関するゴシップ記事が新聞に出たのである。
記事のヒロインは保科竜ということになっている。けれども、宮城女学校からフェリス女学校に移り、今は明治女学校に在学している耶蘇教徒という経歴を見れば、これが星良を指していることは疑いを入れなかった。この記事は、保科竜が色恋沙汰のもつれから「島貫某の邸の井戸にドンブリ飛び込んで」自殺するという内容になっている。
良が現に生きているのだから、新聞記事がインチキであることは明白だった。が、この記事は良の書いた小説の筋立てをそのまま利用したものだったから、良の受けたショックは大きく、彼女は「黙移」のなかに「作家志望を棄つ」という一章をもうけて、当時の心境を語っている。
私ははっきりここで小説がいやになりました。自分の書くものは所詮それ位のものなのか、いやしい敵意を持った人間に早速利用されて世間に恥をかくような、そんな程度のものなのか、自分の目指すものは、もっと高いところにあるのだが、と考え、それが自分への反省となったのは幸いでした・・・・
良が創作の筆を絶ったのには、自身の才能に自信が持てなかったという事情もあるように思う。星野天知から文章の稚拙さを指摘されていた彼女は、「文を綴る」こと、文章作成能力そのものに自信を喪失した節がある。
「黙移」は、良の手になるものではない。「黙移」を掲載した「婦人之友」の羽仁もと子は、良に直接ペンを取って「報告小説」を書くように依頼したのだったが、良はそれを断って口述筆記を島本久恵に依頼している。「黙移」の文章は島本の手になるものなのである。
良にショックを与えたもう一つの出来事がある。布施淡の婚約だった。
良に関するゴシップ記事が出る前に、彼女は島貫に勧められて相馬愛蔵と見合いをしている。島貫は信州に伝道旅行に出かけた際、相馬愛蔵の家に泊めてもらって愛蔵の人柄にすっかり惚れ込んだのだった。相馬愛蔵は信州穂高村で代々庄屋をつとめる名家の跡継ぎで、禁酒運動や廃娼運動に努力しているクリスチャンだった。
良は島貫から、「都会では絶対にみられぬおっとりとした人柄で、じゃじゃ馬のお前を飼い慣らせるのは彼しかいない」と説得され、実際に会ってみて悪い印象を持たなかった。が、その頃の良は独歩と信子の問題に振り回されていたから、話は進展しないまま宙ぶらりんになっていたのである。
その相馬愛蔵との縁談が一気にまとまったのは、布施淡が加藤豊世と婚約したからだった。加藤豊世は、良がフェリス時代に妹のように可愛がっていた後輩で、彼女と布施が親しくなるチャンスを作ってやったのも良だったのだ。
三泊四日の東北旅行ですっかり良と親しくなった布施淡は、その年の暮れに上京して良に会いに来た。たまたま、フェリスの寄宿生の間で鎌倉徒歩旅行の話が持ち上がっていたところだったので、良は布施も誘って二泊三日の旅に出た。
この旅に加わっていた加藤豊世は、寄宿舎では熊の子を真似て仲間を追い回すような無邪気な少女だった。個性の強い良に手を焼いていた布施は、それとは対照的な豊世に惹かれるようになり、旅行後も連絡を取り合って、良を裏切るような形で彼女と婚約したのである。
プライドを傷つけられた良は、二人を出し抜いて一足先に結婚することにしたのだ。愛蔵は東京専門学校を出た村内でほとんど唯一のインテリで、地域の青年たちのリーダー格になっていた。愛蔵が良との結婚を望んだ理由は、良なら自宅に集まってくる仲間たちの話し相手になってくれるだろうと思ったからだ。
明治30年、相馬愛蔵と星良は、東京牛込の日本基督教会で結婚式を挙げた。
明治女学校の級友たちは、良が波瀾万丈の華やかな人生を歩むものと想像していたのに、案に相違して信州の名もない男と見合い結婚したのでみな驚きを隠さなかった。
良は学校を卒業したら、大変な犠牲を払って自分を進学させてくれた母や祖母に酬いるために、就職して家計を助けるべきだった。だが彼女は帰省するたびに実家の惨状を目のあたりにしながら、恩返しの気持ちをついぞ起こしたことがなかった。聖書には「死者をして死者を葬らしめよ」とある。自分だけでも、このみじめな家から脱出しなければならない、これが彼女の身勝手な論理だった。
島貫兵大夫は、信州穂高に出発する新婚の夫婦を途中まで送っていった。良のことが心配でならなかったのである。碓氷峠を越えて、一行は上田で一泊した。旅館で良は、島貫と愛蔵に別室で一人で寝させてくれと頼んだ。彼女は式を挙げてから、まだ一度も夫に肌を許していない。一人になると、良の涙が止まらなかった。自分が鬼界島に流された俊寛のように思われた。
この夜ほど自分のことをしみじみと考えたことはありませんでした。……運命に服従した神妙さを思うと、ただわけもなく泣けて仕様がありません。あたかも二十二年の溜涙が、今宵堤を切って溢れ出したように一夜を泣いて泣いて明かしました。(『広瀬川の畔』)
安曇野の相馬家に落ち着いて一ヶ月もすると、良は「一匹の大きな黒い鳥のような退屈」に襲われはじめる。婚家は豊かで、生活のためにあくせく働く必要はなかったが、良はその点を苦痛に感じ始めたのだ。彼女は「自ら働かず、人の労苦によってのみ生くることの苦しさ」を初めて実感した。
身辺を見廻した時、私ほ全く憂鬱に閉じこめられ、ああこんなことをしていてよいものであろうかと、つくずく溜息されるのでした。何とした安逸、私は全く進歩の止まってしまっている自分をそこに見出したのであります。ああ、あの嘗ての溌剌とした自分はどこへ行ったのであろう、長話にふける村の人にお茶を出したり、炉辺に坐って粗朶を加えたり、この退屈、この沈滞、これ等はすべて人間の自滅に到るみちではないか、ああこんなことして暮して行ってよいものか(「黙移」)
愛蔵を囲む青年たちは、相馬家の広間に集まって芸術や時事問題を論じあっている。良もそこに顔を出して議論に加わったが、心はやはり満たされなかった。
結婚の翌年に長女が生まれる。その次の年には、東大病院に入院して卵巣膿腫の手術を受けている。入院中に穂高出身の萩原守衛が頻繁に見舞いにやってきた。画家志望のこの若者は、相馬家に集まる青年たちの一人だった。写生をしているところを良に声をかけられて以来、二人は親しくなっていたが、その頃、彼も上京して東京で絵の勉強中だったのである。萩原守衛の手記には、次の文字が見える。
二時間談ず 大いに快方に向かわれ うれしき事にぞある
いかなる縁にや真の姉の如き思いして 話す間は実に家庭(にいるごとき)快き心地せらる
三週間で退院して信州に戻った良は、病後のつれづれに病床記や随想を原稿にして、巖本善治に送るようになった。巖本はこれらを「女学雑誌」に掲載するに際し、良のペンネームを相馬黒光としている。野心的で目立ちたがり屋だった良に、あまりギラギラした光を見せるなという教訓をこめた命名だった。
長女出産の二年後に長男が生まれた。この頃から、良の喘息が悪化して床につくことが多くなった。そういう彼女に追い打ちをかけるように、愛する人々との生別と死別がつづて起こった。布施淡の訃報を追うように、佐々城豊寿夫妻の訃報が相次いで届き、その一月後には狂っていた姉蓮子の訃報が届いた。
そんなときに東大病院に入院中に何くれとなく世話をしてくれた萩原守衛がアメリカに留学することになったのである。
打ちひしがれた良は、何としても信州から出たくなった。良は義父である愛蔵の兄に家を出る許しを求める。相馬家の当主は愛蔵の長兄だったが、子供が生まれなかったので彼は末っ子の弟愛蔵を準養子にして跡を継がせることにしていたのである。良は義兄を舅、兄嫁を姑として4年半を安曇野で暮らしていたのだった。
相馬愛蔵の方も、寝たきりになって背中に床ずれの出来た妻を救うには上京するしかないと思っていた。妻は田舎の生活に耐えきれなくなっている、みな良の褥瘡を死の兆候だと噂しているが、このまま放っておけば本当に死んでしまうかもしれない。
義父は良の願いを条件付きで許してくれた。
その条件とは、愛蔵夫婦の長女俊子を家に残していくこと、愛蔵が養蚕シーズンである春から秋にかけて家に戻って仕事をすることの二つだった。夫と半年別れて暮らすことに異存はなかったが、娘を人質に取られることは耐え難かった。しかし婚家を出るには俊子を棄てて行くしかない。
こうして良は再び東京に戻ってきた。良の行動は、叔母の佐々城豊寿のそれに似ていた。叔母も婦人矯風会を辞してから再起を図り、農場経営を夢見て北海道に渡り、女学校・教会の設立などを計画している。だが、事やぶれて東京に帰ってきて、程なくなくなったのだった。
叔母は事業に失敗した。が、叔母と同型の性格を持った良は、東京で見事に成功し従業員300人を擁する中村屋の経営者になるのである。
上京した相馬夫婦は、ひとまず本郷の借家に落ち着いた。現金なもので、良の病気は婚家を離れると同時に、よくなっていた。夫婦が先ず考えなければならなかったのは、何によって生計を立てるかということだった。
相談の結果、学生相手のパン屋をやったらどうかということになって、夫婦は知人から借金して東京帝大前の中村屋というパン屋を買い取ることにした。そして、屋号を「中村屋」としたままで営業をはじめたところ、店は順調に発展し新宿に支店を出すまでになった。愛蔵は長兄との約束を守って毎年信州の実家で半年を過ごしていたから、中村屋の成功は、過半を良の努力によっていた。
良はめざましい勢いで中村屋を発展させながら、子供も盛んに産み続けた。東京に戻ってから7人の子供を産み、彼女は計五男四女の母になっている。だが、母親の多忙のためか、このうち三人は夭折し、二人は20代で死亡、一人は消息不明になって、無事に残ったのは三人の子供に過ぎなかった。
萩原守衛が帰朝して、新宿西口にアトリエを建てたのは、良が新宿中村屋に腰を据えて無我夢中で働いているときだった。守衛はフランスに渡りロダンの芸術に接してすっかり感動し、彫刻家に転身していた。良に会うために中村屋にやってきた守衛は、一人で奮闘する良を見て感動すると同時に、信州の穂高で浮気をしている愛蔵に対する怒りを押さえきれなかった。
守衛は新宿に来る前に郷里に立ち寄り、そこで愛蔵に再会している。そこで彼は、愛蔵が養蚕シーズンの始まるより一足早く実家に帰ってきて、「つまらん女と睦んで」いるのを見てしまったのである。新宿にやってきて「身を粉にして働いているシスター」を目にした守衛は、こんなけなげな妻を裏切るとは何事かと愛蔵への怒りを新たにしたのだった。
末っ子に生まれた守衛は、兄たちから可愛がられていた。新宿のアトリエも、浅草で帽子屋をやっている兄が作ってくれたものだった。甘えん坊の彼は、良にも甘えてシスターと呼んでいたが、夫の裏切りを知らずにいる良を眺めているうちに姉のように思っていた彼女に哀憐の情を感じるようになった。それはやがて良に対する愛へと変わっていった。
新宿のアトリエに移り住んでから、萩原守衛は毎日中村屋に通うようになる。そして良の仕事を手伝い、茶の間で子供たちと遊び戯れ、愛蔵不在の家で家族の一員のようになった。時に守衛は28才、良は32才の女盛りだった。彼は高村光太郎に「我心に病を得て甚だ重し」と手紙を書いて良を愛する苦しみを訴えている。
良の方でも、せっせと守衛のアトリエを訪ねた。そして一向に制作に入ろうとしない守衛に、鎌倉の成就院にある文覚像を見に行くように勧める。そして彼女は守衛と一緒に成就院に出かけ、文覚像を見たあと二人は七里ヶ浜の海岸に出て抱き合って泣いた。文覚の生涯について話し合っているうちに自分たちの未来が思われてきて、感極まって泣いてしまったのである(有夫の女を愛した文覚は、女の夫を殺そうとして女を殺してしまう)。
鎌倉から帰った守衛は、猛然と制作に着手する。
午前中はアトリエにこもって成就院の文覚像をモデルに粘土と箆で格闘し、午後になると中村屋に行って半日を過ごした。二人の親しみは増し、守衛は姉か母のように尊敬していた良に、遠慮なく我が儘を言えるようになる。
友人の結婚式の帰りに中村屋に立ち寄り、良の前で大の字に寝ころんで「ああ、今夜は酒でも飲ましてくれるといいなあ」と甘える。良が「守衛さも、淋しいのね」と慰めてやると、守衛は「かあさん、その通りです」といって大きなハンケチで顔を覆って泣いた。
良の方でも守衛を頼りにしていた。夫との関係に悩んでいた良は、鏡に映る自分の顔が険しくなったのを見て「ああ、私の顔、夜叉になった」と傍らの守衛にささやく。そして、二人は固く抱き合った。彼らの気持ちは、結婚を考えるところまで進んでいった。しかし、良は土壇場でためらう。守衛はいらいらして「何をぐずぐずしているんだ。どうして過去を断ち切らないのだ。何が未練だ」と良をなじった。
守衛にアトリエを作ってやった帽子屋の兄は、良にいい感情を持っていなかった。彼は、良が弟をその気にさせておいて、最後に突き放したと思っていた。守衛の友人の多くも、これと同じ見方をしている。最も激しく良を憎んだのは高村光太郎だった。彼は、「病死であろうと自殺であろうと、(守衛が死んだのは)みんなあの女がからんでのことだ」と罵り、「死因は脳梅毒だ。うつしたのは良だ」とまで言っている。
相馬黒光は人並み優れて情の深い女だった。同時に、彼女は冷酷なほどの現実感覚を備えていた。守衛の愛情にほだされて、彼との結婚を考えはしたけれども、愛蔵を棄てて年少の守衛と将来を共にする気にはならなかったのだ。
良は守衛の死の数日後、戸張弧雁と共にアトリエを訪ね、彫刻台の上に残された遺作の「女」を見たと「黙移」のなかで語っている。
絶作となった「女」が彫刻台の上に生々しい土のままで、女性の悩みを象徴しておりました。私はこの最後の作品の前に棒立になって悩める「女」を凝視しました。高い所に面を向げて繋縛から脱しようとして、もがくようなその表情、しかも肢体は地上より離れ得ず、両の手を後方に回した悩ましげな姿態は、単をる土の作品ではなく、私自身だと直覚されるものがありました。
胸はしめつけられて呼吸は止まり、私は、もうその床の上にしばらくも自分を支えて立っていることが出来ず、孤雁はまたそこに顔を覆って直視するに忍びないのでした。
萩原守衛(作品は「女」)
良がこの彫像を自分の像だと直覚したのは、「繋縛から脱しようとして、もがくようなその表情」や「肢体は地上より離れ得ず、両の手を後方に回し」ている姿態からだった。
彼女は、この一節によって自分が守衛を絶望の淵に追いこんだ理由を守衛の友人たちに弁解しているのである。家庭という繋縛があり、地上に固く結びつけられている自分には、守衛と行を共にする自由がなかったといっているのである。
守衛は中村屋の茶の間で、愛蔵夫妻と卓袱台を囲んで雑談中に喀血して倒れるのだが、部屋中に飛び散った血を見て良は失神している。守衛は結局そのまま中村屋で息を引き取る。この時の良の悲嘆は常軌を逸していた。二日間を泣き続け、棺が運び出されようとすると柩に取りすがって泣き崩れている。汽車で郷里に送られる柩を見送って帰宅してからも、良は突っ伏して何時までも泣いていた。
良と守衛の関係は、本当のところ、どうだったろうか。
守衛が愛蔵夫妻の次男襄二を異常なほど可愛がるので、あの子は良と守衛の間に生まれた子供ではないかと噂されたことがあった。「黙移」のなかの次の箇所にも疑惑が集まっている。前述の良が塑像の前で崩折れたという文章につづく部分である。
やがて私は孤雁の立会いで、ふるえる手を以て机の抽出しを開けました。中には鉛筆で余白がないまで書き記した日記のような帳面が入っていました。故人の遺言に拠り、一行も読まず、そのままストーブで焼こうと致しましたが、ああいう手帳のような紙は、なかなか焼けないものです。もしも燃え残りの紙片のために故人の秘密が人に知られるようなことになってはと、一枚一枚丹念にちぎっては焼き、ちぎつては焼き、眼には一字も見ず火中に投じ尽し、如何に探るとも一切を甲斐なき灰としてしまいました。
孤雁は私の冷酷な仕様を詰るように「イブゼン」の「ヘダガブラ」だと言って泣き、暫くの間死のような画室の静寂を破るものは孤雁の歔欷ばかりでありました。
良は「故人の秘密が人に知られてはと」と心配して、日記らしきものを火中に投じたと書いている。しかし孤雁はこれを眺めながら、良をヘッダ・ガブラーのように冷酷な女だと思ったのである(ヘッダ・ガブラーは自己中心的な女で、恋人が心血を注いで書き上げた原稿を死後に焼き捨てている)。
良が「黙移」を発表したときには、孤雁はすでに亡くなっていたから、この部分を書き足す必要はなかった。書けば、あらぬ疑いを呼ぶことになるだけなのだ。だが、この件が生前の孤雁の口から友人らに語られて、「相馬黒光」イコール「ヘッダ・ガブラー」説が広く流布していたとしたら、良としてもこの一節を書き足して一言弁明しなければならなかったのだ。
良は「目には一字も見ず」に日記を焼き捨てたとあるけれども、わざわざこう書くところに釈然としないものを感じる。良は、まるで自分の家のように守衛のアトリエに出入りしていたのだから、彼が日記をつけていたことを知っていたし、それを読んだこともあるかもしれない。
そもそも、「黙移」のなかのこの記事の全体が、事実に反しているのである。「黙移」によると、良は守衛の死後にアトリエを訪ねて、そこで初めて「女」を見たということになっている。だが、「新宿中村屋相馬黒光」によれば、この作品は良が勧めて作らせたものだった。だから完成すると、守衛は直ぐにそのことを彼女に知らせているのである。
知らせを受けた良は、子供たちを引き連れてアトリエにやってきた。すると子供たちは彫刻台の上の裸像を見るがいなや「カアさんだ!」と叫んだという。
「女」は裸像であり、その顔は空を見上げていて良を思わせるような特徴は何処にもない。顔は守衛が雇った岡田みどりというモデルのものだったのである。とすると、子供たちが「カアさんだ」と叫んだのは、母が守衛のためにポーズを取ってやるところを見ていたとしか考えられない。
岡田みどりは、守衛が過酷なポーズを取らせるので、何度もモデルをやめたいと申し出ている。そして実際に作品が完成する前にやめてしまっている。守衛はモデルがいないと制作できない質の彫刻家だったから、中村屋を訪ねた際、良にポーズを取ってくれと頼み、彼女はその依頼に応えたかもしれないのだ。もちろん、着衣のままだったろうが、その場面を子供たちは見ていたのである。
良がひそかにアトリエに通って、全裸のモデルになっていたということも十分に考えられる。
良はさまざまな男性と「スレスレの関係」を楽しんだけれども、夫以外の男に肌身を許したことはなかったと思われている。だが、萩原守衛との関係だけは特別だったかもしれない。
守衛の死後、良は抜け殻のようになり、床に伏すことが多くなった。この頃、良が安曇野の知人に送った手紙には、「疲れて疲れて丁度骨を抜き去られたように力がなくて、グッタリしてねてばかりいます」とあり、「黙移」には、「一時は重体に陥り、医師も匙を投げてしまいました。・・・・・私の煩悶はその絶頂に達しました」とある。
守衛の死を惜しむ点では、相馬愛蔵も妻に劣らなかった。
愛蔵は不思議なくらいに寛大な男で、良が守衛といくら親密にしていても、また美男で知られた戸張孤雁と二人で奈良京都に仏像を見に出かけても全く干渉しなかった。彼は、守衛の兄と相談して、守衛のアトリエを自宅の裏に移築し「碌山館」と名付けている(碌山は守衛の雅号)。入り口に吊す「碌山館」という軒灯の文字は良が書いた。
良は激情の女だから、人を愛する場合にも極端まで突き進む。だが、ある点まで行くと現実感覚が働いて踏みとどまり、身を翻して相手を突き放してしまう。こうした良の行動が相手を傷つけ、時に致命傷を負わせるほどになる事も多かった。次に紹介する中村彝も、その犠牲者といってよかった。
彼女は愛するものを傷つけると、激しい自責の念に襲われ、健康を害するまでになる。良は「病気への逃避」という言葉や、「ヒステリー性詐病」という言葉を連想させるほど、人生の節目節目で病気になっている。精神的なショックがストレートに健康状態に連動するというのは、それほどに激しい内面生活を彼女が営んでいたことを意味する。こういう良をキリスト教は救ってくれなかったから、彼女は、おぼれる者が藁にもすがるようにして、カリスマ性を持った精神的指導者に頼った。
良が岡田虎二郎を知ったのは、夫の友人・木下尚江が紹介してくれたからだった。守衛が亡くなってから2年後に、木下は病気で寝ている良の枕元に「岡田式静座法」の創始者を連れてきたのである。
岡田は無言でその場に座り込み、良に目を閉じるように命じた。そして20分ほどすると、今度は目を開けるように言った。それだけで、良の気分はすうーっとさわやかになった。この瞬間から、良の岡田に対する盲目的な帰依が始まるのだ。
岡田は毎日、日暮里にある本行寺の本堂で静座会を開いていた。朝6時という早朝に始まる静座会だったが、岡田の弟子たちは本堂に入りきれないで板廊下に溢れるほど集まって来た。良がこの静座会に出席するには、早朝4時48分に発車する始発電車に乗らなければならなかった。
ぞの後日暮里に通う途中、省線の中で突然卒倒して中村彝さんや子供達にかかえられ、駒込駅の待合にねかされたこと、また長男同道で日暮里から帰る省線の中で再発して巣鴨駅で下ろきれたこと、本行寺や静座中に倒れたこと等々屡々繰返して随分人騒がせを致しましたが・・・・
こんな調子で良は一日も休まずに本行寺に通い続ける。そして、きまって岡田と向き合って最前列に座るのである。岡田は静座会の後は、彼を信奉する有名人の家を歴訪するのが例だった。岡田は、ほかの信者を訪ねるのは週一回だけだったのに中村屋には週に二回足を運んでいる。岡田は良が師事してから、8年後に亡くなってしまう。
岡田を失って5年後に、良は浄土宗の権僧正渡辺海旭に師事するようになる。前回は守衛を失った時だったが、今度は長女の俊子を病死させたショックで彼女は生きる張りを失っていた。彼女は俊子の葬儀で導師を務めた渡辺海旭に必死になってとり縋り、芝増上寺で日曜ごとに開かれる海旭の説法会に欠かさず出席するようになるのである。
生活に日毎の食事が必要であるように、先生の講演は魂を養う糧でございました。もしただの一度でも講演をききのがすことがあったら、それはもう終生とりかえしのつかぬ大損をするように感じられ、欠席することは最も辛うございました。それで私は先生のお側にいるお弟子さんにお頼みしておいて、先生のお休みになることが分れば予め知らせてもらい、その休みの間にいろいろ用事を済ましたり、旅行に出かけたりしました。それもどんなに遠方までまいっておりましても、日曜講演の朝までには必ず帰って間に合わしました。
その為も少しゆっくり見物したいと思っております夫まで急き立てるようになりまして、屡々相済まぬことでございました。しかし夫も先生には深く帰依しておりました。
愛する者の死に責任があると感じると、良の精神はパニック状態に陥ってしまう。そのせっぱ詰まった状況から抜け出るには、カリスマ性を持った「精神指導者」に縋り付くしかなかったのだ。無気力な実父に失望してきた良は、父性を感じさせる力強い男性の前に出ると、磁石の前の鉄片のように引きつけられてしまうのである。
良は芸術家、学者のパトロンとして知られている。叔母の佐々城豊寿の邸も千客万来でにぎわったが、中村屋に集まる来客もそれに劣らなかった。
当時「中村屋サロン」と呼ばれた茶の間には、鳥居龍蔵、津田左右吉、會津八一、岩波茂雄をはじめとする有名無名の客が押しかけ、日に20人もが入れ替わり立ち替わりやってくることがあった。そのため良は、彼らを接待するために専用の料理人や女中を雇い入れたほどだった。
そうした客の中から、良と特に親しい何人かの仲間が生まれた。これには三つのグループがあった。萩原守衛の関係から集まる美術家たち、岡田虎二郎の静座会で知り合った静座仲間、中村屋が亡命者をかくまってくれるという噂を聞いて頼ってきた外人グループがそれだった。
良はこの三つの系統のそれぞれから中村彝、桂井当之助、エロシェンコという三人の若者を選んでペットのように可愛がっている。
中村彝(つね)が、中村屋の裏にある守衛設計のアトリエを貸してくれと愛蔵夫妻に頼み込んだのは、それまでそこに住んでいた守衛の友人柳啓助が結婚して新居に移ったからだった。許可を得てアトリエに移ってきた彼はやがて夫妻一家と食事を共にし、家族の一員として遇されるようになる。中村彝は萩原守衛と同様に末っ子の甘えん坊で、良に遠慮なく甘えていったところが気に入られたのである。
良と中村彝は顔を合わせれば、激しい議論を交わした。
談一度芸術や宗教に移るや、随分私達は興奮したものだ。話が高潮に達するに従い、彝さんはポーツと上気する。目が輝く。早口になる。息がはずむ。しまいに膝と膝が打っ突かる迄詰め寄って来る([新宿時代の彝さん」)
中村彝は「カアさんはいつも物欲しそうな顔をしている。俺は嫌いだ」とつけつけ良に当たるかと思えば、「オカーサンは悪党だ、埒のそばまで人を引寄せておいて、その内には一歩も踏み入らせないやり方だ、馬鹿者は知らず知らずにうかうか近寄って来るのだ」と罵ることもあった。
良と中村彝の間に、どんな隠微な関係があったのか知るものはいない。だが、彼は良の寵愛がライバルの桂井当之助の方に傾いたと感じると、娘の俊子に愛情を移すようになった。
人質として婚家に残してきた長女の俊子が信州で義務教育を終えたとき、良は娘を東京に呼び寄せて女子聖学院という寄宿制のミッションスクールに入学させた。俊子は金曜日の夕方に帰宅し、二日家に泊まって日曜日に寄宿舎に帰っていった。
良は田舎から出てきた土臭い娘を、都会風の近代女性に仕立て上げようとして厳しい態度で臨んだ。俊子を寄宿制のミッションスクールに入学させたのも、アメリカ人から直接英語を習得させるためだった。良は週末に帰宅した娘に、口やかましく礼儀作法や言葉遣いを教え込んだ。
俊子は自家に息苦しさを感じて、寄宿舎から帰ってくると母屋には寄らずに裏の中村彝のアトリエに直行するようになった。中村彝は、そういう俊子をモデルにして絵を描いた。そして、その絵が大正博覧会の美術展覧会に出品されることになったのである。
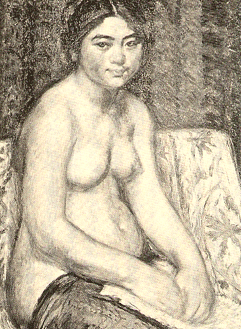 中村彝の描いた俊子
中村彝の描いた俊子女子聖学院では、この噂で持ちきりになった。天才画家中村彝が、わが学院の生徒をモデルにして傑作を完成したというのである。初日には、全校で展覧会を見学に行くことになり、院長のミス・クローソンは前日に下見に出かけた。作品を一目見てびっくり仰天した院長は、作品を撤去するように博覧会当局に申し入れている。絵は清楚な少女像どころか、俊子の裸像だったのだ。
結核を病んでいた中村彝は、この事件の後、出奔するようにして伊豆大島に渡り、島から戻ってくると日暮里の粗末な下宿屋に移ってしまう。そのくせ、中村屋に顔を出すことをやめない。そして茶の間に居座るライバルの桂井当之助を相手に、店を突き抜けて表通りに響くほどの大声で言い争ったりする。愛蔵夫妻は中村彝をもてあまし始めた。
その中村彝から突如相馬夫妻にあてて俊子と結婚させてほしいという手紙が届く。まるで、喧嘩をふっかけるような乱暴な文面だった。夫妻が放っておくと、彼は直接俊子に渡りをつけて、「今夜9時に家出をせよ、一緒に住もう」と連絡してきた。このことを娘から打ち明けられた良は、俊子を隠すことにして、娘の身柄を桂井当之助に預けるのである。すると、その夜、桂井の家に石が投げ込まれ、桂井当之助は震え上がってしまう。良は娘を隠す場所をほかに探さなければならなかった。
中村彝は、その後も愛蔵を殺しに行くといって長い日本刀を振り回したり、手紙で悪口雑言を投げつけてきたり、狂ったような行動をつづけている。そして俊子との結婚を果たせないまま、9年後に亡くなるのである。
桂井当之助は早稲田大学文学部の最年少助教授(20代半ば)で、岡田の静座会に通っているうちに良を囲むグループに加わったのだった。そして、彼はグループの中で良の一番のお気に入りになった。中村彝と同じ年齢の桂井は、無精髭を生やしむさくるしい服装をしている彝とは違って、背広に蝶ネクタイをしめ、髪を綺麗になでつけ髭を青々と剃っている絵に描いたような青年紳士だった。
良はこの桂井当之助とイプセンの勉強をすることを思い立ち、金曜日をその日にあてた。桂井も毎週金曜日を休講にして中村屋に通った。二人は、一日中部屋にこもって英訳のイプセンの劇作を読み、それを全部あげてしまうと、メーテルリンク、トルストイ、ドストエフスキーへと進んだ。桂井は「中村屋の若い燕」と呼ばれるようになった。
桂井も守衛や中村彝と同じように、良の子供たちとも仲良くなり、末っ子の哲子が急性肺炎になったと聞くと、自身も病気で高熱に苦しんでいたにもかかわらず、全身を毛布にくるんでその病床に駆けつけている。その無理がたたって桂井が死んだと聞くと、良は病院に駆けつけ、遺族の目を盗んで霊安室に入り、死体を愛撫している。
私は顔を近く寄せて飽かず凝視しておりましたが、その時は不断の自分と、まるで変ってしまいました。その時私はただただ目前の一つの顔に向って氾濫する感情のみになりました。
私は生前決しで触れなかった死者の頭の毛にそっと手を触れ、氷の針のような感触に身を慄わせました。象牙細工のような額に触れました、頬に触れました。その冷たいこと、冥府の世界の冷たさに通じていました。心のままにその顔を愛撫して私は一種異様な満足を覚えたのでございます。
私は今偏に懺悔教すのでありまして、親しい異性の死者の上に、一陣の魔風を吹かせた私、ああ私という女はと思い、自分の怖ろしさに怖気だつのであります。(「静座十年」)
この一文は、良が桂井当之助をそれとなく誘ったことを告白した文章なのである。「一陣の魔風を吹かせた私」という言葉につづけて「ああ私という女は」と記し、自分自身の恐ろしさに怖気だつと記すところに彼女と桂井の関係がありのままに吐露されている。
良は、まだ年若い相手を中年女の手練手管で誘惑し、「埒の近くまで引き寄せておいて、決してなかには立ち入らせない関係」を楽しんでいたのだ。自分には指一本触れさせないでおいて、相手が死ねばその遺体を愛撫する、この良の行動には、何となく奇妙なものがある。
「新宿中村屋相馬黒光」の著者宇佐美承は、良が「ただ一度たりとも夫の身体を満足させてやったことがない」と書いている。これが何を意味するのか推測するしかないけれども、良には不感症の傾向があったかもしれない。
萩原守衛、桂井当之助を失った後で、良のペットになったのは盲目詩人エロシェンコだった。ロシアを祖国とするエロシェンコは、日本にやってきたものの第一次世界大戦が始まってロシアからの送金が絶たれ、途方に暮れていた。友人の秋田雨雀と神近市子は、(ここは金もあり、弱い者には手を貸す中村屋の女主人の協力を仰ぐべきだ)と考えて、エロシェンコを良に紹介したのである。
トルストイやドストエフスキーに惹かれてロシア語を習っていた良は、たまたま「カラマーゾフの兄弟」を原語で読んでいたところだった。エロシェンコがロシア人であること、自分より14才も年少のこの詩人の邪気のないところが気に入って、良は彼を裏のアトリエに住まわせることにした。
良は、エロシェンコには自分をマーモチカ(母さん)と呼ばせ、実際に母親のように親身も及ばぬ世話を焼いた。食事時には、盲目の彼を自分の隣に座らせ、おカズを皿に取り分けてやった。
私は遂に前後4年の間(エロシェンコを)隣の椅子に坐らせて食事の世話を致しました(「白ロシヤの人々」)。
と良は書いている。
良は年少の好ましい男たちには自分をシスター・マザー・マーモチカなど呼ばせて世間的に通りのいい関係を作り、その裏で「一陣の魔風を吹かせて」それとなく相手を誘う。そして、相手の上位に立って男を翻弄するのである。彼女は告白している。
いささかこちらが強くなると相手を嘲弄したりして手のつけられぬ見事悍馬になってしまいました。これがため周囲の異性や夫をいかに苦しめ、迷惑をかけましたか、思えば恐ろしいことでございます(「半生を顧みて」)
上位にあるカリスマには平身低頭して跪拝するけれども、下位にある男性にはサディスティックな態度で臨む。この理由を、良は姉の問題で「極端に異性を憎悪する」ようになったからだと説明している。彼女のこうした自己弁護には、一筋の真実がまじっている。
有島武郎は、「或る女」のモデルだった佐々城信子を男性本位の古い日本に挑戦したパイオニアだったと解説している。信子は、自我を守って生き抜いたヘッダ・ガブラーのような女だったというのである。
男性本位の社会に抵抗して自我を存分に発揮したという点では、佐々城信子よりも相馬黒光の方が立ち勝っている。信子は官能の欲するままに男を乗り換えていったが、良は女性を犠牲にすることで成り立っている日本社会に対する火のような怒りを意識の底深くに秘めて男を翻弄した。
彼女が妻主導の家庭を築いて亭主を尻に敷いたのも、「若い燕」たちを身の回りに集めて恋の駆け引きを楽しんだのも、本人は意識しなくても古い日本に対する挑戦としてだったのである。
良の反逆精神が、かりそめなものでなかったことは、亡命インド人ボースをはじめ多くの「反逆者」を自宅にかくまったことでも分かる。
弱い者に手を貸すという良の義侠心が最初に発揮されたのは、国木田独歩と佐々城信子の間に生まれた薄幸の女の子を自宅に引き取ったときだった。信子は独歩の子供を身ごもったまま別れ、離婚成立後に生まれた女児を里子に出してしまった。良はこの子を引き取って、自分の子供と一緒に育てているのだ。本郷でパン屋を開業し多忙を極めていた頃のことである。
やがて船の事務長と所帯を持った信子が、娘を返してほしいと言ってくる。だが、実母のもとに戻った娘は8年後に家を飛び出して再び中村屋に戻ってきている。これが手始めだった。その後、良は、直ぐには数え切れないほど多くの人間を援助したり、自宅にかくまったりしている。
そのほか、市電がストライキをしたときに自宅を作戦本部に提供したこともあるし、正月に朝鮮からの留学生30人を招待して雑煮をふるまったこともある。こうした多面的な活動を展開するなかで、相馬家に最も大きな影響を与えたのは亡命インド人ボースだった。
ボースはインド独立運動の闘士で、イギリス人総督を襲撃して負傷させたためにイギリスの官憲から追われる身になっていた。日本に亡命してきたボースを保護したのは、右翼の巨頭・頭山満をはじめとする宮崎滔天、大川周明、寺尾享など大アジア主義を奉じる「国士」たちだった。一方、政府は同盟関係にあるイギリスからボースを引き渡せという要求を突きつけられて困惑していた。折から、第一次世界大戦のさなかで、日本は同盟国である英国の要求を無下には断れない立場にあったのである。
政府はボースの身柄引き渡しを拒否したけれども、彼を国外に追放することで英国の要求に間接に応えようとした。こうなればボースを救うには、彼を何処かへ隠してしまうしかなかった。ボースを自邸で保護していた頭山は、政府の監視下にあって自由に動くことが出来ず、ボースの運命は窮まったかに見えた。この時に、相馬愛蔵がボースをかくまうことを申し出たのである。
ボースを自宅裏のアトリエにかくまったことから愛蔵夫妻は、頭山満との関係を深めていく。もともと夫妻は木下尚江、島田三郎などのキリスト教系社会主義者と懇意で、政治的には社会主義の系列下にあり、体質的に左翼思想になじんでいたのだった。それが、今や右翼の大ボス頭山満の意を受けて行動するようになったのだ。
良が頭山満を崇拝するようになったのは、その頃、彼が政府に対抗する一大敵国と見られていたからだった。頭山には、良好みのカリスマ性があった。巖本善治、岡田虎二郎、渡辺海旭などの指導者を亡くして心のよりどころを失っていた彼女は、頭山という右翼の巨魁のなかに新たな帰依の対象を見出したのだった。
ボースは四ヶ月半中村屋に隠れ住んだ後に、次の隠れ家に移った。警察の目を逃れるには、短い周期で、転々と住まいを変えなければならない。絶え間なく居所を変えながら逃亡生活を続けるボースとの連絡係には、秘密を知っていて、しかも英語の出来る人物が必要だったが、頭山の周囲には、そうした人間がいなかった。
俊子は女子聖学院の高等科に学ぶうちに英語に堪能になっていたし、寡黙で口の固い娘だったから、連絡係に最適だった。しかし良は、娘の俊子をボースと頭山の間を取り結ぶ連絡係にしたことを後で後悔することになる。
やがて頭山から無理難題といえるような話が持ち込まれた──ボースに婆や一人をつけておくだけでは、心許ない。ボースに一日中つきそって、彼の目となり耳となるような女性がいてくれたらと思う、俊子がそうした女性になってくれたら有り難いのだが、というのである。これはつまり、俊子とボースを結婚させろという要求にほかならなかった。
中村彝が俊子に求婚してきたときには、良は相手が肺病持ちの貧乏絵描きだからと突っぱねたけれども、今度は政財界に隠然たる勢力を持つ頭山満の申し入れである。簡単に断ることが出来ない。良は、頭山にOKの返事をする。だが、良の気持ちは複雑だった。頭山の依頼に応えて俊子を承諾させるために自分が親の権威を振りかざして、「圧服的な態度」で娘に臨んだことを自覚していたからだった。
俊子はこの事件に対する私共の最初からの筋合を知っていて、その上先生から強っての懇望とあっては、父母の立場を思って、どうも返答の自由を持たないだろうと思う。今更に私はともすれば圧服的に近親に臨む自分の悲劇を呪わなくてはいられなかった(『満水録』)
良も俊子も、これが一種の人身御供に他ならないことを承知でボースとの結婚を承知したのである。
俊子には哀切な話がある。結婚後、ボースは無口な俊子を誤解して、自分といやいや結婚したのではないかと疑った。それで俊子を問いつめ、本当に自分を愛しているなら、ここから飛び降りることが出来るはずだと地面を指さした。二人は、その時、高い建物の屋上にいたのである。
すると、俊子は無言で欄干に駆け寄り、まさに飛び降りようとした。狼狽したボースが慌てて抱き留めたので、事なきを得たというのである。
俊子はボースとの間に二人の子をもうけた。だが、それも束の間、肺炎を病んで26才の若さで亡くなってしまう。皮肉にもそれは、良が中村彝を追悼する依頼原稿を書いている時だった。この少し前に中村彝は病死し、俊子は彝の跡を追うように幸薄き生涯を終えていたのだ。
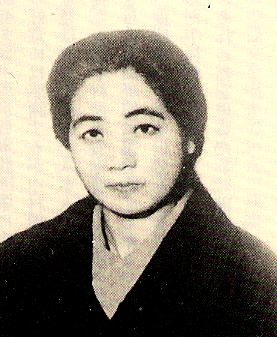 中村彝・俊子を相次いで失った頃の相馬黒光
中村彝・俊子を相次いで失った頃の相馬黒光
俊子に死なれてようやく良は、自分がいかに残酷な親であったかに思い当たるのだ。彼女は信州穂高村から逃げ出したい一心で、俊子を婚家に置き去りにしてきた。そして娘を東京に呼び寄せてからは、新時代のレディーに仕立て上げようと礼儀作法から口の利き方まで厳しくしつけた。そして、中村彝との関係を引き裂いておきながら、頭山の意を迎えようとして俊子を亡命インド人と結婚させた・・・・・
自責の念に駆られた良は、萩原守衛に死なれたときと同様に病気になっている。渡辺海旭に帰依したのは、俊子の冥福を祈るためだった。
良は外面(そとずら)のいい女だった。頼まれれば誰にでも手を貸し、惜しみなく経済的な援助を与えた。だが、その裏では彼女は店の包装紙の裏を便箋に使って、書き損じたところには別の紙を貼ってその上に書くというような倹約をしていた。
彼女の内面(うちづら)の悪さは、店の従業員や家族への態度にあらわれている。良は年老いてからも、ショウケースの上を指でなぞって埃が付いていないかどうか点検し、客用のトイレが清潔に保たれているか細かに調べた。そして、年末になると従業員を集めて、長々と訓辞をするのが恒例だった。店員たちは愛蔵に信服する一方で、良の訓話にはうんざりして「コケコッコウ(黒光)夜が明けた」と陰口を叩いた。
内面の悪さは、家族に対するときに最も露骨に現れた。良は長男の安雄に「わたしぐらい生涯我儘ばかり許してもらった女はいないね」と語っているが、彼女は生涯、家族の全員に自分の考えを有無を言わせずに押しつけている。
良が暴君になったのは、家長の愛蔵が妻に逆らうことをしなかったからだった。彼は妻が、「中村屋の若い燕」と呼ばれる男たちと何をしても、黙って放任していた。良が若い男と二人で旅に出て泊まってきても咎めることをしなかった。
長年、母の行動を間近に見てきた長男安雄は歯に衣着せぬ調子で語っている。
黒光ぐらい生涯を通じて自己の思いの侭をやってのけた人は稀であろう。総ての言動が自己中心に為されている。少くともわが邦の女性として、且また人の妻女でこれ丈け自由奔放に振舞った者は珍らしい。が併し母の自由奔放さは稀に見る寛大な父の性格に因るものであった。それは母に察知出来ない程の大きさであった。恰も孫悟空に対する仏掌の如き関係であったろう。
父親が母の言う侭になっているとしたら、子供たちも母の言いなりになるしかない。俊子は母の気持ちを察してボースに嫁ぎ、俊子の妹の睦は良が首を振らなかったので生涯を独身で通している。孫の一人が、なぜ睦叔母さんは結婚しないのかと祖父の愛蔵に尋ねたら、「自分は結婚させてやりたいが、良が賛成しないのだ」と答えたという。良の反対理由は、睦にいくら持参金を持たせてやっても直ぐ身ぐるみ剥がれて戻ってくるから、というものだった。
中村屋は素人劇団がたびたび家の中で劇を上演したほど大きかったのに、良は未婚の睦とボースから預かった二人の孫を同じ部屋に寝かせている。そして、子供たちが私用で女中を使う場合には、あらかじめ母の許可を求めさせた。この辺は、ある意味で見事といってよかった。だが、良のスパルタ式教育は、しばしば行き過ぎていた。
四男の文雄はおとなしい子だった。だが、学校の成績があまりよくなかった。そういう文雄にいらだった良は、中学校に通っていた文雄を中退させて島貫兵大夫の創設した日本力行会海外学校という南米開拓者用の学校に入学させる。そしてアマゾンに土地を買ってやり、17才の文雄をたった一人で現地に送り出すのだ。
文雄は2年後、19才の若さでマラリアにかかって死んでしまう。
・・・・・昭和5年1月9日、突然一通の外国電報を受け取りました。「11月2日フミヲアマゾンニシス」とあります。急に天日光りを失い、闇黒の世界と化した心地がいたしました。喜々として遊んでいた孫達も声をひそめ、あちらこちらからすすり泣きの声が聞えて来ました。十一月二日といえばニケ月あまりも前でありますのに、どうして今まで通知がなかったものか、誰にも起る疑問でございます。そして彼の死にようが気にかかりました。
アマゾンの江流で鰐にのまれたのか、猛獣の餌食になったものか、それとも人跡未踏の原始林で、ただ一人のたれ死をしたものか、想像はそれからそれへと悪い方に走り、それでもひょつとしたらという万に一つの望みも出て、子供の死をたしかめるために、度々外務省の当局に交渉をいたしましたが、要領を得ません(「発願」)
子供に死なれてみて、はじめて身を噛むような自責の念に駆られる──これが良の繰り返してきた懺悔のパターンだった。彼女は日も夜も泣き明かし、鎌倉に建てた草庵を文雄を慰霊する場にして読経を続けた。
悲嘆でいっぱいになった良は、本来自分に向けるべき怒りをよそに向けた。やり玉に挙げられたのは、文雄の弟の虎雄だった。
文雄に2年遅れて生まれた五男虎雄は、おとなしい兄とは反対に元気のいい子供だった。小学校三年生の時に母のつけてくれた英語の家庭教師を閉口させるほど頭の鋭い子で、学校の成績もずば抜けていた。相馬家では、女の子はミッションスクール、男の子は愛蔵の母校である早稲田と決まっていたから、虎雄は早稲田中学校から早稲田高等学院に進んだ。
文雄の訃報が届いたときに、良は虎雄に退学届けを出させている。表向きは、虎雄が中学生時代に学校騒動のアクティブ分子であり、高等学院に入学後も、思想的な動揺から落ち着かない生活を送っていることを理由に挙げている。
だが、文雄を退学させた良の気持ちは、宇佐美承が推測するように「兄の文雄は中学を中退してアマゾンで苦しんでいたのに、弟の虎雄は親元からぬくぬく学校に通って勝手なことばかりしている」ということだったにちがいない。さらに良は、反抗的な虎雄を罰するために、当座の費用として20円を与え、これで勝手に暮らせと家から追い出してしまった。
問答無用で息子を家から追い出しておいて、その日を虎雄の命日と決めて仏壇の前で彼の冥福を祈り続けたというのだから、良のすることは徹頭徹尾独善的だった。彼女は身を焼くような自責の念から、何の罪もない虎雄に当たり散らし、そのことで彼の人生を狂わせ、またもや自己呵責の種を一つ増やすのだ。後年になって、良は懺悔する。
私は子供達に謝らねばならないことなら沢山あるけれど、讃えてもらうようなことは何一つない……同じ罪はどの子供にも負わねばならぬが、子供達はよく私をゆるしてくれた、ただ一人だけ、私をゆるさない子供があった、それが末男虎雄である(『滴水録』)
虎雄は家を追い出されてから半年後に、愛蔵夫妻の留守を狙って店に現れ、番頭から問屋に支払う金をださせて姿を消している。良は即座に次のような貼り紙を店に掲げた。
<私共の五男虎雄は共産党に入りましたので勘当いたしました 以後中村屋とは何の関係もありません 主人>
やがて思想犯として逮捕された虎雄は、釈放されて家に戻ってくる。その後、彼は仙台の叔母の家で一年を過ごし、東京に戻って上智大学に入学したりしている。だが、やがて再び逮捕され、留置場で監視の巡査の首を絞めて脱出をはかるというような事件をひき起こす。
この頃の良は木下尚江や秋田雨雀、神近市子や市川房枝のような左翼系のリベラリストと親交を結ぶ一方で、心情的には日本の大陸進出を支持する国家主義者になっていた。渡辺海旭に心酔しすることで、キリスト教を棄てて仏教徒になった彼女は、頭山満を崇拝することで、自由主義から離れてナショナリズムの信奉者になっていたのだった。それだけに虎雄の左傾は胸に応えた。
良は、息子の度重なる逮捕に打ちのめされ、ほとんど病人のようになる。虎雄の姉の千香は、良が懊悩の末に「一夜にして白髪になる」という言葉を連想させるほど頭髪があっという間に白くなったと語っている。
虎雄は市ヶ谷刑務所の独房で二年あまり過ごして釈放され、昭和9年の末に家に戻って来た。しかし、これが相馬家で繰り広げられる修羅場の幕開けとなった。虎雄は、母がリベラルなことを口にしながら、頭山のような右翼に叩頭するのが我慢ならなかった。しかし衝突の原因はそのことではなく、虎雄が女中のシズエを愛して、彼女と交換日記を取り交わすようになったためだった。
シズエの両親も中村屋に雇われていたから、良からすればシズエは雇い人の娘に過ぎない。良から見れば、シズエは二重の意味で身分違いの女だった。
母に苦言を呈された虎雄はいきり立ち、大暴れに暴れた後で「お前自身の姿を見ろ」と良を睨み付けた。身分違いだといって反対する汝自身の虚栄心や事大主義を反省せよと言うのである。
母子の争いは激化する一方だった。二階の虎雄の部屋で言い争っているうちに激高した虎雄が母親にものを投げつけ、おびえた良が階段を転げ落ちるように逃げ出すと、上から虎雄が投げる正月の鏡餅や伊勢エビが降ってくるというような騒ぎが頻発した。
良は結局折れて虎雄の結婚を承知する。
長男の安雄も、日本に住み着いたボースも、安雄とシズエの結婚には賛成だった。安雄などは虎雄の耳に「兄弟姉妹のうちで、お前が一番いい籤を引いたよ」とささやいた。
やがて昭和医学専門学校に入学した虎雄は、昭和15年に卒業して東京府立豊島病院の医師となり、シズエと正式に結婚する。だが、幸福な生活は長くは続かなかった。虎雄は招集されて軍医となり、満州北部に赴任して、敗戦と共に消息不明になってしまう。
太平洋戦争が始まったときには、良は日本が米英を撃滅して、アジアの盟主になるといって喜んでいた。けれども、彼女の賛美してやまなかった戦争は、中村屋を灰燼に帰せしめ、末っ子の虎雄を奪ってしまったのである。
相馬愛蔵夫妻は、空襲によって中村屋関連の施設をすべて失ったが、昭和23年には中村屋を復興開店させている。時に良73才、愛蔵78才だった。それから6年後の昭和29年に愛蔵が永眠し、つづいて翌年の昭和30年に良は80才で死去している。
相馬黒光は常々自分のことを「傲慢我執の標本」とか、「生涯我が儘を通した女」と語っており、明治以後のインテリ女性の中では最も主我的な生き方をした一人だった。だが、欧米のその種の女性に比べてみると、やはり日本人らしい特徴が目立つのである。
外国の自我主義者は、女性であっても自分以外の権威を一切認めていないし、新しい恋人が出来れば離婚・再婚を繰り返して平然としている。しかし、相馬黒光は少女期の頃から、自分を指導してくれるカリスマ的な指導者を求めつづけ、世俗的な権威に縋りつづけた。そして結婚後に多くの男たちと疑似恋愛を繰り返しながらも、死ぬまで愛蔵と離婚することはなかった。
実質的に父親不在の家庭にあって相馬黒光は、小娘の身で父親の代役をこなし、家族を意のままに動かし続けた。彼女自身、そうすることを可能にするカリスマ性を備えていたのである。この状態は結婚して家庭を持ってからもつづき、彼女は夫の愛蔵の代わりに家長の役割を果たし、中村屋を創業してからは従業員に対しても家父長として臨んだ。
相馬黒光はカリスマ的人物に師事し、次にその真似をして家族や従業員にカリスマ的指導者として臨んだように見える。けれども、子細に検討すれば順序は逆であり、彼女は当初から小さなカリスマだったのである。
行く先々でリーダーシップを発揮しながら、身近に模範とすべき指導者モデルを持たず、また、確たる行動原理も持たなかった彼女は、内心不安でたまらなかった。それでカリスマ的なリーダーに師事することで、そこから力を借りようとしたのだ。
自分の過ちによって、愛するものを傷つけたり、死なせたりしたとき、相馬黒光の不安と自責の念は頂点に達し、カリスマ型指導者に盲目的に帰依した。そして彼らの発散するオーラを自分のエネルギー源にしたのである。
彼女が真の自我主義者だったら、我流のリーダーシップを押し通し、外部のいかなる権威に頼ることもなかったに違いない。そして、そうしたなら事業家としてもっと成功したかも知れない。だが、彼女は感じやすく涙もろい日本の女だった。
相馬黒光の内部には、国木田独歩が指摘したような「同情の人、野心なき人、上品の人」が隠れていた。だから、二流の指導者にも素直に従い、間違ったことをしたと思えば病気になるほど苦しんだのである。
彼女はナイーブな日本の女性そのものだった。