敗戦直後の日本を、少女の目で眺めたらどうなるか。
それも、末は大学教員になるような賢い少女の目で眺めたら。
しま・ようこの著書「”敗北の豊かさ”からの出発」には、少女期に戦後日本を生きた体験が語られている。これは、加藤周一「羊の歌」の女性版といったような本なのである。
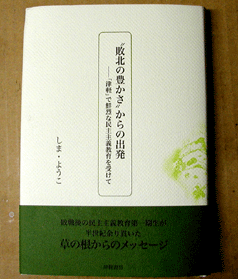
しま・ようこは職業軍人の娘で、父の出征中は温暖な鎌倉で暮らしていた。父が敗戦の年の二月にフィリピンで戦死したのを機に、一家は父の故郷である弘前に移り住むことになる。弘前には、父方の祖父が一人きりで暮らしていた。高齢の祖父が程なく亡くなったため、しま・ようこたちは、なじみのない津軽で、母・姉・妹の女ばかり四人で生きて行くことになった。
生活は、苦しかった。
何しろ、母は職業軍人の妻で、姉は女学校生徒、しま・ようこは小学校5年生、妹はまだ学校にも上がらない幼児だったのである。第一に、毎日の食糧を手に入れるのが大変だった。野菜類は裏庭を畑にして自給するとしても、その他の食糧はタケノコの皮を剥ぐように手持ちの衣類を売り払ったり、リンゴの袋貼りなどの内職によって調達するしかなかった。
そんな生活を苦にしないで元気に生きていくのが子供というものである。しま・ようこは、まず津軽弁の修得に取りかかっている。学校に行っても、教室には級友たちの津軽弁が歌のようにあふれていたが、彼女にはその内容がさっぱり理解できなかったからだ。
そこで彼女は独特のやり方で方言克服の作業に乗り出すのだ。単語カードを作って、一つずつ津軽弁を覚えていったのである。「はんかくせえ=ばかばかしい」、「あんずましい=うんと気分がいい」、「しがま=つらら」・・・・
敗戦後の学校教育は、急速に変化していた。
「初めて迎えた津軽での冬休みの宿題は『自由研究』だった。何でもかまわない、興味を持ったことを採り上げて『題』を自分で決め、どういう形で取り組んでもいい。方法も形式も分量も自由。命令形でがんじがらめの戦時中の教育からわずか数力月後の、このとてつもない宿題の形が、北島先生のアイデアによるものだったか定かではない。始まったばかりの『子どもの自主性を重んじる民主主義教育』の路線に沿った具体策として、進駐軍の指導によるものだったかもしれない」(「敗北の豊かさからの出発」)
しま・ようこは「自由研究」の宿題を、まるで待ち望んでいたプレゼントであるかのように受け取って、早速「研究」に取りかかる。彼女はざら紙を紐で綴った表紙に「しがまの研究」と題を大きく書いた。戦時下の暗い日常にならされた小学生にとって、「自由」も「研究」もキラキラ輝くまぶしい言葉だった。学校という場で、自分で何かを決め、決めたことを自力で実行することが許されたのだ。それは生徒たちに学習を自分で選べるという「主人公感覚」を与えてくれるものだった。
このテーマは、津軽で迎えた最初の冬のしがまへの驚きから決めたのだった。第二大成国民学校の三階建てコの字型校舎の両角に垂れ下がるしがまの大きさを、下から見上げて感嘆していた。その大きさと形の変化はどうやら気温に関係がありそうだった。
冴え返る寒気にしばれた明くる日は太く短く、積もった雪がびしょびしょする次の日は細く長くなる。わたしは冬休み中のしがまの形を写生し、毎日の温度と湿度をグラフにした。日々眺めていた直観を確かめただけの、研究というより観察記録にすぎないものだったけれど、「しがまの研究」はその後のわたしのものごとに対する選択と見方のスタートラインを引いてくれたような気がする。選ぶ原点には生活実感から来る「なぜ?」という問いがあり、問いは自分で確かめなければ解き口は開けない。宿題のテーマが自由に選べた体験の大きさがわたしの自主性の根っこになったと考えるのは、過大評価だろうか。
このあたりの叙述に、後年、研究者になるしま・ようこの素地をうかがえる。彼女は子供の頃から宿題や調べものをすることが好きだった。彼女はそれを娯楽と一続きのものと考えていた。現代の子供たちがパソコンゲームに熱中するように、彼女は調べものに熱中できたのである。
とにかく、津軽の冬は厳しかった。
朝起きると、まず、凍り付いたポンプ式の井戸を溶かすことから始めなければならない。前夜に汲んでおいた釜の水、(これも表面が凍って板のようになっている)を沸かして、熱湯でポンプを溶かすのだ。こうして、ようやく一日が始まる。だが、彼女は「不便さの実感はなかった」と書いている。
しま・ようこは、敗戦後の混乱した社会の中から、新しい時代を嗅ぎ当て、それに全面的に身を任せていった。同様に彼女は、貧しい暮らしの中から手仕事の喜びを探り当てもした。彼女は手元にある布で自分の服を作り、セーター・マフラー・手袋・靴下などをすべて自分で編んだ。毛糸は古いセーターをほどいて湯通しをして再生したものを使った。新しい毛糸を買ったことはなかった。
洗濯も粉石けんを使って、自分で洗った。こうした手仕事を彼女は成人してからも続けている。端切れを集めて手製した衣服を今も常用し、洗濯も手洗いで行っている。洗濯をしているうちに詩や論文の着想が浮かんでくると、泡だらけの手でメモを取りに走るのである。
しま・ようこは、袋貼りの内職も、興味を持ってやった。
機械的・事務的な仕事も固有なリズムをつかめば面白くなる。彼女も袋貼りを続けているうちに手がリズミカルに動くようになり、その仕事を楽しめるようになった。
一般に、人は勝利よりも、敗北によって学ぶことが多い。そして、豊かさの文化よりも、貧しさの文化のなかに楽しみが眠っている。貧しさの文化の中核に、手仕事の喜びが含まれているからなのだ。便利な既製品を買いあさり、もっと便利なものが出てくれば、古いものを捨てて新しいものに飛びつく豊かな文化よりも、自身の生活哲学に合致したものを手作りし、それを家族のように身辺に置く貧しさの文化の方が、より一層人の心を豊かにする。そこには安定した静かな生活がある。
しま・ようこは未だにテレビもパソコンも持たず、「わたしは静かな貧しさを愛する」と語っている。
小学校を終えたしま・ようこは、「新制中学」第一期生として中学校に入学する。
文部省は新制中学の一年生用に「新しい憲法のはなし」を作って配布し、生徒たちは社会科の時間にこれをテキストにして憲法の勉強をすることになった。しま・ようこは、このテキストによって、「これからは一人ひとりが大切にされ、社会の主人公になっていくという”光の感覚”を身につける。
当時の中学校には、若い教員が多く、その能力は必ずしも高いとはいえなかった。今ではとても通用しないような授業をする教師もいた。「アンド」というあだ名の英語教師は、「おれの発音は悪いから、真似するんじゃないぞ」と生徒たちを笑わせながら授業していた。生徒たちは自身の非力についてあれこれ弁解しないで、それをユーモラスな教材にしてしまう相手のしたたかな人間味を歓迎した。
まだ人も制度も整っていない学校には、それ故に不思議な活気があふれ、自然発生的に生徒たちのストライキが起きたりした。しま・ようこのクラスでも、誰言うともなくテストをボイコットしようという意見が持ち上がって、クラス全員が白紙答案を提出したことがある。停電続きの家で、テスト勉強なんかしたら目が悪くなるではないかという理由からだった。
このストライキについて、しま・ようこは「生徒たちの連帯を支えたのは、半分ユーモア、半分本気という了解だった」と書いている。そして、その後で次のように付け加える。「この体験は、その後さまざまな社会運動に参加する折のわたしの原風景になったようだ」
中学時代を彼女はゆとりを持って生きていた。
教師を序列づけたりせず、ダメ教師にはダメ教師の面白味を感じ、教師や生徒の総体をそのまま受け入れていたのだ。これは教師が学習指導要領などに縛られないという制度上の緩やかさによるところが大きかったと彼女は考えている。
あらゆる教科に興味を持って取り組んでいたしま・ようこは、化学分野を担当する教師のところに何度も出入りしているうちに二人の関係が「アヤシイ」と評判を立てられたりした。彼女は、まことに多才だった。そのため、ある教師は、彼女の「サインブック」に「多才、難多し 心して歩め」というはなむけの言葉を贈っている。
卒業が迫り、どの高校に進むか問題になったとき、しま・ようこは前身が女学校だった高校を選んでいる。そのいきさつについて触れている部分を以下に引用する。
一九五〇(昭和二五)年四月、制度改革によって新制高校となった青森県立弘前中央高等学校へ入学した。中央高校は旧制度の弘前女学校で、二・三年生は女子ばかりだった。わたしたちが入学した年度から男女共学となり、八名の男子が入った。四クラス編成で女子は百八十名近かったと思う。この男女の比率のアンバランスの中で、初め男子は居心地がよくなかったかもしれない。しかし、K・Kさんは生徒会長になったし、決して男子が萎縮していたとは思わない。
中央高校を選んだのはこんな経緯からだった。青森県立弘前高等学校(弘高)は旧制度の弘前中学校で父の出身校でもあり、姉は「勉強するには弘高の方がいいんじゃない?」と薦めた。その背景には、「中学校」は「女学校」よりも序列が上という男尊女卑の世間的な見方が新制高校にそのまま引き継がれているように思えて、わたしはその理不尽さに反発していた。いわゆる「上」のランクのところなんかに行かないよという反抗心は、子ども時代に培った軍国主義への違和感の延長線から生まれたようだ。
しま・ようこは高校に入学してからも、選択科目の件でこれと同じような態度を取っている。昔も今も、高校では英・数・国が主要教科になっている。これに反発した彼女は主要教科とされていない「家庭科」を毎年一科目ずつ選択しているのである。
高校で彼女が心惹かれた教師は、抵抗派の国語教師だった。この教師は戦後の「教育漢字」に抵抗して、「どうだ、こんな漢字分かるか」といいながら旧体の漢字を授業で教えていた。彼女はこういう時の相手の楽しげな表情のなかに「余裕たっぷりな抵抗」を感じ取った。
しま・ようこが新憲法精神をたっぷり吸い込んで、周辺の打算的な生き方に反発してその逆のコースを選択したことはよく理解できる。しかし、男女同権の新時代を生きようとしたら、旧女学校を選ばないで、旧中学校を選ぶのが筋ではなかろうか。そして、高校で選択教科を選ぶ場合にも、女子向きの「家庭科」ではなく、より普遍性のある教科にすべきではなかったろうか。
この辺は小さな対抗意識にとらわれて、大局を見誤っているようにも見える。だが、「女の園」の空気を濃厚に残した高校に学び、更にお茶の水女子大に進んだことで、彼女は男女共学の学校にあっては目にとまらないジェンダー問題を視野に取り込むことになるのである。
この頃、国立大学に入学する女子学生はきわめて少なかった。
圧倒的多数の男子学生に囲まれた女子学生は、希少価値によって女王的存在に押し上げられ、心理的に癒されて男尊女卑の現実を直視しなかったが、女子大に学ぶ学生たちはよりシビアに現実を見ていた。彼女らは男子学生のような権力志向を持っていなかった分、より理想に忠実に生きられたのである。
しま・ようこは大学を出てから、山谷地区の長欠児・未就学児を教育する運動に献身し、大学教員になってからは、フェミニズムを日本に根付かせるために努力している。彼女には社会的上昇のハシゴをまっすぐ上ることに対する羞恥があった。だから、しばしば自らの志向にわざと逆らって「自分外し」を試みたのである。こうした一見自虐的にも見える性格を育てたのは、多分、彼女の孤独癖であった。
彼女の著書から関連した部分を引用してみよう。
富田新町(現在の御幸町)の長屋の敷地はかなりの奥行きがあり、そこに作っていた野菜畑の突き当たりは幅半間ほどの小川に面していた。川の向かい側は品川町のMさんの家の裏庭になっていた。日々の食卓を支える野菜畑と小川の間のわずかなスペースに柿とまるめろの木があった。
三中時代からその木蔭にござを敷いて一人で過ごすのが快適になっていた。この一人の時空を、もう一息「わたしの部屋」にしたかったのだろうか。柿とまるめろの間隔に合わせて川端に二本の棒を立て、天井にござを乗せて「自立の家」づくりを思いついた。
それは後で名づけた言葉で、その時「自立」という明瞭な意識を持ち合わせていたわけではなかったと思う。春から秋までの晴れた日しか使えない自分だけの部屋は、心の向くままに自分の宇宙を拡げてくれた。木もれ陽を通してぼんやり空を眺めることが好きだったのは、鎌倉で過ごした幼児期からずっと続いていたようだ。(この挿話は士官学校時代のナポレオンを思い出させる。ナポレオンは校庭の周りにあった立木で囲いを作り、これを「隅」と名付けて放課後その中に立て籠もっていたという)
しま・ようこの家は、何軒かの家が一続きになった旧武家長屋の一つだった
これに続けて、しま・ようこは次のように書いている。
成長期の子どもには、自分の居場所を欲しがる子と、家族と一緒の部屋で過ごしたがる子の二つのタイプがありはしないか。わたしは典型的な前者のタイプだった。弘前へ移る前の鎌倉の借家でも、台所の隣の一畳半のスペースがわたしの「部屋」だったし、富田新町の長屋でもねずみが走りまわる押入れ付きの三畳をわたしが一人占めしていた。姉と妹は自分だけのコーナーを持っていなかったから、母がわたしの性格を見抜いての優遇だったと思う。質素で貧しい暮らしの中に、いつでも逃げ込める小宇宙があることは何よりの支えだった。
彼女にとって家族や仲間から離れて一人になり、独自の「隅」にこもることがどうしても必要だった。多数のなかに埋没している自分を救出するためにも、太宰治などを読んで内部の闇に錘を入れるためにも、ぼんやり物思いにふけって自分の全体像をつかむためにも、一人になる必要があったのである。
「反骨」というものは、一人の時・空のなかで自己と社会の全体像をつかむことからはじまる。全体としての自己と、全体としての社会の間に横たわる齟齬を自覚する、これが抵抗精神の母胎になる。つまり、自分と社会があわないという根源的な自覚が出発点になるのだ。
しま・ようこは細部にとらわれることなく、自己と社会を大掴みにとらえ、それぞれを基本的な構造において把握する。詩人の直感で対象を捉えると言ってもいい。彼女は少女期には新憲法の「光」の面を吸収し、善美なものに向かう人間性を信頼していた。だが、思春期に入るにつれて、自分についても社会についても、「闇」の面に突き当たることになる。彼女は考える、日本人は原爆を落とされるという点では被害者だったが、アジア諸国を侵略する政府を支持し続けたという点では加害者だったのではないか。
戦後の日本人が信奉するようになった人間解放の哲学は美しい。だが、哲学と歴史は異なる。日本人は責任を全部政府に押しつけてはならない。国民の一人一人が、歴史に徴して自分は被害者であると同時に加害者だったことを学ばねばならない。
彼女の「反骨」は、つまるところ戦後日本人の「罪」に向けられている。この罪はむろん彼女自身も深く身に負っているものである。彼女の「影を裁く」という長詩は、次のような厳しい言葉で結ばれている。
・・・・・・・・・・
見えないものを見ない罪
忘れやすいものを忘れる罪
語り継がない物語を反古にする罪
古い海図のまま人を引導する罪
死者を過去形で悼み進行形で暴いても
徽章の裏は裁けない記憶の庭が
わたしを生え抜きのフェミニストに仕立てたとしても
〈罪〉の大文字の残る手で
海図は描くまい
何千の他者から疎まれても
寒々と栄える街を拒み
加害と被害の影の終わりが見えるまでしま・ようこ詩集「北の方位」
しま・ようこの罪責感は、空言ではなかった。
彼女が簡素を旨とした、つつましい日常を送っていること、献体登録をして死後の自分を医学の研究に役立てようとしていることには、贖罪の意味がこめられている(先年亡くなった彼女の夫・谷敬も詩人で、生前に献体登録をしていた。その遺骨はいま献体者の共同墓所に納められている)。