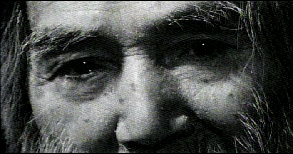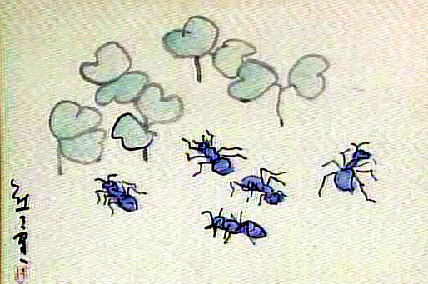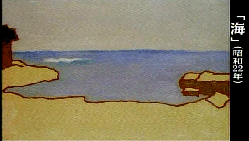人間には、どうすることもできない性格の違いというものがある。
昔、都会のマンション住民を対象にして行われた世論調査に、「どのような生活を望むか」というのがあった。注意を引かれたのは、回答者の24パーセントが「来客のない静かな生活」をあげていることだった。アパートやマンション暮らしの問題点として、よく住民同士の交流が少なく、めいめいが孤立している点が指摘されている。ところが、そうした「問題状況」をこそ望むものが、全体の四分の一もいるのである。気のあったものが集まってワイワイ騒ぐことを喜びとするものがいる一方で、他人が介入してこない静かな生活を求めるものも一定数存在するのだ。
画家の熊谷守一は、文化勲章を受けることを辞退している。その理由というのは、そんなものをもらったら、来客が増えて困るではないかというものだった。仲間と行動をともにすることを求めるタイプを「社会参加型」、来客を好まず自宅にこもるタイプを「隠者型」とするなら、世間的評価の低いのはもちろん後者である。
静かな生活を求めて引きこもるグループは、少数派だからどうしても分が悪くなる。
だが、彼らは他者とのネットワークを作ることを拒んで、完全に孤立しているかと言えばそうでもない。いかに人嫌いな拗ね者であっても、人間であるからには他者とのネットワークを作ることなしには生きて行けない。そこでネットワーク構造を間接化して非接触型の交流を図ることになる。孤独な若者が、テレビで知ったタレントにあこがれ、せっせとファンレターを書き続けるのも非接触型の交流だし、退職したサラリーマンが漢詩を読んで李白や杜甫を愛するようになるのも非接触型の交流である。隠者型の人間は、静かに生きた古今東西の先人たちに注意を引かれ、その暮らしぶりや業績を具体的に調べたくなるものなのだ。以下に述べるのは、私が非接触型の交流を続けている先輩たちのプロフィールである。
1 最初の接触
 熊谷守一:その風貌と生活ぶりから「現代の仙人」と呼ばれていた
熊谷守一:その風貌と生活ぶりから「現代の仙人」と呼ばれていた
40代のある日、図書館でアサヒグラフ別冊の美術特集シリーズを眺めていたら、そのなかに熊谷守一の画集があった。彼が文化勲章を辞退したことを聞き知っていたので、抜き出してページを開いてみた。それまでに、彼の作品を見たことがなかったからだ。そもそも「非接触型の交流」というのは、大体、このようにして始まるのである。
画集を開いたら、抽象画なのか具象画なのか、あるいは日本画なのか洋画なのか、真面目なのか不真面目なのか、見当がつきかねる奇妙な絵がならんでいた。それらの絵には、訳が分からぬなりに、不思議な魅力があって印象に残ったが、見終わってから、所詮これらは「格外」の作品で、現代絵画の主流にはなり得ないという気もした。
画集の終わりに、熊谷守一の略伝やプロフィールが載っていた。
それによると、彼の生き方も作品と同様に破格だった。彼は東京美術学校に学んで、青木繁と同窓だったという。才能の点では青木にまさるといわれ、美術学校を首席で卒業し、文展にも入賞している。その彼が、画家としての華やかな未来をなげうって、いきなり故郷の岐阜県付知町に引っ込んでしまうのである。そして、筏流しの労働を6年間続けている。
36歳、彼は友人に促されて上京し、東京で画家としての生活を再開する。画家として名声を得てからも、熊谷守一の「画学生」風の飾らない生き方は変わらなかった。彼は30年間、庭の草木や昆虫を友として、ほとんど家から出たことがなかった。彼の生活は、庭のいきものを観察することと、画業を深めることだけで成り立っていたのだった。
私は、その本に紹介されているいくつものエピソードに引きつけられた。「学校に行く」と言って彼が画室に向かう話や、「五風十雨」を座右銘にしているというエピソードなどである。「五風十雨」というのは、五日に一度風が吹き、十日に一度雨が降るという中国の諺なのだ。熊谷守一は、こうした自然現象に仮託して、定期的に訪れてくる人生的な苦難を逆らわずに受け入れていたのである。
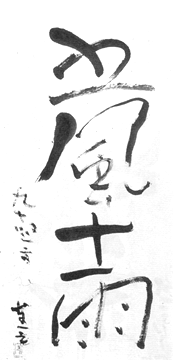 熊谷守一の書
熊谷守一の書
このとき、私は錯覚にとらわれていたのだった。熊谷守一は文化勲章の対象になるほどの大家だから、庭も広く、画室は別棟になっているにちがいないと思いこんだのである。「学校に行く」という言葉には、庭園のはずれにある画室に弁当持参で出かけるというような感じがある。また、30年間戸外にでないで庭だけを眺めていたとすれば、その庭は相当広いに違いない・・・・。
2 再会
絵は嫌いな方ではなかったから、機会があればいろいろな画家の画集を眺めていた。しかし、画集で目にした作品をいちいち記憶しているわけではない。たいていの作品は、その場限りで忘れてしまうのだが、熊谷守一の作品に限って画集で眺めた絵の多くが頭に残っているのである。一度目にしたら忘れられないような作品ばかりなのだ。でも、彼との「関係」は、そのままになっていた。アサヒグラフの特集号を手に入れようと思いながら、買いはぐれていたからだ。
30年近くたって、再び熊谷守一に巡り会う機会があった。平成10年、NHKの「新日曜美術館」という番組で、久しぶりに熊谷守一に再会したのである。私は、番組予告で彼が取り上げられると知って、ビデオをセットして放映される時間を待った。その番組を視聴して教えられることが多かったけれど、熊谷守一に関する自分の知識が、思いこみによって大きく歪んでいることを知ったことが、一意番大きな収穫だったかもしれない。彼は画室に弁当持ちで通うような大邸宅に住んでいたのではなかった。敷地50坪の家に住み、その庭は僅か15坪の広さしかなかったのである。

テレビには熊谷守一宅の白黒写真が映し出されていた。家は平屋で、庭は生い茂った植え込みですっかり覆われている。とても一流画家の邸宅とは思えない簡素なたたずまいである。
番組では熊谷守一の作品紹介にあわせて、彼の日常にも触れていた。とにかく、彼は寡作なのだった。画家として油がのりきっているはずの壮年期の十数年間に、熊谷守一は年に小品を数点しか描いていない。作品を全く発表していない年もあった。
こんな風だったから、彼の家族は経済的に絶えず窮地に立たされていた。熊谷守一の結婚は遅く、42歳で24歳の若い妻をめとっている。この妻との間に5人の子供が生まれているが、そのうちの3人が病死しているのも貧しさからだったに違いない。生き残った次女は、次々に子供らが病気にかかったときの父親の振る舞いについて語っている。
父親は「子供のことが心配で、絵なんか描いていられない」といい、母親は「こういうときだからこそ、病院の費用を捻出するために絵を描いてくれなくては」と言っていたというのである。
彼は家計がどんなにピンチになっても、気が向かなければ絵筆をとらなかった。火の車の家計をよそに、彼は「雑草園」のように草の茂った庭にでて蟻やカマキリを観察し、草や花に見入っていた。そのために彼は手製の腰掛けを20個作って踏み石のように庭に配置し、それに順番に腰を下ろしながらあくことなく虫けらどもを眺め続けた。有名なエピソードがある。彼は蟻を観察しているうちに、蟻が左側の二番目の足から歩き始め、どうのような順序で足を動かして歩行するか「発見」したというのだ・・・・。
昆虫や小鳥、あるいは草花や猫を描いた彼の作品は、その姿態が金釘流と言ってもいいような稚拙な輪郭線で縁取られている。だが、それら生き物たちは、長年の観察に裏付けられ、固有の相を正確に描き取られている。初めて、熊谷守一の絵を見たときに感じたのも、生き物たちの生態的な動きが、一種の瞬間像として実に正確に捉えられていることへの驚きだった。
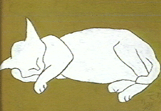 白猫
白猫 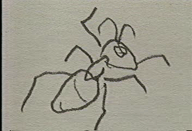
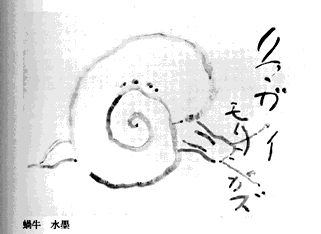 蟻と蝸牛
蟻と蝸牛
私はテレビのモニター上に現れる彼の作品を眺めながら、その多くを自分が今も記憶していることを不思議に思った。30年前にアサヒグラフ特集号で見た絵が、ほとんどそのままで心に残っているのだ。画集に載せられている作品の一つ一つが、心の未知の部分を切り開き、そして当時切り開かれた未知の部分が古びることなく私の心に残っていたのである。
番組の終わりに、熊谷守一展が平成10年2月8日まで飯田市美術博物館に開かれているというテロップがながれた。残念だった。飯田市はJRを使えば、1時間あまりで行ける近くにあるが、折悪しく私は筋肉痛になって家の中でも杖をついて歩く状態にあったのである。
しかし、明日で展覧会が終わりという2月7日になると、我慢できなくなって痛む足を引きずりながら、飯田市に出かけたのだった。
3 展覧会
熊谷守一の展覧会は楽しかった。美術館に入場して最初の作品の前に立った瞬間から、自然に内側から微笑が立ち上ってきた。内なる微笑は、会場を去るときまで途切れることはなかった。
館内はひっそりしていて、入館者が数えるほどしかいなかった。私は、一つ一つの絵を直ぐそばまで寄ってゆっくり眺め、それから椅子に座って離れたところから眺めた。足が痛むので、椅子があれば必ず腰を下ろして休んだのだ。つまり、私は守一の作品を間近から見たり、遠くから眺めたり、遠近二つの視点から眺めたのである。
展示されている作品は、ほとんど全てハガキ4枚の大きさの小さな板きれに描かれている。熊谷守一は、昔からこうした小品しか制作してこなかった。だから、彼は反大作主義者といわれたり、その作品は「天狗の落とし文」と揶揄されて来たりした。世の中には、絵柄は小さくても、その中に画家の全身全霊が注ぎ込まれているような作品もある。だが、熊谷守一の絵には、そうした感じが全くない。彼はものを観察することが好きで、絵は観察の延長上に生まれたものだから、刻苦精励といった印象がないのだ。
刻苦精励の感じがないばかりではない。どこまで真面目だったか疑わせるような作品も散見されるのである。次に示すのは「朝のはじまり」と題する作品で、これを見たら誰でも、これがどうして朝のはじまりなのか首をひねるに違いない。
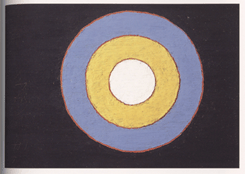
作者本人に言わせると、これは釘穴から朝日が射し込むところを描いたのだそうである。そう説明されると、判じ絵の謎解きをされたようで、成る程と思う。黒地に同心円を描いた絵はほかにもあって、こっちの方は「夕暮れの太陽」と名付けられていたらしい。展覧会に出品されたこの絵を見た武者小路実篤が、「こんなアホらしい絵をよく出したものだ」と嘆じたことを伝え聞いて、熊谷守一はキッパリと「自分は決しておかしいとは思わない」と書いている。
彼は「絵には遊びがあってもいい」と語っているから、これら判じ絵のような作品も遊び心から出たものと取る向きもあるかもしれない。だが、彼は武者小路にけなされた絵を大真面目な顔で「あれは自画像だ」と言っているし、泥のかたまりを描いた「土塊(つちくれ)」という作品についても、あれも自画像だと言っている。
彼の作品には、真面目に描いたのか、遊び心で描いたのか判じかねるものが多い。しかし、彼は仕事と遊びを区別しなかった人間で、遊びのきわまるところに仕事があったのだから、これは真面目、あれは不真面目と区別することができない。同心円型の絵が不真面目だとしたら、彼の作品の全てが不真面目なのである。
展覧会で「生の」絵を見なければ分からなかったのが、輪郭線を描く手法だった。有名な「ヤキバノカエリ」と裸婦像について、それを見てみよう。
 ヤキバノカエリ
ヤキバノカエリ 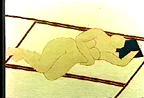
両方の作品は、いずれも輪郭線がくっきり描かれ、背景は平塗りになっている。特徴的なことは、人物の顔が描かれていないこと、そして影が描かれていないことである。これらを見れば、彼の作品が、光と影の対照を重視し輪郭線を省略する印象派のそれと全く異なることが分かるだろう。
輪郭は、後から書き加えるものだから、油絵の具がその部分高く盛り上がっているはずなのだ。ところが、熊谷守一の場合、輪郭線が溝のように窪んでいる。これはどういうことかと言えば、一番最初に輪郭を描き、その他の部分を後から絵の具で塗り上げていったことを意味する。
彼は「物はひとつしかない」といっている。全ての物は固有の形を持っているから、彼はこの形をとらえることに全力を挙げるのである。まず画面に対象の輪郭を太々と書き込んで、これを作品の骨格にする。骨格ができあがると、彼はこの輪郭を傷つけないように、細心の注意を払ってその他の部分を塗っていく。彼が顔の造作やら影やらを省略し、背景を平べったく塗りつぶしてしまうのは、形を大事にするからだ。見るものが細部にとらわれて、全体を見失ってしまうことを恐れるからである。
「ヤキバノカエリ」は、結核で亡くなった長女の遺骨を火葬場から持ち帰る父子三人を描いたものだが、三人の顔はのっぺらぼうで、背景の木立も極端に省略されて棒杭みたいになっている。そのため、横一列に並んだ父子三人の形がクローズアップされ、浮き出して見える。これを見ると、三人があの世の世界を歩いているかのような印象を与える。誰もいない無風沈黙の冥府を行く三人の父子。
裸婦像ものぺらぼうの顔をして、畳に拡がった髪が三角形に描かれている。そのため、矩形の畳と相まって女体の柔らかな形が印象的に目に映じている。
同じ単純化された絵柄でも、そのやさしさと静けさで清水のように心に深くしみこんでくる作品がある。次に示す作品などは、いつまで見ていても飽きない可憐な絵だ。
 「朝露」と題がつけられている
「朝露」と題がつけられている
足が痛かったことや入館者が少なかったということもあるけれど、一つの展覧会にこんなに長くいたことはない。会場にいると、久しぶりに故郷の自分の家に帰ったような安らぎとくつろぎを感じて、去りがたい思いをしたのだ。全部を見終わってからも椅子に腰を下ろし、足の痛みが去ってから気に入った絵の前にもう一度出かけるというようなことを何度も繰り返したのだった。
4「へたも絵のうち」
熊谷守一に強く惹かれながら、私の手元には彼の画集もないし、彼の自伝「へたも絵のうち」も持っていない。だから、彼のことが懐かしくなると、「新日曜美術館」のビデオを巻き戻して眺めているしかなかった。しかし、先日ふと思い立ってヤフーの検索にかけてみたら、熊谷守一記念館(岐阜県付知町)で彼に関連した本を販売していることが分かった。早速、「へたも絵のうち」 と 「赤い線 それは空間 思い出の熊谷守一」(向井加寿枝)を注文した。
本が届いたので、まず「思い出の熊谷守一」の方から読み始める。この本を書いた向井加寿枝さんは、熊谷守一に傾倒していた画商で、足繁く熊谷守一宅を訪れて家族同様になっていた人である。「新日曜美術館」では守一の家は敷地50坪、庭の面積15坪となっていたが、彼女によると敷地は80坪で、その南半分が庭になっていたという。そして彼女は家全体の精細な見取り図を本に載せている。次に示すのは、その見取り図を簡略にしたものである。
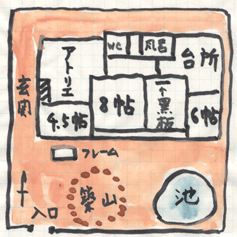 池は都市化の進行で水源が涸れたため埋め戻された
池は都市化の進行で水源が涸れたため埋め戻された
南東にある池は、はじめ穴を掘ったら水がしみ出てきたので、暇にまかせて大人の背丈ほどの深さまで掘り進んでいったら、水源にぶつかって湧水池になったものだ。この時、掘り出した土で出来たのが隣の築山で、池の周りと築山の周辺には雑木がぎっしり植えられている。
家の間取りを見て不思議に思うのは、アトリエが北西隅にあることだ。画家のアトリエといえば、外光を存分に取り込んだ南向きの部屋になるのが普通だが、守一の画室は家の中で一番日当たりの悪い北西の隅にあるのだ。昼なお暗い部屋でよくもまあ、絵が描けたものだと思う。
だが、彼が昼間は奥さんと碁を打ったり、庭に出て虫や草を眺めて過ごし、絵を描くのは夜に入ってからだと知れば疑問も解ける。画室の天井には針金が渡してあり、そこに引っかけた電灯(裸電球の上に唐傘状の笠をつけたもの)をひもで滑らせて移動し、10坪ほどの室内を照らすのに使っていた。壁には昔筏流しをしていたときに使った道具などが保存されていて、まるで物置のようになっていた。室内にはすきま風が吹き込んだが、実害はなかった。彼は冬に絵筆を取らなかったからだ。
 雑然とした画室。リンゴ箱を積み重ねて棚にしている。
雑然とした画室。リンゴ箱を積み重ねて棚にしている。
上掲の間取り図に「黒板」とあるのは、長女が死ぬ間際にチョークで「南無阿弥陀仏」と書き付けた黒板で、守一はこの文字を30年間消さずにおいた。チョークの文字が薄れるまで消さないでいたところに熊谷守一の性格が現れている。
家の入り口も、いかにも熊谷守一らしかった。丸太を二本立てて門柱にして、扉は板を並べて打ち付けたものだった。郵便受けは彼の手製、門札も蒲鉾の板などに墨で名前を書いて柱に架けただけのものだった。門札は、熊谷守一が有名になると、たびたび盗まれたので、そのたびに作り直さなければならなかった。

夫妻は向かい合って碁を打つのを日課にしていたが、定石も何も無視した無茶苦茶な碁だった。この写真を見ると、自陣の前に石を一列に並べている。こんな碁を打つ大人は滅多にいないだろう。
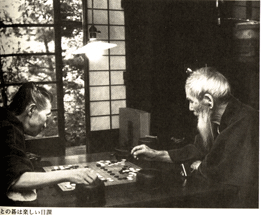
著者の向井加寿枝は、熊谷守一の無欲な日常を記した後で、彼を「神様にもっとも近い人」と呼んで、次のように書いている。
長年接した私には先生は余りにも人間的で、しかも人間の世界の中でまるで
汚れの取り付かない原点、つまり神様にもっとも近い「正に人」というしかな
く、仙人はもとより比べられる人などいない。
次のような写真を見れば、神様に近いという気もしないではない。左手を腰につるした袋に入れているが、この中にはスケッチブックが入っていて、虫などを観察していてポイントをつかむと、これにさっとスケッチしたそうである。そして、そのスケッチをほとんど修正を加えないでそのまま油絵にしていた。
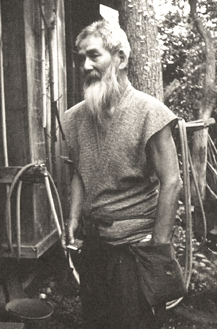
これまでに述べてきたような熊谷守一の生き方は、さまざまな神話や伝説を生み出すことになった。画壇のみならず、マスコミの間にも「現代の仙人・熊谷守一」という評価が定着し、この評判の故に彼に惹かれるファンの群を生み出したりした。
しかし熊谷守一は、こうした世評が気に入らなかったらしく、日本経済新聞に載せた「へたも絵のうち」という自伝で、自ら守一神話を否定している。彼は、異常な家庭で育ったからこういう性格になったので、「普通の家に育っていたらもっとまともになっていたろう」と語っている。
彼は岐阜県恵那郡付知村に生まれた。男女併せて7人兄姉の末子で、父は事業家として成功し、岐阜市の市長になっている。後には衆議院議員になっているから、村で一番の出世頭だった。父は妻子を村に残して、岐阜市内に一戸を構えていたが、守一が3歳になると、子供たちのうちで彼だけを岐阜に呼び寄せた。
この岐阜の家が、何ともかんともないデタラメな家だった。旅館を買い取って自宅にした馬鹿でかい家に二人の妾とそのみよりの者が寄り集まって暮らしており、妾のうちの威勢のいい方が自分を「おかあさん」と呼ばせて家を取り仕切っていた。父は事業やら政治やらで忙しく、ほとんど家に居着かず、家事の一切をこの「おかあさん」に任せきりにしていた。熊谷守一もこの女を「おかあさん」と呼ばなければならなかった。
金はいくらでもあったから、守一とたくさんの異母兄弟には、それぞれに乳母がつき、学齢に達すると家庭教師がついた。子供たちのなかでは、正妻の子である守一は、一応別格に扱われていた。彼は90畳もある二階の大広間を一人で占領し、食事時になると女中が運んで来る膳に向かって一人で食事をしていた。
岐阜の家で贅を尽くした暮らしをしていて時々村の生家に戻ると、母たちは水漏れのするような風呂に入っている。子供心に彼は「何たることだ」と思った。幼少期を一つの家だけで暮らしていれば、子供は家とはこういうものだと素直に受け入れて、どんな家にも疑問を持たない。だが、二つの家を行ったり来たりしていれば、双方の家をそのいずれにも属さないニュートラルな立場から眺めるようになる。彼は醒めた目で、身の回りを観察するようになった。
大きな家の中に、氏も素性も異なる人間がごちゃごちゃ暮らしているから、もめ事が絶えない。子供たち一人一人についている乳母や家庭教師も、自分の担当の子供を極端にかわいがるかと思うと、担当の子供を嫌ってほかの子供をひいきにする者もある。こういう修羅場で、彼に指針を与えてくれる肉親がいたら彼も救われたかもしれない。だが、父は息子を妾に預けっぱなしにして、ろくに言葉をかけもしない。こうなれば、子供は自らの頭で判断し、それに従って動くしかない。彼は書いている、
そんなことで、私はもう小さいときから、おとなのすることはいっさい信用できないと、子供心にきめてしまったフシがあります。子供といっても、何でも理解して確信をもって判断してしまうものです。
こんな具合に、身の回りの世界を距離を置いて冷たく見ている子供は、大人の目には不気味に映る。「守一さんは、いい子だけれど、ちょっとわからんとこがある」という家の中の評判は彼の耳にも入ってきた。「わけのわからんとこがある」子供が、学齢に達したらどうなるだろうか。少し長くなるけれど、「へたも絵のうち」から入学後のようすを記した部分を引用してみよう。
数えで八つのときに、岐阜市内の師範付属小学校にはいりました。先にもふれた
ように大所帯でおとなのいろいろなことを見聞きして、私はもう何もかもわかって
しまった気持ちになっていました。ばあや以外は、おとなはみんなウソのかたまり
だと、心に決めていたフシがあります。
だから、小学校に上がっても、先生の言うことなど、ほかの子供のようによく聞
く気になれないのです。とくに、師範の付属だから先生は若い人が多く、まともに
相手にはできない気持ちでした。
先生が一生懸命しゃべっていても、私は窓の外ばかりながめている。雲が流れて
微妙に変化する様子だとか、木の葉がヒラヒラ落ちるのだとかを、あきもせずにじ
っとながめているのです。じっさい、先生の話よりも、そちらの方がよほど.面白かった。
先生は、しょっちゅう偉くなれ、偉くなれといっていました。しかし私はそのこ
ろから、人を押しのけて前に出るのが大きらいでした。人と比べて、それよりも前
の方に出ようというのがイヤなのです。偉くなれ、偉くなれといっても、みんなが
偉くなってしまったちどうするんだ、と子供心に思ったものです。
そんなわけで、私はよく先生、にしかられました。わけもわからず全員の前に引っ
張り出されたり、立たされたりしました。ところがそれが、なぜそうされるのか、
よくわからない。
あるときは、私があんまりきかないというので校長室まで連れてれて行かれたこと
もあります。連れて行った若い先生が、校長の前に出るとなおのこと興奮してい
ろいろとまくしたてる。結論は、私が授業中に窓の外ばかり見ているからという
ことでした。
特に習字の時間には、ひどい目にあいました。同じ立たされるのでも竹筒の水
入れを、捧げ銃のかっこうで持たされるのです。
まだ力は弱い子子供だから、水のいっぱいはいった竹筒はなかなか重い。しぜんに
脇が下がってくるとまた姿勢が悪いといっておこられるのです。しまいにはこち
らも要領をおぼえて、先生が横を向くと、パッと下におろして腕を休めたりしまし
た。
私はまた、シャツとか下着とかがきらいでした。今でもはだにぴったリつくもの
はいっさいダメですが、小さいときから、きゅうくつな;ことは逃げ回るだけでした。
床屋もきらいで、これもいまだに変わりません。若いころは・髪がのびてわずら
わしくなると自分で適当に切り落としていましたが、今はばあさんから切ってもら
っています。
上着も、きれいなものは困りものでした。祭りのとき、新調の着物をむりやり着
せられて外に連れて行かれたことがあって、ほとほと困ったことがあります。「お
かあさん」と呼ばされていた、父の妾の威張っている方の人に手をひかれて行った
のですが、私は途中でがまんできなくなりわざところんで着物をよごしました。よ
ごれがつけば、多少でもがまんはできる。故意にころぶという変な知恵が、幼い
、子供にもあるものなのです。
しかし、こんなことをしても、「おかあさん」は少しもおこらない。この時だけ
でなく、いつの場合もおこらない。5 隠者の誕生
一家の権力者「おかあさん」ですら、守一のすることに口を出すことはなかった。彼が何をしても怒らなかったのである。こういう環境で育った金持ちの子供は、末は道楽息子になると決まっていたが、熊谷守一はそうはならなかった。道楽息子とは反対の隠者になったのである。
金に不自由しない息子は、成人すると現世の提供する感覚的な愉楽を求めるようになる。毎日遊び暮らしながら、うまいものを食べ、女色をあさるのだ。だが、幼いときから世の中の裏を見て、現世に距離を感じていた守一は、世俗の提供する愉楽というものにいっさい関心を持たなかった。
守一が道楽息子と共通しているのは、働かないで好きなことをして日を送ることだった。無拘束状態で育った彼は、共同体から離脱すること、そして気ままに生きることを求めた。彼は子供の頃から絵を描くのが好きだったから、絵描きになって自由に生きたいと思うようになったのである。
絵を描くことは好きだったが、一生懸命やるというようにはならなかった。彼は「好きは好きだが、ただ好きだというだけで、だからどうだというその先はなかった」と言っている。彼が美術学校を首席で卒業し将来を嘱望されながら、農商務省の調査団に加わって樺太に渡るというようなことをするのもこのためだった。そして、現地に渡って無欲なアイヌ人を見ると、すっかり好きになってしまうのである。彼はアイヌ人について書いている。
彼らは漁師といっても、その日一日分の自分たちと犬の食べる量がとれると、それでやめてしまいます。とった魚は砂浜に投げ出しておいて、あとはひざ小僧をかかえて一列に並んで海の方をぼんやりながめています。なにをするでもなく、みんながみんな、ただぼんやりして海の方をながめている。魚は波打ちぎわに無造作に置いたままで波にさらわれはしないかと、こちらが心配になるくらいです。
ずいぶん年をとったアイヌが二人、小舟をこいでいる情景を見たときは、ああいい風景だなとつくづく感心しました。背中をかがめて、ゆっくりゆっくり舟をこいでいる。世の中に神様というものがいるとすれば、あんな姿をしているのだな、と思って見とれたことでした。私は、そのころも今も、あごをつき出してそっくり返る姿勢はどうも好きになれない。反対に、老アイヌのああいう姿は、いくら見てもあきません。無欲なアイヌ人に共感した守一自身、次のような人間だった。
結局、私みたいなものは、食べ物さえあれば、何もしないでしょう。犬もそうだ。食べ物さえあれば、寝そべっているだけで何もしない。あれは、じつにいい。
こうした守一だから、母が亡くなって故郷の付知村に帰ると、製材業をやっている兄の家に転がり込んで居候になるのだ。彼は郷里で過ごした6年間、ずっと筏流しの人夫をしていたと思いこんでいたが、人夫をしていたのは2年間に過ぎず、それも冬の間だけのことだった。ほかの時には、彼は兄が飼っていた馬を乗り回したり、近所の鍛冶屋の作業場に入り込んで仕事を覚えたりしていた。自ら語るように彼は郷里での6年間を「ぶらぶらして」過ごしたのだった。
一向に仕事をしようとしない弟に腹を立てた兄は、守一がかわいがっていた馬を売り払ってしまった。彼は、子供のように泣きだし、母が死んだときよりも悲しかったと書いているが、この時彼は30代の壮年になっていたのである。
やがて、美校時代の友人に勧められて上京してからも、彼は斉藤豊作という資産家の友人から金を貰って生活していた。その期間が5,6年に及んだというから、彼は42歳で結婚するまで約12年間、仕事らしい仕事を何もしないで、他人に養われて生きていたのである。
結婚してからは、心がけを改めてちゃんと仕事をしていたかと言えば、相変わらずだった。彼は述懐している。
私は若いころ(筆者注:「若いころ」といっても、彼はすでに40代になっている)、子供が次々とできて何かと金が入用の時期に、仕事が全く手につかなかったことがあります。一年間、一度も絵筆を握らなかったこともある。まわりからやいのやいのといわれ、なぜ仕事をしないんだ、わからないヤツだ、などと盛んにせめたてられましたが、できなかったのです。
彼の一家が、からくも生きのびたのは夫人の実家が豊かだったからだった。夫人の実家は昭和4年に家の建築費として3000円を守一に贈与したり、夫人と子供たちを家に引き取って預かってやったりしている。
紀州和歌山の資産家が、どうして生活能力のない貧乏絵描きに娘を嫁がせる気になったか明らかでない。夫人は守一の描く絵のモデルになったことがあるというから、この時、20歳近い年長の守一に愛情を寄せるようになったのかもしれない。
では、ろくに絵も描かず、妻の実家に援助されながら過ごした無名時代に、彼は何をしていたろうか。持ち込まれる懐中時計の修理や、音の振動数の計算に夢中になって昼夜転倒した生活を送っていたのである。絵を描くことには乗り気になれなかったが、こうした一文の金にもならない手仕事には寝食を忘れて熱中していたのだった。
彼の絵が売れ出して、画家として生計が成り立つようになったのは昭和12,3年頃、彼が日本画を描くようになってからで、そのとき、彼はもう57歳になっていた。彼が画家としてまともに働き出したのは、何と57歳から97歳までの40年間なのである。それ以前の彼は、かっては将来を嘱望されていたが、今や才能が枯渇してろくに絵も描けなくなった落伍者だと見られていた。
「ちいさいころから、だれにも気がねせずに、したいことをしてきた」と自ら語る熊谷守一だから、名声を得てからも、従来のペースを変えることはなかった。彼は無為の状態でいることをもっとも好み、何かするとしたら、それは興味のあること、楽しいことだけだった。
若き日の彼は、西洋美術の伝統を忠実に受け継ぎ、その延長線上で作品を描いていた。美校の卒業作品も文展で褒賞を受けた作品も、いかにも油絵らしい油絵である。その彼の作品が、年を追って分かりにくくなり、下手くそになっていくのだ。彼の描いた上手な絵と下手な絵を並べてみよう。
ローソク
宵月
上手な絵を嫌う理由を、彼は行き着く先が見えているからだと説明する。文展で褒賞を受けた「ローソク」はレンブラントの手法を受け継いだすぐれた作品だが、この世界を押し進めて行っても、深くはあるけれど狭い世界に辿りつくだけなのだ。「宵月」は、既存の枠を取り外して、見る者をこれまで知らなかった広い世界に誘い込んでくれる。いつまで見ていても飽きないのは「宵月」の方なのである。ここには絵だけが表現できる現実を超えた世界がある。自由で広くて新しくて・・・・異次元といいたいような世界があるのだ。
距離を置いて現世を見ていた熊谷守一は、美しい景色や名勝絶景のたぐいに関心を向けなかった。厳島を描いてほしいと案内された彼は、どうしても現地の絵葉書的風景を描く気になれず、そこで見かけた茄子を描いて戻ってきたという実話がある。彼が好んで描くのは、画学生たちが「これではとても絵にならない」と見放してしまうような平凡な風景だった。彼はそこに大地に固有な姿を見ていたのだ。サルトルも絶景なるものを、自然の「畸形」と呼んで好まなかった。
上手な絵や美しい景色に冷淡だった彼は、良寛の書にも失望していた。彼はまさか良寛が世俗の好尚に合わせた、こんなに上手な字を書くとは思ってもいなかったのだ。
時代は大作主義に向かい、展覧会には畳何枚分もの画布に描かれた絵が並ぶようになっていたが、彼は名をなしてからも小さな板に平塗りの絵を描き続けている。
こうした一連の常識破りの行動を見て行くと、熊谷守一は抵抗精神に富んだ反俗的な人間だったように見える。しかし、彼は「へたも絵のうち」の最後に自身の生涯を総括して次のように記している。
私はほんとうに不心得者です。気に入らぬことがいっぱいあっても、それにさからったり戦ったりはせずに、退き退きして生.きてきたのです。ほんとうに消極的で、亡国民だと思ってもらえればまず間違いありません。
気に入らないことがたくさんあったのに、彼が抵抗したり戦ったりしなかったのは、子供の頃の原体験からきている。守一は、家や学校で不合理なことや罪深いことをたくさん見てきた。大人のように成熟した目で見てきたのである。しかし孤立無援の彼は、それらを不快感を抱きながらただ見ているしかなかった。
彼は気に入らぬことにぶつかるたびに、一歩退いて現実と関わるまいとしたのである。成人してからも、彼は戦う前に退くことを考え、一歩下がってアウトサイダーの視座に戻った。子供の頃の彼が、周囲の大人たちの目に「分からない子供」と映ったのは、彼が幼児にはあるまじき冷徹なアウトサイダーの目で身辺を眺め、早くも隠者の顔をほの見せたからだ。
彼は後退を続けた。そして前人未踏の画境に辿りついた。熊谷守一の絵に現世から遠く離れた異界からの視線が感じられるのはこのためである。
この大変に面白い自伝は、次の言葉で結ばれている。
私はだから、誰が相手にしてくれなくとも、石ころ一つとでも十分暮らせます。石ころをじっとながめているだけで、何日も何月も暮らせます。監獄にはいって、いちばん楽々と生きていける人間は、広い世の中で、この私かもしれません。
追記 先日、NHKの美術番組「新日曜美術館」で、再び熊谷守一が取り上げられた。熊谷守一が残した日記その他数千点の遺品が、彼の遺族によって岐阜県に寄贈されたののを機に、改めてその業績を回顧しようとの企画に基づく番組だった。
まず、この番組で熊谷守一の写真をたくさん見ることのできたのが有り難かった。高齢に達した日本人の顔で、彼の顔ほど美しいものを見たことがない。若い頃の熊谷守一の顔はどうということもないが、80,90になってからの彼の顔は、絶品といっていいほど高雅で立派なのだ。
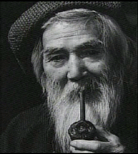
日記の内容も、いかにも熊谷守一らしく面白かった。
大正12年9月1日は、関東大震災の日である。この日、熊谷守一は、自宅を焼け出されて野宿しなければならなかった。見渡す限り廃墟と化した震災地に立って、熊谷守一はその日の日記にこう書くのだ。
九月一日
大地震
トンボガ ユーックリ 飛ンデイル
周りでは近所の住人たちが目を血走らせて立ち働いている。その修羅場の中で熊谷守一も不安でいっぱいになっているのである。その点では、彼は、ほかの人間と何ら変わるところがない。(今回の番組でも、二女の榧が、「父は仙人だといわれているけれど、普通の人間と変わりはなかった」と語っていた)
熊谷守一は世間並みの罹災者としてオロオロしながら、その一方で満目蕭条たる震災地に飛ぶトンボに目をとめる。日記の中にオロオロする熊谷守一と、虚心になってトンボに目をとめる熊谷守一が同時に存在しているのである。
最愛の母の臨終に立ち会った時にも、彼は日記に、「マサニ、生物のオワリダ」と書いている。出産に立ち会った愛妻家の夫が、出産過程の妻をハラハラして眺めながら、ふと、(人間の出産も、犬のそれと変わりがないな)と感じる。だが、そう感じることを人間に対する冒涜のように感じて意識の外に押し出してしまう。だが、熊谷守一はひどく醒めた目で死に行く母を「生物ノオワリ」として眺め、それを手帳にはっきりと書き留めるのである。
彼は、世間並みの人間だった。しかし、そういう自分を他人事のように見るもう一つの自分を持っていて、そのどちらを押さえることもなく両者を共存させていたのだった。
熊谷守一は、絵についても同じような二重基準を持っていた。
何しろ美校をトップで卒業し、文展に出品すれば簡単に入賞するような技量の持ち主である。彼は絵については、すべてを知り尽くしていた。何をどうすれば、どんな作品ができあがり、そしてそれがいかなる世間的評価を受けるか、ちゃんと知っていた。彼は絵の世界に足を置きながら、そこを突き抜けた別次元に立って美術界を即物的に眺めていたのだ。熊谷守一の内部には、仲間の画家たちが、ヨーロッパの美術理論を振りかざして、まるで人生の一大事であるかのように絵画論をたたかわすのを、他人事のように眺める醒めた人間がいたのである。
彼の作品は、震災の修羅場をゆっくり飛ぶトンボに対比できる。
廃墟のなかでせわしく立ち働く罹災者たちと悠然と飛ぶトンボには、取り合わせの妙がある。この両者は「逆対応」という点で、絶妙の関係にある。熊谷守一は画壇の潮流にマッチするような作品を描いて、貧乏暮らしから脱出したかった。だが、それに逆らうもう一つの醒めた自分が邪魔して、どうしても絵が描けなかった。活路は、50才を過ぎてから画壇と「逆対応」するような作品を描くことによって開けたのである。そして画壇における熊谷守一の地位は、震災地の空に浮かぶトンボのようなものになったのだ。
彼はうまい絵を否定して、印象派の対極にあるような絵を描いている。仲間の画家が壁面を覆うような大作を発表するときに、彼はハガキ4枚の大きさの板きれに色紙を貼り合わせたような絵を描いた。画家たちが競って外遊するとき、熊谷守一は、自宅を一歩もでなかった。彼は、まさに焼け出されて右往左往する罹災者の上空をゆっくり飛ぶトンボだったのである。
熊谷守一が、長い低迷期を脱して作品を少しずつ発表するようになったのは、「墨彩画」を描くようになってからだという。この墨彩画には、心惹かれるものが多い。
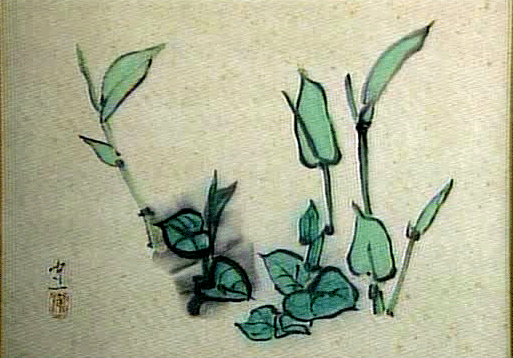
「虎杖」 「蟻」 「虎杖」などは、震いつきたいほどの出来映えである。
熊谷守一が寡作だったのは、描く前の観察時間が長かったこと、それから構図に工夫を凝らしたためだろう。「海」と題する作品でも沖のしらなみの位置が見事に決まっている。画面を単純化すれば、構図が重要になってくる。彼の天賦の才能は、この構図の取り方に現れている。(04/2/16)
この項に採録した図版は、すべてテレビ画像(「新日曜美術館」)から取り込んだものです。