戦前の国民的作家といえば吉川英治だが、戦後の国民的作家は司馬遼太郎である。ところが、私には抵抗があって、この国民的作家の作品をどうしても読み通すことが出来ないのだ。「梟の城」などの伝奇的な作品なら、何とか読むことが出来る。けれども、それ以外の歴史長編となると、もうダメなのである。
ジャーナリズムの世界における司馬遼太郎は、野球の世界での長嶋茂雄のような存在で、誰からも好意を持たれている。二人とも敵を作らない温厚なタイプだから、何処に行っても評判がいいのである。だが、私は、その評判のいいところにひっかかるのだ。
司馬遼太郎の読者には、健全な常識を備えた実務家が多い。一言でいってしまえば、司馬遼太郎を愛読するのは、平均的日本人なのである。だから、彼は読者の好みに合わせて、歴史上の人物を軽量化しアイドル化する。彼の歴史小説を読んでいると、イージーリスニングにしたクラシックを聴くような気がしてくるのだ。
森鴎外や中島敦の作品には、歴史の重さや暗さがリアルに書き込まれている。この点は、松本清張、中山義秀、吉村昭なども同じで、歴史の残酷で非情な面をはばかることなく描き出す。事実、暗黒面を描くことなしに過去を浮かび上がらせることは不可能なのである。
司馬遼太郎は明治を賛美し、昭和時代を酷評している。
だが、明治史は自由民権運動、社会主義者へのむごたらしい弾圧によって血塗られている。為政者間にも、松本清張の「梟首」に見るような陰惨な内部抗争が繰り広げられていた。だが、常識的な歴史は、それらから目をそらして明治日本を賛美する。わが司馬遼太郎も、俗説に調子をあわせて明治をやたらに賛美するのである。彼は、あっけらかんとしてこう書くのだ。
維新後、日露戦争までという三十余年は、文化史的にも精神史のうえからでも、ながい日本歴史のなかでじつに特異である。
これほど楽天的な時代はない。むろん、見方によってはそうではない。庶民は重税にあえぎ、国権はあくまで重く民権はあくまで軽く、足尾の鉱毒事件があり女工哀史があり小作争議がありで、そのような被害意識のなかからみればこれほど暗い時代はないであろう。
しかし、被害意識でのみみることが庶民の歴史ではない。明治はよかったという。その時代に世を送った職人や農夫や教師などの多くが、そういっていたのを、私どもは少年のころにきいている。
司馬遼太郎は明治史の暗黒面を承知の上で、その時代を生き残った庶民が「明治はよかった」といっていたという理由で、明治を明るい楽天的な時代だったという。
彼は、常識に寄り添い、体制に寄り添い、歴史の暗部に蓋をして、明るくて心地よい「庶民向けの」歴史パノラマを繰り広げてみせる。
明治物に限らず、彼が作品に取り上げる主人公は、日本人好みの英雄であり、歴史上のスターであり、日の当たる場所にいる成功者たちだ。彼はそれらの人物に新しい解釈を施し、現代風にリフォームされた人物像を読者の前に提供するけれども、基調は相も変わらぬ通俗的な歴史ロマンなのである。彼が既製の歴史観を大きく転換したことは一度もない。
では、彼の歴史観は、どうして既成観念に媚びる形になってしまうのか。歴史上の権力闘争や合戦を描くに当たって、状況を上から俯瞰するレフェリーの視点に立つからなのだ。
レフェリーの立場で作品を書けば、勝者の勝因、敗者の敗因を記すことで、結局、勝者の行動を正当化することになる。作者は常に勝者の側に立って全局を見通すことになり、関ヶ原合戦を描けば、家康の視点が第一義的に優先され、石田三成は失敗者として位置づけられる。かくて作者は時代の流れを追認する体制派に転落するのである。
鴎外・中島敦の歴史小説を読むと、悲運に倒れた歴史上の人物が主人公になることが多い。そして、それらの作品では局面が敗者の側から見られている。読んでいて、やり場のない悲痛な印象を受けるのは、作品がハッピーエンドで終わらないからだ。
が、司馬遼太郎の作品は、常にハッピーエンドで終わっている。彼の本を読んでいると、自分が歴史を俯瞰する賢者になったような気分になり、勝者との一体感に包まれながら、明るい気持ちでページを閉じることができる。
私は司馬遼太郎の文体から小賢しさを感じる。そして、その作品全体からは夜郎自大の増長慢といった印象を受ける。しかし、世間ではしきりに「司馬史観」なるものをもてはやすのだ。
私は世に言う「司馬史観」というものを研究してみようと思い立って、世評の高い「坂の上の雲」を読んでみた。そして読み終わって、もしかすると自分は司馬遼太郎を過小評価していたのかも知れないぞとチラッと思った。
この作品は正岡子規、秋山兄弟の青春と重ね合わせて、近代日本の青春を描いているということになっている。「坂の上の雲」という題名も、子規と秋山兄弟が坂の上の輝く雲を仰ぎ、明るい未来を目指して闘ったことから付けられたということになっている。
だが、坂の上の太陽や青空を目指したというのなら分かるけれども、坂の上の雲を目指したというのでは、少々、イメージ的におかしくはないか。雲はやはり、明るい空を隠す邪魔物であり、常識的にはマイナス要因なのだ。
私がこうした印象を持ったのは、作者が記している日露戦争後の秋山兄弟の身の振り方に奇異の感を抱いたからだった。司馬遼太郎は、乃木希典と比較して秋山好古のことをこう書いている。
乃木は身を犠牲にすると言いつつも、台湾総督をつとめたり、晩年は伯爵になり、学習院長になったりして、貴族の子弟を教育した。
しかし好古は爵位ももらわず、しかも陸軍大将で退役したあとは自分の故郷の松山にもどり、私立の北予中学という無名の中学の校長をつとめた。黙々と六年間つとめ、東京の中学校長会議にも欠かさず出席したりした。従二位勲一等功二級陸軍大将というような極官にのぼった人間が田舎の私立中学の校長をつとめるというのは当時としては考えられぬことであった。
第一、家屋敷ですら東京の家も小さな借家であったし松山の家はかれの生家の徒土屋敷のままで、終生福沢諭吉を尊敬し、その平等思想がすきであった。
好古が死んだとき、その知己たちが、「最後の武士が死んだ」といったが、パリで武士道を唱えた乃木よりもあるいは好古のほうがごく自然な武士らしさをもった男だったかもしれない。
司馬遼太郎は、さらに秋山好古の弟、秋山真之についてこう書く。
かれは海軍をやめて出家しようとし、そのことを部内のひとびとからとめられると、自分の長男の大(ひろし)に僧になることをたのみ、げんにその長男は無宗派の僧になることによって父親のその希望に応えた。この天才は、敵の旗艦スワロフやオスラービアなどが猛炎をあげて沈もうとしているとき、そのことに勝ちを感ずるよりも、明治をささえてつづいてきたなにものかがこの瞬間において消え去ってゆく光景をその目で見たのかもしれない。
「坂の上の雲」の主役を務めた秋山兄弟は、日露戦争後、軍と政府に背を向け、時代に逆らうような生き方をしている。二人は自らの過去を否定し、日本の将来にむしろ絶望しているかのように見える。
司馬遼太郎が、日本に絶望した秋山兄弟を念頭に置いて作品を書いたとしたら、坂の上に浮かんでいる雲は希望の象徴ではなくて、凶兆としての雲なのである。この考え方が正しければ、司馬遼太郎は私が想像していたよりも遙かに明晰な作家だったということになる。しかし、本当にそうなのだろうか。
トルストイは「戦争と平和」を書くことによって、戦争をくぐり抜けることで変化する人間群像を描いた。「坂の上の雲」に描かれた秋山兄弟も、戦後に全く別人になった。司馬が兄弟の回心、二人の内面的な変化に焦点を置いて、「坂の上の雲」を書いたら、あるいは上質の文学作品になったかもしれない。
ところが、司馬遼太郎は秋山兄弟の内面にほとんど触れていない。彼は、作品の冒頭から兄弟に関する俗耳に入りやすいエピソードを並べて、彼らがいかにすぐれた才能人であったかを強調するだけだ。だから、作品の後半に二人が戦後、軍国日本に背を向けたという記述が出てくると、いかにも唐突だという感じを受けるのである。
好意的に見れば、作者は最初、秋山兄弟の挫折を描くことによって、日本の挫折を描くつもりだったかも知れない。が、日露戦争について調べているうちに、戦史的興味の方が強くなって、登場人物の人間的成長を書くことを放棄したとも考えられるのだ。
実際に「坂の上の雲」の半分以上が、日露戦争に関する戦史的叙述に費やされている。作者はこの作品のために準備期間を含めて40代の10年間を費やしたという。ということになれば、司馬遼太郎の歴史観や人間観を知るには、子規や秋山兄弟の描き方よりは、日露戦争の描き方を見た方がいいことになる。
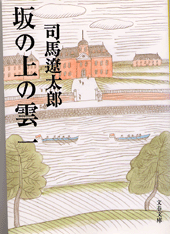
司馬遼太郎は、日露戦争を戦った日本を全面的に肯定している。
だが、今日的な観点から見れば、日本は戦争を始めるべきではなかったし、もし戦争がやむを得ないものだったとしたら、ロシアに負けた方がよかったのだ。そのへんの事情について説明してみよう。
日清戦争は、日本と清国が朝鮮半島の支配権をめぐってはじめた戦争だった。惨敗を喫した清国は、日本に賠償金を支払った上に、台湾・遼東半島・澎湖島を譲渡した。
これを日本の儲けすぎだとして、ロシア・ドイツ・フランスの三国による横槍が入って、結局、日本は遼東半島を清国に返還することになる。
この時、わが国が三国干渉を教訓にして以後大陸への進出を諦め、台湾と澎湖島の経営だけに専念していたら、その後の日本の悲劇はなかった筈なのだ。
(台湾に対する日本の植民地政策は、最初、強圧策を取って失敗続きだったが、総督に就任した児玉源太郎が、後藤新平や新渡戸稲造を登用して融和策を取るにおよんで見事な成功を収めるようになった。日本が太平洋戦争に負けて、中国や朝鮮で反日運動侮日運動が盛んになった時にも、台湾原住民だけが唯一親日的な態度をとり続けている)
ロシアは日本に遼東半島を返還させておいて、その遼東半島を清国から租借し、満州全体に勢力をのばし、さらに朝鮮にも進出し始めた。
中国大陸に進出したのは、ロシアばかりではなかった。イギリスは揚子江沿岸一帯の支配権を手に入れ、フランスは広東・広西・雲南三省、ドイツは山東省を手中に収めた。三国干渉によって国際的に孤立していた日本は、列強諸国の中国進出を指をくわえて見ているしかなかった。
日本がこのまま中国大陸への進出を諦めて、欧米によるアジアの切り取り合戦を座視し、ロシアが満州全域と朝鮮半島を支配下に置くのを傍観していたらどうなったか。──日本国内の商工業は発展し、中国、朝鮮は日本の友好国になったのである。
当時の日本には、二つの路線が争っていた。一つは薩長政府が推進する強国路線・大国路線であり、もう一つは自由民権派の主張する富国路線・小国路線だった。薩長政府は、日本を大国にするために軍事予算を増やそうとし、政党勢力は「民力休養」を唱えて軍事費を減らそうとして争っていたのだ。
大国路線と小国路線のいずれかを選ぶかということになれば、国民は個人の利己心に繋がる大国路線を選ぶ。政府に反対し続けた政党勢力も、日清戦争がはじまると、ころりと態度を変えて軍事費拡張に賛成し、明治28年には総歳出中の軍事費の割合が32%という予算案を承認し、明治30年には総歳出中の軍事費の割合55%という予算を通してしまう。
大国路線を選んだことで、その後の日本は泥沼のような中国侵略戦争にのめりこみ、昭和20年の敗戦を招いたのだから、この路線を推進した明治の元勲たちの罪は深いと言わなければならない。山田風太郎が言うように、明治の日本が昭和の日本を作ったのである。
日本が帝国主義路線ではなく、小国路線を選んでいたら、わが国は北海道から台湾に至る弧状列島国家になり、その地理上の優位性を生かして海洋貿易国家として発展したであろうことは疑いない。それだけではない、日本はアジアにおける近代化運動、植民地解放運動のリーダーになった筈なのだ。
中国も、朝鮮も、日本の明治維新を範として自国の近代化をめざすグループを輩出するようになっていた。そして日本国内には、そうした運動を援助する一群の「大アジア主義者」が現れ、彼らは国境を越えてアジア諸国の志士と手を結ぶんでいたのである。宮崎滔天は、孫文を生涯にわたって援助したし、フィリピンのアギナルドを後援した日本人もいる。
もし日本が台湾を基地にして中国革命を物心両面から援助したら、日本はすべての面で中国と提携するようになり、第一次世界大戦後の「民族自決主義」の潮流に乗じて両国は植民地化されていたアジア諸国の独立運動を支援したと思われる。
第二次世界大戦が始まる頃には、日本・中国を中軸とする東アジア諸国は、「国際連盟」の場で共同歩調を取るようになり、戦争には中立を守ったろう。そして、これを政治的経済的飛躍のチャンスとしてそれぞれが発展路線に乗ったに違いない。
だが、現実には明治時代に富国強兵政策に反対し、小国主義を唱道したのは中江兆民や少数の社会主義者に過ぎなかった。
次に、日露戦争に敗北した場合を想定してみよう。
実際、日本は紙一重の差で勝ったのだった。多くの研究者が指摘するように、もしロシアがもう半年戦争をつづけたら日本は確実に敗北していたのである。
司馬遼太郎も、書いている。
大山巌は・・・・・「戦略目標は敵の塁壕に非ず、敵の野戦軍にあり」と、訓示している。いままでの経験では、日本軍が惨烈な戦いをしてやっとロシア軍の「塁壕」をうばったときは、ロシア軍はさっさと逃げて、より北方の塁壕で待っている、というものであった。たしかに日本軍は勝ってきた。しかしその勝ちは戦略的観点からの「勝ち」という必要かつ十分な条件を具備しておらず、このようないわば追っかけっこを繰りかえしているかぎり、国力の微弱な日本側としてはやがては軍事的体力を消耗し、最終的には大負けに負けてしまうというおそれが濃厚にあった。
大山巌訓示のこの項はそのことを痛烈に指摘し、
「敵の野戦軍そのものをやらねばならない」
という意味のことを言う。ついでながらこの場合も、撃滅、殲滅という過大表現はつかっていない。しかしながら内実はクロバトキンの軍隊をこなごなにくだいてしまう以外に日露戦争の勝利はありえないといっているのである。が、この目的は、結果としてはついに達成できなかった。ロシア軍は一大損害をうけたとはいえ、十分に戦力を残した主力が、鉄嶺へ逃げさらにその北方へ逃げるという過去のくりかえしをこのときも繰りかえした。
さらに彼は次のようなことまで言っている。
たとえばクロバトキンが考えていた大戦略は、遼陽での最初の大会戦で勝つことではなかった。遼陽でも退く。奉天でも退く。ロシア軍の伝統的戦術である退却戦術であり、最後にハルビンで大攻勢に転じ、一挙に勝つというもので、それは要するに遼陽、沙河、奉天で時をかせぐうちに続々とシベリア鉄道で送られてくる兵力を北満に充満させ、その大兵力をもって日本軍を撃つということであった。
もしこの大戦略が実施されておれば、当時奉天の時点ではもはや兵力がいちじるしく衰弱していた日本の満州軍は、ハルビン大会戦においておそらく全滅にちかい敗北をしたのではないかとおもわれる。
司馬遼太郎は、日本の勝利が紙一重の勝利だったことを認めた上で、もし日本が負けたらどうなっていたかを次のように予想する。
当然、日本国は降伏する。この当時、日本政府は日本の歴史のなかでもっとも外交能力に富んだ政府であったために、おそらく列強の均衡力学を利用してかならずしも全土がロシア領にならないにしても、最小限に考えて対馬島と艦隊基地の佐世保はロシアの租借地になり、そして北海道全土と千島列島はロシア領になるであろうということは、この当時の国際政治の慣例からみてもきわめて高い確率をもっていた。
司馬のこの予想は、あまりにも悲観的である。
日本の勝利が紙一重の勝利だったように、ロシアが勝つとしても、それは紙一重の勝利だから、ロシアが日本に過大な要求を突きつけられる筈はない。
第一、戦争は第三国の領土内でなされて、ロシア軍は日本の国土に一歩も踏み込んでいないのである。そして戦争をいくら継続したところで、制海権を日本に奪われているロシア軍は、日本に上陸する可能性は全くなかった。
日露戦争の勝者となった日本は、講和条約で賠償金を要求したがロシアから拒否され、樺太の半分を割譲させただけだった。ロシアが勝利した場合も、ロシアは千島列島と日本周辺の島のいくつかを獲得する程度のことで満足しなければならなかったろう。
国土の幾分かをロシアに割譲したとしても、敗戦後の日本が内政面で得るところはそれらを償って余りあるほど大きかったにちがいない。
敗北によって薩摩・長州による藩閥政治は完全にトドメを刺され、政党政治の時代に入るからだ。政党政治が、戦前の「民力休養」政策をすぐ採用することは出来ないかも知れない。ロシアへの復讐を叫ぶ右派の勢力が存在するからである。
だが、日露戦争に反対した社会主義者や西欧のデモクラシーの洗礼を受けたインテリ層の勢力が徐々に増加していく。国家予算に占める軍事費の割合は縮小を続け、その分がインフラの整備と国民生活の向上に振り向けられる。
国民の生活水準が上がれば、国内市場も拡がり、海外市場の獲得を目指して対外冒険主義に走る必要はなくなる。侵略戦争をやめた日本は、中国、朝鮮の自立を援助してその友好国となり、これらの国への資本輸出によって相手国の産業育成に貢献したはずだ。中国、朝鮮が豊かになれば、日本産業の市場も自ずと増えるのである。
つまり、日露戦争の敗北は、太平洋戦争敗北後の日本の路線変更を先取りする形になり、一足早く戦後民主主義を実現することになった筈なのだ。
司馬遼太郎は、こうした展望を欠いたまま、日露戦争を始めた日本を是認する。
日本は、その歴史的段階として朝鮮を固執しなければならない。もし、これをすてれば、朝鮮どころか日本そのものもロシアに併呑されてしまうおそれがある。
日露戦争前夜に戦争熱を煽る一部マスコミが、ロシアによる日本占領の危機を訴えたのは事実である。だが、その頃、日本は先進国から最新鋭の軍艦を買い集めて、老朽化したロシア艦隊が太刀打ちできないほどの海軍を作り上げていたのだ。
だから、政府部内にもロシア軍が日本に上陸するなどという事態を想定する人間は、ほとんどいなかったのだ。
戦争責任についての司馬遼太郎の見解にも、行き過ぎがある。
戦争責任者はロシアが八分、日本が二分。ロシアの八分のうちほとんどはニコライ二世が負う
日本とロシアは、共に朝鮮を植民地化しようと狙っていた。その朝鮮半島に対するロシアの圧力が増してきたから、日本は自国の防衛のためではなく、朝鮮を確実に自己の勢力下に置くために開戦に踏み切ったのだ。しかも日本は真珠湾攻撃の時と同様にロシア艦隊に奇襲攻撃をかけている。戦争責任は彼我五分五分といっていい。
司馬遼太郎は通俗の日露戦争観をなぞるようにして「坂の上の雲」を書いた。彼は、ロシアが悪いから戦争ははじまり、圧倒的に優勢なロシアが敗れたのは、現地日本軍将兵が優秀だったからだという世上の通説に縛られてしまっている。これでは、仮に彼が秋山兄弟の目を通して日露戦争の暗部を描くという目論見を抱いていたとしても、中途で挫折してしまうのは当然といえる。
日本を誤った方向に導いたのは、明治期に大陸進出路線を決定した薩長系の政治家たちだった。明治前期の政治史は、薩長系の国権派と非薩長系の民権派による対立抗争期だったというふうに要約することもできるだろう。この争いに勝利した国権派は、明治憲法を成立させ、富国強兵路線、つまり中国大陸進出路線を決定した。この縛りがいかにも強烈だったので、その後の日本はこの大国路線をひた走るしかなくなり、中江兆民や石橋湛山の「小国主義」に耳を傾けるものはなくなったのである。
司馬遼太郎は富国強兵路線を敷いた明治の為政者たちを賛美する。そして昭和の政治家・軍人を全否定する。彼らは愚かにも、日露戦争の勝利が薄氷の勝利だったことを忘れて、日米開戦に突き進んだというのが司馬遼太郎の解釈なのだ。
(彼らは反省するどころか)むしろ勝利を絶対化し、日本軍の神秘的強さを信仰するようになり、その部分において民族的に痴呆化した。日露戦争を境として日本人の国民的理性が大きく後退して狂躁の昭和期に入る。やがて国家と国民が狂いだして太平洋戦争をやってのけて敗北するのは、日露戦争後わずか四十年のちのことである。敗戦が国民に理性をあたえ、勝利が国民を狂気にするとすれば、長い民族の歴史からみれば、戦争の勝敗などというものはまことに不可思議なものである。
だが、司馬遼太郎といえども、日露戦争後に参謀本部が官修の「日露戦史」10巻を刊行したことを記さざるを得なかった。日本側に都合の悪いことをすべて隠蔽したこの本は、司馬の賞賛してやまない明治の将軍たちが部下に書かせたものなのである。
これ(官修「日露戦史」)によって国民は何事も知らされず、むしろ日本が神秘的な強国であるということを教えられるのみであり、小学校教育によってそのように信じさせられた世代が、やがては昭和陸軍の幹部になり、日露戦争当時の軍人とはまるでちがった質の人間群というか、ともかく狂暴としか言いようのない自己肥大の集団をつくって昭和日本の運命をとほうもない方角へひきずってゆくのである。
「大本営発表」式の上からの騙しはすでに明治のころから行われ、お人好しの庶民はそれにすっかりだまされていたのである。
しかし昭和の政治家たちは、お人好しだったのではない。明治の為政者がつくりあげた国家の枠組み、司馬の用語で言えば「国のかたち」に忠実だったから、「昭和日本の運命を途方もない方角にひきずってゆく」ことになったのだ。
では、薩長系の政治家たちは、なぜ、大国路線に執着したのだろうか。──日本が貧しかったからなのだ。貧しかったから日本は、日清・日露の戦争に打って出て、挙げ句の果てアメリカにまで戦いを挑むことになったのである。
昭和20年の敗戦後、アメリカから各種の視察団が日本にやってきた。来日した調査団員は一様に、「こんな貧弱な工業力しかないのに、日本はどうして戦争を始めたのか」と呆れたという。
ニコライ二世統治下のロシアが、他国の顰蹙を招くほど露骨な対外膨張政策をとったのも、ロシアが貧しかったからなのだ。日露戦争は、貧しさのために対外冒険主義に走らざるを得なかった日露両国が、成算をを度外視してはじめた非合理な戦争だったのである。
日本もロシアも、国民の圧倒的多数は農民であり、そして両国の農民はいずれも極貧にあえいでいた。両国とも、近代工業育成策を実行した結果、あらたに労働者層が生まれて来はしたが、彼らの賃金は国内に貧農の大群が存在するが故にその線まで引き下げられ、国内の消費市場はほとんど育っていなかった。
国内の消費市場が未発達なら、商工業も発展しない。ということになれば、商工業者の利益を代弁するメンバーが政策決定の場に加わることもない。明治政府を動かしていた政治家は、ほとんど全員が薩摩長州の中下級武士であり、産業経済のエキスパートは皆無に近かった。
明治政府が行った殖産興業政策は、農民から吸い上げた税金で官営模範工場を作り、これを民間に払い下げるというレベルのもので、外貨の獲得はもっぱら生糸の輸出によるという哀れな状況にあった。
当時、朝鮮、満州と日本の間の貿易関係は極めて僅かだったから、明治政府は海外市場を確保するために朝鮮や満州に執着したのではない。武士的意識を清算しきれなかった政府のリーダーたちは、一種のサムライ的感覚からこれらの地域を自国防衛の外郭部分として、また、資源や税収を取り上げる略奪対象として執着したのである。
朝鮮・満州、さらには中国全土が海外市場として浮上してくるのは、大正、昭和と進み、日本の工業生産力がある程度上昇し始めてからだった。軽工業を中心にして工業部門の生産量が増えてきたものの、農民の所得は増えず、これに右へならえして工場労働者の所得も増えない。国内の消費市場が未熟なら、製品は外国に持って行って売りつけるしかないのだ。
日本の周辺には、これはというような軍事強国はなかった。だから、日本は羊の群れの中のオオカミのようにアジア諸国を侵略して、彼らを自己の経済圏に組み入れようとしたのである。従って、日本国家の侵略的性格をなくすには、明治の藩閥政府が敷いた大国路線を改めるだけでは足りなかった。国民全体の生活水準を引き上げて、国内に安定した消費市場を形成しなければならなかったのだ。進駐軍が日本政府に指示して農地解放やら労働組合保護をやらせたのは、この為だったのである。
明治の俊才たちを賛美する司馬遼太郎は、彼らがいかなる土壌から生まれてきたか考察する。彼によれば、それは江戸時代の精神的遺産からだという。
子規は、ごくふつうの人であった。明治期には子規のような一種の人生の達人といった感じの風韻のもちぬしは、どの町内にも村にも、ありふれて存在していたようにおもわれる。江戸期がのこした精神遺産が子規の時代ぐらいまで継続していたといえるかもしれず、ひるがえっていえば日露戦争期の明治というのはそういうものの上に成立している。
正岡子規が「人生の達人」であったかどうかは議論の分かれるところだが、昭和をもたらしたのが明治だったように、明治をもたらしたのが江戸時代だったことに疑いはない。だが、それを「江戸時代の精神的遺産」だとして、問題を精神面に限定してしまうところに司馬遼太郎の限界がある。
明治政府が江戸時代から継承したのは、五公五民の高額年貢制度であり、農民を支配対象としか見ない治者意識だった。幕藩時代の諸藩は、農民から収量の半分を年貢として取り立て、明治になって藩が消滅してからは、地主がこれを引き継いで50%近い高額小作料を取り立てた。明治以後、農村が消費市場として成長しなかったのは、政府が農業問題に積極的に取り組まなかったためである。
明治維新のリーダーたちも、農民を支配対象としてしか見ていなかった。彼らが、いかに農民を軽視していたかは、西郷隆盛の行動を見れば分かる。情愛の人だった西郷は、時代から取り残された弱者に同情の目を注いだとされているけれども、彼が同情したのは維新によって失業した武士たちだった。
彼の征韓論は、少数の旧武士のためのもので、彼が国民の大多数を占める農民のためになにか建設的な提案をしたという話を聞いたことはない。「敬天愛人」の「人」とは身内の武士を意識したものに他ならなかった。西南の役では、その武士主体の西郷軍が、農民主体の政府軍に敗れたのだから皮肉である。
司馬遼太郎は唯物史観や貧農史観に対する反発からか、唯「心理」史観というべきものに傾斜してしまう。
日露戦争に際して圧倒的に優勢なロシア軍が敗れた原因を、彼は指揮官の心理や性格に帰している。司馬遼太郎は、ロシア軍の基本戦略が日本軍を満州奥地に引き込むことにあったと認めていながら、クロパトキン総司令官が戦略的後退をつづけたのは精神病的な心理によると説明する。クロパトキンには、恐怖体質に基づく完全主義があり、自軍の体制が完璧に整わないうちは決戦に出ることを避けたというのである。
日本海海戦に敗北したロシア艦隊司令官も、自分だけが天才で他のものはすべて愚人だと考える自己肥大的性格の所有者だったとしている。そのため水兵でさえ知っている軍隊統率の初歩を実行しなかったというのだ。
ここは、やはりロシアの社会体制を掘り下げて原因を追及すべきだったと思う。ロシアでは貴族でないと将校になれず、従って兵士の間に戦艦ポチョムキンの反乱に見られるような気分が横溢していた。この辺は明治維新によって四民平等の体制を打ち出していた日本の軍隊とは違っていたのだ。
「坂の上の雲」には、日露戦争の様相が生き生きと描かれ、類書にはない充実した内容になっている。何しろ司馬遼太郎はこの作品のために10年をかけたのである。戦争の流れを掴むために、彼は自分を戦争当事者の立場に身を置いた。
満州における陸軍の作戦は、最初から自分でやってみた。満州への軍隊輸送から戦場におけるその展開、そしてひとつひとつの作戦の価値を決めることを自分ひとりのなかで作業してみるのである。戦術的規模より戦略的規模で見るようにしたため、師団以上の高級司令部のうごきや能力を通じて、時間の推移や事態あるいはその軍隊運用の成否を見てゆこうとした。
彼は日露戦争を追体験するに当たって、もっぱら指揮官の立場に自分を置いたのが間違いだった。このため、彼は心理主義的偏向に陥ってしまったのだ。
司馬遼太郎は、指揮官とそれを取り巻く小状況だけに目をやり、社会経済的背景という大状況を検討する労を惜しんだ。
それは彼が当代屈指の流行作家だったからでもある。殺到する原稿依頼に応えるためには、近景に目をやるだけで精いっぱいで、遠景を顧みる余裕はなかったのだろう。
彼の文章を読んでいて、気になる癖がある。「──の奇妙さは」「──の不思議さは」「──の面白さは」というような、叙述法である。「坂の上の雲」にもこの叙法が頻出する。
「明治海軍のおもしろさは、山本権兵衛が一大佐か、少将の身で大改革をやりえたということである」「西郷従道のふしぎさは、海軍について何も知らないこの人物が明治18年伊藤内閣ではじめて海軍大臣をやったのをかわきりに、明治26年に就任し、さらに松方、伊藤、大隈の三内閣とつづいて海軍大臣をやったことである」
だが、こんなことは、面白くもないし不思議でもない。藩閥政府が人材不足の宿命を負っていたというだけの話なのだ。
彼がこういう叙法を多用したのも、そして又、歴史の分岐点になるような事件を、スター的英雄の個性や知略に還元して描いたのも、文筆稼業が繁盛しすぎて沈思黙考する時間がなかったためと思われる。
「坂の上の雲」を通読したところでは、司馬遼太郎の史観は講釈師が張り扇を叩きながら天下国家を論じるのと大差がないような気がする。彼は一つ一つの作品をもっと時間をかけて書くべきだったのだ。そして息抜きに「梟の城」のような忍者物を作っていればよかった。だが、彼は新幹線で突っ走るような超多忙な作家生活を送り、沿線の細部を見落とす大味な歴史小説を書いてしまった。そして自身の寿命まで縮めてしまったのである。