パソコン歴
まだ、パソコンのOSにWINDOWSが使われていない頃、富士通の新聞広告を見て、TOWNSを購入しました。
ビデオデッキの操作にも難渋しているメカ音痴の私がそんな「暴挙」に出たのは、パソコンで「野草図鑑」が作れそうだと感じたからです。半年間、四苦八苦した末にパソコンで図鑑を作製することに見切りをつけました。何しろこの頃のスキャナの性能がひどくて、A4版の画像をパソコンに取り込むのに1時間以上かかるような有様でしたから。
そこで、パソコンをワープロ専用機として使うことにしました。だが、14インチのモニターでは文字が読みづらく、もう、いい加減でパソコンいじりは止めようと思いましたね。17インチのディスプレイを通信販売で買ったことが転機になりました。これだと、全然目が疲れない。で、パソコンをワープロとして活用するようになっただけでなく、パソコン通信も始めました。
NIFTY ,PC-VAN ,ASAHI-NETと三つものプロバイダーと契約して、当時、あちこちのフォーラムにさかんに書き込みをしたものです。半年もしないうちに今度はPowerMac8100/100AVというのを買い込みました。これはその頃のMACの最高機種で、かなり高価でしたが、こうした身の程知らずの行動に出たのも、もとをただせば一度は断念した図鑑作りの夢を諦めきれなかったからです。画像ならMACという話を耳に挟んで闇雲にこれが欲しくなったんですね。とにかく図鑑を作りたい一心でした。

図鑑といったところで、上図にあるようなスケッチ程度のものを観察記録と一緒に残しておくだけのものでしたが。
MACを使って画像の取り込みをすると、評判通りうまくゆく。スキャナの性能も向上して来ていました。けれども、エディター画面に画像を貼り付けようとすると、ダメなんですね。小さな画像ならいいが、大きな画像になるとパソコンは「メモリーが足りません」と受け付けてくれない。
パソコン通信でこのことを嘆く書き込みをしたら、通信上の友人がインターネットのhtml形式なら大きな画像でもテキストの中に取り込むことが出来ると教えてくれました。
このことが頭にあったから、数日して大型電気店に立ち寄って店頭に並んだホームページ作製ソフトを目にするやいなや、前後の考えもなしに手近にあったMAC用のソフトを衝動買いしてしまいました。
家に帰って早速使ってみました。いやあ、驚きましたね。どんな大きな画像でもページの中に貼り付けることが出来る。しかもリンクを使うと、辞典を引くように、好きなページに飛ぶことが出来ます。これこそ、パソコンに手を染めて以来、私が探し求めていたソフトだったのです。
(ふーん、これならホームページだって作ることが出来るかもしれないぞ)
ということで、「野草図鑑」を作成する傍ら、未熟を省みずチャレンジしたのが このホームページです。一気呵成に作り上げたのでミスが多く、早く、全体の手直しをしなければいけないと思いながら、未だにそのままになっています。
その後、パソコンを買い足して、2000年現在で、DOS-V機4台、MAC機2台を持っています。ここまで来ると、道楽を通り越して、最早「放蕩」ですが、パソコンがこんなに増えたのには理由があります。敷地内にプレハブ6畳間の「庵室」をもうけ、冬期間の日中をこの中で過ごすことにしたからです。冬ごもり用の庵室ですね。
暖を求めて温室のように温かな庵室にこもるのはよい。が、昼間をここで過ごすには、電話・テレビ・ステレオなどと共にパソコンも必要です。かくて、ちっぽけな6畳間に電灯線と電話線、それにケーブルテレビのケーブルが引き込まれることになり、更に、母屋のものとは別に、この離れ専用のDOS-V機とMAC機を買い足すことになったのです。
つまり、母屋用と離れ用の二通りのパソコンが必要になった結果として、パソコンとその関連機材が二倍に増殖することになってしまった。
 母屋二階のパソコン
母屋二階のパソコン二階には、DOS-V機2台とMAC機が並んでいます。これら3台はMaclanというソフトとLAN(ハブ使用)で繋げて、相互にデータを共用できるようにしてあります。
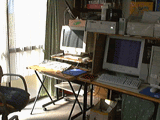 離れのパソコン
離れのパソコン離れのパソコンは二つの机をつなぎ合わせた上に、並べて置いてあります。プレハブ小屋の弱点は屋根ひさしがないため、昼間、室内に陽光が満ちあふれてしまうことですね。お陰で温かくはあるけれど、パソコンのディスプレイが見にくくなります。痛し痒ゆしと言うところです。
私は自分を東洋的・隠者的な人間だと思っていました。それが、目下、パソコンを自力で組み立てようと計画中なのだから自分でも驚いています。
私は、学生時代の昔から自分が世の中に合わない人間だと思っていた。それで、学校を出たら、関西あたりに流れていって三流私立高校の教師にでもなろうと、格別、気負うでもなく、卑下するでもなく考えていたのだった。貧乏教員になって、タバコ屋の二階に下宿し、がめつい大阪人を眺めて暮らしたら、案外、おもしろい一生を過ごせるかもしれない。
そんな事を考えながら、その反面で、いずれ自分は野垂れ死にをすることになるかもしれないとも予想していた。自らを社会的不適応者だと規定しながら、自分を社会に合わせる努力をしなければ、落ち着く先は野垂れ死にしかない。私には当時社会に適応していこうとする気が全くなかったのだ。
「野垂れ死にをする、それも結構」──と居直る気持ちの底には「世捨て願望」「自死願望」のようなものが揺曳している。そのことを私は明瞭に自覚しながら学生時代を過ごしていたのである。
しかし私の人生は、青春を病床で過ごすようになっていた。私が20才に始まる結核を何とかなおして、やっと社会に復帰したときには、もう30を過ぎていた。そんな病み上がりの厭世主義者が、これも成り行きとはいいながら、結婚することになったのだから、皮肉な話としかいいようがない。
「単純な生活」という私の本には、このときの心境が以下のようにありのままに記してある。この本を読んでくれた人々の顰蹙を買うことになった一節である。
私は結婚したくて結婚したのではなかった。私が衷心から望んでいるのは、(発病前に東京で体験した)屋根裏時代の生活であり独居の自由であった。結婚して係累を増やし、子を生んで負担を加え、一家を構えることで近隣と永続的な関係の中に入る。それは何時でも自由にできる女の身体を持つのと引き換えに、独身者の天衣無縫の自由を売り渡すことであった。私は次々に結婚して行く友人達を眺め、彼らは自分の入る檻を探しているのだと思った。
私は結婚したあとで複数の友人から、「お前は一生独身で通す人間だと思っていた」という感感を聞かされたが、結婚は本来私の望むところではなかったのである。
だが、ひとたび所帯を持った以上は、自分の人生は自分のものであって、自分のものではない。私は県立高校の教員になり、世に合わせて生き始めた。現世への違和感を抱いたまま教員になり、鬱々として暮らしているうちに、私は初めて自分が或る思想的な水系に沿って歩んできたことに気がついたのだ。
私がこれまでに心惹かれてきた老子、安藤昌益、中江兆民、ベルグソンなどの思想家、そしてトルストイ、森鴎外などの作家は、同一の思想水系に属する人間たちだった。アナーキズムの系譜に連なる面々だったのである。
現世を容認せず、しかし何時とも知れぬ遠い未来に望みを嘱して生きている単独者は、すべてアナーキストなのだ。その意味では、鴎外によって描かれた「安井夫人」もアナーキストの一人なのである。鴎外は書いている。
お佐代さんは必ずや未来に何物をか望んでゐただらう。そ
して瞑目するまで、美しい目の視線は遠い、遠い所に注がれ
てゐて、或は自分の死を不幸だと感ずる余裕をも有せなかっ
たのではあるまいか。其望の対象をば、或は何物ともしかと
弁識してゐなかったのではあるまいか。
結婚後、私は自らを「老子的アナーキスト」と自称するようになったが、私の言うアナーキズムとは「待ちの思想」を体系化したものにほかならなかった。テロに走るアナーキストは我慢の足りない突出グループで、本来のアナーキストは専制政治から民主政治へ、戦争から平和へと歩んできたた人類史の流れを信頼して、待ちの姿勢に徹する。妄動しないのである。
無支配共存の理想社会を実現するのは、社会的な革命などではなく、個人の意識革命なのである。人間の意識は、じれったいほど緩慢ではあるけれど、確実に進歩している。
私は漠然とあと四、五百年もすれば何とかなるのではないかと考えていたが、最近の国内情勢・世界情勢をみると、理想社会の実現には数千年の時間が必要らしくもある。いや、数万年かかるかもしれないし、「永久革命」を必要とするかも知れない。しかし、いずれは何とかなる──これが私の「信仰」なのである。
待ちの姿勢を続けているうちに、私は意外なほど長生きをすることになった。所帯を持った頃は、とても60までは生きられまいと思っていたのに、間もなく80才になろうとしている。そして、80を目前にした今も、お佐代さんと同じように目を「遠い、遠い所」に注いでいる。愚者というべきかもしれない。
明治44年に冤罪で処刑された幸徳秋水は「無政府主義の学説はほとんど東洋の老荘と同時の一種の哲学」であると言い、アナーキストは「権力・武力で強制的に統治する制度」に変えて、道徳と愛をもって結合する社会を目指すものだと説明しています。
無政府主義の社会は、暴力革命などを介さず、来たるべきものが来たという形で到来するはずです。なぜなら、上からの強制のない自由な社会で、穏やかに平和に生きたいというのが、人類共通の夢なのですから。人類の歴史は、この人類永遠の夢を実現する過程にほかならぬと思うのですが、いかがでしょう。
(04/10/10)
「文藝春秋」新年号の「理想の死に方」という特集記事を読んでいたら、私と同じような考え方をしている筆者を一人発見した。朝鮮出身の姜尚中は、日本人の死に対する禁忌意識に触れたあとで、次のように書いている。
「理想の死」について語ることは、「理想の生」について語ることと同じなのだ。・・・・・・それではわたしにとって「理想の生」とは何だろうか。それは、自分の願いが確実に誰かに受け継がれ、自分がこの世からなくなっても自分の願いの実現に向けて「理想の生」を生き抜こうとする人々がいることを確信しながら、終わりを迎えることが出来ることである。
・・・・・個体としての人間は死すべき運命にあるが、類としての人間は永続的に生き続ける。
人間は個我意識のほかに魂の領域とでもいうべきものを併せ持っている。魂は「永遠の実在」を映し出しはするが、それ自体は永遠ではない。これはそれ自体無内容な鏡のようなもので(禅者は自我の深奥に「古鏡」があるといっている)、個我意識とともに死の瞬間に、跡かたなく無くなってしまうのだ。「死ねば何もかもなくなってしまう」、これが人生の実相なのである。
従って、死後の永生ということも不可能なら、転生ということもありえない。永遠の生を求めるなら、子や孫や国にではなく、遠い未来の人類に自分の願いを仮託するしか方法はないのだ。
個人の死が、何時・何処で・どのような形で現れるかは、全く分からない以上、「理想の死に方」などについて考えるのは詮ないことである。すべてを自然にまかせ、人類の未来に思いをはせつつ心静かに「終わりを待つ」のが正しい晩年の過ごし方ではなかろうか。
(05/1/1)
ホームページに戻る