自己改造
電車賃値上げ反対運動で初めて逮捕された大杉は、一緒に釈放された同志の深尾韶と共に堺利彦の家に転がり込んでいる。大杉には同棲中の年増女がいたはずだが、その女の家には行かないで、堺のところに居候になったのである。女の家に行きにくい事情があったものと思われる。
苦労人の堺利彦の家には、すでに荒畑寒村が居候をしていたし、義妹の堀保子が出戻りになって世話になっていた。そこへ新たに大杉と深尾韶が加わったのだ。この時、大杉は21才、荒畑寒村は19才、堀保子は大杉より2才年長の23才で、深尾韶も同じくらいの年齢だった。一つ家に若い男女が同居していたら、愛情問題が発生するのは避けがたかった。
まず、深尾韶が堀保子を好きになる。保子もそれに応えて「将来を誓いあう仲になった」というから、二人は婚約したのである。そこへ大杉が割り込んでいって保子に求愛したのだ。
保子は大杉と結婚するまでのいきさつをごく簡単にしか書いていない。
当時、大杉は同志の間に有為な青年として望みを託され、殊に電車事件の被告で保釈中という身の上でしたから私も深い同情を以て迎えていましたが、何分年下ではありすぐに承諾する気にはなれませんでした。しかし、大杉が余り迫ってきますので、遂に結婚したような次第です(「大杉と別れるまで」)
その間の事情を近くから見ていた荒畑寒村は、真相をこうばらすのだ。
大杉が兇徒哺衆事件の保釈になって出て来た時に麹町の堺さんのところに、大杉と深尾と〔二人〕して転がり込んだ。私はもとから居候の先輩だった。ところが、保子さんは堺さんの先夫人の妹で、かたづいた先で夫婦仲が悪くやめて、やはり堺さんの所に居候していた。雑誌の広告の仕事などをしており、保子さんと深尾と非常に仲がいい。
……その時やはり大杉に年上の女があって、未亡人かなんかで、その人と別れるのに保子さんが仲に立って手を切らせたのです。すると今度は大杉が保子さんを口説くというんです。
保子さんは深尾との約束があるから容易にいれられない。すると夏のこと、大杉が自分の浴衣に火をつけて、どうだといった。熱烈なる、文字通り熱烈なる口説き方で、とうとう根負けしたというか、意気に感じてああいうことになった。
この時、大杉は着ている浴衣の裾に火を付けて、焼身自殺をすると言って保子を脅したと思われる。大杉の得意とするパフォーマンスである。
大杉と保子は、入籍しないまま新居を構えることになるが、その生活費は主として保子の稼ぎによっていた。
市ヶ谷田町に新居を構えましたが、大杉はまだ二十二歳の青年で定まった収入はなく、私が堺さんの世話をうけながら発行していた『家庭雑誌』で、かなりの収入を持っておりましたので、さしあたりそれを生活の根拠とし、かたわら大杉が仏語とエスペラント語の教授をはじめました。(「大杉と別れるまで」)
保子にとって大杉との生活は苦労の連続だった。何しろ、ちょっと平穏な生活がつづいたかと思うと、大杉はすぐに逮捕投獄される。そのたびに保子は大杉に頼まれた書籍を差し入れなければならなかった。保子は「大杉へは困苦の中でも間断なく、外国から取り寄せた書物を差し入れ、及ばずながら同志の家族のお世話もしたりして、余所ながら大杉の志をたすけておりました」と書いている。
大杉の人生の相当部分は、年上の女から経済的に援助されることで成り立っている。外国語学校を卒業後、そして出獄後、それぞれ別の女の世話になり、その後も、大杉は経済的なピンチを神近市子によって救われているのである。
彼は著作業が軌道に乗るまで「英独仏露伊語教授」という、いかにも大杉らしい看板を自宅にかけて生徒を集めていたけれども、保子の稼ぎをあてにしなければ暮らして行けなかった。結核を病んでいた保子が、大杉を追うようにして病死したのは、この頃の無理な生活がたたったからだった。
大杉が刑務所を出たり入ったりしていた頃、宮中では「山県の密奏」とか「西園寺内閣の毒殺」とかいわれる不祥事が進行していた。山県有朋は西園寺公望内閣に替えて、子分の桂太郎を首班とする後継内閣をつくるために明治天皇への密奏をつづけていたのだ。
山県は、天皇暗殺のアジビラがアメリカの日本領事館にはりだされたことなどを持ち出して明治天皇の恐怖感を煽り、「これも西園寺内閣の社会党取り締まりが手ぬるいからだ」と内閣の更迭をうながしたのだ。
窮地に立たされた西園寺内閣は、明治41年6月に起きた赤旗事件の責任を取って総辞職をする。山県の密奏は見事に成功した。
では、内閣を総辞職に追い込んだ「赤旗事件」とはいかなるものかといえば、全くアホらしいほどつまらぬ事件なのだ。刑務所にいた山口孤剣が出獄したので、同志が集まって歓迎演説会を開き、その後で若い仲間が「無政府共産」の文字を縫いつけた赤旗を振りかざして会場の外になだれ出た。そして、警官隊と揉み合いになったのである。
旗を奪われまいとして警官に抵抗した若い同志も、騒ぎを鎮めようとして割って入った年配の同志もことごとく逮捕された。これが「赤旗事件」の実態なのである。裁判にかけられた同志たちは、たいした事件ではないから懲役二、三ヶ月ですむものと楽観していた。
ところが首謀者とされた大杉は重禁錮2年半、堺・山川は2年、荒畑は1年半という予想もしない重い判決が出たのだ。西園寺内閣の後を継いだ桂太郎内閣は、社会党の息の根を止めようとして苛酷な弾圧に乗り出したのである。
大杉にとって重禁錮2年半というのは、これまでで一番長い服役期間だった。彼が本当に成長したのはこの時だった。
僕の知情意は、獄中生活の間にはじめて本当に発達した。人情の味もわかり、自分とはちがう人間に対する理解とか、同情というようなことも分った。客観はいよいよ深く、主観も亦ますます強まった(『続・獄中記』)
大杉は刑務所で内省を重ねることによって人間的な深みを増したが、対外的には相変わらず突っ張った態度を変えなかった。内務省警保局の調査書には、次のような文字が見える。
千葉監獄入監後全ク改悛ノ状ナク、言動スコブル危険ニシテ現二数回ノ懲罰ヲ受ケタリ。尚、釈放後モ些カモ悔悟ノ念ナク、「二ケ年半ノ在獄ハ、主義二関スル十分ノ研究ヲ為サシメ、吾人ノ意志ヲシテ益々強固ナラシメタリ。コノ点、政府二対シ探ク感謝スル所ナリ」ナドト放言セリ。
赤旗事件の被告が留守をしている間に大逆事件が起きたことは、入獄していた被告たちにとって幸運だったといえる。
社会党の同志が山口孤剣の出獄祈念演説会を開いていた時に、幸徳秋水は病気療養のため郷里の土佐に帰省していたのだった。彼は赤旗事件で社会党の主要メンバーがことごとく逮捕されたことを知って、急いで上京した。堺、山川が逮捕されたいま、党を立て直すのは幸徳をおいて他に人がいなかったのだ。幸徳秋水は上京の途次、各地の同志の家に立ち寄り、党再建の相談をしたり協力を求めたりしている。
上京して千駄ヶ谷に落ち着いた彼のところに、荒畑寒村の愛人菅野須賀子が転がり込んで来た。荒畑の入獄後、菅野須賀子は、持病が悪化し幸徳に頼るしか生きる方法がなかったのだ。幸徳は須賀子を転地療養させるなどして面倒を見ることになる。
妻の千代子と離婚していた幸徳は、菅野須賀子の世話を焼いているうちに自然に夫婦の関係になった。このニュースが拡がると、獄外に残された同志らの菅野を見る目が一挙に冷たくなった。彼女は獄中の荒畑を見棄てて、大物の幸徳に乗り換えたのだ。
仲間から白眼視されたことで持病のヒステリーをいよいよ募らせた須賀子は、デスペレートになって明治天皇の暗殺を考えるようになる。彼女は以前に入獄した際、役人に侮辱され権力に対する火のような憎悪を抱いていたのだ。やがて、この計画に4名の男たちが加わる。
菅野須賀子の計画を探知した内務官僚は、これを絶好のチャンスと見て計24名の社会主義者を逮捕した。首領を幸徳秋水と言うことにして、彼が上京する途中で立ち寄った主義者をことごとく共犯者に仕立て上げたのである。そして12名が死刑、12名が無期懲役になる。もし、この時赤旗事件で獄中にいなかったら、堺をはじめ山川・大杉・荒畑らも共犯ということにされて処刑されたにちがいなかった。だから、大杉は出獄後に「春三月 縊(くび)り残され 花に舞う」という句を作るのである。
大逆事件の後、社会主義運動は火が消えたようになる。「社会」と名の付く印刷物はすべて出版禁止になり、「昆虫社会」という生物学の本さへ刊行が許されなかった。
赤旗事件の被告の多くは文筆業で食っていたから、出獄すると寄稿先がなくなってたちまちお手上げになった。山川均は、「このころ原稿を書いてともかくも原稿料のとれるのは、才人の大杉だけだった。大杉君は文壇人のあいだにも交友があり、<新小説>の編集主任をやっていた田中純氏などもその一人だった」と語っている。
堺利彦は、食うに困っている同志のために「売文社」を作り、広告の文案作製から卒業論文の代作まで、何でも引き受ける文章製造会社を立ち上げた。大杉は荒畑寒村と語らって、これとは別に「近代思想」を創刊する。これは政治関係の論文を載せると発行禁止になるので、掲載記事を小説やエッセーにしぼった文芸雑誌だった。
「近代思想」は、成功した。
雑誌は文壇や論壇の注目を集め、著名の作家や批評家がつぎつぎに同誌に寄稿するようになる。大杉が評論家として確固とした地位をしめるようになるのも、同誌に発表したエッセーや論文のためだった。
大杉の発表する文章は、どれも長くはない。けれども、いづれも力感に溢れていた。
僕は精神が好きだ。しかしその精神が理論化されると大がいは厭になる。理論化という行程の間に、多くは社会的現実との調和、事大的妥協があるからだ。まやかしがあるからだ。精神そのままの思想はまれだ。精神そのままの行為はなおさらまれだ。生れたままの精神そのものすらまれだ。……
僕の一番好きなのは人間の盲目的行為だ。精神そのままの爆発だ。(「僕は精神が好きだ」)
これは未だ加工されない生まれたままの精神へのあこがれを記した小論だが、大杉の発表するすべての文章から生命の純粋状態を希求するこの種の発言を読み取ることが出来る。彼は思慮分別によって汚染されない生まれたままの欲望を肯定する。感情も本能も、発生直後の初期段階のものだけに価値がある。
社会的な圧力によって押しつぶされている純粋状態の生を助け起こすなら、人は「人類」と繋がることが出来る。個人の生は、それが純粋である限り、人類の生にほかならぬ。
僕の生のこの充実は、また同時に僕の生の拡充である。そしてまた同時に、人類の生の拡充である。僕は僕の生の活動の中に、人類の生の活動を見る(「生の拡充」)
社会圧から解放されて自己の生を実現したいという欲求において、人類は一つに繋がる。人類が国境を越えて団結しうるのは、これあるが故なのだ。大杉はこうした立場から、コミンテルン式インターナショナル運動を拒否する。
では、生まれたままの精神に復帰するためにはどうしたらいいか。
人類につながる生命の純粋状態を、いかにして復原すべきか。
「自我の棄脱」によってであると、大杉は言う。
兵隊のあとについて歩いてゆく。ひとりでに足並が兵隊のそれと揃う。
兵隊の足並は、もとよりそれ自身無意識的なのであるが、われわれの足並をそれと揃わすように強制する。それに逆らうにはほとんど不断の努力を要する。しかもこの努力がやがてはばかはかしい無駄骨折りのように思えてくる。そしてついにわれわれは、強制された足並を自分の本来の足並だと思うようになる(「自我の棄脱」)。
征服者や支配者は、民衆のこうした錯覚を利用する。その結果、人々は作り物の感情を本来の感情だと思いこむようになった。
人間本来の感情を、その各個人の利害のために発達させないで主として征服者の利害のために屈折させた。そして数万年間のこの屈折の歴史は、ついにわれわれをして今日われわれの所有するほとんどすべての感情を、人間本来のものと思わしめるまでにいたった(「自我の棄脱」)。
作り物の感情から抜け出て、本来の感情、ほんとうの自分に立ち返るには、自我を棄脱して行かねばならない、自分がゼロになるまで。
かくしてわれわれは、われわれの生理状態から心理状態にいたるすべての上に、われわれがわわれわれ自身だと思っているすべての上に、さらに厳密な、ことに社会学的の、分析と解剖とを加えなくてはならぬ。そしていわゆる自我の皮を、自分そのものがゼロに帰するまで、一枚一枚棄脱してゆかなくてはならぬ。棄脱は更生である。そしてその棄脱の頻繁なほど、酷烈なほど、それだけその更生された生命は、いよいよ真実に、いよいよ偉大に近づいてゆく(「自我の棄脱」)。
そして彼は古い自我を脱ぎ捨てて生を拡充しようとしたら、反逆に向かわざるを得ないという。「生の拡充」イコール「反逆」だと断定する。美は東洋的な調和と安定の中にあるのではない。人が乱調と非難し、無秩序として否定するところにこそ、真の美がある。自然美は、無秩序状態のうえに成立しているではないか。
美はただ乱調にある。諧調は偽りである。真はただ乱調にある。
今や生の拡充はただ反逆によってのみ達せられる。新生活の創造、新社会の創造はただ反逆によるのみである。(「生の拡充」)
時代は日露戦争が終わり、人々が忠君愛国の呪縛から解放された頃だった。大逆事件の悪夢も薄れて国民は、自我を回復してのびのび生きようと願っていた。だから、大杉の溌剌とした議論は歓迎され、彼は論壇の輝けるスターになったのである。
「近代思想」誌の売れ行きは好調で、経営的にも安定していたから、大杉と荒畑がこの雑誌を拠点に活動をつづけたら社会主義の普及に貢献するところ大だったに違いない。ところが、大杉は知識人を対象にした雑誌を刊行しつづけることを、「知的手淫」に過ぎないとして、刊行2年で「近代思想」を廃刊にしてしまうのだ。
大杉の年譜を追っていくと、彼の生活が2年を周期に転換していることに気づく。中学校に在学したのも2年、幼年学校にも2年、クリスチャンだった期間が2年、「近代思想」に依拠していた期間が2年、そして次に葉山日蔭茶屋で重傷を負うまでの期間が約2年である。
彼は安定することを拒否していた。原点に返って生まれたままの姿に戻ろうとするたえざる衝動が、大杉を一カ所に停滞させなかったのだ。
「近代思想」を廃刊した翌月に大杉は労働者向けの月刊「平民新聞」を刊行するが、毎号発売禁止がつづき、半年後には廃刊に追い込まれている。その一年半後に「近代思想」を復刊して再起を図るが、これも発売禁止がつづき半年ともたずに廃刊になる。新しく雑誌を刊行するには、当局に保証金を払わなければならず、雑誌を刷るにも金がかかる。雑誌が発売禁止になり、そして廃刊せざるをえなくなれば、これまでにかかった費用が全部フイになってしまうのである。
大杉は翻訳をしたり原稿を書いたりして金を捻出し、それで雑誌を出版しては官憲によって廃刊に追い込まれ、投資した資金をゼロにしてしまうということを繰り返しながら2年あまりを過ごしている。当局は雑誌を発売禁止にするだけでなく罰金も課したから、この時期の彼は毎日借金に追われていた。
悪戦苦闘する大杉に手をさしのべてくれるのは、やはり、女性だった。彼の前に神近市子、伊藤野枝という二人の女があらわれたのである。
大杉は発禁つづきの雑誌を刊行する傍ら、「サンジカリズム研究会」「仏蘭西文学研究会」「仏蘭西語講習会」などを開いていた。神近市子はフランス語講習会を通じて大杉と親しくなったとされている。だが、大杉に会ったのは東京日日新聞の記者をしていた神近が、大杉の談話を取ろうとしてその借家を訪ねたのが最初だった。
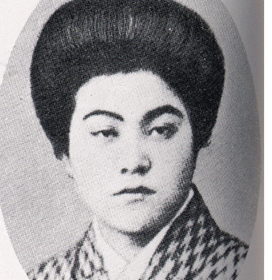 当時の神近市子
当時の神近市子 後年の神近市子
後年の神近市子神近市子は長崎のミッションスクールに学んで、洗礼を受けている。しかし彼女は激しい性格の持ち主で、学校では授業放棄の首謀者になり、意に添わぬ婚約を親から押しつけられると家を飛び出して東京に出ている。上京して津田塾に入学した神近は、平塚らいてうの「青鞜社」に参加して学校の不興を買い、弘前の女学校の英語教師にとばされ、田舎暮らしを強いられる。その女学校からも「青鞜社」のメンバーであるという理由で追い出された彼女は、帰京して東京日日新聞の記者になったのである。
平塚らいてうは、神近が人に強い印象を与える女だったと言っている。
その顔もやはり人につよい印象を与えるものでした。全体としてかたく引きしまった男性的な感じで、大きな目はたえず涙ぐんでいるような、異様な刺激的な光りをおび、なんとなく不安なような、恐ろしいような、危険性をひそめているようにも見えました。(「元始、女性は太陽であった」)
この印象は多くの人間に共通していたらしく、神近の「赤くぬれた大きな口」に妖怪じみた迫力を感じた者もいるし、荒畑寒村などは彼女を一目見て「あれは肉を抱いて餓虎に投ずるようなものだよ」と言っている。この意味はハッキリしないけれども、神近のような女に近づくのは、セックスに飢えた虎に食われに行くようなものだという意味なのだろう。
神近が大杉の借家を訪ねたとき、彼は妻の保子と共にコタツに当たって原稿を書いていた。神近には、大杉が「坊やくさい感じで、保子夫人の弟のように見えた」という。
その後、神近は大杉が主宰する研究会に顔を出すようになり、次第にアナーキストたちに馴染んでいった。そして程なく彼女は大杉と深い関係になるのだ。当時の大杉は「いっぺん会えば、どんな女でも参ってしまう」と噂されるような魅力をそなえていた。きだ・みのるは、女たちに囲まれている大杉を見て「ハレムの親分のようだ」という感想を漏らしている。
大杉は神近からは経済的な援助を受け、伊藤野枝からは発禁になった雑誌の隠匿などで協力して貰っている。大杉と女たちの関係については、次章で詳しく述べたい。(つづく)