未来人
大杉栄の「自叙伝」は、とにかく面白い本だ。
私はこれまでにいろいろな本を人に勧めてきたが、こちらの好みに偏りがあるせいか、相手から「面白かった」という返事を聞いたことはほとんどない。唯一の例外が大杉の自伝で、これを読んだ者は異口同音に「面白かった」「痛快だった」という感想を返してよこす。そして、以後、たいてい大杉栄を好きになり、彼のファンになったりするのである。
大杉栄は、関東大震災のどさくさ紛れに、妻や甥と一緒に憲兵隊で虐殺されたアナーキストである。そういう最期を遂げた男の自伝だから、きっと陰惨な内容の本だろうと思うかもしれない。しかし、それが全く逆なのだ。
彼は軍人の家庭に生まれ、腕白坊主として少年時代を過ごし、陸軍幼年学校に入学している。だが、校内で仲間と決闘をして退学になり、その後、上京して社会主義者になる。政府の弾圧を受けて、刑務所を出たり入ったりしているうちに反権力のスターになり、妻のほかに愛人二人を持つにいたる。そして「情婦」の一人から短刀で首を刺されて重傷を負うという羽目になる──とまあ、概略こうしたことが書かれているのである。
政府の弾圧に抗してたたかうというのは、プロレタリア文学がおはこにして来たテーマだし、女性をめぐる三角関係四角関係の果てに首を刺されるなどというのは自然主義文学が好んで取り上げそうな事件である。だが、彼の自伝には、プロレタリア文学に共通する被害者意識もなければ、自然主義文学のもつ陰湿な感じもない。
社会主義者になるまでの前半の記述には、漱石の「坊っちゃん」を思わせる爽快な躍動感があり、官憲との闘争記録や獄中生活に関する記述には、おそれを知らない若者の闊達な行動が描かれている。女に首を刺される前後の描写も臨場感に溢れている。
彼は自分に不利なことでも何でも、すべてをあけすけに書くのである。
通例、こうした書き方をすると、いい気な居直りや野卑な暴露趣味が表面に出て不快な印象を与えるものだが、大杉の自伝には、不思議と品の良さがあってすらすらと抵抗感なく読める。
そして、何よりもすばらしいのは大杉の文章なのだ。エッセーでも自伝でも、彼の文章には何時の時代にも通用する本質的な新しさがある。現代人の目からすると、明治・大正期に書かれた文章には、どうしようもない古さがある。凡庸な著作家にとっては、時間が一番の大敵なのである。現在、われわれが目にしている文章の多くも、50年もすればきっと古びて誰からも見向きされなくなるにちがいない。
しかし、大杉の文章はどんな時代になっても古びることはない。そう思わせる新しさを持っているのである。
大杉の文章を読めば、誰でも彼が好きになるのだが、これは文体による効果だけなのだろうか。同時代の人々にも、彼は愛されていたのだろうか。大杉よりも数才年長の山川均は、大杉のことを「年齢以外のすべての点で、私より遙かにおとなであり、先輩であった」と褒めている。
大杉君ほど遠目に見ている者からはこわがられ、近づいた人からしたしまれた人はない。大杉君には強い性格のどこかに、大きな魅力があった。そしてひとたびこの力にふれた人々は、時には大杉君に不平や不満をいいつつも、結局は大杉君を離れまいとした。先ごろある新聞の記事に、大杉君は借り倒しの名人だったというようなことが書いてあった。なるほど大杉君は、よく原稿料や印税のさき借りをしておった。しかし大杉君に借り倒された人で、ほんとに大杉君を恨んでいる人はないだろう。いちど大杉君に借り倒された人は、ぶつぶついいながらも、その実もっと借り倒されたい気もちがしたらしい。
大杉君には、そういう一種の徳が備わっていた。大杉君の性格には、それほど人をひきつけ、それほど人をしたしませるところがあった。あれほどの剛情張りで、あれほど人を人とも思わぬ態度で、あれほどいいたい放題をいい、したい放題をし、あれほど我を押し通して、しかもあれほど人を怒らせず、あれほど人からしたしまれた人はない。(『山川均自伝』)
アナ・ボル論争で大杉と厳しく対立した山川均のことだから、大杉のすべてを肯定していたわけではない。「大杉君は、『多数決』が大嫌いだった。これは、彼の理論からきたように、おそらく彼の性格からもきていた。大杉君はいろいろの意味において、『非凡』であった」と述べて、大杉の非妥協的な態度を暗に批判している。
しかし、彼の思想的立場が終始一貫してぶれなかったからこそ、彼は固い結束を示す「大杉一派」のリーダーたり得たのだ。山川は、大杉の周囲にはいつでも彼に傾倒する一団の同志が集まり、彼はその中心でまぶしく輝いていたと回想する。
大杉君はいつでもその周囲に、自分自身の雰囲気をつくり、それにとりまかれていた。それは彼を大きくし、光を強くした。と同時に、それはまた彼をしてこの雰囲気のうちにのみ回転し、そして自分自身の軌道をのみ走る慧星たらしめた。
大杉と政治的に対立した近藤栄蔵も、はじめて彼の主宰する研究会に出席したときの印象を次のように述べて、賛辞を呈している。
大杉の指導ぶりにも、私はこの会議の席で惚れた。彼は他の同志たちの言うことを黙って心棒よく聴いている、そして自分の意見を出す時には、相談をかけるような口調で、或は暗示的にそれを持出す。彼が命令的に自己の主張を押しっけた場合を私は、その後とも知らない。にも拘らず彼の主張は、彼の同志の間で大概通っている。
彼は結果において独裁者だったが、その独裁の過程は、ほとんど女性的とさえいえる柔かい言葉と、思いやりの深い仕草で常に包まれていた。彼は驚くべき外交家といえば外交家であり、指導者として観れば天才的指導者であった。
私は彼と識り合いになってから僅か一年たらずで、主義上敵の地位にまわって、心ならずも彼を裏切らねばならぬことになり、近藤は「ゴマの蝿」だと彼から罵られたが、それでも私はちっとも腹は立たぬばかりか、彼から罵られて却って嬉しい気がすることほど左様に、私は彼に惚れた。
私が識り合った日本の全ての社会運動者のうち、彼に比較しうる人物は、残
念ながら一人もない。彼が甘粕に殺された仇打ちを、死を賭して敢行せんとした同志が三人も現われた事実が、彼の人格の何よりの保証づけだ。大杉栄
これ以外にも大杉を讃える回想記は数多いのだが、学生時代の私は大杉に好意を感じながらも、どうも彼は過大評価されすぎているのではないかと思っていた。
大杉の結核(妻の堀保子から感染したといわれている)は、かなり進行していて、甘粕憲兵大尉に殺されなくても余命僅かだった思われる(堀保子も、大杉の死後間もなく結核のため死んでいる)。私は大杉がああした無惨な死に方ではなく、家族に看取られながら畳の上で大往生していたら、これほど注目されなかったのではないかと疑ったのである。
それより何より、マルクス主義の本になれ親しんでいた当時の私は、大杉のアナーキズム理論そのものを滑稽だと思っていた。
わが國における無政府主義運動は、明治39年にアメリカから帰朝した幸徳秋水が神田錦輝館の歓迎演説会で「世界革命運動の潮流」という演説をしたことからはじまった。荒畑寒村は「当夜の演説は幸徳氏一代の名演説というべきもので、聴衆に深甚な感銘を与えたばかりでなく、後に日本の社会主義運動に一局面を開いたいわゆる直接行動論の骨格が、この時すでに明示されていた」と言っている。
「直接行動」とは、テロや暴動を意味するのではない。労働組合のゼネストによって革命を実現しようとする理論なのだ。それを何故「直接」と言うかといえば、これと対になる「間接行動」というべきものがあったからで、議会に左翼議員を送り込んで政権を奪取する議会主義が「間接行動」と位置づけられるのである。
幸徳の記念碑的な演説以来、大杉らはこぞって直接行動論者になったが、山川均によれば、その理由は「革命を遂行するためではなく自分がよりより革命的であることを実証する」ためだった。
しかし、「直接行動論」を支持し、アナーキズムに傾斜した主義者たちも、ロシア革命が成功すると相継いでマルクス主義に転向する。そして知名の社会主義者でアナーキズムの孤塁を守るのは大杉栄一人だけということになってしまう。
以前の同志から、共同戦線に加わるように説得されても大杉はこれを頑として拒否する。そして、固い友情で結ばれていた山川均や荒畑寒村に向かって「山カン均、おなじく菊栄、バタバタキャンソン」と悪たれ口をきくのだ。
僕は今、日本のボルシェビキの連中を、例えば山川にしろ、堺にしろ、伊井敬にしろ、荒畑にしろ、皆ゴマノハイのような奴らだと心得ている。ゴマノハイなどとの協同は真っ平御免蒙る。
だが、マルクス主義の精密に組み立てられた革命理論に比べると、大杉の無政府主義理論は、たんなる思いつきにも見え、感情論にすぎないようにも見える。
マルクス主義は、社会が定められた発展段階を経て、最後に共産主義社会に到達するとする必然史観に立っている。革命のための戦略戦術も、社会の発展段階に応じて違ってくる。日本のマルクス主義経済学者が講座派と労農派に別れ、日本経済がいかなる発展段階にあるかについて熾烈な論戦を交わしたのも、それが戦略問題に直結していたからだった。
ところが大杉は、マルクス主義の必然史観も、経済の発展段階理論も信じなかった。
社会は、段階を踏んで時計仕掛けの機械のように進化発展するのではない。むしろ、突然変異する生命体のように、予測できないときと場所で不意に変化する。革命が何時いかなる時点で成就するか、誰も予測できないのだ。大杉はこうした観点から、必然史観に対抗して蓋然史観を展開する。
大杉は、また、マルクス主義が権力に対抗するには組織しかないとして、中央集権的な組織作りに熱中することを批判する。
組織を作り、戦略を練り、万全の体制を整えてから行動に移ろうとしたら、時期を逸してしまう。チャンスと見たら、即座に行動に移るべきなのだ。労働組合を横につなげて連合体を作り、ゼネストに打って出れば革命は成功する。
マルクス主義者は、とにもかくにも組織を作ることを優先させる。そして労働者が解放され、自由な人間として行動するようになるのは、革命が成功してからだと考える。つまり、社会革命の後に人間革命がくると考えるのである。だから、ロシア革命に際して、ボルシェビキが他派を弾圧して独裁体制を作っても、マルクス主義者たちは黙っていた。
しかし大杉は、猛然とロシア革命に反対した。ロシア革命は、ブルジョアの支配に代えて共産党の支配をもたらしたにすぎない。社会革命のあとに人間革命が来るのではない。人間革命と社会革命は同時進行的に実行さるべきなのだ。労働者が解放され自由になれば、その自由な生き方そのものが既成社会を崩壊させるのである。
こういう大杉栄の言い分をマルクス主義の整然とした理論体系の前に置いてみると、なんともお粗末に見えるのだ。彼は計画的な行動を軽視して、即興的な行動、単純直截な行動を推奨する。そして論敵から、「そんなものは感情論だ」と攻撃されると、「感情論で何が悪い」と反駁する。彼は理性より内部生命につながる本能や感情の方を高く評価していたのだ。
大杉栄が惨殺され、「大杉一派」が姿を消してから、わが國のアナーキズムは社会的な影響力を完全に失ってしまった。
私がこの目で見たアナーキストは、新宿駅構内で無政府主義の機関紙を売っている一人の若者だけというありさまなのだ。敗戦後のある日、国鉄の電車で新宿駅に降りたら、小田急の乗り場でその若者が無政府主義の機関紙を立ち売りしていた。彼は新聞が売れようと売れまいと意に介しないというような表情で、新聞を載せた台を首からつるし、無言でその場に立っていた。そのニヒルにも見え、超然としたようにも見える男の立ち姿が、私にはアナーキズムそのものを象徴しているように思えたのだった。
それから60年近くたった今、私はアナーキズム特に大杉栄を再評価する時期が来ていると考えるのである。私たちは大杉栄の墓前に花束を捧げるべきではなかろうか。
彼が憎んだソ連は崩壊した。そして、中央集権的な組織に代えるに自由連合をもってする大杉の主張は、NPOや住民運動、あるいは選挙における「勝手連」などによって現実のものになりつつある。
大杉は、何よりも個人の発意を重視した。革命運動というものは個人の発意をほりおこすことから出発すべきものと考えていた。自覚した個人が、同じく覚醒した別の個人と自由に結びついて連合する。そうした連合がいくつも寄り集まり、横に拡がれば、政府を倒すエネルギーになる。
大杉のこうした楽観的な見通しは、彼が日本の社会を民衆の奴隷根性によって支えられている脆弱な組織体と見るところから来ていた。大逆事件のあとに書かれた彼の「奴隷根性論」は、明らかに日本の天皇制を意識したものだった。
未開社会においては種族間の戦いに勝った方が支配者になり、負けた方は全員が奴隷にされる。奴隷は支配グループの首長の前に出るときには四つん這いになり、犬のポーズをとって低頭しなければならない。
野蛮人のこの四這い的奴隷根性を生んだのは、もとより主人に対する奴隷の恐怖であった。けれどもやがてこの恐怖心に、さらに他の道徳的要素が加わってきた。すなわち馴れるにしたがってだんだんこの四這い的行為が苦痛でなくなって、かえってそこにある愉快を見いだすようになり、ついに宗教的崇拝ともいうべき尊敬の念に変わってしまった(「奴隷根性論」)
犬のポーズは、犬のモラルを生み、ついには「臣下は酋長のために死ぬことを至上の義務」と心得るようになる。これにつづけて彼の言いたかったのは、「国民はやがて死んで靖国神社にまつられることを至上の名誉と考えるようになる」ということだったろう。
彼は日本的順応主義が奴隷道徳や犬のモラルを生んでいるのだから、日本人が順応主義を棄て、奴隷道徳やそれに基づく古くさい習俗を葬り去れば新しい時代が到来すると考えた。彼が願っていたのは、本来的人間の回復ということであり、人が本当の人間になることだった。彼がアナーキストになったのはこの目的を達成するために有効だったからにすぎない。大杉は、人が一念発起して本当の自分に立ち返えれば、即座に革命は成ると信じていた。そして、この点が「大杉の唯心主義」として以前の同志から批判されるところになったのである。
大杉栄は、すこし早く生まれすぎたのだった。
日本人が個人の発意に基づいて「勝手連」やNPOを作って横に連合するようになるためには、敗戦とその後に来る戦後民主主義を待たねばならなかった。敗戦というようなショック療法なしに、一国の内部に自由連合運動がうまれるためには、国民の生活水準が一定のレベルを越えなければならない。
だが、当時の日本は、あまりにも貧しすぎたのである。
荒畑寒村は、刑務所で耳にした受刑者と役人の問答を「寒村自伝」の中に書き留めている。
衝立を隔てて私の隣で一人の囚人を調べていた看守長は、吃驚したような声を立てた。
『母親の名を知らないって? じや、お前は自分のオッカさんをいつもなんて呼んでいたんだ?』
『オッカア、オッカアって、いっていました。』
『お前、女房の名は知っているか?』
『へい、知っています。』
高村光太郎は「無政府社会なんて、地球が冷たくなる頃でなければ実現しないよ」と予言している。その頃、多少とも「教育のある人間」は、例外なくこうした感想を持っていたのだ。にもかかわらず、大杉は無政府主義社会の到来を信じて疑わなかった。
彼の楽観主義は、彼が日本の古い道徳や習俗を激しく憎み、憎んだだけでなく周囲の目には一種のアウトローとして映るような型破りの生き方をしたことからきている。彼は無政府社会を仮想的に生きる人間として行動してみて、それが大変気持ちがいいものであることを発見した。こんな気持ちのいい生き方を可能にする無政府社会が、早晩、出現しないはずはないのだ。
習俗に抵抗した彼の生き方は、中江兆民を思わせる。
兆民は弟子たちに自分を君づけで呼ばせたが、大杉は指導者格の先輩堺利彦や幸徳秋水を平気で君づけで呼んでいる。
大杉は、「権威にはそれがどのような種類のものであっても批判し反抗しなければならぬ」と考えていたから、彼の批判を免れる聖域のようなものはどこにもなかった。彼は「社会主義に限ってどうして権威を認めなければならないのか」として、内外の社会主義理論家に忌憚のない批判をぶっつけた。彼は自分が世話になっている先輩たちも批判の俎上に乗せた。その結果、堺や山川均などに「無政府主義についての理解は、(師匠である)幸徳秋水より(弟子である)大杉の方が深い」と言わせるようになっている。
中江兆民は、仰々しい名前を嫌って自分の子供に干支にちなんだ名前を付けた。息子には丑年生まれだから丑吉、自宅に引き取って扶養することになった弟の娘は申年だったから猿吉という名前を付けたのだ。大杉は長女が生まれたときに、「魔子」と命名している。世間から悪魔と呼ばれている大杉栄の子だからという理由だ。
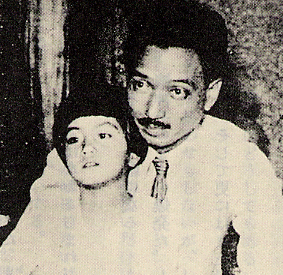 大杉栄と魔子
大杉栄と魔子こういう男が、世間並みの礼儀作法を守るはずはない。
大杉の不作法な食事の仕方については、多くの証言があるし、佐藤春夫は「大杉はろくすっぽ世間並みのあいさつができなかった」と言っている。
彼に対する不満は同志の間からも出ていた。「大杉の態度は不遜であり、人を人とも思わぬ」というのである。しかし、これらはシャイだった彼が、その弱気を隠す偽装につかっていたという面もあった。
だが、次のような行為には、世俗に対する彼の本気の挑戦が感じられる。
彼は堀保子と結婚しても役所に届けを出さなかったし、伊藤野枝と一緒になったときも入籍しなかった。従って、野枝との間に出来た子供たちはみな無籍児になっている。彼は男尊女卑の社会への抵抗として夫婦別姓を実践し、日本の戸籍制度を否定するためにあえてわが子を無籍児にしたのである。
その時分、裁判所では検事の論告中、被告は起立していなければならなかったが、一審でも二審でも大杉は坐ったままでいた。そのため、彼はこれを咎められて二審で一審より重い刑を科せられたりしている。たが、彼は平然として起立を拒み、とうとう裁判所にそれを認めさせてしまった。また、彼は裁判所内で禁制の団扇を使い、刑務所に移されてからは、禁則を恐れずに「わがまま」に行動した。
彼の「わがまま」については、同志だった和田久太郎の証言がある。
大杉はわがまま者だったが、また、他のわがままも喜んで受ける男だった。その持論は「お互いがうんとわがままになればいいんだ。そして、その上でお互いが腹の底をぶちまけて自由に話し合えば、直当に正しい理解をみんなが持つようになるんだ。そこから自由で愉快な社会が出来上がるんだ」というものだった。
そのわがままな大杉が、演説について次のような意見を述べて賀川豊彦を感心させている。
演説も会話的でなくてはいかん。一人が一時間も二時間も一本調子でしゃべるのは専制的だ。聴衆と講演者が合議的に話すのが真のデモクラチックなやり方だ。
大杉栄のこうした常識を超える斬新な行動を数え上げて行けばキリがないが、一見、破天荒に見える彼の行動も現代社会に置き直し、さらに来るべき未来社会に置き直せばちゃんと筋の通ったものになる。彼の文章は何時の時代にも通用する新しさをそなえていた。同様に、彼の日々の言動も何時の時代にも通用するまっとうなものだったのである。
彼は未来から来た人間だった。
こういう人間が、どうして明治18年という時代に生まれてきたのだろうか。
彼の「自叙伝」をたどりながら、これからその辺のところを探ってみたいと思う(つづく)