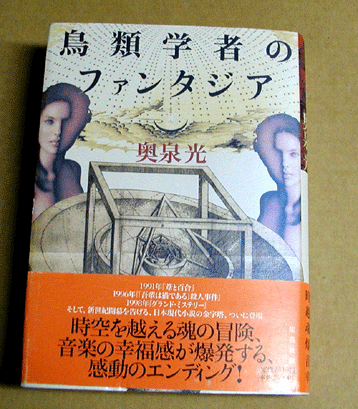
インターネット通販で「鳥類学者のファンタジア」(奥泉光)を注文したときには、著者から鳥に関する幅広い調査結果を聞かせてもらえるものと思っていた。何しろ、奥泉光という作家は、これまでずっと万全の調査の上に立った情報量豊富な小説を書いてきたからだ。
ところが読んでみると、私が期待した野鳥の話などは全く出てこない。
この小説は、ジャズ喫茶で働いている女性ピアニストをヒロインにしている。こちらはジャズには不案内の上に、このピアニストは、第二次世界大戦中にドイツで行方不明になった祖母を捜しているうちにタイムスリップすることになっている。こういう話も、私の苦手とするところだった。
そうと知っていたら、この本を注文しなかったのだが、とにもかくにも読み始め、いつの間にか全編を読み終えた。雑誌「すばる」に22回にわたって連載されたという長編だから、読了するまでに相当時間はかかったけれど、失望はしなかった。話の本筋とはあまり関係のなそうな二つのエピソードに刺激されて、こちらの眠っていた頭が急に目を覚ましたからだ。
私を刺激した最初のエピソードは、ヒロインが「柱の陰の聞き手」を意識しながらピアノを弾くというものである。
ジャズ喫茶に集まる客たちは、かならずしもいい聞き手とはいえない。
だからピアノを弾いていて、客の反応に失望して意気阻喪してしまうことも多い。が、柱の陰に、優れた耳を備えた聞き手がかくれていると想像すると、気分が乗って演奏に集中できる。それで、ヒロインは、何時でも柱の陰にいる聞き手を意識しながらピアノを弾いているのである。
(なるほど、そういうものかな)と私は思った。
これはステージで演奏する音楽家に限らないだろう。世の著作家たちも、頭の中に鑑識眼を備えた優秀な読者を想定し、それに向けて原稿を書いているに違いない。
確かにそうなのだ、目に見えない優秀な聴衆や読者を想定するかどうかで、理想主義者と大衆迎合家の差が出てくる。目前の聴衆や読者を満足させることを主眼にすれば、結局相手にそのレベル以下のものを与えることになる。小泉首相は国民を幾分馬鹿にしているから、やたらに大見得を切ってみせるのであるし、小学校教師のあるものは、生徒を軽く見ているから、教壇で大げさにおどけて見せるのである。
猥雑な「当面社会」と向かい合いながら、それを超えた不可視の高い世界を目指さなければならない。そうしなければ、表現者としては失格する。いや、表現者ばかりではない。われわれ市井の人間も「柱の陰の聞き手」を頭に置いていないと、とめどもなく堕落していく。
第二は、「宇宙オルガン」のエピソードである。
タイム・トリップして敗戦間近のナチス・ドイツに飛んだヒロインは、そこで探し求めていた祖母に出会う。祖母の周辺にいるさまざまな人間と交渉しているうちに彼女は、地球を抜け出て宇宙の深淵に達するという神秘的な体験をして、そこで宇宙オルガンの調べを聞くのだ。
そして彼女は、宇宙の中に音楽があるのではなくて、音楽の中に宇宙があることを悟る。
・・・・・・これは、なかなか鮮やかなイメージ転換ではなかろうか。
宇宙が始まってから今日に至るまで、宇宙は無意志・無目的に運動しているという見方がある一方で、そのなかにある種の「宇宙意志」を読む見方がある。
この「宇宙意志」の内容には、宗教的なものから運命論的なものにいたるまで多くのバラエティーがあるのだが、宇宙の振る舞い、その挙動に倫理的なものを見るという点では各論者の立場は共通している。そして自然科学的な宇宙無目的論者が一番反発を感じるのも、この点なのである。ビッグバンに始まるこの混沌たる宇宙のどこに「意志」があるというのか。
しかし宇宙意志の代わりに宇宙オルガンを持ってくれば、無目的論者も少しは同調できるのではないだろうか。宇宙オルガンが奏でる音楽は、音に依存しない。膨張と縮小を繰り返す宇宙のリズム、星座の配列、流星の描く軌跡など、宇宙の動きのすべてが音楽なのだから。
われわれは、鳥の声・虫の声のほかにも、木々のざわめきや、小川のせせらぎに音楽を感じる。それだけではない、空を流れる雲や、朝焼け夕焼け、さらに四季の移り変わりそのものにも、音楽を感じる。確かに宇宙の中に音楽があるのではなく、音楽の中に宇宙があるのである。
・・・・宇宙オルガンという壮大なイメージを持ちだした著者が、「祈り」について触れているいるのは奇妙なことに思える。それは、書中の二カ所に出てくるにすぎないが、やや唐突な形で出現するため、読者の印象に残るのである。その一つをここに引用してみる。
「そうなのだ。覚えていること。それが大切なのだ。生きている者が 死者に対してできる唯一のことは、死んだ人を思い出すことであり 、それはつまり祈ることなのだ。」
現世利益を求めてする祈りは、真の祈りとはいえない。以前に正月のTVを見ていたら、神社への参拝 を済ませてきた中年の男が、「去年はいいことがなかった。だが、今年は1万円の賽銭を上げてきたから、きっといいことがあると思う」と真顔で語っていた。
真に祈る者は、自身の祈りが現世的幸福に役立たないこと、祈りには現実的な力が皆無であることを知っている。となれば、真に祈る人間の祈りは内容の点で、現世利益的な祈りとは違ったものになるはずである。神のために祈るか、衆生のために祈るか、個人を対象にして祈る場合でも、功利的な立場を離れた祈りになるはずだ。
祈ったところで何の効能もなく、こちらの思いは何処にも届きはしないとしたら、あとに残るのは祈る人間の思念だけである。事実、一心に祈っていると、相手の存在も自我意識も消えて、世界には自分の思念しか存在しないという気がしてくる。
著者が「死者を思い出すことは、祈ることだ」というのも、その思い出には現世利益願望などのよけいな添加物がなく、純粋に思念があるだけになるからであり、結果として
祈りに近くなるからだ。
さて、私はこれまで「柱の陰の聞き手」と「宇宙オルガン」のエピソードを紹介し、祈りについて触れてきたが、このバラバラな三つの部分をつなげて、なんらかの結論を導き出すことはできるだろうか。
無理を承知でこれらに脈絡をつけようとすれば、次のようなことになるのではないか。
演奏家や著作家が、自分を理解してくれる聴衆や読者を求める気持ちは切実である。だが、彼らが求めるような人間はどこにも存在しない。現実には存在しないことを承知で、しかもなお探し求めないではいられないから、この希求は祈りに似てくるのだ。
演奏家・著作家に限らず、見果てぬ夢を見ている人々は多い。この世は、こうした人たちの祈りに似た思念で埋め尽くされているかもしれない。
宇宙オルガンは、目に見えないもの、何処にもないものを希求する人間に癒しを与えるものなのだ。
宇宙オルガンの旋律は、耳で捕らえることができない。
この世にある物質や生き物が 織りなす構図や図形、それらの運動が視覚に与える残像、地上を彩る色彩のうつろいなどが、人の心を洗い、壮大な「音楽」を感じさせる。
この音楽は祈る人の耳には惻々として迫るけれど、「当面社会」しか見えない現実家の耳には届かない。
この世には、「求めるものは与えられ、悲しむものが慰めを得る」という聖書的な現実がある。これも人間が宇宙オルガンの下にあるからこそだと言ったら、独断のそしりを受けることになるだろうか。