1
どうした訳か、父の書架には直木三十五の本が何冊かあったので、私は中学生の頃から、それらの本を読んでいた。私が中学生の頃といえば、吉川英治の新聞小説「宮本武蔵」が読者を熱狂させていた頃で、昭和九年に没した直木三十五はすでに過去の人になっていた。だが、読んでみると直木の「南国太平記」はすばらしかった。私がこれまでに読んだ時代小説で、「南国太平記」に比肩できるのは、僅かに山本周五郎の「樅の木は残った」があるだけである。
時代小説というものは、いくら魅力のある武士や町人を登場させても、それだけでは薄手なものになってしまう。これが奥行きを備えた重厚な作品になるためには、主役の男女と平行して権力者像がリアルに描かれていなければならない。封建社会では、すべての人間が巨大な藩権力・封建権力の重圧下で生きていたからだ。
つまり、江戸時代を舞台にする作品だったら、大名や藩老職の意識と生活が実在感をもって描きこまれている必要がある。藩政トップの人間たちの老獪な政略と、無名の庶民の一途な生き方が表裏の関係で描かれていて、はじめて作品は深みのあるものになる。その点で「南国太平記」には、仙波小太郎や益満休之助とともに、薩摩藩の老職調所笑左右衛門や藩主、そして側室お由羅が確かな実在感をもって描かれていて、大人の鑑賞に堪える小説になっていた。
「南国太平記」のほかに、書架には直木原作の「源九郎義経」「荒木又右衛門」「黄門回国記」などがあったが、それらより面白かったのは雑文を集めた二冊の随想集だった。この二冊には作家たちを俎上に乗せたゴシップ記事がたくさん掲載されていて、これがとてつもなく面白かったのである。直木が次々に書きとばすゴシップ記事には辛辣なユーモアといったものがあり、これには菊池寛も心底から感嘆の声を放っている。
「あんなゴシップは、書けといっても誰も書けない。・・・・・あれは天才だよ」
戦後になると、直木三十五の名前は作品よりもその型破りな生活によって知られるようになる。生前の直木と交友のあった作家たちが、競って直木の放胆な日常を紹介するようになったからだ。それら数ある文章のうちで、広津和郎の実見した直木の借金取り撃退法が最もよく直木の面目を伝えている。
広津が直木に家を訪ねると、何時でも八畳間に何人もの借金取りがたむろしていた。
小さな庭の縁側から上って、障子を開けると、そこの八畳の真中に、大きな四角い火鉢があり、その火鉢を囲んで、いつでも三四人乃至五六人の男達が坐ってゐる。それはみんな債鬼なのである。印刷屋、紙屋、製本屋、かと思ふと、小間物屋、呉服屋 (銀座の越後屋) 等々々。その八畳の向うに何畳かの部屋があり、その部屋の奥に四畳半だか六畳だかの部屋が更にある。 直木はその一番奥の部屋に寝てゐる。而も大胆不敵なる彼は、此方の八畳に債鬼共を待たせながら、その八畳から彼の寝てゐる部屋まで、唐紙も障子も閉めさせずに、見通しにして、悠々と寝てゐるのである。唯彼の寝てゐる夜具のところだけ、屏風がまはしてある。
(中略)
債権者達は奥の方の屏風を眺め、時計を眺めしながら、彼の起きて来るのを、首を長くして待ってゐる。時々彼の細君に向って、「まだお起きにならないでせうか?」 と不平さうに云ふ。細君はにこにこしながら、「もうそろそろ起きるでせう。無理に起すと機嫌が悪うござんすから、もう少し待って下さい」 と云って、決して彼を起さうとしない。部屋は薄暗くなって来る。電燈がついて来る。「仕様がないな。ぢや明日まゐりますから」一人二人と、しびれを切らした債権者達は立ち始める。さうして債権者共がゐなくなつてしまふと、彼は悠然として、屏風の中から起き出し、「みんな帰ったか?」 とにこりともしないで細君に云ひながら、火鉢の側に来て坐り、「やあ」 と自分に云ふ。
中には頑強なのが一人二人、電燈がともっても執念深く帰らずにゐる事がある。直木は起きて来ると、別段債権者達が眼にも這入らないといふ平然とした顔をしながら、火鉢の側に坐り、煙草を喫ひ始める。「待たして気の毒だった」 などと無論云ひはしない。凡そ弁解めいた事は彼は口にするのが生来嫌ひらしい。
(中略)
債権者達は揉み手をしながら哀願する。彼は返事をしない。債権者達は今度は腹立ち声で威嚇的な事を云ふ。彼は同じ表情でやはり返事をしない。泣いても怒っても笑っても怒鳴っても返事をしない。
「植村さん(注・直木の実名)、それはあんまりだ。それぢや、一体どうしてくれるのです?」
最後に投げ出したやうに債権者が云ふ。
そこで始めて、彼は顔を上げて、彼独得のぼそぼそした低い声で、
「出来たら払ふ。今はない」 と同じ表情で云ふ。債権者達は泣きさうな顔をしながら、「ではよろしく御願ひします」 と云つて、撃退されて行く。
「うん」彼はうなづく。そして彼等が玄関口から出て行ってしまふと、彼はやはり同じぶっきら棒な表情で、自分の方を振向き、「広津、何処かに花でも引きに行かうか」
借金取りに対する態度と並んで、友人たちを驚かせたのは、直木の執筆速度だった。作家たちは普通、一日に400字詰め原稿用紙10枚程度書けばいい方なのだ。これを10日続ければ一ヶ月100枚になり、これで十分食って行けるのである。
ところが、直木は一時間で平均6枚から7枚半書いている。こうした速筆だから彼は、雑誌社・新聞社から執筆を頼まれれば、なんでも全部引きうけた。彼は文章を練るとか、書き上げた原稿を読み返すというようなことを一度もしたことがなかった。従って、その原稿には誤字や脱字がゴロゴロしていたが、彼は平然たるものだった。
文芸春秋の編集者が原稿の催促に行ったら、直木は「まあ、これでも吸っていてくれ」といってウエストミンスターの箱を渡し、編集者がタバコを一本吸い終わらないうちに雑文一編を流れるように書き上げたという。
直木はカリエスが重くなって入院したときにも、午前中30枚、午後30枚、夜30枚、合計一日に90枚の原稿を書く予定を立てている。こんなふうに無茶苦茶な執筆活動を続けたから、彼は43才の年齢で死ぬことになる。そうした彼を、当時の新聞雑誌は「斬り死に」と表現している。直木の生涯は、まさに白刃一本を振りかざして斬り込み、全身血まみれになって倒れるような一生だった。
私は若い頃から、日本が生んだ本格的なニヒリストは直木三十五と坂口安吾ではないか思っていた。それで、まとまった直木の評伝が出るのを心待ちにしていたのだが、今度、直木賞創設七十周年記念出版ということで、待望の直木三十五伝が出たのである。直木の甥・植村鞆音の著した「直木三十五伝」がそれである。
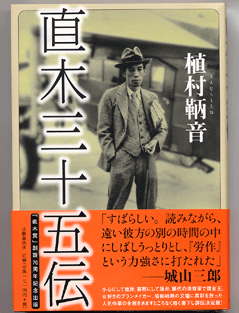
著者の植村鞆音は、直木の死後4年目に生まれているから、この本から近親者の証言のようなものを期待することはできない。著者は直木の弟だった父植村清二(歴史家)や直木の妻・愛人からの聞き書きを核として、その周辺に直木に関するさまざまな回想記を配しているだけである。
だから、これは直木三十五にかんする「神話」を集めた伝説集と見ることが出来る。私はこの本に集められた多くの「伝説」に依拠して、直木の生涯とそのニヒリズムについて概観するのである。
2
直木三十五のニヒリズムを調べるには、改めて彼の作品に目を通さなければならない。ところが手元には、彼の本が一冊もないのだ。私はこれまで小説本を主として古本屋から仕入れてきたが、直木の本を古本屋で見かけることはほとんどなかったからだ。
作品が手に入らないのだから、数ある直木伝説のうちから重要と思われるものを拾い出すしかない。そこで、まず私が注目したいのは、彼が酒を飲まないにもかかわらず、酒席を好んだというような話なのだ。
彼は誰もが認める無口な男だった。無口で、ぶっきらぼうで、無軌道で、ずぼらで、手が付けられないほど傲慢な男だった。だとすると、彼は人間嫌いで孤独癖の強い男だったろうと思うとさにあらず、人恋しくて菊池寛と共同出資で作った文芸春秋社倶楽部に住み込んでいたのである。
彼は、三階建ての倶楽部の最上階に愛人とともに居着いていた。そして、原稿を書くときには、わざわざ二階に下りてくるのだ。ところが、その二階は、作家や編集者のクラブであって、雑談するものあり、麻雀や将棋に興じるものありで、到底執筆できるような場所ではないのである。が、直木は作家らが議論している隣で、黙って原稿用紙を広げ、ペンを走らせていたのた。
酒席で酔った仲間が羽目を外して騒ぐのを、素面(しらふ)で眺め、倶楽部で作家らが白熱した議論を交わしている横でペンを走らせる──これは何とも不思議な才能といえる。
彼は内心で作家仲間を冷たく突き放して眺めながら、他方で彼らに同志愛的な友情を感じていた。だから、騒然たる座中にあって、一人自分の仕事に没入できたのである。彼は、仲間に同調することを拒みながら、彼らと共に生きることを求めていたのだ。仲間に対して抱く冷熱二つの対立する感情、直木はこれと同じ感情で、人生の万般に相対していたのである。
直木三十五は、大阪市南区内安堂寺町二丁目にある小さな古着屋の跡取り息子に生まれた。家は、三畳の店、三畳の茶の間、四畳半の奥の間からなり、とにかくちっぽけで暗い家だった。子供の間食といえば、焦げ飯で作った握り飯か、母が釜やお櫃の洗いのこりの飯粒を笊に入れて天日で干しておいたものだった。
直木自らが「桓武天皇以来の貧乏」と呼んでいるにもかかわらず、父の惣八は長男の直木も次男の植村清二も幼稚園に入れ、苦労して息子二人を旧制中学校・大学にやっている。惣八は、近隣で並ぶものない儒学者だった父八右衛門を尊敬していたから、しがない古着屋に落ちぶれても、せめて子供だけは学問のある人間に育てたかったのだ。
父の惣八は、大学に行くなら「商科か法科か医科がええ」といって、直木に岡山の旧制高校を受験するように勧めた。直木は親の手前、汽車に乗って岡山に出かけたが受験せず、岡山城下の旭川でボートを漕いで、何食わぬ顔で家に戻ってきた。そして一年浪人してから翌年に念願の早稲田大学に入学する。
彼が入学した英文学科予科は、生徒数僅か32人にすぎなかったけれども、呆れるほど「人材」がそろっていた。同期には木村毅、宮島新三郎、田中純、西条八十、青野季吉、細田源吉、細田民樹、保高徳蔵、鷲尾雨工、岩淵辰雄、谷口正春(「成長の家」の開祖)、坪田譲治などがいた。いずれも大正から昭和にかけてマスコミを賑わせた第一線級の文筆家たちで、一つのクラスからこれだけ多数の知名人を輩出した例は、後にも先にもない。まさに空前絶後の現象といってよかった。
極端に無口な直木は、教室で何時も一番背後の隅の席に座り、室内の級友を見渡しながら新聞や本を読んでいた。教場内でのこの位置取りは、その後の彼の生き方を象徴しているように思われる。
東京では、中学時代の親友藤堂杢三郎の下宿に転がり込んで、二人で共同生活を始めている。この二人の部屋に、間もなく、もう一人、年上の女性が転がり込んでくることになる。仏子寿満という27才になるこの女性は、直木らの中学時代の級友井上市次郎の叔母だった。直木は浪人中に井上の家に遊びに行って、彼女と顔見知りになっていた。
部屋に上がり込んだ仏子寿満は、しゃあしゃあとした顔で言った。
「ここに置いてもろていい?」
直木と藤堂は狼狽した。なにしろ相手は京町堀小町といわれた評判の美女である。
「しかし、寝るところはここしかないですが」
「ええわ。一緒に寝るわ」
こうして三人は、狭い部屋で川の字に寝ることになった。
仏子寿満は住職をしている兄と喧嘩をして寺を飛び出し、闇雲に上京してきたのである。直木は、しばらくすると彼女と結ばれ、早稲田下戸塚の二軒長屋を借りて、同棲することになる。
無収入の直木は、女と同棲するようになっても、実家からの20円余の仕送りだけで暮らさなければならなかった。仏子寿満は金回りのいい大寺で贅沢な暮らしになれていたから、葉書を一枚買って来てくれと言われると、「ハガキ一枚なんて買えますか」といって10枚買ってくるような女だった。二人はたちまち経済的に窮地に陥った。
問題は、それだけでなかった。
直木の借家には、大学の級友が次々に遊びに来て、猥談などをして行く。すると、放埒な寿満(すま)は平気で話に加わり、直木の前でわざと彼らといちゃついてみせるのである。そのうちに寿満は田中純と深い関係になった。冬のある日、直木が帰宅したら田中と寿満がコタツの同じ枠内にぴったりくっついて座っていた。二人の関係は級友たちの間でも、すぐ評判になった。
ある日、青野季吉は直木と連れだって散歩し、借家に戻って来た。直木は玄関の格子戸を開けて中に一歩踏み込んだものの、それきり棒立ちになってしまった。彼はくるりとくすびをかえして外に出てくると、青野に、「もう一度散歩しよう」と言ってすたすた歩き始めた。
青野がぐずぐずしていると、格子戸が開いて一人の友人(田中純)が出てきて逃げるように立ち去っていった。直木は青野が注意しても、そっちを振り向きもしなかった。直木の表情は少し曇っているように見えたが、ぐっと踏みこたえて平然としたポーズを崩さなかった。
青野は、「彼との永い交友で、私が常に感じていたことは、彼の中に非常に多くの要素があり、一個の人間としては破綻だらけであるにも拘わらず、芸術的にはそれが渾然と融和されていたことである」と書いている。
古着屋をやっている父の月収は、多いときでも6,70円しかなかった。その父に辞書を買うなどと嘘をいって追加の仕送りをむしり取る直木のやり方は、相手の肉をむさぼり食うに似た利己的な行為だった。だが、彼は級友に自分の女を奪われても黙って耐え続け、自分の肉を他人に食わせもしていたのである。彼は、平然と他人を利用する反面で、自分も他人の裏切りを許し、自虐と他虐をないまぜにした生き方をしていたのである。
直木の懐はいよいよ寂しくなり、大学の本科に入ってから授業料を払うことができなくなった。教師も同級生も、彼が授業料未納で学籍を失ったことを承知で、依然、彼が教室に出入りすることを許してくれた。
直木はこうして本科三年を過ごしたが、卒業証書を親に見せることが出来ない。苦肉の策として思いついたのが、卒業記念の写真に顔を出し、その写真を実家に送って卒業の証とすることだった。彼は写真撮影の現場に出かけ、青野季吉の協力を得て、そのとなりに滑り込んだ。彼はこの写真を実家に送り、親をだますことに成功している。
3
早稲田を出たものの、卒業免状を持たない直木に就職の口はなかった。
そこへ妻の寿満が、女の子を出産したから、夫婦の暮らしはどん底まで落ちた。直木は蔵書のすべてを売り払い、着物は質入れした。醤油で炊いただけの飯で、3,4日を過ごすような日々が続いた。
この頃、青野季吉が訪ねていったら、夫妻が長火鉢を挟んで所在なげに座っていた。見ていると、寿満の抱いていた猫がよろけるように膝から下り、庭に出て行ったと思うとつんのめるようにして後足を長く引いたまま動かなくなった。青野は書いている。
妻君は走り寄ってその死骸を抱きあげ、こんなにして死ぬやうだったら何故私達のところへ迷ひ込んで来たのかと、声を立てて泣いた。この小猫の死が、何か不運な自分だちの運命を暗示するものであるかのやうに、妻君には思ひなされたらしい。直木はと見ると、黙然と手を組んだまま妻君の悲歎を見てゐたが、次第に目がしらがうるんで来て、涙が鼻の脇をつたって落ちて釆た。それをべつにぬぐいもせず、ややあって僕の方を向いて、寂しく微笑した。
マスコミ関係に就職した級友たちは、直木の窮状に同情していろいろと就職口を持ってきてくれた。だが、直木が「お願いします」という言葉をどうしても言えなかったり、相手の私宅を訪ねて玄関の戸口から首だけ突っ込んで話をしたりするので、どれもものにならなかった。
そんなところへ読売新聞社に就職した保高徳蔵が、外勤の婦人記者の口があると知らせに来てくれたのだ。
「やります」と寿満は必死の面持ちで言った。
「でも、子供はどうします」
直木が言った、「子供は僕が育てる」
こうして縦のものを横にもしなかった直木が、寿満の留守を引き受けて、育児から炊事・洗濯に至るまで家事一切を担当することになった。昼になると、赤ん坊に授乳させるために直木は娘を抱いて京橋の読売新聞社まで出かけ、給料日の夕方にも妻を迎えに新聞社の前に姿を現した。
当時、編集長だった上司小剣は、白絣兵児帯姿の直木が柳の木陰で赤ん坊を抱いて立っているのを窓から見て、「さあ、行ってあげなさい」と寿満の早仕舞を許してくれた。
その後、直木が日本薬剤師会の書記になったり、美術記者になったり、転職を繰り返しているうちに、早稲田の級友が思わぬ計画を持ちこんできた。出資者がいるから一緒に出版社を立ち上げようではないかという話だった。
この話は順調に進み、出版社「春秋社」が発足した。直木は、これとは別に資産家の息子だった鷲尾雨工に出資させて春秋社の兄弟会社「冬夏社」を立ち上げさせた。鷲尾は、ニヒルな直木に惚れ込んで、まるで家来のように何でも彼の言いなりになっていた。「直木三十五伝」の著者植木鞆音は、鷲尾に一社をやらせておけば、いずれ直木が二社を牛耳るようになると計算していたのではないかと推測している。
宗一(注・直木)と鷲尾に共通しているのはヤマ気であった。二人とも安月給や安原稿料でこつこつ生きていこうなどという気はまるでない。とくに宗一は、そもそも作家になるよりも、出版社、美術商、芸術家の倶楽部、はては鉱山会社、材木会社など、事業を起こしてひと山当てようといつも考えていた。そして、こうした彼の事業欲は生涯続く(「直木三十五伝」)。
直木は資金を一文も出していなかったのに「春秋社」の創立者の一人として、月給を百五十円取ることになった。婦人記者をしていた寿満の月給が18円だったことを思うと、これがいかに高額だったか分かる。
当初、直木は月給に見合う貢献をしていた。彼の提唱で「トルストイ全集」を予約販売したら大成功をおさめ、暫くして再募集をしたらこれも当たったのである。
だが、出だしは好調だが、直ぐにダメになるのが直木の事業の特徴だった。会社が順風満帆だったのは僅かに半年間で、彼は社内の友人と衝突を繰り返し、挙げ句の果てに会社の金主とも対立するようになった。その責任は、すべて直木の側にあった。彼の公私混同が目に余るようになっていたからだ。
彼は集金のために関西に出張すると、仕事が済んでも10日、20日と逗留を続けて芸者遊びに明け暮れた。そして大阪の義大夫芸者豆枝(まめし)が気に入ると、彼女を東京に連れ帰り、一週間もの間、寿満と三人で一つの部屋に寝るというようなことをする。寿満は寿満で、会社に送られてきた金を着服したりした。
「春秋社」にいずらくなった直木は、「冬夏社」の仕事に専念することになったが、新たな企画「マーテルリンク全集」「ドストイエフ全集」「ツルゲニエフ全集」「ダヌンチオ全集」などはいづれも振るわず、「冬夏社」は急速に傾いていった。
田中純は、「冬夏社」の不振は直木らの浪費のためだと指摘している。「鷲尾家の財産を鷲尾と直木で飲みつぶし遊び尽くし」てゼロにしたというのだ。鷲尾が無一文になった時に、直木は冷然と鷲尾と袂を分かっている。
鷲尾と別れた直木は、吉井勇・久米正雄・田中純らの同人雑誌「人間」の経営にあたることになる。彼はこのほかにも6号で終わった海外文芸雑誌「主潮」を編集・発行したこともあり、この頃から彼と文壇人との付き合いが急に増えている。けれども、これは収入には全く繋がらなかった。増えるのは、借金ばかりだった。
植木鞆音は、直木の借金が急増した背景についてこう説明している。
前に、長女木の実の生れた頃の植村家を、「貧乏極点に達す」 と表現したが、当時の貧困はまだ赤字の高が知れていた。収入は少なかったが、支出もまた限られていた。しかし、大正十年から十二年九月の関東大震災にいたる三年間の植村家の家計は、借金の高が極めて大きい。宗一も寿満も、収入が激減したにも拘わらず春秋社時代に膨らんだ家計を一向に引き締めようとしなかったのである。
風呂好きの宗一のために、風呂は一日中沸かしっぱなしであった。着物は銀座の越後屋から、下駄ほ麹町の下駄屋から柾目の通った上等の桐下駄が始終届いていた。近くの丸梅から豪勢なおでんが届く。どこに出かけるのも車であった。二人だった女中が、いつの間にか三人になっていたりする。
先に引用した直木の「借金取り撃退術」は、この時期のものである。あの文章を書いた広津和郎と直木の交友も、広津が腹を立てて直木を訪ねたことから始まっている。広津が「人間」に書いた小説の原稿料として、直木は郵便振替を送ってきたが、それが不渡りだったので彼は直木のところに抗議に出かけたのだ。
ところが直木は、ちゃんと謝罪するどころか、ぶっきらぼうで、傲慢な態度で臨んできた。不思議なことに、広津はそういう相手が好きになってしまったのである。
翻訳家の妹尾アキ夫も、稿料をほとんど払ってもらえなかった。催促に出かけると、直木は財布から一円札を一、二枚出して、「今日はこれしかない」と言って渡した。妹尾が相手を恨む気にならなかったのは、その「ずぼらや無軌道には滑稽味があり、卑劣なことが爪の垢ほどもなかった」からだった。
再び広津和郎の証言を引用する。
つまり、借金取りがみんな直木に惚れたのである。やっと午過ぎになって起き出した彼と、無言の睨めっこをしてゐるうちに、同情と尊敬がまじり合ったような気持ちになるらしかった。
その結果、彼の腹心の参謀になって、債鬼撃退の役をひとりで引き受けるやうな男も出て来たほどであった。
菊池寛に言わせれば、「黙っているんで人がひっかかるんだね」ということになる。直木が雑誌社運営で四苦八苦しているときに、菊池寛はポケットマネーで「文藝春秋」を発刊し、見事に成功する。そして「文藝春秋」の成功は直木のお陰だといわれるほど、直木は同誌に貢献しているのだ。
直木は仲間から「天才的なプランメーカー」といわれるほど豊かな着想の持ち主だったが、自分でそれを軌道に乗せて行く忍耐力や実務能力に欠けていた。だが、菊池寛にはそれがあり、彼は直木の献策を入れて新しい企画を次々に成功させていったのである。
直木は菊池に知恵を授けるだけでなく、盛んに「文藝春秋」に雑文や随筆を書いた。文壇人を対象にした彼の辛辣極まるゴシップ記事は、「文藝春秋」の呼び物になった。彼は雑文を書いて雑誌の発行部数をのばしただけでなく、自らの存在を文壇に認知させることに成功したのだった。久米正雄は「大正十二、三年の文壇は直木のものであった」とまで言っている。
4
作家仲間とのつきあいが増えた直木は、富士見町の茶屋で酌に出てきた芸者の一人に惚れ込んだ。香西織恵というすらりとした細面の芸者だった。「好きな女は芸者だ」と公言する直木も、惚れた弱みで直ぐには相手に手が出せず、風呂に通う香西織恵を一目見ようとして、いやがる宇野浩二を誘って連日風呂屋の近くで待ち伏せした。織恵を座敷に呼んでも、女を前にして時々タバコをふかしながら黙然と坐っているだけだった。焦れてきたのは、女の方だった。織恵は「あなたが好きよ」と書いた紙片を直木に手渡し、直木はそれを財布の中に大事にしまっておいた。
織恵を完全にわがものにしてしまうと、彼は「俺の惚れた女を見せてやる」といって、妻の寿満を富士見町に連れて行った。こうして直木は、織恵を妻公認の愛人にしてしまった。
妻との間に新たに男の子が生まれ二人子持ちになった上に、愛人を持ったのだから、直木は経済的面でにっちもさっちもいかなくなった。こうした時に関東大震災が襲来したのである。
震災の直後に直木は、広津和郎に会うとめずらしくニコニコ顔を見せた。
「俺の家が焼ければしめたものだよ。全部のものが差し押さえられているんだから、焼けてしまえば、それで一切さっぱりするからね」
幸か不幸か、直木の家は焼失を免れた。けれども、彼はチャンス到来とばかり、わずかばかりの家財と山のような借金を東京に残して慌ただしく大阪に逃げ出した。抜かりのない直木は、愛人の織恵を一足先に大阪に向かわせていた。時に、彼は32才だった。
大阪に落ち着いた直木は、直ぐにプラトン社に就職している。
プラトン社は化粧品であてた中山太陽堂の出資した出版社で、「苦楽」という読み物雑誌を発刊する計画を立てていた。そこへ菊池寛・芥川龍之介・久米正雄など錚々たる作家たちの著作に関する業務一切を一任された直木が、そのお墨付きを持参して現れたのだから、一発で直木の採用が決まったのである。
「苦楽」の編集にあたる一方で、直木は自らも同誌に小説を発表し始めた。
彼はこれまで「文藝春秋」などに健筆を振るってきたが、それらはすべて雑文か評論で、小説を書いたことはなかったのである。
彼が怒濤のような勢いで小説を量産したのは、死ぬまでの僅か10年間に過ぎない。
それにしても、彼は多忙を極めた日常の中で、何時作品のネタを仕入れたのだろうか。時代小説を書くには、ある程度の資料が必要なのである。ところが彼が取材や資料収集のために時間を使った形跡はほとんどないのだ。
直木が多忙な日々を送りながら、暇さえあれば雑書を読みふけっていたことは事実である。風呂好きの彼は、昼頃に起床すると直ぐ新聞か本を手にして、ざぶんと風呂に飛び込み、便所の中でも本を手離さなかった。しかし、それだけでは、あれほど中身の濃い時代小説を次から次に生み出せる訳はない。
作家としての彼の資産は、子供の頃からの多種多様な読書にあった。直木は小学校に上がる頃から、父に「宗一、又ここに来てけつかる」と怒鳴られながら十歳違いの弟を背中に負ぶって、近所の貸本屋に入り浸っていた。
講談の口演筆記をはじめ、塚原渋柿園、黒岩涙香、村井弦斎、広津柳浪、押川春葉、徳富蘆花、村上浪六など、何でもかんでも片っ端から読んだ。大学を出て失業中も、赤ん坊の子守がてら、多量の本を読んでいる。直木は俊敏で頭が良く、読んだ本の勘所をすぐにつかんだ。こうした資産を持っていたから、彼は流行作家になってからも、素材不足に悩むことはなかったのだ。
「苦楽」を編集する傍ら、依頼に応じてあちこちの雑誌に原稿を書いていた頃が、直木の一生で最も幸福な時期だった。プラトン社から毎月月給が入ってくるし、原稿料収入も少なくない。そして寿満と織恵の折り合いもよかった。二人の子供も日ましに可愛くなっていく。
だが、直木は、どうしても安定した生活を持ちこたえることができないのである。公私混同を十八番にする彼は、編集室に平気で織恵を呼び寄せ、織恵の方もしょっちゅう「苦楽」社に立ち寄っていた。雑誌に使う紙を検討するためにプラトン社の社長が富士製紙の工場を視察にでかけたことがある。社長が自動車で直木を迎えに社に立ち寄ると、彼が着物を着た丸髷の女と出てきて黙って車に取り込んだ。
社長は憤慨して、「直木があの女を連れて行くというなら、工場見学は中止する」と抗議した。同乗していた川口松太郎が「今更そんなことは出来ない」と反対したので、一行は予定通り工場に向かった。が、その間、直木は弁解もしないし、社長に織恵を紹介もしなかった。
直木は浪費がたたって、小遣いにも苦労するようになった。
ある日、プラトン社専属の挿絵画家岩田専太郎が居残りで仕事をしていると、直木が無言で部屋に入ってきた。
「五銭あるか」
岩田が何に使うのかと尋ねたところ、風呂賃だという。
数日後、直木は岩田をハイヤーに乗せて南の一流料亭に招待した。それが五銭の借金に対する彼のお返しだった。こんな調子だから、彼が金に困るのは当然といえる。
直木を更に窮地に追い込んだのは、映画製作だった。
彼が香西織恵の名前で「苦楽」に発表した「心中きらら坂」が好評で、マキノキネマの社長牧野省三はこの作品に目を付けて映画化した。これが縁で直木と牧野は親しくなり、直木が映画界に足を踏み込む端緒になる。
直木が牧野と肝胆相照らす仲になってから暫くして、東亜キネマと合併したマキノキネマはスター俳優だった板東妻三郎などを競争会社に引き抜かれて窮地に陥った。この時、直木はその穴埋めに早稲田大学で一年先輩だった沢田正二郎の新国劇を映画に出演させたらどうかと提案し、仲介の労を取った。
直木の着想は見事に成功して、新国劇を出演させた映画は大当たりを取った。息を吹き返した東亜キネマとマキノキネマは、直木を企画顧問に招くことになる。以来、直木は、牧野省三と組んで「連合映画芸術家協会」を設立し、映画製作に本腰を入れることになるのである。
彼は出版に手を染めたときに「トルストイ全集」で大当たりを取った。だが、間もなく事業仲間と衝突したり、目に余る公私混同を敢えてして、膨大な借金を背負い込むことになった。映画製作でも、彼は同じ失敗をしている。プラトン社を辞めて、映画製作の仕事に専念するようになったが、映画芸術家協会は半年もしないうちに行き詰まりの兆候を見せ始める。そもそも直木には、実務家としての能力など、ないにひとしいのである。
有力な監督や俳優が相継いで他社に去ってしまったので、菊池寛の「第二の接吻」を映画化するにあたって、直木は愛人の香西織恵を主役にし、長女の木の実を子役で出演させなければならなかった(ちなみに直木も久米正雄も映画監督になって映画を作っている)。
映画製作で、またもや山のような借金を作った直木は、関西に在住すること三年でほうほうのていで東京に舞い戻ってくるのだ。
5
坂口安吾と直木三十五の共通点は、健康と金銭に関する配慮をほとんどしなかったことだろう。例えば健康については、本人たちはそれぞれ養生に気を遣っているつもりでいても、第三者の目から見れば無茶としかいいようのないことをしている。
流行作家になった坂口安吾は、睡眠不足の状態で書いた文章に力感がないとを痛感し、夜ぐっすり眠るために睡眠薬を常用するようになった。だが、睡眠薬を飲んだ朝は、頭が重く気分がすっきりしないことに気づくようになる。
そこで彼は、覚醒剤を飲んで頭をハッキリさせることにするのだ。こうして彼は睡眠薬と覚醒剤を交互に服用するという無茶なことをはじめ、その双方の服用量をどんどん増やしていった。そしてヒロポン中毒になり、被害妄想に襲われるようになる。直木が原稿の注文を際限もなく引き受け、その結果斬り死にするような最期を遂げたのも、健康に配慮しなかったためだ。
坂口は税金が高すぎると言って、税務署と喧嘩を始めたくせに稼いだ金の使い方はいい加減だった。直木も出版業や映画製作などの事業に手を染めて、山のような借金をつくている。二人が金銭に無頓着だったことと、妻の選び方がイージーだったことの間には関係があるかもしれない。坂口の妻はパンパン(街娼)だったといわれるし、直木の妻も性的に放埒だった。いずれも家計をまかせるには問題のある女たちだったのである。
坂口・直木の対極にあるのが、世の金満家たちである。
金持ちというのは、通例、溜め込んだ金が出て行くのを病的に恐れるもので、吝嗇・しぶちん・ケチを共通項にしている。もう一つの共通項が小心翼々と健康に留意することなのだ。彼らは、身体にいいということは何でもする。このためなら、大切な金を使うことも惜しまないのである。
ニヒリストが金にも寿命にも無頓着なのは、社会の枠外に出てしまって世の常の自己保身とは無縁な生き方をしているからなのだ。金満家の成功の秘訣は金と寿命への執着の強さにある。世俗内存在として勝者になるには、この二つが必要なのである。
同じ程度の頭脳をもつ人間が、一方は世俗的な価値を追尋して金持ちになり、他方は世俗を無視してニヒリストになる。この両者の人生コースを分けるものは何なのだろうか。
その要因の一つに本の読み方があると思うのだ。
成功する人間は、親や教師が勧める良書やら、学校の教科書・参考書をよむ。成功するのに必要な本だけを読むのである。ニヒリストは、PTA推薦といったような本にうさんくささを感じ、好んで雑多な悪書を読む。
戦後に「堕落論」によって華々しく登場した坂口安吾は、人の意表をつくような発言で読者の心を捕らえた。敗戦後、特攻隊の生き残りは闇屋になり、夫を戦場で失った「靖国の妻」は新しい恋に身を焼くようになる。人はこれを堕落と呼ぶけれども、実は彼らは人間本来の姿に立ち戻ったに過ぎないのだと坂口はいう。そして堕落せよ、堕落して本来の人間性を回復せよと説くのだ。
こうした世間の盲点をつくような発言は、坂口が日本・フランスの雑書を読みこんだことから来ている。彼が戦争中に書いた「日本文化私観」も、新鮮な発想で光っていた。ブルノー・タウトらが、法隆寺などの日本建築を礼賛したのに対して、坂口は盲目的に古建築を礼賛する風潮に一石を投じたのだ。
形あるものは必ず滅びる。法隆寺や金閣寺の保存に神経質になる代わりに、現代社会の生み出す美に──たとえば銀色に輝く巨大なガスタンクの美しさに注目せよ。
坂口の史眼も独創的で異彩を放っているし、「安吾巷談」に見る風俗批判も卓越している。坂口のような発想は、優等生がどんなに頭を絞っても出てこないのだ。優等生は読書上の偏食に陥いり、知的な面で栄養不良になっているから、「常識」を超えた豊かな発想を育てることができないのだ。
直木が出版と映画製作で当初大穴を当てたのも、彼が雑書を乱読し、現世をニヒリズムの高みから大観してきたからだ。彼は、早稲田の級友やら、出版・映画製作で知り合った作家や映画人など、多様な人脈を持ち、多くの友人と親交を結んだが、前に触れたように彼らと完全に一体となることはなかった。彼が絶妙なゴシップ記事を書き得たのも、相手と馴れ合うことをしなかったからだ。彼の目は、常に冷たくさえていた。
戦後、剣豪作家として名をはせた五味康祐は、直木三十五のイミテーションのような人物だった。五味康祐は、ニヒリストを気取りながら、その身勝手な行動によって他人に被害を与えるだけで、自らを苛めることがなかった。つまり、公正さに欠けていたのである。坂口も直木も公正な人間で、他を批判すると同じ目で自らを裁き、現世を冷ややかに眺めながら、その俗世を愛していたのである。
直木の処世哲学は、「どっちでも同じ」ということだった。人生の岐路に立ったとき、損得を計算して得な方を選ぶということをしないで、無頓着に成り行きにまかせた。
──さて、映画で失敗して東京に逃げ戻って来た直木にとって、金を稼ぐために残された方法は最早、執筆活動しかなかった。映画製作の裏話を書くにあたって、題名を「映画界泥ばなし」「映画界七花八裂」としたり、小説の題名を、「由比根元大殺記」「槍の権三重帷子」とするところに作家としての天賦の才腕が感じられる。
彼が自ら語った執筆生活は、次のようなものだった。
机によりては書けず、臥て書く習癖あり。夜半十二時ごろより、朝八、九時まで書き、読み、午後二、三ごろ起床する日々多し。速筆にて、一時間五枚ないし十枚を書き得。最速レコード、十六枚。
「臥て書く習癖あり」とは、こんな具合だった。
まず絹の敷き布団を二三枚重ね、その上に腹這いになる。枕を抱くようにして顔を乗せ、顎を突き出してペンを取る。枕元には、きちんと重ねられた原稿用紙の束がある。寝そべりながらも、身辺を整然と整えて執筆する。
「直木三十五伝」の著者植村鞆音は、このへんをもう少し詳しく書いている。
四季を通じ和服の着流しで、どこへ行くにも袱紗包みを持参していた。中には二百字づめの原稿用紙と、銅色のGペンというペン先がぎっしり詰まった小さなボール箱とインク壷が入っていた。参考書や辞書の類は一切入っていなかった。行く先々で、袱紗包みを開くと、ペン軸にGペンを挿しこみ執筆が始まる。頭の中に浮んでくる文章をパソコンのワードのように、猛烈なスピードで文字に変えていくのだった。
速筆である。文字は速筆を助けるために極度に省力された小さなものだった。「関ケ原御屏風」(「改造」昭和五年九月号)は、一日で百二十枚書いた。文学の質よりむしろ執筆の速度を誇りにしている。直木はよく愛人の織恵に執筆の速度を計らせ記録を楽しんだ。
直木がこの速筆で書きとばせば、原稿料収入は急増する。だが、支出の方がそれを上回ったから、借金取りとは最後まで縁が切れず、年に一二度は必ず差し押さえを受けていた。そのくせ、大衆文学全集の印税が入ると、自家用車を手に入れる算段をはじめるのだ。
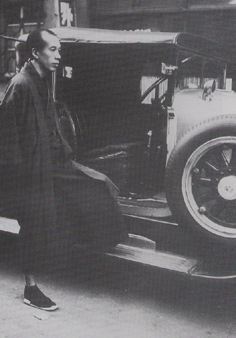 愛車に乗り込もうとする直木
愛車に乗り込もうとする直木直木は盟友の菊池寛を説得して、アメリカ製の自家用車を直木・菊池・文芸春秋社三者の共同出資で購入し、さらに直木・菊池・香西織恵三者の共同名義で木挽町に「文藝春秋社倶楽部」を作った。
これらの費用は直木への友情から菊池が大半を負担したが、直木も応分の分担をしなければならない。彼は紀尾井町の自宅に妻と二人の子を置いて扶養する一方で、倶楽部の三階に愛人の香西織恵と所帯を持っていたから、この出費も馬鹿にならなかった。他に芸者遊びの道楽があり、飛行機に乗るのも大好きだった。彼は飛行機に乗る回数が日本一という珍妙な記録を持っていた。
6
この時期の直木の日記を読んで驚くのは、来客の多さで、彼が流行作家になると、さまざまな用件を携えた人間が連日おしかけてきて彼を悩ますようになった。ある日の来客は12人で部屋がいっぱいになった。別の日には、客を二部屋に待たせておいて、彼は両方の部屋を掛け持ちで応対した。冬になってストーブを買いに出かけようと毎日思うのだが、来客の応対で一日が暮れてしまい、全く外出できない。
こんな暮らしをしながら、毎夜何十枚もの原稿を書き続けるのだから、身体が持たなくなるのは当然といえる。
頑健を誇っていた彼の肉体に、いつの間にか結核菌がとりつきはじめた。病菌は肺から脊椎に移って、脊椎カリエスを発症させ、つづいて脳を犯すようになった。脳膜炎になってから、直木の行動に変化があらわれた。自虐と他虐のうち、他虐だけが一方的に猛り狂うようになったのだ。
耐えきれなくなった寿満は離婚して紀尾井町を去り、織恵も直木を見捨てて倶楽部から姿を消した。孤独になった直木を憐れんで、菊池寛が真館はな子という結婚歴のある26才の女を連れてきた。彼女を秘書にしたらどうかというのである。
直木は、「秘書もいいが、女房にはどうだ」と言って、はな子との交渉がはじまった。だが、直木の横暴な態度は変わらなかった。はな子が咳をすると、「外に出てくれ」と言って追い出し、銀杏の殻を剥いて音を立てると「音を立てずに剥け」と命じる。死が間近になった頃には、薬缶の音がうるさいといって、沸騰した薬缶をはな子に投げつけたりした。
脳膜炎による頭痛が激しくなったので、強情な直木も遂に自分から入院すると言い出して帝大病院の患者になった。そして入院後、わずか16日で息を引き取るのである。死の四日前には幻覚に襲われ、「おれはいま化物小屋にいる」とつぶやいた。
ニヒリストは、世俗的な利害を問題にせず、既成のモラルに縛られないため選択肢が常人より多い。そして何かを選択すると、自分が選んだ世界をとことん追求する。直木は、豊かな才能に恵まれながら、晩年の10年の選択肢として大衆小説作家の道を選んだ。金を手っ取り早く稼ぐ手段だったとはいえ、どうしてほかの道を選ばなかったのか。憾みは深いのである。
直木の葬儀は、文芸春秋社の社葬として盛大に執り行われた。
彼の愛した二人の子供の運命も父と同様にあまり幸福とは言い難かった。長女の木の実は、父の自家用車の運転手と愛し合って私生児を生み、26才で死んでいる。自殺だったと言われている。長男の昂生は太平洋戦争に召集され、25才で戦病死した。
これに反して、直木と関係のあった女たちは長生きをしている。正妻の仏子寿満は84才、愛人の香西織恵は82才まで生き、昭和35年に建設された「芸術は短く、貧乏は長し」という直木を記念する建碑式にそろって出席している。やはり、女の方がタフなのである。
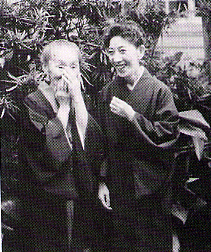
建碑式に顔をそろえた妻と愛人
左が寿満
右が織恵