中江兆民は歴史的には日本における最初の唯物論者として、そして又自由党初期の指導的理論家として記憶されている。しかし、一般に彼の名前は軽妙な毒舌家として、或は明治期の代表的な奇行家として知られている。
中江兆民に対する多くの同時代人の評価は「直言の士」という点で一致していた。例えぱ、大石正己は「中江君は実に単刀直入で、思う所を云い、為きんと欲する所を為すという点に於て我邦の絶品であった」と書いているし、後藤象二郎は中江を評して、彼は三国志に出てくる禰衡だと言っていたという。
禰衡は酒興に名をかり、全裸体となって宴席上に踊り出て、権勢並ぶものない曹操を罵倒した人物である。この後藤の批評は中江を知る者の共感を集めたらしく、中江=禰衡論は広く人口に膾炙するところとなっている。
しかし私は中江兆民に関する本を読むたびに、彼の純理的な一貫性・徹底性に強く惹かれる。彼は、波乱にみちた騒々しい一生を送ったように見える。だが、先入観を捨てて眺めたら、誰でも彼の生涯全体を貫ぬき流れている基調音の簡潔さや、鬼面人を驚かすその言説の背後にある魂の地平の静けさなどを感じ取ることが出来る。
学生時代に、中江兆民の経歴を調べ、彼の著作を読んでいるうちに、目を洗われるような驚きに襲われた。ダムの水が水路の未端まで届くように、兆民の思想はその生涯の最後の瞬間にまで行き及んでいるのである。
中江兆民の数ある逸話のうちで、一番好感が持てるのは次のようなエピソードだった。兆民は自分が開設した「仏学塾」の学生達と近くの飲屋に行って談論風発するのが常だった。学生達は、師匠の兆民を平気で、「中江君」と呼び棄てにし、兆民の方も淡白にこれに応じていたというのである。
彼の門下生だった小山久之助(自由民権運動家)は、世に出てからも兆民のことを「中江君、中江君」と言っていたが、これも「仏学塾」以来の習慣からだった。
これが明治十年代の話なのである。師弟間に儒教道徳に基く厳然たる区別のある時代に、現代においてすら成り立ち難いこうした自由な師弟関係を生み出したのは、中江兆民のパーソナリテイの独自構造によっている。
師弟・親子の間には、この世に出現した時期の先後という差があるだけだ。教師が教え、親が育てるのは、当然の世代継承業務であり、そのことをもって特別の恩愛を期待しあういわれはない。弟子がその師を神のごとく畏敬するのは、実は教師の方でそれを求め強要しているのである。
人間はすべて単位存在として完全に平等につくられている。これが中江兆民の信じてやまないところであった。
中江兆民の新しさは、畑を全部天地返しするように、自らの全生活を理によつて鋤ぎ返した人間の新しさであった。知らぬ間に私達を縛っている習慣的な思考や感情から自由になり、感傷的残滓を徹底的に削ぎ落したあとには、せいせいした単純な世界が残る。中江兆民は幻想の消滅した清潔な世界に住んでいた。同じ人間としてこの地上に生れて来て、王があったり部落民がいたりする滑稽さ。
自身の作り出した約束制度に縛られてフロックコートに威儀を正して登院する高官達の馬鹿さ加減。中江兆民は、「民主」の主とは王の頭に釘を打つことだという痛烈なドド逸を作り、第一回国会議員選挙には大阪地区の部落民の支持を受けて当選し、議会に登院する時にはドテラを着て出かけた。
実際、兆民の生涯は純理的な志向で一貫していた。
彼は汽車や船に乗るときは、三等の赤切符で通したし、持参する弁当は梅干し入りの握り飯を竹の皮に包んだものと決まっていた。無妻主義を通して家督を弟に譲ってしまった彼が、40歳になって結婚した相手は旅館の女中をしている「私生児」だった。しかも彼女は、離婚歴のある「出戻り女」だったのである。
晩年、三菱財閥から兆民に生活費援助の申し出があったとき、「涎を流しつつ、残念ながら痩せ我慢を張りて御辞退申し候」と謝絶の手紙を書いているし、死に際して、兆民は遺体を解剖用に提供し、無葬儀で葬るように言いのこしている。
国も個人も上昇欲求に支配されていた明治の時代に、無位無冠の「平民」として生きる覚悟に徹した兆民とは、どんな人間だったのだろうか。その素性を探ってみよう。
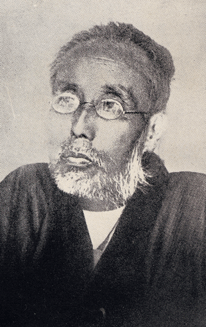 兆民は写真嫌いで単独で撮った写真は二枚しか残っていない。彼は日記もつけなかったし自伝も書かなかった
兆民は写真嫌いで単独で撮った写真は二枚しか残っていない。彼は日記もつけなかったし自伝も書かなかった彼は土佐藩の下士の家に生まれている。父は江戸詰だったから、郷里で母と暮らしていた兆民は父の影響をほとんど受けることなく成長した。生前、落ち度があったため、何度か謹慎減俸の処分を受けたという父が死去した後、兆民は15歳の若さで家督を継いでいる。
意外なことに、子供の頃の兆民は女の子のように物静かな勉強家だったという。しかし近所の褒め者だった中江少年には、奇癖があった。瀬戸物を石にたたきつけて割ったり、夏の暑さをさけるために井戸の中にこもったりする癖だった。
親戚の者が中江宅を訪ねるときには、おもちゃの代わりに兆民に与える皿・小鉢などの瀬戸物を土産にしたと言われる。これらの挿話から、彼が幼児期から家長並に大事に扱われていたこと、彼に掣肘を加える大人が家内にいなかったことで、子供の頃から思うままに振る舞っていたことが分かる。
当時の土佐藩は政争が盛んで、公武合体派や尊王攘夷派が争い、血で血を洗うような刃傷沙汰が起きていたけれど、「女児のように温和」な兆民は局外中立を守っている。彼は荒々しい暴力を嫌悪し、暇があれば自宅で本を読んでいたのである。難解な文字にぶつかっても他に教えを乞うことなく、字引を使って独力で読み解いていた。
こうした兆民だったから、藩校の「文武館」での成績は優秀で、19歳で藩の留学生に選ばれて長崎に学び、21歳で、江戸に移ってフランス語の勉強に取り組んでいる。
江戸に赴いた頃から奔放な行動が目に付くようになる。彼は当時学んでいたフランス語の私塾を放蕩のため破門されている。伝手をたどってフランス公使の通訳になると、ラシャメン(外人の妾)やコック・馬丁などに混じって花札を引くというような日々を送った。
明治維新後は、政府留学生としてフランスに渡り、3年間滞在している。
フランス滞在中も江戸時代以来の奔放な生活は変わらなかった。彼は自ら「余の天性不作法なり、仏国に居り、重に下等職人連と交わり、且酒を飲むや・・・・性行益々極点に達したり」と書いている。
その一方で、フランス語の会話をマスターするために小学校に入学するというような行動に出ており、この徹底性でもって彼は西欧の思想・文物の吸収に努めたのだった。
 フランス留学時代の兆民
フランス留学時代の兆民安酒を飲んで娼婦を買い、下等な職人連と交わるというような奔放な生活は、勉強好きの温和な少年という子供の頃の彼のイメージに反し、渡仏後のフランス学の研究に打ち込んだ学究という彼のイメージとも一致しない。しかし、「下等民」たちとの交友が彼の思想形成を背後から支えていたことは疑いなかった。
人の意識の表皮を覆うのは、子供の頃から馴染んできたその国の慣習であり文化であって、その背後にある人類普遍の合理的な感覚(兆民が少年期に学んだ朱子学の用語で言えば「理」、パリに来て学んだルソーの用語で言えば「一般意志」)にたどり着くにはボーリングの錐が必要である。
兆民の場合、下等職人たちとの交友がボーリングの錐の役割を果たしたのだった。彼は下等職人や娼婦の中にも、「理」や「一般意志」が生きていることを実感したのである。
自由・平等はフランス革命が生んだ美しい観念で、政治的な後発国が目指す目標になっている。けれども、自由・平等の観念だけが独走すれば、暴発して無用の流血沙汰を起こすことになる。自由平等に「博愛」がプラスされて、はじめて歴史を動かすイデオロギーたりうるのである。
中江兆民が、理を持って生涯を生き抜く「純理の人」となることができたのは、彼が底辺に生きる庶民との交わりを深め、そこから一種の人道感覚を育てたからだった。留学を終えて帰国するとき、トルコやインドで白人が現地人を虐待する現場を見て、強い憤りを感じたのも、帰国して日本人が部落民やアイヌ人を差別するのを見て激しい怒りを覚えたのもこのためだった。
兆民が生きていた頃の日本は、朝野をあげて富国強兵を目指し、大陸に進出して列強の一員になることを夢見ていた。この時期に兆民は、富国と強兵は矛盾するという至極当たり前な議論を展開している。日本の将来を大国主義ではなく、島国日本に留まって国内を充実させる「小国主義」の方向に向けるべきだと説いているのである。
彼は時の日本人が範としていた先進強国を「英仏虎狼の国」として否定し、スイス・ベルギー・オランダなどの非強兵国を模範としてあげている。その先見性は、実際目を見張るほどなのである。
こういう透徹した見識を支えたのも、彼の人道感覚だった。彼が富国強兵策に反対したのは、徴税強化によって苦しむ民衆に目を向けていたからであり、列強進出の犠牲になる植民地大衆に熱い同情を寄せていたからだ。つまり、「博愛精神」がバックにあったからなのである。
中江兆民は、日本の政治家・思想家として希有に近いほど一貫した生き方をしている。たが、その彼の生涯にも、屈折や停滞、偏向や逸脱が数多く見られる。日本という国は、啓蒙思想家が生きにくい社会なのである。少し事例を挙げてみる。
周囲から直言の人と評価されていた中江は、自身でも迂路を取らず、直線的に行動すべきことを説いてやまなかった。
「思想を秘して発洩せざる(は)東洋人種の通弊なり」として「偽深沈詐淵穆」を排した東洋自由新聞所載の論文を読むと、中江の西欧合理主義と論理への信頼の念の深きが想像出来るのである。
しかし、中江自身の主張や中江の友人達の証言にもかかわらず、現実の中江の行動は明快率直とは称し難い。青年に向って「公等は折角政治文芸の定跡を研究して初段より二段と漸々進み、九段名人の地位に昇り」、そこで専制権力と「勝負を決めよ」と勧め、老人の素人碁打式の詭手を打つて人を驚してはならぬと力説した中江自身、逆説と飛躍を好み、ことごとに人の意表に出る奇行
によって世人を驚した明治期の代表的な奇人の一人となったのである。
事実、中江は広く一般に信じられている程、明朗快活な正義派ではない。
思想を論理的、体系的に展開せよと説いた中江は、分散的にしか彼自身の思想を表明しなかった。彼の言論活動の特色は、計画性・持続性・綜合性に欠けるということである。地味で平明な文章を尊重し確実で粘り強い文体を使用することを説いた中江は、晦渋で屈折に富み、独断的で奇矯な文章を多く残している。
中江は平常福沢諭吉の文章を高く評価していたといわれるが、同じ啓蒙家であっても、この二人の文章・文体は全く対照的である。東洋豪傑的・志士的な生活態度を否定し近代的な生活意識の普及に努めた中江は、実はかなり陰惨な暗い生活を送つている。彼の私生活のニヒリスチツクな側面については、後に二、三紹介してみる。
それから、近代政党活動の公開性組織性を百も承知していろ筈の中江の政治行動は、頗る策謀に富み、一部の同志からその「陰謀癖」を排斥された程である。
理によって生涯を一貫させた兆民をもってしても避けることが出来なかった人生行路の屈折、これはいかにして生まれて来たのか。
中江兆民が約三年にわたるフランス留学を終えて帰朝したのは明治七年のことである。
この明治七年という年は自由民権史上甚だ重要な年で、征韓論に敗れて下野した板垣退助・江藤新平等が民選護員設立の建白書を提出している。これは旧幕臣の不平分子が維新政府への反感に駆られて嫉妬まじりに放つた中傷ではなく、政権の座から去ったとはいえ当時における気鋭の実力者連がずらっと名を連ねて民権論を主張した堂々たる建議書であった点で、広く世人の注目を集めたのだった。
続いて、建白書署名者を中心に愛国公党が発足するに及んで民権運動は俄然活気づき、同党への入党者が続出する形勢となった。結びつくべき中核体を持たないまま、それ迄分散し浮遊していた反政府的勢力が、愛国公党というザルツプルグの小枝を得て、急速に結晶し始めたのである。
しかし愛国公党の社会的基盤は極めて不安定なものだった。同党に集って来た諸勢力は維新政府に対する反対派という点に共通点を見出しただけで、将来に対する意図や目論見において同床異夢の状態にあった。
彼等は士族に非ずんぱ公卿であった。彼等の運動を背後から支える社会的な階層はなく、愛国公党もまた積極的に大衆層へ接近する努力を払わなかった。
民権運動家達は維新政府に対して自己を「国民」と規定しその運動を「国民運動」と位置づけていたが、彼等は国民のどの階層からも遊離していたのである。
だから台湾遠征以後、国民の眼が外に向けられて民権運動への関心が薄らぎ、さらに土佐の壮士連による岩倉具視謀殺事件が起きて民権運動家に対する一般の猜疑の念が深くなると、党は早くも動揺しはじめ、江藤新平が不平士族を
糾合して佐賀に乱を起すや、江藤との通謀の疑いを受けた愛国公党は忽ち崩壊し、運動の指導者だった板垣退助は東京を去って土佐に帰郷してしまうのである。
それから明治十年の西郷一派の反乱に至るまでの数年間、民権運動は痛ましい混乱と錯誤の途を辿ることになる。国民的な基盤を持たない民権運動は、各地の政社の統合と分裂、提携と反発を繰り返し、貴重なエネルギーを浪費してゆくのだ。
各政社間の統合と分裂は、デタラメで無原則だった。
例えぱ、福岡の政治グループを率いていた後年の右翼の巨頭・頭山満は、板垣との連携を企て、土佐の立志社を訪問している。
頭山から提携を申込まれた立志社は、薩南の逆コース的保守派・西郷隆盛グループとの連携を模索し、後にこのことが発覚して板垣の盟友・片岡健吉は逮捕されている。
こうした矛盾と錯誤は、立志社だけに留まらなかった。士族出身の民権運動家達はサムライ式のヒロイズムに酔って武力蜂起を企て、或は本来敵対すべき反動的な保守主義者と通謀し、あるいはアジァの幼弱諸国への侵略政策に魅力を感じたりしていたのである。
近代的な政党組織が玄洋社風の地縁的な朋党組織から分化しなかつたと同じように、この頃の民権運動家には、国士的な済天下思想と開明的な政治イデオロギーが未分化のまま同居していた。
彼等の行動には、地道な啓蒙によつて民衆を組織化し、民衆の意志を物理的な力に転化しようとする近代政党活動の萌芽が僅ながら見られると同時に、激情が直ちに東洋的な権謀術数と結びつき、それが更に鋭角的な行動と最短距離で結ぴつく志士風の性急さが見られる。この弱点からは聰明な中江兆民と難も免れることは出来なかった。
帰朝後、元老院権小書記官、外国語学校長を歴任した中江は、やがて官途を辞して在野の人となり、番町に私塾を開いてフランス語の速成教授に当ることになった。当時の彼が「独り革命思想の鼓吹者たるのみならず、更に革命の策士断行者たらん」(幸徳秋水「兆民先生」)と決意したのは、藩閥政府の横暴が目に余るからだった。
薩摩・長州の政治家たちは政権を自派で固めるだけでなく、税金で官営模範工場を建て、それを薩長出身の政商たちに安く払い下げるというようなこともしていた。中江兆民は、この特権集団を打破しないことには日本の将来はないと考えたのである。
その為に、彼は国粋的傾向の強い九州の「志士」達と交りを結ぴ、「支那に為すあらん」として東洋学館を起したりした。
そして、中江は勝海舟を介して島津久光に会い、「策論」一篇を呈して島津に反乱を勧めている。この計画は、島津久光をして西郷隆盛を薩摩から上京せしめ、近衛の軍を奪つて太政官を囲むといつた風の短兵急なものであつた。
彼が交りを結んだ九州の「志士」達は、行動力には富んでいたが理論的な純度に欠けていた。また、勝海舟・島津久光・西郷隆盛等は当代一流の名士で、時代を動かすだけの実力の所有者だったが、所詮彼等は保守的なイデオローグに過ぎなかった。
しかし、中江は彼等のもつ保寄性には眼をつぶつて、その政治的な名声だけを利用しようとしたのだった。彼は専ら現実の力関係だけに関心を持ち、壮士・大物に働きかけて既存の勢力を再編成し、時の政治的なバランスを崩
すことに腐心したのである。中江の行動は、既に啓蒙家のそれではなく逆徒のそれであった。
その結果、彼の企図はことごとく失敗に終わり、絶望した彼は「放縦度なきに至れり」ということになる。
明治十年、西郷一派は遂に維新政府に対して武力蜂起を企てた。そして勇戦奮斗も空しく反乱軍は壊滅し、事破れた西郷は城山で自刃して果てた。西郷のこの悲劇的な最後は全国の民権運動家達に警鐘を高く打ち鳴らすことになった。
日本の自由主義運動は西南戦争を境に武力蜂起の途から絶縁し、一大転換を試みる。
彼らに残きれた途は、最早、言論しかないのであった。讒謗律・新聞条例を武器にした政府の弾圧に屈しないで、執拗に斗つたこれ以後の自由民権論者の活動は賞賛されてもいい。
方針転換後の自由主義運動が運動の基盤としたのは、地方のマニユファクチユア資本家であった。民権運動家達はそこに自己の運動を支える同盟者を発見したのである。
地方のマニユフアクチユァ資本家は、政府と結びついた特権的金融資本・巨大産業資本と敵対する社会的勢力にまで成長していた。政府は近代的な機械工業を育成する為に三井・三菱など少数の大資本を保護していたが、その工業育成資金は地方の中小マニユフアクチユア資本家から徴収した税金から出ていたのである。
政府はこれらの税金を「営業税」という形で中小資本家から徴収していた。これに対抗して中小資本は「営業の自由」を強調し、政府の政商擁護をはげしく攻撃した。民権論者は中小資本の政府及ぴ大資本への不満を代弁することによって、地方に勢力を拡大していったのである。
酒税の引上げに反対する全国の酒造業者(酒造業は地方に発達した代表的な工場制手工業である)に働きかけて、立志社の植木枝盛が「酒屋会礒」を開催したことなどは、この時期の民権運動家の運動方式を典型的に示す事例だった。
これ迄、反政府的な士族達を中心にしていた自由民権運動は、各地のマニユフアクチユァ資本家から運動資金の提供を受けて、目覚ましい発展を示すようになった。各地の政社を連合した愛国社は再興きれ、愛国社の大会は四回にわたつて開かれた。明治十三年三月、大阪に開催された第四回大会には二府二十二県の代表百十四名が一堂に会している。
愛国社は国会期成同盟へと発展し、期成同盟はやがて自由党の母胎となる。こういう民間の活発な動きは、政府をして明治十一年に府県会を設置せしめ、明治十四年には国会開設を公約せざるを得ないところまで追い込んだ。
明治十年から「東洋自由新聞」創刊(明治14年)にかけての数年間、中江兆民は番町のフランス語私塾で学生たちの教育に専念していた。
中江の「仏学塾」は、最盛期には学生数2000名を数えるほど繁盛したが、彼は学生を規制しようとはしなかったし、学校経営にも無頓着だったから、塾は学校というより「進歩的青年」たちの集会所という観を呈した。
役人時代に袂に炒り豆を入れて、ぽりぽり囓りながら仕事をしていた兆民は、仏学塾で講義をするときには、傍らに酒瓶を置いていた。こうした兆民だったから、師弟間にオレ・お前のつきあいが成立したのである。
彼は全国を捲き込んだ華々しい自由主義運動をよそに、実際的な政治運動にタッチすることを控えていた。この時期の彼は、深く沈潜していたのである。
河野広中が明治十二年頃、自由主義のメッカ土佐に遊んだ時の日記中に、板垣退助から「中居徳助」という男の名前を聞かされたことが書いてある。これは明らかに「中江篤介(兆民め本名)」の誤記であるが、河野から名前を誤記される程度にしか、中江の存在は知られていなかったのである。
ここに西南戦争から彼が受けた打繋の大きさを知ることが出来る。後年の彼の活動は、すべてこの時の深刻な反省から来ている。
兆民の思想に独特のニユァンスを与えている東洋的な虚無思想も、この沈潜期に養われたものと思われる。西南戦争前の政治行動の失敗によって傷ついた彼が「放縦度なきに至」ったことは後年彼自身告白しているところだが、これは同時に彼をして禅による精神の安定を求めさせることになり、彼の東洋思想への親炙を一層深めることになった。
中江兆民は、ルソー・モンテスキユーを私塾の学生に教授すろ傍ら、私室に戻ると坐禅に没頭し、「碧巌録」を読み、「荘子」「史記」を愛読していた。東洋的なニヒリズムに裏打ちされたフランス合理主義、これがその後の兆民の思想を彩る特徴となるのである。
中江兆民が「正史」の上に登場するのは信州松本の人松沢求策の尽力によって甚だ短命だった「東洋自由新聞」が創刊きれ、その主筆に招かれてからだった。この新聞の名誉社長に推挙された西園寺公望は、フランス留学時代の中江の学友である。
久しい間の沈黙を破り、新聞人として活躍の場を与えられた中江は、自由主義思想を論理的・体系的に展開することに努めた。
オーソドツクスな方法と学識で裏打ちされた「精密な論」によって、真っ正面から読者に訴えてゆこうと考えたのだ。岩波文庫「兆民選集」に集録された「東洋自由新聞」第二号の社説を読むと、中江はこの点について読者にあらかじめ注意をうながしている。
「吾輩の事を論ずる辞気諄々として老人の談話に類する」ものがあるから「世の矯激の徒」は或は自分のことを「大寛」に過ぎると非難するかもしれない。だが、昔から人民が大業を創建したのは、過激な論を騰げたからではなく、精密の論を立てたからである・・・・・。
中江には「学者」としての自負はあったが、「ジヤーナリスト」としての自信はなく、同じ洋行帰りの福沢諭吉や成島柳北がジヤーナリズムの世界で博したような人気を全く期待していなかつた。それに彼は既に福沢や成島の時代は過ぎたと考えでいた。
中江は、将来の社会を指導することになる知識人を読者に想定して、質の高い新聞を作ろうとしたのだった。彼は進歩的な若手官僚にも期待していた。
明治初期における福沢の成功は、平明な口語的表現をかりて、普通の庶民に向かって個人対個人の平等を主張したからだった。福沢が終始一貫力説してやまなかったのは人間的価値の平等という、素朴だが力強い原理だった。
彼の書葉は常に生活者としての現実から発し、その理論を具体的な自己の生活体験の集積の上に構築している。粉飾をこらした晦渋な漢学的文体に抵抗を感じ、封建的な身分制度に苦しんでいた士分以下の実務的な庶民にとって、福沢のこの新しい文体と思考がいかに強烈な魅力をもつて迫ったかは、彼の「西洋事情」が二十万部から二十五万部売れたという驚くべき数字からも想像出来る。およそ文字の読めるほどの人間は、皆この本を買って読んだのである。
福沢に続いて活躍した成島は、軽妙酒脱な才筆で藩閥政府を揶揄した。彼は理論やモラルを盾に政府に迫ることはなかった。彼は、政府高官の成り上がり的、田舎っぺ的な言動を洗練された都会人的な覚で侮蔑嘲笑したのである。従つて彼の読者は教養ある東京人士に限られていた。
福沢と成島に共通するのは、二人が敵本主義的な反対派だったということである。元来、啓蒙家の役割は当面する歴史的現実に対して打撃を加えることにあって、批判する根拠が正確であるかどうかではない。問題は批判の鋭さと激しさであり、その正確さや深さではない。啓蒙家の能力はその破壊力によつて測られ、建設力は問われないのである。
これは啓蒙家の置かれた歴史的境位が封建制杜会と資本制社会の中間にあり、社会の表面を蔽う規範は封建的な身分制的階層秩序であっても、既にその内部には資本主義的な社会関係が存在しているという事実に照応している。
つまり、啓蒙家は新しい社会関係を理念的に創出すろ必要はないのだ。彼は自然的秩序として既に存在する資本主義的ないし前資本主義的な社会関係を提出し、これに対して封建的社会関係がいかにに不自然であるか対置して見せさえすればいいのである。要はこの対照を鮮明ならしめることであり、対置された結果に対する断罪が峻厳なことにある。
福沢は人間平等の見地に立つて「反自然的」な士分意識を苛惜なく批判した。批判される事例の選択は恣意的であり、反対派的な立場からこれに対置した民主社会の図式も前者と正確な対応関係を示していなかったが、福沢の敵本主義的な態度はそれでも十二分の効果をあげたのだった。
成島に至つては薩長高官の不粋.野暮・独善を嘲笑し、彼等の持つ権力の大きさと彼等の見せる地方人的な蒙昧を対照して見せたに過ぎなかった。しかし、この対照によって拡大きれたグロテスクな滑稽さが、専制政治の反自然的な性格を見事に浮彫りにしたのである。
明治十年代に入ると、福沢や成島に代って植木枝盛や大井憲太郎が出現し、福沢等の基礎的な啓蒙の上に立って具体的な政治形態の問題を取り上げ始めた。明治十年以後の自由主義運動の昂揚は、単純な人間平等論から進んで人民主権の問題、憲法の問題、国会開設の問題を中心的な課題にするところまで成長したのである。
中江兆民の執筆活動も、この課題に応えようとするものであった。彼が対象とした読者は一般庶民ではなく、まして東京居住の都会人士でもなく、日本の自由主義的民権運動を推進する中堅分子、即ち、進歩的士族・若手官僚及び中小マニユフアクチユア資本家であった。
そして、これらの階層は、欧米文化への希求を内に燃やしながら、その教養は昔ながらの漢学を基本にしていた。中江の文章が漢文読み下し式の硬い文体を使用していたのは、彼自身の嗜好ということを別にして、当時の知識人達の好尚に合わせるためだった。「常山紀談」十巻の漢訳を試みるほど漢学に通じていた中江は、読者の要求する形式美を備えた漢文崩しの美文を書くだけの修練をすでに積んでいたのである。
しかし、一方で智識人の要求に応えようとすれぱ、他方では自から読者の範囲を限定すろ結果になる。中江の読者は福沢はもとより、成島の読者と比較してすら多くはなかった。
執筆活動を開始した当座の中江は読者に妥協することを拒否していた。彼は窮極における理論の勝利を信じていたのである。初期の論文には「意匠業作」(「意匠」は理論、「業作」は実践で、理論と実践の一致を説いたもの)を始めとして、論理・法則の重要牲を説いたものが多い。
中江は純度の高い理論のみが読者を獲得し、自由民権運動の発展に寄与しうると考えたのだ。難解な漢訳「民約訳解」(ルソーの「民約論」を翻訳したもの)を出版したのも、政治理論誌「政理叢談」を刊行したのも、こうした信念からであった。
中江は歴史の発展段階を四時期に区分している。歴史の流れに普遍的な法則性を認めていたのである。それによると、人類の歴史は、原初期には無秩序混沌たる無政府状態があり、継いで「君相専檀の制」となり、続いて「立憲の制」となり、最後に「民主の制」となるとされている。
中江は当時の日本を「君相専檀の制」から「立憲の制」へ移行する過渡期にあると規定していた。天皇制について討論した仏学塾の学生たちの大半は「廃帝論」に賛成していたが、中江は専制政治から一足飛びに民主政治へ飛躍するのは「進化神」に背く反法則的行為だから、さしあたり「立憲の制」を目標とすべきだと説いている。そして中江説によると、専制政治から立憲政治へ移行する段階においてこそ、「学者」の役割が大きくなるのであった。
立憲政治が実現するためには、それに先行して立憲政治の原型像が国民の脳中に定着していなければならない。つまり、立憲制という「新事業を建立せんと欲するとき」には、その立憲制についての「思想」を国民の「脳髄中に入れて過去の思想とする」(「東洋自由新聞」)必要がある。しかし、専制政治下においては「リベルテー・ポリチツク(即ち行為の自由)」のみならず「リベルテー・モラル(即ち心身の自由)」すら国民に与えられていないから、立憲制に関する新しい観念は自生的に創造され得ない。
ところが、ここに「学者」なるものがある。学者は自由なき専制政治下にあって、自由についてイメージすることが出来るエリートであり、無から有を創造し、自由なき世界から自由についての観念を産み出す能力に恵まれている。
学者は、自由の観念を人々の「脳髄中に入れて過去の思想」とする歴史的世界のプロンプターなのである。中江兆民は無論自からをこの「学者」と考えていた。
彼が読者との妥協を排し、高踏的な態度で論文を書いていった理由は、学者をジヤーナリストの上に置き、彼らを歴史の創造者と考えていたからだった。そして、このことは、彼が日本の社会を西欧と同質の知的な社会と見なし、日本は西欧と同様の発展段階を歩むものと想定していたことを意味する。間もなく、中江はこのオプテイミズムに対する報復を受けることになる。
政治講談によって自由民権思想の普及を志した自由党の闘士伊藤仁太郎(痴遊)は、中江兆民に関する陰惨な挿話をいくつか伝えている。
中江が「東洋自由新聞」の主筆として、又、自由党の機関紙「自由新聞」の社説班員として売り出していた頃の話である。当時、中江はさかんに遊里に出没して痛飲していたが、その席に侍る芸妓の中に中江に順倒している女がいた。
ある夜、中江はこの芸妓に向って「俺は金盃を一つ持つている。これから、この金盃でお前に酒を飲ませてやるが、どうか?」と訊ねた。女は平常尊敬している中江が盃を呉れるというので、喜んで承知した。すろと、中江は着物の前をまくって男根を引き出し、その皺をのばして窪みに酒をつぎ「きあ、これが金盃だ、飲め」と言ったというのである。
女は決心して酒を飲んだ。飲んだあとで女は「自由民権運動の指導者である先生が、こんなことをなさっては、体面にかかわりませんか」と諌め、これにはさすがの中江も一言もなかつたというのだ。
この挿話は、民権運動の理論家達に共通する暗い半面を示している。中江と並ぴ称きれた自由党左派の理論家大井憲太郎は、女性解放運動の先駆者景山英子と関係し、彼女が妊娠するとこれを弊履のごとく捨てている。
植木枝盛も女性関係が乱脈だった。彼等が女に向って溺れてゆくのは、運動が坐折した時に多く、彼等は運動の挫折から受けた傷を、女性に嗜虐的な態度を取ることによつて癒していたのである。
妻子を有しながら大井が景山英子と交渉を持つたのは、自由党解党後、彼が運動の主流からはずれて孤立していた時期だった。中江が芸者に金盃を飲ませたときにも、日本の民権運動は重大な危機にさしかかっていた。
明治十年以後の自由民権運動を支えた支柱が地方の中小マニユフアクチユア資本家だったことに触れたが、彼らの多くは実は同時に地主だった。農村における地主は米穀仲買業、小売業、高利貸業等に従事し、あるいは酒造業、製糸業、絹織物業などを兼業していた。
つまり、日本の地主は二重の性格を持ち、小作に対する時には半封建的・保守的態度をもって臨みながら、他力、政府に対する時には自由主義運動の支柱として進歩的な態度を取っていたのである。
この二重性は明治十五年迄は後者に比重をかけ保守的な性格を背後に隠すようにしていたが、明治十五年以後になると階級分化の進展を反映して比重が逆転し、寄生地主的な反動性が前面に出て来たのである。
小生産者や家内工業が急速に没落し、一般農民の貧農化が進むと、地主は反射的に保守化して寄主地主・高利貸としての性格をあらわにし、急進化した農民と敵対するに至る。
こうした情勢は自由党の分裂をもたらすことになった。地主・豪農.地方資本家の利害を代表する板垣・後藤等の自由党幹部は保守化し、他方、小商品生産者・貧農と結ぴついた自由党の下部党員は急進化したのである。こうした自由党内の対立は政府の乗ずるところとなった。藩閥側のリーダー伊藤博文は、術策をめぐらせて自由民権運動のリーダー板垣を洋行させることに成功するのである。
板垣の洋行を不満とした馬場辰猪・大石正己・末広重恭は自由党を脱党してしまう。馬場らは、兆民と共に「自由新聞」の社説係をしていた同僚で、これら有能な理論家を失った自由新聞は急速に精彩を失っていく。中江も社員の職を辞して第一線を退いてしまう。
これより先、「東洋自由新聞」は廃刊になっていた。「御内勅」を振りかざした政府の弾圧によって潰れてしまったのである。社長の西園寺は実兄の泣訴に会つて社長のポストを退き、御内勅問題の真相を紙上で発表した松沢求策は逮捕され、曲折の後に獄中で悶死している。
そして、今度は「自由新聞」を失ってしまったのである。中江にとっては、政見発表の場を失ったことよりも、民権運動に対する自身のオプティミズムを崩されたことの方が大きかった。彼は、民権運動の中堅分子に失望したのである。
党の幹部に対しては無論のこと、これに敵対して実力行動に走り、福島事件、高田事件、加波山事件、名古屋事件等を起した自由党の青年党員に、彼は信頼を繋ぎ得なくなったのだ。
彼等は、あるいは中江の先輩・同僚であり、あるいは弟子たちだった。郷里の先輩のなかで最後には中江を苦笑させるに至った厚顔なオポチユニスト後藤象二郎は、その昔、二十一才の中江が長崎から江戸へ出府すろ際の旅費を出してくれた恩人であった。
政府の術策に乗つて外遊する板垣や後藤が中江の恩義ある先輩なら、「進化神」に背き歴史的発展段階を飛び越えた革命行動に走る青年党員は、中江を「東洋のルソー」と仰いだ弟子達であった。
保守化した幹部と革命化した青年党員のいずれにも組し得ないで孤立した中江は、彼等が以前自分の知己であっただけに裏切られた思いがひときわ深かったのである。
自由党の壮士等に対する中江の感惰がどのように変化して行ったかを示す書簡が一通残っている。この中で彼は以前の同志達を「一山四文の連中」と呼んでいるのである(保安条例によつて東京在住の民権連動家と共に帝都から退去を命ぜられた時、中江は未広鉄腸(重恭)に宛てた書簡で「余は実に恥入りたり、一山四文の連中に入れられたり」と書いている)
明治十七年十月、自由党は遂に解党した。解党の趣意書には、政府の弾圧が激しくなったことと、下部党員が「駿馬ノ覇ナクシテ奔逸スル」ような暴走をはじめ党の統制が取れなくなったことを原因に挙げている。解散に先立って諮問を受けた中江兆民は、異議なく解党に賛成している。
「自由新聞」を離れ、自由党幹部・青年グループのいずれとも手を切った中江は、明治二十年の大同団結までの数年間、陋巷に隠れて翻訳・著述によって生計を立てている。中江にとっては、二度目の沈潜期であった。
そして、彼はこの沈潜期を通じて再び力向転換を試みるのである。中江が奇行家として、そして、毒舌家として出現するのは、明治二十年以後のことである。
保安条例によって東京を追われた中江兆民は、家族と共に大阪に移り、明治二十一年の春から再ぴ活動を開始する。中江の「東雲新聞」時代が姶まるのだ。
この新聞は大阪の中小実業家数十名の出資によって生まれたもので、特権的大資本に対抗する中小産業資本の立場を代弁する日刊紙であった。「東雲新聞」に発表した中江の文章には、それ迄になかった特殊な調子が現われている。高踏的な態度を捨てて、庶民的・通俗的なスタイルに移ろうとする志向である。
最早、中江は、理論的な精密さや文章の格調にこだわることを止めてしまった。「東雲新聞」時代に書いた中江の原稿は、ほとんど「放言」だの「月旦」と題された短評ぱかりで、このスタイルで中江は生来の諧謔と毒舌を武器に、時の政府(黒田・三条内閣)に向かって即戦即決式の攻撃を浴せたのだ。
その文体は式亭三馬風の戯文で説明と描写を行い、結論の部分を響きの強い漢文崩し調の章句で締めくくるといった風なものだった。会話体と論説体、口語と文語、草双調と悲憤慷慨調等が硬軟自在に入り混った彼の文体はコラム式の「放言」を書くには最適だった。
この時期に相前後して彼が発表した単行本やパンフレットに見られる文章も「東洋自由新聞」「民約訳解」「政理叢談」時代のような晦渋な調子は見られない。「三酔人経綸問答」(明治20年)、「平民の目ざまし(一名、国会のこころえ)」(明治20年)、「選挙民の目ざまし」(明治23年)、「憂世慨言」(明治23年)などの文章はことごとく口語・文語の入り混り体である。
これらの啓蒙書から、いくつかの文例あげてみよう。
「今や公等(註国民)の雇人たる彼ら内閣政府の為す所は果して如何。外交は通りに隣児に虐められつつある虫持の小児なり。教育は子々(ボウフラ)の生じたろ溜り水なり。交通機関は芋虫の横這なり」
「今の所謂輿論は一派政党員の勝手に吐き出したる唾の泡也」
「昔日の百姓町人は肉体的に切棄てにされしも、今の百姓町人は財布的切棄てにされつつある也」
といつた調子である。このような文体の変化は、明治十五年以後における中江の坐折によってのみ説明される。
中江は、日本の政治形態が社会進化の法則から逸脱しないものと楽観し、ほどなく西欧的な立憲制確立の時期が到来すると信じた。だから、彼は福沢・成島型の敵本主義的な啓蒙活動から一歩を進めて、立憲制に関する理念的な原型像の描出に努め、理論的・学問的な方法で士族的教養を身につけた自由党員に訴え続けたのである。
しかし、立憲制確立の日が近いと考えたのは中江の幻想に過ぎなかった。彼は日本の社会構造造の合法則性に関して深刻な疑惑を抱くようになり、自由党の志士をも含めた日本人の心性に暗い不信の念を持つに至ったのだった。
そのことは、明治二十二年憲法が発布された時の中江の態度によく表われている。彼は、全国の民衆が明治憲法発布の予報を聞いて大歓迎するのを眺め、苦笑を禁じ得なかった。
「吾人賜与せらるるの憲法果して如何の物乎、玉耶将た瓦耶、未だその実を見るに及ぱすして先す其名に酔ふ」
と嘆じたあとで、彼は「我国民の愚にして狂なる何ぞ如此くなるや」と噛んで吐き出すように呟いている。
そして、いざ全文が発表されると、中江は一読して苦い笑いを浮かべただけだった(幸徳秋水「兆民先生」)。
わが国民の愚にして狂なることに絶望したのは中江ぱかりではなかった。パリ在学中、中江と共に学び「東洋自由新聞」の社長に就任した西園寺も、日本に絶望した一人だった。
彼は冷たいシニシズムに陥り、政界から遠ざかって風流の世界に遊んでいる。中江は後年「一年有半」に西園寺の人物論を書いている。
それによると、西園寺はあまり聰明過ぎて始めから結論が判つてしまうために好寄心の発生すろ余地がなく「天下如何なることも侯に於ては奇なる莫し」とうことになってしまう。
だから「其冷々然として些の内熱」をも感じさせない西園寺に接すると、こちらまで「亦皆其内熱を冷却し」てしまう。
中江と西園寺の共通の友人だったパリ留学生光明寺三郎も、一時期「東洋自由新聞」に参画して民権運動に関わったが、やがて日本に愛想をつかし、女色に耽けるようになる。
だが中江は、「愚にして狂なる」日本の民衆を啓蒙してみたところで結局徒労に終わることを体験していながら、シニシズムに逃げてしまうことは出来なかった。
中江は心構えを新たにして、平俗な文章で実業家と庶民を対象とする啓蒙活動を開始し、論理ではなく毒舌と諧謔を武器にして敵本主義的な発言を展開することになるのだ。以前、兆民と共に論陣を張った民権運動の理論家たちは、運動への逆風が強くなると、沈黙を守るようになった。この反動期に孤軍奮闘の言論活動を展開したのは、兆民だけだった。
中江が風刺と毒舌を最大の武器とするようになったのは、革命の段階規定において福沢・成島の線まで後退したことで彼の筆致に余裕が生まれたからでもある。一方、この時期に彼は戯文や嘲罵文だけでなく、「理学鉤玄」(内容は一種の哲学概論)というような本も書いている。
圧倒的に巨大な歴史的現実に対し、故意に正格を崩した倒立式文章を対置するとき、毒舌が生まれる。そして歴史的現実に自己の人間全体を倒立した形で対置するときに「奇行」が生れる。
日本は昔から動乱時に多くの奇行家を生み、「狂」を自称する志士たちを輩出して来た。凶暴な権力と戦うためには、権力と正面から敵対しないで「奇」や「狂」を偽装しなければならなかったからだ。
強力な国家権力を向こうに回して、単身で戦うこと自体が既に「奇」「狂」であるけれど、更に自から「狂」を自称し好んで奇行を演じるのも被害を最小限に食い止める苦肉の策なのである。
鉱毒事件の田中正造は、「狂態」を最大限に利用した「奇人」だった。彼はその奇行によって世人の注意を鉱毒間題に集めたのみならず、その狂態によって官憲の注意をそらし、支配層を安堵させたのだった。
中江の奇行にも官憲の圧迫に対すろ保護色といった気味がないではない。
しかし、彼の場合、奇行は飽くまで人間全体を以てする体当り的な現実否定だった。
「東雲新聞」時代の中江は、長髪を蓄えてその上に真赤なトルコ帽を冠り、紺の股引をはき、新聞社名を染め抜いた印半纏を羽織って出社した。演説会に招かれて演壇に立つ時も同じ恰好をしていた。彼の煙草入れには「火の用心」と筆太に書いてあった。
第一回の国会選挙に立候補して一銭の費用を費すことなく当選した中江は、青い綴糸のついた温抱(どてら)を着込んで登院して人々を驚かせた。
「温抱は日本のオーバーコートさ」それが彼の釈明の弁であった。
昼になると、中江は竹の皮に包んだ弁当を出したが、中味は梅干の入った握り飯だった。
このような奇行は、ほとんど売名行為に近い。しかし、中江に売名の必要は全くなかった。時代に対する批判をこういう没常識な形で表現することを許したのは、彼のニヒリズムだったに違いない。中江は、自己を奇型化し、自虐的な変形を施した上で、日本の政界と交渉したのである。
第一回議会の中途で、中江は辞表を提出する。第一回議会は、藩閥政府に対する国民のプロテストを表現するための議会になる筈であった。だが、議会は政府に懐柔されて、政府提出の予算案を651万円の削減を加えただけで通過
させてしまう。中江はこの経過を見て、議会を「無血虫の陳列場」と痛罵し中島信行議長に辞表を提出する。
「アルコール中毒のため、評決の数に加はり兼ね候につき辞職仕候」
この辞表は中江兆民について触れる時に必ず引用される有名な文章である。しかし、これは痛烈な批判でもなければ爽快な弾劾文でもない。彼の憤懣は、直接議会に向けられないで、一旦、内へ折れこんで自虐的な表現となって表出されている。
そこに感じられるのは中江の毒々しく屈折した暗いマソヒズムである。
自分を崇拝している芸者に「金盃」をつきつけた中江の行動はサドのようにも見える。だが、お高く止まった器量自慢の芸妓にではなく、内心彼の方でも好意を持っている女に衆人環視の中で「金盃」を突きつけたところにマゾイズムの気配が感じられるのである。
中江は早世した実弟虎馬の娘を引き取って、これに猿吉という名前をつけている(猿年生まれだったから)。丑年生まれの自分の息子には、丑吉と名づけた。名前は符丁に過ぎないという彼一流の合理主義と、明治期の元勲達が、功成り名逐げた後に下士時代の卑俗な名前を改名し、田中顕助が光顕となり、佐々木三四郎が佐々木高行になることに対する抵抗だったと思われる。
それにしても、姪に「猿吉」とは冗談の度が過ぎる。ここにも一見サデイズムの形を借りたマゾヒズムの臭いが感じられる(彼女の名前は、後に「艶子」と改名された)。
「奇行」によって社会の慣行や道徳を無視し、共同体的規制の枠外に飛び出して辛辣な批判を試みるのは、変則的な奇手として一時的には効果的である。しかし、一種アウト・ロウ的な立場からの発言は、華々しくはあるが地道な生活者を動かすにはいたらない。
彼等はアウトローの派手な言辞を面白がりはするけれど、これを尊重することはないのだ。彼等を動かす為には、彼等と同じ生活者の立場に立ち、彼等と同じ責任を分担しなければならない。中江の嘆きは、このアウトローの恨みに繋っている。
彼は田中正造の言葉として「私が演説すると真面目でも、人が滑稽と思うので困る」と書き、その後に続けて次のように書いている。
「思うに世間此くの如き事誠に多し。荘厳にして酒脱と思われ、謹慎にして奇矯と思われ、無意の言行にして有意の言行と思われ、皮相もて胸中を料られ年中新聞雑報の種子にせられ、影と身と全く別個の両人にて此世を送ろ者幾何人なるを知らず。独り此人のみに非ず」(「兆民文集」議員批評)
この文の趣旨が「独り此人のみに非ず」という最後の一節にあることは明らかだろう。彼も自分に貼りつけられた「奇行家」というレツテルのために、内部で血を流していたのである。
理論的に厳密であろうとすれば、その論説の影響力は小範囲に留まり、戯文と奇行によって世の視聴を集めれば、その影響力は表面的なものに終る。
いずれにしても、啓蒙の効果には限界がある。これは天皇制絶対主義下の啓蒙家に負わされた宿命的な悲劇であった。
議員の職を辞し、堕落した自由党と完全に手を切った中江は北海道小樽の「北海新報」に招かれて主筆となり、更に身を実業界に投じて札幌で紙商を経営したが失敗している。議員を辞職したときの中江は45歳で、喉頭ガンのため死去したとき55歳だった。だから、中江の「実業家時代」は、10年間に及んだことになる。
この間、彼が関係した事業は北海道山林組、毛武・河越・常野鉄道会社、東都パノラマ会社、中央清潔社などで、時には群馬県に娼楼を開こうとしたことさえあった。注目すべき点は、実業家時代の中江には奇行に類する話が皆無だったことである。彼は好きな酒を断ち、別人のように身を慎んで仕事に精励した。
だが、事業は失敗続きだった。彼は冗談交じりに次のような述懐をしている。
「余の事業におけるや、利益はすなわち他人これを取り、損失はすなわち余これに任じ、その末や裁判・弁護士・執達吏・公売等ぞくぞく生起し来たりてやむ」
彼は自らの貧乏についても、「大飢饉なるかな、朝暮ただ豆腐の滓と野菜のみ」とユーモラスに語っている。
しかし、いかに窮したと言っても、遊郭設置の事業に加わったのは行き過ぎだった。彼もかなり気が咎めたらしく、しきりに弁明に努めている。金持ちや役人には、芸妓を相手に性を楽しむ自由があるのに、庶民には、それだけの経済力がない。公娼制度は、そういう彼らのために制定されたものだから、遊郭を作るのは決して不道徳ではない。金持ち相手の芸妓は廃止すべきだが、公娼はむしろ保護すべきだ、というのである。
公娼制度擁護の苦しい弁明と同じような弁解を、彼は「国民同盟会」についても行っている。
晩年になって中江兆民は、近衛篤麿の主唱する「国民同盟会」に入会している。同会はロシアとの開戦を主張する好戦的な右翼団体であった。中江が国民同盟会に加入した経緯を「良心を持つが故に孤立し、その孤立を脱け出ようとすれば逸脱する」と説明した史家がある(遠山茂樹)。この「逸脱」を責めた門下生幸徳秋水に対する中江兆民の答は次のようなものであった。
「(我は)露国と戦んと欲す、勝てば即ち大陸に雄飛して以て東洋の平和を支持すべし、敗るれば即ち朝野困迫して国民初めて其迷夢より醒む可し。能く此機に乗ぜば、以て藩閥を勦滅し内政を革新することを得ん」
「三酔人経綸問答」時代の中江から見れば、これはとんでもない暴言なのである。「三酔人経綸問答」には、洋学紳士君・豪傑君・南海先生の三名が登場し、中江の説を代弁するのは南海先生だと言うことになっている。だが、南海先生の発言は、国際情勢についてのものが主で、分量としても僅かでしかない。兆民の思想を代弁しているのは洋学紳士君なのである。
洋学紳士君は、「思想という部屋で生活し、道義という空気を呼吸し、論理の直線のままに前進して、現実のうねうねコースをとることを潔しとしない哲学者」ということになっていて、これこそ彼の自画像なのだ。
中江は、洋学紳士君があまり理想に走りすぎて現実を無視しているから、自分としては同調できないと断っておいて、この本の中で延々と洋学紳士君に自説を展開させている。これが中江のよくやる手なのである。彼は本来原理主義者であり、純理主義者だから、本質は過激な「危険思想家」なのだ。だが、聡明な彼は自分の本質をさらけ出すことの危険を常に意識して、自説を述べるに当たって複眼的な見地を披露するのである。急進論と穏健論を併置しておいて、自身を穏健論の側に置くのだ。しかし彼の真意は急進論の側にあるのである。
ところで、洋学紳士君=中江兆民が「三酔人経綸問答」のなかで展開する非武装平和論は、「国民同盟会」の方針と真っ向から対立するものだった。彼は、民主国家が増えてくれば世界国家が生まれ、人民に犠牲を負わせるだけで百害あって一利もない戦争は消滅すると説いていたのである。
中江は今日のリベラル派の主張を先取りするような理論を展開していたのであった。人も社会も永久に進歩し続けるという強い信念を持っていた彼は、世界国家が成立すれば戦争がなくなるだけでなく、刑法も変わり、死刑制度は消滅すると予言している。
洋学紳士君の論敵豪傑君は、「三酔人経綸問答」のなかで、ほぼ「国民同盟会」の主張に近いような発言をしているから、今や中江は洋学紳士君の立場を捨てて、豪傑君のそれにスライドしたような印象を受ける。
豪傑君は、失業武士たちに活躍の場を与えるために朝鮮に出兵すべきだと強調した西郷隆盛の征韓論のようなことを言っている。国内には「新しずき」もいれば、「昔なつかし」派もいる。「昔なつかし」派を動員して中国大陸に攻め込んでここに首都を移せば、日本には「新しずき」の民権派だけが残ることになって、お互いに都合がいいじゃないか、というのである。
自由民権運動の輝かしい理論家中江兆民は、事業に手を染めるようになってから業界と歩調を合わせて反動化し、左翼から右翼に転向したように見える。だが、事情はそれほど簡単ではない。彼が「国民同盟会」に加入したのは、同会が反政友会の旗幟を明らかにしたためなのだ。
中江は、自由党がかっての敵伊藤博文に身売りして政友会になったことに怒りを感じていたから、政友会に反旗を翻す団体にはすべて好意を感じていたのである。
しかしながら中江が「国民同盟会」に加入したことで「反動陣営」に走ったことは否定できない。だが、彼は死期を悟ってから、再度転向して本来の姿に戻るのである。
明治34年、中江兆民は55歳になっていた。
この年の3月に商用で大阪に旅した中江は、仕事を終えて休養のため和歌浦に遊び、ここでノドに激痛を覚え呼吸困難に陥るのだ。すぐに大阪に戻って医師の診察を受けた彼は、ノドの癌と診断され、余命一年半と宣告されるのである。
5月末になると、窒息を避けるために気管を切開する手術を受け、気管に銀管を挿入されている。この結果、彼は言葉を話すことが出来なくなり、筆談で意志を通じることになる。食物も固形物を受け付けなくなったので、豆腐などを常食とするようになった。
襲いかかってくる痛みを忘れるためには、ペンを取って原稿を書いているのがよかった。それで彼は、死後に発表することを予定して「生前の遺稿」と題する本の執筆に取りかかる。内容はその時どきに思いつくことを題材にした随想録で、好きだった義太夫や芝居について論じるかと思えば、政治・経済の時事問題や人物論に触れ、新時代に生きる日本人の心得について書くというふうだった。
このかなりの分量がある原稿を、彼は8月のはじめには完成しているから、相当乗り気になって筆を進めたことが分かる。兆民がこの原稿を見舞いに来た弟子の幸徳秋水に示したところ、幸徳はこれを博文館に持ち込み、翌月の初めには「一年有半」という題で出版されることになった。すると、これがベストセラーになるのである。
病床で痛みと戦いながら書いた本だから、平生の持論を書き綴っただけのものである。だからこそ、この本には中江兆民という人間の実像が過不足なく現れている。例えば、彼は自分の病気についてこう書くのである。
自分は今業病にかかっている。東京の自宅には、借金取りが来たり執達吏が来たりしている。このように内憂外患が降りかかるのは、自分が明治の社会に不満で、筆や口で攻撃してきた罰が当たったのだろう。だが、自分は、これからもへこたれることなく罵詈病を続けるつもりだ。罵詈病こそ、自分の宿業なのだから・・・・
確かに彼は内憂外患が降りかかる中で、へこたれてはいない。と言って、怒りにまかせて罵詈病を発揮しているわけでもない。淡々と、日本人の弱点や明治社会の問題点を指摘し続けるのだ。
彼が繰り返し指摘するのは、日本人が常識に富み、小利口ではあるけれど、それ以上には決して出ないことなのである。言い換えれば、日本人は哲学を持たず、一貫した原理で動くことがないことを論じている。
兆民はいう、欧米と違って日本には宗教上の争いは少ないし、大政奉還と言うことになれば三百の諸侯が先を争って政権を新政府に返上している、血を流さずに時代を先へ進めるのは日本人が賢明であるためだ、が、これは裏を返せば哲学の不在を示している、と。
西欧では、封建時代に封建社会を転覆させるような思想や運動が生まれている。しかし日本には、長い封建時代を通して封建制を否定するような思想も運動もついに生まれてこなかった。国民が哲学を持たず、ひたすら小利口に生きてきたからだ。
哲学を持たない日本人の軽薄さを指摘してきた兆民は、政党政治の混迷もこうした弱点の現れだと断じる。藩閥政治と闘ってきたはずの自由党や改進党が簡単に政府に懐柔され、果ては伊藤博文に政党ごと身売りするような無惨なことになるのも、政党政治家が目先の利益に目がくらんで大局を見通す哲学を持たないためである・・・・
そして藩閥政府の横暴に触れる段になると、兆民はもう、それまでの平静な調子を保ち得なくなる。藩閥に対する兆民の怒りは尋常ではないのだ。彼は「山県は小黠、松方は至愚、西郷は怯懦、余の元老は筆を汗すに足る者莫し。伊藤以下皆死し去ること一日早ければ、一日国家の益と成る可し」とまで言っている。
自由民権運動家の大半が牙を抜かれて政府にすり寄っているときに、兆民だけがなお権力に対して毅然たる姿勢を保持し続けているのである。
「一年有半」を読んでいて、調子が変わってきているなと思うところもある。例えば、兆民が礼節を守ってまじめに生きることを説いている点で、第一議会にドテラを着て出席した兆民が、今や婚礼・葬式に着流し姿で出席する者が増えてきた現状を嘆いているのだ。彼は一般庶民に礼節を守らせるのも為政者の心がけるべき点だといっている。
真面目に生きよというテーゼは、この本の各所で語られている。欧米の人士ではニュートンやラボアジエ、日本人では井上毅・白根専一を真面目人間の典型にあげて敬意を払い、繁栄する国の国民はみな真面目だと教訓をたれる。
こうしたくだりを読んでいると、中江兆民という男の本質が静かな合理主義者だったことに思い当たるのである。21歳で上京するまでの兆民は人と争うことの嫌いな「君子」で、女児のように温和だった。実業に従事するようになった45歳以後は、酒を断ち身を慎んで良識に富んだ模範的紳士として行動している。
奇人の名をほしいままにした壮年期にも、彼はしばしば旅に出て孤独になることを求めたものだった。その理由を彼は、自分には昔から仙人志願の夢があるからだと語っている。「虚無海上の一虚舟」とは自らを規定した彼の言葉である(松本清張が中江兆民の評伝を書いたのも、「虚無海上の一虚舟」という言葉に惹かれたからだった)。
彼がマイホーム人間だった理由も、「虚無海上の一虚舟」という孤絶感から来ている。時代に同化できず孤絶感を抱いて生きる人間は、マイホーム主義者になる傾きがある。森鴎外もそうだったし、中江兆民もそうだった。
フランス留学中、兆民は月に二回ずつ、欠かさず故郷の母に手紙を書き送ってその安否を気遣い、自身の無事を知らせているし、帰国後も「余の生涯の楽しみといふは、一人の老母に安楽をさせ一人の老母をして随意に此の世を送らしむるより外なし」と語っている。
子供も可愛がった。兆民の避暑法は子供を盥の舟に乗せて、池の中を押し回ることだった。少年時代の彼は独りで井戸の中に入って暑さをしのいだけれども、父親になってからは父子相楽の方法を案出したのである。
 息子の丑吉と
息子の丑吉と「一年有半」の出版後、兆民の病状は悪化した。そんななかで彼は次の著作に取りかかるのだ。このときの様子を幸徳秋水は「続一年有半」の序文に次のように書いている。「日本の名著・中江兆民」(中央公論社)には、その口語訳が載っているので、そこから引用してみよう。
「切開した気管の呼吸はたえだえであり、身体は鶴のように痩せているが、ひとたび筆を取れば一潟千里の勢いである。奥さんをはじめみんなが、そんなにお書きになると、とりわけ病気にさわりましょう、お苦しいでしょうと言っても、書かなくても苦しさは同じだ、病気の治療は、身体から割り出したのでなく、著述から割り出すのだ、書かなければこの世に用はない、すぐに死んでもよいのだと答えて、セッセと書く。
疲れれば休む、眠る、目がさめれば書くというふうであった。病室は廊下つづきの離れで、二部屋の奥のほうに、夜も一人で寝ておられる。半夜夢醒めて四顧寂蓼として人影なく、喞々たる四壁のこおろぎの声を聞くと、すでに墓場にでも行っているようで、心が澄みわたって哲理の思考にはもっともふさわしいから、たいていは夜中に書くとのことであった。
そして日に一時間か二時間かで、病気の悪い時には二、三日もつづけて休まれたが、九月十三日からはじめて、わずかに十日ばかりで、二十二、三日には、はや完結を告げていた。いまさらながらその健筆、じつに驚くべきである。」
こうした無理がたたって病勢は急速に進み、兆民はもう仰向けになることも、横を向くことも出来なくなった。喉頭部が腫れ上がったため、俯せになり両手を枕に置いて頭を支えているしかなくなったのである。彼は「続一年有半」完成後、三ヶ月と持たずに永眠している。
「続一年有半」には、「一名無神無霊魂」という副題がついている。
副題が示す通り、これは彼の信条とする唯物論哲学を述べたものである。彼の唯物論はフランス留学中、フランス唯物論の影響を受けて以来のものだと思われるが、僅か十日で書き流したものだから、中学生にも分かるような平易な内容になっている。
われわれが生きている宇宙は、最初からこうした形であったのであり、誰が創造したものでもない。宇宙を形成する元素は、転々と形を変えて存在し続けるから、この宇宙に終わりというものはない。物質は不増不減、宇宙は無始無終、永遠に存在するのがあるとしたら、元素によって組成された「モノ」だけである。
人間も元素で組成されている。人間の本体は物質で、精神はその作用に過ぎない。だから、人間が死んでも霊魂は残るというような考え方は、唐辛子がなくなっても辛みは残る、あるいは太鼓がなくなっても音だけは永遠に残ると言うに等しい妄言なのだ。
人が死ねば、その意識は無に帰して痕跡をとどめない。シャカ・イエスの霊魂は死ねば忽ち無に帰するが、「路上の馬糞は世界と共に悠久で有る」。生きているうちは自己社会の改善につとめ、死んだら綺麗さっぱり無に帰する。これ以外に入間の生き方はあるか。
「続一年有半」は、こうした単純明快な原理を比喩を用いながら多方面に押し広げるのである。
この世界は、見た通りのもの、これだけのものでしかない。人間社会を規制する永遠の道や規範のようなものはない。神や仏もいないとしたら、社会は誰によってでもなく人間自身の努力によって良くして行くしかないではないか。彼は癌にかかって余命三ヶ月足らずという段階で、泰然としてわが国最初の唯物論哲学入門書を書き、ありもしない絶対者などに頼ることなく、自力で世界を変えていくことを世に訴えるのだ。
死が目前に迫っているにもかかわらず、彼は個人的な安心立命の必要やら、「死後の自分の都合」を考慮に入れて思考しなかった。人類のために甘い夢物語を語ることもなかった。彼は所与の単純平明な事実を基盤とし、万人の納得する公理に従って考えただけである。その思考の赴くところがどうなろうと、その結論から逃げなかったし、その帰結をごまかしたりしなかった。
人間の問題は人間自らの手で処理し、「自己社会の不始末」は自分の手で処理して行くしか方法はない。すべては自分の手で播いたタネである。責任を他へ転稼する訳にはいかないのだ。
唯物論は、合理主義・純理主義の行き着く先にある哲学である。兆民はためらうことなくこの哲学を受け入れたが、唯物論を受容するには、精神や魂の問題についてある種の見切りが必要だし、人生観上のいさぎよさも求められる。いさぎよさという点で、兆民ほど徹底していた人間はほかになかった。
唯物論を受け入れ、自己と世界に対してキッパリ見切りをつけたときに、内面の静謐が訪れる。物もクリアに見えてくる。兆民が明治という時代をリアルに眺め続けることが出来たのも、唯物論者の静謐な目があったからだった。
元々、中江兆民は孤独を好む物静かな人間だったから、啓蒙家・民権運動家として活動を続けるためには、本来の自分を踏み出したところで別の人間になる必要があった。シャイで小心な人間は、追いつめられると大胆な行動に出る。それと似た心理で、彼にとって異界と感じられる政界にあって、兆民は本来の性行とは反対の奇人の役を演じ続けたのである。時代に対する怒りが激しくなるにつれて、彼の奇行も激しくなっていった。
彼の奇行がしばしば行き過ぎてマゾヒズムを感じさせるほど陰惨な色彩を帯びる。不自然な自己劇化を繰り返したためである。
学生時代の私は、啓蒙家・民権運動家としての兆民に目を奪われて、彼が二重底の人間だとは思い至らなかった。中江兆民には、マスコミをにぎわす奇行家という面と物静かなマイホーム主義者という面があり、前者は後者によって支えられていたのである。21歳で上京するまでの兆民と、政界から退いて実業に従事した45歳以後の兆民は謹厳実直なマイホーム主義者だった。彼の生涯は始めと終わりで繋がっている円環型の構造をしており、奇人中江兆民はその上に咲いたあだ花だったのである。