刈り入れ前
水田の稲の色は、刻々、変化して行く。刈り入れの直前には黄色になるが、その手前の段階では、「黄緑色」といった色合いになる。これは濃密な印象を与える色で、この時期にこうした濃密な色彩を備えた植物は、水田の稲以外には存在しない。以下の写真によって、水田の稲と、周辺の木の色、草の色とを比較していただきたい。

上下二枚の写真は、時期を異にしてほぼ同じ位置から撮ったものだ。稲刈りの前と後では、感じがガラリと変わっていることが分かるだろう。

美和ダムの奥にも、下図に見るような水田が広がっている。山奥の高地に、帯のように細長くのびた平地があり、それがすべて水田になっている。人家は平地の端についている道路の両側にあるだけ。私がこの地を訪れたときには、あたりはひっそりしていて、道路にも、水田にも、ほとんど人影を見なかった。

山また山、そんなところに、まるで碁盤そっくりな田んぼがあった。周りは落ち込んだ沢になっていて、その中にほぼ正方形の田がセリ上がり舞台のように浮き上がっていた。

以上見てきたのは山奥の水田だった。次は市街地のすぐそばまで迫ってきている田んぼで、これらは天竜川に流れ込む支流のほとりに雛壇状にならんでいる。中央に見える樹列が支流の位置を示している。この水を利用して川の両側に田んぼを作っているのだ。

天竜川流域の平坦部に開けた水田は、耕地整理事業の効あって碁盤目状になっている。ここも一面黄緑の水田で埋め尽くされている。

野面を埋めるのは黄緑の稲田だけではない。下に見るように真っ白な田んぼもあちこちにある。白く見えるのは転作用の作物、蕎麦の花だ。

下図。段丘から平地に向かってなだらかに傾斜している。その緩斜面が刈り入れ前の稲田で埋められ、大河が流れるように見える。
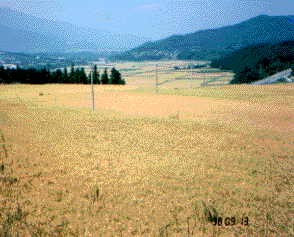
今では案山子もあまり見られなくなった。たまに見かけると、足を留めて眺めるほどになっている。

下の案山子はよくできている。頭をネッカチーフで包んで、若い女性が手を広げて立っているように見える。

伊那谷では、刈り取った稲はハザ木に架けて干しておくのが普通だが、湿田ではそうしたことをしないで稲を集めて半開の傘を並べたようにしておく。どうしてこうするのか、寡聞にして知らない。
