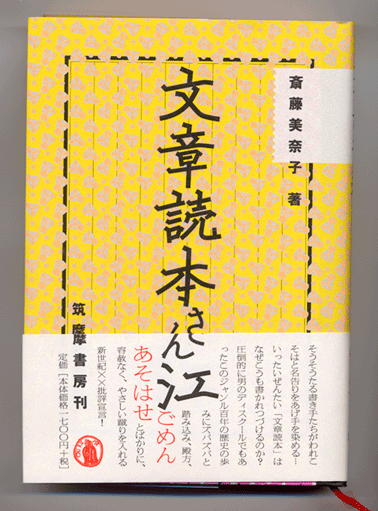女の毒舌 中野翠 斉藤美奈子は、女の毒舌について、こう書いている。
「男はバカだから」ってなことを男の人は年じゅう自慢げにいうくせに、同じ指摘を女性に面とむかってされると頭に血が上るらしい。いわれなれていないのかな、みんなすぐ怒る。そんなに打たれ弱くてはいけない。女どうしの茶飲み話なんか聞いたら憤死しちゃうぞ。
実際、おんな三人寄って男どもをこき下ろしているところを本人が聞いていたら、その場で卒倒しかねない。情け容赦がないとはこのことで、相手を一寸刻みに切り刻んでおいて、さいごに回復不能のトドメを刺してしまうのだ。
こうした辛辣な毒舌が、外部に漏れることのないのには、きっと理由があるに違いない。その問題は後で考えてみることにして、ここではまず「偽天国」(中野翠)と「あほらし屋の鐘が鳴る」(斉藤美奈子)という二冊の本を読むことから始めたい。
行きつけの古書店の100円コーナーに並んでいたこの二冊の本を買う気になったのは、私の頭に中野翠・斉藤美奈子の二人が辛辣なコラムの書き手として記銘されていたからだ。彼女らは新聞・週刊誌・雑誌などにコラムや短いエッセーを書いていて、それを興味を持って読んだ記憶があるのである。
この二人は経歴の面でもよく似ている。中野翠は早稲田大学政治経済部を卒業後、雑誌編集者を経てコラムニストになり、斉藤美奈子は成城大学経済学部を出て編集者を経て評論家になっている。
似ているといえば、本文の中に自分のミーハー性や愚かしさを白状して読者の共感を呼ぼうとする手法も似ている。二人は、目線を低くして、そこらの大衆の一員という立場から、斯界の大物を狙撃する戦略を取るのだ。たとえば、中野翠はこんな風に書く。
まったく自慢にはならないことだが、私は睡眠時間が異常に長い。「平均睡眠時間をヒトケタ台に!」というのは、もほや本人にも信じられなくなっている永年の悲願だ。たまに早起きすると、安心してついつい昼寝してしまうので、かえってトータルの睡眠時間が長くなってしまう。まずい。
斉藤美奈子の方は、こうである。
日曜日の朝七時台といえば、あなたはまだベッドの中でしょう。もちろん私も原則としては寝ています。が、たまに早起きした(か前の晩から起きていた)朝は大忙しだ。七時半から「電磁戦隊メガレンジャー」をみて、八時から「ピーロボカブタック」をみて、八時半から「週刊子どもニュース」をみて、九時から「ゲゲゲの鬼太郎」をみて、九時半にまた寝る……。
やれやれ、なんでこんな変な習慣になっちゃったのか。困ったものです。
本文の中でさんざん毒舌をふるった後で、語調を和らげて融和的な「あとがき」を記すところも似ている。アグネス論争でフェニミズムを叩いた後で、中野翠は、こう書くのだ。
柄にもなくコワモテで「女」と「進歩派」への悪口が多くなってしまって自分でもあきれているが(そしてまた今はこの二つが同義語だったりするのよね)、愛すればこそと受け取っていただきたい。「女」と「進歩派」が嫌いなのではない。たんに〝エラソ一にする馬鹿″を憎んでいるだけです。自分で思いっきりエラソ一にしてるくせにね。
オヤジたちを思う存分からかった斉藤美奈子の弁明は次の通り。
大人の男性をからかうような論調に偏っているのは、初出媒体の性質上、女性の読者とわかちあえる話題を意識したためで、べつに 「二〇世紀は『お
やじの世紀』であった」と思っているわけではありません。女子社員が仕事をサボって給湯室でおしゃべりしている、そんな「戯れ言」 の集積と思ってくださればいいでしょう。
だが、二人が似ているのはここまでで、執筆する際の両者の姿勢にはかなりの差がある。年齢のせいか、中野翠の方は無用の敵を作るまいとする配慮を怠らないのに反し、斉藤美奈子は女にあるまじき不適な面構えで、敵が何人生まれようと一切頓着しないという闘志満々たる態度を取っている。
「偽天国」を開くと、中野翠がいかに相撲取りの大乃国に夢中になっているか縷々書いてある(この本は15年前に出版された文字通りの古本だから、こんな骨董品みたいな名前も出てくるのだ)。彼女が自らの愚かしいファン心理を大げさに披瀝してみせるのも、自分にはこんな脳天気な面もあるのだと広告するためであり、読者に背面から媚びるためなのである。
そして自らの悪口癖について、
今さらここで書くまでもないが、私ほ悪口は大好きだ。私は(ほとんど生まれた時から)世の中のいろいろなことを笑いものにすることが大好きという業病に憑かれている。世の中を笑いものにせずにほいられないところ、私は自分を「ワル」だと思う。
と説明するのも、悪口を言った相手の感情を少しでも融和するためなのだ。彼女の本には、この種の気配りが多すぎるのである。
アグネス論争についても、一席ぶった後で、必ずと言っていいほど「確かにお調子者の私、挑発に乗ってつまんない話書いちゃったな。私は<活字のコメディアン>をめざしているのにね。笑える話でなくてすまぬ。もう、とうぶんアグネスのアの字も書かないぞ」というような言葉を書き加える。
知名の著作家を取り上げて批判した後では、判で押したように「私この人の作品、とても好きなのですが」と付け足すことを忘れない。知名人を敵に回すことを警戒するだけではない、読者の非難にも神経質に反応する。その気持ちを彼女は次のように率直に告白する。
小心者の私は、「女らしくない人」(この言葉には一番傷ついた!)とか、「非常識な人」とか、「イヤミな女」とか書かれた手紙には、簡単に震えあがった。むきだしの敵意がこわかった。まるで濡れぞうきんをいきなり顔に押しっけられたような気味の悪さも感じた。
注目すべきは「女らしくない」と言われれると一番傷つくという部分である。中野翠は、早稲田に在学中は社研のメンバーで、学生運動もやっていた。その彼女が、今やフェニミズムを目の敵にして、「女らしくない」といわれると、一番傷つくというのである。
ここに中野翠の本質が露呈しているように思う。
彼女がむかし、反体制の旗を振り、世俗を軽蔑して見せたのは、それがトレンディーだったからであり、今、サヨクを小馬鹿にしてフェニミズムに冷笑するのも、それがトレンディーになってきているからなのだ。その昔、学生運動の闘士だった女子学生が、今や女らしい女を気取る。これは、ガンクロルックで六本木を徘徊していた女の子が、顔の塗料を落として、いいとこのお嬢さんを気取るようなものではないか。中野翠に対しては少々酷な言い方をしてきたが、「偽天国」にも見るべきところが少なくない。たとえば、浜田幸一(ハマコー)をサンプルにして「傲慢度の高い人間は卑屈度も高く、傲慢度の低い人間は卑屈度も低い」という「法則」を提唱しているあたりがそれである。
つまり、ふだんやたらとエラソ一にふんぞり返っている人間は、ちょっと立場が変わると、平気で人にべコペコしてしまう。また逆に、ふだんやたらとペコペコしている人間は、ちょっと立場が変わると平気でエラソ一にふんぞり返ってしまう(日本人全体の、白人社会に対する態度とアジア人社会に対する態度の激変ぶりなど象徴的)。
斉藤美奈子 1 中野翠がオモテに辛口コラムニストという看板を掛け、裏で世俗との妥協をはかっているとしたら、斉藤美奈子は表も裏もない辛口評論家である。彼女は中野翠よりも一つ下の世代に属しているため、数多い毒舌女のなかでは一番の若手に属する。
斉藤美奈子の著書「モダンガール論」に、彼女の恩師である成城大学経済学部教授が解説を書いている。
斎藤さんが入学した頃は、「大学紛争」から何年も経ち、キャンパスはとっくに静けさを取り戻していました。今でも思い出しますが、彼女ほその頃から野次馬精神が旺盛でしたので、「私たちは祭りの後の世代だ」と、さかんに口惜しがっていましたね。「女性問題研究会」を立ち上げて、派手なタテカンを出して一人で気を吐いていました。空疎であったにせよ、騒々しくて、ノリの良かったあの「祭りの時代」に遭遇できなかったのは、ご本人にとっては気の毒なことでした。
私は斉藤美奈子について誤解していたようである。彼女が全共闘やフェニミズムを批判しているので、彼女はこれらを過去の遺物として葬り去ろうとしていると思ったのである。フランス革命時代に活躍した百科全書派の血を引く彼女なら、団塊世代の反体制運動を古くさいアンシャンレジームと決めつけても不思議ではない。
ところが、彼女の恩師の懐旧談によれば、斉藤美奈子は全共闘的反逆精神の持ち主らしいのである。卒業論文が丸岡秀子の「日本農村婦人問題」に触発された農村婦人史をテーマにしていたと聞けば、なおさらこの印象が強まる。
斉藤美奈子本に附せられた別の解説を読んでみよう(米原万里による解説)
彼女の批評は斬新で刺激的ですから、最近では多くの新聞雑誌で見かけます。おそらく、あまたのお誘いがあるものと推測します。ところが、テレビや文学関係のパーティーなどでは決して彼女の姿を見かけたことがない。自己顕示欲や虚栄心、ちやほやされたい気持ち、群れたい気分、などなど並の人なら容易に流されてしまう。そういうスケベ心を禁欲している。心地よいかもしれないが、批評家にとっては命とも言える舌鋒を鈍化させうる、ギヨーカイ人との人間関係が生まれるのを極力避けているのではないかと穿っています。どうです。食えないでしょう。
斉藤美奈子がメディア関係のパーティーに顔を出さないのは、非社交的な性格からでもないし、下手に知人を作って折角の舌鋒が鈍ることを警戒したからでもあるまい。彼女は俗なるものが嫌いなのである。多少とも人間嫌いの傾向を持っていないと、斉藤美奈子のような斬人斬馬調のコラムは書けないのだ。
斎藤氏以前にも女性の「率直な辛口評論家」はいましたし、結構もてはやされてもいましたが、彼女の登場とともに完全に色あせてしまいました。単に自分の好き嫌いを何の説明も根拠も示さず(せず~)に表明するという、己の好みと感受性を疑いすらしない幼稚な倣慢を、「率直な」「歯に衣着せぬ」と重宝がられていたのですね。
ところが、斎藤氏は、胡散臭いものに対する嫌悪感を隠さないと同時に、その嫌悪感の生まれる原因をもちゃんと突き止めようとする。妹尾河童の自伝小説『少年H』に関する本書の批評など、その最たるものだし、柳美里の作品について、「いつも軽い不快感を覚える」とドキッとするほど率直な感想を述べると、それに続けて、「『フルハウス』に出てくる失語症の少女。『もやし』 に出てくる知的障害のある青年。こういう種類の人物に対する視線に、無意識の差別感、といって悪ければ『鈍感さ』を感じちゃう」と、その根拠を示してくれるのです。
これは同じく女性毒舌評論家として知られている米原万里が、「最強無敵の毒舌評論家」と題して「読者は踊る」の末尾に書いた解説の一節である。確かに、男女を問わず斉藤美奈子を凌駕するような辛辣な評論家はいない。
斉藤美奈子
想像するに、小学校時代の彼女は学校の図書室から毎日一冊ずつ本を借り出して読んでいた読書家だったのである。それで、大岡昇平同様、「字が読めるようになってから、人から教えられることは何もなくなった」のである。学ぶべきことは、皆、本から自力で習得するようになったのだ。
旺盛な読書は中学校に入ってからも続き、空威張りする男の子がバカに見えて仕方がない。それで彼女は、「ヒーローは男だけの専売特許か」という問題を巡って男子生徒と激論を交わしたりする。
高校では、読書範囲を広げてマンガや文学書以外にも雑多な本を読むようになった。面白いと思えばサイエンス本、左翼本、哲学書などもどんどん読み、思想的にそこらの大学生も太刀打ちできないほどになる。当然、受験勉強はお留守になり、大学の選択も限られるようになる。彼女は女の子好みの文学部に行く気にはなれなかった。それで、女だてらに経済学部に進むことになる。
大学に入ってからは、大学紛争が終息して静けさの戻ったキャンパスで、全共闘の生き残りのような活動ぶりを見せる。
卒業後、活字中毒の彼女が、編集者の道を選んだのは至極自然な成り行きだった。児童書編集の傍ら書き上げた「妊娠小説」によって、彼女は新進評論家として注目されるようになる。コラム専門のB級評論家から、押しも押されぬA級文芸評論家になったのである。
2
古書店の100円コーナーで購入した「あほらし屋の鐘が鳴る」に話を戻せば、この本を買ったときには斉藤美奈子が「最強無敵の毒舌評論家」であることを知らなかった。だから、何気なしに最初のページを開き、ものの数ページも進まないうちに(これは)と目を見張ったのだ。冴えているのである。
第一章は「ハードボイルドな彼」となっていて、江戸川乱歩賞と直木賞をダブル受賞した「テロリストのパラソル」を例に挙げて、中年の男性がハードボイルド調の推理小説を愛好する現象を分析している。
ハードボイルドの国は「中年すぎた男の夢」をあられもなくテンコ盛りにし
た非現実的な世界。分別のあるおじさまがたがふと現実を忘れ、主人公に感情移入してウットリと夢見心地になるために建設された国なのですね。バカじゃないの、などといってはいけません。こういうジャンルなら女性用のだってちゃんと用意されている。はら、お金持ちでハンサムな青年が突然あらわれる物語が……。
ハードボイルドとは男性用のハーレクインロマンスなのだ、と考えれば疑問の半分は解決するでしょう。まあ、ハーレクイン=社会的に差別され、読者は陰でコソコソ読む。ハードボイルド=社会的に認知され、ときには立派な賞までもらえる、という差はあります。しかし世の中は大人の男が仕切っているのだから、多少の不公平は仕方ありません。
ハードボイルドは男性向けハーレクインだと指摘されると、(そうだよな)と首肯せざるを得なくなる。そしてこの本には、読んでいて首肯せざるを得ない指摘が次から次と出てくるのだ。
斉藤美奈子が標的にするのは、偽良識であり、習慣的な思考様式であり、男性優位社会であり、業界人のなれ合いであり、利口ぶったバカである。
この本が出版されたのは、今から5年前で、その頃には歴史教科書が論議の焦点になり、渡辺淳一の「失楽園」がベストセラーになっていた。彼女は当然これらの問題を俎上に乗せる。
戦後の歴史教育を自虐史観に基づくものだと糾弾して、東大教授藤岡信勝らが「教科書が教えない歴史」という本を出した。これは教科書には出てこない「日本人の素晴らしい業績」を列挙した本で、斉藤美奈子はこの本に出てくる日本人の業績なるものを一つ一つ検証していくのである。一例を挙げる。
【景山英子】
◆『教科書が教えない歴史』自由民権運動が盛んだったころ、岡山の集会で「民権大津絵ぶし」 の弾き語りをする一五歳の少女がいました。景山英子です。そのころ、お隣の朝鮮は清国の傘下にありました。自由党の人々は、朝鮮の独立を助けてやろうと考え、半島で爆弾事件をおこすことを計画しました。景山英子もこの計画に加わり、女ならあやしまれまいと汽車で爆弾を運ぶ役目を買ってでたのです。ときに彼女は一八歳。途中で計画は発覚し、一同は逮捕されてしまいました。しかし、彼らの行動は国民の同情をよび、景山英子は東洋のジャンヌ・ダルクといわれました。パチパチパチ。
これじゃ、景山英子はB級スパイ映画に出てくる安っぽい女工作員そのものです。いったい彼女は、ただの 「歌う爆弾娘」だったのでしょうか~ 残念ながら、そうではありません。◆『教科書が教えない歴史』が教えない歴史
そもそも景山英子が運動に加わったのは、女性解放を志していたからです。この事件で四年間投獄された後、彼女は自由民権運動の限界をさとって社会主義者となり、女性の権利をさらに訴えつづけました。景山英子はおじさまがたがもっとも苦手とするタイプの女性、あの「青踏」より三〇年も早くあらわれた日本のフェミニズム運動の先駆者、だったのです。
歴史教科書論争については、斉藤美奈子は「読者は踊る」でも取り上げている。彼女は両派を藤岡信勝派と家永三郎派と命名して、双方の論点を検証し、「新しい歴史教科書をつくる会」(藤岡派)の主張は古めかしく、これなら会の名称を「古い歴史教科書にもどす会」にした方がいいよと皮肉っている。
にもかかわらず、世間的には論理に破綻の多い藤岡派の方が優位に立っている。これはなぜかと彼女は反問する。
ではなぜ、藤岡派が幅をきかせているのか。おそらく家永派的な(あるいは岩波・朝日新聞的な~)歴史観が浸透し、その優等生ぶりにも飽きはじめた今日、それをキッパリ否定してみせる言説が、新しいもん好きの人々、特に出版業界人には新鮮に映ったのだと思います。
加えて藤岡派は、広告代理店的な宣伝が上手です。得意技は単純明快かつ刺激的なキャッチコピー。暗黒史観。自虐史観。反日史観。コミンテルン史観。東京裁判史観などなどのキーワードを機関銃のように連射して、読者の気分を高揚させます。つまり講談みたいに「おもしろい」のです。
両派の論争を軍配片手に観戦しながら、彼女は「左翼にはもはや未来はないね」と感想を漏らす。今は「正論」が通じなくなっている時代なのだから、藤岡派を叩くのに、相手側の史実誤認やアジア蔑視・女性蔑視を糾弾するようなオーソドックスなやり方を続けていたら、ますます孤立する一方だというのだ。
進歩派やリベラル派の正論は、かつてはありがたがられたが、今では、だからこそ敬遠されているというのが斉藤美奈子の現状認識である。
時代が変わってきていることに疑いはない。昔は、進歩的知識人の説く愛と平和の理論、武装放棄と国際協調の理論に多くの国民が耳を傾けていた。それは学級の生徒が級長の言葉をおとなしく聞いているようなものだった。
だが、今やその平均的な生徒たちが優等生の高邁な理想論に不信の目を向けるようになったのである。そして級長の言葉に潜む矛盾や、言行不一致に反発しはじめたのだ。「そんなお固いことを言うなよ。もう聞き飽きたぜ」と反旗をひるがえしはじめたのである。
3
斉藤美奈子は、攻撃的な論陣を張るに当たって、こうした平均的生徒の視点を借用する。専門家の愚かしさを無名の市民は鋭く感じ取る。彼女は、こうした民衆の視座を自己の立脚点にするのである。
「あほらし屋の鐘が鳴る」の鐘が何かといえば、NHKののど自慢で、レベル以下の歌い手に浴びせるカーンという鐘の音であり、斉藤美奈子はマスコミを賑わすさまざまな言説に対して、平均的日本人の視点から、カーン、カーンと鐘を鳴らすのである。
藤岡教授の「教科書が教えない歴史」。
カーン。
渡辺淳一の「失楽園」。
カーン。
中野翠のフェニミズム批判。
カーン。斉藤美奈子は、中野翠のフェニミズム批判にも、カーンと鐘を鳴らしている。俎上に載せられた中野翠の文章は次のようなものである。
私がフェミニズムに興味がないのは、フェミニズムというのは①ださくて②頭悪そうな感じがするからである。これに尽きる。/私は男女平等とか男女同権なんて「当たり前のことじやあないか」と思って育った。
もちろん時代が変わっても、相変わらず弱い立場にいる女の人はたくさんいる。しかし、恵まれている人間、努力すれば何とかなる人間が、「女=弱者」なんて言うのは嘘っぽい。まともな女だったらプライドが許さないだろう。私はプライドのない思想は美しくないし、ダメだと思う(『生意気時代』文芸春秋)
これに対して斉藤美奈子はミシガン大学の研究結果を引用しながら、中野翠的エリート女性の心理を以下のように分析する。
「あたしはそんな運動に助けてもらわなくても、自分ひとりの力でここまできた。ならば、ほかの女性にだってできるはずだ」
いるよいるよ、よくこういう人。勉強のできる優等生とか、仕事のできるキャリアウーマンのなかには特に。成功した人の常として、彼女は自分の成功は(幸運な偶然のせいではなく)自分自身の才能と努力の賜だと信じることを好む。じじつ、彼女はその地位を得るまでにひとかどの努力をしてきたので、後から続いてくる者たちが自分よりラクにその門をくぐることを好まない。
彼女は自分を成功させてくれた制度にうらみを抱くはずはなく、自分をユニークな存在として認めてくれる男性社会に敵意をもつこともない。成功者は、異なった制度のもとでは異なった勝者と敗者が出ることを直感的に知っているため、現行のルールを一部改訂して、もっと多くのプレイヤーを導き入れようとするフェミニズムを無意識におそれている。
それゆえ彼女は、女性が権利獲得のために徒党を組むのは醜い行為であると断じ、運動そのものを否定しょうとする。そうすることで自分の身の安泰をはかりつつ、自分はあのような醜く危険な女の一派ではない、と同志である男性にむけてアピールする。
事実、フェニミズムに背を向けている「独立独歩」型の女性の心理はこの通りであるに違いない。
男どもがひとまとめにしてやり玉に挙げられることもある。
角川書店が「女性作家シリーズ」という文学全集を企画したときに、6人の男性作家が推薦文を書いている。これを読んだ斉藤美奈子は、推薦文の多くが「紫式部に始まる日本文学は、今後も女性作家によって支えられて行くであろう」というようなステロタイプで書かれていることに、カーンと鐘を鳴らすのだ。彼女は、近代文学については死ぬほど細かいことにこだわる男性作家が、こと女性文学になると途端に死ぬほどおおざっぱになって古代と現代の見分けもつかなくなることに失笑する。
かれらのレトリックは、ひどく単純です。
日本文学は紫式部からはじまったから→日本文学は本来女性作家のものである。すばらしい短絡のワザですね。こんな理屈でいいなら何だっていえちゃうぞ。日本最初の支配者は卑弥呼だったから→日本の支配者には本来女性がなるべきである、とかさ。
こんな具合に、カーンカーンと鐘を鳴らし続けた結果として、斉藤美奈子は天下無敵の毒舌評論家になったのであった。
4
「あほらし屋の鐘が鳴る」が面白かったので、斉藤美奈子に対する論壇の評価を確立させた「妊娠小説」「文章読本さん江」をはじめ数冊の美奈子本を書店に発注して読んでみた。「妊娠小説」「文章読本さん江」は、両者とも、同じスタイルで書かれている。「妊娠小説」は、まず、鴎外の「舞姫」から当今の流行作家の作品に至るまで、作品の中に妊娠を取りこんでいる小説を集め(その総数は40余に達している)、リンネの植物分類学式にそれらをタイプ分けし、それぞれの特徴を記述するというスタイルを取っている。
「文章読本さん江」も同様で、既刊の多数の文章読本を集め、これらを分類し、その特徴を洗い出している。
この両書は、純然たる文芸評論で、「文章読本さん江」などは第一回小林秀雄賞を受賞しているほどだが、その論述の仕方は、ザアマスことばあり、女番長式のタンカあり、OL風のひそひそ話調ありという具合で、いつもの八方破れの話法を変えていない。例えば、こんな具合である。
妙齢の女性を平気で赤痢にかからせたり下痢させたりして悦に入っていたふうの谷崎潤一郎などは、そうとうな偏屈じじいなのである。
着眼の斬新さは相変わらずで、庄司薫以後の私小説を「僕小説」と呼ぶことにしようなどという提案は、並の評論家の思いつくところではない。斉藤美奈子の文芸評論の特徴は、自らをアマチュアの立場に置き、対象とされる作家や作品を商品テストの手法を使って鑑定するところにある。
彼女にとって批評の対象になる作品は、自分とは無関係な他者であり、市場で広く売り買いされる商品であって、評者と作品の間に感情的な関係は一切存在しない。
彼女はさまざまな評価基準を持ってきて作品を点検し調べ上げる。だが、文学的な価値を問題にするのではない。金を出して本を買う読者の立場から、その作品の商品としての特性を問うだけなのである。
子供の頃から手当たり次第に本を読み、学術的な専門書であれ、少年向けのアニメ・SFであれ、面白いと思うものはなんでも読んできた斉藤美奈子は、一種独特な鑑識眼を身につけている。彼女の内部に融通自在の統合感覚のようなものが生まれ、これをバックに批評対象に対して純実利主義的な判断を下すのである。
彼女は、どこかで自分は対象の構造に立ち入らないで、外側の現象面だけを取り上げるといった意味のことを書いていた。彼女は看板倒れの失格作品には、カーンカーンと鐘を鳴らし、腹の足しになるような実質的な読み物だけに経済合理主義の立場から軍配を上げる。
だが、こうした実利主義は、評論活動に当たってプラスにはならない。彼女が貰った賞の名義人小林秀雄は、作品の内部に踏み込まない客観批評というものを否定している。批評者は、批評する作家や作品に惚れ込み・のめり込んで、内側からその作品を生きてみなければならない。そうしみて、はじめて書く方にとっても読む方にとっても、意味のある批評がうまれるというのだ。
この観点からすると、斉藤美奈子のように、文学史上の傑作を商品として、物としていじり回すのは邪道だということになる。
同じことは、斉藤美奈子の社会批評についてもいえる。
「ひめゆりの塔の乙女たちは沖縄戦の広告塔か」という彼女の書いたエッセーがある。「ひめゆりの塔」が4回も映画になり、反戦運動の広告塔になっていることを揶揄したエッセーである。彼女はまず、吉田司の発言を紹介する。
戦争被害者のシンボルのように喧伝されてきたひめゆりの物語は <冷徹な歴史の証言というよりは、生き残った者たちが余りにテープレコーダーみたいに語り過ぎて話が様式化し、いささかお芝居じみてきた〝定番悲劇″>にすぎない。被虐的でお涙頂戴の殉国美談。<その国民的伝承のカラッポな姿>は、あの「忠臣蔵」とそっくりだ、というのである。
そして、彼女は「いわれりゃ、まったくその通り」と吉田の意見に賛意を表し、沖縄戦ではひめゆり部隊以外にも犠牲者が多く出ていることを指摘してから、こう結論づける。
戦争体験をもつ人は、いまやみんな六〇歳以上である。残り少ない人生、語り継ぐものがある方は、そりやもうガンガン語り継いでくださればよい。肝心なのは、語り継がれる私たちが、それを相対化できる程度の耳(と知識)をもつことだろう。ありがたく拝聴してなんかやるものか、と気構えるくらいでちょうどいいかもしれない。
斉藤美奈子は、このエッセーを書いてから6年後、アメリカの同時多発テロ以後の状況を踏まえて、次のように述べる。
「湾岸戦争のときと同様、米国にいかに協力するかが日本政府の最大の案件になってしまった。やっぱ、ひめゆりの悲劇に紅涙をしぼっている場合じゃないんだよな。<戦争を語り継ぐ>って何なのさ」
斉藤美奈子ともあろうものが、ここではアメリカに追随する政府べったりの姿勢を取っている。底辺にある被害者の味方をするという「うざったい正義感」をあっさり棄てて、時の権力に同調する道を選んでいるのである。
彼女もちゃんと述べているように、沖縄戦では男という男が老いも若きも防衛部隊にかり出された。女子学生も学校別に6チームに組織されて、県民が総力をあげて米軍に抵抗したのだった。その結果、沖縄県民の犠牲者は、14万人余にのぼっている。
もし、本土決戦ということになったら沖縄の悲劇が全国規模で展開し、新潟県に斉藤美奈子という才媛が出現することもなかった筈だ。沖縄の悲劇などが、歯止めになってくれたから、政府も本土決戦を回避したのである。
沖縄は戦争が終わってからも、占領軍の統治下におかれ、これを跳ね返すために県民は反基地運動で血を流さなければならなかった。
全共闘の山本義隆議長が、本土全体を反基地闘争の戦場にすることを企てたのも、沖縄県民だけに反基地闘争を押しつけて「内地」の日本人が高みの見物を決め込んでいたからだった。彼は、沖縄への借りを返すためには、本土全体を焦土にすべきだとさえ考えていた。
彼はまた、大学出が特権的な地位を占めて庶民を苦しめているとしたら、大学そのものをなくしてしまうべきだとも考えた。山本義隆の下、全国の大学生らが自らの生活拠点である大学を解体する闘争に取り組んだのも、贖罪の意識からだった。
今日の目から見れば、自己を痛めつけることによって贖罪を果たそうとした全共闘の考え方は、いかにも幼稚で非現実的である。だが、この自己犠牲の理論には、何かしら人を感動させるものがありはしないか。
ひめゆりの悲劇に胸を痛め、特攻隊員の手記に涙することは、恥ずべきことではない。そうした感動が、人をして個を超えたものに目を開かせ、健全な社会意識を育てていくのである。
文芸批評の領域で作品の構造に立ち入ることを避け、社会批評の領域では戦後民主主義を黙殺する。斉藤美奈子が、硬直した常識や固定観念にトドメを刺そうとするのはいい。しかし、それと一緒に人間の真情や共感能力まで抹殺してしまったら、元も子もなくなるのである。
5 さて、女三人寄れば、男どもを震撼させるような毒舌が飛び出すのだが、それが内輪に留まって外部に拡がっていかないのはなぜだろうか。
まず、女性が男たちになぜ辛辣な悪口を浴びせるかと言えば、つまるところ、この社会がいまだに男性優位に作られているからである。男には男の連帯感があって、仲間が失敗しても大目に見てやる。そして、女性からの非難に対しては、「奴らは責任のある地位にいないからな。だから、無責任な批判ができるんだ」とかばってやるのだ。
男たちは「責任のある地位」を自分たちで独占しておいて、女の無責任な発言を責める。男たちは無意識のうちに連帯し、女たちは砂のように孤立し分散しているという社会的な現実が、女だけになったときの彼女らの舌鋒を鋭くするのだ。
一言でいえば、男社会への共感の欠如が女の毒舌を生んでいる。
共感できないといえば、世の中を動かしている理念や思想・哲学に対しても、女性は共感していない。これらは、ほとんどすべて男によって作られた思想体系であるからだ。女性は、男たちの持って回った大議論に対して、聞く耳を持たない。そんな屁理屈よりも、目の前にある具体的な現実を先に見てしまうからだ。だが、女たちは知らなければならない、思想的な裏付けを持たない発言は、社会的な力を持たないということ、そして個人的な意趣晴らしを先行させて公的な観点を欠く発言は、その内容がいかに辛辣であっても対外的には何の力も持ち得ないということを。
女性毒舌家に通底するのは、男性的論理に対する不同意の姿勢であり、男が暗黙のうちに取り決めている契約や約束事を断固として拒否する姿勢である。だが、男を叩くには、論理によらなければならず、体系的思想に対抗するには、やはり思想体系によるしかないのである。
思想体系の核にあるのは、人間の真情であり、普遍的な情念なのだ。斉藤美奈子が、男どもの取り交わしている約束事を木っ端みじんに吹き飛ばすのはいいとしても、それと一緒に人間の真情に対してカーンと鐘を鳴らしてしまったらおしまいだと思うのである。