NHKの教育テレビをよく見ていた頃、中野孝次が出演している番組を二つ見た。その一つは、大岡昇平との対談番組で、中野は大岡昇平から戦争体験を聞き出す役をしていた。このときの中野は、かなり緊張していたようで、番組が終わるまで彼はにこりともしなかった。
今でも記憶に残っているのは、この番組でフィリピンでの戦場体験について語っていた大岡が不意に言葉を詰まらせ、涙声になったことだった。磊落でシニックな人間だと思われていた大岡が、視聴者にかいま見せた意外な一面だった。だが中野は格別動揺した様子も見せず、目に涙を浮かべた大岡の顔をむしろ険しい表情でじっと正面から見つめていた。
もう一つの番組は、高校生3名を彼の自宅に派遣して中野に自作について語らせるという趣向のものだった。前回は質問する立場だったが、今度は彼は質問される側に回ったのである。こうした場合、作家は若い読者に愛想を見せるのが通例だが、彼はやはり笑顔を全く見せず、番組が終わるまで硬い表情を崩さなかった。
そのうちに中野の「ハラスのいた日々」が評判になったので、読んでみた。
ハラスというのは、中野夫妻が横浜の郊外に新居を構えたとき、新築祝いに義妹から贈られた柴犬の名前で、子供がいない中野夫妻はハラスを実の子供のように可愛がっていたのである。
愛犬物語は、ただ犬を可愛がるというだけの内容では人を打つ力を持たない。愛妻物語もそうで、夫が妻をいかに愛しているかを書き綴ったとろで、単なるノロケ話に終わってしまう。皮肉な話だが、妻が重病にでもなってくれないと、愛妻物語は成立しないのである。かくて横光利一以来、愛妻ものといえば、病妻ものと相場が決まってしまっている。
「ハラスのいた日々」も、ハラスが志賀高原で行方不明になった4日間の騒動記や、彼が近所の紀州犬に腹を食い破られるという悲話、そしてガンにかかったハラスが死を迎えるまでの臨終記が中心になっている。
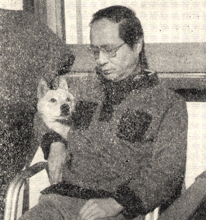 中野と愛犬
中野と愛犬雪の高原で飼い犬が行方不明になったときに、夫妻は半狂乱になって犬を探している。中野は犬がいなくなったときの気持ちを「腰が抜けたようになった」とか、「はらわたを抜かれたような状態」と表現している。そして、飼い犬に対する自らの感情を「私の半生において愛という感情をこれほどまでに無拘束に全面的に注いだ相手はいない」とまで書くのである。
ハラスが13才で死んだとき、その墓前に立った中野孝次は「私たちの40代から50代にかけての13年間がここに葬られた」と呟くのだが、こう述懐する中野孝次と、険しい表情を見せていたテレビでの彼が、どうもうまく繋がらなかった。テレビなどに出ると自意識過剰になって身構えてしまう性格だから、犬には心を開いて接するのだろうか。
一切合切が腑に落ちたように思ったのは、つい最近、「麦熟るる日に」を読了してからだった。彼は「専検」の出身なのである。
専検制度というのは、旧制中学に進むことができなかった者に検定試験を行って中学卒業資格を与える制度で、昔の専検は、難関をもって知られていた。中野はこの専検にパスして旧制高校に進み、それから戦後に東京大学に入学する。「麦熟るる日に」は、こうしたコースをたどった人間の鬱屈した内面を率直に告白したものであった。
腕のいい大工だった中野の父は、何人かの職人を抱える棟梁になった後も、子供たちを義務教育だけで終わらせ、頑として進学させなかった。成績のよかった長男も進学をあきらめて就職し、次男の中野孝次も中学に進むことを許されなかった。
父は穏和な長男より、きかん気で才覚に富んだ次男に期待をかけ、中野を手元に置いて跡を継がせようと思っていたらしい。
その頃の小学校6年生にとって、進学出来るかどうかは大問題だった。そのあたりの消息は、「麦熟るる日に」の次のくだりをを読めばわかるだろう。
進学がやがて隠しようのない問題として口にのぼりだして、一番変わったのは、それまで一つだったクラスのなかが、とげとげしく二分されてしまったことだった。わけのわからない口論やけんかがふいに起こった。放課後の掃除をしているうちに、突然だれかがだれかにホウキをふりあげたり、ゲンコを窓ガラスにとびこませたりして、しかも大抵はどうしてそんなことが起こったのか理由がわからないのだった。
進学したいという中野の気持ちは、同級生の誰よりも強かった。それは彼が同じクラスの須藤と親しくしていたからでもあった。裕福なサラリーマンの子供だった須藤は、台所のわきに3畳の自室を持ち、月々雑誌や本をふんだんに買ってもらっていた。須藤家の母親は外出がちだったので、中野は気兼ねなしに須藤の家に入り浸り、日が暮れるまで友達の部屋で読書に没頭して、「知的な生活」への渇望を育てていたのだ。
担任の教師が説得に来てくれたのに父を翻意させることができず、遂に進学を断念しなければならなくなったとき、中野は、放課後、学校の砂場に一人でいる須藤を見かけていきなり殴りかかるようなことをしている。
そういう彼を見ているうちに、突然なにか狂暴な、わけのわからぬものがうちに衝きあげてきて、ぼくはやみくもに須藤めがけて突っかかっていった。突進していった全身の力で須藤をつき倒し、のしかかり、殴りつけた。自分でもどうしてそんなことをしたかわからずに、ただ、いま自分はなにか非常に卑怯な、浅ましいことをしているのだと自覚しながら、泣きながら須藤を殴りつづけた。
この頃、家が貧しい子は小学校6年だけで学校をやめて働きに出ている。やや生活にゆとりのある商家の子供たちは、高等科に進んで2年間ソロバンなどの実務的な知識を身につけていた。中野は鬱々として高等科の2年を過ごしてから、教師の勧めで海軍航空廠技手学校に入学している。父親は中野が高等科を出てたら、すぐ家に残ることを期待していたが、彼はどうしてもそんな気になれなかったのだ。
だが、海軍工廠の上級工員を養成するためのこの技手学校は、中野の肌に合わなかった。三ヶ月ほどで誰にも相談せずに学校をやめた中野は、家に戻ってぶらぶらする生活をはじめた。父の仕事が忙しいときに彼は四分板をカンナで削る手伝いなどをして、それを見た職人が「いい跡取りができたじゃねえか、親方」と父に言ったりしたけれども、家業を嫌う中野の気持ちは変わらなかった。
母は彼がぶらぶらしているのを見て「おまえはこれからどうするつもりだえ」と膝詰め談判で責め立てる。「うるさいな、いま考えてるとこだよ」とその場逃れの応対をするものの、中野には未来が全く見えなかった。まるで闇の中で手探りしているようだった。
彼は両親や家族を愛していたが、新聞を音読して読むような父や、ただコマネズミのように働き続ける母には、遠い距離を感じていた。周りを見回すたびに、自分の生まれ育った境遇への嫌悪と憎しみが湧いてくるのだった。彼はそこから抜け出したいと焦りながら、空しく日を送るだけだった。中野は、暗い穴の底に落ち込んだような絶望感に捉えられていた。
無為に過ごす日々への悔恨に胸を噛まれているうちに、彼は近所の人妻と関係を持つようになる。だが、それも彼の焦慮を一時忘れさせるだけだった。
こうした絶望的な状況から抜け出すための唯一の出口が専検制度だったのである。彼は陸軍士官学校に合格した須藤から受験参考書一式を譲り受けて勉強を再開する。一度で専検にパスした中野は、次に旧制高校を目指して予備校に通い、いくつもの試練を乗り越えてついに九州にある高等学校に入学するのだ。
中野は、必死になって所与の現実から抜け出そうとした。すると、その瞬間から、所与の現実は忌まわしい桎梏に変わり、彼の嫌悪感をかき立てる地獄になった。そして、その嫌悪感はすぐさま自らに跳ね返って来て自己嫌悪になるのだった。
彼は父の期待を裏切り、就職した弟妹の稼ぎにも依存しながら学業を続ける立場になったのだ。中野は、家族を犠牲にして自分一人だけ上昇の階段を上りはじめたという事実から、目をそらすことはできなかった。彼の表情が自ずと厳しくなっていくのは当然だった。
彼は海軍航空廠技手学校に入学すると銃剣術の教官から目の敵にされ、高等学校に入学すると軍事教練の教官にいじめ抜かれた。戦争末期の駅では、ごったがえす乗客の中で彼だけが警官や憲兵に目をつけられ、まるで手配書に載っていた犯人であるかのように尋問を受けた。
これは中野が現世と自分の双方に、厳しいというよりはむしろ険しい目を向けていたためだった。それが彼を特徴づける暗鬱な表情になり、現実を否認するふてぶてしい人相ともなって、警官・憲兵・軍事訓練教官など小権力者たちを警戒させたのである。
テレビで見た中野孝次の硬い表情は、世に出るまでの彼の苦闘と、今なお続いている内面の葛藤をあらわしていた。
「麦熟るる日に」を読むまで、私は専検出身者の心事に思いをいたすことがなかった。中野の苦闘は、すべての専検合格者に共通するものかもしれないのである。
私は、一年間同じ教室で机を並べていた専検出身の田島のことを思い出した。
私たちが在籍した学校は、官立の学校で授業料が不要だった上に、成績上位者への給費制度もあったから、専検出身の田島は経済的な面に魅力を感じて入学して来たのだろう。だが、私は彼の人となりやその経歴については全く知らなかった。これは奇妙なことだった。何しろ、学科の定員が僅かに20名ほどの小さなクラスだったから、私たちは、北向きの薄暗い教室で毎日顔を合わせているうちに、級友の大方について、相手がどこの県の出身で、どの中学校を出ているか、というようなことを頭に入れていたのだが、田島についてだけは何も知るところがないのだ。
彼の素性が不明だった理由は、彼が級友の誰とも親しくなろうとしなかったからだ。彼は違和感なくクラスに溶け込み、総じて級友から好感を持って迎えられていながら、誰とも踏み込んだ関係に入ろうとしない。あの年代は人間に対する好悪が格別に激しい筈なのに、彼はすべての級友と差別なく平等に接し、全員ともつかず離れずの関係を保っている。それは、まさしく奇跡のようなことだったのである。
学年末に近くなって、勤労動員でクラス全員が軍需工場の寮に移ることになった。だが、そのなかに田島の姿はなかった。田島はやせ形の細身の体で、細長く白い顔をしていたから、健康上の理由で動員を免除されたのかもしれない。彼が不在になっても誰もあまり気にしなかったのは、やはりクラスにおける彼の存在仕方が特殊だったためだろう。
戦後、病気で一年休学した私は、学校に戻って今は一学年上になった以前の級友と顔を合わせることになった。その旧友の中に、田島の姿はなく、その理由について教えてくれるものも誰もいなかった。田島は私たちの前から、知らぬ間にふっと消えてしまったという感じだった。そして、私は、それきり田島について思い出すことなく今日まで生きてきたのである。
「麦熟るる日に」を読んで感じたのは、中卒の人間が専検出身者の心情をほとんど理解していないということだ。中野は旧制高校に入学して戸惑ったこととして、武道や教練の授業をあげている。旧制中学では、全員が柔道・剣道をやり、軍事教練の時間に38式小銃を担いだり分列行進の訓練を受けたりしていた。だが、中学校を飛び越して入学してきた専検出身者たちは、柔道の乱取りをしたこともなければ、鉄砲を担いだこともないのである。
つまり、専検出身者と中卒の学生の間には、共有する体験の不足という事情があるのだった。今となれば、ハッキリ分かるのだが、田島は英語の発音とか体技の点で私たちに及ばないものを感じていた反面、世の辛酸を知らない私たちになにがしかの「幼児性」を見出していたに違いない。彼が級友のすべてと、つかず離れずの関係を保つことができたのは、私たち全員を子供だと思っていたからなのだ。
私は今、田島の若き日の風貌をありありと思いだしながら、自分がこれまで見落としてきたものがいかに多いかを改めて痛感している。