詩人であるための資質
谷敬と私は、結核療養所で競い合うようにして俳句を作っていたが、数年後、大体同じ頃に俳句から離れてしまった。私はなぜ、そうなったかを、原稿用紙10枚ぐらいに長々と書いたことがある。ところが谷敬は、淡々と「俳句に対するぼくの気持ちは、いじくり過ぎてこわしてしまった玩具をかなしむ子どもに似ている」と書くのだ。
私が原稿用紙10枚に書いた内容と同じことを、彼はたった一行で表現してしまう。私の釈明が要領の悪い悪文になった理由は、形式論理にとらわれて筋を通そうとしたためだが、谷敬はそんなものには目もくれず、詩的直感ともいうべきもので本質をズバリと言い表しているのである。
去年の12月に夫人の手で編まれた谷敬詩集を読むと、こうした彼の詩人としての資質を随所に見ることができる。
彼は大都市の中枢を流れる川をながめ、その川底を語るのに「糊づけされたどぶ泥」という比喩を用いる。実に巧妙な比喩である。
「からみ合う川のよだれたちが密会している運河べりの石の河床」
これも同じ「水底へ」という詩の一節だが、「川のよだれ」という言い方は見事というほかはない。
こうした描写以上に光っているのが、人間を見る卓抜した眼で、「仕掛花火とその領域」という比較的初期の作品について、これを見てみよう。
がんじがらめにしばられて
ぼくはしゃべることもできやしない
仕掛花火は、人間存在の象徴なのである。人は権力に押さえ込まれ、人間関係のしがらみに縛りつけられ、縄がけされたように動きがとれなくなっている。そして、点火されると火花や硝煙を上げて、仕組まれた通りの図柄に「なってみせる」。
そして「ヘイワ」というような文字を暗い川の上に描いてみせるのだ。
しくじらずに燃えつきれば
拍手さえする 招待席のやつら
しゃべることもできないぼくが
時代のたくさんの支柱の上で おびえながら描くのは
意味にはぐれたぼくの衣装だ
仕掛花火はお仕着せの図柄になりすまし、歪んだ文字を観衆の前で描いてみせながら、こころのなかで別の遠い町並みを思い描いている。それは、
ぼくの文字のみえない地点で
ぼくらを気づかってくれるやさしい町並み
である。
富と権力の前で隷属を強いられている弱者は、遠いところにある自由な精神に思いをはせる。ひとは、自らの隷属を通して、解放された人々の世界を浮かび上がらせ、その純粋な美しさを際だたせるのだ。この詩は、次のような印象的な言葉で終わっている。
文字のみえない街並みのために
ぼくらがふちどる純粋な高い夜空
庶民を描くのに仕掛花火を使った谷敬は、女を描くのに壺を用いる。初めて土をこねて壺を作った縄文の女たちは、そのなかに男の知らない秘密の心を封じ込めた。そして、
ひとりになると女は 壺の暗部へ降りていった
女はこの原初の壺を持つゆえに何時までも若く、魅惑に富んでいる。この壺は女性そのものを意味し、そして子宮を暗示している。壺は、女性的なるものの象徴なのである。現代の女たちは、この壺をなくしてしまったから、老いやすく、浅はかな存在になってしまった。しかし、すべての女がダメになったわけではない。
老婆たちは夜ごと 壺を抱えて集まってきた
裏町の二階の窓に灯がともり
神さまをとりまいて岸べをつくった
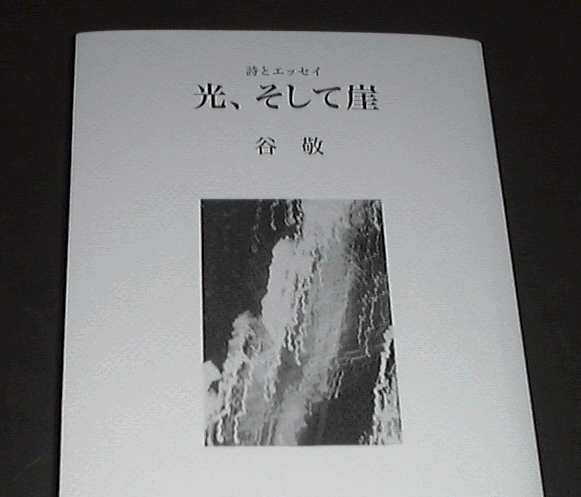 詩集「光、そして崖」
詩集「光、そして崖」
詩集を編んだ夫人は、この本に「光、そして崖」という題を付けている。題名通り、前半の作品には澄明な光を感じさせるものが多い。彼は街頭の所見をうたい、療養所の日常を切り取り、人間というものについて人類の起源までさかのぼって思索する。どんな絶望的な状況を描いても、彼は絶望していない。作品の中に一点の希望の灯をともしておくのだ。
後半の作品で私たちは、谷敬の前に立ちはだかっていた壁や崖を見ることが出来る。彼の人生は、出生直後の生母との死別によって始まるが、第二の母とも4歳で死別し、その葬儀の席上で彼は、はじめて「壁」を感じる。まだ幼かった彼は、事態が飲み込めず、「誰か、死んだの?」と質問して、刺すような視線を浴びたのである。
戦争末期に宮城県に学童疎開していた彼は、中学校受験のため上京し3月10日の大空襲を体験する。家族とも離れ、裸足になって猛火の下を逃げまどった彼は、50人ほどの被災者と一緒にビルの陰にうずくまって難を避ける。目の前で衣服に火がついて路上を転げ回りながら助けを求める者もいたが、救いの手をさしのべる者は誰もいなかった。家族と再会したら、姉は全身を火傷し、母(三番目の母)はにわか盲目になっていた。
こうした記憶を織り交ぜながら、彼は壁と崖について考える。その思索は自由にのび拡がって、読者はその後を追うのが困難になるほどだだが、結局、谷敬の思考は病気と倒産という自らの体験した二つの壁に収斂する。彼は闘病中、肺から次々にせり上がってくる血や喀痰を壁だと思った。気管の中を層をなしてせり上がってくる粘体の一つ一つを壁だと感じたのだ。そして、その血や痰を壁に向かって吐いているとも感じた。「壁に向かって吐く」という言葉は謎めいていて、分かりにくい。
この種の分かりにくさは、詩にはつきものといえるけれども、彼の次の文章を読めば、疑問は氷解する。
「壁に向かって直接吐くのではなく、血を吐くという行為は、おのれに向かって吐くのだ。おのれの生命をいたわるために身をかがめて静かに血を吐く。その前面にはいつも壁があった。沢山のベットが並んでいる部屋の中で血を吐くときは、背後からおびただしい数の視線の矢に射られているのをありありと感じる。視線は壁には当たらず、血を吐く人の背中に当たる。だからおのれのために血を吐くという行為は、背中を丸めて壁と見つめ合う位置になる。そのようにして、たくさんの人間が壁に向かって血を吐き、中にはたちまち血糊でのどを詰まらせて死んでいった人もいる」
喀血するときに病人は、同室の患者たちの目を避けて、壁に向かって静かに血を吐くから「壁に向かって吐く」のである。ここには、散文とは異なる詩に特有の作法がある。作者は実際に体験したことを、説明抜き、解説抜きで、端的に投げ出すのだ。だから、分かるものには分かるし、分からないものには永久に分からないという事情が発生する。
空襲、喀血と並んで谷敬の前に立ちふさがった壁が、事業の倒産だった。彼は倒産前後の苦渋に満ちた時期を「倒産法」という一群の詩を作ることで乗り切っている。あるかなきかの微笑を顔から絶やさなかった温厚な彼が、この詩作の中で激しい怒りをあらわにする。融資を約束しておきながら、直前になって電話一本で融資を断ってきた銀行の支店長を、彼は水槽の中の軟体動物に喩える。
三十分以内に三十万円の現金を おれは届けねばならぬ
幾度か叫び声を口の中で噛み殺しながらサインをし
おれは やっとその金を作ってきた
今このカバンの中に それはある
帳尻にその苦々しい札束を加算すると
おれの寿命はすこし延びるはずだ
金策に明け暮れする瀬戸際の日々を、彼は「のどの奥から画鋲を抜き取る」ような苦しみと表現し、皮膚をはがれるようだとも表現している。これらの詩を読めば、倒産が彼の死の遠因になっていると語る夫人の言葉も頷ける。
しかし、今更のように驚かされるのが、戦災・病苦・倒産というような険しい壁の前で血を流しながら、彼が第三者にはそれを微塵も感じさせなかったことだ。私はてっきり、彼をなに不自由なく育った良家の世継ぎと思いこんでいたのである。
空襲の猛火の中で、ビルの壁が谷敬を救ったように、詩作と詩作を通して知り合った友人知己が壁になって苦難の時期の彼を守ったのだ。
夫人は、詩集のあとがきで、谷敬の仕事上の苦労を支えたのは「詩の心」だったと書いている。そして、「(夫は)生きることも書くことも職人肌だった」と付け加えている。同感である。彼は生まれながらに詩人としての資質を持っていたが、それを花開かせたのは職人的なたゆまぬ修練だったのである。
(「光、そして崖」津軽書房 ¥2200円)