若き詩人
結核療養所で知り合った谷は、これまでに見たことのないタイプの若者だった。彼とは、療養所内の俳句サークルに加入したときに知り合ったのである。
「二十日会」と名付けられたそのサークルでは、毎月20日に作品を持ち寄り、ナマ原稿をとじ合わせた回覧誌上で合評を行っていた。会員のなかには、重症者もいて同じ療養所にいても簡単に集まるわけには行かなかったから、回覧誌を利用することになったのだ。
回覧誌に出す草稿は、各自が直接当番の会員のところに届けるか、人を介して届けるかする。谷と知り合ったのは、私が当番になったときに、彼が作品を持参して私の病室にやって来たからだった。
私は当時20代の終わりで、彼は多分20代に入ったばかりの年齢だった。彼は、背が高かった。顔から穏やかな微笑を絶やさない静かな男で、若いのに似合わず余裕のある人柄に見えた。話をしていると、時々、穏やかな微笑が消えて、考え込むような表情になる。すると、自然に表情が、思い詰めたような真面目なものに変わるのだった。純真で誠実な人柄がその表情に表れていた。
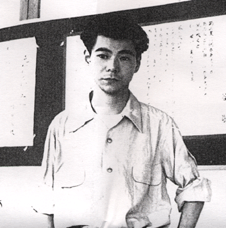 入院中の谷敬
入院中の谷敬
そのうちに、病状の安定している会員が集まって句会を開くというようなこともあり、私はほかの会員とも親しく行き来するようになった。すると、それぞれの経歴も自ずから明らかになる。相手の人生観や主義主張のようなものも、たちまち頭にはいって来る。
ところが、谷とはグループ内で一番親しくしていながら、彼について知ることは僅かしかない。彼が、自らについて語ろうとしないからだった。
私は、谷が高校に在学していた頃に発病したこと、クリスチャンであること、実家は浅草の玩具問屋であることなどを聞き知っているに過ぎなかった。
「二十日会」の会員には、在家仏教の信者や女性のクリスチャンがいて、それぞれ自分の信仰について語ったり、信仰をバックにした作品を発表したりしていた。ところが、谷は自らの信仰について口にしたことがない。自身の経歴についてと同様、信仰についても固く沈黙を守っているのである。
私たちは、青年期にある人間の常として、内にあるものを一刻も早く表白してしまわないと気が済まなかった。そんな中で、谷だけが大切なものを静かに守り育てて人に告げないのだ。彼は痛切な想いや感動を心の底深く秘めて、人にはその周辺部だけを言葉少なに語るだけなのである。
私は谷のこうした「持ちこたえる能力」に脱帽せざるを得なかった。実際、彼の表情も所作も何かをうちにじっと持ちこたえているように静かだった。私の病室にやってくるときにも、気がついたらそこに彼が来ていたというような、音のない現れ方をした。谷と話していると、教養とか知的理解力が学歴とは無縁であることが分かるのだった。私はこれまでに、彼ほどの深い理解力を持った人間を数えるほどしか知らなかった。
肺の摘出手術に成功した私は、程なくこの療養所を退院する。これ以後、私たちは文通によって互いの消息を知らせ合うことになる。
谷もやがて退院し、スカウトされて雑誌の編集者になった。彼は、俳句と平行して詩を書くようになり、詩壇の新人賞を獲得している。
その頃のことだった。谷は手紙に近作の俳句をいくつか書き送ってきたが、その中に、次のような作品があった。
「五月の水流れ水底に石ぎっしり」
「えご咲くや背高き女らはかなし」
この二句を読んで、私は直感的に彼が恋愛をしているのではないかと思った。それで、その旨を問い合わせてやると、谷は冗談混じりに「恐れ入った眼力」と私を持ち上げておいて、「窓の女」との恋愛をうち明けてきたのである。
男女別々になっている療養所の病棟には、男子病棟の患者がマドンナのように仰ぎ見ている「窓の女」がいた。谷は、男たちのあこがれの的だったその女子患者と愛し合うようになっていたのだ。
「窓の女」との恋愛についても、こちらが質問しなければ、彼は沈黙を守っていたに違いない。やがて、この恋は実ることなく終わり、谷は同じ詩人仲間の女性と結婚する。相手は大学で教鞭をとっている、とびきり上等な才媛だった。
この結婚を知らせる手紙で、谷は新婚旅行の際、私のところに立ち寄りたいと言ってきたが、結局、これは実現しなかった。
谷はその後、父のあとを継いで、玩具問屋の仕事をするようになる。私は詩人肌の彼が、玩具業界でやって行けるかどうか、一抹の不安に襲われたものの、彼ならば大丈夫だろうと思い返した。世に出てからの彼は、堅実に身を処して着々と業績を上げているのである。
患者数千人の療養所でマドンナと仰がれていた女性のハートを射止め、いまや高校中退の身で第一級の女性と結婚した。谷は、何処に行っても、周囲の人間から信頼され、愛される人間的な資質を持っているのだ。彼なら経営者になっても、それなりの結果を残せるに違いない。
しかし谷の会社は倒産した。会社がつぶれるまでには、友人に裏切られたり、いろいろな修羅場があったようである。が、彼は手紙で淡々と倒産の事実を告げ、すべての残務整理を終えた後で、口辺に苦笑いを浮かべているような筆致で「今では、関係の公庫に月*万円ずつ払っているだけです。倒産のことについて口にする者は誰もいません」と書いて来た。
谷が倒産によるショックを軽く受け流して、素早く「平常心」に戻ることができたのは、育ちがいいからだろうと私は思った。ああいう人柄は、普通の家庭からはなかなか生まれてこない。すべてに行き届いた温かな家庭で育ったから、苦難に臨んでも取り乱さない心豊かな人間になったのだ。
その後、谷と私の間の文通は途絶えた。谷が転居し、私の方も畑に建てた家に引っ越して、互いの住所が分からなくなってしまったからだ。その谷の訃報が、今年の5月18日に届いたのである。
詩人の裏側
谷は、既に3月14日早暁に急逝していたのだった。谷夫人によれば、音信不通になってから、彼は私に手紙を出したいと願っていたという。だが、それを果たさないうちに亡くなってしまった。それで、夫人は私の以前の住所宛に夫の死を告げる手紙を書いたが、宛先不明で戻って来た。夫人は諦めずに、地元の新聞社宛に問い合わせの手紙を出し、ようやくこちらの現住所を探し当てたのである。
夫人は、谷の死顔が俗事を超えてもう一つの宇宙に旅立つかのように穏やかだったと言っている。そして、夫が献体登録をしていたので葬儀は行わなかったと、付け加えていた。谷はクリスチャンらしい死に方をしたのである。
これを機に、夫人と私の間に数回の手紙の往来があり、私は彼女から谷夫妻が関係していた詩の同人誌を贈与された。更に谷が書き残した日記のコピーを送ってもらった。私はそれまで、漠然と彼はいいところで育った苦労知らずのお坊ちゃんではないかなどと考えていたが、夫人から送られてきたものを読んで、とんでもない思い違いをしていたことに気づいた。
彼の詩に「崖の話」と題する一編がある。その冒頭の部分を引用してみよう。
少年の頃
崖が大きく大きく見えたことがある
そこへ登ろうとしたからだ
それから二十数年経ったある日
崖の高さと自分の目盛りを
すばやく計算したことがある
そこから飛び降りようとしたからだ
少年の日の彼の心に映った人生は、平坦なものではなかったのだ。目の前に立ちはだかる崖のように見えたのだ。
生まれたときから、谷の前には悲しみと苦しみが待っていたのである。彼の母親は、彼を生んでから十日後に死んでいる。実の姉も小学校6年で病死しているから、結核による家庭内感染という事情があったかも知れない。母の死後、父は死んだ妻の妹を後添えにしている。叔母が、彼の第二の母になったのだ。
昭和20年3月10日の東京大空襲で、谷は浅草の家を焼失している。父は、焼け跡で露天商をして再起を図り、まだ少年だった彼もその手伝いをしている。一家協力して家業を再建して、ようやく一息ついたと思ったら、谷は結核を発病して療養所に入ることになったのだ。
療養所で彼は、肺の摘出手術を受ける。が、予後が悪く、合併症で長い間、死線をさまよっている。気管支瘻(気管支が腐る病気)と膿胸を併発し、手術をしなかった方の肺に結核菌が転移したのだ。彼は再手術を受けることになり、個室のドアには「面会謝絶」の札が掲げられた。強心剤やらブドウ糖やら、日に5,6本の注射をされる日が続いた。結核という病気の特色は、最後まで意識が混濁しない点にある。彼は自分でも(もう、駄目かも知れない)と覚悟を決めた。
私が谷と知り合ったのは、綱渡りするような危険で長い療養の末に彼がようやく回復した頃だった。この頃、彼は信仰の面でも新しい段階に踏み出していた。
肺の摘出手術を受ける時分の彼は、神に正対することを避けていた。神の真向かいに立つと、自分の醜さが残らずさらけ出されるような気がしたからだ。
仲間のクリスチャンに完全に同調することも出来なかった。信仰を持つが故に、底に強さと明るさをかくした信者がいる反面、信仰の殻をかぶったエゴイストも目に付いたのだ。
キリスト教に対するこうした中途半端な姿勢は、彼の不徹底な祈り方となって現れていた。彼はハッキリと口に出して「主に祈る」ことが出来なかった。知り合いが決然とした態度で祈るのを見ると嫉妬を感じたが、自分ではどうしてもそうすることが出来ない。祈ろうとすると、その声は人に聞かれることを恐れて小声になり、表情も自然に恥ずかしげなものになってしまう。そして、祈る格好をしている自分を、もう一人の自分が抜け出て傍から眺めているような気がしてくる。
結局、神に正対していなかったから、祈れないのだった。神と正面から向き合うことが出来れば、祈ることも可能になる。彼に祈りへの道を開いてくれたのは、二度目の手術の前夜、見舞いに来てくれた療養所内の「キリスト者会」のメンバーだった。最初にやって来た患者は、ベットの脇で彼のために祈ってくれた。
次に来た患者は、宗教関係のことには一切触れず、冗談を言って谷を笑わせて帰っていった。手術を控えて緊張していた彼は、笑ったことで珍しく朗らかになった。彼は、何の不安も矛盾もない精神状態で、知らぬ間に祈っていた。不思議なくらい素直な気持ちで祈っていたのである。
彼は手術後の死線をさまよっている時期にも、苦しい息づかいの下で何度か主の名を呼んでいる。胸の中に居座っていた不安の塊が、ふと崩れ始める瞬間に、彼は主の名を呼んでいた。不意に瞼の裏を、影を引きながら光が通過するのを感じたときにも、彼は主の名を呼んだ。
危地を脱した彼は、自分の生命が人々の恩愛と、それよりも更に大きなものによって支えられていたことを実感する。彼が自分の信仰について語ろうとしなかったのは、信仰が希薄だったからではなく、自分と神との関係が新たな段階に入ったことを感じていたからだった。彼はひとり静かに信仰を深めようとしていた。だから、これについて口を緘して語らなかったのだ。
立ちはだかる壁
谷が自分の前に立ちはだかる「壁」を最初に感じたのは、家族が力を合わせて焼け跡から立ち上がろうとしていた時に違いない。彼の姉も、この苦闘のさなかに死んだのだろう。
次に彼がぶつかった壁は、病気との闘いだった。ここで危うく彼は敗北しそうになるが、ついにこれを乗り越えて退院することに成功する。
最後の壁は、倒産だった。私は、谷がこの危機を平静な気持ちで乗り切ったと思っていた。しかし、夫人の意見は違っていた。彼女は倒産前後に彼が味わった苦悩が、今回の病気の遠因になっていると考えている。ショックは、それほど大きかったのである。
谷と40年間生活を共にしてきた夫人は、夫の「持ちこたえる能力」に注目している。彼女は、夫の生涯は耐え続けた生涯であり、、肉体がその負荷に耐えなくなったときにくずおれたと見ていた。
生まれて10日で実母と死別したことから始まる彼の生涯は、確かに耐えることの連続だったに違いない。彼の慎重で控えめな生き方も、生育環境から来ていると考えれば、納得がいくのである。
倒産のショックが大きかったとすると、「崖の話」の意味するところも自ずから明らかになる。少年の頃、崖を上ろうとしたら大きく見えたという。この部分は、これから生きようとする子供の目に人生や社会がとてつもなく巨大に見えた事実を示している。
それから20数年たって、谷は改めて人生について見直しを行うことになる。20数年後といえば、彼が倒産という事態に直面した時期である。彼は崖の高さと自分の目盛りを計算して、崖から飛び降りることを考える。
ということは、彼が実社会とそこで生きる自分の能力を計算して、生きることをやめるか、この社会からドロップアウトすることを考えたということを意味している。クリスチャンの彼は、自殺することまでは考えなかったかも知れない。しかし、倒産の前後に、何もかも投げ捨てて山にでも籠もってしまいたいと考えたであろうことは容易に想像がつくのだ。
だが、彼は人生を投げてしまうことがなかった。そこが夫人も指摘する谷固有の「耐える能力」の強さなのだ。彼は夫人と共に詩を作りながら、肝臓病と心臓疾患で倒れるまで、淡々と生きた(夫人は「仙人のように」と言っている)。
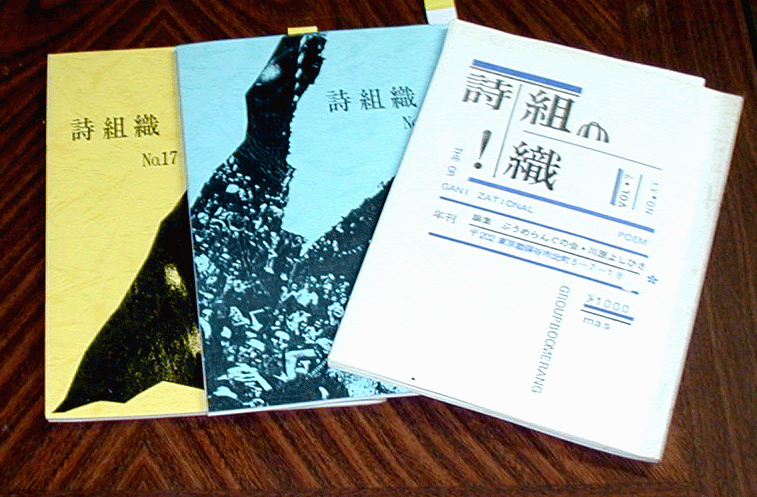 谷夫妻が編集委員をしていた同人誌
谷夫妻が編集委員をしていた同人誌
ほぼ半世紀前に、私は療養所で谷という若者に出会った。彼と親しくしていたのは、一年にも足らない短い期間で、当時、私は相手の人間の外側を見ていただけだった。しかし表皮を撫でただけでも彼の優れた人柄が分かり、谷という男は私にとって忘れがたい人物になっていたのだ。
その彼の生涯のあらましを、50年近い時間を置いて、私はやっと知ることが出来るようになった。それまで表面だけしか知らなかった相手の裏面をおぼろげながら掴むことが出来たのだ。谷は今になって、私に真実に近い姿を見せてくれたのである。
(注:谷のことは別掲ホームページ「私の宗教的体験」にも書いてあります。「結核療養所」の項)