宮沢賢治の作品をまとめて読んだのは、戦後もかなりたってからだった。角川書店版「昭和文学全集」の中の一冊に「宮沢賢治集」というのがあって、それを肺摘出手術前の病床で読んだのである。当時、詩人としての賢治の名声は高く、その聖者のような生き方は神格化されていた。けれども、私はこの本の読後にある種のもどかしさを感じたのだった。賢治の生き方は、すべての点において中途半端なのである。彼は本当に書きたかったことを書いていないし、本来願っていた生活を実現していない、そんなふうに思われたのである。
角川版「宮沢賢治集」巻末の解説で、小倉豊文は、賢治を郷里を棄てた同郷の石川啄木と比較して、「幾度か家を出る決意をしながら、遂に郷土を棄て得なかった」と書いている。事実、彼は「雨ニモマケズ」を書き記した「最後の手帳」の冒頭に次のような文章を掲げているのだ。
昭和六年九月廿日再ビ東京ニテ発熱
大都郊外ノ煙ニマギレントネガヒ
マタ北上峡野ノ松林二朽チ
埋レンコトヲオモヒシモ
父母共二許サズ
廃躯ニ薬ヲ仰ギ熱悩ニアヘギテ
唯是父母ノ意僅二充タンヲ翼フ
この断章を見る限り、賢治は家を棄てて郷里とは別の土地でひっそりと生きたいと願っていたのである。「大隠は市に隠る」の格言に従って東京の裏町で生きようと思ったり、僻地の森にこもってソローのように孤独に生きたいと考えていた。
そして、実際に彼は26才のとき、突如上京して「大都郊外ノ煙ニマギレ」る生活に入り、30才を過ぎてからは、一軒家で独居自炊の生活を始めている。だが、東京での生活は僅か半年あまりでうち切られ、独居自炊の舞台になった一軒家も遠い他郷に存在したのではなく、実家の近くにあった自家の持ち家だったのである。
つまり彼は何度か家郷からの脱出を企てながら、病気や父母の反対を理由にして初志を棄て、パラサイトシングルの日常に戻ってしまったのだ。賢治が自分の収入だけで自活した時期は極めて短く、地方財閥だった実家に寄食する形で生涯の大部分を過ごしている。彼は教師時代に病気で休んでいる同僚に密かに自分の給料を贈っているけれど、賢治が実家の援助なしに自活する身だったら、こうした「善行」も不可能だったにちがいない。
同じようなことが、彼の作品についても言える。
宮沢賢治は、大正デモクラシーの空気をたっぷり吸って青春を過ごし、マルクス主義運動全盛の昭和初期を生きて、昭和8年に38才で死去している。彼はマルクスやブハリンを読み、何冊もの唯物論哲学書を所持していた。法華経に心酔するようになってからも、マルクス主義運動への同情的な態度は変わらず、彼は左翼運動に参加しない理由を弁明するかのように、自分の出番は共産主義革命実現後にやって来る、と言っている。
賢治の最初期の短編を読むと、物書きとして彼が目指したのは詩や童話を書くことではなく、社会派の小説を創作することだったのではないかと思われる節がある。学生時代に書かれたとおぼしい「家長制度」「大礼服の例外的効果」などは、プロレタリア小説の未定稿と見ても決しておかしくはない。実際、「大礼服の例外的効果」には標題の後に括弧して「短編梗概」という注釈を書き加えている。彼は機会があったらこれを風刺小説に仕立て上げようと思っていたのである。
参考のために、ここに「家長制度」の全文を引用してみよう。これをプロローグにして長編小説を書いたら、長塚節の「土」を思わせる「農村小説」が生まれたかもしれないのだ。
家長制度
火皿は油煙をふりみだし、炉の向うにはこ
この主人が、大黒柱を二きれみじかく切つて
投げたといふふうにどつしりがたりと膝をそ
ろへて坐ってゐる。その息子らがさつき音なく外の闇から帰っ
て來た。肩はばひろく「けら」を着て、汗ですつ
かり黒寒天みたいに黒びかりする四匹か五匹
の巨きな馬を、がらんとくらい厩のなかへ引
いて入れ、なにかいろいろまじなひみたいな
ことをしたのち、土間でこつそり飯をたべ、
そのままころころ、藁のなかだか草のなかだ
か、うまやのちかくに寝てしまったのだ。もしも私が何かちがったことでも言った
ら、そのむすこらのどの一人でも、すぐに私
をかた手でおもてのくらやみに、連れ出すこ
とはわけなささうだ。それがだまってねむってゐる。たぷんねむつてゐるらしい。
火皿が黒い油煙を揚げるその下で、一人の
女が何かしきりにこしらへてゐる。酒呑童子
に連れて來られて洗濯などをさせられてゐ
る。そんなかたちではたらいている。どうも私の食事の支度をしでゐるらしい。
それならさっきもことわったのだ。
いきなりガタリと音がする。重い陶器の皿
などがすべつて床にあたったらしい。主人がだまって、立ってそっちへあるいて
行った。
三秒ばかりしんとする。
主人はもとの席に帰ってどしりと坐る。
どうも女はぶたれたらしい。音もさせずに撲ったのだな。その証拠には
土間がまるきり死人のやうに寂かだし、主人
のめだまは古びた黄金の銭のやうだし。
わたしはまったく身も世もない。
学生の頃、彼は意識の底で作家になることを夢見ていた。そして、その能力を十分持ちながら敢えて作家志望の方向に踏み出さなかったのではないか。脱家族、脱故郷の欲求を持ちながら家郷を離れなかったように、彼は作家志望の夢を抱きながら、本格的な小説を書くことなく終わったのである。
賢治が自らの欲望を最後まで押し貫くことをしないで、中途で踏みとどまってしまったのは何故だろうか。結核という病気を抱えていた彼は、健康に自信がもてなかったのだろうか。それとも、地域の名望家だった両親に迷惑をかけることを恐れたのだろうか。「最後の手帳」に記されたメモでは、病気と父母の反対を理由に挙げているが、それが原因のすべてだったとは思われない。
賢治の不決断は、それらよりも大きな関心事があったからではなかろうか。
ちくま新書版「童貞としての宮沢賢治」(押野武志)には、次のような一節がある。
賢治にも寄宿舎時代があった。一九一五(大正四)年四月に賢治は、盛岡高等農林専門学校の農学科に一浪して入学した。同期入学の高橋秀松は、寄宿舎で賢治と同室で、彼との想い出を書き残している。賢治の風変りな言動から友達はほとんどいなかったが、高橋は、布団を接していたことから、入学早々親しくなったと言う。賢治は毎晩自ら考案した暗号文字を用いて詩や歌、日記を書いていた。高橋だけが唯一読むことを許されたが、暗号の鍵を教えずに独力で解読せよと命ぜられ、その詩のノートをまる一日かけて解読した。その最初の暗号文字の主人公は高橋自身だった。
最初の暗号文字の主人公は何と私を扱つてるではないか。これには驚 かざるを得なかったが、賢治の淋しい気持もハツキリ解り、それか ら親しさが加速度的に加わり、土曜日日曜日は勿論暇さえあれば 私は彼のお供をして、盛岡附近の山野を践渉した。休みが二、 三日続いたときは、出来る丈遠くへ出かけた。
これはどうみても、賢治が高橋に同性愛的感情を持っていたとしか言いようがない。後で触れるが、一年後、同じく賢治と寄宿舎で同室になる保阪嘉内とも、濃厚な男同士の友愛関係を築く。
同性愛的感情といえば、高橋に対するものよりも、保阪嘉内に対するものの方が一層深刻だったようだ。保阪は賢治とともに文芸同人誌「アザリア」発刊に関わったが、程なく彼は退学処分を受け(危険思想の所有者として処罰されたらしい)郷里に帰ってしまった。賢治は、この保阪に法華経への入信を勧め、彼が帰郷してからは頻繁に手紙を書いている。
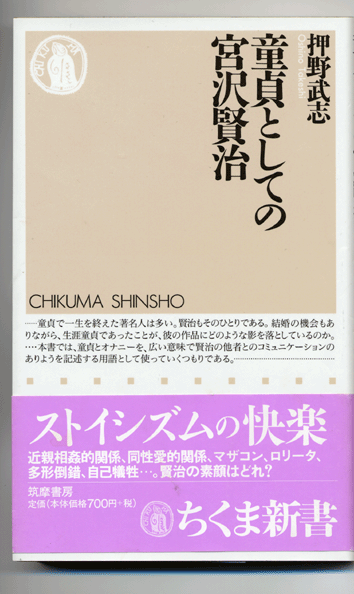 押野武志「童貞としての宮沢賢治」
押野武志「童貞としての宮沢賢治」その手紙の中で、賢治が
「わが友保阪嘉内、わが友保阪嘉内、我を棄てるな」
と繰り返し懇願しているところを見ると、この友人への執着が並々ならぬものだったことが推察できる。
彼は身近にいる者たちから一人か二人を選んで深く交わるタイプで、家族との関係もその例外ではなかった。賢治は両親とは合わず、妹のとし子と弟の清六、とりわけとし子と濃密な関係を結んでいる。賢治にとっては、高橋や保阪、そして妹とし子との関係が何よりも重要だったのであり、それ以外の家郷からの脱出願望や作家志望などは第二の案件に過ぎなかったのである。
これを物語る典型的な挿話がある。
賢治は26才になって、かねての念願だった家郷からの脱出を敢行する。突如上京して、宗教団体「国柱会」を訪ねた彼は、筆耕・校正などで生活費を稼ぎながら東京で自活をはじめたのである。覚悟を決めて上京したにもかかわらず、彼が半年あまりで帰郷したのは結核を再発した妹を看病するためだった。念願の「大都郊外ノ煙」に紛れる生活を始めながら、妹が病気と聞くと、別にそれほど急を要する症状ではなかったにも関わらず、あわただしく帰郷してしまっている。
だが、二者関係への執着は、彼の人生を狂わせるほどのものでなかったことも事実である。
賢治は寄宿舎で同室になった二人の友人と同性愛を疑われるほどの排他的な交友を結びながら、その関係は長続きしていない。絶交によって疎遠になったのではない。相手と接触する機会が少なくなるにつれて、その関係は自然に遠くなったのである。賢治は相手に強く執着しながら、相手を執拗に追い回すようなことはしなかったのだ。
「童貞としての宮沢賢治」を読んで初めて知ったことだが、賢治は17才のとき鼻の手術のため岩手病院に入院し、そこで知った看護婦への恋の歌をいくつか作っている。退院後、彼は両親に看護婦と結婚したいとせがむが、この希望は、無論、容れられなかった。若すぎるからと父親に一蹴されたのである。
賢治を神格化するファンの間には、彼がオナニーすら自ら禁じた完全童貞者だったとする神話が流布している。異様なほど鋭敏な賢治の感受性は、生涯にわたって一度も女性に触れなかった彼の完璧な禁欲生活から来ていると説く論者もある(谷川徹三)。しかし、これらの挿話に見るように彼とても木石の身ではなかった。17才で早くも結婚をせがむほど、早熟な若者だったのである。
親に反対されて賢治が看護婦への思いを断ち、その後の交渉が途絶えたらしい点は、高橋や保阪嘉内の場合と同様である。一見、彼は「去る者は日々に疎し」という人間関係を営んでいたように見える。だが、それが事実に反することは、彼の作品を見れば明らかで、彼の作品には、一対一の友人関係や兄妹関係をあつかったものが、異様なほど多いのだ(「銀河鉄道の夜」など)。彼の頭は、友人との関係、妹との関係で一杯になっていて、その他の問題を省みる余裕がなかったのだ。
確かに、彼には、二者関係以外の問題を受け付ける心の余裕がなかった。次に引用するのも、「童貞としての宮沢賢治」の一節である。
一九二七(昭和二)年の秋の日、森荘已池は下根子にあった賢治の羅須地人協会を訪ねた。その途中、向こうから二十二三歳の和服を着た女性がやって来た。そしてその女性の様子が異常だと森は直観した。眼が輝き、体全体が上気していたという。「かなりの精神の昂奮でないと、ひとはこんなにからだ全体で上気するものではなかった。歓喜とか、そういう単純なものを超えて、からだの中で焔が燃えさかっているような感じだった」らしい。・・・・・・・・・
(賢治に会うと)彼はじっと私の心の底をのぞきこむようにして
「いま、とちゅうで会ったでしょう?」
といきなりきいた。
「ハアー」
と私が答え、あとは何もいわなかった。少しの沈黙があった。
「おんな臭くていかんですよ。」
彼はそういうと、すっぱいように笑った。彼女が残して行った烈しい感情と香料と体臭を、北上川から吹きあげる風が吹き払って行った。そして彼はやっと落ちついたらしかった。・・・・・・・・・・・・
これらの状況から、森は女性の方が賢治に肉体関係を迫ったことを直観して書いている。賢治はそれに応えたのだろうか。おそらく拒絶したのだろう。だが、「性愛の墓場」まで行きそうになったことだけは確かだ。この出来事だけに限らず、賢治のその女性への拒絶ぶりは尋常ではない。はじめこそ賢治の企画する芝居に出演してもらうことを考えて、しっかりした人だと協会員にも語って喜んでいたのだが、彼女の好意や贈り物攻撃に賢治は恐縮していく。
彼女の積極性にたじろぎ、居留守を使ったり、わざと顔に灰を塗って出て来たり、手料理のカレーを彼女が作って皆にふるまった時、賢治だけが食べようとしなかったり、きわめつけは二度とやって来ないようにと自分は「レプラ」(ハンセン病)だと彼女に嘘をついてもいる。
しかしその嘘が逆に彼女を殉教的にして、彼女の方はこの人と結婚して看病しようとしたらしい。森はそのような一方的に押しかけてくるその女性に対しては露骨に不快感をあらわしている。だから、本の中ではその名を明かしてはいない。
その女性の名は、当時、小学校の先生で羅須地人協会の近くに住んでいた高瀬露という。高瀬は一九〇一(明治三四)年十二月生まれで、賢治より五歳下である。一九一八(大正七)年、妹トシと同じく花巻高女を卒業後、准教員の資格を取り、次いで一九二三(大正一二)年九月には正教員になり、稗貫郡湯口村宝閑小学校に勤める。そして、高瀬はクリスチャンであった。
初めは好意を抱いていた女性でも、賢治は相手が強く迫ってくると、急速に感情が冷却して逆に嫌悪を感じるようになる。これは彼が一般の人間とは、深い関わりを持つことを避けていたからだ。賢治は観念の上では、多くの人間と愛し愛される関係を保ちたいと考えていたし、事実、周囲の人間に惜しみなく愛情を注いでいたが、相手の愛情を受け入れて、これと深い関係に入ることは避けていたのである。
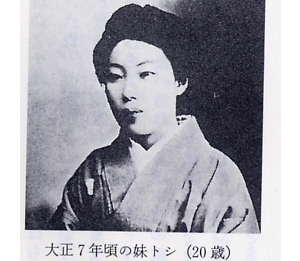 妹 とし子(20才)
妹 とし子(20才)
私は、賢治が童貞を守ったのは、宗教的な信念に基づくというよりは、こうした性格的な理由からではないかと考えている。特定の人間としか二者関係を形成しない彼が、多量の枕絵(春画)を収集していた理由も理解できる(賢治は厚さにして30センチ余になるほどの浮世絵版性交図絵を愛蔵していた)。
彼がこれら膨大な枕絵を眺めて、密かにオナニーにふけっていたかどうかは知らない。異性への関心をもちながら、選択基準が厳しすぎて誰とも具体的な関係にはいることができないとしたら、代償行動に走るしかない。欲望を中途半端で封じ込めてしまうことを特技とする賢治が、春画によって鬱を散じていたとしても格別奇とするには足りない。
宮沢賢治には、その生涯全体を神格化して考えたくなるような逸話が多い。
子供の頃、友達が車に指を轢きつぶされたのを見て、「痛かんべ、痛かんべ」と言ってとっさにその指を自分の口に入れてしまったという話や、農学校の屠殺実験で殺される家畜の悲しげな泣き声を聞いた日から固く肉食を断ったというような話まで、心打たれる逸話が多い。
だが、すこし賢治のことを調べてみると、思春期の彼がごく普通の権威に反抗する元気な若者だったことが明らかになる。賢治は14才で盛岡中学校の寄宿舎に入るが、寄宿舎騒動に加わって、寄宿舎を追放されているし、盛岡高等農林学校に入学してからは、「大礼服の例外的効果」にあるように「国体の意義」について突っ込んだ質問をして校長を困らせている。
盛岡高等農林学校を卒業した賢治は、父が徴兵猶予の特典を得るために執拗に進学を勧めるのを断り、自ら進んで徴兵検査を受けている(丙種不合格となる)。
賢治と父親の関係はかなり微妙で、彼が法華信者になり、妹のとし子まで法華経の信者にしてしまったのは、篤信の真宗信者だった父に対する異議提出としてだったかもしれない。
賢治の死後、我が子の名声が高くなった時に賢治の父は、家族に対して浮かれてはならぬと厳しく釘をさしていたという。父の目から見たら、賢治は何時までたっても腰の据わらない不肖の息子だったのである。高等農林を卒業して家業の手伝いを始めたと思ったら、二年もたたないうちに突如上京して宗教団体の下働きを始める。
ようやく家に連れ戻して、花巻農学校の教諭になることを許したら、その仕事も4年あまりで辞めてしまう。教員になるのを許したのは、家業の質屋を引き継ぐまでのつなぎにとしてだったが、賢治は退職してからも家の手伝いを碌にしないで、暇があれば、蓄音機でベートーベンを聴いたり、オルガンやセロの独習をしたり、酔狂にもタイプライターの練習まで始める。
父親が賢治のこうした気ままな行動を黙認し、彼が持ち家の一軒家で暮らすことを許したのは、世間体を考慮したからだった。賢治の父は、息子が妻や娘と同じ病気(結核)に罹患していたから、彼に世間並みのことを要求せず、持ち家に移して家族から隔離したのである(妹も結核を再発してから同じ家に隔離されている)。名門の宮沢家としては、肺病の血統だとささやかれることを避けたかったのだ。
賢治は父に同調できなかったが、決定的に離反することはなくて、重要な問題については父母の命に従っていた。彼は死が間近に迫ったときに、次のような詩を作っている。
病相
われのみみちにただしきと
ちちのいかりをあざわらひ
ははのなげきをさげすみて
さこそは得つるやまひゆゑ
こゑはむなしく息あへぎ
春は來れども日に三たび
あせうちながしのたうてば
すがたぱかりは録されし
下品ざんげのさまなせり
賢治はこの詩の中で、これまで自分だけが正しいと思いこんで、父の怒りを嘲笑し、母の嘆きを蔑んできたと懺悔している。「父と子」の対立をぎりぎりのところまで押し進めることを避けて、自身の行動をこれも「病相」の現れだったと弁明しているのだ。
賢治は本格的な小説を書くことなく終わった。
小説に近いものは、彼が「少年小説」と呼んだ「風の又三郎」以下数編の作品があるだけである。だが、代わりに彼は夥しい詩と童話を書いた。賢治の残した童話は不思議な味わいを持ち、子供を対象にした物語というより、子供と大人を含めた汎人間を対象にした作品になっている。不気味で残酷な「注文の多い料理店」などの作品は、到底子供向きの読み物とは思えない。彼は「童話」という名のもとに、万人に通じる平易な寓話を編み出したのである。
賢治の特異な童話を背後から支えたものは、大乗仏教だったと思われる。彼が法華経を読んだのは、旧制中学校を卒業して一年浪人しながら受験準備をしているときだった。
賢治は初めて法華経を読んだときの印象を「驚喜して身顫ひ戦けり」と書いている。けれども、25才で高等農林研究科を終了するまでは、妹や親友に法華経を読むことを勧める程度で本格的な布教活動をしていない。彼が真の法華行者になるのは、研究科卒業後「国柱会」に入会してから以後である。
「国柱会」は田中智学が明治17年に創立した日蓮主義の在家仏教組織だった。「国柱会」に加入した賢治は、その年の12月には花巻町の路地を巡る寒行に参加している。寒行というのは、日蓮宗の信者が寒夜に題号を唱えながら団扇太鼓を打ちならし、路地から路地へと巡り歩く行事で、私も戦前松本市に住んでいた頃、毎年、冬の夜の風物詩として家の前を行き過ぎる信者たちを見ていた。寒い真冬に薄い白衣を着ただけで、憑かれたように「南無妙法蓮華経」と唱えながら門前を通り過ぎる信者たちは、見るからに異様だった。
宮沢賢治は題号を声高に朗唱しつつ暗い路地を巡り歩いているうちに、神秘的な恍惚境に入り宇宙意志と一体になるという体験をしている。この体験は、その後の彼の生活を一変させることになるのである。賢治が父に遺した遺言には、法華経に対する切々たる熱情があふれている。
「国訳妙法蓮華教全品約千部を出版下され、知己の方にお贈り下さい。<私の全生涯の仕事はこの経典をあなたのお手許におとどけしてその仏意に触れて、無上道には入られることを>という意味を記してください」
賢治がその神秘体験を通して感じ取った宇宙意志とは、「あらゆる生物にほんとうの幸福をもたらそうとする意志」であり、従って宇宙意志を体して生きる人間にとっての愛とは、何か特定のものを愛する個別愛ではなく、生きとし生けるものすべてを愛する全体愛になる。
彼の死後に発見された手紙の反故には、こんな文字が見える。
「私は一人一人について特別な愛というようなものは持ちませんし、持ちたくもありません。そういう愛を持つものは、結局じぶんの子どもだけが大切というあたり前のことになりますから」
実際、賢治はこの宇宙意志を身に体して生きようとしたのだった。
年譜を開くと、26才の項に、
「1月23日、突如上京の途につく。翌日、国柱会訪問。爾来、筆耕校正等により自活自炊。2月頃、国柱会の高知尾智耀の奨めにより、文芸による大乗仏教の真意普及を決意す」
とある。
この時点で、彼は作家志望の夢を完全に捨て去り、大乗仏教で味付けされた童話を書くようになる。神秘体験以前に試みた小説の習作「家長制度」「大礼服の例外的効果」のようなものは、最早書かれることがなくなったのである。
宇宙意志を体感した賢治が、エスペラント運動家になったのは不思議ではない。彼は世界や宇宙を視野に入れた鳥瞰的な目を持つようになった。彼の作品にはエスペラント風な地名・人名が増え、彼は好んでユートピア世界を描くようになった。
エスペラントは世界の共通語をめざして考案された人工語である。
これは合理的で美しい言語ではあるが、人工言語によって人種・国籍を越えて世界を一体化する可能性はほとんどない。賢治はエスペラント運動の空想性を十分承知の上で、あえてこれを基盤とするユートピアを描き続けたのである。
かくて、排他的な二者関係を追求しながら、それをエスペラント的世界性で包み込む賢治作品のスタイルが完成する。大乗仏教の心髄に触れることがなかったら、彼は二者関係という檻の中に閉じこめられて動きがとれなくなっていただろう。凶作にあえぐ岩手の山野に浄土を見たのも、これにイーハートボオという名前を与えて、エスペラント的世界の一環に組み入れたのも、大乗仏教のお陰であった。
賢治作品の魅力は、二者関係に執着しながら、法華経的慈悲の世界を描いたことである。つまり彼は「個別愛」と「全体愛」を共存させることに成功したのであった。