石川三四郎がフランス船ポール・ルカ号に乗って日本を旅立ったのは、大正2年3月のことだった。フランスのマルセーユにたどり着くまでに要した時間は38日、この間を彼は三等船室で過ごしている。マルセーユで下船したとき、さすがの石川も不安でいっぱいだった。彼は、高島米峰にこんな手紙を書いている。
言語は通ぜず、一人の知人もなく、これからこの船を出て、いったいどうすればよいのか、税関はどうして通過する? パリ行きの汽車にはどうしたら乗れる? 何ひとつわからない。
それでも何とか、パリ経由で目的地のブリュッセルについた。最初の八ヶ月を彼はブリュッセルの下宿に腰を据え、「万朝報」や「新日本」に宛てた原稿をせっせと書いていた。懐が空っぽになっていたので、滞在費を稼がねばならなかったのである。
ヨーロッパに渡ったら、何を置いてもエドワード・カーペンターに会いたいと思っていた石川は、彼から「講演のためロンドンに来ている」という手紙を貰うと、すぐにロンドンに出かけた。カーペンターは、普段、ロンドン北方200キロのミルソープに住んでいたが、石川は旅費の関係でとてもそこまで行けなかったのである。
ロンドンでカーペンターに会い、更にミルソープに出かけてみると、彼の家は文字通り野中の一軒家で、周囲には家が全くなかった。カーペンターは仲間と一緒に農業共同体を作り集団生活を送っていると思っていたのに、同性愛者の彼はその野中の一軒家でメリルという30代の男性と二人だけでひっそりと暮らしていた。
石川は、カーペンターから愛人のメリルを撮影した全裸の写真を見せられた。カーペンターは、また、石川が裸になって行水をしている部屋に、自分も裸になって入ってきて体に触れたりしたが、石川は軽く受け流して拒まなかった。
石川はカーペンターの世話で彼の姪が嫁いでいるロンドン郊外の銀行家の家に寄宿し、半年を過ごしている。彼は皿洗いをして生活費を稼ぎながら、何とかしてイギリスで定職につきたいと願ったが果たせなかった。そんな石川を救ってくれたのが、ブリュッセル在住のポール・ルクリュだったのである。ポールは、石川がロンドンで困っていることを知ると、ブリュッセルに戻ってくるように勧め、彼のために自宅の三階(注:石川は「三階」と書いているが、本当は屋根裏部屋だったのではないか)を提供するといってくれたのだ。
ポール・ルクリュは、無政府主義者として世界的に有名なエリゼ・ルクリュの甥で、ポール自身も無政府主義者だった。石川はカーペンターを訪ねる前に、ポール宅を二度ほど訪問したことがあり、すっかりポール夫妻から気に入られていたのである。
石川がポール・ルクリュ宅に落ち着いたことを知ると、現地の友人が彼のためにペンキ職人の口を探してきてくれた。石川はブリュッセルにいた八ヶ月の間に、出来るだけアナーキストの会合に顔を出すようにしていたから、そうした集会で親しくなった友人を数多く持っていたのだ。
ようやく定職に就くことが出来たものの、彼はペンキ職人の仕事を覚えるまでに身震いするような経験をしなければならなかった。旧家に生まれた石川は、それまで一度も肉体労働をしたことがなかったのだ。
最初あてがわれた私の仕事は、両ばしごの頂上に立って、高い天井裏に下ぬりをすることであった。左手に白色のペンキを満たしたバケツを下げ、右手には大きなブラシを持って、毎日十時間も左官仕事をすることは、私にとってかなりの苦痛であった。最初の二、三日は発熱して夜もよく眠れなかった。ことに両ばしごの頂上に立つときの緊張と疲労は甚だしいものだった。一度すべれば命がなくなる危険な芸当だ。けれど、この場に及んでは一心不乱であった。今になって思い返しても戦慄を禁じえないような仕事が、平気で遂行された。環境が私をきたえてくれたのだ。(「浪」)
「両ばしご」とは、二つ折りの脚立のことをいうのだろう。その高い脚立のてっぺんまで登って、片手にペンキのバケツ、片手に大きなブラシを持って仕事をするのである。生まれつき蒲柳の質で、性格的に臆病だった石川には、仕事をするのに決死の覚悟が必要だった。
毎朝5時に起きて、一人だけで朝食を済ませ、夕方に疲れ切って戻ってくるという生活は、彼にとってはきわめて過酷なものだった。だが、お陰で彼は安定した収入を得ることができた。そして、その後の体力仕事にも、自信を持って臨めるようになったのだった。
石川三四郎が外国で順調に自活しはじめたとき、第一次世界大戦が勃発して戦火はベルギーに及んでくることになる。ドイツ軍がベルギーに進出し、ブリュッセルを占領したのだ。途端に、石川の仕事がなくなった。仕事の腕を上げた彼は装飾職人になっていたが、ドイツ軍の占領下に建物を塗料で飾ろうというという奇特な注文主はいなくなったのである。
石川はブリュッセルを脱出して、ロンドンに渡り、それからパリに移った。パリでルクリュ夫人と再会した彼は夫人の斡旋で、パリの北方50キロにあるリアンクールという小さな町に住むことになった。この町にルクリュ夫人の友人である大学教授が住んでいたが、教授は出征し、その夫人もパリ市内の実家に引き上げたため、邸宅が空き家になっていた。石川は、その無人になった教授の家の留守番をすることになったのである。
留守宅に行ってみると、庭園には立派な温室があり、それに続く広い畑には果樹がたくさん植えられていた。ほかにも菜園用にかなりの空き地が用意してある。石川は、この空き地に野菜を作ることにした。戦争の余波で革命でも起きるとしたら、まず必要になるのは食料だと考えたからだった。
畑仕事など一度もしたことのなかった彼は、近所の住民に野菜作りのイロハから教えて貰った。畑仕事は、彼に満ち足りた喜びをもたらしてくれた。毎朝、早起きして作物の生長を眺めるのが、たとえようもないほど楽しかった。野菜は食べきれないほど出来たので、パリ市内の家主の所へ定期的に届けた。
作物はどれも良くできたが、例外はジャガイモだった。農業に無知な石川は、ジャガイモもトマトやナスと同じように茎に実るものだと思いこんでいたから、10月の末になっても何も実らないまま茎が枯れるのを見て、ジャガイモだけは失敗だと決めてしまったのだ。
家主の教授夫人が女中を連れてようすを見に来たとき、女中が石川に注意した。
「イシカワさん、ジャガイモを早く収穫しないといけませんよ」
「いや、これは失敗でした」
教授夫人が質問した。
「で、あなたは掘ってみたのですか?」
彼がちょっと土を掘ると、ジャガイモが続々と出てくる。
石川がジャガイモは茎になるものだと思いこんでいたことを知って、夫人も女中も笑い崩れた。
彼はこの教授夫人の留守宅を一年あまりで去って、そこから70キロほど離れたドンムの町のポール・ルクリュ家に移っている。東京に出てきた石川は、あちこちたらい回しされた挙げ句に、最後に福田友作の家に落ち着いているが、亡命中の彼もいくつかの家に寄食した末に、ポール・ルクリュの屋敷に落ち着いたのである。彼が福田家に定着したのは、夫人の英子に気に入られたからだったけれども、ルクリュ家に居着いたのも、夫人が石川に一方ならぬ好意を持ったためだった。
ポール・ルクリュは、とにかくフランス語を早くマスターするように彼に忠告した。それには積極的に仏語で会話することだというので、石川はポール・ルクリュの息子たちとよく話をした。だが、一番話し相手になってくれたのはルクリュ夫人だった。彼女は食後の一時間を彼との対話に裂いてくれ、石川を促して出生から現在に至るまでの身の上話をさせた。
石川の方でも誠心誠意夫人の厚意に酬いた。夫人は長い病気を患っていたから、彼は夜中に一度はその病室を訪れてようすを見ることにした。夫人に対する彼の行き届いた介護には、家族の誰も頭を下げた。
石川を追悼した文集には、夫人の息子の言葉が載っている。
こんなことを書くのは恥ずかしいことだが、私をはじめ実の息子たちが、あまり母のことを気にかけていなかったのに、それ以上の忠実さと献身さをもって三四郎が母を看護をしてくれたことは、私たちにとっても決して忘れることのできないことである。
彼は心を込めて病人の面倒を見るだけでなく、ルクリュ家の敷地内にある畑を耕した。10年間も放置されて、すっかり荒れ果てていた畑をよみがえらせたのである。ルクリュ家にとって、石川は日本からはるばるやってきた賓客であると同時に、夫人の看護人であり、住み込みの農夫だった。
彼はすっかりルクリュ家にとけ込み家族に一員になった。石川は、3年半に及んだドンムの生活を「私の全生涯中、最も深く最も広い教育を私自身に施」すものだったと回顧している。
彼はルクリュ家から恩恵を受けたが、看護人として農夫として同等のものをルクリュ家に返した。彼とルクリュ家の家族は、対等の互恵関係を保ち、互いに干渉することなく自由に生きたのである。こうした関係こそ、人間関係の原型ではないかと、石川は思った。
彼は帰国する前の半年あまりを、ルクリュ夫妻と共にアフリカのモロッコで過ごしている。夫人の病状がよくないので、モロッコにいるポールの弟のところに転地療養することになったのだ。そして、このモロッコ滞在が、石川の8年に及ぶ亡命生活を切り上げて日本に帰るきっかけになったのだった。
 ポール・ルクリュ夫妻と三四郎
ポール・ルクリュ夫妻と三四郎一般に、海外に滞在ないし亡命している「革命家」が、急遽、帰国を思い立つのには然るべき理由がある。アメリカで新しい革命理論と運動方式を吸収した幸徳秋水は、一刻も早くこれを日本で実行しようとして帰国したし、レーニンも革命のチャンスが到来したと見て亡命先から急ぎ帰国している。ところが、石川三四郎は、そうした社会情勢とは関係のない、全くの個人的な動機から帰国を思い立ったのである。
石川はモロッコに滞在中に、暇に飽かせてポールの弟が所蔵している本を読みあさった。ポールの弟は、宗教学の権威だった父の蔵書を所持していた。石川は、獄中で古事記を読んで興味を感じて以来、記紀に関する本に馴染んでいたから、モロッコで宗教関係の学術書を読む機会を与えられ、改めて記紀に対する興味を呼び覚まされたのだ。
彼は古事記に盛り込まれている神話の数々が、メソポタミア地方で生まれたのではないかと思った。
ニニニギノミコトは、山や海を渡り歩いた後、タカチホに到着して、ここに定住した。この「タカチホ」とは、シナイ半島のジェベル・エル・チフであるように思われる。そもそも「タカ」は「高」あるいは「嶽」を意味し、タカチホをアラビヤ語に訳すと「ジュペル・エル・チホ」となる。この山の固有名詞は、三千年間に、単に「チホ」が「チフ」と変じたに過ぎない。(「古事記神話の新研究」)
音韻の相似を根拠に、異質な二つの文化を強引に結びつけるのは、アマチュア学者がよくやる独断的な手法である。石川もアマチュアの陥りがちな独断とこじつけのとりこになって、自分の新説を是非日本で完成したいと考えるようになった。帰国する理由はそれだけだった。彼は自信満々で、自分の著書を出版すれば、政府が宣伝する、「神国日本」というウソ八百も崩れ去るはずだと思った。
もし、彼がモロッコでメソポタミアの神話を読むことがなかったら、フランスに永住することになったかも知れない。彼はフランスに永住することを匂わせるような趣旨の手紙を、日本にいる兄弟にあてて書いている。
アフリカからフランスに戻った石川は、直ちに帰国の準備に取りかかり、大正九年の十月に日本に戻っている。昔の仲間たちは、帰国した彼を盛大に迎えたが、石川は自分が時代の流れから完全に取り残されていることを知った。彼自身も歓迎会の席上でスピーチを試みたものの、思うように日本語が出てこないことに戸惑いを感じた。
石川が日本を脱出した頃は、幸徳秋水がアメリカから持ち帰ったアナーキズムも、革命後のロシアから直輸入されたボルシェビズムも、まだ、草創期にあった。この両派は当局の弾圧が強化されると協調してこれに対抗していたが、第一次世界大戦が終わり、政府の弾圧がゆるむと、一転して相手陣営を攻撃し始め、いわゆる「アナ・ボル対立時代」に突入する。石川が帰国したのは、アナ・ボル抗争の開始期だったのである。
これまで終始一貫マルクス主義を批判してきた石川は、周囲から当然アナーキズムの陣営に加わるものと見られていた。しかし彼は躊躇していた。大逆事件で幹部の大半を失ったアナーキズム陣営は、大杉栄をリーダーにして態勢の建て直しをはかり、その運動は過激の一途をたどっていたからだ。
アナーキストたちも、大先輩の石川に一応の敬意を表していたけれど、「闘争よりも伝道を」と説く彼を過去の人として敬遠していた。アナのなかにもボルのなかにも、石川三四郎の居場所は何処にもなかったのだ。
それでも石川が帰国後に出版した「古事記神話の新研究」は読者に歓迎され、増補改訂を加えながら10版もの版を重ねた。石川に対する講演依頼も多く、彼の社会的な声望は依然として衰えることがなかった。そのうちに奇妙な現象が現れはじめた。左翼陣営からは過去の人として敬遠されている彼を、一部の知識人や少数の若者が熱烈に支持し始めたのだ。
例えば、後に同志社大学総長になる住谷悦治は、東京帝大新人会の主催した石川三四郎の座談会に出席し、寄宿舎に戻ってから日記に次のように書いた。
石川三四郎氏の玲瓏玉のごとき人格に接し、敬慕の情を起こす。
石川が新聞・雑誌に寄稿したり講演会で語ったりしたのは、ポール・ルクリュ家で農夫として過ごした3年間の体験だった。
十年以上も荒れ果てていた(ポール・ルクリュ家の)庭園を開墾したので、ずいぶん骨が折れました。最初はジャガイモがトマトなどのように枝上に実るものと思っていたほど、それほど耕作に無知だった私にとっては、人には想像できないような苦労もありました。しかし、私はこの数年間に、ずいぶんたくさん人生の必要事を学びました。この間における私の労働は、実に私のために、新しい美しい世界を開いてくれました。私は、今、あの愉快な生活を私に与えてくれたルクリュ家・ことにポール・ルクリュ夫人に深く感謝せざるを得ません。
私の理想とする社会は、こうした土民生活を中心として、その周囲にいろいろな産業・工業が営まれるというように組織された社会であります。農業は、単に人類生活の基礎的事業であるばかりでなく、自然の美的生活、あるいは自然の芸術的労作に直接に参加するものであり、高尚な意味における一種の芸術といわねばなりません。
石川が、土地に根ざした労働の生活という意味の「土民生活」を説くのは、自由民権運動家や社会主義者の変節と堕落を見てきたからだった。かつて理想に燃えていた彼等が、次々に権力の前に膝を屈し、その走狗になって行くのはなぜだろうか。
彼はそれを彼等が「土」から離れて都会に移住したからだと考えた。都会で根無し草のような心理状態になった彼等は、土に代わるものを求めて富や地位に走ったのである。従って、誘惑に屈しない生き方を求めるには、地方に戻って土の生活を再開するしかない。
現代人は、本来の地(「ホーム」)を離れて、異境の地をさまよう旅人だという観点に立って、彼は次のように説くのだ。
そもそも我らは地の子である。我らは地から離れ得ぬものである。地の回転と共に回転し地の運行と共に太陽の周囲を運行し、また太陽系そのものの運行と共に運行する。我らの智恵は、この地を耕して得たるものでなくてはならぬ。我らの幸福は、この地を耕すことにあらねばならぬ。我らの生活は、地より出て、地を耕し、地に帰る、これのみである。これを土民生活という。真の意味のデモクラシーである。地は我ら自身である。
石川は無政府社会を実現するための方法を論じる前に、資本社会の誘惑に負けない生活スタイルについて論じる。彼は社会革命の前に人間革命が必要だと強調してきた。だが、人間革命によって実現さるべき各人の存在仕方、処世法が何であるか、明確には掴めないでいた。それがカーペンターやポール・ルクリュの生き方に触れ、自らも農民として生きてみて、土に根ざした労働の生活ではないかと思い当たったのである。
それでは、土に根ざした労働の生活と「美的生活」とは、どのようにかかわってくるのだろうか。土の生活について述べるとき、彼は何時でもそれとのセットのように美を持ち出すのだが、どうしてそんなものを持ち出す必要があるのだろうか。
これも実はカーペンター直伝の思想なのである。
カーペンターは、自然の生み出したものをすべて美とする立場に立っている。衣服には自己顕示欲のような不純な欲求が刻印されているが、人間の裸体にはそんな要素が混じっていない。生身の四肢の一切が、そのままで純粋に美しいのである。美は衣服にではなく、裸身にある。
同様に、天体の運行から四季の循環まで、大自然の生み出すものの一切、つまり「自然の労作」の一切は、すべて芸術的作品にほかならない。すべてが美なのである。機械文明は、この自然の美を破壊するという点でも、排除されなければならない。
石川三四郎は、無政府主義者として階級社会や権力機構を攻撃したが、その言説の背後には常に真実の人間とは何かという求道的な問いがひそんでいた。時には、その求道的な部分が正面にせり出してきて、革命論議が二の次になることもあった。ここに彼が一部の知識人や若者から厚い信頼を寄せられる理由があった。影ながら左翼を応援していた知識層や学生は、プロパガンダの名手や百戦錬磨の闘士に惹かれるのではなく、人間として本当に信頼できる革命家を求めていたのだ。
帰国した石川は、福田英子と暮らしていた家に戻らないで、神田鍛冶町に住んでいる兄犬三宅に旅の荷を下ろしている。ここで三ヶ月近く厄介になった彼は、神田錦町に引っ越して間借り生活に入った。兄の家を出た後も、やはり英子のところには戻らなかった。石川は渡欧前に英子と話し合って、二人の関係を清算する同意を取り付けていたのかも知れない。
英子と疎遠になった空白を埋めるように、石川の前に新しい女性が出現した。読売新聞の婦人記者望月百合子だった。昔から、石川の周辺には親衛隊のように数人の青年が集まり、彼の手足になって動いていたが、これに女性が加わることはなかった。そこへ、断髪、洋装のモダンガール望月百合子が、石川親衛隊に加わってきたのだ。
新聞社の上司から、石川の訪問記事をとってくるように命じられた望月百合子は、まだ20才の若さだった。彼女が新聞記者を志すようになった頃には、石川はすでに海外に亡命していたから、石川三四郎が何者であるか知らないでいた。
その頃の望月百合子が正義感に燃える情熱的な記者だったことは、彼女の言葉からも知られる。
学校を出て独立の生活をしようと思った私は、一つの大きな理想をいだいて新聞記者となった。すなわち、「社会の木鐸」という、清廉潔白・公平無私の新聞記者として、少しでも社会の役にたとうというつもりだった。しかし私のこの夢は、たちまち破られてしまった。社会の役に立とうなんて考えている新聞記者なぞ一人だっていない。もしいたら、それは全く危険な存在なのだ。内情がわかったとき、自分ひとりがんばろうとしたところで、大きな力に押さえつけられてどうにもならないのだと気づいたとき、私はがっかりした。それでも私は、あくまで自分だけは清廉潔白で公平無私の態度を保持しよう、それを武器として要塞と戦おうと思った。
家にまで送り届けられる贈り物を書留郵便で突き返し、夕食の招待などにも絶対に応じない私を、「あなたは、どうしてそう角がとれないのだろう。もう少し柔らかくなれないかな」と上役たちは批難したが、私は自分の信念を正しいと思い、正しいかぎり恐れるものはないと思っていた。(「ディナミック」誌)
こういう彼女にとって、石川三四郎は初めて見るようなタイプの男性だった。石川は当時44才、若い女性を性の対照としか見ない日本の中年男とは違って、百合子を極めて紳士的な態度で遇した。彼女を対等の人格として扱ってくれるのである。一遍に惚れ込んだ百合子は、その後もたびたび石川を訪れ、その度に敬愛の念を深くしていった。
 望月百合子
望月百合子その頃、石川は再度、渡欧の準備をしていた。
石川はパリで知り合った男爵石本恵吉が、エリゼ・ルクリュの所有する地理学書を欲しがっていることを知って、仲介の労を取ることにしたのだ。地理学者でもあったエリゼの蔵書を管理しているのは、甥のポール・ルクリュだった。ポールは叔父の革命思想を受け継ぐと同時に、彼も又地理学者になって、叔父の蔵書をブリュッセルの研究所に託していたのである。ポールから蔵書を譲渡するという返事が来たので、石川は6万冊の専門書を受領するため、石本の代理人としてヨーロッパに渡ることになったのだ。
その話を耳にした望月百合子は、自分も是非同行したいと石川に頼み込む。それで石川は百合子を養女と言うことにして、フランスに連れて行くことにした。百合子は現地で石川の仕事を手伝い、その後、フランスに留まって大学に入る予定だった。
石川が百合子を伴って渡欧の旅に出たのは、大正10年11月のことだった。二人が乗った箱根丸には、皇族の北白川宮も乗船していた。前年に来朝したルーマニアの皇太子への答礼のための渡欧で、ほかにその随員として尾張徳川家19代目の当主徳川義親も乗っていた。徳川義親は東大の史学科・理学部を卒業し各方面で活躍しているインテリであった。
石川三四郎は、この徳川義親と船中で親しくなるのである。そのいきさつを徳川義親は自伝の中に書いている。
北白川宮のお供をして、神戸から箱根丸に乗ると、刑事がぼくをたずねて訴えた。
「この船に、注意人物の石川三四郎が乗っています。石川は社会主義者で、大逆事件の幸徳秋水の友人です。宮様に万が一のことがあっては大変ですから、護衛をよろしく瀬みます」もちろんのことだが、ぼくは石川三四郎の顔も知らない。だが刑事に紹介してもらって会ってみると、石川くんは立派な学者であった。その辺の紳士族よりはるかに立派な紳士であった。石川くんは三等船客だが、一等船客でも石川くんほどの人物は少なかった。
・・・・・石川くんは温厚な紳士で学者である。ばくは友人として尊敬した。石川くんを北白川宮にも紹介した。警察が言うように危険でも過激でもない。むしろ北白川宮もぼくも、石川くんに教えられて視野がひらけたと言える。
徳川義親の知遇を得たお陰で、石川はその後物心両面でどれほど助かったかしれない。
フランスに渡った石川は、ポール・ルクリュと一緒にブリュッセルに赴き、研究所に所蔵されている膨大な蔵書を日本に送り出す仕事にとりかかる(苦労して日本に持ち帰った蔵書は、関東大震災のため、すべて焼け失せた)。無事任務を果たした彼は、望月百合子をフランスに残して、直ぐに帰国している。
徳川義親は、帰国した石川を学習院に在学している三人の娘の仏語教師に雇ってくれた。彼が徳川家の家庭教師になったことが知れわたると、ほかの家からも語学教授の依頼があり、石川は家庭教師の収入で自活できるようになる。彼が崖の下を国鉄の線路が走る滝野川区中里に、家を借りられたのもこのためだった。借家は、小さな二階家だった。
翌年の8月に、石川は徳川義親に招かれて北海道の八雲村を訪ねている。八雲村は失職した尾張藩士を移住させるために尾張藩主が開いた開拓村で、徳川義親はこの年、家族全員を引き連れて村に赴いたのだった。
北海道で徳川家との交わりを一層深めて東京に戻った石川を待っていたのは、関東大震災だった。震災の混乱に乗じて社会主義者の一掃を目論んだ政府は、戒厳令を公布して、「保護検束」の名の下に社会主義者を片っ端から逮捕しはじめた。
石川の故郷埼玉県本庄地方には、「石川三四郎が朝鮮人500人を率いて襲撃してくる」という流言が飛び交っていた。だが、実はその頃、石川は滝野川警察署に「留置」され、危うく殺されそうになっていたのである。震災のどさくさに紛れて、大杉栄夫妻をはじめ、平沢計七、川合義虎などの無政府主義者・社会主義者が官憲の手で次々に虐殺されたが、石川もその犠牲になるところだったのだ。
石川が助かったのは、急を聞いて滝野川警察署に駆けつけた徳川義親が、署長に面会して彼の釈放を求めたからだった。徳川義親は貴族院議員・侯爵の名刺を見せ、署長から、「身元を引き受けてくださるなら釈放します」という約束を引き出したのである。
アナーキストの陣営にとって、震災の影響は甚大であった。
大杉栄を殺されたことに憤激した仲間たちは、一人一殺のテロに乗り出し、戒厳司令官だった福田陸軍大将らを襲撃しはじめた。だが、その計画はほとんど失敗に終わり、アナーキストグループは残されたメンバーまで処刑されたり投獄される羽目になってしまったのだ。
石川三四郎は、こうしてアナーキスト陣営が崩壊して行く様を、黙って座視しているしかなかった。帰国後、実際運動から離れていた彼には、運動を再興する手がかりがなかったし、逮捕を免れたアナーキストたちも石川をリーダーに仰ぐ気持ちはなかった。
唯一の救いは、アナーキズム系の労働組合が全国的な連合組織を作り、「自由連合」と題する機関紙を発行し続けていることだった。石川はこの機関紙に定期的に寄稿することで、僅かに運動とのつながりを保っているに過ぎなかった。
そんな時に、望月百合子が3年半ぶりにフランスから帰ってきたのである。彼女は滝野川中里の小さな二階家で、名目上の「養父」石川三四郎と生活を共にすることになった。石川はこれ以後、活発な著作活動を開始している。ソルボンヌ大学に学んだ百合子からの刺激もあったし、生活面で彼女の支えを得て安心して執筆に専念できるようになったためだった。彼は、「西洋社会運動史」「非進化論と人生」「サンジカリズムの話」「労働組合の話」などの著書を次々に出版している。
これらの著書で彼は、マルクス理論を否定してサンジカリズムの立場を強調している。
マルクスは歴史を背後から動かす動力として、生産力と生産関係の間の矛盾をあげているが、石川は歴史を動かすのはヒューマニティーだという。どんな人間も、生命の根源に善美な世界を求める欲求を秘めており、これが歴史を動かす原動力になっているというのである。
続いて彼は「土民生活について」「農民の新社会」などの著書を出版した。やがて、石川はペンで啓蒙活動をするだけでなく、実際に自分の理想とする「土民生活」を実践したいと思うようになった。石川が、東京郊外千歳村の水車小屋を買い取って、ドンム以来の夢想の実現に乗り出したのは大正15年のことだった。
千歳村の水車小屋について、望月百合子はこんなふうに書いている(文中、パパとあるのは石川のこと)。
この土地は近くの八幡神社の所有になるもので、村の人たちが昔はここで水車を回していたという大きな小屋があり、その中央を川が流れているといった、ものすごいところだった。百年以上もたつ水車小屋の天井は、すすにまみれて竹もワラもまっ黒であり、それに白くヘビの抜けがらがからまっていたりした。
村人の話では、ここは少し前までキツネの巣だったという。パパは、この大きな水車小屋がとても気に入って、さっそく内部を改造して住むと言い出した。私はびっくりして、「それならパパが一人で住みなさい。私はいやだ」とかぶりをふった。そこでパパも、改造しても新築しても同じくらいの費用がかかるのだからと思い直して、この水車小屋はつぶすことにした。
屋敷の中には古井戸が二つもあり、樹齢百年あまりの松やカシの大木が生い茂っていた。畑は二反歩。ここで百姓のまねごとと執筆、そして若い人々との共学生活が始まったのは昭和二年のことであった(注:この年に福田英子が死亡している)。
千歳村の家
石川が「土民生活」にのめり込んで行くのには、「自由連合」紙から彼が閉め出されるという事情も関係していた。同紙に内紛が起き、反石川グループが編集の実権を握るようになったのだ。昭和5年の3月頃から、「自由連合」紙に彼を攻撃する記事が載るようになった。
機関紙には、石川の著書の広告も一切載らなくなった。51号に「石川イズムの迷妄」なる題で、次のような記事が載っている。
彼は人間としてはいいのだが、日本の無政府主義運動の実際の動きに無知であるために転落していった。石川はアナーキストの武力的自由連合活動を理解せず、弾圧の度が高まるごとに非暴力的・個人主義的になっていく。
さらに64号には「似非(えせ)アナーキスト・いかもの伝・石川三四郎の巻」という中傷記事が載り、彼は最後に残された実際運動の場からも排除され、最早、千歳村での活動に専念するしかなくなったのだった。
その千歳村での活動は、最初から波乱含みだった。
石川は自分が建てた家を中心に、農村的共学組織を形成できたらと思っていた。志を同じくする芸術家や学者が集まり農耕世活を営みながら自活し、互いに学びあい教え合って「共進」する。そして、こうした共学・共進する組織が全角に拡がり、それらが自由連合形式で結びつけば、新しい時代を開く礎石になりうると考えたのだ。
だが、彼の考え方は、あまりにも夢想的だったから、足下から反対意見が飛び出した。
いよいよバラックができあがって、そこに移転したのは昭和二年の五月であった。移転祝いをかねて同志の研究会を開いたときは、かなりうれしかった。だが、その祝いの日から、共働者の一人が癇癪を起こして大波乱を演じ、祝いも何もめちゃくちゃになってしまった。最初は、ここに小さいながらも農園を作って、同志と協同生活を試みようとしたのだが、それも、すでに私自身の足下から破綻を生じてしまったのである。(「自叙伝」)
彼はぼかした書き方をしているため、これだけでは何のことか分からないが、「癇癪を起こした共働者」たる望月百合子の手記を読めば、事態が明らかになる。
千歳村の新しい家を私たちは「共学社」と呼んだが、それは「今日の資本主義社会においては、産を共にすることば容易ではない。せめて学問・知識だけでも共にしよう」という意味で、滝野川に住んでいた頃からパパが掲げていたわが家の看板だった。パパは移転祝いの席上でも、
「私有財産を持つことは私の信条に反するから、この家も諸君の共有物として正式に登記したい」と言いだした。すると、さっそく同志の一人である鑓田研一が、「それでは、お言葉に従って、ぼくたちもここへ引っ越して来よう」というのだ。私は、いくらパパの提案でも、こんな狭い家に二家族どうやって暮していけるのか見当もつかず、第一パパ自身の仕事の場所すら無くなる恐れもあるので猛烈に反対した。
すると鑓田氏は、「あなたは欲ばりだ。そんな考えでは千歳村の理想郷は実現できない」と批難する。だが理想郷を作ると言ったところで、周囲はみな他人の地所だ。数年前から武者小路実篤らが宮崎県に建設を進めていた「新しき村」のように、広大な土地でもあるならともかく、ここには二反の土地づきの小さなバラックがあるだけである。
それも、私たちが苦労して建てた家ではないか。そんなわけで鑓田氏と私とは、しだいに感情も高ぶって言い争ったが、結局は私の主張どおり石川三四郎が登記して家の所有主になった。
昭和2年といえば、石川は51才、望月百合子はまだ20代だった。二人は少なくとも滝野川の借家で同居していた頃には男と女の関係になっていた筈で、百合子が石川と「内縁の夫婦関係」にあったとすれば、彼女が理論や理想を二の次にして強烈な主婦感覚で家を守ろうとしたことも理解できる。
実際、百合子は我が儘な主婦だった。
執筆に追われている石川は、自分で二反歩の畑を耕作することが出来ず、百合子に指示して野菜や果樹を作らせた。しかし百合子はこれまでに農作業などやったことのない素人だった上に、農業に対する情熱も持っていなかったから、農作物は全滅に近い出来だった。大体、石川が習得してきたフランス式農法が、気候風土の違う日本で成功する筈もなかった。
百合子は失敗に懲りたのか、畑仕事へに熱意をいよいよ失い、自宅に住み着いた青年たちに農作業を任せてしまった。「共学社」と名付けられた石川の家には、数ヶ月あるいは一年の期間でいろいろな青年が住み着いていたのだ。兵庫県からやって来た奥谷松治という23才になる青年は、すっかり家族の一員になってしまった。
甲府出身の森熊ふじ子も、家に住み込み家事を手伝いながら美術学校に通っていた。彼女は、甲府出身の百合子と同郷の娘で、実家同士が親しかった関係で、百合子が同居を引き受けたのである。
その森熊ふじ子が、思い出を書いている。
先生は週に二回ほど徳川さんのお宅へフランス語を教えに行かれ、在宅のときは書斎でした。畑の方は、ほとんど奥谷さんがなさっていました。先生のお宅の玄関には、「共学社」と書かれた、たしか先生の筆になる小さな看板が掲げられていました。若い同士の方がよく尋ねてこられ、望月さんや奥谷さんもご一緒にお話をなさいます。そんな時の先生は、それは楽しそうでした。
望月さんがどんなにわがままを言われても、いつも静かに聞いておやりになり、奥谷さんや私にもとてもやさしくしてくださいました。私は末っ子で料理も下手で、望月さんにはよく叱られました。そんなとき、いつも、「心配しなくてもいいんだよ」と励ましてくださいました。
寒くなってヒビとアカギレではれあがった手を見て、「かわいそうに」と慰めてもくださいました。
森熊ふじ子は、学校を卒業してから、石川の世話で松坂屋デパートの美術部に就職する。
ひとりの生活に入ってから、いちどだけ先生のお宅へ伺ったことがあります。画材を買いすぎて一文なしになってしまい、郷里の家へ電報を打ったけれど送金が遅れ、どうにも困り果ててお願いにあがったのです。しかし望月さんから、「米が無ければイモを食べたらよいだろう」と教訓され、しょんぼり帰ってまいりました。そのとき、長い長い塀のいくつめかの曲がり角で、ばったり東京からお帰りの先生にお会いしました。「どうしたの」と繰り返しお聞きくださるので、お腹がすいていること、お金がないことなどを、母親にあまえる子どものように、なんの恥らいもなく安心して申し上げました。
「かわいそうに、さあ、いっしょにもどって御飯を食べよう」と言ってくださるのですが、どうしても引き返す気になれません。それで、「やはり帰ります」と言って歩き出しました。先生は黙って私の手に五円札を握らせ、「困ったら、またおいで」と頭をなでて、「気をつけてお帰り」と言われました。
私は、そのお札を握ったまま泣きながら駆け出しました。誰もいないたんぽの隅っこで、おいおい声をたてて泣きました。「先生ありがとう。きっと立派な絵かきになります」と心に誓いながら泣きました。
これを読めば居丈高な百合子の性格と、弱いものに優しかった石川の人柄がよく分かる。若い頃に他人の飯を食った石川には、一歩退いて相手を受容する受け身の姿勢があり、これが福田英子や望月百合子のような攻撃的なタイプの女性を引きつけたのである。
石川は、百合子の命じるままに彼女の髪を梳いてやり、石川のところにフランス語を習いに来る女性たちを百合子が出刃包丁を振りかざして追い払っても、黙って見ていた。
石川が「姉弟関係」「養父娘関係」という虚構の関係を作って彼女等と結婚することを避けたのは、既成の婚姻制度への反発もあったであろうが、やはり内心、彼女等と永続的な関係を持つことにためらいを感じたからではなかろうか。この辺に関する石川三四郎の計算は何時でも確かなのである。
石川が千歳村に「共学社」を開いた頃の日本は、第一次世界大戦後の不況に苦しんでいた。大戦中は空前の好景気に恵まれ、極東の小国だった日本が一躍「世界的な強国」になったものの、戦争が終わると政治・経済の後進性があらわになり、日本は世界に先んじる形で戦後不況に落ち込んだのである。そして、「共学社」が発足した昭和2年には、金融恐慌に襲われ、つぶれた銀行が28行に及ぶという惨状になった。
昭和5年になるとアメリカに始まる世界大恐慌の波が日本に押し寄せ、日本は都市も農村も不景気のどん底に落ちる。同じような状況下で、ドイツではナチス党と共産党が急進したが、日本でも右翼と左翼が勢力を伸ばし、軍の内部に「一君万民」を唱える青年将校の群れが生まれたのに対応して、民間では労農党、日本共産党の勢力が大きく伸びることになった。
こうして社会全体が大きく動揺している時代に、石川は昭和4年「ディナミック」を発行している。発行部数1000部、A4版4ページのリーフレットである。「ディナミック」の基本路線は、マルクス主義が生んだ双生児として「ボルシェキスムとファスシスム」の双方に挑戦するものだったから、最初から廣い読者層を期待出来なかった。石川はそれを承知で、少数派に徹する路線を選んだのである。
「ディナミック」は、石川が自分の思想を発展させるための「ノート代わり」という役割もそなえていたため、紙面の半分以上は石川自身の論考で埋められていた。
「ディナミック」の創刊号に、石川の次のようなアピールが載っている。
読んでもらいたいのは山々であるが、しかし私の第一の要求は、自分が書きたいのである。翻訳に追われて忙しい中にも、時々は「書きたいなあ」と思うような感想などが浮かぶ。裏の畑で果樹などを眺めながらも、「おもしろいな」と感じるような思想がわいてきたりする。だが、そうした思想や感想は、いつも必ず、すぐ他の仕事の中へ消え去って再びつかまえることが出来なくなってしまう。・・・・だからこの小紙片は、私のノートを保存するつもりで印刷するようなわけなのだ。
狂気のような言論弾圧が吹きすさんでいたあの時代に、「ディナミック」の刊行が5年間もつづいたのは、大衆路線を狙わないで、自問自答するような形で自らの思想を紡ぎ、それを少数の読者に頒かっていたからだった。ここに反動期に生きる人間の生活スタイルがある。石川三四郎は勇敢な人間ではなかった。難しい局面にぶつかるとその場を逃げ出して亡命したり、自己の拠点を少数者の世界に移したりする。幸徳秋水や大杉栄が自身の思想の命じるままに、一本道を突き進んで悲劇的な死を遂げたのに比べると、石川は明哲保身の術に長けていたのである。
「ディナミック」に掲載された文章の多くは、「近世土民哲学」という冊子に転載されている。これを読んでみると、かなり現実離れした意見が多い。現代人には、無政府主義そのものが現実を無視した空論にしか見えないのだが、石川の議論は特に空想的に見えるのだ。
彼は国家が年々作り出す法律の複雑煩瑣なことに触れて、国家を解体してそんな法律を必要としない自治的な小集団に分解すればいいという。ところが現実には、国家組織は巨大化し複雑化する一方だし、経済のグローバル化によって世界全体が巨大な単一経済システムになって来ているのである。
彼はいう──農民も職人も、他人を雇用することなく、その経営規模を自己資金と自己の労力だけで運営可能な範囲に留めるべきだ。集団内の人間は、すべてを自力でこなさなければならないから、多芸多能のオールランドプレーヤーになる。そうなれば殊更他人を雇用する必要はなくなるのだ。
彼の提言はすべて机上の空論であり実現不可能に見えるけれども、百年先、千年先の尺度で見たらどうだろうか。
石川は、土地改革に関連して「自作農ならざる土地の所有者から悉く之を徴収して其れを耕作者に分配する」ことを提案している。彼がこの提案をした頃には、こうしたプランは痴人の夢と考えられていた。だが、戦後の日本は占領軍の指示のもとにこれをちゃんと実現しているし、現代の先進国にあっては、自作農に農地を与える土地政策は当たり前のことになっている。フィリピンのように、土地改革に手をつけず、昔ながらの地主制を温存している国は、経済発展から取り残されて開発途上国レベルから抜け出せないでいるのだ。
彼はまた巨大都市を分割し分散させる必要性について論じる。今でこそ、これは途方もない夢物語と思われているけれども、さほど遠くない将来においてこれが政策課題のレールに載せられることは疑いないように思われる。
石川三四郎は、その独自の宇宙観・世界観によって、無政府社会は放っておいても実現すると見通していた。宇宙を無限に拡がる無中心の空間と考えていた彼は、無数の星々は手近なところで自由連合方式の星座を作り、その星座同士がまた自由連合方式でつながらざるを得ないと考えた。この宇宙は、一種美的な構造を生み出しつつ、無限に変化し生々流転を続けるのだ。
地上の世界も、自由連合する個人・集団が相互に関連しあう網状組織を作り、一波が万波を呼ぶ「変化発展」を続ける。この生々流転相には「必然のプラグラム」のようなものもないし、終点もない。ただ、無限に変化し続けるだけなのだ。この変化を拒み、一度確立された社会体制を守ろうとするのが、権力なのである。しかし、権力の試みは失敗する。すべての人間は、その生命の根源に「イデー・フォルス」を秘め、これが歴史を動かす推力になっているからだ。
「イデー・フォルス」とは、力学的な力を持ったイデーであり、美的世界を実現しようとする創造力である。宇宙が生々流転するのは、宇宙の背後に美的秩序を生み出そうとする生命的なものがあるからであり、社会が無政府社会を志向するのも、宇宙生命を分有する人間の生命に「イデー・フォルス」があるからなのだ。
石川は、「イデー・フォルス」によって放っておいても無政府社会は実現すると考える一方で、人間の生命は「イデー・フォルス」を打ち消す「無明」を内包する故に、社会は常に不完全なものに後戻りするとも考えていた。彼は楽観主義者であると同時にニヒリストだった。人間は永遠に目的に達することが出来ない、むなしく途上を彷徨するに過ぎないという諦観を抱いて生きていた。
「ディナミック」の読者のすべてが、石川の見解に賛意を表したのではなかった。
「石川三四郎の生涯と思想」の著者北沢文武は、石川に対する読者の不満や、石川の敵対者側からの悪罵を紹介している。
読者の一人であった村上信彦も、「創刊以来一年あまり、ディナミック紙上には、毎号ただ同じような空漠とした原理だけが載せられているのみ」と不満をぶちまけた上で、「しかし、問題は〝いかにして!〟 にあるのです。この点にこそマルキシズムとアナーキズムの差があるのです」と結んだ手紙を三四郎に送ってきている。・・・・・「自由連合新聞」派などは、昭和六年十一月十日付同紙上で、「ディナミックは、石川宗のおさい銭あつめの機関紙」と罵り、その「教祖」を次のようにこきおろしている。
「いつの間にか民衆にとり残された石川は、悶々のあまり、おのれがわずかばかり趣味の畑を持っているところから、アナーキストの生活態度をとやかく攻撃したりしている。ねこの額ほどの畑を借り受けて小作人となったことを自慢するあたり、昔ながらのキリスト教社会主義者だ。その辺は、『新しき村』の武者小路実篤あたりとびったりする共通点だ。『土を愛する会』か『土の趣味の会』でも始めたらよかろう」
そのうちに「自由連合新聞」派を喜ばせるような事件が起きた。石川三四郎に不満を持つようになった望月百合子が、千歳村を出て行ったのだ。これに関連して「自由連合新聞」には次のような記事が出た。
ヒステリイで村中を駆け回る千歳村の名物女・望月百合子は、このごろツバメをこしらえたらしい。それで洗濯物でも何でも石川のはせずツバメのことばかり熱心にするので、どうも折り合いがうまくいかず、別居することになったそうだ。
一体、百合子は石川の何処に不満を持つようになったのだろうか。
百合子が石川に惹かれたのは、その受け身とすらいえる穏やかな対人態度や、女性を尊重する騎士的精神に対してだった。だが、同棲生活をつづけているうちに、百合子は最初惹かれた、その点に不満を持つようになったのである。
小柄で華奢な美女だった百合子は、幼い頃から「かわいい、かわいい」と頭をなでられて育てられてきた。百合子は、こんなふうに人形扱いされることに反発して、「女は知能を発達させると同時に体力・腕力も養わねばならない」と主張するようになる。白粉を塗るひまがあったら、男に負けない腕力を身につけよというのだ。彼女は「ディナミック」誌上で女が腕力・体力の面で男と対等になって、はじめて男女同権は実現すると断言している。
周囲からヒステリー女と評されるほど激しい性格を持った彼女は、石川の暴力否定の戦術論にも不満を抱くようになっていた。そして、金子文子の友人で、獄死した文子の遺体を引き取りに行ったことのあるアナーキスト古川時雄と親しくなると、古川たちの前で石川のことを「あのオヤジはバカでどうにもならない」と罵るようになった。百合子のこの放言は、石川の耳にも入り、やがて彼女は千歳村を出て行くことになるのだ。
千歳村を出た百合子は、古川時雄と結婚して新宿一丁目に「仏英塾」という塾を開き、かたわら「フランス書房」という古本屋を開業している。この店について百合子は、「私の店では、モミ手をしたりネコなで声を出してまで買わせたくない。そんな卑屈な資本主義的商人になりきるほどなら、私はむしろ餓死を選ぶ」と勇ましく宣言している。彼女の宣言通り、店は一年後にはつぶれてしまっている。
百合子が家を出る前後の昭和8年、石川は三度目の渡欧を考えるようになった。
切っ掛けはポール・ルクリュが渡欧を勧めてきたからだが、内実は百合子とのトラブルにうんざりした石川が、得意の遁走術に出たのではないかと思われる。この年の9月に発行された「ディナミック」誌には、「一身上の都合で、今後約一年間、放浪の旅に出る」という石川の予告が載っている。
だが、ヨーロッパ行きの旅券がなかなか下付されなかったため、彼はひとまず中国を目指して日本を出発した。中国に渡った石川は、ルクリュ家の一族ジャック・ルクリュが北京大学の教授をしていたので、その屋敷の厄介になった。そして北京を起点にして中国の史跡を訪ね歩いているうちに、すっかり中国の古代文明に魅惑され、中国史を本格的に勉強する計画を立てるようになった。
もともとヨーロッパ旅行には確たる目的があるわけではなかった。それで、石川は渡欧の計画を打ち切り、一旦日本に戻り、東洋史研究の方策を探ることにした。こうして彼は中国に滞在すること三ヶ月で日本に舞い戻ってくるのである。
帰国した石川のところに、新たに彼の世話をする女性が現れた。石川三四郎という男の前には、何時でも親身になって面倒を見てくれる女性が現れるのだ。
山梨県出身の新津志寿は、はじめ百合子を頼って新宿一丁目の「仏英塾」にやってきて、フランス書房の店番や家事の手伝いをしながら、タイピスト学校に通っていた。それが、千歳村の「共学社」へ手伝いに行ったのを機縁に、ついにはここに永住することになるのだ。石川と志寿は深く信頼し合う仲になり、二人は正式に養父・養女の関係になった。志寿は、それ以後改名して「石川永子」となる。
北沢文武は、「石川三四郎の生涯と思想」のなかで石川永子について次のように書いている。
昭和三十一年九月下旬、死が迫りつつあることを覚悟した石川三四郎は、病床に半身を起こして両手をひざに重ね、永子を見つめながら、
「長い間ありがとうよ。永子のおかげでオレはこれだけの仕事ができたんだよ。しかしねえ、こんな素直ないい娘をずっとオレのそばに置いちまって、しかも、そのあんたに少しのお金も残すことができなくて済まなかった。だが、オレが八十年の生涯で一ばん愛したのはあんただった。ほんとうだよ。もう二十年も永子が年をとっていたら結婚したかったんだが」
と、しみじみ語ったという。
石川永子が「共学社」に住み込むようになった昭和9年の10月に「ディナミック」は矢折れ刀つきる形で廃刊になった。度重なる発売禁止の処分を受け、出版費用が枯渇してしまったのだ。終刊号は僅か1ページというさびしいものだった。廃刊するに当たって、石川は「私は、常に同志を百年の後に求める気持ちで、ものを書いてきた」と総括している。自分は、アジテーターたるよりも、エデュケーターたらんとして「ディナミック」を刊行してきたというのだ。
「ディナミック」廃刊から昭和20年の敗戦まで、石川は激しくなって行く戦争をよそ目に千歳村にこもって東洋文化史の研究に専念している。そのかたわら、畑を耕して野菜を作っているから、文字通り「晴耕雨読」の10年間だったのである。研究の成果は、まず昭和12年に「東洋古代文化史談」の刊行という形で現れ、その後も、「東洋文化史百講」と銘打った著書が断続して出版されている。
食料が配給制になったときには野菜類の配給を辞退したり、友人に収穫物を分けたりしているところをみると、彼は野菜作りの面でも相当な成績をあげていたらしい。こうした平穏な生活を送る石川の身の上に、小さな波乱をもたらしたのは随筆集の「時の自画像」が発売禁止になったことと、中山益子に求婚したことだった。
「時の自画像」は、石川が「日本学芸新聞」などの寄稿した文章を集めたささやかな本だったが、時局に対する批判的な発言があるという理由で発売禁止になった。批判といっても大したことはなかった。「満座のものが酔っぱらったからといって、自分まで酔うわけにはいかない」とか、「日本精神の宣揚ということが流行になっているが、かえってそれは日本精神を亡ぼすものだ」という趣旨の文章が書きこまれているに過ぎなかった。だが、文筆業者のほとんどが、声を揃えて「聖戦」を礼賛している時代だったから、こうした片々たる文章も当局の忌諱に触れたのである。
石川が中山益子に求婚したのは、「ディナミック」廃刊後の心の空虚を埋めるためだったかもしれない。廃刊から半年ほどして、石川は養女の永子を呼んで、突然、結婚したいと切り出したのだ。
「中山益子さんと結婚したいと思うのだが、使いを頼まれてくれないか」
石川には、三人の女友達があった。一人はバイオリニスト諏訪根自子の母諏訪たきであり、一人は俳人一茶の研究者川島つゆで、もう一人が中山益子だった。中山益子は徳川義親家の家庭教師をしている4,50才の独身女性で、彼女が徳川家の執事らとトラブルを起こすたびに石川が乗り出して取りなして来たという仲だった。
永子は目白の女子大アパートに住んでいる中山益子を訪ねて石川の希望を伝え、中山益子もよろこんで千歳村にやって来るようになった。だが、この話は望月百合子の反対で、稔ることなく終わった。永子は書いている。
それから中山さんは、たびたび千歳村に見えるようになりましたが、望月さんはこの話を耳にするや猛烈に反対しました。中山さんから送られてくるカンづめ類まで、直ちに送り返すぼどでした。やがて、中山さんからは手紙だけが時おり届く程度になり、それから二年ばかり後に、信州の大学教授と結婚されたとか、父(石川三四郎)から聞かされました。
不思議なのは、石川と望月百合子の関係だった。百合子は古川時雄と結婚しているにもかかわらず、石川の求婚相手に猛烈に嫉妬している。そして古川時雄が日中戦争のはじまった昭和12年に満州に渡ると、百合子は千歳村に戻って石川と同居するのである。同居一年足らずで、百合子は夫のあとを追って満州に渡るけれども、この時には今度は石川が反対している。石川を振り切って渡満した百合子は、その後彼が亡くなるまで顔を合わせることがなかった。
昭和20年になると、米軍機の空襲が激しくなった。3月の末日に石川は山梨県上野村にある永子の実家に疎開する。実家には永子の実父母が生きていたが、石川のために物置を改造して書斎にしてくれた。石川は疎開したその日から、午前中は机に向かって研究し、午後はクワをとって庭先の畑を耕すという生活をはずめた。
永子によれば、石川は直ぐに村の生活に馴染み、村民から歓迎させたそうである。
「父(三四郎)のかざらぬ態度は、特に村人たちに好感を与えたらしい」と彼女は追憶記に書いている。石川には農民にありがちな卑屈さも、よそ者になじまぬ偏屈さもなかったというのだ。
若い頃から病弱だった私の実母は、その当時ガンで病んでいた。腰が地に吸い込まれそうにダルイと訴える母に、夜のひととき、「フランスで習ったハクライアンマですよ」なんて言いながら、父は指圧をしてあげた。また茶が好きだった母に、父はクワの葉をつんで、「上野村の銘茶〝不尽″です」と言いながら、ふかしてほうじてやった。母は一服ゆっくりとすすって、「この茶には少し力が足りない」と、やつれた顔で笑った。母の父に対する感謝は厚かった。
石川が永子の実父母にも温かく迎えられ、東洋文化史に研究に打ち込んでいるうちに、8月15日、敗戦の日が来るのである。
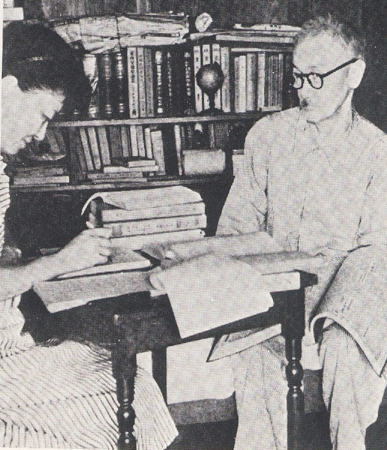 口述する三四郎と石川永子
口述する三四郎と石川永子8月15日、天皇の放送を耳にした石川三四郎は、異様なほどに興奮した。そして永子の実父母が引き留めるのに耳を貸さず、その次の日には東京に戻っている。無政府社会実現のチャンスが到来したと思ったのである。彼は全国に散在する同志に宛てて「無政府主義宣言」というアピールを配布し、大同団結を訴えた。
しかしアナーキストの全国組織を作るには予想以上に時間がかかり、翌昭和21年の5月になってようやく「アナーキスト連盟」の結成大会を開くことが出来た。委員長には岩佐作太郎が就任し、石川三四郎は顧問に推挙された。この時、石川はすでに71才の高齢であった。
それまで実践運動にはあまり関与しなかった石川は、戦後、人が変わったように熱心に活動しはじめた。彼は老躯をむち打って全国各地を巡り、エネルギッシュな「伝道行脚」を展開している。だが、運動家としての彼には、とかく風変わりな言動が目立った。
彼が心の中に描いていた青写真は、地方組織・地方集団を自由連合方式で結びつけ、その上に政治上の実権を持たない天皇を置くというものだった。石川は記紀研究の影響からか、天皇が好きで、無政府社会が実現しても、天皇にしかるべき居場所を与えたいと思うようになっていた。彼は、天皇を「愛の象徴」としてなら、残すことができるのではないかと思ったのである。こうした彼の構想は、無論、同志の容れるところとはならなかった。
「アナーキスト連盟」の運動方針も、何かしらピントが狂っていた。選挙のたびに連盟は、国会をも地方議会をも否定し、「棄権によって、不信任の意志を表明しよう」と訴える。これでは、選挙と名の付くものすべてに候補者をくりだす日本共産党にかなうはずはなかった。
連盟の機関紙「平民新聞」は読者の減少のため廃刊し、昭和24年には「アナーキスト連盟」そのものも内部的対立のために解散してしまう。石川は連盟の解散に屈せず、同年にアナーキズムの共同研究会を発足させ、昭和26年にはこれを「近代学校」に発展させている。
彼はこの学校の基金を作るために大事な蔵書まで売り払っている。だが、借りていた会場から閉め出されて学校は、僅か二回開講しただけで終わりを迎える。石川が脳溢血に襲われて病床に伏すのは、近代学校閉鎖の翌年、昭和27年のことだった。半身不随になった彼は、言語障害を併発し、もはや執筆も講演もかなわぬ身になった。それでも彼は病気の合間を縫って、永子に筆記させて自伝の口述に着手している。
自伝の筆記は、過去に発表した文章を時代順に並べ、それに口述部分を追加するという形で続行された。
「一々資料を読ませては記憶を系統づけながらの口述であり、ことに想を練りながらも、言語障害のため思うように発表できぬ焦慮は、はたの目にもつらく、何度この仕事を打ち切ろうとしたかしれません」
と永子は語っている。
口述筆記の「自叙伝」が完成し、理論社から出版された昭和31年、石川三四郎は突然発作に襲われて危篤状態に陥った。呼びかける永子に、石川はとぎれとぎれに告げた。
「ベンキョウ・・・・・ヒトヲ、シンジ・・・・・ナカヨク」
そして、永子に囁いた。
「エイコ、アリガトヨ」
昏睡状態になった彼は、その二日後に息を引き取っている。遺言により、石川の葬儀は行われなかった。享年80才、アナーキストとしては異例の高齢であった。
こうして概観してみると、石川三四郎の生涯は当時の「主義者」らのそれに比べて地味で、印象が薄い。彼が運動に貢献したのは「新紀元」を刊行してキリスト教系の社会主義者をまとめたことくらいのものなのだ。社会主義者としてもアナーキストとしても影の薄かった彼が、現代にいたって格別の評価を得ているのはなぜだろうか。
一言でいえば、石川三四郎がブレなかったからなのだ。
自由主義者も社会主義者も、太平洋戦争が始まると雪崩をうって「聖戦」賛美にまわり、最後まで節操を守ったものはごく僅かでしかなかった。石川は最初から最後まで戦争に反対し、権力に対する抵抗の姿勢を崩さなかった。影が薄く一向に目立たなかった人物だけに、彼の志操の固さが人を驚かせるのだ。
しかし、「影の薄い目立たなかった人物」だったからこそ、ブレなかったとも言えるのである。廣く名前の知られた、「全国的な人物」だったら、時代の空気に逆らうことは困難になる。自分の知名度を保とうとすれば、大勢に同調し、世論を鼓舞する言動を示さなければならない。有名人は、多数意見の代弁者たることを自分に負わされた義務のように考えてしまうものなのだ。
亡命生活を切り上げて帰国した石川は、「土民生活」を実践するためのささやかな拠点を千歳村に設けた。以来、彼は午前中に研究と執筆、午後は畑仕事という単純な生活を約30年にわたって続けた。千歳村の小さな家で繰り広げる静かな日常そのものによって彼は堕落から守られ、権力に抵抗する意志を保持できたのである。
石川は獄中で人間には「ホーム」が必要だと考え、出獄後に、「ホームに帰れ」と力説する本を書いた。そのホームとは、人間自性のエネルギーを過度にもならず、また過少にもならず、適正に行使する場のことであった。彼は千歳村にこのホームを作り出し、人に支配されず、また支配もしない30年を過ごしたのだった。
ホームでの静かな日々は、石川の意識を広大な宇宙に向かわせた。戦後になって彼が執筆した「社会美学としての無政府主義」「幻影の美学」などを読むと、彼が宇宙に思いを寄せながら戦中・戦後を生きていたことが分かる。
宇宙は一つの芸術体である。春夏秋冬、花鳥風月、自然の奏づる交響楽でないものはない。社会もその宇宙の一部分であり、また特殊の芸術体である。その芸術体の構成者である民衆は芸術家であり同時に鑑賞家である。(「社会美学としての無政府主義」)
人間は宇宙の一員であり、宇宙交響楽を演奏する楽団員の一人だが、この「オーケストラには、コンダクターは居ない」と彼はいう。
人が地上に生み出す芸術上の美は、当人には善として意識される。芸術的な観点から見れば美であるけれども、社会的な観点から見れば善なのである。われわれは善を実現しようとして反権力闘争に乗り出すが、これは実は宇宙的な美を実現するための活動に他ならない。
彼は人間も宇宙の一員だという立場から、インターナショナル、国際連盟、国連などにも批判のメスを加えた。これら国際連帯を説く組織のメンバーは、無意識のうちに自国の利益を頭に置いて行動するから、実効があがらないのである。ソクラテスは「俺はアテネの市民ではなくて、コスモスの市民だ」と言ったし、ギリシャ産のアナーキスト、ディオゲネスも「俺はコスモスの市民だ。コスモスの政府しか認めない」と宣言している。自国意識から抜け出し、コスモス(宇宙)の市民だという自覚に立たなければ、一切の国際組織は有名無実のものになってしまう。
戦後に世界政府の運動が起こり、世界市民を自称する文化人が多く現れたが、石川三四郎はこれを一歩飛び越えて「宇宙市民」としての自覚を持つ必要性を説くのである。私はここに彼の生き方の真髄があるように思う。
彼は小さな迷いや過ちを重ねながら、トータルとして見れば首尾一貫したアナーキストだった。これは彼が、宇宙市民として生きたからではなかろうか。彼はテロや暴力に反対し、階級闘争よりも「伝道活動」を重視した。ストライキを成功させようと一喜一憂するのは、局地戦にとらわれて目が見えなくなっているからだ。彼は第一次世界大戦、第二次世界大戦を潮の干満を眺めるような俯瞰的な目で見ていた。何ものにもとらわれない「宇宙市民」の目で見ていたのだ。
石川がブレなかったのは権力に対する姿勢ばかりではなかった。
彼は誰の前に出ても卑屈にならず、反抗的にならず、平常心で接していた。平常心を保てなくなると、遁走を開始したが、基本的に彼は人を差別したり、えり好みしたりすることがなかった。彼は弱いものに手を貸し、病人にやさしかった。こういったことのすべては、彼が現世から一旦自分を引き抜き、宇宙市民として再度この世に立ち帰って来た人間だから可能だったのではないか。
われわれが石川三四郎に続こうとしたら、まず、「土に根ざしたホーム=自立した生活空間」を持たなければならないだろう。次に、宇宙市民として生きる安定した生活システムを取得しなければならない。こうなって、初めて権力にも習俗にも屈しない少数者としての生を貫徹できるのである。