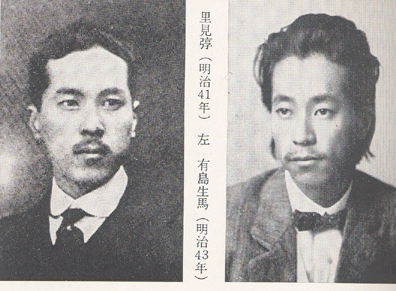有島武郎の生と死(3) 1 皇太子への拝謁を拒絶された事件の3年後に、有島武郎は農科大学を退職してフリーの身になった。大学を退職した直接の原因は、結核になった妻の安子を転地療養させるためだったが、教職を去りたいという希望を彼は以前から持っていたのである。友人に語ったという彼の言葉が残っている。
「教師なんか、とうに止めたいのだが、弟たちが皆官職についていないので、昔気質の父は長男の僕が官職についているということが大きな慰めだったのだが、今度は萬やむを得ない事情から父も仕方なく退職を許したのだ」
安子の病気は、寒冷の地で男の子を三人毎年続けて産んだことが原因になっていると思われる。
鎌倉に転地することになったとき、安子は病気の感染を恐れて、全快しない限り子供たちとは会わないと言い切っている。彼女は武郎には泣き顔ひとつ見せなかったが、実母と義母の前に出ると泣き崩れ、容易に泣きやまなかった。彼女は杏雲堂病院に入院して療養に努めたものの、病状は一向に好転しない。そのため退職後の武郎は、東京の自宅から鉄道を乗り継いで湘南に出かけ、妻を見舞ったのちに帰宅して幼い三人の子供の面倒を見るという生活を続けた。
死を控えた安子は、武郎に長い遺書を書いている。
……こんな何一つとりゑのないふつっか者をよくも愛して下さいました。導いて下さいました。ほんとに心の底の底から私は難有いともうれしいとももったいないとも思って居ります。あなたのやうな美しい尊い方を夫に持ったと言ふ事が短い生涯の中の唯一つのほこりで御座います。この誇りの為めに私は淋しい中にもよろこんで死ぬ事が出来るので御座います。……
此十日ばかり私の心は死といふ事ばかり思ひつヾけました。そうして今では死を思ふ事は楽しみの様になりました。恋人の上でも思ふ様に死ばかりを思ってゐます。
それから私はあなたの御成功を見ないで死ぬのが残念で御座いますけれども、必ず御成功遊ばす事と信じて居ります。凡ての事に打勝って御成功遊ばして下さい。あなたに対しての唯一の御願で御座います。
武郎は既に農科大学にいた頃から、「白樺」に加入し作品を発表していたけれども、それらは短い感想か小説の習作に過ぎず、本格的な創作活動を開始するには至っていない。しかし妻の安子は、夫の願いが作家として大成することにあると知っていたから、遺書の最後にこの点を書き入れたのである。
武郎が妻の心情に触れたのは、安子の死後、彼女が病中に記した数多くの遺稿を整理しているときだった。彼は新婚当時、床についてから妻に毎晩一つずつ話をしてやったことを思い出した。年若い妻を慰めるために、彼はそんなこともしていたのである。
武郎は今はない妻に向かって語りかけた。
安子! 私はお前の中に、その愛を全く私にのみ注いだ一つの魂を発見した。私は何の保留もなく信頼しうる人を、少なくとも一人は持っていることを悟った。私は全く価値なしに生きてはいない。彼女を追想することは力を獲得することである。その死によって彼女は愛から力に変わったのだ。
安子は、ただ夫だけに看取られて死にたいと願っていたが、希望していたとおり彼女は武郎一人に見守られながら臨終を迎えたのである。妻に続いて、同じ年に父も胃ガンで死去した。
武郎は、父が死んだときに後顧の憂いなく創作に没頭できる環境が整ったと思った。彼は友人たちに、父の生存中は作家活動を本格化できないと語っていた。妻の安子は、夫が父に遠慮して踏み出せないでいることを一番よく知っていたから、遺稿のなかにこう書き残していたのだ。
あなたは御自身の真実の生活に飛び入らずに遠慮してゐらっしゃるのです。あまり人の為めばかりを思ひ過ぎなさる。親孝行の美しいあなたの御性質がそれを躊躇させてゐるのです。私はあなたのその御心を思ふ毎に泣きます。
だが、武郎が父の目を恐れたのは、単なる遠慮からだけではなかった。父をニーチェ主義者だと考えていた彼は、そんな父に自分の作品を「人生における敗残者の産物」と見られることを好まなかったのだ。父は普段、こう言っていたのである。
「万物は生存競争によってその存在を維持し、自然力の制裁によって健全、卓越、強壮なものだけが残るのであり、大慈悲心というごときは人間最高の徳などではなく、逆に人間進歩の真諦をあやまらせるものだ」
父は、バイタリティーに欠ける武郎を、「自然の制裁」を受けて敗北して行くのではないかと常に懸念の眼で眺めていた。そんな父からすれば、息子が情痴小説の作家になり、「カインの末裔」「或る女」というような作品を発表すれば、きっと、これまでの懸念を裏書きされたように思うに違いないと、武郎は想像していたのであった。
2 妻と父を葬った有島武郎が、本格的な作家活動を始めようとしていたときには、「白樺」の仲間たちは、すでに新進作家として文壇で華々しい活躍をしていた。武者小路実篤・志賀直哉・長与善郎ばかりでなく、弟の有島生馬も里見弴もすでに作家としての地位を確立していたのだった。
武郎は最初から「白樺」にあっては、別格の存在だった。武者小路らは、生活に不自由のない華族・資産家の息子たちだったから、学習院を出ても定職につかず文学青年として、「のらくらしていた」のに対し、武郎は彼等より一回り年長であり、その上、帝国大学教授という赫々たる地位にあった(「白樺」加入時には彼は講師から教授になっている)。その彼が、父と妻の死後、堰を切ったように作品を発表し始めたのである。「白樺」派の異色分子、遅咲きの大型新人として、有島武郎は世の注目の的になった。
武郎自身、急に脚光を浴びることになった自分に戸惑っている。
私は過去八年間白樺誌上で感想や創作を発表してきました。発表した数と量とは情けない程貧弱なものではありましたが、公衆の評壇からは全く無視され度外視されてゐました。それが、どういふ風の吹きまはしか、今年になって、急に兎や角云はれ出しました。多分公衆の眼に触れやすい色々な文芸雑誌が私の作物を買ふやうになったからでせう。
大正六年に、彼は以下のような作品を発表している。
「死と其前後」
「惜しみなく愛は奪う」(第一稿)
「平凡人の手紙」
「カインの末裔」
「クララの出家」
「実験室」
「凱旋」
「奇蹟の詛」
このうち「カインの末裔」は、多くの作家を瞠目させた近代日本文学の本道を行く秀作だったが、その他の有島作品は他作家の作品に比べて少しずつ毛色が違っていた。「死と其前後」「奇蹟の詛」は戯曲形式で書かれ、「クララの出家」「奇蹟の詛」は題材を外国から取っている。「平凡人の手紙」は私小説に違いないけれども、反省や分析をまじえた一種の観念小説だった。
読者はこれらの何処か西洋臭い作品を通して、土着の日本人作家にはない博大な学識と知性の輝きを感じ取ったのである。武郎は漱石・鴎外の後継者と見なされ、実際、彼は漱石が得ていたと同様な人気を知識層の読者の間に獲得したのである。
だが、武郎には漱石・鴎外と決定的に違うところがあった。
彼は、あらゆる行動のうちで本能的行動を最高位に置いていた。漱石も鴎外も、自分が行き着いた信条・思想から退転することはなかった。武郎は、作品の中で彼にとって理想的人格であるところの本能的生活を推進する人物を描きながら、最後に彼等を冷厳な現実のまえに突き落として、敗者にしてしまう。それが武郎の到達点だったとしたら、彼はこの視点を簡単に放棄すべきではなかったのだ。武郎が漱石・鴎外と違っているところは、初志を貫徹し得なかった弱さであった。「カインの末裔」の主人公広岡仁右衛門は、旧約聖書に出てくるカインのような無法者で、本能の命じるままに行動する。武郎は周囲に混乱と摩擦を引き起こしながら生きるこの乱暴者を、その直情的行動の故に肯定する。武郎が生きようと欲して生き得なかった人生を、広岡仁右衛門が代りに生きてくれているからだった。ところが、その広岡仁右衛門は地主の前に出るとへなへなと意気地無く屈服し、悄然と農場を去っていくのだ。
「実験室」の医師も、妻が結核のため喀血死したとき、親族等の反対を押し切って死体の解剖を強行する。死因について、病院長を始め同僚の医師たちと見解を異にした彼は、自説の正しさを立証するために妻の遺骸を切り刻んだのである。解剖の結果、彼の見立てが正しかったことが証明される。彼は一旦は勝利の喜びにひたるが、その後に荒涼としたむなしさに襲われるのである。
広岡仁右衛門も、妻を解剖した医師も、自らの生命的要求を貫きながら、最後に冷え冷えとした現実に直面する。私小説「An Incident」に描かれた武郎も、激情に駆られて子供を折檻した後で空虚感に襲われているし、「或る女」の葉子も、作者によって最後に破滅させられている。向日的な気分を感じさせる作品は、僅かに「生まれ出ずる悩み」程度であって、その他の生命的行動を主題にした作品は、ほとんど暗い結末をもって終わっているのだ。
こうした作品に見られる「悲観的な姿勢」は、現実に対処するときの武郎の内面構造を現しているように思われる。彼は武者小路実篤が「新しき村」を始めたときに、計画は失敗するだろうが、あえてチャレンジした勇気には敬意を表すると書いて、武者小路を怒らせている。武郎は理想を阻む現実の壁を、常に過大に意識していた。狩太農場を小作人に無償で譲渡したときにも、彼は自作農になって喜んでいる農民等が、そのうちに奸悪な地主等の餌食になっていずれは農地を奪われ、再び小作人に転落してしまうだろうと予想しているのである。
現実の日本社会を、「白く塗りたる墓」「糞桶」と見ていた武郎は、革命でも起こらない限りどんな改善策も実現不可能だと思っていた。だが、彼はテロリズムに賛同できなかった。すると、彼はクロポトキンが描いて見せたような理想的な「相互扶助」社会を夢見ながら、同時に矯正不能の日本社会を眺め、この二つの世界に挟まれて座して耐えているしかないのだった。
サンドイッチのように二つの世界に挟まれ、身動きがとれなくなっている状況は、武郎の内面にも存在した。内心で、本能のままに行動しようと欲しながら、現実の彼は肉親や世俗への配慮から、当たり障りのない偽善的な行動を選ぶしかなかった。武郎の内部には本能的自己と世俗的自己という二項対立があり、彼の自我はこの二つの中間にあって右顧左眄しているのである。
彼は、中川一政に次のような手紙を書いている。
・・・・私は虚偽でいっぱいになった人間です。・・・・私は如何に私自身を粉飾すべきか心得ています。心得ているばかりでなく、悲しいことには不知不識の間に実行しています。而してそれが私の唯一の仕事なる芸術の中にも隠見するようなことを思い出すと、この上なく自分が卑しめられます。
友人への手紙だけではなかった。彼の日記や手記のいたるところに、この種の自分を責めさいなむ激しい言葉が溢れている。こんな調子で自分を責めてばかりいたら、その先はどうなるだろうか。河野信子の結婚を知った武郎は、小樽近郊の赤岩温泉にこもって懊悩し、自己を責めさいなんだ末に自殺するしかないと考えてピストルを購入している。彼が常に死を意識し、ホイットマンとは別の意味で死を賛美していたのは、病的に厳しい自己否定の結果だったと思われるのだ。
しかし、何人かの評家が指摘しているように有島武郎は激しい口調で自己否定しているときが、実は、一番安定していた時だったのである。危険は彼が生命的行動と信じるものに向かってエネルギーを集中するときに起きている。このへんのカラクリは、三島由紀夫の場合と同じなのだ。
三島由紀夫は戦後民主主義と対峙し、その俗物性を痛烈に批判しているときに安定していた。彼は、自身の俗物性を戦後民主主義に投射し、自分を否定する代わりに戦後日本を攻撃したのだった。卑俗な社会、実のところは卑俗な自己を絢爛たる言葉を駆使して攻撃しながら、彼は内面に高貴な貴族的自我を擁立するために苦闘していた。「葉隠」に心酔し、天皇主義者になり、「陽明学」・バタイユを持ち出し、ファッションショウのように思想的衣装を次々に取り変えたのも、何とかして「高貴な自己」を自他に認めさせるためだった。
卑俗な自分に代えて、卑俗ならざる自分を演出してみせる、そんなことを繰り返しているうちに、三島は深刻なニヒリズムから抜け出せなくなった。残された方法は、乾坤一擲の行動に出て生命を異常燃焼させることしかなかった。三島は成算のないクーデターに打って出て、それをスプリングボードにすることで、はじめて自殺に成功する。
有島武郎も、あれほど激しく自己を否定し、見ているものに、このままでは死ぬしかないのではないかと思わせながら、一向に死なずに生きていた。そして、念願の本能的生活なるものを実践する渦中で、彼はあっけなく死んでいる。つまり、三島も武郎も、足下の嫌悪すべき現実に顔を向けているときに安定し、情熱に燃えて飛躍を試みた時に自殺しているのである。自殺願望とともに生きていながら、彼等が実際に自殺するには、情熱を過度燃焼させる異常状況を設定する必要があったというわけだ。
死を選ぶ頃の武郎は、ひどく虚無的になっており、ここにも三島との相似が見られる。三島は思想的な衣装を次々に取り替えているうちにナイーブなものをすり減らしてしまった。武郎も「惜しみなく愛は奪う」という信条を実践し、生きる基軸としての愛の対象をあれこれ切り替えているうちに、真の自分を見失ってしまったのである。
三島が次々に知的衣装を取り替えたのは、彼を満足させる本当の思想を取得できなかったからだし、武郎が頻々と愛の対象を変えたのも、真に愛すべきものを発見できなかったからだった。三島も武郎も、求めていたものは、自我の下層にあったのだが、彼らは自我の表層面で生きていたのである。
有島武郎は、「私の小さな愛の経験」に基づいて「惜しみなく愛は奪う」というエッセーを書いている。彼はこの中で、「愛とは与えるものではなく奪うものだ」という事実を強調し、この主張をふくらませて、「(人間は)絶えず外界を愛で同化することによってのみ成長」してきたと言い、「(個人の内容とは)私と私の祖先とが、愛によって外界から自己の中に連れ込んできた捕虜の大きな群れ」に他ならないと力説する。
彼は、愛する対象を奪い取って来て自分を拡張し増補することができるというのだが、果たしてそんなことが可能だろうか。愛によって、外界が自我内に摂取されるなどということがあり得るだろうか。
例へば私が一羽の小鳥を愛するとする。私はそれに美しい籠と新鮮な草葉とやむ時なき愛撫とを与えるだらう。人はその現象を見て、私の愛の本質は与える事によってのみ成立つと推定しはしないだらうか。然しその推定は根抵的に謬ってゐる。私が小鳥を愛すれば愛するほど、小鳥はより多く私その者である。私にとって小鳥はもう小鳥ではない。小鳥は私だ。私が小鳥を生きるのだ。私は美しい籠と新鮮な草葉とやむ時ない愛撫とを外物に恵み与えた覚えはない。私はそれらを私自身に与えているのだ。私は小鳥とその所有物の凡てを外界から奪い取ったのだ(惜しみなく愛は奪う」第一稿)。
事実は、この反対ではなかろうか。愛が深ければ深いほど、愛する対象が自分とは異なる実質を持ち、絶対他者として自己に対立していることを実感するのではないか。人間は漠然と自分が世界と同化しているように感じる。だが、愛によって個々の事物、個々の人間が自分とは異なる絶対他者性を持つことを痛感すればするほど、同化意識などはどこかに吹き飛び、他者の集合体としてのこの複雑多岐な世界に恐れと尊敬の念を覚えるようになる筈だ。
東洋人は、外界を対象化して見るのを西欧式の分析的思考のせいだとする。ホイットマンも東洋思想の影響を受けて、個人の生命は宇宙的生命の一部であり、自己は全存在と一体になっていると強調する。しかし自他の一体性を感知するのが愛なのではない。理性も参加した個人の全能力によって、世界の他者性を確認し、壮大で尊厳な世界を無条件で受け入れることが愛なのである。
愛によって相手を奪い取るのではなく、愛によって絶対他者である相手を外に措定するのである。そもそも相手の人間性を奪い取るなどということが出来るはずはないのだ。高潔な人格を持つ他者を愛したからといって、その高潔な人格を自らの内部に取り込むことが出来るだろうか。可能なのは、精々、相手の生き方を見て感化されることくらいなのだ。
愛が為しうるのは、他者である相手の全存在を虚心に受け入れ、そのことによって自他一体の甘い幻想の中に沈んでいた古い自分を新しく編成し直すことだ。愛はわれわれの幻想を壊し、自己を日々新しくする。そして世界を見る目を、幼子のように素直なものに立ち還らせてくれるのである。
有島武郎は、愛の人だった。彼があまり長くはなかった生涯に、2683通もの手紙を残していることを見ても、周辺の人々に注いだ彼の温かな心情を知ることが出来る。だが、彼が「愛」だと思ったものは、本当は、一時的な感情移入に過ぎなかったのではないかという疑いが残る。感情移入によって一時的に相手と一体化したことをもって、彼は相手の総てを奪い取ったと錯覚したのではなかろうか。
籠の中の小鳥は、止まり木で休み、愛らしい仕草で首をかしげてみせる。小鳥を深く愛し、注意深く観察している者は、それが飼い主に対する愛情表現でもないし、餌を要求するシグナルでもないことを知っている。だが、多感な武郎は小鳥に自己の感情を移入し、その仕草を人間的に解釈するという誤ちを犯してしまうのだ。武郎は感情移入によって相手と一体化し、その瞬間の相手に理想的な人格を読み取るという過ちを繰り返していたように見える。
親の遺産を受け継いだ彼のところには、さまざまな目論見を持って人が集まってきた。武郎はこうした人々から騙され裏切られ、若年の頃から抱いていた人間不信の念を加速させていったと想像される。
彼は死ぬ前に足助素一に、「人間性と言ったって自分だけのもので、惜しみなく愛は奪うといってみたところで、実際には少しも奪いはしない」と悲痛な告白をしている。
3 大正時代は前期と後期に区分され、前期の特徴は人道主義を基盤にする思想・芸術が盛行したことだった。こうした背景のもとに民本主義の吉野作造や白樺派の若き作家たちが時代の寵児になったのである。有島武郎が漱石に匹敵するほどの人気を得たのも、人道主義に加えて、作品の根底に西欧風の清新なロマン主義を盛り込んだからだった。「宣言」は、武者小路実篤の「友情」よりも一歩早くインテリ青年の三角関係を取り上げている。武郎はこれらの作品によって、自然主義作品には見られなかった知的な男女の恋愛と運命を描いて見せたのである。
有島武郎の周囲には、学生や若い知識人が集まるようになり、彼等の懇請に応じてあちこちの大学で講演する機会も増えた。武郎のもとに集まる学生たちは、自分たちの集まりをホイットマンの詩集にちなんで「草の葉会」と名付けた。このメンバーのなかから、蝋山政道・大佛次郎・谷川徹三・芹沢光治良などの知名人が生まれている。
学生たちよりも人目をひいたのは、武郎ファンの女たちだった。武郎のロマン的な作風や、中年になっても衰えない貴公子風の風貌が女性の心をとらえたのだ。
武郎に接近してきた女性のなかには、大杉栄を刺した神近市子や、後に石川三四郎と同棲する望月百合子も含まれている。神近市子とは散歩の途中に接吻するところまで行ったが、自分の軽率な行動を恥じた武郎が、直ぐに別れの手紙を書き送ったので、神近の方も同意の返書を出し、二人の関係は短期間で終わっている。武郎は自ら別れを切り出しておきながら、神近の最後の手紙を読んで深い孤独感に襲われた。
望月百合子は、石川三四郎宅をしばしば訪れながら、同時に武郎の邸宅を頻繁に訪問していた。百合子はやがて石川三四郎に同行してフランスに渡り、石川の帰国後もパリに残って勉強を続けることになる。武郎は、パリの百合子に宛てて心境を吐露した便りを再々書き送っている。彼は自分と同じアナーキズムを奉じる百合子に、同志に対するような感情を抱いていた。
有島武郎を当代一の人気作家にした時代の空気は、大正後期になるとがらっと変わってしまう。武郎の作品が時代にマッチしたのは大正9年頃までだった。それ以後になるとロシア革命の影響が日本に及んできて、ジャーナリズムの関心は人道主義から階級闘争、アナボル論争などに移り、武郎は新しい時代をいかに生きるべきか苦慮するようになる。
もともと、彼はアナーキストであり、弟の生馬とヨーロッパ巡遊の旅に出たときには、ロンドンに亡命していたクロポトキンを訪ねて、彼から幸徳秋水への手紙を託されたほどだった。帰国してからは、アナーキストのパトロンになり、大杉栄の渡航費用として2000円という大金を用立てている。
だが、父亡き後、有島家を統括する家長になった武郎は、札幌時代のように軽々に動くことは出来なかった。今や、彼は一族に対する彼自身の不満をかくして、有島家の屋台骨を支えて行くしかなかった。
家長になる以前の彼は、日記に有島家や家族に対する不満を縷々書き残している。
──夕食後余の胸中は我が家人の処世の法方につき堪え得られざる不平を感じぬ。──今夜不快の事あり。余と余の家風とは遂に一致すること能わず。
──(妹シマの婚礼は)是亦生が嘗て見ざりし華奢の宴なりき。・・・・余は予言者の如く余の家の近き将来に必ず大破綻あらんことを想像するに難からず。
──余はこの間殆ど農場の事のために悩殺せられぬ。余は殆嘔吐を以て之に対す。
アメリカ留学を控え、父から家事の処理を命じられていた武郎は、渡米の日が来てその仕事から解放された時には、心からホッとしたのだった。彼は出発前に友人の末光績に宛てて次のような手紙を書いている。
生は今生の信仰の許す限り彼等老いたるものの意志に従わんことを勉む。されどもし生此家の主権を握るべき運命に立たば生は大胆に生の所信の如く行かんことを切に切に祈りつつあり。
両親が生きているうちは、自分を押さえているが、家督を相続するようになったら思い切って所信を実行するつもりだと宣言しているのだ。この段階ではまだ社会主義の洗礼を受けていなかったから、彼は聖フランシスのように私財を貧者に分かち与えるつもりでいたのである。
父なき後、武郎が財産放棄を含む家政改革に乗り出そうとしたとき、最大の障害になったのは母だった。激しく感情を揺すぶられると、卒倒して意識を失う癖のあった母は、武郎の祖母に当たる女性が自宅に同居するようになると、真宗信者だった祖母の感化を受けて、表情も穏やかになっていた。しかし、武郎がキリスト教に入信したことを知ったときなどは、自分の家から乱臣賊子を出したように悲憤慷慨して、息子を激しく責めたものだった。
武郎は家長として母に気を遣うだけでなく、弟妹のひきおこしたトラブルの処理にも当たらねばならなかった。今回、志賀直哉の「蝕まれた友情」と里見弴の「安城家の兄弟」を読んでみた。それによると、有島生馬も里見弴もさまざまなトラブルを引き起こす問題児だったのである。
志賀直哉は有島生馬より一歳年少に過ぎなかったが、文学の面でも美術の面でも自分よりずっと先を行っている生馬に兄事していた。生馬に兄事するだけでなく、同性愛に近い感情で生馬を愛し、彼の名前を書いた紙片を胴着の中にしまい込んでいたほどだった。
志賀は、学生時代のこんな話も書いている。生馬が落第するのではないかと心配した志賀直哉は、生馬のために懸命に祈ったというのだ。その頃の志賀は芝公園の弁財天を信仰していたから、弁財天に願掛けした。
彼は池の中にある祠に向かって祈るよりも、便所の壁にある小さな傷を弁財天と見立てて、これに祈ることの方が多かった。1センチに満たない小さな壁の傷は、人の形をしているように見え、祠に祈るよりも便所の中で祈った方が精神統一が出来たと志賀は書いている。そのお陰か生馬は落第せずに済んだ。
やがて有島生馬は絵の修行のためヨーロッパに旅立つことになる。その直前に彼は志賀と黒木という友人に自分には結婚を約束した女がいると打ち明け、自分の留守中、その女の面倒を見てくれないかと依頼したのだった。
相手の女というのは、今は生馬の屋敷で女中をしているけれども、もともとは電話交換手をしていたのを生馬が見そめ、まず絵のモデルになって貰ったじょせいだった。生馬は、その後に彼女を女中として自宅に迎え入れていたのである。
「友達の外遊中その恋人を託されるということは当時の僕達にとって決して悪い気のすることではなかった」(「蝕まれた友情」)から、志賀と黒木は生馬の頼みを承知した。二人は、女に教養をつけさせるために女中を止めさせて麹町の成女学校に入学させた。二人は、それぞれ小遣い銭を削って、女学校の授業料を出してやった。
滞欧7年で、生馬は帰国してくる。生馬を迎えに駅に出かけた志賀は、生馬の妙に「悠然たる態度」を眼にして百年の恋も冷めるような思いをするのだ。一等車から降り立った生馬は、プラットフォームで待っている出迎えの人々に眼で会釈しただけで、先に下車した樺山海軍大将を追って別れの挨拶し、それから悠然と引き返してきたのである。その後も生馬は、「安っぽい容体ぶった様子」を続け、志賀をガッカリさせる。
生馬が時に思い上がった態度を示すことは、兄の武郎も苦々しく思っていた。札幌農学校に在学していた頃、帰省して実家に戻った武郎は、自分が以前に学んでいた学習院の生徒たちの所作を眺め、嫌悪のあまり吐き気を感じた。彼等は揃って、優柔不断の臆病者の癖に、いやに傲慢なのである。
学習院学生ヲ見ルニ多クハ優柔不断ニシテ軽薄極レルモノ多ク……人ヲシテ嘔吐ヲ催サシムル事アリ。況ンヤ壬生馬(生馬)ノ如ク倨傲他人ヲ無二スルモノニ於テヲヤ。……浮々泛々人ノ甘言ニ乗リテ事物ノ分別ヲ知ラズ殆ド流行書生ノ風ニ倣フ。
武郎が家族に対してこんなに激しい嫌悪を示した記述は、外にはない。
だが、生馬には特有の魅力があり、滞米中の武郎は弟が絵画修行のために渡欧すると聞いて、実家が彼への送金を増やせるようにと、アルバイトをして自分の生活費を切りつめている。生馬の弟の里見弴は、兄が渡欧するとき中学生だったが、横浜まで見送りに行き、船が埠頭を離れるやいなや声を上げて泣き出し、回りのものがいくら慰めても、どうしても泣きやまなかった。
志賀直哉を更に怒らせたのは、帰国した生馬が7年間待ち続けた婚約者を放置して別の良家の娘を追い回し始めたからだった。生馬は心変わりしたことについて、志賀と黒木に何の説明もしなかった。ほどなく生馬は女との婚約を解消する。だが、生馬はもちろん女の方からも、この件について何の報告もなかった。
志賀も女中と結婚したいと言い出して父親と衝突したことがある。この時には、武郎が乗り出して仲介にあたってくれたが、生馬の婚約者に対しても武郎は陰ながら援助していたのではないかと、志賀は推測している。
生馬は昔のことは口をぬぐって別の女性と結婚した。が、その女性が結婚後に家を飛び出して実家に帰ってしまうという事件が起き、この時にも武郎が乗り出して解決にあたっている。
里見弴も女性問題では、親族一同の手を焼かせていた。
彼は養子になって別姓を名乗っていたが、有島家の一員同様の生活を続けていた。若い頃から色町に出入りしていた里見は、一族の反対を押し切って芸者を妻に迎え、その妻との間に何人もの子供をもうけながら、放蕩を止めようとしなかった。その費用を調達するために彼は養家先の財産をすっかり費消し、有島家からも金を引き出していた。こうした親族をまとめながら、武郎は階級闘争で騒然としはじめた大正後期を迎えたのである。これまで有島武郎の面会日にやってくるのは、夏目漱石の場合がそうだったように東京帝大の学生が中心だった。ところが、大正後期になると、正体不明のアナーキストや女性読者が加わり、面会日の有島邸は門前市を為すありさまになった。面会日だということを知らずに有島邸を訪れた里見弴は、玄関が男女の履き物で一杯になっているのを見て、舌打ちをして引き上げている。
里見弴は、心中行のために兄が行方不明になったとき、兄弟たちと武郎の貯金通帳を調べた。そして10円、20円、50円というような金額が頻繁に引き出されているのを見て、面会日にやってきた連中にせびられたからだと直感し、再び舌打ちををした。放蕩者の里見弴からすると、広大な農場をただで小作人にくれてやったり、アナーキストや社会主義者に寄付と称して金をばらまくほど馬鹿馬鹿しい金の使い方はないのであった。
しかし武郎は真剣だった。
大正11年3月、彼は母に反対されることを予想して、まず、弟妹を集めて北海道の農地を解放する決意を告げた。弟妹達が賛成してくれたので、それをバックに母親の説得に取りかかったが、母は泣き出すばかりでどうしても承知してくれない。母は、武郎にもう一度、弟妹を集めて相談し直すように命じた。彼女は、再度集まった子供たちが農場の開放に賛成していることを知ると、ようやく我を折って渋々同意した。北海道の農場を手放した彼が、次に実行したのは自邸を引き払ってささやかな借家に移ることだった。面会日に素性も知れない「主義者」や失業者たちが集まってくるのも、麹町の一等地に広大な屋敷を構えているからではないか。彼は麹町の屋敷を売って、その代金で老母の新居と生活費に充て、残りは6人の弟妹に分与するという計画をたてた。
だが、計画は難航し、母のために赤坂に新居を建て、そこに母が引っ越すところまでこぎ着けたが、屋敷の売却には母があくまで反対する。結局、麹町の邸宅は無人のまま放置されることになった。そして、この状態のまま武郎は、波多野秋子と心中してしまうのである。
この頃、有島武郎は作家として深刻なスランプに陥っていた。
彼は、親譲りの膨大な遺産をバックに安穏な生活を送ることをやめれば、創作活動にも新生面を開くことが出来るかも知れないと期待をかけていた。このスランプの期間中に発表されたのが、論壇に旋風を巻き起こした「宣言一つ」だった。彼はそれまでホイットマンの影響下に、全人類は一体であり、男も女も、貧乏人も金持ちも、有徳の人間も犯罪者も、生きとし生けるものはすべて、向日性の生命を持つ点で同種同等だと考えていた。
ところが、「宣言一つ」で武郎は、人類がいくつもの階級に分裂し、未来のあるグループと未来なきグループに分かれていると言いだしたのだ。第4階級の労働者は、未来を創造する立場にあるが、第3階級に属するインテリは何ら未来に貢献し得ない。今や労働者階級は内部からすぐれたリーダーを続々と生み出すようになっている。だから、従来、労働運動を指導する立場にあるとされてきた知識階級は、完全に不要な存在になったと武郎は断定する。
こうした現状認識を背景に、有島武郎は今後自分がなすべきことは、労働階級のために何かをすることではなく、自壊する運命にある第3階級の、その崩壊を促進することにあると結論づける。階級闘争には不要の人間だと自認する武郎の告白は、実質的に革命運動への縁切り宣言にほかならなかった。武郎の財産放棄が一種の経済的自殺を意味したとすれば、「宣言一つ」は彼の思想的自殺を意味していたのである。
4 妻の安子と死別してから、武郎は女性と無縁でいたわけではなかった。
彼は「或る女」執筆のため円覚寺の別院にこもっていた頃、休み茶屋の女と体の関係を持っていたし、円覚寺近傍の寿司屋の娘とも愛人関係にあり、この関係はその後もずっと続いたといわれる。他に彼は帝劇の女優唐沢秀子と恋愛中であり、石川県選出の代議士夫人桜井鈴子からも、しつっこく追い回されていた。そんな彼の前に現れた波多野秋子は、「婦人公論」誌の記者だった。
彼女は某実業家が新橋の芸者に生ませた私生児で、青山学院に学びながら波多野春房の英語塾にも通っていた。やがて彼女は波多野と愛し合って結婚し、高島米峰の紹介で中央公論社に勤務することになった。同じ頃、波多野も知人の斡旋で火災保険協会の書記長になっている。波多野秋子
不思議なことに、波多野秋子の写真は一枚しか残っていないようで、どの本を開いても同じ写真しか掲載されていない。その写真を見るかぎり、彼女はそれほど美しかったとは思えない。武郎の友人達は、彼にふさわしい女はほかにもっといたと証言する。が、室生犀星は秋子には、「眼のひかりが虹のように走る」感じがあって魅力的だったと言っている。生前の秋子に会っている里見弴や足助素一は、彼女にあまりいい印象を持っていない。彼女からコケティッシュな印象を受けていたからだ。
大正11年の冬頃から武郎に対する秋子の攻勢が始まった。が、武郎は彼女に何となく恐ろしい感じを抱き、深入りすることを避けている。翌年の春になると、秋子はますます執拗に武郎に迫るようになり、そうされると何時でも抵抗力を失ってしまう武郎は、遂に秋子と行くところまで行ってしまう。だが、直ぐに武郎は反省し、逢い引きの約束を取り消す手紙を書いている。
(逢い引きの約束を破る理由は)愛人としてあなたとおつき合ひする事を私は断念する決心をしたからです。あなたにお会ひするとその決心がぐらつくのを恐れますから、今日は行かなかったのです。私は手紙でなりお目にかかってなり、(秋子の夫の)波多野さんに今までの事をお話してお詫びがしたいのです。
・・・・あなたも波多野さんの前に凡ての事実を告白なさるべきだと思ひます。而してあなたと私とは別れませう。短い間ではあったけれども驚く程豊に与へて下さったあなたの真情は死ぬまで私の宝です。涙なしには私はそれを考へることが出来ません。
・・・・あなたが自分ではとても死ねないと仰有る言葉なぞも私にはよく解ります。而してあなたのそのやさしい心をなつかしく思ひます。死んではいけません。
この手紙から、二つの事実が明らかになる。
一つは、秋子が自分の夫を高潔な人格者であり、妻である自分を純粋な気持ちで愛してくれていると誇らしげに武郎に説明していたことであり、もう一つは秋子が武郎を道連れにして一緒に死ぬ気になっていたことだ。武郎には、女と死ぬ気はなかったし、秋子の夫がそれほど立派な人物なら、彼を悲しませるようなことをすべきでないと考え、秋子に別れることを提案したのである。馬鹿正直な武郎は、二人揃って秋子の夫の前に出て謝罪すべきだと考えていた。秋子も一旦は武郎と別れることを承知した。が、関係はすぐに再燃し、二ヶ月後の6月4日に二人は船橋の旅館で泊まってしまう。この時にも秋子は死ぬことを迫り、武郎は逃げ切れなくなって、10月になったら実行すると約束している。
秋子は何はともあれ心中することを武郎に承知させ、満足して翌日帰宅した。秋子が武郎に打ち明けたところによると、彼女の帰宅を待ち構えていた夫は夜通し彼女を責め立て、しまいには催眠術まで使ってすべてを白状させたという。だが、「催眠術まで使って」というところに釈然としないものが残る。彼女は武郎の気持ちを揺るがぬものにするためには、むしろ二人の関係を夫にばらした方がいいと考えた節がある。
翌6日、武郎は秋子と共に波多野の事務所に呼び出された。
実際に会ってみると、波多野春房というのは、とんでもない男だった。この日、波多野と武郎が取り交わしたやりとりは、足助素一の「淋しい事実」のなかに克明に描かれている。武郎は死ぬ前に、秋子との関係、秋子の夫との関係を総て足助に打ち明けていたのである。足助の「淋しい事実」の内容は、里見弴の「安城家の兄弟」にほぼそのまま引用されている。以下は、「安城家の兄弟」からの抄録である。
(波多野春房は事務所に現れた武郎に)「お前は有名な吝嗇ン坊(しわんぼう)ださうだから芸者なんぞに係わり合ふことはし得ないで、金の要らない人妻ばかり狙うんだらう。敏子(秋子)は、自活の出来る職業婦人だから、その点、益々好都合だと思って誘惑したんだらう」
と、頭から罵言を加へて置いて、「それほどお前の気に入った敏子なら、慰斗をつけて進上しないものでもないが、併し俺は商人だ。商売人といふ者は、品物を無償で提供しやアしない、敏子は、既に十一年も妻として扶養して来たのだし.それ以前の三四年も俺の手元に引き取って教育してゐたのだから.それ相当の代金を要求するつもりだ。俺ぁこんな恥曝しをしては、もう会社にも勤めてゐられない。これ、この通り辞表も書いで来てゐるんだ」と、言って、和洋二通の辞表を出して見せた。そこには、「家庭内に言うに忍びざる事件起り」といふやうな文言もあった。
なほ続けて言ふには.「敏子は、今すぐにでも離籍してやるが、併し、それでい~気ンなって、おいそれとお前たちが夫婦になるやうなまねは断然許さん。少くも一年か一年半たってからでなくっちア、第一世間がうるさくって困る。それから、金は、一度だけ支払えばそれですんだと思うな。俺は、吝嗇ン坊のお前を、一生金で苦しめてやるつもりなんだから。それは今から覚悟しておけ!」
この調子だった。文吉(武郎)は、かねて敏子から、どれほど良人に愛されてゐるか!といふやうな話ばかり聞かされてゐたので、この会見にも、「お前たちはとんでもないことをしでかしてくれたもんだ。敏子は、俺には一日もなくてならないもんだったのに!」といった調子を予期し、それには一言の返す言葉もないと、恐縮しきってゐたのだが、案に相違した罵詈讒謗に、却ってすっかり気持を楽にして了った。で、まづ自分には、命がけで愛してゐる女を、金に換算し、取引するやうな、そんな侮辱は自他のために所詮忍び得るところでない、と拒絶すると、
「よし! ぢア、ニれからすぐ警視庁へ同行しろ!」
と、息巻いたが、文吉は、もとより望むところと、即座に、「よろしい、行かう!」
と座を立った。──これは、明かに萩原(波多野)の予算違いで、もしさう言ったなら、ひとたまりもなく文吉が震え上がり、床に額を摺りつけて、哀訴嘆願するものとばかり思いこんでゐたらしい。で、ややたじろぎながらも、
「お前は、警視庁へ行ったら、敏子を裏切って、美人局だなんて言び張るつむりなんだらう!」
と、一喝しておいて、更に、「お前は、今のうちこそ、そん空威張りをしてゐるが、実際監獄にはいってみろ!お前には三人の子供や、また老(としと)った親もあるって話だが、さういふ人たちのことは、何とも思わないのか!あとなんぞ、どうなって構わないっていふのか!……俺にしたって、十一年も一緒に暮して来た、無邪気な、まるで鳩みたいな敏子を監獄へなんぞやりたかアない。いくらお前が吝嗇ン坊だって、まだしもそれア、金で始末をつけた方が楽だらうぜ!」
そこで文吉は、
「・・・・・いづれにせよ、僕は愛する女を金に換算する要求には、断じて應じられないんだから、一時も早く警視庁に突き出して貰はう!」
、
これには、萩原も手こずった様子で、おどしたりすかしたりして、文吉の決心を翻さすことに努め、最後に、「どうしてもお前が支払いを拒むんなら、一人一人お前の兄弟たちを呼びつけて、お前の業晒しをしても、きっと金は取ってみせるからさう思え!」
と罵り・・・・・食堂へおりて行ってしまった。(「安城家の兄弟」里見弴)
波多野と別れた武郎は、その足で当時入院中だった足助を訪ね、波多野との会見の一部始終を打ち明けている。武郎が帰ってから足助は、あれこれ考えた末に、さしあたり波多野に金を払って相手の気持ちを落ち着かせた方がいいのではないかと思い、夜になってから武郎の竹馬の友で、彼とも親しかった原久米太郎に直ぐ上京してくるように電報を打った。
足助は波多野が弱腰になったと聞いて、原を間に立てて波多野と掛け合えば、先方の要求する金額を値切ることもできるし、今後、金の要求はしないという念書を書かせることも可能だと思ったのだ。世慣れた原に一任すれば、事を穏便に納めることができると判断したのである。
翌日、足助は病院を抜け出して武郎の住まいに出かけた。武郎のところには、波多野秋子も来ていた。足助が原久米太郎に交渉を任せるように献策すると、武郎は首を振って、相変わらず、愛する女を金に換算することは出来ないと言い張るのだ。
そればかりか、武郎はまるで夢見るような口調で、こんなことを言い出した。
「…情死者の心理に、かういふ世界があることを解って呉れ。外界の圧迫に余儀なくされて、死を急ぐのは普通の場合だが、はじめから、ちやんと計画され、愛が飽満された時に死ぬといふ境地を。……死を享楽するといふ境地を。僕等二人は今、次第に、この心境に進みつつあるのだ。」
「‥………」
「君が僕を惜しんで呉れるのは能く分ってゐるが。・・・・・ああ、何といふほほゑましさだ。ねえ、秋子さん、こんな寂光土がこの地上にあるとは今まで思ひもそめなかったね」(「淋しい事実」足助素一)
波多野は、前日、武郎が帰って秋子と二人だけになったなったときに、「作家というのは姦通罪で入獄でもすれば却って人気が出るそうだから、もう、お前たちを訴えることを止めることにした。有島が金さえ出せば今度の件は、内聞にしておいてやる」と告げた。
足助の計画通りに事を運ぶには、弱気になっている波多野に強硬姿勢の武郎をぶっつけて活路を見いだす必要があった。足助が武郎と別れた時には、この線で突っ張ってくれそうな気配があったのである。武郎は姦通罪で入獄することを、むしろ望んでいるように見えたのだ。
武郎は私財を投げ出すことで経済的自殺を試み、「宣言一つ」を発表することで思想的自殺を試みるという風に、自分を徐々に破滅に向かって追いつめていた。その彼が姦通罪で二年間入獄すれば、今度は社会的な自殺を強いられることになる。彼は本当に自殺することを回避するために、擬似的な死を次々に重ねることを選んでいたのである。そして、今度もし監獄に入ることになれば、情死を迫る秋子の矛先をかわすことも出来るのだ。
武郎は森本厚吉と心中を企てるほど、深い親交を結んでいたけれども、当初は森本を好んでいなかった。秋子についても同じで、武郎は昨夜、病院で足助に、「秋子と長く同棲していたら、きっと倦怠を感じるようになると思う。彼女がそういう女だということは、今からもう分かっている」と語っていた。
だが、武郎はこの日、波多野の伝言を携えて訪ねてきた秋子と膝をつき合わせて話しているうちに、彼女に押し切られて死ぬことを約束してしまったのである。そもそも、姦通したといって自首して出ることなど、ありえない話なのである。被害者である夫が訴えて出て、はじめて姦通罪は成立する。武郎が、本気で自首を実行しようとしたら物笑いの種になるだけなのだ。
秋子に押し切られ、死を決意すると、武郎の胸に予想もしなかったようなよろこびがわいてきた。これで本来収まるべきところに収まったという気がしてきて、死を享楽するというような気持ちになったのだ。足助はこういう武郎を見て絶望した。そこで彼を説得することをあきらめ、秋子の説得に取りかかった。
「秋子さん、有島には三人の子供もいるし、老母もいるんです。武郎を殺さないで下さい」
すると、秋子は初めて気がついたというように武郎の方を向いて、「そうね、あなたには係累があるんでしたっけねえ」と空とぼけて話しかけ、「二人で解っていればいいのね」と足助には理解不能な言葉で武郎に念押しをする。秋子は、足助に取り合う気配を微塵も見せなかった。足助は、かっとなって、「この女の冷たい目を見ろ。残忍そのものじゃないか。君はこんな女と情死するのか」と武郎をなじったが、武郎は口ごもって、「──どうもそれは、仕方のないことだ」とつぶやくばかりだった。足助は何の成果も得られず、引き上げるしかなかった。
武郎は、その翌日から行方不明になる。新橋駅のレストランでしたためた「二、三日旅に出る」という葉書が自宅に届いたきりで、消息が全く知れなくなるのだ。そして約一ヶ月後に軽井沢の別荘で縊死している遺体が発見される。その場に武郎自筆の遺書がなければ、誰のものか分からないほど二人の遺体は腐乱していた。
死を目前にして、したためた武郎の遺書には、次の文字が見える。
(足助素一宛)「山荘の夜は一時を過ぎた。雨がひどく降っている。私達は長い路を歩いたので濡れそぼちながら最後のいとなみをしている」(森本厚吉宛)「私達ハ愛の絶頂に於ける死を迎える。六月九日午前2時」
5 波多野秋子は、なぜあれほど有島武郎との心中に執心したのだろうか。太宰治と死んだ女性も、また、不思議なほど心中することに執着していた。
彼女等は天下に名だたる一流作家を独占して、自分一人のもにしたことを世に誇示したかったのではなかろうか。秋子にとって情死は、女としての勝利宣言を意味するものだったから、武郎に3人の子と老母がいることはむしろ彼女の勝利を輝かす勲章になるのである。この世に未練を残し、後ろ髪を引かれる思いでいる武郎を、彼女が強引にあの世にさらっていったとすれば、彼女の女としての魅力を一層強く証明することになるからだ。
それにしても、有島武郎は何故秋子と心中したのか。ここに至るまでに、彼は再三死を迫る秋子の訴えを退けてきたではないか。「小さき者へ」を読んで感動していた読者は、武郎が三人の愛児を残して死んだことに驚かないではいられない。武郎は、この作品で幼くして母を失った子供達のために石にかじりついても生き延びると誓っていたと思われるからだ。
もともと秋子を高く買っていなかった武郎は、波多野の要求する金を払い、それを機に女と別れることも出来たはずなのだ。そうすればすべてが円満に収まったのである。にもかかわらず、武郎はこの情事が表沙汰になったことを利用するかのように、死に向かって飛び込んで行った。
有島武郎の不可解な行動を理解するには、ナルシシズムとの関連を検討する必要があるかも知れない。この観点に立って、有島武郎の生と死を眺めたら、どうなるだろうか。
彼の私小説風の作品──「小さき者へ」「平凡人の手紙」「An Incident」「死と其前後」を読んでいると、奇妙な尻こそばゆさを感じる。読んでいて、こちらが何となく恥ずかしくなってくるのである。武郎と三人の子供
これらの作品からは、死んだ妻や三人の子供達に対する武郎の愛情がストレートに伝わってくる。だが、最初から最後まで純度100パーセントの愛情で満たされた作品を読まされると、読者は何かしら困惑を感じる。「An Incident」には、父親の嗜虐性のようなものや、夫婦間の感情的な齟齬などが描かれているが、読み終わって感じるのは、やはり純度の高い家族愛なのだ。
これらの作品を書くときに、武郎は家族に対する自らの愛情を疑っていない。彼は別に自分の愛情を誇ろうとしているのではない。けれども、彼は、おのれの感情の純粋無雑なことをいささかも疑っていないのである。これが読者をして面はゆい思いをさせるのだ。
これは足助素一の「悲しい事実」を読んだときに感じる面はゆさに似ている。武郎は自宅に駆けつけてきた足助に、
「君、どうか秋子を許してやってくれ。君から僕を奪った秋子を・・・・」
といって、自分の「裏切り」を詫びるのだが、足助の前でぬけぬけとこんなことを口にする武郎の神経は、やはり尋常とはいえない。
武郎が家族に対する自らの感情を疑わないこと、そして周辺の者の自分に対する愛を疑わないことは、表裏の関係で一体になっている。上流の家庭に生まれ、大事に育てられてきた人間は、自身の善意と自分に対する周辺の人間の愛情を信じて疑わない。その結果、彼等は成長してから「鼻下長族」と揶揄されるようになる。有島武郎が「鼻下長族」の一人だったことに疑いを入れないのである。
武郎は、幼時に父母から厳しくしつけられ、横浜の米人家庭でもキリスト教道徳を仕込まれた。外見上彼は周囲の大人達から過酷な扱いを受けていたように見えるけれども、彼を取り囲む大人達に悪意はなく、皆、武郎を一人前の人間にしようと願っていたのである。だから、スパルタ式の訓育を受けながら、武郎は彼等を恨むことがなかった。
自分の善意と周囲からの愛を信じていた彼を、直ちにナルシストと呼ぶことは出来ないだろう。「わが肉体は美の殿堂」と豪語した三島由紀夫は、金箔付きのナルシストだった。けれども、武郎のように自分の善意を信じていたというだけでは、自己愛主義者とは言えない。自分以外の他者を蔑視して、自分だけに排他的な愛を向けるときにナルシストになる。有島武郎は、他者を排除し自分だけを取り出して、これに一途に執着するような人間ではなかった。
彼は自分を肯定すると同じ気持ちで、他者を肯定しようとし、自分を愛するように他者を愛そうとした。そうした努力の末に、自他の融合を感じることが出来たから、「愛は惜しみなく奪う」というテーゼも生まれてきたのだ。武郎は森本厚吉と抱き合って誓いを交わし、「悲しい事実」の足助素一とも、秋子の見ている前で抱き合って、号泣している。こういうときに、彼は相手の人間性が自己の内面に流れ込んだように感じ、相手の内面を奪い取ったと感じたのである。
しかし彼は、かなり早い時期から周辺の人々の他者性にも気づいていた。父母や弟妹の中にも、恋人の中にも、友人の中にも、自分とは融合できない別人格のあることを感じ取っていたのだ。彼の精神は、自他の善意と愛を信じているときには安定し、人々の他者性を意識したときに不安定になった。もっとハッキリ言えば、彼はナルシシズムに包まれていたときに、安定し、それが醒めたときに不安定になったのである。
彼が自分を否定しているときに安定していたという奇妙な現象も、これで分かるだろう。彼は自分の善意に絶対的な信頼感を抱いているときにのみ、果敢に自己の欠点に切り込み、自らを厳しく断罪できたのである。自信のある人間は、平気で自分の欠点を認めるものだ。うちに揺るがぬ自信を持っていたから、彼は自己をあんなにも厳しく否定できたのである。
しかし周囲の人間が信じられなくなり、ナルシシズムが薄れてくると彼は動揺しはじめる。河野信子や妻への愛情は反転し、面会日にやってくる思想上の同志達とは縁を切りたくなる。
死ぬ前の有島武郎は、「惜しみなく愛は奪うといってみたところで、実際には少しも奪いはしない」と語り、実質的にこれまでの楽観的な人生観を放棄している。自己を囲繞する人間たちの絶対他者性に突き当たり、自他融合の自信が揺らぎ出すと、彼は深刻なスランプに陥り、作品が書けなくなった。彼の創作意欲は、自分を全肯定しているときにのみ、活発に活動するのである。
だが、波多野秋子に強いられて情死を決意した瞬間に、自他融合の感覚がよみがえり、つまりナルシシズムの感覚がよみがえり、彼は寂光土にあるような安心を感じたのだった。彼の胸からは「小さき者へ」に記したような子供達への哀憐の情はすっぽり抜け失せ、「死を享楽する」気持ちが優位を占めた。
こうして夏目漱石の再来と言われた作家は、女の伊達巻きを首に巻いてナルシストとして死についた。
有島武郎