中学時代に一番心惹かれていた作家は芥川龍之介だったが、その割に彼の作品を読んでいなかった。というのは、家にある彼の本は戦前の改造社版「現代日本文学全集」中の芥川龍之介集一冊だけだったし、学校の図書室にある青い布表紙の芥川龍之介全集も、その大半が紛失していて、書架にはほんの僅かしか残っていなかったからだ。
その代わり、利用可能な芥川の本は全部読んだ。本当に、隅々まで読んだのである。図書室に残っていた芥川全集の書簡集も、その全部を読み通した。
書簡集を読み進んでいくうちに、身体の不調を友人に訴える手紙が増え、そのなかに「屁をしたら、糞が出た」という一節があった。痛ましいと思った。彼が自殺を選んだのには、極点に達した体調不良という理由もあるに違いないと思った。
あんなに芥川を愛していたのに、旧制中学校を卒業するともう彼の本は、全く読まなくなった。戦後になって、筑摩書房版「芥川龍之介全集」を購入したにもかかわらず、それに手を付けることもなくて過ぎていたのである。
それでも、マスコミに散見する芥川に関する記事は読んでいた。岡本かの子の「鶴は病みき」には、彼女が電車の中で芥川と乗り合わせた折りのことが書いてあった。この時、岡本かの子は幼い息子(岡本太郎のことだろう)と一緒だったのだが、息子は芥川を見て「あ、お化けだ」と口走ったという。自殺直前の芥川は、それほど気味悪く病み衰えていたのである。
中野重治は、同じ頃、芥川に呼ばれて彼の家を訪問している。
その訪問記によると、芥川はほとんど入浴していないらしく、彼の長い指先が垢でつるつる光っていた。この一節も、死を間近に控えた芥川の実像を、生々しく伝えていた。
やがて私は、晩年の芥川の内面を如実に示すような実写映画を見ることになった。戦前に、ある出版社が16ミリフィルムで作家を撮影したことがあり、そのうちの一つに生前の芥川を実写したものがあって、それがテレビで放映されたのだ。
そのフィルムは二つの場面から構成されていた。
一つは、彼が息子と二人でカメラに面して座っている場面だった。並んで座っていた息子が、いかにも悪戯っ子らしく隣の父親の麦わら帽子を引っ張ると、芥川はニコリともしないで帽子をかぶり直す。息子が面白がって、また、帽子の縁を引っ張って阿弥陀かぶりにすると、芥川は再び傾いた帽子をきちんと元に戻すのである。
その間、彼はギロリとした目をカメラの方に向けたきりで、一度も息子の方を見なかった。その表情が見るからに異様なのである。ギラギラ光る目が正体不明の感情を浮かべて、カメラを凝視してじっと動かないでいるのだ。
もう一つの場面は、もっと異様だった。
芥川は庭の真ん中に生えている木のそばに立っていた。その芥川をカメラはかなり後景に退いて撮している。芥川が棒のように突っ立ったまま動かないので、最初は静止写真のように見えた。突然、彼が動いたと思ったら、芥川はするすると木に登って高さ3メートルほどの枝の上に立ってカメラの方を見つめたのだ。木の上でも、彼は直立不動の棒のような姿勢を崩さなかった。その所作は、まるで機械仕掛けのロボットのようだった。
ありようは、芥川がはじめて16ミリカメラの前に立って、緊張しすぎただけかもしれない。しかし、芥川の表情や所作の示しているものは、まぎれもなく荒廃した内面だった。芥川龍之介の何者であるか知らない外国人がこれをみたら、精神病者を撮した記録映画だと思うに違いない。
私は、テレビでこの実写フィルムを見た後で、芥川をここまで追いつめたのは何なのか知りたくなった。さらに自分が中学を卒業してから、彼の作品を全く読まなくなった理由をハッキリさせたくもあった。
だが、そのためには、彼の全集を読まなくてはならない。
芥川龍之介全集を読まなければならないというという義務のようなものを感じながら、私はぐずぐず日を過ごしてきたが、それを実行させたのは大岡昇平全集を読んでいて、芥川が日本の読書家の敬愛する作家の三番目になっていることを知ったからだった。大岡は、雑誌「群像」が「尊敬する文学者」に関する読者アンケートを募集したら、芥川が漱石・鴎外についで第三位になったことを紹介していたのである。
私は、芥川龍之介が、まだ、それほど高い評価を受けているとは知らなかったのだ。だとしたら、こっちもそろそろ自分に課していた「宿題」に取りかからなければならないなと、そんな気持ちになったのである。
芥川龍之介は「人生は地獄より地獄的である」というようなことを口にして、しきりに生きることの難(かた)さや娑婆苦について語っている。しかし35歳で死んだ彼の人生が、それほど苦痛に充ちたものだったとは思えないのだ。一体、彼に娑婆苦を感じさせたものとは何だったのだろうか。まず彼の生育環境から検討してみよう。
芥川龍之介は、生誕十ヶ月後に母が発狂したため、母の実家である芥川家に預けられた。
 実母に抱かれた龍之介
実母に抱かれた龍之介龍之介の実父新原敏三は牛乳の製造販売で成功したが、喧嘩早く気性の荒い男だった。龍之介の生母のフクは「御奥坊主」の家系に生まれ、夫とは反対に極端に小心で内気な女だったという。母の一族には、ほかに精神異常者は出ていないから、フク発狂の遠因は粗暴な夫との関係にあったかもしれない。
生家の新原家と母の実家芥川家は、まるでシャム兄弟のように密接に結びついていた。芥川家の当主芥川道章には三人の妹があったが、この三人がそろって新原家と深い関係を持っているのである。
三人姉妹のうちの次女フクは、新原家の当主新原敏三と結婚して芥川龍之介を含む一男二女を生んでいるし、フクが発狂したとき、その妹である三女のフユは新原家に住み込んで新原敏三を助け、結局、姉のあとを継ぐ形で敏三の後妻になっている。
三人姉妹の長女フキはどうしたわけか、未婚のまま兄の家に留まっていた。そのため乳飲み子の龍之介の面倒は、手の空いている彼女が担当することになった。彼女は毎晩龍之介を抱いて寝て、牛乳で彼を育て上げたのだった。かくて芥川家の三人娘は、全員が何らかの形で新原家と深い因縁を持つことになったのである。
 左が長女フキ 右が三女フユ
左が長女フキ 右が三女フユ芥川家が新原家のために一方的に奉仕したのではない。新原の方でも、芥川家が本所の旧宅を引き払って田端に移る前に、自家の持ち家を住まいとして提供している。
龍之介は芥川家の養子になってからも、新原家に頻繁に出入りし、実父から相撲の勝負を挑まれたりしていた。龍之介の初恋の相手は、新原家で働いていた女中の吉村千代だったし、後年、実姉久子の夫が問題を起こして自殺したときなど、その後始末に奔走したのは龍之介だった。実父が事業に失敗して亡くなった後、龍之介は新原家からも頼られる身になり、成り行き上、芥川・新原両家の家長の役割を負わされることになるのである。
龍之介が芥川・新原両家のいずれかを愛していたかといえば、養家の方だった。
養家の当主芥川道章は、東京府土木課長の職にあった。取り立てて豊かとは言えなかったけれども、本所小泉町の界隈では恵まれた一家だった。龍之介は、18年間を過ごした本所について、「江戸二百年の文明に疲れた落伍者が、比較的多く住んでいた町である」と述べている。
貧しい庶民の家が建て込む下町にあって、門構えの家を備えた芥川家は別天地といってよかった。この孤島のような家の中で、一家はあまり外出することもなくひっそりと暮らしていた。養母と伯母の楽しみは、日の暮れになると代わる代わる門迄行って、その脇に取り付けた小さな郵便受けの口から往来の人通りを眺めることだった。
龍之介も外出するときには、子守女に背負われるか、女中に手を引かれるかしていた。こうして、危険な外界から隔離されて育った龍之介が、猥雑な「下流階級」に対して嫌悪ではなく一種のあこがれを感じるようになるのもうなずける。彼はこの貧民に対する自分の感情について「病的なあこがれ」とまで言っている。「羅生門」をはじめ、彼の作品には多くの下層民が出てくるが、これは幼少期の「病的なあこがれ」の反映だったのである(祖母から外出を禁じられた少年三島由紀夫も、糞尿汲み取り人の若者に熱い憧憬の情を寄せている)。
養父母には子供がなかったから、龍之介は養父母と伯母という大人のなかのただ一人の子供として大事に育てられた。文学好きの養父母・伯母は自宅に江戸時代の草双紙からはじまって、怪談本やら何やらたくさんの読み本を揃えていた。外界から隔離されて育った病弱の龍之介が、早くから本の世界に親しみ、やがて作家を志望するようになったとしても不思議ではない。彼は「文学好きの家庭から」と題する随筆に次のように書いている。
文学をやる事は、誰も全然反対しませんでした。
父母をはじめ伯母も可也文学好きだからです。その
代り実業家になるとか、工学士になるとか云つたら
反って反対されたかも知れません。
芥川龍之介は、こうした家庭に安らぎを感じていた。学生時代に芥川と親しかった恒藤恭は、夏休みを前にして龍之介と次のような会話を交わしている。
『君、どこかへ行く?』と私はたづねた。
『東北の方へ旅行して見たいと思ふけれど、夏は暑くてね。
僕は暑さには辟易する。それに少しでも家に余計ゐ
たいよ』と彼は答へた。『なぜ?』と重ねて問ふと、『なぜって、僕は少しでも
父や母と一緒に居たいんだ。父や母も最早年をとつてゐ
るからね。父や母はただ僕一人を希望に生きてるんだ。
それに何人にも何物にも侵されない家庭の城壁の中はほ
んとうに安らかなんだからな』といふやうなことを言った。
試みに、恒藤のこの文章と、芥川の「点鬼簿」のなかにある次の記事を読み比べてみよう。
実父の新原敏三は、芥川家に龍之介を託したものの、彼を取り戻そうとして度々説得を試みたらしい。それは、龍之介が正式に養父の戸籍に入り、芥川姓を名乗るようになる11歳以前のことだったと思われる。
僕の父は幼い僕にかう云ふ珍らしいものを勧め、養家
から僕を取り戻さうとした。僕は一夜大森の魚栄でアイ
スクリイムを勧められながら、露骨に実家へ逃げて来い
と口説かれたことを覚えてゐる。が、生憎その勧誘は一
度も効を奏さなかつた。それは僕が養家の父母を、殊に
伯母を愛してゐたからだった。
当時、新原、芥川の両家には跡継ぎの男の子がいなかったから、両家の間で龍之介を奪い合う隠微な争いが続いていたのだ。こうした争奪戦に巻き込まれた龍之介が、実父についても、また、芥川家についても「大人のエゴイズム」を身にしみて実感したことは疑いない。後年、龍之介は作品の中に家族の愛情に潜むエゴイズムについて、繰り返し書くようになる。
彼は恒藤に「何人にも何物にも犯されない家庭の安らかさ」について語っているけれども、養父母と龍之介の間には、互いが生さぬ仲であることからくる奇妙な礼節と遠慮が流れていた。
彼はいつ死んでも悔いないように烈しい生活をするつもりだった。が、相変わらず養父母や伯母に遠慮勝ちな生活をつづけていた。それは彼の生活に明暗の両面を造り出した({或阿呆の一生」)。
これには、伯母にも遠慮がちだったとあるが、同じ「或阿呆の一生」には次のような記述がある。
彼は或郊外の二階の部屋に寝起きしてゐた。それ
は地盤の緩い為に妙に傾いた二階だった。
彼の伯母はこの二階に度たび彼と喧嘩をした。そ
れは彼の養父母の仲裁を受けることもないことはな
かった。しかし彼は彼の伯母に誰よりも愛を感じて
ゐた。一生独身だった彼の伯母はもう彼の二十歳の
時にも六十に近い年よりだった。
彼は或郊外の二階に何度も互に愛し合ふものは苦
しめ合ふのかを考へたりした。その間も何か気味の
悪い二階の傾きを感じながら。
とにかく、龍之介と養父母・伯母との関係、特に伯母との関係は微妙だったのである。
龍之介は大学を卒業する前年に、養父母らに従妹と結婚したいと申し出ている。彼はその従妹が他の男性と婚約するまでは、相手にほとんど関心を払っていなかったが、結婚すると聞いて急に相手を失いたくないと思い詰めるようになったのである。
これに対して、養父母も伯母も、激しく反対した。特に、伯母の反対は強硬を極めた。この話は、結局、不成立に終わり、従妹は青年士官と結婚してしまうけれども、この間のいきさつを親友の恒藤恭に知らせる手紙で、龍之介はこう書いている。
家のものにその話をもち出した。そして烈しい反対を受けた。伯母が夜通しないた。僕も夜通し泣いた。ある朝むづかしい顔をしながら僕が思切ると言った・・・・・
この文面から、奇妙な感じを受けないではいられない。
この時、伯母は60に近く、龍之介は大学を終えようとする23歳の青年だった。十分に分別を備えているはずの二人が、縁談をめぐって衝突して、揃って「夜通し」泣いたというのだ。
実の母と息子だったら、互いの意見が衝突して泣くことがあっても、「夜通し泣く」というようなことにはならない。伯母と甥という関係にある二人の間に、男女間の愛情に近いものが存在したと仮定すれば、夜通し泣き合ったという話も理解されて来る。
遺稿として残された「歯車」には、彼が喫茶店で一組の母子と同席する場面が出てくる。
僕の向うには親子らしい男女が二人坐っていた。
その息子は僕よりも若かったものの、
殆ど僕にそっくりだった。のみならず彼等は恋
人同志のやうに顔を近づけて話し合ってゐた。僕は
彼等を見てゐるうちに少くとも息子は性的にも母親
に慰めを与へてゐることを意識してゐるのに気づき
出した。それは僕にも覚えのある親和力の一例に違
ひなかった。同時に又現世を地獄にする或意志の一
例にも違ひなかった。
母親に慰めを与えている息子を見て、彼は自分にも覚えがあると語る。彼が慰めを与えたと自覚している相手が伯母であることは明らかだろう。そして龍之介は、こうした愛情関係が現世を地獄に変えると言っているのだ。
27歳で結婚した龍之介は、当初、新妻を養父母の家に残して、自分だけ横須賀で暮らしていた。彼は筆一本で生きて行くことに不安を感じて、安定した収入を得るために海軍機関学校の教官をしていたのである。やがて鎌倉に手頃な借家が見つかったので、妻を呼び寄せて新婚生活を送ることになる。この時、養父母は東京の田端に残ったが、伯母は新妻と一緒に鎌倉にやってきて、龍之介夫婦と同居することになる。
伯母がとついできたばかりの嫁にどういう態度を取ったかは、次の一節を読めば明らかだろう。
彼は結婚した翌日に「来勿々無駄費ひをしては困
る」と彼の妻に小言を言った。しかしそれは彼の小
言よりも彼の伯母の「言へ」と云ふ小言だった。彼
の妻は彼自身には勿論、彼の伯母にも詫びを言って
ゐた。彼の為に買って来た黄水仙の鉢を前にしたま
ま。………
伯母は龍之介の妻に対して姑のような態度で臨んだらしいけれども、この一事が原因で龍之介に次のような発言をさせたとは思えない。吉田精一の「芥川龍之介」は、自殺を決意した彼が、佐藤春夫に「僕の生涯を不幸にしたものは××なのだよ。もっともこの人は僕の無二の恩人なんだがね」と語った事実を紹介したあとで、「この××は伯母をさすものにちがいない」と書いている。
もし吉田精一の言うとおりだとしたら、龍之介は伯母が妻につらく当たったというような些事ではなく、もっと根深い問題で伯母の責任を問うているのである。
一生結婚しなかった伯母にとって、手塩にかけて育て上げた龍之介は何物にも代え難い存在だったにちがいない。龍之介は、彼女の甥であると同時に、息子であり、恋人であり、夫であり、一切を兼ねる存在だったのである。彼女は、ためらうことなく自分の思いや嗜好を彼に押しつけた。伯母は、自分にはその権利があると思っていたのだ。
龍之介はこれに抵抗して夫婦喧嘩のように伯母に逆らい、養父母の仲裁を受けながら、結局は精神的に伯母に組み敷かれていったと思われる。
芥川龍之介と伯母の関係が濃密なものになったのには、伯母が兄夫婦に扶養される身だったという事情が関係している。兄夫婦の厄介になっていても、家の中に彼女の手助けを必要とするような仕事があれば心理的負担も少なくて済むが、サラリーマン家庭の芥川家には、そうした仕事はひとつもなかった。
女手が余っている芥川の家には、さらに女中が二人もいた。これは、一つには東京府土木課長という当主の体面を保つためだったろう。江戸時代以来の遺風を残す東京市民の家庭では、親戚とのつきあいが多く、そのために下働きの女中を必要とするという事情があったにちがいない。だが、親戚が訪ねてきても、応対に当たるのは兄夫婦であり、台所仕事は女中がやるから、伯母の出番はない。
そうした伯母の手に、龍之介が託されたのだ。彼女が芥川家の内部に確たる座を占めるには、いずれはこの家の当主になるはずの龍之介を立派に育て上げることしかなかった。龍之介が世間の褒め者になるような「いい子」になってくれれば、彼女の株は親戚間でも大いに上がるのである。
三島由紀夫が病臭のこもる祖母の部屋に閉じこめられて、その囚人になったように、芥川龍之介も伯母の手の中に囲い込まれてマンツーマンの訓育を受けることになった。
三島由紀夫の祖母は一家の中で絶対的な権力を握っている独裁者だったから、孫をしつけるに当って自分の思うところを暴力的に押しつけている。この結果、成長した三島は祖母と同様な攻撃的な人間になった。事情は、河上肇の場合も同様で、彼が階級闘争の闘士になったのは、世の中のしきたりを屁とも思わぬ攻撃的な祖母から育てられたためでもある。
三島や河上肇の祖母が、孫を攻撃的な人間に仕立て上げたのとは反対に、龍之介の伯母は甥を防御的な人間にしてしまった。世話になっている兄夫婦の前で遠慮がちに暮らしていた伯母は、近親者の目を恐れるだけでなく世間を必要以上に恐れていた。扶養される身で世間の荒波を知らないために、必要以上に世間を恐れるという面もあった。
彼女が思い通りに行動できるのは、手塩にかけた幼い甥と一緒にいるときだけだった。彼女は龍之介がいたずらをしたりすると、きまって足の小指に灸をすえた。こうして彼女は龍之介を厳しく叱ったり、優しくすかしたりしながら、彼を老嬢好みの小綺麗な子供に仕立て上げていったのである。
子供の頃から伯母に義理と人情を大切にするように仕込まれた龍之介は、長じて「礼儀好き」の人間になり、あまり礼儀正しく義理堅いので、時に後輩の作家たちに気づまりを感じさせるほどになった。芥川龍之介に関する追想記を読むと、その種の叙述をいたるところに見ることが出来る。
私が田端に住んでる時、或る日突然、長髪瘠躯の人が訪
ねて来た。
「僕は芥川です。始めまして。」
さういって丁寧にお辞儀をされた。自分は前から、室生
君と共に氏を訪ねる約束になってゐたので、この突然の訪
問に対し、いささか恐縮して丁寧に礼を返した。しかし一
層恐縮したことには、自分が頭をあげた時に、尚依然とし
て訪問者の頭が畳についてゐた。自分はあわててお辞儀の
ツギ足しをした。そして思った。自分のやうな書生流儀
で、どうもこの人と交際ができるかどうか。自分はいささ
か不安を感じた(萩原朔太郎)「(芥川は)極めて謙遜な、注意深い、挙止端正な若い東京人だった」(久保田万太郎)
「麻川氏(注・芥川のこと)は、両手をばさりと置いて丁寧にお辞儀をした。しつけの好い子供のようなお辞儀だ」(岡本かの子)
龍之介の礼儀正しい振る舞いが、半ば反射的なものにまでなっていたことは、彼自身の語るところでもある。
僕は見知越しの人に会うと、必ずこちらからお辞儀をしてしまう。従って向こうの気づかずにいる時には「損をした」と思うこともないではない(「僕は」)
芥川龍之介は、力のある先輩や友人に対して特に鄭重に礼を尽くした。彼を計算高い人間と見る世評は、このあたりに胚胎している。だが、これは「御奥坊主」の系譜を引く芥川家の家風のようなものであり、世間を恐れる伯母の徹底した訓育の結果だったのである。
龍之介が漱石から「鼻」を賞賛する手紙を貰ったとき、彼は家人から直接「お礼言上」に行ってくるように命じられている。それで、漱石宅に出かけるに当たって、彼は久米正雄に一緒に行ってくれないかと頼んだ。その時、彼はこう言っている。
「僕ん所の家の者も、実は之れだけのお手紙を頂いたんだから
取り敢へず御礼状を出して置いたにしても、特に改めて自分
で罷り出て、御礼を申上げて来いと言ふんでね」(久米正雄「風と月と」)
文壇の大先輩正宗白鳥に褒められた時に、龍之介は折り返し感謝の手紙を出している。「文藝春秋の御批評を拝見しました 御厚意有り難く存じました 十年前夏目先生に褒められた時以来最も嬉しく感じました」と記す長文の手紙である。
芥川の死後、この手紙について正宗白鳥は、次のように言っている。
かういふ私の批評を読んだ芥川氏は、私に宛てて、自
己の感想を述べた手紙を寄越した。私が氏の書信に接し
たのは、これが最初であり最後でもあったが、私はその
手跡の巧みなのと、内容に価値があるらしいのに惹かれ
て、この一通は、常例に反して保存することにした。
辛口の批評によって文壇から一目置かれていた正宗白鳥をして、このような文章を書かせたところからも、龍之介の手紙が効果的だったことが分かる。彼はこうした効果的な手紙を、まだ無名だった頃に、久米正雄へも書いているのだ。
一高に入学した芥川龍之介は、初めのうちは寄宿舎で同室になった恒藤恭と親しくしていた。病気で数年間療養していたため4才年長だった恒藤に、彼は兄事するような形でつきあっていたのである。一高を恒藤が一番、龍之介が二番で卒業すると、恒藤は京都大学の法科に移ってしまった。それで、東大の英文科に入学した龍之介は、久米正雄らと交際するようになる。久米は、「文壇進出」という点では、仲間より一歩先行していた。龍之介は「あの頃の自分の事」のなかで、久米の事をこう紹介している。
久米は文壇的閲歴の上から云って、ずつと我々より先輩だった。と同時に又表現上の手腕から云っても、やはり我々に比べると、一日の長がある事は事実だった。特に自分はこの点で、久米が三幕物や一幕物を容易にしかも短い時間で書き上げる技量に驚嘆してゐた。だから我々の中で久米だけは、彼自身の占めてゐる、或は占めんとする、文壇的地位に相当な自信を持ってゐた。
その久米が、「帝国文学」に発表した龍之介の作品「羅生門」を酷評したとのである。それを耳にして恐慌状態に陥った龍之介は、その頃、さほど親しくもなかった久米にあてて長い手紙を書いている。それは、まるでラブレターのような手紙だった。進藤純孝の「芥川龍之介」は、この手紙を引用するにあたって、以下のように注釈を付けている。
「僕は一切の遠慮をすてゝ云ふ 僕はすべての他の人間を軽
蔑するだけそれだけ君を尊敬する」と書き出された、大正四年十一月十六日附の久米宛の書簡は、
芥川自身「あるセンティメンタルな感動の為にこの手紙をかいた
僕はその感動の去った時にこの手紙をみるのを恐れてゐる
同時に君がこの手紙のセンティメンタリズムを哂ふ事を恐れ
てゐる 僕は僕自身今感じつゝある感情が人生意気に感ずと
云ふ中学程度の感情に近い事を知ってゐるからである」と認めてゐるやうに、ほとんどラヴ・レターに近いものである。
久米にあてて恋文のような手紙を書いた時点では、龍之介は先行する久米を追う立場にあったが、やがて龍之介が「鼻」によって漱石から認められると、この関係は逆転する。芥川龍之介は新進作家としてマスコミの脚光を浴び、久米の影が薄くなるのだ。
だが、久米はすぐに龍之介に追いつき、中央公論や文章世界に続々と作品を発表し、通俗小説にも筆を染めるようになる。金回りのよくなった久米は、新思潮時代の仲間とは疎遠になって、吉井勇・田中純・里見弴らの「遊蕩文学者」と行動を共にするようになった。
大正8年に旧新思潮同人が集まって新年宴会を開いたとき、珍しく龍之介は放蕩にふける久米に強い非難を浴びせた。公開の席上で厳しく忠告されたために、かえって反抗的になった久米は、会場を飛び出して里見や吉井らがいる料亭に駆け込み、胸の憤懣をぶちまけた。
これを迎えて久米を慰めた里見弴の言葉は、芥川龍之介の生き方を諷したもので、当時、人気絶頂だった龍之介が一部の作家仲間からどう見られていたかを物語る内容になっている。
「(略)君も僕の見る所では、どうも今の仲間と離れた方が、君のためにはいゝやうだよ、君はあの人たちのやうに、小利口に世間を立ち廻って、破綻のない生活を送れる人とは違ふんだ。三十にならぬ若い身空で、細君を貰ってすっかり家に収まったり、巧みに創作の調節を取って、確乎と文壇の地位を高めて行くと云ったやうな、さう云ふ甲斐性のある人間ぢやないんだ。君はあの人たちとちがって、もっと出鱈目な、もっと脱線的な生活を送るべき人なんだ。人生ってものは、彼らのやうな、破綻のないものぢゃないんだよ。芸術ってものも、彼らのやうに、キチンとしたものじゃないんだよ」
龍之介が強い言葉で久米をいさめたのは、仲間を里見らに奪われたくなかったからだとする見方がある。つまり自派が弱体になるのを恐れたエゴイズムに基づくという見方があるのだ。作家仲間の多くは、年に似合わず老成した印象をあたえる龍之介の言動を計算高いと見る傾向があった。だが、彼は、この時には久米の「堕落」を本当に心配していたのである。
久米正雄の評価を恐れて、彼に恋文のような手紙を書き送った龍之介は、佐藤春夫にも同じような手紙を出している。進藤純孝は「大正6年4月5日付けの、佐藤に宛てた芥川の書簡は、厭でも佐藤の心を惹きつけないではいないような恋文に似た調子で書かれている」と書く。
龍之介は同輩の作家の中では、佐藤春夫を最も高く買っていたため、佐藤が同人誌の六号雑記で自分のことを褒めてくれたチャンスを逃さず、「褒めていただくのが有り難い以外に、恐縮した理由があるのです」という文章にはじまる長い手紙をしたためるのである。
感激した佐藤は、久米正雄などを差し置いて、芥川の出版記念会を開くことを提唱し、実際、それを実行に持ち込んでいる。進藤純孝は先の文章に続けて、「芥川も、佐藤の肩を叩いていい気になりながら、一人の強敵を味方につけ得たと、胸をなで下ろしたのではあるまいか」と推測する。
龍之介が肩を叩いて味方に引き込もうとしたのは、同輩のライバルだけではなかった。後輩の作家や、同人誌にくすぶっている作家の卵たちにも、まめに手紙を出している。小島政二郎に手紙を出したのも、彼に「地獄変」を叩かれたためだった。以下は進藤純孝「芥川龍之介」からの引用である。
もつとも悪評に神経質になる理由はあった。といふの
は、『地獄変』に対する、「三田文学」の批評が、芥川の説
明癖なるものをかなり強く叩いてゐたからである。この
『地獄変』評の筆者は、小島政二郎だったらしく、芥川は早
速に端書三枚にわたつて抗議をした。(この抗議の手紙は、
「三田文学」に掲載されたらしい・・・・ 七月二十二日附、薄田
淳介宛書簡に、「僕が抗議を申し込んだらその又手紙が活字
になって現れました」とある)
ところで、芥川の小島への抗議は、「・・・・ 三田文学で褒めて下すったのはあなただと云ふから申
し上げますあなたのやうな具眼者に褒められる性質のも
のぢやありませんこの間よみ返して大分冷汗を流しました」
と、まづ、褒めた批評を皮肉り、さらに、
「・・・・それから説明と云ふ事に就いて私の文章上の説明癖
なるものはそれが鑑賞上邪魔になるとあなたが云ふ範囲
では so far 私も抗議を申し込む資格はありません然し
『あの小説の中の説明』になると私にも云ひ分があります
と云ふのはあのナレエションでは二つの説明が互にから
み合ってゐてそれが表と裏になってゐるのです(後略)」
彼が 『羅生門』 の悪評から久米正雄に急速に近づいた
やうに、小島政二郎にも、この『地獄変』 の悪評をきっか
けに近づいてゐる。言ひ換へれば、芥川は、弱味を見抜い
た相手を、味方にしてしまはうとする処世上の知恵を、露
骨にあらはす傾きがあり、小島に近づいたといふことは、
小島の悪評なるものが的を射て、芥川の弱味を的確に言ひ
当ててゐたことを意味するのである。
龍之介の狙いはあたり、この後、小島政二郎は芥川邸で開かれる面会日の常連になる。パソ通仲間の友人が教えてくれたところによると、小島は「眼中の人」という著書の中で、面会日における龍之介を次のように描いているそうである。
シーンと冷たく澄み切った、閑静な山の手住まいといったたたずまいだっ
た。 広い平庭を見下ろす12畳の2階の書斎に、芥川は、2尺の紫檀の机を前にして座っていた。小さな長火鉢には、鉄瓶が白い湯気を静かに立てていた。壁の中へ作り付けの本箱の中は勿論、棚の上、机のまわり、壁際の畳の上、至る所に外国の本が、豊かな感じで散乱していた。
シシス・グリヤーソン風に髪の毛を乱した芥川の、額の広い秀麗な顔が、青い空気の中に白く浮き出ていた。何とも云えない澄んだ目をしていた。鋭くって瑞々しくって叡智に濡れていた。女のような長い睫毛が、秀麗な容貌に一抹の陰影を添えていた。「こりゃぁただ者ではない」
初対面の挨拶をしながら、私は打たれた感じがした。こんな素晴らしい顔をした人間にこれまで出会った事がなかった。話題は豊富だし、座談はうまいし、私はつい誘い込まれて、初対面の窮屈さなんかすぐ忘れて、腰を落ち着けて話し込んでしまった。それには東京の下町っ子らしい共通の匂いを嗅いだ心やすさも大分預かって力があった。
その間にも、後から後から来客があって、たちまち書斎が一杯になってし
まった。主人は誰に向かってもまんべんなく話題を持っていた。ときには機知を交えて議論を上下した。聞いていて、私は主人の博識に舌を巻いた。理論の透徹した鋭さに耳を洗われるような思いがした(中略)。芥川の読書の範囲、趣味の限界は、実に広範にわたっていた。ドイツ語、フランス語が口を突いて出た。西洋の絵画、彫刻、音楽、哲学、歴史、支那画、日本画、陶器、織物・・・文学だけだって、いま近代の話をしたいてかと思うと、古典の話になったりした。アメリカ文学の現代作家をさえ彼は読みあさっていた。
一方に機関学校の教官という職を持ちながら、こんなに盛んに読書をし、しかも毎月一編か二編かずつ推敲に推敲を重ねた小説を雑誌に発表している芥川に比べると、私の生活などは死んだようなものだった。
面会日の様子は、龍之介の弟子格である滝井孝作も書いている。
面会日には芥川龍之介先生は朝から客に会い夜更けに至るまで客を飽かせずに務めておられた。(今考えるとこれは大変骨の折れることだったろう。囲棋カルタ遊戯の道具の傍で時間の消費は手易いが、主人公は主に談話で座を持ってゐられたから、談話だけでどの客もどの客も倦ませないと云ふことは大した業だった)主人公は飽くことのない知識慾生活慾の把持者だつたから、客と互に共に楽しみ合ったのだ。が、修羅道だつた。
面会日の龍之介は、いきいきとして多弁だった。彼は知人への手紙に「わたしは天の成せる駄弁家」だと書いている。佐藤春夫は芥川の文章を論じた際、その会話は光彩陸離としている、彼の文章はこれに比べるとまるで光彩がない、あえぎあえぎ書かれた感じがすると言っている。
この面会日に集まるのは、小島政二郎・南部修太郎・中戸川吉二・佐々木茂索・滝井孝作・谷口喜作などの若い作家志望者たちだった。こうした気鋭の面々の中央に、28才の龍之介が傲然と立ちはだかっていたのである。吉田精一は「これを谷崎潤一郎や志賀直哉が、所謂文壇からはなれて、ただ創作に没頭していたのに比べると、態度にかなり開きがある」と指摘している。
龍之介の会話が光彩陸離としていると褒めた佐藤春夫も、面会日にたくさんの人を集めて談論風発したり、作家や批評家に肩たたきの手紙を書き送ったりする龍之介のやり方に次第に批判的になっていく。
人気作家ともなれば、まわりに心酔者やファンが集まってくるのは自然現象のようなものだ。佐藤は、そんなことに浮かれて、龍之介が時間とエネルギーを浪費していることを惜しんだのである。志賀直哉や谷崎潤一郎は、こうした取り巻きから逃れるために関西に引っ越して、執筆環境を整えている。芥川龍之介も関西あたりに引っ越して腐れ縁を切り捨てるべきだと、佐藤は考えるようになった。
だが、龍之介は友人の忠告に耳を傾けるどころか、ちょっと暇になると人恋しくなって、やたらに遊びに来るように仲間を誘うのである。
日曜に遊びにござれ梅の花
これはそうした勧誘のハガキに書き添えられた俳句である。海軍機関学校を辞めて、東京に戻りたいと考えたのも、自由な時間がほしかったこと以外に、孤独に耐えない人恋しさがあったからだった。
落ち目になってきたとはいえまだ文壇の主流は自然主義系の作家だったから、彼らは龍之介がまわりに人を集めるのは、政略のためだと考えていた。佐藤春夫すら、ある日、龍之介と並んで道を歩きながら、こんなふうに考えるのである。
へんに淋しくって芥川と別れ度くなかった。その感情を
彼に伝へると彼はそれでは自分の家へ来いといふ。そこで
自分は彼に随いて行った。道々自分は芥川程の人物が、敢
然と孤高の生活をすることをせず身辺に沢山の同輩や後輩
を集めて何か世俗的の勢力のやうなものを喜びまた芸術上
の精進を一心に練るだけで充分とせずに、社交的の方法で
その市価を維持しょうとするかのやうに考へた。
こうしたことが頭にあったから、佐藤は週刊誌から雑文の依頼があったときに「処世術」という題名で、芥川を念頭に置いて5,6枚の原稿を書いてしまったのである。その内容は、次のようなものだった。
ある作家は、作家たちの集まる宴席などでは、非常に遠慮深そうに末席にいる。そのため同業者の間では、彼は謙遜な人間だと思われている。ところが、いざ記念写真を撮る段になると、その作家はいつの間にか真ん中に坐っているのある。
彼は、写真が掲載される新聞・雑誌の読者に、いかに自分が皆から重んじられているかを知ってほしいのだ。
さらに彼は仲間の作品をけなしておいて、それが当人の耳に入る前に相手の所に出かけていって、「君の作品をけなしたが、僕の目が足りなかった。あれはなかなかいい作品だ」と褒めるようなこともする。これは、自分の非を率直に認める誠実な人間だと相手に思わせるためだ・・・・
芥川龍之介は、これを読んで引っかかるものを感じたが、何も言わないでいた。彼がこの雑文の件をを持ち出すのは、自殺を決意した彼が別れを告げるために、佐藤春夫を訪ねたときだった。龍之介の死後、佐藤は「芥川龍之介を憶ふ」という追悼の文章を書き、その中で彼は芥川から「『処世術』は僕のことを書いたのではないか」と訊ねられたことを明かしている。そう問われて佐藤は、狼狽した。
「そんなことを君、あれは君、架空談ではないか。さう開
き直って問はれては……」
自分がさう云ひかけると芥川は自分の言葉を引き取つ
て、
「困るか・・・・漏してはくれられないか」
自分は尚ほ一層うろたへ乍ら言った.
「君のやうに独りできめて了っては困るな……」
自分は寧ろ卑屈な態度でじっと芥川の顔を真面に見た.すると彼の目には涙が浮んでゐた。自分は始て彼の顔をゆ
つくり見たやうな気がした。一杯涙の溜って来た切れの長
い大きな眼を美しいと思った。自分は彼の気迫に呑まれて
了った.
「いいよいいよ.漏らし度くなければいいのだよ」
彼は相手をなだめるやうにやさしく云った。
「処世術」に佐藤が書いたようなことが、仮にあったとしても、これは軽く黙殺してしまってもいい文章だった。集団写真を撮るときに、真ん中に坐ろうとする者もあれば、端の方を好む人間もいる。龍之介は、養家では主観的には遠慮がちに過ごしたかもしれない。だが、彼は大人社会の中のただ一人の子供として、家の中では王子のような存在だったから、写真を撮るときに真ん中に坐るのは習慣的な行動だったかもしれないのだ。
それよりも注目すべき点は、日曜日の面会日には昂然とした表情で群がる若手を片っ端から論破していた彼が、作家の集まりでは遠慮がちに末席に座っているという部分で、ここに「皆によく思われたい」という龍之介の固定観念のようなものが見て取れるのである。
芥川龍之介は、この軽く黙殺してもいいような雑文にこだわり続けた。そして、最後の別れを告げる時になって、ようやく佐藤に真意を糺し、相手がたじろいでいるのを見て、「いいよ、いいよ」と優しくなだめるのだ。
目に涙を浮かべたことを含めて、佐藤をやさしく許したところに、芥川龍之介という作家の世評とは相反する少年のような純情を見ることが出来る。この無邪気なばかりの彼の稚さを、広津和郎は次のような比喩で語っている。
彼の風格は、坐っていると、四十男の老成ぶりを見せて
いながら、立上ると実は子供で、足を見ると、七文半の足
袋を穿いていたといったようなユウモアを、生涯を通じて
持っていた。そして七文半の足袋を穿いている事を、彼が
如何に巧みに隠し了せようとしても、決して隠し了せては
いなかった。そこが彼が私などには最も親しみあり、最も
愛らしくあり、そして最も好い感じに思われたところであ
る。
「皆によく思われたい」という多分伯母から植え付けられた固定観念に近い思いを激しく揺るがしたのは、書肆の依頼で「近代文芸読本」全5巻を編集したことにからまる一件だった。彼は誰からも不満が出ないように、この読本に百二三十人もの作家の作品を盛り込んだのだが、これが裏目に出たのである。
作家ひとりひとりの作品群の中から、適当なものを一つ選び出すには下読みが必要で、この作業は体力が弱ってきていた晩期の龍之介に予想以上の労苦を強いた。だが、出来上がってみると、読本は、あまりに凝りすぎ、あまりに文芸的だったために売れ行きは芳しくなく、印税は編集を手伝った二三人に分けると終わりになってしまった。
龍之介自身も編集責任者として応分の謝礼を受け取ったものの、菊池寛によればその額は芥川の費やした努力の十分の一にも足りないものだった。
だが、作家たちのなかに「芥川は、読本で儲けて書斎を建てた」というデマが流れ、「われわれ貧乏作家の作品をかき集めて儲けるとはけしからん」という声が起こった。菊池寛は、この件について次のように証言している。
かうした妄説を芥川が、いかに気にしたか。芥川
としては、やり切れない噂に達ひなかった。芥川は、堪
らなかったと見え、「今後あの本の印税は全部文芸家協
会に寄附するやうにしたい」と、私に云った。私は、そ
んなことを気にすることはない。文芸家協会に寄附など
すれば却って、問題を大きくするやうなものだ。そんな
ことは、全然無視するがいい。本ほ売れてゐないのだし、
君としてあんな労力を払ってゐるのだもの、グズグズ云
ふ奴には云はして置けばいゝと、私は口がすくなるほど、
彼に云った。
菊池寛に反対された龍之介は、それなら今後入ってくる印税は関係作家全員に分配すると言いだした。だが、教科書類似の読本には、作品を無断で収録して、印税も払わないというのが当時の慣習だったから、これにも菊池寛は反対した。菊池がそういえば、龍之介はその場では承服する。
彼はやっぱり最後に、三越の十円切手か何かを、各作家の許に洩れなく送ったらしい。私は、こんなにまで、こんなことを気にする芥川が悲しかった。だが、彼の潔癖性は、こうせずにはいられなかったのだ。
菊池寛は、こう書いて芥川のことを悲しんでいるのだが、「こうせずにはいられなかった」のは彼の潔癖性のためだけだったとは思われない。
彼は生活のため、身を守るためには、最後まで小心翼々と生きた。彼が「皆によく思われたい」と願ったのは、虚栄のためというよりは、矢張り生活のためだった。こうした自分自身を、龍之介は「生活的宦官」と呼んで自嘲しているけれども、自嘲しながら彼はなお顧みて他を言うような発言を繰り返すのだ。その辺を指摘するのは、明敏な目を備えた広津和郎である。
広津は、芥川が遺書の中に、「自殺した後に自分が家族に残しうるものは百坪の土地と幾間かの家と二千円の貯金しかない」と書いていることに触れて、次のような事実を指摘する。
実際は彼は死を決すると間もなく、(死ぬ
よりも半年以上も前に)或る書店に行って、彼の死後の全
集の契約をしている。彼はその全集からの収入が、遺族の
生活にどのような助けとなるかを冷静に計算に入れてい
る。そればかりではない。既に会員部数の決定した二つの
円本からどの位の収入があるかという事も、冷静な彼が計
算に入れていなかった筈はない。それだのに彼は遺書に
は、銀行預金が二千円しかないという事を麗々しく書いて
いる。そう書くのが彼の好みなのである。
龍之介は遺族の将来を考慮する余裕がないほど、エゴイスティックになっているとPRしているけれども、彼は自分の死後についても万全の手を打っているのである。こうした先の先まで考える用心深さは、兄夫婦に扶養されて生きた伯母からマンツーマンで仕込まれた訓育の結果だと思われる。
だからこそ、彼はふとしたはずみに「僕の生涯を不幸にしたのは伯母だ」ともらし、養家に引き取られることがなかったら「いつ死んでも悔いないような烈しい生活を」したろうと悔いたのである。
龍之介の中学時代の親友に山本喜誉司という男がいた。彼の家と芥川家は家同志でも交流があったので、龍之介は山本家によく遊びに出かけた。山本家には、ほかに一組の家族が住んでいた。海軍将校に嫁いだ喜誉司の姉が、夫に戦死されたため娘を連れて実家の山本家に戻ってきていたのである。この海軍軍人の遺児が、龍之介の妻となる塚本文子なのである。
文子は、龍之介より8才年下だから、龍之介が山本家に遊びに出かけていた頃は、文子はまだ小学校の生徒だったことになる。龍之介は未来の妻を子供の頃から見知っていたのである。
この少女に惹かれていた龍之介が、具体的な行動に出るのは大学を卒業する24才の時で、この大正5年に彼は山本喜誉司に宛てて次のような手紙を出している。いかにも龍之介らしい言外に計算を秘めた手紙である。
僕のうちでは時々文子さんの噂が出る 僕が貰うと丁度いいというのである 僕は全然とり合わない 何時でもいい加減な冗談にしてしまう 始めはほんとうにとり合わないでいられた 今はそうではない
と書いて、彼が文子に「可成りの興味と愛」を抱き始めたことを告白しておいて、一転してこの縁談は到底成立しないだろうと悲観的な予言をしてみせるのだ。
其の予感というのは文子さんを貰うことは不可能だという予感である 第一文子さんが不承知それから君の姉さん(注:つまり文子の母)が不承知それから君が不承知それから色んな人が皆不承知という予感である
彼はマイナスの条件を列挙した後で、
僕は文子さんの話が出ると冗談にしてしまう 此の後もそうするだろう そして僕のうちの者が君の所へ何とか言ってゆくのを出来る限り阻止するだろう 或はその後は思いもよらない所から思いもよらない豚のような女を貰って一生をカリカチュアにして哂ってしまうかもしれない
と自暴自棄なことを書いてみせる。そして最後は、相手の同情をそそるような言葉で手紙を終えるのである。
僕はさびしい しかし僕は立っている者の歩まなくてはならないのを知っている (中略)だから僕は歩む 歩んでそして死ぬ 僕はさびしい
この話は成立しないだろうとの彼の予感は、精神病者の実母を意識してのことだったかもしれない。だが、これはレトリックである可能性が高い。彼がこの手紙を親友の山本に出した狙いは、誰の目にも明らかだろう。家の者が山本家に出かけて縁談話を切り出した場合、側面からの応援を頼むという手紙なのだ。
この手紙の効果はあったらしく、芥川家の希望は山本家と文子に伝えられ、龍之介は直接文子と交渉できるようになった。この年の8月に龍之介は、はじめて文子に手紙を出している。当時、文子は16才で、まだ女学生の身だった。
文ちゃんを貰いたいと言うことを、僕が兄さんに話してから、何年になるでしょう。(こんな事を文ちゃんにあげる手紙に書いていいものかどうか 知りません。)貰いたい理由は、たった一つあるきりです。そうして、その理由は僕は、文ちゃんが好きだと言うことです。(中略)僕には、文ちゃん自身の口から、かざり気のない返事を聞きたいと思っています。繰り返して書きますが、理由は一つしかありません。僕は文ちゃんが好きです。それだけでよければ、来て下さい。
龍之介は、手紙を書くときには、句読点抜きの書き流し式文体を使用するのが例で、漱石のような特別の上長に出す手紙にだけは、句読点を付けている。文子に出したこの手紙に句読点がついているところをみると、彼はかなり緊張してこのプロポーズの手紙を書いたのである。
文子は、求婚の手紙に対してOKの返事を出したらしい。文子に宛てた次の手紙は、いつもの通り句読点抜きのリラックスした調子になっている。
文、ちやん
少し見ないうちに又脊が高くなりましたねさうして
少し肥りましたねどんどん大きくおなりなさいやせ
たがりなんぞしてはいけません体はさう大きくなって
も心もちはいつでも子供のやうでいらっしやい
これに続けて彼は、文子にやさしい調子で、いろいろな「訓戒」を与えている。以後、龍之介は教師が生徒に対するような、あるいは兄が妹に対するような手紙を許婚者に出し続けるのだ。何しろ、相手はようやく少女の域を脱したばかりの稚い娘なのである。
えらい女・・・小説をかく女や画をかく女や芝居をか
く女や婦人会の幹部になつてゐる女や・・・・は大抵に
せものですえらがってゐる馬鹿ですあんなものにか
ぶれてはいけませんつくろはずかざらず天然自然の
ままで正直に生きてゆく人間が人間としては一番上等
な人間ですどんな時でもつけやきばばいけません(中略)人間は誰でもすべき事をちやんとして
行けばいいのです文ちやんもさうしていらっしやい
学校の事でもうちの事でもする丈をちやんとしてい
らっしやいしかしそれから何か報酬をのぞむのは卑
しいもののする事です学校の事にしてもよい成績を
とるために勉強してはいけませんそれはくだらない
虚栄心です唯すべき事をする為に勉強するのがいい
のですそれだけで沢山なのです成績などはどんなで
もかまひません成績は人のきめるものです
翌年になると、文子は文壇の寵児になった龍之介に引け目を感じ始めたらしい。龍之介は、そういう文子を励ます手紙も書いている。
文学なんぞわからなくったって いいのです スト
りントベルクと云ふ異人も「女は針仕事をしてゐる
時と子供の守りをしてゐる時とが一番美しい」と云
ってゐます ボクもさう思ひます手紙もかざってなど書かない方がいいのです 思ふ
事をすらすらそのまま書く方がいいのです だから
いつもの手紙で結構です少しもまづいともおかしい
とも思ひません いつ迄もああ云ふすなほな手紙が
書けるやうな心もちで お出でなさい
文子に出す手紙には、素直でいてほしいという言葉が繰り返されるようになる。「文ちゃんは何にも出来なくていいのですよ 今のまんまでいいのですよ」とか、「赤ん坊のようでお出でなさい それが何よりいいのです」というよう手紙が連続する中に、次のようなものも混じっている。
僕が文ちゃんに「僕の手紙はよみにくいでしょ」と言ったら 文ちゃんが「ええ」と言ったでしょう。その時僕には素直なうれしい心もちがしました
やがて、龍之介の手紙からは、訓戒調が徐々に消えて、次第に恋文らしい調子が出てくる。
二人きりでいつまでもいつまでも話していたい気がします そうしてkissしてもいいでしょう いやならばよします この頃ボクは文ちゃんがお菓子なら頭から食べてしまいたい位可愛いい気がします
挙式一ヶ月前の手紙には、文子に宛てた自分の手紙を全部持ってきてほしいと書いている。
文ちやんは御婚礼の荷物と一しよに忘れずに持って
来なければならないものがあります それは僕の手
紙です 僕も文ちやんの手紙を一束にして持ってゐ
ます あれを二ついっしょにして 何かに入れて
何時までも二人で大事にしておきましょう
二人の手紙を愛の記念として秘蔵しておこうという提案は、体裁屋だった龍之介がこれらの手紙を他人に見られることを恥じていたことを示している。これ以前にも、彼は「自分の手紙を人に見せないでくれ」と文子に頼んでいるのだ。
 女学生時代の文子
女学生時代の文子実際、未来の妻に宛てた手紙は、手紙魔だった龍之介の書簡の中でも特別の位置をしめている。彼の手紙の特色だった文人調のひねった筆致を捨て、彼はただ自分の気持ちをそのまま文章にしているのだ。いずれも、静かな愛情に溢れた美しい手紙になっている。
二人は結婚した。結婚したものの、当初は文子が東京田端の芥川家に、龍之介は海軍機関学校教官として横須加に別れ住んでいた。二ヶ月ほどして、龍之介は、文子と伯母を呼び寄せて鎌倉で新居を持つことになる。27才の彼は、機関学校の月給百円のほかに原稿料収入が月に百円ほどあったから(ほかに毎日新聞社の社友としての謝礼月50円が加わる)、同年配の仲間よりもはるかに豊かな新婚生活を送ることが出来た。
この鎌倉で暮らした一年あまりが、龍之介の生涯で最も幸福な時代だったといわれる。この一年間は、創作の面でも充実し、「枯野抄」、「地獄変」など優れた作品を次々に発表している。だが、文子との生活は、必ずしも彼を満足させなかった。
結婚前には、「何よりも早く一緒になって仲良くくらしましょう そうしてそれを楽しみに力強く生きましょう」と書き送って文子との新生活を待ち望んでいた龍之介だったが、実際結婚してみると失望することの方が多かった。
彼は挙式の前日に松岡譲に宛てて「僕は明二日に結婚する・・・・これが僕の書いた唯一の結婚通知状だ」というハガキを出し、その四日後に同じ松岡に「新婚当時のくせに生活より芸術の方がどの位つよく僕をグラスプするかわからない」と書いている。
龍之介は最初文学などには無関心な文子の素直で穏和な人柄に惹かれていた。が、結婚してみると最初惹かれたその点に不満を感じるようになったのである。彼は恒藤恭宛の手紙で、結婚生活の内情を明かしている。気の利かない文子に向かって龍之介が莫迦と叱ると、彼女は「私莫迦よ」と意気地なく悲観してしまうという手紙である。
龍之介が結婚に失望したのは、彼の気心を知り尽くした「心きいた」伯母が傍らにいたからかもしれない。この伯母を彼は、新婚の妻に劣らず愛していたのである。
彼は結婚前、すでに文子への手紙で自分は文子と同じ程度に伯母を愛していると告げている。
ボクはすべて幸福な時に、一番不幸な事を考へま
す さうして万一不幸になった時の心の訓練をやって
見ます その一つは文ちやんがボクの所へ来なく
なる事ですよ。(そんな事があったらと思うだけで
す。理由も何もなく。)それから 伯母が死ぬ事で
す。この二つに出会っても ボクは取乱したくない
と思ふのですね。が、これが一番むづかしさうで
す。もし両方一しよに来たら、やり切れさうもあり
ません。
又、こんなものもある。
それからもう一つうれしかったのは、伯母が文ちや
んの正直なのに大へん感心してゐた事です。あとで
文ちやんから手紙が来た時などには、涙をこぼして
うれしがってゐました 正直な人間には 正直な人
間の心がすぐに通じるのです 不正直な世間がどう
する事も出来ないやうな心が、動かされるのです
僕も伯母と一しょに 僕たちの幸福をうれしく思ひ
ました。文ちやんも一しょに、うれしく思って下さ
い
龍之介は、文子から来る手紙を伯母には全部見せていたのである。普通、恋愛中は、お前しか愛する者はいないと誓うものだが、彼は文子と伯母を同じ程度に愛していると言っている。文子は、龍之介にとって、当初から相対化された存在だったのだ。
(女人から芸術的刺激を得たい)と願っていた彼の希望に、文子が応え得なかっことも不満の原因だったろう。結婚前から彼のところには文学少女や自称女流作家が訪ねてきていた。彼はこういう女たちを嫌悪し、文子がそれとは全く逆な女であることを喜んでいたのだが、実際に文子と暮らすようになってみると、芸術を解しない妻に不満を感じ始めたのだ。
龍之介は、文子とは違った芸術を解する、中身の濃い女を求めるようになった。そして「狂人の娘」と彼が呼ぶ秀しげ子と出会うことになるのである。
「或阿呆の一生」は、龍之介が本格的な自叙伝を書こうとして果たせず、とりあえず短い断章を寄せ集めて自伝に代えたものである。断章は51章に及んでいる。彼は、この51章を貼り合わせたら、芥川龍之介という人間の内面を描きうると考えたのだ。
だが、これらの断章は彼の外形を示しはしたが、その内面は空虚なまま残されている。
「或阿呆の一生」の末尾に、芥川龍之介を論じる批評家が必ず引用する有名な一節がある。
彼は「或阿呆の一生」を書き上げた後、偶然或古道具屋の店に剥製の白鳥のあるのを見つけた。それは頸を挙げて立っていたものの、黄ばんだ羽さえ虫に食われていた。彼は彼の一生を思い、涙や冷笑のこみ上げてくるのを感じた。
龍之介は、自分を羽毛で飾り立ててはいるものの、中身は空虚な剥製のような人間だと自認していたのである。
では、彼に欠落している中身とは何だろうか。
彼は、自分には思うところを思うがままに実行して憚らない志賀直哉、谷崎潤一郎、室生犀星らの強さが欠けていると考えていた。そしてゲーテの西東詩集に見られるような自然な知性を持たないと思っていた。
彼が実質を欠如した剥製のような人間だったとしたら、「或阿呆の一生」も51の断章を貼り合わせた剥製のような作品だった。このなかの女たちに関する記述も、レトリックがあるだけでほとんど中身がないのだ。
登場する女性は、妻以外に4人いる。
龍之介は仮名という形ですら彼女らの名前を記していないので、便宜上彼女らを「月光の女」「狂人の娘」「越し人」「青酸カリの女」と呼ぶとすれば、「月光の女」などは7年間も体の関係を続け、彼の最愛の女だったらしいのに、相手の素性や人柄については全く触れていないのだ。ただホテルの階段で偶然出会ったのが始まりだと述べているだけである。
それでも「狂人の娘」については、やや踏み込んだ説明をしている。
「二台の人力車は人気のない曇天の田舎道を走って行った。・・・・前の人力車に乗っているのは或狂人の娘だった。のみならず彼女の妹は嫉妬のために自殺していた」
この女には夫がいるという説明があり、「動物的本能ばかり強い彼女」という一節もあるから、二人が不倫の関係にあったことは明らかだ。が、その他はすべて曖昧にぼかされている。それも思わせぶりなぼかし方をしているのである。
例えば、上掲の引用の中に「のみならず彼女の妹は嫉妬のために自殺していた」とあるけれども、彼女は姉と龍之介を争って自殺したのか、龍之介とは無関係に自殺したのか明らかではない。
この狂人の娘は、「歯車」にも、「復讐の神」として登場する。この「復讐」の意味がまた、よく分からないのである。何に対する復讐なのだろうか。彼が不倫を犯したことに対する復讐なのか、それとも彼の人生全体対する復讐なのか。彼女は芥川龍之介の人生において一種象徴的な役割を与えられているらしいけれども、肝心のポイントが明かされていないのだ。
関係者の語るところによれば、「狂人の娘」は秀しげ子という歌人で、龍之介は文子と結婚した翌年の大正8年に、「十日会」という作家の集まりで顔を合わせている。秀しげ子は、高利貸しの父と芸者上がりの母の間に生まれ、劇場の電気技師をしている男の妻だったという。歌人という看板を掛けているが、実態は作家のあとを追い回すグルーピーだったようである。
龍之介は、最初、愁いを帯びた彼女に惹かれ、秀しげ子を「愁人」と呼んでいる。これと同じ頃に、龍之介は「月光の女」とも交渉を開始している。「月光の女」は、何時会っても月の光の下にあるような感じを与えたというから、彼女も竜之介好みの憂いを帯びた静かな女だったのである。
龍之介は秀しげ子と知り合った翌年に、たった一度だけ性交渉を持った。その前後に、龍之介は恒藤恭にあてて、こんな手紙を書いている。
相不変女にも好く惚れる。惚れていないと寂しいのだね。惚れながらつくづく考えることは、惚れる本能が煩悩即菩提だという事・・・
ところが、愁いを帯びた高雅な歌人だと思っていた秀しげ子は、とんでもない女だった。龍之介は間もなく、彼女が弟子格にあたる南部修太郎や、友人の宇野浩二とも関係していることを知るようになる。この厚顔な女が、龍之介との一度だけの関係で妊娠したと主張しはじめるのである。
龍之介が一番恐れていたのは、秀しげ子の夫から姦通罪で告訴されはすまいかということだった。名の売れた作家や詩人に近づいてくる人妻は多く、そのため彼女らと深い関係になって、窮地に追い込まれる文学者は後を絶たなかった。北原白秋は姦通罪で告訴されて入獄しているし、当時、龍之介と人気を二分していた有島武郎は、女性の夫から脅迫されて軽井沢の別荘で女と心中している。
秀しげ子で懲りたのか、龍之介は女性からの誘惑には簡単に乗らないようになった。青根温泉に避暑に出かけたときに、彼はお藤さんという文学少女につきまとわれたが、「芥川龍之介窮したりといえども、まだ、お藤さんの誘惑にはのらんよ」と言って斥けたという実見談がある。
龍之介が「越し人」と呼んだ松村みね子は、歌人として又アイルランド文学の翻訳者として知られている。彼女は、龍之介が海軍機関学校の教官をしていた頃にファンレターを出して彼と知り合い、龍之介が病院に入院したときには見舞いに訪れたりしている。
その松村みね子と軽井沢で再会した彼は、彼女を自分と才力の上で格闘できる女だとして愛情を感じたが、相手が人妻だったから、深入りすることを避けた。
わが名はいかで惜しむべき
惜しむは君の名のみとよ
彼はこんな叙情詩を作って、危機を脱出するのだが、「名を惜しむ」という部分に、終生、名聞にこだわり続けた龍之介の素顔がちらりと現れている。
「青酸カリの女」は、龍之介の妻文子の親友平松麻素子で、彼女は「死にたがっていらっしゃるのですってね」と言って龍之介に近づいてきて、彼と心中の約束をするようになる。この約束は果たされずに終わったけれども、彼女は所持していた青酸カリの瓶を龍之介に渡し、「これさえあればお互いに力強いでしょう」と告げている。
 「青酸カリの女」平松麻素子
「青酸カリの女」平松麻素子私は芥川龍之介が睡眠薬で自殺したものと思っていたが、実は青酸カリによる自殺だった。彼は平松麻素子から貰った青酸カリを飲んだのである。
彼は、「月光の女」「狂人の娘」「越し人」「青酸カリの女」に関して、関係者の解説がなければとても理解できないような漠然としたことを書き連ねた後で、これもまた解説者を必要とする次のような断章を書いている。
夜はもう一度迫り出した。荒れ模様の海は薄明り
の中に絶えず水沫を打ち上げてゐた。彼はかう云ふ
空の下に彼の妻と二度目の結婚をした。それは彼等
には歓びだつた。が、同時に又苦しみだった。三人
の子は彼等と一しょに沖の稲妻を眺めてゐた。彼の
妻は一人の子を抱き、涙をこらえているらしかった
解説によれば、龍之介は死の前年に静養のため養父母の家を離れ、妻子を伴って鵠沼に移っている。彼が妻と二度目の結婚をしたのは、この鵠沼の借家でのことだった。
しかし、「二度目の結婚」とは、そもそも何を意味するのだろうか。冷たくなっていた夫婦関係が、復活したということだろうか。養父母に遠慮して暮らしていた田端の家を離れたことで、夫婦仲がよくなったというのなら、それまでの田端の家の重苦しさについて書かなければ意味が通じなくなる。
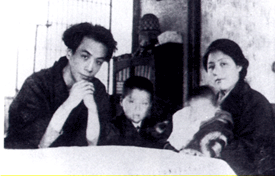 鵠沼にて。龍之介と文子
鵠沼にて。龍之介と文子暗示的で含みの多い「或阿呆の一生」を読んでいると、彼は一般読者の目を意識すると同時に、身近な人間の思惑を必要以上に強く意識していたのではないかという気もしてくる。
彼は「青酸カリの女」の章では、「彼は彼女に好意を持っていた。しかし恋愛は感じていなかった。のみならず彼女の体には指一本触らずにいたのだった」と断るだけでは足りずに、次のような二人の会話を書き加えている。
「プラトニック・スイサイド(注・自殺)ですね。」
「ダブル・プラトニック・スイサイド」
彼がこれほど二人の潔白だったことを強調するのは、帝国ホテルで平松麻素子と心中しようとするところを危うく取り押さえられるという「事件」を起こしていたからだろう。
彼は死に臨んでも、自分の行動について釈明につとめている。彼が「狂人の娘」をあしざまに罵ったのも、自分と相愛関係にあると公言している女の言い分を否定するためだったにちがいない。
最後に、こうした遺稿や遺書に対する辛口の批評があるので引用しておきたい。龍之介の旧友池崎忠孝の批評である。
「自殺者の心理・・・・レニエ・・・・不安・・・・マインレンデル・・・・非人間的・・・・美的嫌悪・・・・阿含経・・・・クライスト
・・・・女人・・・・人間獣・・・・エムぺドクレス……」
難解な語句の羅列する遺書を前にして、何か事あれか
しと待ち構へてゐた世間の呆然自失した顔は、今に至るも
尚ほ僕を苦笑させねば止まない。世間は意外に単純だ。終に自殺者の博識の前に甲を脱いで、
「世には、われわれ凡人のとても理解出来ない死がある。」
と、素直に観念する外はなかったらしい。不可知のものに対する驚異の情が宗教的
礼拝への道を開くことは素より君の理解するところだ。
君の自ら選んだ死が、君の「みづから神としたい欲望」の
上から観て、頗る策を得たものであったことは、僕の毫も
疑ふところでない。
若い頃に芥川龍之介の書簡集を読んだときには、彼の手紙の一つ一つが面白かった。手紙には、自作の俳句や短歌や、さらに河童の絵なども描きこまれ、それ自体が文学作品になっているように思われたからだ。
しかし、今度改めて書簡集に目を通してみたら、自作に関連した釈明や言い訳ばかりが、やたらに目についた。「開化の殺人」の執筆中に、彼は松岡譲にこんな手紙を書いている。
中央公論に探偵小説を書く約束をしたのでいやいやへんなものを書いている どうも才能をプロスティテュウトするような気がして心細くていけない
進藤純孝は、この手紙に注釈を付けて「おそらく書いているうちに嫌気のさしてきた芥川は、それでも書き上げねばならず、悪評を気にして、友人には、先まわりして、仕方なく『いやいやへんなものを』書いたのだと、釘をさしたのであろう」といっている。
彼はいくら金が欲しくても、久米正雄や菊池寛の真似をして通俗小説に筆を染めるようなことはしなかった。文士としての矜持を持っていたのである。だが、その彼も時に稿料目当てに執筆することがあり、そういうときには、売春婦が体を売るような気がすると弁解するのだ。
彼は自信のない作品を書いたときには、自ら失敗作であることを認める手紙を書き、友人や後輩作家に、これは多忙に追われた結果だとか、体調不良のためだとか釈明している。
松岡譲宛ての手紙には(この時、中央公論誌に頼まれて「偸盗」を執筆中)「深夜の愚痴」と題して、こんな短歌を書き付けたりしている。
中央公論はじまりしよりの駄作にも
なりなむとする小説あわれ
この種の彼の手紙を集めたら「釈明集」という本が一冊出来るほどなのだ。
ほかに書簡集を読んでいて注意を惹かれたのは、保養先から伯母や養母に出している手紙だった。
龍之介は絶えず手脈を取るほど自分の健康に気を遣っていながら、体をいたわる事をしなかった。特に問題なのが喫煙癖で、医者からいくら注意されても改めようとしていない。佐藤春夫の追憶記に次のような記事がある。
(話をしながら)彼は非常に盛んに煙草を吹かし大きな火鉢のぐるりには吸い殻が林立し気がついてみると部屋には煙が立ち込め、障子を開けておいたくらいでは間に合わなかった。煙草の箱は何度もすぐからになってしまった。どんなに少なく見積もってもその一晩中に彼は90本以上は吸っている。
健康を害した彼は、一人になって執筆に専念すべく、しばしば温泉や保養地に出かけている。だが、暫くすると伯母や養母に旅館へ来るように誘うのである。
彼が軽井沢から、そして修善寺から出した手紙には、まるでわがままな子どもが親に無理を言ってせがむような調子がある。
「今客がなくて閑静故、をばさん、おばあさん二人でちょっと遊びにこないか」
だが、伯母も養母もなかなか腰を上げようとしない。すると、彼は甥の葛巻義敏に宛てて、かんしゃく混じりに次のような手紙を書くのだ。
「をばさんやおばあさんに折角来いと言っても来ないで思い知れと言ってくれ。おみやげなどは汚れたシャツや猿またの外に何にも持って行かない」
彼が妻子ではなく、伯母と養母を呼び寄せようとしたのは、孝養のためと言うより、彼女らの前で子どもに帰り、二人の老女から叱られたり励まして貰ったりして、「安心」を得たかったのだろう。
こうして書簡集を眺めていると、芥川龍之介という作家が隠し持っていた幼さが透けて見えてくるのである。自作についてあれこれ釈明を繰り返したり、さびしくなると伯母や養母を呼び寄せたりするのは、彼がまだ完全に大人になりきっていないからなのだ。
ここで思い出すのは、広津和郎の(上半身は四十男のように老成して見えるが、下半身は七文半の足袋をはいている子どものように見えた)という芥川を評した言葉である。
佐藤春夫は、もっとハッキリしたことを言っている。
・・・・一種の発育不全のやうなといふより外に仕方がないそんなものを感じさせる人であった。思へばあのあまりに老成したやうな一面とこの発育不全的な純真とが芥川を悲劇的人物にしてゐたのかも知れない。
龍之介が発育不全の印象を与えるほど幼なく見えたとしたら、原因は生育環境にあるとしか思えない。やはり、伯母の影響が大きかったのである。
といっても、伯母が甘やかして彼を幼児化してしまったというのではない。伯母が、龍之介を世間の褒め者になるような「お利口さん」に育て上げたことを言っているのである。幼い時分からこましゃくれている子どもを「大人子供」というけれども、芥川龍之介は伯母の手で大人子供に躾られてしまったのだ。
あまり早く世間知を注入された人間は、子供の要素を後々まで残してしまう。抑圧された幼児性は、原型を保ったまま意識下に残存するのだ。
彼は四十男のような老成した表情を見せるかと思うと、「私の軽薄な根性」と言い「兎角おしゃべりなものだから口禍ばかり招きます」と言って、自身の青臭さを告白する。こうした青臭さと共に、彼は生母の愛を知らない人間の持つ欠落感を併せ持っていたのである。
実際、彼はデビュー当初から死ぬまで、一種不安な心持ちを抱いて生きていた。彼は傲慢に見えるほどの自信を口にすることがある。恒藤恭宛の書簡で彼は昂然とした調子で「材料に窮すると言うことはうそだと思う どんどん書かなければ材料だって出てきはしない 持っているうちに発酵期を通り過ぎると腐ってしまう 又書く材料に窮するような作家なら創作をしてもしかたがない」と言い放っている。
ところが「鼻」で認められた後、雑誌「新小説」から執筆依頼を受けると急に心配になり、友人たちにしきりに不安を訴えて激励して貰うだけでは気が済まず、漱石にまで救いを求める手紙を出している。漱石は、万事を飲み込んだ上で、龍之介の求めているような返事を書いてくれた。
大変紳経を悩ませてゐるやうに久米君も自分も書いて来たが、それは受合ひます。君の作物はちゃんと手腕がきまってゐるのです。決してある程度以下に書かこうとしても書けないからです。
龍之介が友人や後輩作家に釈明の手紙を書き、将来、ライバルになりそうな作家にラブレターのような手紙を出し、党派活動に精を出して「文壇処世術」と冷評されたりするのも、彼が少年のような不安な心性を抱えていたからだった。
だが、敵を作ることを恐れ、誰にもいい顔を見せていたら、荷を満載した舟のように絶えず荷崩れの心配をしていなければならない。彼は一人になると不安になるので、友人・後輩などに声をかけて「知己」を増やした。だが、知己を増やせば、それだけ積み荷が増え、心労の種も比例して増加するのである。
実際、彼の心は絶えず揺れ動いていた。はじめて開いて貰った出版記念会の席上、色紙に揮毫を求められた彼は、「本是山中人」と書いた。人々からもてはやされることを欲していながら、いざ、華やかな席に主賓として立つと、今度は、山中の静謐が欲しくなる。
彼は落ち着くことを求めながら、実際その状態を与えられると、平静を失い、ようやくかち得た安定を崩しにかかる。
こういう芥川龍之介のひととなりを冷厳に見ていたのは谷崎潤一郎だった。彼は、芥川龍之介を評して「この世に生活するに最も不向きな体質と気質とを持ち、而も最も多方面な才能に恵まれ、最も明晰な頭脳を備へた一つの魂」だったといっている。
芥川龍之介は海軍機関学校の教官だった頃に、少年のような純な気持ちを込めて二枚続きのハガキを松岡譲に出している。
ボクは今後頼まれて而して書く事はやめにしたさう
しなくっちや教師をして生活費を得てゐる甲斐がな
いその位なら作家商売をやる方が余程気が利いてゐ
る一年に一つ位書ければそれで本望だ場合によっち
や一年位韜晦するのもいいと思ってゐるそれから今
後新聞雑誌の文芸批評は一切縁を切つてよまない事
にするつもりだあれを読んで幾分でも影響を受けな
いにはあまりに僕は弱すぎるから。そうして少しづつでもしっかり進むつもりだ乗らな
いつもりでも調子に乗っていた自分をかえり見ると
醜悪絶類だこれから尻を落ちつける今気がついてよ
かったという気がするよ
彼はこの気持ちを何時までも持ち続け、教師生活を続行していればよかったのである。だが、彼は創作に専念するため、そして友人・後輩と文学談にふけるために、海軍機関学校を辞めてしまう。そして、ものの10年もしないうちに「売文糊口の難き」を思い、機関学校教官時代に戻りたいと嘆くようになるのである。
「近代日本文芸読本」の件で神経を悩ましていた頃、龍之介は親族間の問題でも心を悩ましていた。姉の夫が保険金詐欺の疑いをかけられて鉄道自殺してしまったのである。この時、実父とその後妻フユは死去してしまっていたから、姉のヒサにとって血を分けた肉親は龍之介しかいなかった。
こうなればヒサとしては、実弟の龍之介しか頼るものはいない。
こういう時に、龍之介に協力してくれるはずの妻の弟八洲は、喀血して療養中だった。かくて龍之介は病躯にむち打って、一人で後始末に飛び回らなければならなかった。
彼は以前に久保田万太郎に「東京に家庭を持っていると言うことは、纏まった大きな災難は来ないけれどもなしくづしに小さな家庭に関連した紛糾がたくさん起こってくる。さういふ細々したいろいろなごたごたは纏まった大きな災難よりも不幸だね」と語ったことがある。
龍之介は、問題の処理を一存で決める訳にはいかなかったから、義兄の後始末の件で「親族会議」を何度も開いている。親族会議をまとめるようなことは、彼の最も苦手とするところだった。
とうとう、龍之介は、実姉の一家を扶養する責任をも負うことになった。彼は南部修太郎に手紙で「又荷が一つ殖えたわけだ。神経衰弱治るの時なし。毎日いろいろな俗事に忙殺されている」とこぼしている。
さらに龍之介を悩ませたのは、お膝元の芥川家の老人たちだった。
主治医の下島勲が龍之介の健康を心配したのに対して、彼は「こちらのことは御心配なく。それよりもどうか老人たちのヒステリーをお鎮め下さい」と頼んでいる。
彼はまた別のところで、(老人のヒステリーに対抗するには、こちらもヒステリーになるがいいと教えられたので、今それを実践中です)というような手紙も書いている。
芥川家の老人たちは、なぜ彼を追いつめるほどのヒステリーを起こしたのか。
もちろん、肝心なことは部外者には分からない。だが、龍之介が一族の中心になるにつれて、養父母と伯母の力関係が微妙に変わってきたことは考えられる。それまで兄夫婦の厄介になって肩身の狭い思いをしてきた叔母は、龍之介が一家の主になったことで、兄夫婦より優位に立つようになり、それがトラブルの原因になったのかもしれない。
家の問題で神経をすり減らしていた彼は、「河童」のなかで家族制度に対して呪詛に近い批判を投げつけている。
親子夫婦兄弟などというものは悉く互いに苦しめ合うことを唯一の楽しみにして暮らしているのです。殊に家族制度というものは莫迦げている以上にも莫迦げているのです。
しかし龍之介ほど伯母や養父母を愛し、妻子の将来を心配した人間はいないのである。彼は暫く家を離れていると、しきりに家の「老人」たちを恋しがり、伯母などからの便りを心待ちにしている。彼にオアシスがあるとしたら、それは老人たちと妻子が同居する自分の家に他ならなかった。その家が彼には、地獄とも感じられたのである。
彼にとって、家と同様の関係にあったのが文壇で、彼は鴎外に倣って、文壇に冷笑を浴びせるような比喩小説をいくつも書いている。そして、文芸時評のようなものは一切読まないことにしたとか、毀誉ともに勘弁して貰って、原稿だけを書いていたいとか、文壇と没交渉で暮らしたいという趣旨の書簡を数多く書いている。
だが、彼の活力源になっていたのは、その文壇だったのである。彼は「秋」の世評がいいと知ると、とたんに舞い上がってこれからは「悟後の修行に努める」などといい、世評が悪いと打ちのめされたようになって、将来を悲観する。彼の喜びも悲しみも、文壇からの評価にかかっていたのだ。
だから、菊池寛が執筆に疲れた彼を見かねて、京都に来て大学の英文科教師になったらどうかと勧めたときも、断っている。若くして名声を得た作家は、名声を離れては生きていけないのである。
谷崎潤一郎が、芥川龍之介を評して「この世に生活するのに最も不向きな気質を持っていた」と言ったのは、ここのところだった。彼の生きる場は、家と文壇しかないのに、彼はどうしてもそこに落ち着くことができなかったのだ。
生前の龍之介を撮影した最後の写真を次に掲げるけれども、ここにはかっての秀麗な面影はどこにもない。あたかも彼の内面を物語るように、鋭く険しい表情をしている。
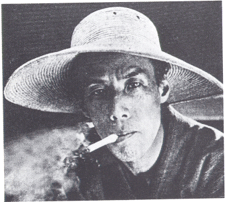
近頃目にした芥川論のうちで、記憶に残っているのは芥川龍之介の作品を「人生体験がなくても分かる」としているものだった。何気なく読み過ごしてしまったので、誰が書いたものだったか、何で読んだのか思い出せないのは残念だが、それを読んだときに私は全くその通りだと思ったのである。
旧制の中学校に入ってから、自宅にある15,6冊の改造社版「現代日本文学全集」を読み始めたけれども、面白そうなものをとびとびに拾い読みするだけで、熟読するというところまでいかなかった。
例えば、「志賀直哉集」を取り出して、「小僧の神様」とか「范の犯罪」とかの短編を読むことはあっても、とても「暗夜行路」を読む気にはなれない。冒頭に主人公がだらだらと芸者遊びをする場面が出てくるのだが、そんなものは中学生にとっては面白くもおかしくもないのだ。
比較的面白かったのは「徳富蘆花集」だったけれども、さすがに「不如帰」の様なものは古すぎて読む気がしないし、「みみずのたわごと」の世界にも入っていけなかった。
結局、全編を頭から尻尾まで残らず読むことが出来たのは「芥川龍之介集」一冊だけだったのだ。そして、その芥川の作品を中学卒業後、もう読む気がしなくなった。
何故読む気がしなくなったかと言えば、中学を出て大人社会に足を踏み出そうとする人間に、芥川の作品は何の力も貸してくれなかったからだ。
青年期に入った読者は、人生に対処する「大方針」を得ようとして、思想書や社会科学書を読みあさる。私も人並みにベルクソンやマルクス主義の本を読み、戦後派の文学に親しむようになったけれども、これらに比べると芥川作品は何とも物足りなかったのである。
芥川は、釈迦と老子を「東方の人」、イエスを「西方の人」と呼び、イエスについてかなり長文のエッセーを書いている。だが、彼は釈迦と老子については無知に近い程度の知識を持っているだけだったし、イエスに対する理解も哀れなほど浅薄に思えた。何しろ彼は、イエスをジャーナリストだなどといって喜んでいるのである。
彼は人生についても、社会についても、本質的な興味を持っていないように見える。小林秀雄が「彼の個性は人格となることを止めて一つの現象になった」と言ったのも、芥川にあるのは常識とそれを裏返した逆説だけで、独自の原理で動く人格にまで成長していないと見たからに違いない。
事実、社会を見る芥川の目は、お粗末だった。
関東大震災の直後に、「不逞朝鮮人」が井戸に毒薬を撒き、倒壊家屋に放火して回っているというデマが流れた。これを簡単に信じ込んだ芥川は、菊池寛に向かって「大火の犯人は朝鮮人だそうだ」と告げて、菊池から「『嘘だよ、君』と一喝」されている。それにも懲りずに、芥川が「なんでも不逞朝鮮人はボルシェビキの手先だそうだ」というと、「菊池は今度は眉を挙げると、『嘘さ、君。そんなことは』と叱りつけた。僕は又『へえ、それも嘘か』と忽ち自説(?)を撤回した」と書いている(芥川「大震雑記」)。
とはいっても、彼を中身の空っぽな空虚な人間だときめつけるのは酷に過ぎる。
彼は、広津和郎や佐藤春夫が指摘したように、老人の世間知と世に出る以前の少年の合理主義を併せ持った複合人間だったのである。彼は世間知と抱き合わせる形で、無垢な少年の心を保持していた。彼は頭の中に内外の知識を詰め込んでいたが、その心性においては、まだ少年のレベルに留まっていた。だから、青年期の諸々の欲求・・・・アイデンティティーの確立とか、世界観の取得とかいった欲求を持たずに済んだのだ。
芥川龍之介の作品は、ほとんどすべて大人の習慣的な見方・考え方を少年の鋭敏な目で裁断し転倒させる形式を取っている。彼は既成観念にとらわれない秀才の目で世事を眺める。その分析は透徹していて、曖昧な部分を残さない。
芥川は、リメイク版の「桃太郎」という作品を書いている。これを書くに当たって、彼は桃太郎一行の物欲の強さに焦点を合わせ、この視点を踏み外すことなく、一貫したストーリーの作品を書き上げる。
確かに「桃太郎」は、物質至上の臭いのするお伽噺で、桃太郎はキビ団子を餌にして犬・猿・キジを家来にするし、鬼ヶ島に乗り込むと「金・銀・珊瑚・綾錦」を山のように分捕って意気揚々と家に帰ってくる。
芥川によれば、桃太郎が鬼ヶ島征伐に出かけるのは、地道な仕事が嫌いで一攫千金をねらう「一発屋」だったからなのだ。鬼たちは本来平和愛好の種族で、鬼の婆さんは、日頃から孫に向かって人間のことをこう教えているくらいである。
「お前たちも悪戯をすると、人間の島へやってしま
ふよ。人間の島へやられた鬼はあの昔の酒頴童子の
やうに、きっと殺されてしまふのだからね。え、人
間といふものかい?人間といふものは角の生えな
い、生白い顔や手足をした、何ともいはれず気味の
悪いものだよ。おまけに又人間の女と来た日には、
その生白い顔や手足へ一面に鉛の粉をなすってゐる
のだよ。それだけならばまだ好いのだがね。男でも
女でも同じやうに、嘘はいふし、慾は深いし、焼餅
は焼くし、己惚は強いし、仲間同志殺し合ふし、火
はつけるし、泥棒はするし、手のつけやうのない毛
だものなのだよ……」
芥川龍之介は、桃の木は一万年に一度ずつ、赤ん坊のいる桃の実を落とすと説明してから「ああ、未来の天才はまだそれらの実の中に何人とも知らず眠っている」という言葉で、この皮肉な作品を終わりにしている。アメリカ映画「13日の金曜日」のような幕切れである。
この首尾一貫した明快な物の見方は、まさに少年のものではないだろうか。作品には、桃太郎の性格分析も帝国主義的行動様式への批判もない。これなら「人生経験を持たない」読者にも、ちゃんと分かるのだ。
私は今度、芥川龍之介全集に目を通すようになるまでは、概略、以上のような見方をしていたのだった。
ほこりをかぶっていた芥川龍之介全集を取り出して、未読の作品を拾い読みしながら、あわせて芥川に関する諸家の批評を読み始めたのは、6月に入ってからだった。そして、いくつかの芥川論を読んで知ったのは、芥川の優しさや無垢の愛について語る評家が昔からちゃんといたことにほかならなかった。
福田恒存は、芥川の「優情」を強調しているし、中村真一郎は彼の童話について次のように書いているのだ。
童話は、彼の魂の最も無垢な部分を盛ることのできた形式だった。彼はこれらの作品を残すことによって、恐らく小説だけだったら、作りだされたかも知れない、理知的な冷血的な怪物である彼の肖像に、生きいきとした暖かみと優しさを加えることができた。童話を読むと、宇野浩二氏が『芥川は悲しい、弱い男だつた』と云うような云い方で懐かしんでいるのが自然に感じられる。
童話のなかに芥川の素顔を見ていた同時代の作家は、宇野浩二だけではなかったし、時を隔てて現代においても、芥川的エッセンスを童話の中に認める研究者が少なくない。
そして、観察するにどうやら芥川の繊細な優しさや「本来の育ちのよさと高貴な性格」(中村真一郎)について語るのは、都会的なセンスを持った作家や批評家に多いらしのである。
若い頃の私は、芥川作品に思想的なバックボーンやモラルが欠けている点を不満としていたのだが、それは無粋な田舎者の無い物ねだりなのであった。都会的な感覚を持った読者からすれば、作家がそうしたものを作品に持ち込むのは邪道であって、作家個人の思想やモラルは、暗喩や象徴によってそれとなく語るべきなのだ。
私は新しい見方を教えられたような気がした。が、童話を読んでも依然として芥川に関する疑問はそのまま消えることなく残った。
「蜘蛛の糸」は、極楽を散歩していた釈迦が、蓮の葉の間から地獄の血の池を見下ろし、そこにカンダタの姿を発見するところからはじまる。カンダタは、生きていた頃、蜘蛛を踏みつぶすことを思いとどまったことがある。それが、この亡者の生前に残した唯一の善行だったけれども、釈迦はそれを思い出して彼を地獄から救い出してやろうとするのだ。
そこで、釈迦は一筋の蜘蛛の糸を垂らしてやるのだが、彼がこうした行動に出たのは全くの思いつきからだった。釈迦が「蓮の葉の間から」地獄の血の池に浮き沈みしている亡者を発見するのも、「ふと下の容子」を眺めたからだし、蜘蛛の糸を垂らしてやったのも、とっさの着想であり、すべては「偶発事」に過ぎなかったのである。
極楽目指して蜘蛛の糸を登り始めたカンダタは、糸を独占しようとして、血の池に墜落してしまう。
御釈迦様は極楽の蓮池のふちに立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがてカンダタが血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、又ぶらぶらお歩きにになり始めました。
釈迦は悲しそうな顔をしただけで、ぶらぶら歩きを再開しカンダタを救うことを断念してしまう。結果として、釈迦がカンダタのためにしたことは、彼に極楽に来る資格があるかどうかをテストすることだけであり、それに合格しなかった彼は、あっさり見捨てられてしまうのだ。
今日では、「蜘蛛の糸」の原典が明らかになっている。鈴木大拙訳述の「因果の小車」という冊子がそれで、原典では、釈迦は地獄の底まで入ってカンダタとその仲間たちを救出することになっている。
「因果の小車」は、「人間には誰にも悟りの芽があり、地獄の底でうごめく亡者もすべて仏性を備えている」と説く。蜘蛛の糸は、極悪人の心にも存する一筋の求道の志を意味し、自分一人のために悟りを得ようとしたら、その糸はぷつりと断たれて救いは永久に得られないとしている。
だが、芥川は釈迦もカンダタも矮小化してしまう。彼は地獄と極楽を峻別した上で、悪人はそのエゴの故に永遠に地獄に留まるしかないと突き放してしまう。
芥川は、釈迦にカンダタを見捨てさせたけれども、「杜子春」では仙人をして、偶然知り合った若者を最後まで見守り続けさせている。杜子春の人生は、ハピーエンドをもって終わるのである。しかし、本来これは逆にすべきではないか。
釈迦の本願とするところは衆生済度にあるのだから、極楽でぶらぶら歩きなどをしている暇はないはずである。一方、仙人の方は、世事を超越した傍観者であり、人間世を自然現象のように眺めているだけだ。仙人には、苦悩する民衆を救済する必要も義務もない。彼は悠々と生きることによって、あくせく生きる俗人どもへの「生き見本」になっていればいいのである。
「蜘蛛の糸」は、お子様向けの童話だから、大乗仏教の趣旨から離れ、勧善懲悪のお話にしてしまったのかもしれない。では、「西方の人」はどうだろうか。芥川は福音書を愛読し、自殺した枕元に聖書を置いていたほどだが、彼はイエスをどう見ていたのだろうか。
イエスについても、彼はその一部分しか捉えていなかったと思わざるを得ないのだ。
「西方の人」は、福音書に出てくる人物や事件について芥川式の論評を加えたものである。例えば、イエスの父ヨゼフについては「ヨゼフはどう贔屓目に見ても、畢竟余計者の第一人だった」と評している。昔これを読んだときには、イエスをジャーナリストと呼んだり、ヨゼフを余計者と呼んだりする芥川式の気の利いた言い回しに興味を感じたものの、あまりいい感じを受けなかった。
だが、今度あらためてこれを読み直してみると、彼はこのなかでかなり本心を吐露している。芥川の見るところでは、人間には「永遠に守らんとする」意志と「永遠に超えんとする」意志があり、前者の意志を体現するのが母マリアであり、後者を体現するのがイエスだとしている。
この二つの意志は、人間の内部にあるばかりではない、「永遠に守らんとするもの」は、炉に燃える火や畠の野菜や素焼きの瓶や頑丈に出来た腰掛けのなかにもあるし、「永遠に超えんとするもの」は風や旗、蝋燭の火に焼かれる蛾のなかにもある。現世は、この二つの力の組み合わせによって成り立っている。
マリアは現存の社会の中で家庭を営み、子供を育てる女性の安全志向・保守志向を代表し、イエスはそうした秩序を桎梏と感じて永遠の世界に飛躍しようとする超越願望を代表している。そして現実のイエスは、うちにマリア的なものをかかえたまま超越願望に身を焼いた火蛾のような男だったと、芥川は見ているのである(「クリストは彼自身に、・・・・彼自身のうちのマリアに反逆している」)
芥川が「西方の人」のなかでくどいほど強調しているのは、昔から無数のイエスが出現して既成秩序に戦いを挑んできたということだった。彼らを反逆に駆り立てるのは、理性や良心ではなく、デーモンと呼ぶしかない「あるもの」のうながしによる。
そして彼らは等しく挫折し、それぞれの十字架にかけられる。キリストは、人類の歴史が生み出してきた無数のキリスト的人間の一人に過ぎない。彼はこう力説しながら、もちろん自分をキリスト的人間の一人だと思っていた。
「内なるマリアに反逆したイエス」という構図は、「内なる伯母に反逆した龍之介」という構図に置き換えることができる。マリアの持っていた「永遠に守らんとする」ための知恵は、芥川が伯母から仕込まれた老人の世間智とおなじものであり、イエスの「永遠に超えんとする」意志は芥川の内部にあった少年的合理主義と同じだったように見える。つまり「クリストは、彼自身のうちのマリアに反逆している」という「西方の人」の一節は、伯母的な世間智に反逆する少年龍之介をあらわしていると読み解くことが出来るのである。実際、芥川は伯母とマリアを頭の中で等置していたかもしれないのだ。
芥川は、人間の内部にあるマリア的要素とイエス的要素の対立を、ハートと頭脳の対立というふうに言い換えてもいる。彼は国木田独歩について、こう書く。
独歩は鋭い頭脳を持ってゐた。同時に又柔かい心臓を持ってゐた。しかもそれ等は独歩の中に不幸にも調和を失ってゐた。従って彼は悲劇的だった。(略) 彼は鋭い頭脳の為に地上を見ずにはゐられないながら、やはり柔かい心臓の為に天上を見ずにもゐられなかった。
芥川も、その「鋭い頭脳の為に」地上のさまざまの桎梏を眺め、これに従って生きた。だが、彼の「柔らかい心臓」は、世のしがらみを離れて、自由に生きることを求めていたのである。
芥川の悲劇は、「生活的宦官」として頭を使えば使うほど、世の煩累を比例して殖やしてしまったことだった。下町の風習に従って親戚とのつきあいを疎漏なく実行したために、彼は養家の三人の老人の外に実姉の家族と実家の義弟の面倒を見なければならなくなった。
文壇に出てからは、同輩・後輩の作家との関係を大事にしたために、自然主義系の先輩作家から憎まれ、仲間からも疑惑の目で見られることになった。
彼は空高く飛翔することを求めながら、ハエ取り紙に捉えられたハエのように現世に捕捉されて身動きが取れなかった。彼は「人生の悲劇の第一幕は親子となったことに始まっている」(「侏儒の言葉」)と書き込みながら、親兄弟や妻子を捨てることは無論のこと、距離を置いて生きることすら出来なかった。芥川に出来ることは、「みんな死んでしまえ」とヒステリックに呟くことだけだった。彼は、しばしば肉親の死を願ったことを書き記している。関東大震災のとき、彼の家は被害に遭わなかったが、親戚は家を焼かれた。
彼の姉や異母弟はいづれも家を焼かれてゐた。
しかし彼の姉の夫は偽証罪を犯した為に執行猶予中
の体だった。
「誰も彼も死んでしまへぼ善い。」
彼は焼け跡にたたずんだまま、しみじみかう思わずに
はゐられなかった。
家族関係・親戚関係に悩まされつづけた彼が描くユートピアとは、次のようなものだった。
唯此処に住んでゐれば、両親は子供の成人と共に
必ず息を引取るのである。それから男女の兄弟は
たとひ悪人に生まれるにもしろ、莫迦には決して
生まれない結果、少しも迷惑を、かけ合はないの
である。
自分を「永遠に超えんとする」願望にとりつかれている点でイエスに等しい人間と考えていたにしては、芥川の言葉はあまりにも弱々しい。泣き言に近い響きがある。鴎外も複雑な家族関係に悩み、文壇では終始居心地の悪さを感じていたけれども、決してこんな弱音を吐いていない。
鴎外の作品には、現世を俯瞰するような趣きがある。「永遠に超えんとする」ことに成功しているという感触があるのだ。だからこそ、芥川龍之介も、芥川と同じ体質を備えた三島由紀夫も、鴎外を創作上の師と仰いだのだが、鴎外が芥川・三島と決定的に異なる点は、明治社会の矛盾や不合理を鋭く批判しつつも現世を総体として受容していたことだった。
鴎外は生きることを業苦と感じながら、この世はこうしたものだと、現世を全的に受け入れていた。人はそれを「鴎外の諦念」と呼ぶのだけれども、彼は現世を全的に受容することによって、現世を俯瞰する立場を獲得したのだった。釈迦もイエスも、「現世の全的受容による現世からの超越」を成し遂げた存在であり、鴎外もこの路線をすすんで鴎外的視点を確立したのである。
芥川も三島も、鴎外に深い敬意を捧げながら、現世に臨む鴎外の姿勢を学ぶことをしなかった。ここに彼らの悲劇の根があったのである。
芥川龍之介がなぜ自殺を選んだのか、その理由についてはいろいろな説がある。芥川と親しかった小穴隆一は、「狂人の娘」が原因だろうと推測しているし、菊池寛はいかにも実際家らしく「原因は経済的な問題ではないか」と言っている。
部外者の目には、さまざまな心労に押しつぶされて、芥川が大量の睡眠薬を服用しなければ眠れないようになり、その結果、持病の痔や胃病を悪化させて生きる気力・体力をなくしてしまったことが原因であるように見える。
こんど全集を読んでいて注意を惹かれたのは、「闇中問答」のなかの次の一節だった(「闇中問答」も、遺稿の一つ)。
僕の意識しているのは僕の魂の一部分だけだ。僕の意識していない部分は、――僕の魂のアフリカはどこまでも茫々と広がっている。僕はそれを恐れているのだ。光の中には怪物は棲まない。しかし無辺の闇の中には何かがまだ眠っている。
これを三島由紀夫の「荒野より」の一節と比較してみよう。「荒野より」は、死の三年あまり前に三島が発表した短編で、文中に「あいつ」としてあるのは、三島邸に不意に闖入した青年を指している。
それは私の心の都会を取り囲んでいる広大な荒野である。私の心の一部にはちがいないが、地図には誌されぬ未開拓の荒れ果てた地方である。そこは見渡すかぎり荒涼としており、繁る樹木もなければ生い立つ草花もない。ところどころに露出した岩の上を風が吹きすぎ、砂でかすかに岩のおもてをまぶして、又運び去る。
私はその荒野の所在を知りながら、ついぞ足を向けずにいるが、いつかそこを訪れたことがあり、又いつか再び、訪れなければならぬことを知っている。明らかに、あいつはその荒野から来たのである
芥川の生存してた頃のアフリカは、猛獣の支配する人跡未踏の「暗黒大陸」とされていた。芥川は、自らの魂がそうした暗黒の世界に取り巻かれていると感じ、三島由紀夫も「心の都会」を荒涼とした原野が取り囲んでいると感じていた。これは、二人の創作活動が意識の一部分だけを使ってなされ、その他の部分が手つかずのまま放置されていたことを意味するのではなかろうか。
志賀直哉や谷崎潤一郎が、全人格を活動させて創作をしていたとすれば、芥川は自我の一部分しか使っていなかった。彼は、作品の供給源を「魂」そのものに求めないで、その一画を囲い込み、そこで人工培養されたものだけを利用していた。そのために、「魂」はジャングルみたいに荒れ果ててしまったのではないか。
三島も劇的効果を計算した作品ばかりを書いているうちに、「心」の一部分はネオンサインの輝く都会のようになったけれど、他の部分は荒涼とした原野と化してしまった。
だが、「魂」や「心」を一定の広がりを持った領土のようなものと考えるのは錯覚でしかない。彼らの「自我荒廃感」なるものは、意識を偽現実の創造だけに使って来たことに対する劫罰だったのではないかと思われる。
芥川は創作力を枯渇させていたのではなかった。「魂」の全部、感受性の総体を駆動させた創作活動をしてこなかったから、書くことに喜びを感じなくなったのだ。
昔、芥川作品を読んだときには、まず、その銀細工のような文章に感心した。次に、情景描写の見事なことに感嘆した。佐藤春夫は芥川の文章を「金石文」と表現しているし、菊池寛は銀のピンセットで言葉を並べて行くようだと言っている。そしてその金属的で精緻な文章でつづられた叙景の鮮やかさが、類を見ないように思われたのだった。
しかし、今度、芥川龍之介全集を通読してみて、一点一画もおろそかにしない彼の文章が、マイナスになっているように感じた。彼が長編小説のほとんどすべてを中断したまま投げ出してしまったのも、あの研ぎすまされた文体のためではなかろうか。ああした文章で長編を書こうとするのは、シルクハットに蝶ネクタイという正装でヒマラヤに登ろうとするようなものなのだ。
文体の問題よりも、もっと引っかかったのは彼の鮮やかな情景描写だった。
どの作品を読んでも、それぞれの場面にふさわしい背景が用意されていて、まるで芝居の書き割りを見るようなのだ。だから、風景を描写しても、自然の大きな広がりが感じられない。人工的に設営された舞台上の装置を見るような印象を受ける。
この舞台上に並べられた「いかにもそれらしい」小道具は、芥川固有の俳句的感覚によって用意されたかのように見える。それもあるかも知れない。けれど、中心になっているのは彼が読書から得た素材なのである。
博覧強記の彼は、ある場面を描こうとすると、即座にこれまでに読んだ本から得た関連イメージが頭に浮かんで来るのだ。これを作品内の各所に配置すれば、現実以上に本物らしい場景が生まれる。
つまり、芥川が描くのは、既製の部品を組み立ててこしらえたプラモデル式の現実なのである。模型的な現実だからこそ、情景はあんなにも鮮明に読者の目に映るのだ。
彼は体験を通してものの見方を学んだのではなく、本を通して人間や人生の見方を学んだと告白している。
人生を知るために街頭の行人を眺めなかった。寧ろ行人を眺めるために本の中の人生を知ろうとした(『大導寺信輔の半生』)
彼が本から学んだのは人間や人生の見方ばかりでなかった。風景の見方や文章の書き方も本から学んだのである。
芥川は、5,6才の頃、大森の海岸に行って、はじめて海を見ている。海の色は、絵本にあるように青くはなかった。バケツの錆のような代赭色をしていた。それで、彼は養母が買ってくれた浦島太郎の絵本に水絵具で彩色を施すに当たって、海の色を代赭色にしたのだった。
この絵を見た養母は、「海の色は可笑しいねえ。なぜ、青い色に塗らなかったの?」と反問し、龍之介と以下のような問答を交わしている。
「海はかう云ふ色なんだもの」
「代赭色の海なんぞあるものかね」
「大森の海は代赭色ぢやないの?」
「大森の海だってまっ青だあね」
「ううん、丁度こんな色をしてゐた」母は彼(龍之介)の強情さ加減に驚嘆を交へた微笑を洩らし
た。が、どんなに説明しても、―― いや、癇癪を起
して彼の「浦島太郎」を引き裂いた後さへ、この疑
ふ余地のない代繚色の海だけは信じなかった。……
子供の頃にこういう体験をした芥川は、しかし作家になってから海の色を代赭色に描こうとはしなかった。
成人した彼が飽くまで代赭色の海を描くことに固執し、自分の実感に忠実な作品を書いていたら、芥川の作家的コースは変わったものになったかもしれない。彼は「海の色は可笑しいねえ。なぜ、青い色に塗らなかったの?」という声なき声に敏感すぎる結果、自分の実感や感動に目をつぶって、いかにもそれらしい場景を量産してきたのである。表現法を本から学んだ彼にとっては、読者の既成観念に合わせて海を青く描く方が楽だったのだ。
読者の意表をつく物語性の濃い小説や、通説を裏返した逆説的な作品を量産するようになったのも、彼の頭に読書から得た既製世界・常識的世界が牢固として居座っていたためだ。これを母胎にしていたから、これをひっくり返して意表をつく物語、逆説的な作品を制作することが可能になったのである。
「侏儒の言葉」には、「貝原益軒」という章がある。
大儒貝原益軒が、乗合船に乗ったら、乗客相手に古今の学芸を論じる若い書生がいた。船が岸について、乗客が姓名を名乗りあったときに、書生は初めて益軒が同乗していたことに気づいて自分の言動を深く恥じたという。芥川は、この話を小学校時代に教えられたのだが、これに関連して芥川は次のように書くのだ。
当時のわたしはこの逸事の中に謙譲の美徳を発見
した。少くとも発見する為に努力したことは事実で
ある。しかし今は不幸にも寸毫の教訓さへ発見出来
ない。この逸事の今のわたしにも多少の興味を与へ
るは僅かに下のやうに考へるからである。一無言に終始した益軒の侮蔑は如何に辛辣を極めてい
たか!
二書生の恥じるのを欣んだ同船の客の喝采は如何に
俗悪を極めていたか!
三益軒の知らぬ新時代の精神は年少の書生の放論の
中にも如何に溌剌と鼓動していたか!
ここには、芥川龍之介の発想法がくっきりと浮かび上がっている。
彼の発想は、この挿話を謙譲の美徳とする既成観念を母胎とし、それを斜めから眺めたり、後ろから眺めたりすることから生まれている。だが、そうした枠を離れてみれば、これはなかなか面白い話なのだ。益軒は青臭い書生の大言壮語を、穏やかな表情で聞いていたのだ。その穏やかな眼差しには、若者をいたわる老年の目もあったろうし、新時代の見方に対する純粋な興味もあったに違いないのである。
貝原益軒に反発した芥川の感想は、小学校から中学校に進んだ少年のそれを思わせる。一応、気が利いているけれど、とても成熟した人間の発想とは思えない。
彼の未熟さは、徒然草への感想にも見られる。
わたしは度たびかう言はれてゐる。――「つれづ
れ草などは定めしお好きでせう?」しかし不幸にも
「つれづれ草」などは未嘗(いまだかつて)
愛読したことはない。正直な所を白状すれば「つれづれ草」の名高いのもわ
たしには殆ど不可解である。中学程度の教科書に便
利であることは認めるにもしろ。
徒然草は、旧制中学校の国語教科書には必ず載っていた教材で、反語や逆説の散在する点で芥川の作品に似ていなくもない。だが、これは達人の書であって、これを評価できないようだったら、その鑑識眼を疑われても仕方がないというような質の本なのである。
芥川は恐らく、徒然草の表層に浮遊する「中学程度の」反語や逆説に目をとめ、同類相反発する感情を覚えたと思われる。だが、反語や逆説は表層のことであって、その下には、兼好法師の透徹した目が随所に輝いている。兼好は、近代人というより未来人の感覚を持って生きていた老熟の大人だったのだ。
芥川同様、若くして死んだ中島敦は、「弟子」という作品で悠揚迫らぬ孔子の人間性を描いている。中島には孔子の大を虚心に受け入れる感受性があったが、芥川にはその種の感覚がなかったように見える。芥川の手にかかると、イエスも釈迦も妙にいじけた矮小な存在になってしまうのだ。イエスや釈迦ばかりではない、大石内蔵助は凡庸な常識人と化し、乃木希典も偏執的な異常性格者になってしまう。
だが、これも魂のアフリカを生んでしまうような芥川の手法のためだった。彼はそれらしい小道具を並べて模擬現実をこしらえ、その中で矮小化された人間を動かす作品を書いてきたから、やがて壁にぶつかり、書くことに喜びを感じないようになったのである。芥川の自殺の原因はいろいろ考えられるけれども、決定的な原因はやはり彼の文学にあったとするしかないかもしれない。
芥川の創作上の師だった鴎外も、「即興詩人」の頃までは文章に念を入れて、規格通りの小綺麗な作品を書いていた。それが四十代になって、「何をどのように書いてもいいのだ」と居直ってからは、優れた作品を次々に発表するようになる。「豊熟の時代」がはじまったのである。
芥川も、もう少し辛抱して彼が当面していた危機を乗り切ったら、鴎外の塁に迫るような作品を書くようになったかもしれない。そうした可能性を含めての上なら、明治以降の作家の序列を、1位鴎外・2位漱石・3位芥川龍之介とすることに異論はない。実際、同時代の作家と比べると、芥川の作品は一頭地を抜いているのだから。
最後に、自殺直前の芥川について記した吉田精一「芥川龍之介」の一節を紹介する。
その夜(注:昭和2年7月23日)、伯母の考へでは午後十時年頃、彼は伯母の枕許に来た。「煙草をとりに来た」と云って。そして二十四日、伯母によれば午前一時か一時半頃、彼は又伯母の枕もとに来て、一枚の短冊を渡していった。「伯母さんこれをあしたのあさ下島さんに渡して下さい。先生が来た時、僕がまだ寝てゐるかも知れないが、寝てゐる僕を起こさずに置いて、そのまままだ寝てゐるからと云ってわたして下さい。」
これが彼の最後の言葉となった。
彼は青酸カリを飲む前に、別れを告げるため、「煙草をとりに来た」という口実で伯母の部屋を訪れている。だが、彼はそれだけでは気が済まず、薬を飲む直前になって別の口実を作って伯母の寝室を訪れているのだ。芥川にとっては、やはり伯母の存在が一番大きかったのである。