「老人力」ブームは弱者の居直りか
不毛な努力主義
老人が「早く惚けた方が勝ち」とうそぶくのを時々耳にすることがある。誰も、本心からボケることを望んでいる者はいないのだから、これは避けようとしても避けることのできない老化現象への老人たちの居直り発言である。
この頃、老境に入った人たちが「老人力」という言葉を口にするようになった。これも、弱者の居直りという心理が背景になっているだろう。だが、惚けることによって、新たに一種の「力」を獲得するという事実は確かにあるのだ。だからこそ、「老人力」に関する本が売れたり、中年の男女までもこの言葉に共感して、何かと話題にしたりするのである。
年をとれば、体力も衰え、記憶力も鈍ってくる。人間としての総合力が確実に落ちてくるのだ。他面、若い頃の無駄な力み方が抜けて、そこから回収された力が新たなエネルギーとして老人に付加されるという現象も出てくる。
「現役」の頃には、「気配り」と称してあちこちに注意を払っていた。兵士が戦線に沿って広く散開するように、エネルギーを各所に広く配置して競争社会を生き抜いてきた。このエネルギーの平面的展開には、無駄が多かった。だから、退職して、こうした気配りをしなくなれば、老化によって低下するエネルギーを補って余りある力が生まれてくるのである。足し算、引き算を合算すると、プラスの方が多くなるのだ。そして努力主義を止めることによって、さらに大きなエネルギーが付加される。
現役の頃は、気配りによって背後を固めながら、「仕事」に全力を挙げて来た。人間は自分が実現しようとする未来のために、貴重な現在を犠牲にする動物である。「未来実現」に対して効果がないと思えば、日々の努力を無価値だったと否定してしまう。
かくて、人は努力とは未来のために、イヤな仕事、苦痛を伴う仕事に専念することだと考えるようになる。不毛の努力主義。こうした実りなき努力に向けて投入されていた夥しいエネルギーが、現役を退くことによって回収され、老人に還付される。
問題は、回収され還付されたエネルギーを、どう使うかということである。「生涯現役」と称して現役の頃の延長上で仕事をしていたのでは意味がない。
反努力主義
イヤなことを我慢してやるのが努力なのではない。本当の努力とは、結果を考えず、打算的にもならず、好きなことを一生懸命やることなのだ。「バカバット・ギーター」というバラモン教の聖典によれば、よく生きるための唯一最良の方法とは、結果を考えないで努力することなのだそうである。
老人は「不毛な努力主義」を放棄する。しかし、努力しなくなると言うのではない。楽しいことを見つけて、楽しく努力するようになるのだ。努力のないところに達成感はなく、達成感のないところに喜びはないのだから。
昔、何かの雑誌に現役を退いた著名人たちが、老後を何をして過ごしているかという特集記事があった。印象的だったのは「高等数学」をやっているという回答が多かったことだ。彼らの多くは、会社重役や経営者で、経済学部や法学部を出ている者が多かったにもかかわらず、畑違いの数学の勉強に精出している。
反対に、工学部を出た技術系の重役が、退職後、世界文学全集を一冊ずつ読んでいるという回答もあった。高等数学を解く、世界文学全集を読む、いずれにしろ、なにがしかの努力が必要である。こうした努力を伴う趣味・道楽を持続することで、充実した老後が約束される。努力することによって、エネルギーに一定の志向性を与えなければ、引退後の生活を安定させることはできないのだ。
老いることは、生まれ変わること
人は未熟な青年期に自分の一生を決めなければならない。そのため、自分の性格に合わない仕事を選んでしまったり、中年になって新たに天職と呼ぶべきものを発見したりする。女性の場合は、思い違いをして間違った結婚をしてしまったりする。老後は第二の人生であり、、こうした人々にやり直しのチャンスを与えてくれるのだ。
私が老いるということは、古い自分から解放されることであり、新しい人生を歩き出すことだと悟ったのは、退職後、読む本ががらりと変わってしまったからだった。私はそれまで、自分は文人趣味の人間だと思いこみ、中国の古典や禅宗関係の本を集め、歴史書や江戸から明治にかけての日本思想、日本文学の本を読んでいた。退職して暇ができたら読もうと考えて買い込んだ本も、すべてこうした文人趣味に関連したものだった。
だが、退職2年後に、行きつけの古本屋から翻訳物のミステリーを買ってきて読んだのがきっかけで、明けても暮れても、外国産ミステリーを読むようになってしまったのだ。翻訳物のミステリーなら、古本屋で一冊100円で売っている(文庫本)。これをまとめて数十冊、段ボール箱で買ってきて、暇があれば読むようになったのである。それまでは、ミステリーなど、作り物の最たるものだと見向きもしなかったのに。
本格的にバイクを乗り回すようになったのも退職後のことだし、パソコンをいじるようになったのも退職後である。現役の頃には、考えられなかったような変化だ。73にもなる老人が、パソコンをやり、ホームページを開設しているというので、先日、週刊のローカル紙に下記のような記事が載ったくらいである。
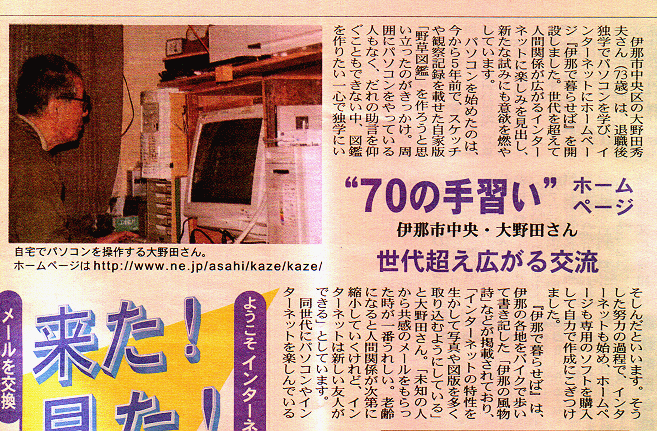 左の写真が筆者
左の写真が筆者
この記事の見出しは「70の手習い」となっている。老年を「新生」の時代とすれば、年をとってからやることは、すべて手習いにほかならない。夫が定年退職するのを待って離婚に踏み切る妻たちも、新たに独居自立の生活を学習しつつ生きて行くのだ。
今や私は、これまでの人生を裏返ししたような生き方をしている。若い頃に年寄りじみた生き方をしていた人間が、年をとって逆に「若いもん」がするようなことをやっているのだ。「人間としての全体性」を回復することを念願としてきたにもかかわらず、私は生活の中に現代というものを取り込むことをして来なかった。私は今、これまでの人生で欠けていたものを補充し、青春を生き直おそうとしているのである。