羨望の地(2)
東京で生まれ、東京で暮らしているOLには、「田舎は怖い」という感想を漏らす向きがあるそうだ。田舎は人が少なく、淋しいところだからというのが、その理由である。
だが、そうした「怖いくらいに淋しい場所」に惹かれる人間もある。例えば、下図を見ていただきたい。山懐に見かけるこのような場所は、人によっては「怖い」と感じるかもしれない。が、私などには魅力あふれる場所と映るのだ。
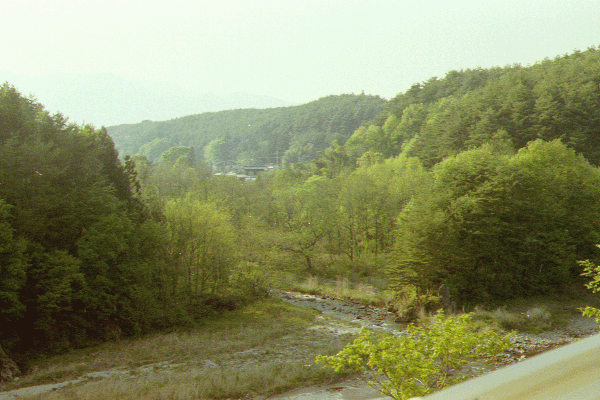
下図のような場所に出ると、「恐怖感」も薄らぐに違いない。山裾にあって、平地に向かって開けてた地形だからだ。この画像はスナップ写真を縮小したものなので、道路や民家が確認できなくなっている。これを拡大すれば数軒の民家とそれを繋ぐ道路が認められる。

下図はその道路。

平地を目指して降りて行くと、林・人家・水田・原野の入り交じった風景に変わる。このあたりでは変化に富んだ、細部まで美しい景観に出会うことが出来る。

互に適当な間隔をとって点在する「散村」の形態で家数が増えてくるのだ。それらの更に降りて行けば、人家の数も増えてくる。しかし軒を連ねるという形ではなく、相家は周辺に防風用の立木を巡らすのが一般的で、その様相は下図によっても明らかだろう。

更に下って行くと、段丘の先端部に出る。段丘先端部は従来採草地として放置されて人家は少なかったが、戦後、ここに家を建てる人々が増えてきた。
次の二枚は段丘先端部に散在する家々を撮影したもので、この直ぐ下が天竜川流域の平坦部になる。


段丘を下って平地に出ると、道幅も広くなり「里」という感じが濃くなる。

山麓から徐々に下に降りて行く途中、下図のような民家を見かけた。家の正面は舗装された道路に面している。が、裏に回ると、畑や水田が一段ずつ低くなる雛壇式の景観に面しており、それを眺めながら暮らすのは気分が良さそうだ。

次に見るような家も目についた。傾斜面の土を削って盛り上げたために碁盤状になった台地の上に家や立木が並んでいる。鎌倉時代以降、地方の「名主」(開発地主)は自営のため山城風の屋敷を構えていたから、これは彼らの住居跡かもしれない。

上図にも茅葺きの家が見えるが、下図になると、茅葺き屋根の家が二軒並んでいる。茅葺きの家を求めて、上伊那一円を歩き回ったけれども、二軒並んだ茅葺きの家を見るのは初めてである。背後の防風林の高さから推察するに、この二軒とも先祖代々この地から離れなかった農家だったのだろう。
