1月1日(漱石「明暗」の続編)
漱石の「明暗」は、山場にさしかかったところで中断されている。この作品を読んだ人は誰しも、津田やお延がどうなるのか知りたいと思うに違いない。読者のそうした期待に応えて書かれたのが木村美笛の「続・明暗」である。しかし、その内容は、私の予想した展開とは大きく異なっていた。
作家が作品をどう展開しようと考えていたか、その手がかりになるのが作品の中に織り込まれている伏線と、それまで作家が繰り返してきた作品展開のパターンだ。
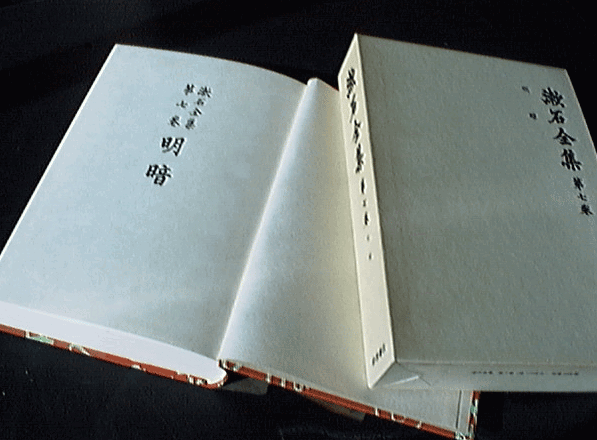
「明暗」には、随所に伏線と思われる部分が織り込まれている。津田は妹や知人からその自己中心的な行動を糾弾され、将来ろくなことにはならないと警告されているし、もっとハッキリした伏線としては、この作品の実質的な主人公であるお延による「やがて絶体絶命の危機がやってくる。その時には、ありったけの勇気を奮い起こして事に当たらねばならないだろう」という独白がある。
これらの伏線を、作品の最後にデッドロックを持ってくる漱石作品のパターンと考えあわせてみると、津田夫婦が四面楚歌の状況に追い込まれ、そこでお延が死中に活を求めるような思い切った行動に出るという筋書きが浮かんでくる。
「明暗」という題名に関連して、津田の恋人だった清子を「明」の世界の象徴としてとらえる読み方が一般化している。作品の中に清子が登場するまで、そこに描かれているのはエゴで動く人間たちの「暗」の世界だった。お延だけはやや好意的に描かれているが、その他の登場人物はいずれも救いようのないエゴイズムの世界でうごめいている。そこに、濁世を照らす観音のように清子が出現したところで作品は中断されているから、読者はその後の展開は清子を核とするだろうと思いこんでしまうのだ。それに、「きよ」という婆やを愛情をもって描きだした「坊ちゃん」もあるから、どうしても清子を明るい世界の象徴と考えたくなるのだ。
だが、清子を主役にしてしまえば、お延の出番がなくなる。
清子が津田を捨てて別の男と結婚した理由を、津田の人間性に失望したからだとするのは考えすぎだろう。津田は泌尿器科の病院に入院して手術を受けたとき(多分、痔の手術)、病院で清子の夫を見かけている。これが伏線の一つだったとすれば、清子の夫は性病の治療を受けに来院したのだ。清子が温泉場に出かけて湯治しなければならなくなったのも、夫から病気をうつされたためかもしれない。
清子はごく普通の女だった。津田を捨てたのも、彼が彼女にハッキリした態度をとらなかったからなのだ。漱石の作品に出てくる男たちは、ほとんどすべて愛する女の前で自意識過剰に陥って相手を失望させている(漱石自身、そうしたタイプだったから、登場人物に自身の姿を投影させたのだ)。
清子は積極的な態度に出た男と結婚した。だが、相手は放蕩者で彼女を裏切り続けた。そのため、清子は旧知の吉川夫人の工作を受け入れ、津田が後からやってくることを承知で温泉場に出かける。吉川夫人はお延憎しの一念から、お延に一泡吹かせてやろうとしてこうしたことを仕組んだのである。
再会した津田と清子の関係は、すぐには進展しなかったろうと思う。そのうちに清子の夫が津田の存在を嗅ぎつけ、津田の妹なども騒ぎだし、急に二人の周辺が慌ただしくなる。そうなって初めて津田と清子は結ばれる・・・。
そして、二人が結ばれた後の展開については、さまざまなケースが考えられるのだ。
€1 二人は手に手を取って駆け落ちする(「それから」のケース)
2 湯治場にこもって籠城する
¡3 二人はそれぞれの家庭に戻り、表面上以前の状態に戻る
もっとも可能性の高いのは「¡3」のケースで、このときにお延の人間が試されるのである。人に弱みを見せまいとして頑張ってきたお延が、帰宅後もひそかに清子と情を交わし続ける夫に怒りを爆発させるか、それとも夫を許すか、明暗の明の次元が開かれるとしたら、この局面においてなのだ。
誇り高いお延が、その誇りを捨てたときに新しい世界が開ける。漱石は、そう考えていたかもしれない。しかし、それをそのまま教科書風に書くようなことはしなかったはずだ。彼は何か趣向を考えていたはずであり、それを後世の私たちは知りたいのである。
有名な「則天去私」というスローガンと結びつけて、次のような結末も考えられる。複雑な人間関係に疲れた清子が、夫とも別れ津田とも手を切って実家に戻ってしまう。津田とお延はすっきりしない感情を抱えたまま、二人だけの生活に戻る。束の間訪れた平穏な日常の中で、夫婦は諦めに近い気持で現状を容認する。
そして、すべて人は未解決の問題に埋もれて生き続けるのだ、という諦観に達する。エゴイズムを基調とする人間関係の暗い連鎖、つまり「暗の世界」を消し去ることは不可能であり、「明の世界」はこれをそのまま一種の摂理として受け入れるときにだけ開ける。これは「門」の境地である。津田夫婦が救われる道は、二人が「門」の境地にたどり着くこと以外にないと思われる。
1月2日(鴎外「灰燼」の続編)
例年、元旦は暇なのでパソコン相手に碁を打つことを続けている。今年も碁を数番打った後で、上記のような漱石作品を推理する日記を書いた。漱石について触れた以上、バランスをとるためにも鴎外について触れなければならない。鴎外には未完の大作「灰燼」があるからだ。これは医務局長時代の鴎外が、陸軍を辞して本格的な作家活動に入ろうとしていた時期に手を着けた野心的な長編小説なのだ。
鴎外という人は、他人の著作に質疑や反論をぶつけることから文筆活動を開始し、他者の作品に評釈を加えることを主に執筆活動を続けてきた。軍官僚としてエリート街道を歩き、二足の草鞋をはいていた彼には、こうしたスタイルが一番書きやすかったのだ。
小説を書くときにも、「止むにやまれぬ内発的な動機」から出発するのではなく、他人の作品に刺激を受け、これに自作を対置してみる「あそび心」から出発することが多かった。例えば、彼は漱石の「三四郎」に刺激されて「青年」を書いている。そして「灰燼」は、この「青年」を発展させたものなのである。
「三四郎」という作品は、上京後、迷い彷徨して落ち着く場所を見いだせない一人の青年を描いている。三四郎は、都会の知識人や洗練された若い女性とつきあうようになる。が、これといった目的も方針もなく唯うろうろするだけなのだ。彼は地方から出てきたイモであり、典型的な非エリートであり、哀れな「迷える子羊」なのである。
「青年」の主人公も田舎から都会に出てくる。純一の将来の方針は最初からハッキリしている。作家になることなのだ。だが、作家として何を書くべきか未だ決まっていない。上京したのは、それを探すためだった。だから、傾倒する文学者の下宿を訪ね、著名作家の講演を聞きに行く。そして目から鼻に抜けるようなこの若者は、たちまちのうちに目的を達してしまう。
女性関係でも純一は、三四郎のようにもたもたしていない。彼からの誘いを待っている良家の令嬢を袖にして、身辺に謎めいたものを漂わせている未亡人に接近して深い仲になる。が、相手が通俗小説を読んだり、男あさりをするしか能がない女だと見極めをつけると、さっさと別れてしまう。いささかの迷いもないのである。
愚図でのろまな三四郎が、あてどもなく彷徨を繰り返すのに対し、純一は要領よく時代を駆け抜けて自分独自の世界を発見する。そして猥雑な現代社会に背を向けて、尚古と観想の世界に沈潜する。

確かに「青年」はメリハリが利き、小綺麗にまとまっている。陸軍省医務局長の余技としては、まず、申し分のない出来映えである。だが、「三四郎」と比較してみると、明治という時代に対する踏み込んだ批判がないし、枝葉を削りすぎてリアリティに欠けている。
鴎外は陸軍省内部で上司と衝突し、退官して専業作家になろうとしたときに、「青年」を改作して、これとは逆の世界を描いた作品に仕立て上げようとした。軍官僚という「仮面」の下に隠してきた彼本来のニヒリズムをさらけだし、文壇に衝撃を与えるような問題作を発表しようと企てたのだ。
「青年」の純一は、雛鳥のようにみずみずしい目をした若者だった。だが、「灰燼」の主人公節蔵は、悪童たちを居すくませるほどの鋭い目をしたアウトサイダーとして描かれている。吹く風にも傷つくほど繊細な神経を持った鴎外は、同時にその「弱い自分」をカバーするニヒルでタフな側面を併せ持っていた。彼は節蔵にそのニヒルでタフな面を仮託し、節蔵を明治社会に生きる鬼っ子として位置づけたのだ。
「灰燼」の構成は、最初に節蔵の回想場面を持ってきて作家として立つまでの過去を物語り、それから本筋に入って行くということになっていた。しかし作品は節蔵の回想場面が半分ほど進行したところで中断し、鴎外が本筋で何を語ろうとしたのか全く見当が付かなくなっている。でも、「青年」の構成を思い出し、回想部分に散見される伏線をたどれば、おぼろげながら浮かんでくるものがあるのである。
人物配置の点では、「青年」と「灰燼」はよく似ている。純一は良家の令嬢に関心を示さず、年上の未亡人に惹かれていったが、節蔵も寄食していた谷田家の一人娘と体の関係を持ちながら、彼女を棄てて谷田家を立ち去っている。そして彼は純一と同様に、初対面の未亡人と交渉を持つことになるらしいのだ。
節蔵は、谷田家の令嬢につきまとう変性男子の相原という若者と墓地で会う。この時、節蔵と相原は、鴎外によって次のように描写されている「墓参の女」と遭遇するのである。
「無造作に束髪を結った、色の白い、痩型の女で、黒縮緬の羽織が、凄みのある美しさによく似合っている」
この女は、樒を持った女中を従えているところから、亡夫の墓にやってきた未亡人だろうと推測される。節蔵に心服するに至った不良少年相原が、この女に目を付けるのだ。これだけで、その後の展開が自ずと読めてくる。節蔵は相原を介して、この「凄みのある女」と交渉することになるのだ。
その頃、節蔵は氷のように冷酷な現代小説を書こうとして想を練っていた。今風に言うなら、題材はマスコミが作り出す虚像によって動かされる現代社会である。「灰燼」は、節蔵が時代を嘲笑する「新聞国」の構想を頭に思い描きながら眠りにつくところで終わっている。
何が灰燼に帰したのかが問題だ・・・・。
「新聞国」を発表した節蔵は、新進作家として華々しくデビューすることになったろう。彼は冷眼鉄面の作家として、「危険思想」の持ち主として、文壇から恐れられる存在になったに違いない。そして彼は「墓参の女」の家に出入りし、私生活でもマスコミの標的になりはじめる。純一が相手にした未亡人は、底の浅い偽物だった。だが、節蔵の相手は、美しいだけでなく人間としてシャープで深みがあった。さしもの節蔵も押され気味になり、女の前で次第に冷静さを失って行く。
ツルゲーネフの「父と子」を読むと、バザーロフというニヒリストが出てくる。今は細部を思い出せないけれど、バザーロフは彼と対抗できるような年上の女と知り合いになって、その思想的な基盤を揺るがされる。牙を抜かれた狼のようになるのだ。
何が灰燼に帰したかと言えば、未亡人と交渉する過程で節蔵の築いてきた世界が灰燼に帰したのである。ロマンスを冷笑し、ナイーブな心情を否定することで成り立っていた節蔵の世界が、女を真剣に愛するようになって崩壊してしまうのだ。時を同じくして、彼の痛烈な社会批判に対する当局の弾圧が始まったかもしれない。著作活動を禁じられた彼は、生活上の基盤をも失ってしまう。
節蔵は出発点から、灰燼の世界で生きていた。彼は既成の価値観や美意識を否定し、すべてを焼き尽くした虚無の世界から出発したのである。従って、改めて作品の題名として「灰燼」という言葉が付与され、それが意味を持つてくるためには、その節蔵がナイーブな世界に立ち返り、それまで軽蔑してきた「世間並みの幸福」を追求し始めるという状況を設定しなければならず、そして、その世間的幸福が脆くも崩壊したことで、彼は再度、ニヒルな世界に回帰せざるを得ないという場面を想定しなければならない筈だ。としたら、以上述べてきたような推測も成り立つのである。
鴎外が「灰燼」を完成させたら、節蔵という日本文学史に例のないユニークな人物が創造されるところだった。その意味で、私は「明暗」の中絶よりも、「灰燼」の中絶を惜しむものである。