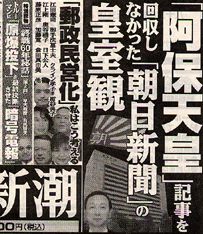新「尊王攘夷の時代」 貴乃花問題では正反対の立場に立った週刊文春と週刊新潮は、反朝日新聞キャンペーンを張る点では足並みをそろえている。この両誌の親会社は、昔から岩波書店と朝日新聞社を目の敵にしてきたのだ。
新聞広告を見たら、週刊新潮がまたまた朝日攻撃の特集を組んでいる。
度重なるバカバカしい記事を読まされていると、この週刊誌のことをまともに取り上げる気がしなくなるのだが、その反面で次は何を言い出すのだろうかという妙な興味も感じてくるのだ。今回の見出しはこうなっていた。
──「阿保天皇」記事を回収しなかった「朝日新聞」の皇室観──「阿保天皇」とは何だろうか。
まさか朝日新聞が、天皇を阿呆呼ばわりした記事を載せたわけではないだろうな。気がついたら、私は週刊新潮を買いに出かけていた。この週刊誌が商売上手であることだけは認めなければならない。
入手した雑誌を持ち帰って読んでみたら、やはりバカバカしい内容だった。
朝日新聞は、週末になると本紙の他に別刷りの付録紙を出している。その最近号が在原業平を取り上げたのだが、その記事のなかに誤記がひとつあったのである。業平の父を阿保親王とすべきところを「阿保天皇」としてしまったのだ。週刊新潮は、この点をとらえて附録紙を回収すべきだと強調しているのである。そして同誌は近年に起きた皇室に関係する誤植事件を列挙する。
88年には『女性自身』10月11日号が、昭和天皇の写真を裏焼きで掲載して発売中止となった。翌89年には、週刊誌『SPA!』2月9日号が、見出しの「大正天皇」を「大正洗脳」と誤植し、これまた発売中止に。さらに昨年暮れの『女性セブン』12月23日号では、見出しの「皇太子さま」の「太」が「大」になったミスのために、雑誌の発売を4日延期する騒ぎとなっている。
週刊新潮は、印刷の世界では「誤植」が宿命のように避けがたいことを認めながら、「女性自身」以下の諸雑誌の自粛的対応を「こうあるべきだった」と肯定する。「女性自身」は逸失広告料から輸送のキャンセル料まで含めて3億円近い損出を出して発売中止に踏み切ったのだが、週刊新潮誌はこうした犠牲を払うのを当然のこととして是認しているのである。そして朝日新聞にも、これにならえと要求する。
週刊新潮の指摘するとおり誤植や誤記は避けがたいことだから、通例、マスコミ各社はそうした場合、訂正や謝罪をするだけですましている。だが、皇室に関する誤植に限って各社は恐懼身の置き所を知らず、問題の出版物を発売中止にしたり、全体を刷り直しをしてきたのだ。
だが、常識を備えた人間なら、皇室関連記事だけを特別扱いする慣習に疑問を感じるのが当然なのだ。こんな妙ちきりんな話が通用するのは、日本だけなのである。週刊新潮の編集者がまともな神経を持っていたら、こんな慣習は否定しなければならない。それに、彼らはどうして「明日は我が身」と考えなかったのだろうか。
出版人なら、大正7年8月に起きた「白虹日を貫く」事件を知らないわけはあるまい。大阪朝日新聞がうっかり「白虹日を貫けり」という言葉を新聞紙上で使ったために、内務省から「天皇の暗殺と、クーデターをそそのかしている」と断定され、新聞を永久に発行禁止にすると威嚇されたのだ。このため、新聞社長・編集局長・社会部長は全員辞任に追い込まれた。長谷川如是閑もこの時辞任した一人である(中国の故事によると「白虹日を貫く」は、革命の前兆ということになっている)。
大正デモクラシー運動をリードしてきた新聞・雑誌は、この「白虹」事件によって自主規制に努めるようになり、運動は急速に衰えていった。これこそ当局が、反政府・反体制の言論を取り締まるときの決め手だったのである。反政府の言論を封じ込めるには、皇室の尊厳を侵し、国体の精華を傷つけたというような口実を使うのが一番手っ取り早かったのだ。
──国体の問題については、初代の東大総長加藤弘之が次のように書いている。
「こころみに思ふべし。君主も人なり、人民も人なり。決して異族の者にあらず。しかるに、ひとりその権利に至りては、かく天地の懸隔を立てしはそもそも何事ぞ。かかる野卑陋劣なる国体に生まれたる人民こそ、実に不幸の最上と言ふべし」(「国体新論」)
君主も人民も、同じ人間である。だから、人間としての扱いに差があるべきでないとする加藤弘之の議論は、世界中の誰もが公理として承認するものなのだ。
しかも、今回の誤記は、現存する皇族に対するものではなくて、1200年も昔に生きていた無名に近い親王に関するものなのである。そんな問題をほじくり出してきて、新聞を刷り直せと要求するのは、言論機関自らが検閲制度の導入に手を貸すようなものである。それとも週刊新潮は、自らが検閲官になって敵対する言論機関をつぶしにかかったのだろうか。
日本人は明治以後、天皇の名による政府・軍部の圧政に苦しんできた。数百万人の犠牲者を出した敗戦によって、ようやくこうした日本政治の悪弊から抜け出せたと思ったのに、週刊新潮は「尊王思想」を持ち出すことによって時代を逆行させようとしている。
勤王の精神を鼓吹する同誌は、他方では反中国の論陣を張るのに熱心で、片手に尊王もう一方で攘夷論を宣伝している。この週刊誌が尊王と攘夷の二本柱を編集方針にしているところは、幕末の浪士を思わせるのだ。幕末の尊王攘夷論は、海外情勢に無知な下級武士や地方の上層農民に支持されはしたが、やがて開国論の前に敗北を喫することを週刊新潮は銘記すべきだろう。
もっとも、現代を幕末の動乱期に比定するのは間違っているので、こちらの議論も少し修正しておく必要がある。
新保守主義の中曽根内閣が成立してから、日本の世相は将軍家斉の時代、つまり文化文政期に酷似してきたのだ。以前にも引用したけれども、化政期の庶民(特に町人)は現世主義に徹し、彼らの願うところは家内安全・商売繁盛だけであり、余裕が出来たときに彼らが手にするのは洒落本・人情本・浮世絵などだった。つまり、彼らは、現世主義に見合った浮世感覚でもって人生を生きていたのだ。
鎖国下にある化政期の庶民には、国際感覚のようなものはゼロに等しく、普遍性を持った知識や学問への渇望もなかった。彼らは、広い世界を知らず、現状維持的な娯楽や読み物で充たされる程度の文化的欲求しか持っていなかったのである。
この時期に発展した国学も、基本的には閉鎖社会向けの自己満足原理で一貫していた。本居宣長の見識はかなり高かったけれども、その彼に言わせると敷島のわが日本は世界で最古の国家なのであった。彼は、理性よりも生まれたままの真情(大和心)の方が真実をとらえうると考えていた。こうした夜郎自大的な考え方を更に推し進めたのが尊王攘夷を説く平田国学であり、水戸学だったのである。
新保守主義以降の現代日本人も、化政期の庶民と同じように現世主義に徹し、テレビや雑誌で浮世感覚のエンタテインメントを愛好するようになった。平和と繁栄が続くと、難しいことは考えなくなり、現状肯定のお気楽人間になって、浮世感覚にどっぷり漬かってしまうというのが、日本人の習性らしいのだ。
こうした日本人の習性ほど、政権担当者にとって都合のいいものはない。
天皇崇拝の尊王論とすべての人間の価値を等しいと考える人間平等論を比較し、そして中国憎しの排外主義と世界平和をを希求する国際協調主義を比較すれば、その優劣は明らかであるにもかかわらず、右派の政治家は、天皇崇拝、中国敵視のPRをつづける。前近代的な議論を展開することで、彼らは自分の立脚する古くからの利権構造を存続させようとしているのである。
二流三流の学者や評論家も、読者の「遅れた意識」に媚びることで活躍の場を広げている。そして彼らに活躍の場を提供し、日本人の夜郎自大的意識を煽り立てているのがマスコミなのだ。
マスコミは、ドイツが周辺諸国に日本の65倍の賠償金を支払っていること、そしてドイツの大統領・首相が相手国に謝罪するだけでなく、ドイツ国民に対しても自国の侵略行為を心から懺悔し、相手国に誠意をもって謝罪しなければならぬと訴えていることを伝える必要がある。
アジアの諸国が日本への疑念を棄てきれないのは、日本の首相が外国向けに謝罪しても、自国の国民に向かって何も説得しないどころか、15年戦争を肯定していると誤解されかねない行動を繰り返しているからだ。
ところが、マスコミはこの点に目をつぶって、満州事変以来の15年戦争を日本の自衛戦争だったと強弁する政治家・評論家をもてはやしているのだ。
政治家・評論家・マスコミに多くを求める気持ちはない。バカ丸出しというような意見が大手を振って横行している今の世の中、万国共通の常識というものがあることを知ってほしいだけである。