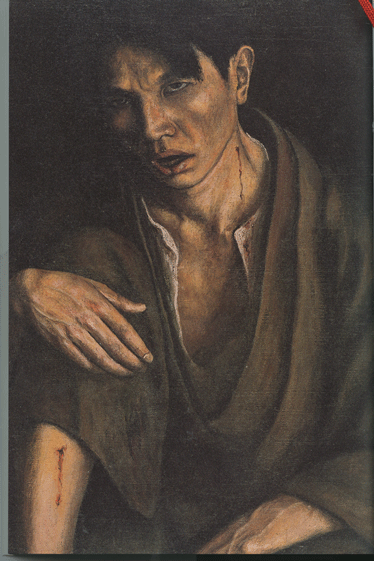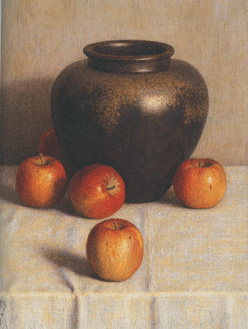孤高の画家・高島野十郎
またNHK「新日曜美術館」の話で気がひけるけれども、テレビ画面に映し出された画家高島野十郎の作品を眺めているうちに、思わず吸い込まれるように見入ってしまった。高島野十郎が85才で死ぬまで独身を通したことや、東京帝国大学の農学部をトップで卒業したという経歴や、そして生前は画壇に知られることなく終わったという事実に興味を感じたが、それより何より、とにかく彼の作品が面白かったのだ。
私は野十郎の作品が、岸田劉生に似ていることに興味を感じたのかもしれない。だが、野十郎の作品は、劉生と同じように細密な写実画でありながら、どことなくアマチュア風の泥臭さがあり、劉生作品に見るような高い哲学性を欠いているように思われた。にもかかわらず、野十郎の作品には妙に人の心に迫ってくるものがあるのである。
同じ細密描写でも、岸田劉生は描く対象を微妙に歪め変形させている。そこに彼の作品の精神性や思想性が浮かび上がってくるのだが、高島野十郎の作品は、写実は写実でも、カラー写真式の写実なのである。野十郎作品にゲテモノ風の感じがつきまとうのは、このためかもしれない。
野十郎は精密な写実画を描くにあたって、対象を長い時間をかけて観察している。渓流を描くために奥秩父に出かけたときなど、旅館に泊まり込んで何日も同じ流れを凝視し続けたので、水流が止まり、両岸の岩が流れ始めるような錯覚に襲われたほどだった。こうした逸話がある一方で、野十郎は描く対象をあらかじめ写真に撮って参考にするようなこともしている。彼は戦前のまだカメラが普及していなかった時代に、高価なカメラを買い込み、アトリエの隣には写真現像用の暗室を作っていた。
高山辰雄もそうだったが、観察するために長い時間をかける画家はモデルの背後に一種魔的な相貌を幻視することが多い。劉生はこのことを自覚していて、自らを「写実的神秘派」と呼んでいる。劉生の有名な麗子像は、ほとんどすべて神秘的な薄笑いを浮かべており、「野童女」と題する作品に至っては妖怪の相すら見せている。
「傷を負った自画像」
同じ悪魔的作品でも、高島野十郎のものは実にリアルなのだ。「傷を負った自画像」と題する作品を見れば、劉生との違いがよく分かる。写真的写実という性格を残したままのデフォルメなのだ。野十郎はどうしてこんな奇怪な絵を描くようになったのだろうか。次に彼の生き方を眺めてみよう。
高島野十郎の経歴を調べるために、彼の評伝「過激な隠遁(川崎浹)」を取り寄せて読んでみた。著者の川崎浹は早稲田大学の教授で、21年間の長きにわたり生前の野十郎と親交を結んだという経歴を持つロシア文学の研究者である。その評伝によると、高島野十郎は九州久留米の裕福な酒造業者の家に生まれた。五男二女の子供達のうちの四男である。長兄の宇朗は強い霊性を持ち、時折、「神憑り」の状態になるような男だった。宇朗は家業を弟に譲り、禅寺に入って修行した後に、上京して詩人になっている。彼の交友歴は多彩で、友人には岩野泡鳴、蒲原有明、青木繁らがいる。
信じる道に突き進む宇朗の血は子供達にも流れ、息子の一人は共産党員になり、その妹も兄の後を追って入党している。高島野十郎の甥と姪にあたるこの兄妹は、間もなく悲惨な死を遂げる。姪はアジトを警官に踏み込まれたとき、隣家に飛び移ろうとして転落し、以後寝たきりの状態になって死亡、甥の方も逮捕されて刑務所に送られて亡くなり、二人とも24歳の若さでこの世を去っている。
宇朗には、もう一人息子がいたが、これも禅寺に入って雲水の修行をしているから、彼が父親として、いかに子供達に大きな影響を与えたか分かる。高島野十郎が孤高の生涯を送ったのも、敬愛する長兄の影響力によるところが大きかったと思われる。宇朗は野十郎より12歳年長だったから、野十郎は宇朗に兄事するというより彼を父親のように思っていたのである。
野十郎は旧制第八高校を経て、東京帝国大学農学部の水産学科に入学する。成績は極めて優秀で、特待生になり、首席で卒業している。
大学を卒業した野十郎は、大学に残って学究の道を選ぶでもなかった。民間会社に就職することもなく、いきなり画家になると言い出したから母を始め、親戚の者たちはこぞって反対した(父親は野十郎の在学中に死去。母も彼の卒業後に亡くなっている)。惣領の長兄が詩人になって徒食の生活を始めたと思ったら、今度は秀才の誉れ高い四男が画家になるといいだしたのである。
帰郷した野十郎は、行く先々で親戚・知友から画家志望を変更するように勧告された。彼は一言も反論しないで、黙って話を聞いていた。長兄(後に禅寺の住職になる)さえ、「絵描きなんぞになったら、家庭を持てなくなるぞ」と反対したが、野十郎は志望を変えなかった。
一切の退路を断って上京した高島野十郎は、東京で画家としての生活を始めたが、彼がどのようにして衣食の道を講じていたのか、明らかではない。彼は東大在学中に24歳で「傷を負った自画像」を描いているけれども、野十郎がこれほど完成度の高い作品を描く技量をいつ何処で身につけたのかということもまた明らかでない。
彼が特定の師について油絵を学んだとは思えないし、画家志望の仲間と研究会のようなものを作っていたとも思えない。野十郎は独力で学び、自力で研究して、あの「細密写実画法」を身に付けたのだ。ここに高島野十郎という無名画家の比類のない独自性がある。
水産学科に籍を置いていた彼は、魚類や水棲動物を精密に模写した図版をいくつも残している。これらは学術用に使用されるものだから、一点一画までおろそかにせず、正確に描かれなければならなかった。彼は写真のように精密な生物実写図を描いているうちに、一種の法悦のようなものを感じ始めたのではなかろうか。彼は絵筆を取ることに敬虔な喜びを感じ始めたのである。
高島野十郎は終生、「絵を描く」とは言わなかった。描くのではなく「研究する」と言い続けたのだ。彼にとって絵を描くということは、対象の真に迫り、その本質を明らかにすることだったのである。
それにしても、「傷を負った自画像」の異様はどこから来るのだろうか。
画中の野十郎は、唇・首筋・脛の三カ所から血を流している。これを見ると、彼は転んで傷ついたとは思われない。自虐と呪詛の表情を浮かべているところからすれば、喧嘩でもしたのだろうか。それとも自死を試みて、途中で思いとどまったのか、高島野十郎の不思議な生涯を解く鍵は、この絵の中にあるかもしれない。
「日曜美術館」を見ていて、もう一つハッキリしなかったのは、高島野十郎がどうして生活費を捻出していたかという問題だった。
彼は一枚の作品を仕上げるのに、2年間をかけるのが普通だったという。しかも、その作品は週刊誌かグラフ雑誌程度の大きさしかないものが多かった。そんなものに2年もの時間をかけて描いていたら、収入は微々たるものだったはずである。にもかかわらず、彼は40才になってから、4年間もヨーロッパに留学しているのだ。としたら、彼は実家から扶養されていたのだろうか。
この疑問は川崎浹の書いた評伝を読むことによって、ほぼ解けた。著者川崎浹が東京青山にあった野十郎のアトリエを訪ねたら、板張りの床にたくさんのカンバスが置かれていたというのである。これらが制作途上のカンバスだったとしたら、彼は同時並行的に多数の作品に着手しており、それらに少しずつ手を加えていった結果、どれもこれも完成するまでに2年内外の歳月を要したのだ。「雨 法隆寺塔」という作品にいたっては、完成するのに17年かかっているのである。
こういうやり方なら、ある程度の量の作品が出来上がるから、定期的に個展を開くこともできる。野十郎には、個展による売り上げがあっただけでなく、大学時代の仲間や知己になった医者などがパトロンになって絵を買ってくれたし、故郷の親戚たちもちょいちょい作品を購入してくれていたらしかった。
こうして、野十郎は実家に頼ることなく日々の生活を維持することが出来たのだった。それにしても、大学を卒業して85才で死ぬまで、60年間をたった一人で生きた野十郎に、寂寥感や惑いはなかったのだろうか。彼は、60年をいささかの破綻を見せることなく静かに暮らしているのである。
明治23年に生まれた彼は、中学生の頃に日露戦争を体験し、青春真っ盛りの20代に大正デモクラシーの洗礼を受け、壮年期に軍国化した日本が破滅に向かって進むのを見ていた。そして50代半ばで日本の敗戦に遭遇し、昭和50年に85才で死去するまで、鳴かず飛ばず、市井の無名画家としてひっそり生きていたのである。
高島野十郎は、85年の生涯を完全なアウトサイダーとして生きた。こうした人生を送る芸術家には、密かに女を囲っているものが少なくない。だが、野十郎は女色にも無縁だった。渓流の絵を描くために奥秩父に逗留したとき、夜、宿の女将が野十郎を誘惑しようとして、「暑いでしょう」といって彼の寝ている蚊帳の中に入ってきて団扇で煽いでくれたりしたが、そんなときにも、野十郎は女に取り合うことなく黙って本を読んでいた。彼は女性から物を贈られることがあったが、それらを捨てるか、その場に置き残して立ち去るのが常だった。
野十郎の85年は、細密写実の油画を描くだけで終わった人生だった。
彼は同時並行的にいくつもの作品を描き続け、気分転換のためには、自分で使う家具を作ったり、家の補修をした。細密画を得意とした彼は、細かな手仕事にも妙を得ていたのである。
こういう野十郎にとっては、長い年月をかけて描きあげた作品の一つ一つが家族であり、自己の分身だった。だから17年かけて完成した「雨 法隆寺塔」という作品を世話になった知人に贈るときに、玄関まで見送りに出た彼の目に涙が溜まっていたのである。
「雨 法隆寺塔」
高島野十郎は絵を描いていれば、幸福だった。
東京オリンピックのための道路拡幅工事のため、青山のアトリエを追われた野十郎は千葉県の増尾に移り、野菜畑のうち続く静かな場所にアトリエ兼用のささやかな家を建てた。家にはアトリエの他に寝室と台所があり、間口三間・奥行き二間という物置のように小さな住まいだった。水道も電気も来ていなかったので、夜は石油ランプで過ごした。入り口の戸には複雑な仕掛けがあって、野十郎でないと開けられない仕掛けになっていた。椅子も手製なら、ベットも手製だった。ベットは、藁を芯にして外側を布で包んだものだった。
彼は訪ねてきた川崎浹に、「ここは人っ子一人通らず、私にとっては天国だよ」と語ったという。野十郎は隣の田の一部を借りて池を作り、そこに睡蓮の花を咲かせて、「睡蓮」という作品を描いたりした。
高島野十郎は、静かに生きた。
彼は師にもつかず、仲間も作らず、同伴者なしの人生を歩んだ。彼は制作中心の生き方を求めて、こうした一人だけの静かな人生にたどり着いたのである。つまり、彼の孤独な人生は、作為したものではなかった。野十郎のような人間にとって、至極まっとうな祝福された人生だったのである。
野十郎の研究者たちは、彼が写実に執着した理由を形の奥にある原型を探るためだったと主張する。野十郎はノートに、
「花一つを、砂一粒を人間と同物に見る事、神と見る事」
「壺とりんご」
と書き残していたから、彼はすべての物が内包する神性のようなものを描こうとしたのかもしれない。だがそれだけでは、十年一日のように絵を描き続けた理由を説明できない。
野十郎は画壇と関係することを避けただけではなかった。彼は自分と社会との間の接点をすべて切り払って、現世と無関係に生きていたが、時には外部と交渉しなければならないこともあった。彼はオリンピック道路の拡幅工事で東京青山の住まいを追われているし、やむを得ず移り住んだ千葉県柏市増尾の住居からもアパート建設工事のため転居を強いられている。こういうときに、野十郎は訪ねてきた関係者と激しく争っている。彼は相手と交渉するに当たって一歩も引かなかった。こういう時に現世に対する彼の厳しい姿勢が垣間見えたのである。アウトサイダーとして世俗を強く拒否していた野十郎は、最後に誰にも看取られず野垂れ死にすることを覚悟していた。最晩年の野十郎は、千葉県内の特養ホーム鶴寿園に運ばれることになったが、この時彼はアトリエの柱にしがみついてテコでも動かなかった。それで、係員は彼の指を一本一本剥がすようにして連れて行かなければならなかった。
野十郎の知人は、「彼は死の間際にも、『自分は本当はだれもいないところで野たれ死にをしたかった』と言って涙を流していた」と語っている。野十郎は、だれにも構われず自然に死にたかったのである。
「野たれ死に」の概念は、宗派とか教義によって異なるらしいが、私は高島野十郎がどんな独自の「野たれ死に」を念願していたのか、そこまでは知らない。作家のチェーホフも「私は行き倒れて塀の下で野たれ死にするだろう」と語っているので、一般には「野たれ死に」とは行き倒れとか餓死を意味しているようである。野十郎は一人で歩いてきたので、一人で死にたかったのだろう、と川崎浹は考えている。
彼のエネルギー源は、卑俗な現実に屈服することなく、静かに戦い続ける決意にあったのだろうか。彼が画壇と無関係に生きたのは、自然にそうなったのではなく、自ら語っているように「世の画壇と全く無縁になること」を意図したからに他ならなかった。
高島野十郎が内心で現世と激しく対峙していたことを考えると、「傷を負った自画像」に見る自虐と呪詛の表情も自ずと理解されてくる。この作品は写真のようにリアルに描かれながら、表情だけがデフォルメされて非現実的に描かれている。これはどうしても現実と折れあえず、自分の将来を野垂れ死に以外にあり得ないと思い定めた若者の表情である。この絵を描いた20代の頃から、彼は社会に対して怨念を抱いて生きていた。この怨念こそが、60余年の間、一日も休まず彼に絵筆を握らせたエネルギー源だったのだ。