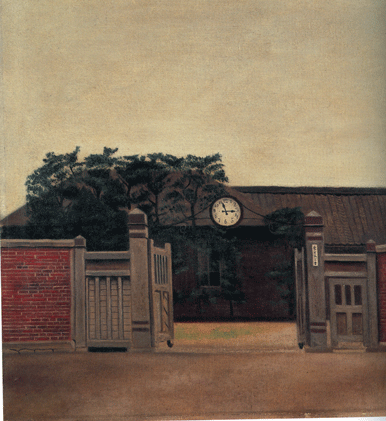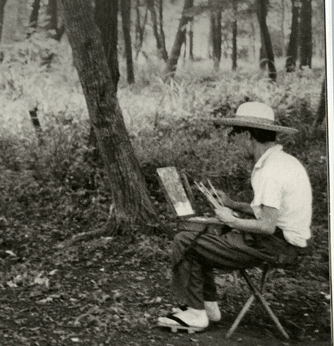孤高の人・長谷川りん二郎(その2)
孤高の画家といわれる長谷川りん二郎と高島野十郎には、寡作の画家だったという共通点がある。生涯にわたって僅かしか作品を残さなかったのに、二人が平穏な生涯を送ることができたのは、実家や親戚に資産家が多かったからだった。長谷川の父親は函館新聞社の社長兼主筆だったし、長兄の海太郎は昭和前期を代表する超弩級のベストセラー作家だった。海太郎は、谷譲次・林不忘・牧逸馬という三つのペンネームを使い分けて、「丹下左膳」などの娯楽小説を大量に生産し、大衆文壇の帝王と称された。
りん二郎は海太郎を長男とする四人兄弟の次男だったが、りん二郎も後に続く二人の弟も文学的な才能に恵まれていたため、「長谷川四兄弟」と呼ばれていた。りん二郎は幻想的な探偵小説を「新青年」「探偵趣味」などの雑誌に発表しているし、三男はバイコフの「偉大なる王」の翻訳者として知られ、末弟の長谷川四郎は「シベリア物語」などの小説のほかに、戯曲・評論・翻訳など多方面の著作で知られている。
経済的に豊かで、知的な刺激にも恵まれた家庭で育ったりん二郎は、函館中学校に入学したものの、型にはまった学業に身を入れる気になれず、一年落第している。中学校を卒業した彼は、詩人になるか絵描きになるかという選択の前に立たされたが、後者を選んで上京し、川端画学校に入学することになった。だが、通学すること数ヶ月で画学校を退学して、その後は独学で油絵を描き続けている。
1930年(昭和5年)、りん二郎の父親は26歳になってもまだ芽の出ない息子を心配して、アトリエ付きの家を荻窪に建ててくれた。りん二郎は、この父のためにも早く一人前の画家にならなければならなかった。それで、渡仏して本格的に画の勉強をする決意を固める。
当初の計画では、5年から10年パリに滞在する予定だったが、彼は僅か一年で日本に戻ってしまう。その理由を彼は芭蕉と蕪村の俳句を読んで、日本の風物を描きたくなったからだと告白している。
「(芭蕉・蕪村の俳句に接して)日本の風景が、季節の風物が、目前の巴里とは、まったく異なった別世界の美しさで浮かび上がって来た。私は日本について外国人のように無知であることに、気がついたのだった。
日本を出発した時、汽車が京都付近を通った時、私は窓外の風景の、なごやかな美しさに強いショックを受けた。ぜひ此処へ来たいとその時思ったのだ・・・・・
やがて巴里の風景は巴里人にまかせればいい、私は日本の自然を研究することが、私たちの仕事ではないかと思うようになって来た」
彼は漫然と日本の美しい風景を思い出し、既成の美意識に基づいて風景画を描こうとしたのではなかった。これまで誰も手をつけなかった全く新しい角度から、日本の風景を描こうと思ったのである。それは、ゴーギャンが、今まで誰も画にしなかった始原の光景を描こうとしてタヒチに渡ったのと同じ心境からだった。
「私は故郷が懐かしくて帰るのではなく、強い好奇心と期待と、野心を持って帰ったのだ。私の作画についての信念を、日本の自然について成長させ、新しい絵を造ろうと思ったのだ」
帰国後の4年間は、長谷川りん二郎が最も旺盛に作品を生み出した期間だった。彼は、二科会にも盛んに出品した。後年、彼は「二科に出品したのも父のためだった」と語っている。自分のためにアトリエ付きの家を建ててくれ、フランス留学の費用も出してくれた父に、「自分がアトリエで昼寝ばかりしているわけではない」ことを証明するために制作に精を出さなければならなかったのだ。
彼が、親孝行のために二科会に出品した作品の中に、名品といわれる「時計のある門」がある。ここに示した図版は、右側部分を切り落としてあるけれども、この世のものとは思えない、しいんとした無音の世界を描きだしている。確かに,これまでの風景画とは類を異にする斬新な作品であった。
風景を目の前に置いていないと、筆を動かすことのできなかった彼は、林の中であろうが、雑踏する街中であろうが、画架の前に座って何時までも制作を続けた。頭には古びた麦藁帽子をかぶり、足には下駄というラフな格好で描いていると、当然衆人環視の中で絵筆を動かすことになる。ところが彼は、通行人に画を見られ、時に話しかけられたり,その画を売ってくれないかと頼まれたりすることを楽しんでいた。
彼は、「雑踏の中にいて画を描いていると、自分の画室にいるような落ち着いた気持ちになって、通行人も気にならず、ゆっくりと仕事ができる」と語っている。この辺が、やや狷介の気味のあった高島野十郎と違うところだった。
彼は実物を前にしていないと画を描けない画家だったが、まわりから現場主義の画家だといわれると反論を試みている。
「私は確かに目の前にある実物を描く。しかし、それは実物によって生まれる内部の感動を描くのが目的ですから、実物を描いているとはいえません。つまり私が描いているのは実物ではありません。しかし、それは実物なしでは生まれない世界です」
彼が土の美しさについて書いているのを読むと、この言葉が嘘でなかったことが分かる。
「私が本物の土を見て『素晴らしい。何という美しい土の色だ』と感動しなければ、何事も始まらないと思う。理想的な土を見るには次の条件が必要だった。四月未から五月中旬までの間で、晴天が二、三日続いた日である。その日をのがしたら来年まで待たなくてはならないのだ。雨の多い年は駄目だし、植木の手入れをして、庭を整備しておかなくてはならない。
五月の土の色と、七月の土の色は、まったく異なっている。土は周囲の雰囲気で、その表情を変える」
上記の文章を読むと、彼が寡作であり、そして描きかけの画を多く残していた理由も理解されてくる。風景や実物は、特定な瞬間にしか本来の美を見せてくれない。だから、その瞬間を逃がしてしまったら、辛抱強く次の瞬間が到来するのを待つしかないのだ。「長谷川りん二郎画文集」の表紙を飾る「猫」の画は、6年間かけても完成に至らなかったという曰く付きの作品である。
昭和51年、りん二郎72歳の9月、彼は室内で転倒して右腕を骨折した。入院して治療している間に左足の変形性関節症で歩行困難になってしまう。これ以後、彼は気に入った風景を求めて旅をしたり、散歩したりすることが不可能になった。晩期の室内画制作時代がはじまるのである。
晩期の静物画には、それまでと打って変わった明るい清涼感に満ちた作品が多い。空の空き箱だけを描いたものもあって、作者の多面的な才能を示している。
長谷川りん二郎は84歳で死去している。多彩な才能を持っていた「長谷川四兄弟」のなかでは、最も長命だった。