しま・ようこ詩集「北の方位」
谷敬夫人のしま・ようこさんとは、まだ一度もお会いしたことがない。多分、今後もお会いすることはないに違いないが、谷敬の没後、何度も手紙を取り交わしているうちに、「静かな貧しさ」を愛する彼女の深い人柄に敬意を覚えるようになった。
しまさんの手紙は、美しい細字で書かれている。そして、細やかな心遣いが感じられる達意の文章でつづられている。手紙だけを見れば、彼女は日本古来の礼節を心得た、つつましやかな女性と思われるのである。
ところが、この人の詩を読むと、印象が一変する。
夫の谷敬は、平明でリズム感もある詩を書いていたのに、夫人の詩は難解で謎に満ち、手紙から受けた印象とは全く違っているのだ。
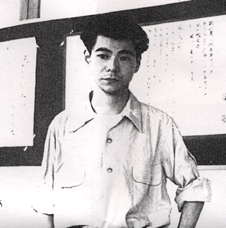 入院当時の谷敬。私は彼の写真を一枚も持っていなかったが、しまさんから子供時代のものも含めて数枚の写真を送ってもらっている。
入院当時の谷敬。私は彼の写真を一枚も持っていなかったが、しまさんから子供時代のものも含めて数枚の写真を送ってもらっている。
彼女には社会批判をテーマにした詩が多い。題名に 「わたしが狂暴になるとき」 とか 「座ったままのテロリズム」 とか、激しいプロテストを突きつけていると思われるものがあるが、彼女は決して逆上することはない。知的に構築された枠組みの中で、独語するように自らの想いを語るだけなのである。このへんにも、一筋縄ではいかない彼女の人柄が現れている。
私はこれから、しまさんの詩集「北の方位」を手がかりに、その経歴を追ってみることにする。あわせて、彼女の詩がどうして難解なものになるのか、その背景を探ってみたい。まず、最初に「難解な詩」の一例を示すことからはじめることにしよう。
「海の装置」とは風変わりな題名だが、作意は大変分かりやすい。男性本位に作られた既成社会を「陸」、フェミニズムの世界を「海」に見立て、期待を込めて海の未来を展望した作品なのである。心ある女たちは、「陸」社会のカリスマに欺かれることなく、安全に構築された港を捨てて、未知の海に向かって漕ぎ出す。しかし、海には、まだ陸のそれのように安定した秩序や社会装置が備わっていない。
陸にとどまって娘たちは、行動に出ない。じっと、「母の出帆」を見送っているだけだ。だが、彼女らは不安な気持ちを抑えながら、海の装置をいかに構築すべきか思索し始める・・・・・
この作品には、フェミニズムを女たちが考案した護身用ジャケットと考える男友達を 「にんげん目フェミニスト科中退の」落第生と揶揄する部分などがあって微笑を誘われる。が、これには次のような分かりにくい一節も含まれているのである。
(樹は樹であることから脱出できない)
F・ポンジュは女ではなかったので
物と言葉の影を透かして
男の懐疑に女の独断を棲まわせた
丘をたたえる構図がまた一枚描かれる日
現代詩に接することのなかった読者は、この一節にぶつかって困惑し、動きがとれなくなる。
「海の装置」では難解なところはこれだけだが、始まりから終わりまで謎めいた表現ばかりが続く作品も多い。こういう作品を開くと、読者は一行ごとに立ち止まって頭を絞らなければならず、まるで針山を上るような気になるのだ。
しまさんの経歴
詩集「北の方位」の奥付には、彼女の簡単な略歴が載っている。しかし、それは原稿用紙にして二枚に満たない短いものである。しまさんは 「わたしの詩は、個人史から自由になりにくい」 と自ら書いているのに、ご自身の経歴について暗示的にしか語っていなのだ。やむをえず、空白の部分は想像によって補うしかない。
著者略歴の冒頭には、
1934年佐世保生まれ、鎌倉・弘前で育つ。
と書かれている。
しまさんは軍人の家庭に生まれた。「影を裁く」 という作品には、自由主義的だった父親の面影が描かれている。父はしまさんに
きみは おんなのこ
でもすきなように いきなさい
と語り、そして、
せんそうは ひとごろしする わるいこと
でも とうさんはぐんじんだから いくさにいく
と話している。こうした父の言葉にはじまるこの作品は、ショッキングな事実を織り交ぜながら後半に移り、つぎの一節になる。
『K島戦記』は
あなたの息絶える指揮を
向こう岸の迷彩服から接写した
この部分については、説明が必要だろう。しまさんにオーストラリア人(あるいはアメリカ人か)の友人があり、その友人が現地の古書店で「K島戦記」という本を見つけて、しまさんに送ってきたのだった。現地で発行され、英文で書かれたその本の中に、しまさんの父親らしき人物が日本軍指揮官として登場しているからだ。
しまさんは、その本を読んで敵側の目から見た父の姿とその最後の様子を知る。外地の友人が、偶然にその古本を手にすることがなければ、しまさんは戦場での父の様子を知ることがなかったのだ。「神の糸で結ばれた」 ような偶然である。
その父の留守中、しまさんの一家は鎌倉で暮らしていたらしい。そして、そこで彼女は、異様な体験をしている。そのことを彼女は「北の方位」の後記に次のように記している。
(・・・自分が個人史と結びついた詩を書くのは)幼少期に木漏れ陽のぶらんこに揺られながら宇宙時間の不思議さに刺し貫かれてしまったからだろうか。
この宇宙時間体験が、しまさんの詩作に大変大きな影響を与えている。では、その体験とはいかなるものだったのだろうか。
座ったままのテロリズム
─ヒストリイまたは歴史について─むかし
〈飛んでいる矢は止まっている〉
ということばに出くわして
とつぜん数学が好きになった少年のように
暗い河に出会ったわけではないある日
気まぐれに
縄ぶらんこの小宇宙が止まり
まんだら模様の木もれ陽に
幼ない時間がさしつらぬかれ
暗い河が銀の背をひるがえし
逆流するのを見た
幼い少女が、木漏れ日を浴びながらブランコに乗っている。不意に彼女は時間が止まってしまったような不思議な感覚に襲われる。その感覚は、彼女に永遠の世界を実感させた。
しまさんは成長してから、繰り返しこのときの不思議な体験を反芻したに違いない。そして、あの瞬間に、時計的時間・歴史的時間をさかのぼって永遠の時間にたどり着いたというような感覚があったことに気づくのである。
この永遠の時間・宇宙時間に比べたら、時計的時間・歴史的時間は「暗い河」のように思われる。「飛んでいる矢は止まっている」という言葉に霊感を受けた少年も、時計的時間の不思議に気がついただけで、宇宙時間の神秘をかいま見ることはなかった。
しまさんは、歴史的時間が宇宙時間を水源として流れ出し、再び宇宙時間に回帰して行くというイメージを得たのかもしれない。私たちにはその内実を知ることは不可能だが、しまさんがこの感覚を基盤にして世界を眺めるようになったことは疑いないだろうと思われる。
カミュは「異邦人」という小説で、身の回りの慣習や制度を異邦人の目で見るようになった青年を描いている。他者とは異なる時間を持ってしまった人間は、ムルソー青年のように異端者として生きるしかなくなる。しまさんは、世界地図を国別に塗り分けられる以前の白紙の状態で眺めるようになり、自分を無国籍人と感じるようになった。
でも、しまさんは異端者・傍観者として何時までも宇宙時間の高みに留まっていることはできなかった。彼女を地上に引き下ろすのは、彼女の罪の意識であり、そしてまた拒まれてきた女性たちとの連帯意識だった。
見えないものを見ない罪
忘れやすいものを忘れる罪
語り継がない物語を反古にする罪
古い海図のまま人を引導する罪
死者を過去形で悼み進行形で暴いても
徽章の裏は裁けない記憶の庭が
わたしを生え抜きのフェミニストに仕立てたとしても
〈罪〉の大文字の残る手で
海図は描くまい
何千の他者から疎まれても
寒々と栄える街を拒み
加害と被害の 影の終わりが見えるまで(「影を裁く」)
しま・ようこの詩が難解の度を加える理由は、ここにある。彼女が宇宙時間の感覚を持ちながら歴史的時間の中で生き、この現世において被害者であると同時に加害者でもあるからだ。彼女は体制を否認しつつも、罪の意識からこれに代わる新しい社会の見取り図を描くことができない。そこに至る道筋を探ることにもためらいを感じる。彼女が、こうした複雑な内面を描こうとすれば、表現はおのずと晦渋にならざるを得ないのである。
少女期を鎌倉で過ごしたしまさんは、戦後、母(あるいは父)の実家があった津軽に移る。彼女は、多分高校時代を弘前で過ごし、やがて上京して東京の大学に進むことになったろう。
大学を出てからの行路について、しまさんは詩集の略歴欄に「山谷の長欠・未就学児の教育、業界誌の仕事等を経て**大学教員」となると記すばかりで、詳細については口をつぐんでいる。
しかし山谷時代を題材にした作品は「北の方位」に載っている。
山谷
―消えた画面──おーい、先生よ!一杯やってけ、
おれさまの盃、受けねえってこたあ、ねえだろ、
─あーら、(きのうのおっさん!)
泪橋交差点で、車座の菜っ葉ズボンから
〈ワンカップ大関〉を受けると
ほんとうに飲める気になって
記憶のえんの下へもぐり込む─せんせ、ずるいや、おっちゃんとワンカップして、
かん高く甘えるいがぐり坊主はもういない
血を売った〈大関〉のかけらが赤信号に散らばっている・・・・・略・・・・・
酔っぱらいも交えて掛け算九九を復唱する
しわがれ声の母を装っていたのは戸籍から消された父
〈パレスハウス〉の度肝を抜く物語はふっつり切れて
ここは変哲もない町清川二丁目
長欠・未就学児の教育に取り組んだのは、時代に対する彼女の抵抗精神からだった。次の作品も、その抵抗精神の産物のように見える。
むかし
あの人が座っているという
やしろ
小さな社に
頭を垂れるならわしならわしに慣れた人びとは
あのひとの苦痛を思いめぐらすことはなかったが
子どもたちは
少し心配した
あのひとはおしっこに行かないのか?わたしは実験精神旺盛で
あのひとが刷り込まれたぺージで鼻をかみ
ひらひら飾りに包まれた心臓のあたりを
踏んでみた
何ごとも起きはしなかったので
ならわしの暗がりを信じないことにした(「夜汽車で」)
この詩に「あの人」とあるのは、小学校の奉安殿に祭られた「生ける神」天皇にほかならない。その天皇が刷り込まれたページで鼻をかんだりするところは、福沢諭吉のエピソードを思い起こさせる。だが、しまさんはこの作品で天皇制を否定しているわけではない。そのことは、この詩が 「わたしはあの人の実像を一度も見たことはない/ あの人は始めから居なかった /夜汽車は不在の主人公の物語を突き抜ける」 という言葉で終わっているのを見れば明らかである。
しまさんは、この作品で戦争責任が問われている昭和天皇について、「不在の主人公」 という視点を提供している。皇居を「首都の中心に存在する真空点」と表現した外人作家の視点を先取りしたような斬新な視点である。
しまさんの抵抗精神は鋭いが、その批判は、白か黒かという二者択一の立場からするのではなかった。常にそれらを越えた第三の視点からなされている。そうした視点をハッキリ示しているのが、詩集の最初にある「招待」という作品なのだ。
戦があって
争いがあって
小さな和解の向こうに
また沼が迫って
古いフィルムに雨が降り
<家族>の装置が外されていく
はじめから〈ひとり〉であったように
ひとりひとりで草をむしる
父の死後、しまさんと残された家族の間に 「争い」 が生まれ、一旦は和解したものの再び感情的なしこりが発生する。そして肉親の温かな思い出もだんだん遠くなり、家族は解体して、一人一人になる。そんななかで、母が 「よかったら あんたもお入んなさいよ」 としまさんを 「招待」 してくれたのである。
どこに招待してくれたかといえば、墓所なのである。母は、自分と同じ墓にはいるように娘を招待したのだ。招待された 「わたし」 が何者かといえば、「よそ者」 で 「掟を犯し/そしり声をまっすぐうけて」 遠くで暮らしている不肖な娘なのである。
北国の習慣では、遺骨は壺に入れないで、ほかの骨と一緒に葬られる。しまさんは、母から招待されても、先祖代々の墓に入る気持ちを持っていない。母を憎んでいるからではない。そして、北国の土俗的な慣習を嫌っているからでもない。墓の中で睦み合う骨を 「あなたたち」 と呼ぶほど親しみを感じているが、同じ墓に入る気持ちはないのである。
北の故郷を捨てて谷敬と結婚したしまさんは、当時としては珍しかった15階建ての高層マンションに移り住んで、団地での日常を 「第三の眼」 で眺めるようになる。そして、「ビルの内臓に/ くらしの形を流し込」 んだ団地生活の断片を次々に切り取って来て、風変わりな作品群を誕生させることになる。「『高層』感情論」 の目次を開くと、エレベーター、ダイニングルーム、バスルーム、焼却炉、集会室、広場というような題字が眼に飛び込んでくる。
通読していくと、次のような分かりやすい作品もある。
おまえのうえにわたしが重なり わたしのうえにあなたが積んでいく朝 夢の層を近しい人びとに囲まれ 鉄の足音は穏やかに反響する 廊下にうたれる 水の連帯 階下へしだいに太くなる配水管に怒りを誘われる者はいない すみませんねえ留守をちょっと あなたのいれるお茶のおいしいこと 揺れる香りの領域でなにかが始まり続けた(「ある予感」)
だが、読む者をとまどわせる作品も少なくない。試みに 「『高層』感情論」 の末尾を引用してみよう。住民が眠りについてしまった高層マンションをうたった部分である。
暮しが音立てている間
集団の時を背負っていたおまえが
窓々の千の灯が消えていくのを待ちわび
かすかに色槌せた
硬い装置のなかの見えない媒質を眠らせる
あす人びとを艀化させるため
未練たっぷりの今日を脱ぐ
風に抱かれる不動の凧のように不透明な霧を縫って
遠く江戸川を渡ってくる朝の塩
夜っぴておまえの私有できる
わずかな時間を占っていたわたしは
(もうろうとした意識が積んでいく階の高さに
かすかな不安をかかえたまま)
ここで老いていく魚たちの
静かな意志を聞く
幾たびもめぐって来た夏の終わりに
「あす人びとを艀化させるため/未練たっぷりの今日を脱ぐ」 というところまではよく理解できる。人びとを孵化させるために今日を脱ぐというふうな言い方はしまさん独特のもので、こうした新鮮な表現法は余人にはちょっと真似ができない。
しかし、次にくる 「風に抱かれる不動の凧のように」 という表現は素直に胸に落ちてこない。読む者を分かったような、分からぬような混乱した気持ちにさせるのだ。そして最後の9行も同じように読む者をとまどわせ、不消化な印象を後に残す。現代詩が形式論理の枠を越えた世界を表現しようとして、言葉をアクロバット的に使うことはよくあることだが、この分かりにくさはそれとは少し違っている。
しまさんは、暮らしの細部から世界を照射しようと心がけている。いきなり体制の変革に進むのではなく、生活の細部から社会を見直していこうとする現代女性運動の動向を頭に置いて、自らの日常を作品化していくのだ。基層には宇宙時間に刺し貫かれた一種の神秘体験があり、表層には「どんな個人的問題も、政治的意味合いを含んでいる」 という女性運動家としての使命感がある。しまさんの人柄と作品が、一筋縄ではいかないものになるのは当然なことなのである。
問題を解くキーは、詩人の内部で神秘体験者と女性運動家が合体していることにある。
詩集「北の方位」には、しまさんの本質を示す長大な力作もあるけれど、現代詩に暗い私には手に余るため紹介することができなかった。
詩集「北の方位」 しま・ようこ(津軽書房発行)