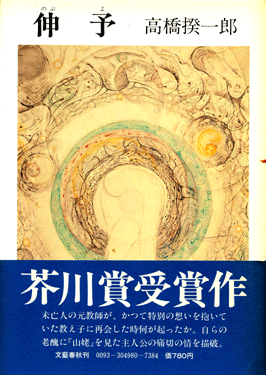女性心理の研究 大型古書店から大量に仕入れてきた古本の一冊に、
「伸予」 高橋揆一郎(文芸春秋社)
という本があって、これを長梅雨のつれづれに読んでみた。
実のところ、当方はこの著者のことは何も知らないのだった。腰巻きの広告に「芥川賞受賞作」とあったので、それに惹かれて買ってきただけなのだ。
三編の小説が載っていた。
最初の「ぽぷらと軍神」は、サディスティックな小学校教員を生徒の目から描いたもので、なかなか面白かった。戦争末期、下士官上がりの右翼教員が小学校に赴任してきて、横暴の限りを尽くすという話である。下士官には世故に長けて抜け目ないけれど、何となく俗臭にまみれているという感じがあるけれど、この教師は下士官の悪い点をことごとく体現しているような人物なのだ。学校の生活がリアルに描けているので、巻末の著者略歴を調べたら、「札幌師範学校中退」とある。(成る程ねえ)と思って、受賞作の「伸予」を読んだら、これも小学校が舞台になっていた。
主人公の伸予は、戦後の混乱期に女学校を出ただけで小学校の臨時教員になる。あの頃は教員不足で、そんな便法が取られていたのである。そして当時は小学校と新制中学が同じ学校の中にあって、運動会などの際には中学生が小学校低学年の生徒の面倒を見るというようなことも行われていた。
小学校2年生の担任だった伸予は、運動会当日、自分のクラスの面倒を見てくれた「ブリキ屋の善ちゃん」という中学3年生に惹かれ、彼と親しくなるためにいろいろと画策するようになる。放課後、誰もいなくなった教室に善吉を呼び寄せて、そっとアメリカ製のチョコレートを手渡したりするのである。
重要なことは、この時伸予には許婚者がいて彼女は相手と結婚するつもりでいたことである。「ブリキ屋の善ちゃん」に対する彼女の愛は、異性に対する愛には違いなかったが、性的な欲求とは直接繋がらないトキメキ主体の愛だった。少女というよりも童女に近い心持ちになって、あこがれの異性に対してドキドキわくわくする「片思いの」愛だったから、許婚者への愛情と矛盾しなかったのである。
程なく伸予は許婚者と結婚し、二人は離ればなれになる。だが、伸予は49才になって別れていた善吉の消息に接し、彼を自宅に呼び寄せる段取りをつける。夫は3年間に死別して、彼女は寡婦になっている。
再会を果たしたときの伸予は、もう昔のお嬢さん育ちの生娘ではなかった。
自宅に訪ねてきた善吉が、何となくもじもじしているのを見て、「なんにもしてくれないの」と行動に出るように促したり、向かい合って話をする段になると大胆にも「わたしはね、善ちゃんのお嫁さんになりたかったんだ」と言ったりする。そして「不謹慎よね、前はこんなふうじゃなかったのに」と弁解するのである。次に訪ねてきた善吉が、思いも寄らなかったことを言い出す。昔、彼女に抱かれたり接吻されたりしたというのである。伸予の方はそのことを全く覚えていない。当時伸予は純粋な「童女の愛」で善吉に向かい合っていたから、善吉を抱いたことも接吻したことも意識の外に押し出してしまって、ただひたすら相手にあこがれていた部分だけを記憶にとどめていたのである。
善吉は続けて「あなたと人のいない教室で抱き合ったときのあなたの体温だの、唇の感触だの」を思い出してオナニーをしたと告げる。それを聞いて彼女はぞっとするのだ。
その部分を引用してみましょう。
<それじゃあ、(善吉は)わたしよりずっとおとなだったんだ>と伸予は胸のうちでつぶやいた。
あのときすでに情欲の対象とされていたのだろうかと身の竦む思いがする。
だが、変わってしまっていたのは伸予の方だった。
伸予は、善吉と顔を合わせたとたんに「なんにもしてくれないの」と催促して抱き上げて貰ったり、前回別れるときには、今度は泊まっていってとせがんだりしている。そして善吉から情欲の対象にされていたことを知ってぞっとした癖に、その日彼女は善吉と身体の交わりを持ってしまうのだ。童女の愛から中年女の情事へと転換したのである。
伸予は善吉に家の鍵を渡すが、二人の関係はそれっきりになる。
伸予が善吉の会社に何度電話しても、相手は電話口に出ようとしない。そればかりか、家の鍵を何の説明も付けず郵便で送り返してくる。こうしたことが原因になったのか、伸予の顔は顔面神経麻痺にかかってひん曲がってしまう。彼女は鏡のなかの顔をつくずく眺めて、自分は「山姥」のようになってしまったと考える。そして、苦い気持ちで、(このたびは善吉の抜け殻を愛していたのだろうか)と自問するのである。
「ものもいわずに鍵を突き返してくるような無礼な男は、とてもあの善吉ではない。そして、その善吉に狂ったように求めていった自分もまた、伸予であって伸予ではない。たしかに山姥がいただけだ。その山姥の肉を食いちぎって逃げていった男がいただけだ」
「伸予」という小説は、伸予が最後にこう考えるところで終わっている。
読み終わって、私はいささか自得するところがあったのである。
私はこれまで盛りを過ぎた女性が亭主持ちの身でありながら「何時までも、恋をしていたい」とか、「生き生き過ごすには、何時も恋をしていないと駄目ね」などと語るのを聞いて、不思議に思っていた。浮ついた放言だと顔をしかめていたのである。それから老境に入った女性が、孫のように若い演歌歌手に夢中になったり、年若い役者の楽屋にちまちましたプレゼントを届けたりする光景も理解できなかった。だが、この小説を読んで分かったのだ。
彼女らが「恋」と称して若いタレントを追いかけるのは、女漁りをする年輩の男たちとは異なる感情からなのである。恋は恋でも、それは性欲以前の童女の恋であって、相手と肉体的な関係に入ることなど望んでいない。老女らの心は、ただ相手にあこがれるだけで充たされ、彼女らが願うところは相手が何時までも輝いていることだけなのである。報酬や見返りを求めない無償の愛なのだ。
伸予も善吉を童女の心で愛していたむかしは、幸福だった。世の中が明るく美しく見えた。が、善吉と情痴の関係に入ると、いらいらして落ち着きを失い、容姿まで山姥のように醜くなった。
昔から、愛には二種類あるとされている。キリスト教では利己的な愛と区別して兄弟愛・神の愛が強調されたし、仏教でも我執に基づく盲愛と区別して覚者による慈悲が説かれた。これをギリシャ哲学の用語でいえばエロスとアガペということになる。個人や個物に対する個別愛がエロスで、存在するものすべてに向けられた無私の愛がアガペなのだが、われわれはわが身を省みて兄弟愛・慈悲・アガペなどの存在を直ぐには信じようとしない。
しかし、アガペの愛は形を変えて至る所に露頭しているのである。
われわれのすべてに魂や仏性が具わっていることは確実であり、そこから兄弟愛・慈悲・アガペが流れ出ていることも疑いないところなのだ。普遍的な愛とは無縁のように思われる童女の恋にも、アガペの要素が混入している。だからこそ、この恋心は本人を幸福にするのである。実際、いい年をして若い歌手の追っかけをしている女性たちは、大体において、みんな幸せそうな顔をしているではないか。
戦前には年輩の男たちが「水揚げ」と称して半玉を買い取る風習があったし、戦後になってこれはロリコン趣味と名前を変えて生き残っている。これに比べたら年輩の女たちが若いタレントに血道を上げ「追っかけ」をしている方が遙かに健全なのである。
「伸予」を読んで、女性心理について認識を新たにしてから何日かたって、「文芸春秋」の新聞広告を読んだ。芥川賞受賞作が掲載されているという。広告には、受賞作に関する簡単な説明が載っていた。今期の芥川賞受賞作である「ハリガネムシ」は、高校で倫理を教えている教師が暴力衝動にとりつかれていく経過を描いたもので、この危険な匂いのする作品を、女性の選考委員がこぞって支持している、という文面だった。
暴力を描いた作品を女性選考委員が支持しているという点に、興味をそそられた。早速雑誌を買ってきて作者の略歴に目をやると、「京都教育大学卒、東京、大阪で高校教諭を務め、現在は養護学校に勤務」とある。この作者も、「教育関係者」らしいのである。
作品は、まず高校教師がカマキリを殺す場面から始まる。教師は顔の上のカマキリを払い落として伏せたコップの中に閉じこめ、やがてこれを殺してしまう。
彼は、まず鎌を振り上げて抵抗の姿勢を示すカマキリの頭を指ではじき飛ばす。カマキリが首なしになってもまだ鎌を振り回しているので、今度は新聞紙で掴んで握りつぶすのだ。すると、尻から真っ黒なハリガネムシが悶え出てくる。この真っ黒なハリガネムシが、人間の心に潜む暴力性の象徴であることは言うまでもない。
そして、このカマキリは、高校教師からいたぶられるサチコの化身でもあって、彼女は顔の上を這いまわるカマキリのようにして男の前に現れたのだった。そして、男につかまってコップのなかに封じ込まれ、痛い目にあわされる。
作者は坂口安吾の「白痴」のような「思想小説」を書きたかったのではないだろうか。そういえばサチコを含め高校教師の周辺に出没する人物は、「白痴」の中の登場人物のように皆猥雑を極めている。そして高校教師には何となく「白痴」の主人公伊沢の面影があるのだ。
伊沢は、逃げてきた白痴の女を押入にかくまい、これに哀憐の情を注いでいる。坂口安吾は、こと精神の問題に関する限り女は白痴同然であり、男との間に接点はないと考えていた。だからこそ彼はおのれの内部の無明を通して、女の無明を眺め、これに哀憐の情を注いだのだ。
サチコも、「白痴」の女と同じように救いようのない存在として描かれている。
「サチコは極めて不完全な生き物で、人をして何か手を加えずにおれ
なくさせる未完成な部分を常時露出させていた」「どんな酷い目に遭わされてもこの女は決して生まれ変わる事はな
く、いかに不完全に見えたとしてもこの女は既にこれで完成体らし
い」サチコは、中学校すらまともに出ておらず、刑務所で服役中の夫との間に生まれた二人の子供を施設に預け放しにしてて働いているいるような女なのだ。
高校教師は、トルコ風呂の客としてそこで働くサチコと性交渉を持った。それでおしまいと思っていたら、突然、サチコからの電話をうけて交渉を再開し、一緒に旅行をしたり結婚を申し込んだりする間柄になる。が、彼は彼女に哀憐の情を注ぐどころか、次第に嗜虐的になって、夜の工事現場で全裸のサチコを縛り上げて宙づりにするようなことまで敢えてするのだ。
高校教師は、「ある天才思想家」(作者はその名前を明らかにしていない)の「ひとはいかにして本来のおのれになるか」という本を愛読している。その思想家は良心の呵責などというものを頭から否定し、そんなものに惑わされるから真実が見えなくなるのだと説いていた。この本には「自分のある行為が失敗した場合、失敗したからこそ、なおさらその行為に対して敬意を持ち続けることが必要だ」という一節がある。
坂口安吾も同じような考え方をしていた。
安吾は、人が忌み嫌う堕落行動のなかに人間本来の姿があると考え、堕ちよ、堕落せよ、そして本来の自己を回復せよ、と説いている。われわれは自分の犯した失策や罪を思い出して自己嫌悪に陥り、それらの記憶を抹殺してしまいたいと思っている。高校教師がこういう自分に反発して真率に生きようとしているのだとしたら、サチコに暴力を加えて恬として恥じない彼の行動も理解できる。
だが、理解することと共感は別で、男性一般からすると、この作品には、どうしても共感できないものがある。男性の選考委員の多くが、自分の好みではないとか、趣味に合わないなどという言い方で、この作品に合格点を与えるのを躊躇っているのも、作品の出来栄えとは別に、この作品には何かしら不快なものがあると感じているからだ。
それはこの小説が、男性の内部に巣くうハリガネムシを刺激するせいかもしれない。
男の選考委員の評価は必ずしも高くないのに、三人の女性委員は揃ってこの作品に高得点を与えている。作品の評価にモラルや風教への影響を持ち出すのは邪道だとしても、彼女らは同性のサチコが徹底的に痛めつけられる小説を読んでも、全く「義憤」を感じないらしい。
私はここにも女性特有の心理が働いていると思うのだ。
経験的に言って、ダメ人間に対する女性の評価は男のそれよりもはるかに厳しい。女に一旦愛想を尽かされると、最早関係を修復することは不可能になる。サチコは不完全なままで完結している女として描かれ、彼女が今後人間として向上する見込みは皆無だと規定されている。こうした女に対する世のエリート女性たちの見方は、辛辣を極めている。彼女らはダメ女を直接いじめたり攻撃したりしない。だが、ダメ女の悲運を身から出た錆と冷たく傍観し、救助の手を差し伸べることはないのである。
「優等生」の集まる学校では、能力の低い教師や出来の悪い生徒は徹底的に冷遇されるし、「劣等生」の集まる学校では、インテリタイプの教師や成績のいい生徒が犠牲の羊になる。いずれの場合も、いじめの先頭に立つのは少数の男生徒で、女生徒は背後からそれを眺めているだけだが、数量的にはいじめへの賛同者は何時でも女生徒の方が多いのである。
勘ぐれば、三人の女性選考委員は高校教師と同じ視点からサチコを眺め、彼女への暴力行為に心理的に加担している。委員の一人高樹のぶ子は、高校教師の暴力衝動がいかにして発生したかを次のように説明する。
「サチコという肉体も精神も貧相な女と出会い、その誇りのなさや卑小
さへの嫌悪が、主人公を怒りや暴力に駆り立てた」サチコの卑小さに嫌悪を感じたのは、実はこう指摘した高樹のぶ子自身ではないだろうか。彼女はいう、「作者はカサブタを引き剥がして血を流して見せた」と。だが、暴力場面にカサブタを引き剥がすような苛烈な快感を感じたのは、高校教師ではなくて評者自身だったように思われる。
「伸予」「ハリガネムシ」を読んで、文学というのはよきものだと思った。人間について、人生について、いろいろなことを考えさせてくれる、特に女性の心理について。 (03/8/18)